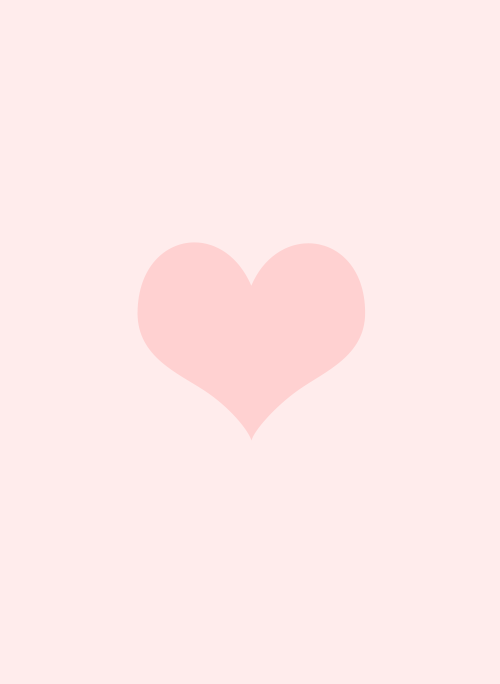恋するバンコク
エピローグ
スクンヴィット通りを少し奥に進んだところに、そのホテルはある。生い茂った椰子の葉の隙間から、白い砂壁が覗く。強い日差しを受けて輝く門の向こうに、一段が高い白い階段。
サワン・ファー・ホテル
砂壁には青い文字でそう書かれている。
「ついたぁ!」
まっさきにタクシーから降りた小学生くらいの女の子が、うれしそうに飛び跳ねる。その後ろから両親が降りて、車道と歩道の間ではしゃぐ娘の手を捕まえた。
広いロビーの中央に、少し段差を作って作られた噴水の水面には大きな蓮の花が浮かんでいる。噴水の水は大きく立つことはなく、ゴポゴポと小さく丸く、下からの青いライトに当たって柔らかに光っている。その噴水の向こう側にはカウンターが並んで、青い制服を着たスタッフたちが微笑みながらお客を出迎える。
なんだか、天国に来たみたいだ。
シャンデリアがきらめく高い天井をうっとりと見上げて、少女はそう思った。
「ねぇママ、プール! プールがある!」
ガラス張りの壁からはガラス玉やタイルで飾ったプールが見渡せた。このプールは数年前から子供用のウォータースライダーを二つ取り付けていて、それが陽光を反射して彼女を魅了してくる。少女の小さな胸は興奮でぞくぞくした。
「あとでね」
「あとっていつ?」
「今日はもう遅いから、明日にしましょう」
あした! そんな遠く!
途端に打ちひしがれて窓に額をこすりつける。
「やだぁ、今がいい~」
すぐ近くに座っている老人が、新聞から視線を離してこっちを見る。そんなことも気にならず、少女はわめいた。
カツン。
革靴の音が大理石の床を鳴らす。
「サワン・ファー・ホテルへようこそ」
声に振り返る。父親がよく着ているスーツとよく似た、でもちょっとちがうその服を着た浅黒い肌の男の人が胸元で手を合わせている。少女の父親とそう変わらない歳にみえるのに、全然ちがう。
すごくかっこいい。俳優さんみたいだ。
その隣に立つ女の人。やっぱり母親と同い年か、少し若いくらい。日に焼けた肌でニコリと笑うその顔が、おひさまみたいにきれいだった。
女の人の胸元に飾られた薄青い雫の形のペンダントがつるりと輝いていて、少女はぼうっとそれを見た。
ニコニコと微笑んで立っている大人たちの前で、赤ん坊みたいにわめいたことが急に恥ずかしくなった。いたたまれない、という言葉をまだ少女は知らなかったけど、衝動にかられてそのままロビーをぴゅんと駆け抜ける。後ろから父親の声がする。
「まって」
突然聞こえた高い声に、ピタリと足をとめた。おそるおそる振り返ると、そこには同い歳くらいの女の子が立っていた。
キャラメル色の肌、長い黒髪、丸い二重の目。キティー柄のTシャツに赤いショートパンツ。
日本人にしてはエキゾチックな顔立ちの彼女は、少女を見るとにっこり笑った。
「プール、入りたいの?」
少女はむっつり黙ったまま、コクンと頷く。彼女はますます笑みを深めた。
「なら私と入ろ」
「……ほんとに?」
彼女はこっくり頷いた。少女の胸によろこびがじわんと広がる。
後ろから追いかけてきた父親が少女の頭にポンと手をおいた。少女は目を輝かせて父親を振り返る。
「この子とプール入ってくる!」
その発言に面食らったのは両親だけじゃなかった。後ろに立っていたスーツの男の人と青い服を着た女の人が、とまどったように顔を見交わせる。
驚く大人たちを尻目に、キャラメル色の肌をした彼女は言った。
「お友だちになろう。私、ヨウっていうの」
プールは大人がそばにいるときだけ、そう言い聞かせると小さな二人は存外おとなしく頷いて、ロビーにあるソファの片隅で遊び始めた。その様子を結は黙って見つめていた。すると片側の肩と背中にぬくもりが宿って、振り返ることなく微笑む。
「昔の私たちみたい」
「そうだね」
タワンが耳元で笑う。
「あの子、やっぱりさみしいのかしら」
娘のヨウを目で追う。割に静かな子だからこうやってたまにロビーに連れてきているけれど、あんなふうに積極的に誰かに声をかけるとは思わなかった。
「そんなことないさ」
結の肩を抱いたまま、タワンが甘く囁く。
「あの子はこの場所が好きなんだよ、僕と君の子だから。それでここに来た人たちにも興味が出てきた、それだけだよ」
この数年間ずっとそうだったように、タワンがニコリと微笑んで言うことは、いつも結の胸に深い安らぎを与える。ほっと笑って頷くと、背後からオッホン、と咳ばらいがした。
振り返ると、パラハーンが目を細めて結とタワンを見つめていた。
「いいかげん離れなさい。うちのホテルの品格をGMが進んで壊してるなんて、トリップアドバイザーに書かれたらどうする」
慌てて離れようとする結を制するように、タワンはにこやかに笑って結の肩を抱いた。
「リピーターのお客様には評判なんだよ。いつも仲が良くていいですねって」
パラハーンは呆れたように首を振って、バックヤードへと向かっていく。歩きながら、
「後でまた打ち合わせだ。一時間後にな」
「二時間後にしてくれ。今日はロビーに立ってたい」
タワンがそう返すと、パラハーンは振り返らずに小さく頷いた。
タワンは去年からGM――General Manager(総支配人)になった。肩書は総支配人だけど、パラハーンの手伝いがメインで、徐々に経営を引き継いでいるようだった。ロビーに出る時間は減ったけれど、それでもわずかの時間を見つけてはフロアに立ち、スタッフの動きを見たりお客のケアを率先して行っている。
そんなタワンをずっと支えたい。娘のヨウと一緒に家でタワンを待っているのも良いだろう。だけど、できるだけ近くでタワンを見ていたいと思うから、結はこの場所に立ち続けている。
「それとな」
パラハーンが正面を向いたまま言う。
「あの子が、ヨウがこのホテルが好きなのは」
振り返ると、結とタワンを見て笑った。
「この私の孫でもあるからだぞ。忘れるでない」
その言葉におもわず笑みがこぼれる。パラハーンは自分の言葉を噛みしめるように数度頷き、息子と同じように伸びた背筋でバックヤードへと歩いて行った。その後ろ姿を結は口元に笑みを浮かべたまま見つめる。
何年も前、義父にタワンともう会うなと言われたことがある。その後にタワンとパラハーンがどんなことを話し合ったか、今でも結は知らない。幾日もに渡る話し合いに、パラハーンはチェンマイに戻る予定の航空券をキャンセルしたと、これはずいぶん後になって義母が教えてくれたことだ。
自分の知らないところでずっとタワンは戦ってくれていた。そしてパラハーンもまた、帰る日を先延ばしても話し合いを続けてくれた。受け入れる努力をしてくれたことに、結はずっと感謝している。
外国人との結婚、だからじゃない、と思う。結婚すること、家族になることはどんな誰でも難しくて、いろんな人が譲ってくれたり理解してくれたり、そんな幾重もの優しさが折り重なっているのだと思う。
だからこそ、結は願う。
ずっとずっと、あなたのそばで。あなたとともに。
振り返ると、タワンが甘く笑う。年齢とともに深みが増した表情は、夫をさらに魅力的に見せている。
ガラス張りの窓から差し込む陽光がフロアを照らした。ささやかな音をたてる噴水も、花器に盛られた蘭の花も、艶めくレストランの扉も。すべてが美しく整えられている。数多のスタッフの手によって。
ドアマンが扉を開いた。目の端で娘が新しい友だちと笑い合っている。その幸せに満ちた笑い声を聞きながら、結とタワンは昨日も、さっきもしたように、互いに目を見交わすとお客を迎え入れた。
「サワン・ファー・ホテルへようこそ」
ーーENDーー
サワン・ファー・ホテル
砂壁には青い文字でそう書かれている。
「ついたぁ!」
まっさきにタクシーから降りた小学生くらいの女の子が、うれしそうに飛び跳ねる。その後ろから両親が降りて、車道と歩道の間ではしゃぐ娘の手を捕まえた。
広いロビーの中央に、少し段差を作って作られた噴水の水面には大きな蓮の花が浮かんでいる。噴水の水は大きく立つことはなく、ゴポゴポと小さく丸く、下からの青いライトに当たって柔らかに光っている。その噴水の向こう側にはカウンターが並んで、青い制服を着たスタッフたちが微笑みながらお客を出迎える。
なんだか、天国に来たみたいだ。
シャンデリアがきらめく高い天井をうっとりと見上げて、少女はそう思った。
「ねぇママ、プール! プールがある!」
ガラス張りの壁からはガラス玉やタイルで飾ったプールが見渡せた。このプールは数年前から子供用のウォータースライダーを二つ取り付けていて、それが陽光を反射して彼女を魅了してくる。少女の小さな胸は興奮でぞくぞくした。
「あとでね」
「あとっていつ?」
「今日はもう遅いから、明日にしましょう」
あした! そんな遠く!
途端に打ちひしがれて窓に額をこすりつける。
「やだぁ、今がいい~」
すぐ近くに座っている老人が、新聞から視線を離してこっちを見る。そんなことも気にならず、少女はわめいた。
カツン。
革靴の音が大理石の床を鳴らす。
「サワン・ファー・ホテルへようこそ」
声に振り返る。父親がよく着ているスーツとよく似た、でもちょっとちがうその服を着た浅黒い肌の男の人が胸元で手を合わせている。少女の父親とそう変わらない歳にみえるのに、全然ちがう。
すごくかっこいい。俳優さんみたいだ。
その隣に立つ女の人。やっぱり母親と同い年か、少し若いくらい。日に焼けた肌でニコリと笑うその顔が、おひさまみたいにきれいだった。
女の人の胸元に飾られた薄青い雫の形のペンダントがつるりと輝いていて、少女はぼうっとそれを見た。
ニコニコと微笑んで立っている大人たちの前で、赤ん坊みたいにわめいたことが急に恥ずかしくなった。いたたまれない、という言葉をまだ少女は知らなかったけど、衝動にかられてそのままロビーをぴゅんと駆け抜ける。後ろから父親の声がする。
「まって」
突然聞こえた高い声に、ピタリと足をとめた。おそるおそる振り返ると、そこには同い歳くらいの女の子が立っていた。
キャラメル色の肌、長い黒髪、丸い二重の目。キティー柄のTシャツに赤いショートパンツ。
日本人にしてはエキゾチックな顔立ちの彼女は、少女を見るとにっこり笑った。
「プール、入りたいの?」
少女はむっつり黙ったまま、コクンと頷く。彼女はますます笑みを深めた。
「なら私と入ろ」
「……ほんとに?」
彼女はこっくり頷いた。少女の胸によろこびがじわんと広がる。
後ろから追いかけてきた父親が少女の頭にポンと手をおいた。少女は目を輝かせて父親を振り返る。
「この子とプール入ってくる!」
その発言に面食らったのは両親だけじゃなかった。後ろに立っていたスーツの男の人と青い服を着た女の人が、とまどったように顔を見交わせる。
驚く大人たちを尻目に、キャラメル色の肌をした彼女は言った。
「お友だちになろう。私、ヨウっていうの」
プールは大人がそばにいるときだけ、そう言い聞かせると小さな二人は存外おとなしく頷いて、ロビーにあるソファの片隅で遊び始めた。その様子を結は黙って見つめていた。すると片側の肩と背中にぬくもりが宿って、振り返ることなく微笑む。
「昔の私たちみたい」
「そうだね」
タワンが耳元で笑う。
「あの子、やっぱりさみしいのかしら」
娘のヨウを目で追う。割に静かな子だからこうやってたまにロビーに連れてきているけれど、あんなふうに積極的に誰かに声をかけるとは思わなかった。
「そんなことないさ」
結の肩を抱いたまま、タワンが甘く囁く。
「あの子はこの場所が好きなんだよ、僕と君の子だから。それでここに来た人たちにも興味が出てきた、それだけだよ」
この数年間ずっとそうだったように、タワンがニコリと微笑んで言うことは、いつも結の胸に深い安らぎを与える。ほっと笑って頷くと、背後からオッホン、と咳ばらいがした。
振り返ると、パラハーンが目を細めて結とタワンを見つめていた。
「いいかげん離れなさい。うちのホテルの品格をGMが進んで壊してるなんて、トリップアドバイザーに書かれたらどうする」
慌てて離れようとする結を制するように、タワンはにこやかに笑って結の肩を抱いた。
「リピーターのお客様には評判なんだよ。いつも仲が良くていいですねって」
パラハーンは呆れたように首を振って、バックヤードへと向かっていく。歩きながら、
「後でまた打ち合わせだ。一時間後にな」
「二時間後にしてくれ。今日はロビーに立ってたい」
タワンがそう返すと、パラハーンは振り返らずに小さく頷いた。
タワンは去年からGM――General Manager(総支配人)になった。肩書は総支配人だけど、パラハーンの手伝いがメインで、徐々に経営を引き継いでいるようだった。ロビーに出る時間は減ったけれど、それでもわずかの時間を見つけてはフロアに立ち、スタッフの動きを見たりお客のケアを率先して行っている。
そんなタワンをずっと支えたい。娘のヨウと一緒に家でタワンを待っているのも良いだろう。だけど、できるだけ近くでタワンを見ていたいと思うから、結はこの場所に立ち続けている。
「それとな」
パラハーンが正面を向いたまま言う。
「あの子が、ヨウがこのホテルが好きなのは」
振り返ると、結とタワンを見て笑った。
「この私の孫でもあるからだぞ。忘れるでない」
その言葉におもわず笑みがこぼれる。パラハーンは自分の言葉を噛みしめるように数度頷き、息子と同じように伸びた背筋でバックヤードへと歩いて行った。その後ろ姿を結は口元に笑みを浮かべたまま見つめる。
何年も前、義父にタワンともう会うなと言われたことがある。その後にタワンとパラハーンがどんなことを話し合ったか、今でも結は知らない。幾日もに渡る話し合いに、パラハーンはチェンマイに戻る予定の航空券をキャンセルしたと、これはずいぶん後になって義母が教えてくれたことだ。
自分の知らないところでずっとタワンは戦ってくれていた。そしてパラハーンもまた、帰る日を先延ばしても話し合いを続けてくれた。受け入れる努力をしてくれたことに、結はずっと感謝している。
外国人との結婚、だからじゃない、と思う。結婚すること、家族になることはどんな誰でも難しくて、いろんな人が譲ってくれたり理解してくれたり、そんな幾重もの優しさが折り重なっているのだと思う。
だからこそ、結は願う。
ずっとずっと、あなたのそばで。あなたとともに。
振り返ると、タワンが甘く笑う。年齢とともに深みが増した表情は、夫をさらに魅力的に見せている。
ガラス張りの窓から差し込む陽光がフロアを照らした。ささやかな音をたてる噴水も、花器に盛られた蘭の花も、艶めくレストランの扉も。すべてが美しく整えられている。数多のスタッフの手によって。
ドアマンが扉を開いた。目の端で娘が新しい友だちと笑い合っている。その幸せに満ちた笑い声を聞きながら、結とタワンは昨日も、さっきもしたように、互いに目を見交わすとお客を迎え入れた。
「サワン・ファー・ホテルへようこそ」
ーーENDーー