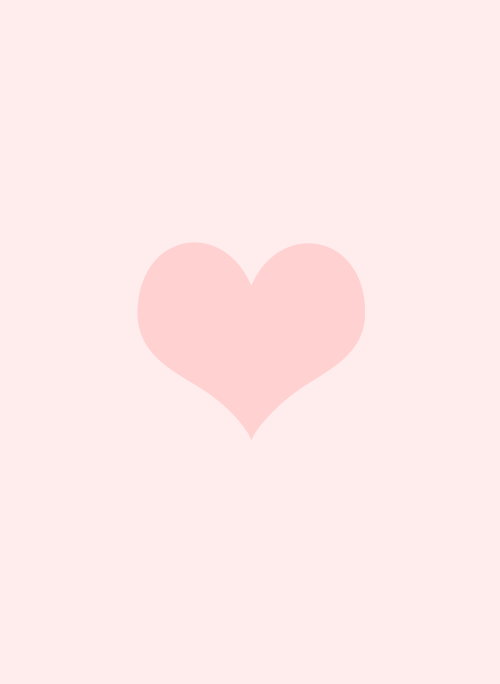龍とたんぽぽ
おじさんが落ちていた。
何を言っているのか、自分でもよく分からない。ただ、私の家の玄関にもたれ掛かるようにして、その人は意識を失っていた。なんでこんなところで人が倒れているんだろう。しかも何故私の家の玄関なんだろう。疑問はたくさんあったけど、真冬の寒い中におじさんを放っておくこともできず、私は彼を部屋に入れた。部屋の暖房を入れて、暖をとってからおじさんを床に寝かせる。おじさんが目を覚まさないから、どうすることもできなくてとりあえず私は課題をする。なんてシュールな光景だろうか。おじさんを拾う女子大生なんて、前代未聞だろう。私も、まさか自分がこんな行動をとるなんて、今でも信じられない状況だ。そんな時、おじさんがもぞもぞと身動ぐ。
「あ、起きた」
案外動じていない私は、おじさんに声を掛ける。うっすらと目を開いた彼は、次第に目を見開いてがばりと起き上がった。
「お前、誰だ!」
状況が飲み込めていないらしい彼は、壁までずりずりと後退る。
「この部屋の家主といいますか、賃借人ですけど」
とりあえず軽く自己紹介してみる。「宇森菜乃花(うもりなのか)です」と言うと、彼はまだ訝しそうにしているものの、「梅崎(うめさき)だ」と名乗った。混乱しつつも、彼が話してくれた話はこうだった。とある事情で逃げていて、昔の女の部屋を尋ねたら留守だったので、玄関で待とうと思ったら寒さで気を失っていた。そして、気がつくと室内で、知らない女が目の前に居た、ということらしい。残念ながら二年前には私がもう住んでいたので、その昔の女という人の情報は全くと言って良いほど無い。このアパートの大家さんも遠方に住んでいる方だから、聞くことは難しいだろう。そう説明すると、彼は「そう、か……」と肩を落とした。何だかよく分からないけれど、ボロボロのおじさんを、アテのないこの田舎の住宅街に放り出すのも気がひけるので、「しばらくうちに居ます?」と聞いてみる。
「お前、馬鹿なのか……?」
初対面のおじさんには言われたく無い。でも、その言葉は、大学の友達にもよく言われる。そう。私は普通とは少し価値観というか、感覚が違うらしい。
「だって、おじさん追われてるんでしょう?なんの関係もない私の部屋にいた方が、見つからなくないですか?」
もっともらしいことを言ってみる。追われているというおじさんも、少し考えているようだ。その時、盛大に腹の虫がなった。出どころはおじさんのお腹。
「ご飯、食べます?」そう聞くと、おじさんーー梅崎さんは顔を少し赤らめながら、「頼む」と大人しくなった。
この辺りでは、わりと田舎の方にある大学。そこに私は通っていた。何かがしたくてそこに行った、というよりは、大学に行けば多分就活が少しは楽で、でも街中には行きたくない。たったこれだけの理由で今の学校を選んだ。私には夢がない。何かになりたいという気持ちも無く、何と無く生きているだけ。そんな私が拾い物をした。何かから逃げているというおじさん。刺激のない生活に、ピリッとしたスパイス。楽しみね。梅崎さん。私と一緒に暮らしてみましょうよ。
数日経った頃、近所の大型ショッピングモールでメンズ服をいくつか見繕ってきた私は、梅崎さんを着替えさせ、彼が着ていた服を洗濯した。本当にボロボロの服。一体何から逃げているんだろうか。ズボンの至る所がほつれ、上着も煤のような汚れがいくつもある。少し間違えば浮浪者にも見えたその格好のまま部屋に置いておくのも嫌だったので、思い切って服を買ってきた。
「すまねえな」
梅崎さんは申し訳なさそうに、部屋の隅に腰掛けている。
「もう少し広いところに座ればいいのに」
そう言う私の言葉は聞き入れず、彼はじっとしている。洗濯物を干し終わった私は、彼の前にしゃがみ込む。
「お話し、しませんか。梅崎さんのこと、もっと知りたいです」
彼の目を覗き込むと、戸惑うように少し揺れたけれど、「少しだけな」と言って彼は語り出した。
「疑いを掛けられたんだ。頭(かしら)の首を狙ってるって……そんなこと微塵も考えてなかった俺からしたら、本当に晴天の霹靂だよ。」
彼は、私の知る言葉で言い表すと、ヤクザらしい。階級は低くも無く、高くも無く。上下のどちらにも顔が知れている程度の中間職だったと。
「突然身を追われた俺に逃げ場なんて多く無くてよ、とっさに昔の女を思い出してみてもこのザマだ」
このザマと言いながら彼は私の鼻をムニっと摘む。ふがっと変な声を出して私は尻餅をついた。
「梅さんって呼んでも良いですか?」
摘まれた鼻をさすりながら、彼を見る。
「愛称なんかで呼んで、お近づきにでもなるつもりか。俺はヤクザだぞ」
知り合ったって、お前にはなんのメリットもないと言って、彼はそっぽを向く。
「今は同居人です。いいじゃないですか、少なくとも私はこの状況を楽しんでますよ」
えへんと胸を張ると、梅崎さんーー梅さんは心底不思議そうな顔をする。
「お前、本当に変なやつなんだな」
よく言われますと返事をすると、「それはもう聞いたよ」と彼は苦笑した。
今日はバイトの日だった。スーパーのレジ打ちのバイトは、ひたすらレジを打って、ひたすら「いらっしゃいませ」と「ありがとうございました」を連呼していれば終わるものだと思っている。サボる気はないけれど、やる気もない私は、そこそこでバイトをしている。生活が出来ればいいのだ。必要以上に稼ぐつもりもない。梅さんが一人増えたところで、困るような生活もしていないし、頑張る必要もない。シフトを終えた私は、値引きになった惣菜を買って、さっさと家へ帰った。
「ただいまー」
玄関を開けると、食卓の椅子に腰掛けた梅さんが新聞を読んでいた。
「おう」とひとこと返事をした彼は、また手元へと視線を戻す。
「それ、買ったんですか?」と新聞を指差す私に、彼は「隣の爺さんがくれた」と返事をする。
隣のお爺さんとどこで接点が……と考えていると、煙草を吸いにベランダに出た際に、顔を合わせたとのことだった。元の身内から逃げてきた、と言う割には危機感が薄い気がしたけれど、彼がそれで良さそうにしているので、深くは追求しない。隣のお爺さんはもう長くここに住んでいるらしいので、もしかしたら元から顔見知りだったのかも知れない。そんな気もした。
梅さんが買い物に行きたいと言い出した。この人は本当に逃げている人なんだろうか。
「煙草も切れたし、酒が飲みたい」と言う彼は、しょうもない内容に対してとても真剣な目で見てくるもんだから、じゃあ私と一緒にコンビニ行きましょうと、一緒に外出することになった。近所に一軒だけあるコンビニは、梅さんにも覚えがあったらしい。迷うことない足取りでそこへ辿り着くと、さっさと中で用事を済ませて出てくる。外で待っていた私に、「ん」と何かを突き出してきた。その手には饅頭の形をしたアイスが握られている。
「これ、なに?」
そう聞く私に、彼は「世話になってる礼だよ」とアイスをずいっと押し付けてきた。居候のお礼なんていいのにという私に、居候はやめろと彼はげんなりする。見返りなんて求めてもいなかった私は、意外な頂き物に少し嬉しかった。ただ、真冬のアイスは少し寒かった。
「梅さん、寒い」
私が受け取ったアイスを食べながらそう言うと、そこで彼はしまったという顔をした。
「わりい、冬だったな」
季節感のない贈り物ですねと嫌味を言ってみると、彼は心底すまなさそうにして「戻ったらあったかいコーヒー淹れてやるよ」と言う。何だか距離の縮まったようなやりとりに、私は心が浮かれた。
彼の淹れてくれたコーヒーを飲みながら、なにもせずにだらだらとする休日も悪くはない。あぐらをかいて座る梅さんの膝に頭をのせて、私は昼のサスペンスドラマを観ていた。今日のドラマの内容は、事件の真相を握る男が犯人に追われるというもの。なんだか梅さんの状況に似ていて、彼に「似てますね」というと、こんな生優しいもんじゃねえよと彼は今日も新聞に目を落とす。しばらくそうしていると、ドラマの場面が官能的なシーンに変わった。
「あらー、えっちですね」
あまり激しくはない表現に、私は照れることはなくドラマを観ていると、わりいと声がして私の頭がごちんと床に落ちる。じんじんと痛む頭をさすりながら梅さんを探すと、彼はそそくさとトイレに駆け込んでいた。どうしたものかとトイレの扉をノックして「体調悪いんですか?」と声をかける。中から「生理現象だから気にすんな」という声が聞こえてきて、数分すると何事もなかったかのように、すっきりとした顔の梅さんが部屋に戻ってきた。「溜まってたんですね」と声をかけると、もうしこし恥じらいを持てよと梅さんに諭される。別に二十歳を超えた女が今更それで恥ずかしがることもない。
「生娘じゃないんだから、いちいち恥じらってられませんよ」
そう言うと、私は梅さんにベッドへ投げ飛ばされた。彼は眉間にシワを寄せながら「煽るようなことを言うな」と私に釘を刺してくるけれど。年頃の女が何の予想もなしに男を部屋にはあげませんよと言って、彼に口付けると、それを皮切りに私たちは体を重ねた。服を脱がす時間も惜しいのか、彼は私の体の形を服の上から執拗になぞってくる。そのうちひんやりとした梅さんの手が私の服の中に入ってきて、胸へと手をかける。頂の蕾を彼は指で転がしながら、シャツが捲れて露わになった私の腹部に舌を這わせる。声も無い、静かな情事。彼が私の中に侵入してきた時も、私は声もあげず、ただひたすら貪るように彼と唇と重ねた。おじさんと言う割に、彼は少し若い気もする。それでもおじさんに変わりはないけれど。顔は悪くない。正直、そこに私の下心が無かったかと聞かれれば、あったと答える。そんなルックス。
「あーあ、関係もっちゃいましたね」
彼が中に吐き出したものが、つうっと伝って溢れてくる。コンドームなんて準備はない。本能のままに貪りあった私たちは生でセックスをしてしまった。枕元のティッシュを数枚取り、梅さんが私の足の間から溢れるそれを拭き取る。
「わりいな。ちゃんとアフターピル飲んどけよ」
彼はそう言うとシャワーを浴びに浴室へと向かう。
「安全日なので大丈夫でーす」という私の声は、彼には聞こえていなかった。その日から、私たちは度々体を重ねる仲になった。
数日後。バイトも大学も休みだった私は、梅さんと部屋でごろごろしていた。特に何をするでもなく、さわさわと胸を揉まれている時、玄関の呼び鈴がなった。私の部屋を知っている友達はいない。誰だろうかとドアスコープを覗き込むと、色とりどりのスーツに身を包んだ男たちが、こちらを覗き込むように立っている。
「ゲームセット、だね。梅さん」
彼にも外を見るように促すと、「迷惑かけて悪かったな」と彼は言った。そのまま玄関の鍵を開けると、雪崩れ込んできた男たちに彼は取り押さえられた。
「梅崎テメェ!」「ふざけるな」「頭を裏切るなんて」「この不義理」
次々に罵声を浴びせられながら、彼は数発顔を殴られる。それでも彼は抵抗せず、部屋の中では決して暴れようとしなかった。梅さんが外に連れ出された後、男の一人が私に詰め寄ってきた。
「女、お前梅崎庇いやがって、何モンだ⁈」
舌を巻きながら舐めるように私を見てくる不躾な視線に、私は淡々と答える。
「宇森菜乃花、二十一歳です。あなた達の頭って、堂島?」
私の問いに男が一際吠える。
「頭を呼び捨てにしてんじゃねえぞアマァッ‼︎」
男の口から飛び散った唾が、私の頬に飛ぶ。指で拭いながら「きったな」というと、どうやら彼の神経を逆撫でしてしまったようだった。私は胸ぐらを掴まれて、アパートの廊下に引きずり出される。「あいたたた」と言っていると、私の胸ぐらを掴んでいる男が、今度は私を壁に打ち付けた。思わずげほっと咳込むと、それが耳に入ったらしい梅さんが「菜乃花!」と初めて私の名前を外から呼んだ。あれ、なんだか嬉しいな。この気持ちはなんだろうか。なんだか、この気持ちは失いたくない。そう思った時、私を拘束している男の額に、力いっぱいの頭突きをお見舞いした。
「あいったぁ……」
自分でしておきながら、私も痛みに悶絶する。男は打ちどころが悪かったらしく、そのままばたりと倒れ込んで動かなくなった。私は駆け出し、梅さんをタコ殴りにしている男たちにこう告げた。
「常盤組(ときわぐみ)頭の堂島直志(どうじまただし)に伝えな。洋子(ようこ)の娘が生きてるって」
そう言い放つと、男たちの顔は見る見るうちに青ざめていく。
「私の男が頭を裏切っただって?冗談はやめてよ。で、あんたらどうするの?」
状況が分かっていない梅さんだけが、目をぱちぱちと瞬かせてこちらを見ている。
「こんなことが無ければ、一生名乗るつもりなんてなかったけどね。私はね、堂島の一番愛した女と堂島の間に生まれた、その娘だよ」
梅さんの疑いは晴れた。そして堂島に存在が知れた私は、組に迎え入れるとの申し出があったけど、それを断って今まで通り、田舎のアパートで生活している。今までと少し変わったことと言えば、梅さんと正式にお付き合いをするようになったこと。それも、結局は今までと何ら変わりはなくて、今日も私たちは平和に暮らしている。
何を言っているのか、自分でもよく分からない。ただ、私の家の玄関にもたれ掛かるようにして、その人は意識を失っていた。なんでこんなところで人が倒れているんだろう。しかも何故私の家の玄関なんだろう。疑問はたくさんあったけど、真冬の寒い中におじさんを放っておくこともできず、私は彼を部屋に入れた。部屋の暖房を入れて、暖をとってからおじさんを床に寝かせる。おじさんが目を覚まさないから、どうすることもできなくてとりあえず私は課題をする。なんてシュールな光景だろうか。おじさんを拾う女子大生なんて、前代未聞だろう。私も、まさか自分がこんな行動をとるなんて、今でも信じられない状況だ。そんな時、おじさんがもぞもぞと身動ぐ。
「あ、起きた」
案外動じていない私は、おじさんに声を掛ける。うっすらと目を開いた彼は、次第に目を見開いてがばりと起き上がった。
「お前、誰だ!」
状況が飲み込めていないらしい彼は、壁までずりずりと後退る。
「この部屋の家主といいますか、賃借人ですけど」
とりあえず軽く自己紹介してみる。「宇森菜乃花(うもりなのか)です」と言うと、彼はまだ訝しそうにしているものの、「梅崎(うめさき)だ」と名乗った。混乱しつつも、彼が話してくれた話はこうだった。とある事情で逃げていて、昔の女の部屋を尋ねたら留守だったので、玄関で待とうと思ったら寒さで気を失っていた。そして、気がつくと室内で、知らない女が目の前に居た、ということらしい。残念ながら二年前には私がもう住んでいたので、その昔の女という人の情報は全くと言って良いほど無い。このアパートの大家さんも遠方に住んでいる方だから、聞くことは難しいだろう。そう説明すると、彼は「そう、か……」と肩を落とした。何だかよく分からないけれど、ボロボロのおじさんを、アテのないこの田舎の住宅街に放り出すのも気がひけるので、「しばらくうちに居ます?」と聞いてみる。
「お前、馬鹿なのか……?」
初対面のおじさんには言われたく無い。でも、その言葉は、大学の友達にもよく言われる。そう。私は普通とは少し価値観というか、感覚が違うらしい。
「だって、おじさん追われてるんでしょう?なんの関係もない私の部屋にいた方が、見つからなくないですか?」
もっともらしいことを言ってみる。追われているというおじさんも、少し考えているようだ。その時、盛大に腹の虫がなった。出どころはおじさんのお腹。
「ご飯、食べます?」そう聞くと、おじさんーー梅崎さんは顔を少し赤らめながら、「頼む」と大人しくなった。
この辺りでは、わりと田舎の方にある大学。そこに私は通っていた。何かがしたくてそこに行った、というよりは、大学に行けば多分就活が少しは楽で、でも街中には行きたくない。たったこれだけの理由で今の学校を選んだ。私には夢がない。何かになりたいという気持ちも無く、何と無く生きているだけ。そんな私が拾い物をした。何かから逃げているというおじさん。刺激のない生活に、ピリッとしたスパイス。楽しみね。梅崎さん。私と一緒に暮らしてみましょうよ。
数日経った頃、近所の大型ショッピングモールでメンズ服をいくつか見繕ってきた私は、梅崎さんを着替えさせ、彼が着ていた服を洗濯した。本当にボロボロの服。一体何から逃げているんだろうか。ズボンの至る所がほつれ、上着も煤のような汚れがいくつもある。少し間違えば浮浪者にも見えたその格好のまま部屋に置いておくのも嫌だったので、思い切って服を買ってきた。
「すまねえな」
梅崎さんは申し訳なさそうに、部屋の隅に腰掛けている。
「もう少し広いところに座ればいいのに」
そう言う私の言葉は聞き入れず、彼はじっとしている。洗濯物を干し終わった私は、彼の前にしゃがみ込む。
「お話し、しませんか。梅崎さんのこと、もっと知りたいです」
彼の目を覗き込むと、戸惑うように少し揺れたけれど、「少しだけな」と言って彼は語り出した。
「疑いを掛けられたんだ。頭(かしら)の首を狙ってるって……そんなこと微塵も考えてなかった俺からしたら、本当に晴天の霹靂だよ。」
彼は、私の知る言葉で言い表すと、ヤクザらしい。階級は低くも無く、高くも無く。上下のどちらにも顔が知れている程度の中間職だったと。
「突然身を追われた俺に逃げ場なんて多く無くてよ、とっさに昔の女を思い出してみてもこのザマだ」
このザマと言いながら彼は私の鼻をムニっと摘む。ふがっと変な声を出して私は尻餅をついた。
「梅さんって呼んでも良いですか?」
摘まれた鼻をさすりながら、彼を見る。
「愛称なんかで呼んで、お近づきにでもなるつもりか。俺はヤクザだぞ」
知り合ったって、お前にはなんのメリットもないと言って、彼はそっぽを向く。
「今は同居人です。いいじゃないですか、少なくとも私はこの状況を楽しんでますよ」
えへんと胸を張ると、梅崎さんーー梅さんは心底不思議そうな顔をする。
「お前、本当に変なやつなんだな」
よく言われますと返事をすると、「それはもう聞いたよ」と彼は苦笑した。
今日はバイトの日だった。スーパーのレジ打ちのバイトは、ひたすらレジを打って、ひたすら「いらっしゃいませ」と「ありがとうございました」を連呼していれば終わるものだと思っている。サボる気はないけれど、やる気もない私は、そこそこでバイトをしている。生活が出来ればいいのだ。必要以上に稼ぐつもりもない。梅さんが一人増えたところで、困るような生活もしていないし、頑張る必要もない。シフトを終えた私は、値引きになった惣菜を買って、さっさと家へ帰った。
「ただいまー」
玄関を開けると、食卓の椅子に腰掛けた梅さんが新聞を読んでいた。
「おう」とひとこと返事をした彼は、また手元へと視線を戻す。
「それ、買ったんですか?」と新聞を指差す私に、彼は「隣の爺さんがくれた」と返事をする。
隣のお爺さんとどこで接点が……と考えていると、煙草を吸いにベランダに出た際に、顔を合わせたとのことだった。元の身内から逃げてきた、と言う割には危機感が薄い気がしたけれど、彼がそれで良さそうにしているので、深くは追求しない。隣のお爺さんはもう長くここに住んでいるらしいので、もしかしたら元から顔見知りだったのかも知れない。そんな気もした。
梅さんが買い物に行きたいと言い出した。この人は本当に逃げている人なんだろうか。
「煙草も切れたし、酒が飲みたい」と言う彼は、しょうもない内容に対してとても真剣な目で見てくるもんだから、じゃあ私と一緒にコンビニ行きましょうと、一緒に外出することになった。近所に一軒だけあるコンビニは、梅さんにも覚えがあったらしい。迷うことない足取りでそこへ辿り着くと、さっさと中で用事を済ませて出てくる。外で待っていた私に、「ん」と何かを突き出してきた。その手には饅頭の形をしたアイスが握られている。
「これ、なに?」
そう聞く私に、彼は「世話になってる礼だよ」とアイスをずいっと押し付けてきた。居候のお礼なんていいのにという私に、居候はやめろと彼はげんなりする。見返りなんて求めてもいなかった私は、意外な頂き物に少し嬉しかった。ただ、真冬のアイスは少し寒かった。
「梅さん、寒い」
私が受け取ったアイスを食べながらそう言うと、そこで彼はしまったという顔をした。
「わりい、冬だったな」
季節感のない贈り物ですねと嫌味を言ってみると、彼は心底すまなさそうにして「戻ったらあったかいコーヒー淹れてやるよ」と言う。何だか距離の縮まったようなやりとりに、私は心が浮かれた。
彼の淹れてくれたコーヒーを飲みながら、なにもせずにだらだらとする休日も悪くはない。あぐらをかいて座る梅さんの膝に頭をのせて、私は昼のサスペンスドラマを観ていた。今日のドラマの内容は、事件の真相を握る男が犯人に追われるというもの。なんだか梅さんの状況に似ていて、彼に「似てますね」というと、こんな生優しいもんじゃねえよと彼は今日も新聞に目を落とす。しばらくそうしていると、ドラマの場面が官能的なシーンに変わった。
「あらー、えっちですね」
あまり激しくはない表現に、私は照れることはなくドラマを観ていると、わりいと声がして私の頭がごちんと床に落ちる。じんじんと痛む頭をさすりながら梅さんを探すと、彼はそそくさとトイレに駆け込んでいた。どうしたものかとトイレの扉をノックして「体調悪いんですか?」と声をかける。中から「生理現象だから気にすんな」という声が聞こえてきて、数分すると何事もなかったかのように、すっきりとした顔の梅さんが部屋に戻ってきた。「溜まってたんですね」と声をかけると、もうしこし恥じらいを持てよと梅さんに諭される。別に二十歳を超えた女が今更それで恥ずかしがることもない。
「生娘じゃないんだから、いちいち恥じらってられませんよ」
そう言うと、私は梅さんにベッドへ投げ飛ばされた。彼は眉間にシワを寄せながら「煽るようなことを言うな」と私に釘を刺してくるけれど。年頃の女が何の予想もなしに男を部屋にはあげませんよと言って、彼に口付けると、それを皮切りに私たちは体を重ねた。服を脱がす時間も惜しいのか、彼は私の体の形を服の上から執拗になぞってくる。そのうちひんやりとした梅さんの手が私の服の中に入ってきて、胸へと手をかける。頂の蕾を彼は指で転がしながら、シャツが捲れて露わになった私の腹部に舌を這わせる。声も無い、静かな情事。彼が私の中に侵入してきた時も、私は声もあげず、ただひたすら貪るように彼と唇と重ねた。おじさんと言う割に、彼は少し若い気もする。それでもおじさんに変わりはないけれど。顔は悪くない。正直、そこに私の下心が無かったかと聞かれれば、あったと答える。そんなルックス。
「あーあ、関係もっちゃいましたね」
彼が中に吐き出したものが、つうっと伝って溢れてくる。コンドームなんて準備はない。本能のままに貪りあった私たちは生でセックスをしてしまった。枕元のティッシュを数枚取り、梅さんが私の足の間から溢れるそれを拭き取る。
「わりいな。ちゃんとアフターピル飲んどけよ」
彼はそう言うとシャワーを浴びに浴室へと向かう。
「安全日なので大丈夫でーす」という私の声は、彼には聞こえていなかった。その日から、私たちは度々体を重ねる仲になった。
数日後。バイトも大学も休みだった私は、梅さんと部屋でごろごろしていた。特に何をするでもなく、さわさわと胸を揉まれている時、玄関の呼び鈴がなった。私の部屋を知っている友達はいない。誰だろうかとドアスコープを覗き込むと、色とりどりのスーツに身を包んだ男たちが、こちらを覗き込むように立っている。
「ゲームセット、だね。梅さん」
彼にも外を見るように促すと、「迷惑かけて悪かったな」と彼は言った。そのまま玄関の鍵を開けると、雪崩れ込んできた男たちに彼は取り押さえられた。
「梅崎テメェ!」「ふざけるな」「頭を裏切るなんて」「この不義理」
次々に罵声を浴びせられながら、彼は数発顔を殴られる。それでも彼は抵抗せず、部屋の中では決して暴れようとしなかった。梅さんが外に連れ出された後、男の一人が私に詰め寄ってきた。
「女、お前梅崎庇いやがって、何モンだ⁈」
舌を巻きながら舐めるように私を見てくる不躾な視線に、私は淡々と答える。
「宇森菜乃花、二十一歳です。あなた達の頭って、堂島?」
私の問いに男が一際吠える。
「頭を呼び捨てにしてんじゃねえぞアマァッ‼︎」
男の口から飛び散った唾が、私の頬に飛ぶ。指で拭いながら「きったな」というと、どうやら彼の神経を逆撫でしてしまったようだった。私は胸ぐらを掴まれて、アパートの廊下に引きずり出される。「あいたたた」と言っていると、私の胸ぐらを掴んでいる男が、今度は私を壁に打ち付けた。思わずげほっと咳込むと、それが耳に入ったらしい梅さんが「菜乃花!」と初めて私の名前を外から呼んだ。あれ、なんだか嬉しいな。この気持ちはなんだろうか。なんだか、この気持ちは失いたくない。そう思った時、私を拘束している男の額に、力いっぱいの頭突きをお見舞いした。
「あいったぁ……」
自分でしておきながら、私も痛みに悶絶する。男は打ちどころが悪かったらしく、そのままばたりと倒れ込んで動かなくなった。私は駆け出し、梅さんをタコ殴りにしている男たちにこう告げた。
「常盤組(ときわぐみ)頭の堂島直志(どうじまただし)に伝えな。洋子(ようこ)の娘が生きてるって」
そう言い放つと、男たちの顔は見る見るうちに青ざめていく。
「私の男が頭を裏切っただって?冗談はやめてよ。で、あんたらどうするの?」
状況が分かっていない梅さんだけが、目をぱちぱちと瞬かせてこちらを見ている。
「こんなことが無ければ、一生名乗るつもりなんてなかったけどね。私はね、堂島の一番愛した女と堂島の間に生まれた、その娘だよ」
梅さんの疑いは晴れた。そして堂島に存在が知れた私は、組に迎え入れるとの申し出があったけど、それを断って今まで通り、田舎のアパートで生活している。今までと少し変わったことと言えば、梅さんと正式にお付き合いをするようになったこと。それも、結局は今までと何ら変わりはなくて、今日も私たちは平和に暮らしている。