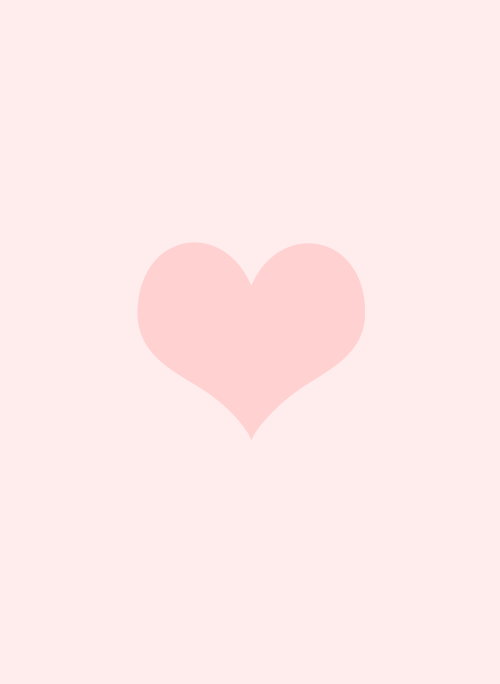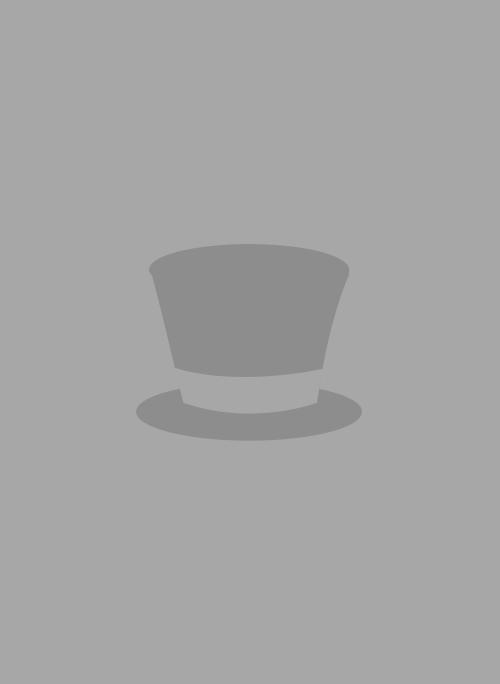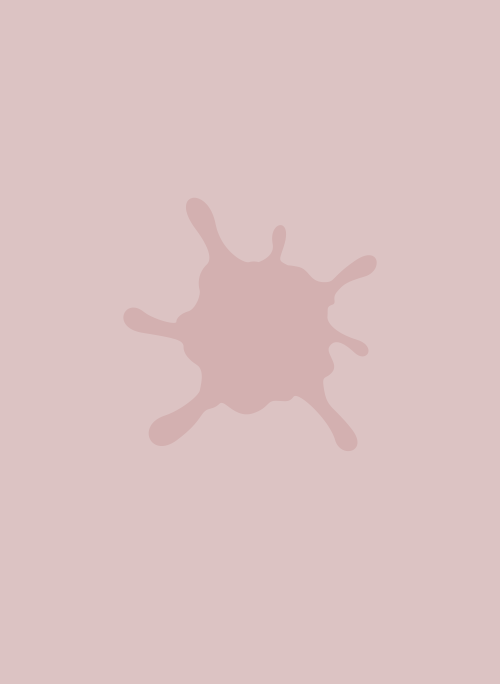不完全な完全犯罪ZERO
ゴールドスカルのペンダントヘッドの秘密
マネージャーは音楽系の専門学校で業界に必要な知識を習得し、卒業後小規模のプロダクションに入った。
大手でも就職活動はしていた。でも内定をもらえなかったのだ。
最初の仕事は売れない歌手の施設巡りの同行だった。
スーパー銭湯内にある小さなステージでのカラオケ大会や、老人ホームなどでのコンサート。それは憧れていた華やかな世界とはまるっきり違っていた。
夢は破れたと思っていた。そんな時、訪れた施設で木暮敦士と出会ったのだ。
一目惚れだった。木暮敦士にマネージャーは恋をしてしまったのだ。だから恋心を隠して木暮敦士に接近し、所属していたプロダクションへ誘ったのだ。
原田学を一緒に勧誘したのは下心を見抜かれなくするためだった。
でもマネージャーは原田学のギタリストとしての才能に着目して、ロックバンドとして売り出すことを社長に進言したのだった。
早速ライブ活動をすることにした。
練習場所は専門学校時代の仲間が働いているスタジオだった。
マネージャーの力で安くしてもらった訳でもないのに、低料金だったからプロダクションとしては両手を上げて喜んだようだ。
だからマネージャーは少しずつ自分の意見も言えるようになったのだ。
CDが売れない時代にヒットした楽曲は着うたやカラオケにもなった。
木暮敦士が亡くなった時にはカラオケランキングトップにも輝いた。
マネージャーは悲しみの中に栄光を掴んだのだった。
傍に原田学が居てくれたことも一因だったに違いなかった。
原田学の優しさがマネージャーを癒し、木暮敦士を手に掛けてしまった悪夢の事件を遠退けてくれたのだろう。
ボンドー原っぱの恋人はやはりマネージャーだったに違いない。
木暮敦士亡き後、マネージャーは原田学の誠実な態度に救われたのだ。
意気消沈しているマネージャーを原田学はケアしてくれたのだ。
親友だった木暮敦士の死は原田学自身でも辛いはずなのに、彼は優しかった。
その人柄に惚れ込んでしまったのだった。
木暮敦士を殺した犯人がマネージャーだと夢にも思わない原田学。
だから付いていく決意をしたのだった。
マネージャーは原田学のギターテクニックを売り出そうとしていた。
木暮敦士のいたロックグループが売れたのは、バックに確かな技術のギタリストがいたからなのだ。
マネージャーはその事実を知っていた。
それでも、木暮敦士に賭けてしまったのだった。
その事実を反省し、気持ちを新たに他のメンバーのために立ち上がったのだ。
それが自分の不注意から死に追いやってしまった木暮敦士への追悼でもあったのだ。
でも社長の方針でコミカルなバンドを目指すことになってしまったのだった。
ボンドー原っぱと言う名前にマネージャーは抵抗があった。
だから必死に止めようとしたのだ。
でも覆らなかった。
物の試しにと出場した視聴者参加型テレビ番組で大ウケしてしまったからだった。
社長はそれで気を良くして、本格的に売り出したのだ。
そんな時MAIさんに彼氏が出来たことを知ったのだ。
未だに自分が殺した木暮敦士のことが忘れられないマネージャー。
又ストーカーのようにMAIさんを付け回すようになったのだった。マネージャーは自分に見せ付けるためにスキンヘッドにしたことを知っていた。
それ故殺してしまったのだと恨んでいたのだ。だから尚更付け回していたのだった。
MAIさんと隣り合わせたカラオケルームで、マネージャーは新恋人の歌声を聴いたのだ。
『欲しい』と思った。
心血を注げる相手に又出逢えた奇跡に震えた。
その途端、マネージャーの心の中にはもう原田学は居なくなっていた。
その代わりに、邪魔な存在としてその大半を占めるようになっていったのだ。
ボンドー原っぱなんて奇妙な名前の原田学は恋人でも何でもなくなっていたのだった。
MAIさんの実家が美容院だと知っていたマネージャーは、其処が居抜きで売りに出されている情報を得て利用することにした。
だから原田学を其処に移動させようとしたのだ。
方法は車椅子だった。
マネージャーと原田学が出会ったのは介護施設だ。たまには車椅子移動も頼まれるから扱いには馴れていたのだ。
スタジオで原田学は眠らされていた。
マネージャーは用意したドリンクの中に睡眠薬を混入した。
社長から叱責された原田学はそれを一気飲みしてしまったのだった。
それは何時もドリンクではなく、アルコールだった。
だから原田学は全く気付かない内に故郷まで連れて来られたのだ。
マネージャーは見よう見まねで原田学の頭をスキンヘッドにしたのだ。
そして行動を監視した。
イワキ探偵事務所を訪ねた時には驚いた。
でもその前に携帯に保存してあった画像は全て消したから安心していたのだ。
まさか、木暮敦士が恋人だったMAIさんの画像を名刺に入れていたとも思わずに……
『すいません遅くなりまして。木暮を殺したの犯人が逮捕されたと聞きまして……』
あの時、犯人しか知り得ない事柄を言った。刑事が少し首を傾げたので気になって聞いてみたら、警察は連続殺人だとは言っていなかったのだ。
原田学殺害の罪を被せることさえ出来れば……
殺人が発覚した時、マネージャーはMAIさんを逮捕させようと目論んだ。
だからボンドー原っぱの恋人だと噂を流したのだ。
それはアマチュアロックバンドのボーカルを獲得する手段でもあったのだ。
木暮敦士が死んだのは、MAIさんがあれを買ったからだと思っていた。
愛する人を殺してしまったのは、MAIさんが悪巧みをしたせいだと逆恨みしたのだ。
原田学の葬儀の日、ゴールドスカルのペンダントヘッドを彼に渡したのはマネージャーだった。
マネージャーはMAIさんの反響を見たかったのだ。
ゴールドスカルのペンダントヘッドは、きっと木暮敦士との思い出に繋がる。
そうなれば、彼はMAIさんから離れるに違いないと踏んだのだ。
きっと二人は別れる。
マネージャーはそう思い込んでいた。
でもマネージャーはもう一つミスをおかした。
俺に霊感があると知らないマネージャーは原田学の首にあのゴールドスカルのペンダントヘッドを掛けたのだ。
もっとも、いきなりのスキンヘッドに驚いた原田学が木暮の兄貴の携帯に電話するとは思ってもいなかったのだ。
折りさえあれば何時でも殺害しようと、マネージャーは原田学の後を付けた。
でも原田学が向かった先はバス停でも駅でもなかった。
原田学が着いた先はイワキ探偵事務所だったのだ。
木暮の兄貴の携帯電話に残った映像。
パソコンに保存されていたボンドー原っぱが隠し撮りした映像。
それらを見比べている内に俺は何か違和感を覚えた。
俺はどうして彼女に会いたいと懇願した。
「あのペンダントヘッドは私が買ってしまっておいた物に間違いありません」
MAIさんは俺の前でそう言った。
そんなことを聞きたくて刑事に伝言した訳ではない。
俺はただ、彼女を助けてやりたかったのだ。
俺の霊感全てを使って、木暮敦士がMAIさんに伝えたかったことを代弁したかったのだ。
MAIさんは道端で男性の売っていたゴールドスカルのペンダントヘッドを見つけた。
いや、魅入られたと言うのが正解かも知れない。
それは握り拳位い。
流れた胎児の大きさだったのだ。
全身が震える。
ゴールドスカルから目が離せない。
MAIさんはゴールドスカルが流れた胎児の生まれ変りのように感じていたのだ。
MAIさんは遂にそれを愛しそうに掌に乗せたのだ。
我が子が戻ってきた。
MAIさんはそう思ったのだ。
「でも木暮には内緒にしておきたかったの。彼は私が妊娠した事実も知らなかったから……」
「それを木暮の兄貴が見つけて、プレゼントだと思ってしまったのか?」
「だと思います」
辛そうにMAIさんは言った。
ストーカーはマネージャーだった。木暮敦士の時も、原田学の時も。
原田学は木暮敦士がスキンヘッドで殺された事実を知っていた。
何故なら彼はあの現場を見ていたからだ。
ライブイベントパフォーマンスで、あのデパートにギタリストとして参加していたからだ。
だから原田学は自分がスキンヘッドになっていると気付いた時震え上がったのだろう。
その事実を知らされた彼氏は押し黙ってしまった。
もしかしたら、ラブデスゲームの被害者になるかも知れなかったからだ。
自分が好きになった男の気持ちを掴むためには手段を選ばない。
彼女もきっと邪悪になっていたのだろう。
MAIさんやみずほは別として、女性は怖いと思った。
でも何時かは俺も恋をしたい。
みずほのことを忘れるつもりはないけれど、いつまでもウジウジしていたらみずほが悲しむと思ったんだ。
「義姉貴の彼、何て言ってた?」
木暮はMAIさんの彼のことを聞きたいらしい。
秘密厳守なんだけど、叔父の許可はもらっていた。
「あのマネージャーからスキンヘッドを勧められた時、あのペンダントヘッドも託されたそうだ。『彼女の気持ちを確かめるには、これをするのが一番よ』そう言ってたそうだ」
「それじゃあ……」
「うん。だから事件の全容を知った時総毛立ったんだって、スキンヘッドだけどな」
「自分が好きになった男の気持ちを掴むためには手段を選ばない女か」
「そんな彼女にマネージメントを頼もうとしていたのだから……」
俺は染々と呟いた。
街はクリスマスツリーが輝いている。
駅前広場に飾り付けられたイルミネーションが、急ぎ足の人も楽しませている。
俺に新しい恋人でも出来たらきっと二人で……
何て思いながらそんな風景を木暮と見ていた。
「さあ、早く行こうよ」
木暮が急かす。
そうなんだ。今日は少し早目のクリスマス。
事件も解決したし、依頼人だった原田守の母親にも報告出来たからだ。
本物のクリスマスは其々の家族とって言うことで今日に決まったのだ。
本番までまだかなりあるけど暇な時にってことなのだ。
ま、年がら年中似たようなものだけどね。
でも一つ困ったことが起きた。
すっかり女装に木暮が嵌まってしまったのだ。
「今後はもっと上手くやるから又手伝わせてくれ」
木暮がはそう言いながら叔父にウインクした。
(えっー!? もしかしたら俺の相棒? やだ、益々サッカーが出来なくなる。あぁ、俺の夢が……)
「なぁ、また女子会に潜入しようよ」
木暮が俺の耳元で囁く。
「でも学校に知れたら大変だぞ」
俺はさも知り尽くしたように言ってやった。
木暮を見ると、相変わらず叔母さんのワンピースに目を輝かせていた。
「女装なんて、仕事だけで充分だ」
俺はそう言いながらも楽しそうな木暮とワンピースを見ていた。
(そうだよ。浮かれている場合じゃなかった。叔母さんの敵討ちが先決だったんだ)
形見のワンピースにそっと触れる。
(叔母さん待ってて、必ず叔父さんと一緒に犯人を探して出してみせるから)
そっと叔父を見る。
優しそうな眼差しが、余計に悲しく映る。
その途端。
心がジンジンと疼き、新たな闘志に掻き乱さられていく。
俺は改めて、事件解決を誓っていた。
そんなある日。
MAIさんから女子会への招待状がイワキ探偵事務所に届いた。
MAIさんは俺達を女装をさせて楽しもうとしていたのだ。
ま、木暮はすっかりうつつを抜かせていたけどね。
「今後はもっと上手くやるから、なあ瑞穂一緒に行こうよー」
「お前解っているのか? 主催するのはMAIさんなんだそ。お前の兄貴の奥さんだった人だぞ」
「うん。解ってる。それが何だって言うんだ」
木暮はすかっり我を忘れて、女装出来る喜びに浮かれていた。
「瑞穂の叔父様、お願いしますね」
木暮はそう言いながら叔父にウインクした。
「又お仕事お手伝い致しますので……」
その発言にドキンとした。
それは俺のエースになるという夢が遠退くことを意味していた。
「なぁ、また女装しようよ」
木暮が俺の耳元で囁く。
「やだ。絶対にやだ」
MAIさんに弄ばれことが解っていた俺は突っぱねようとあれこれ考えていた。
(きっとからかわれる)
そう思いつつ招待状を良く見てみた。
「あれっ、これ叔父さんも一緒に。ってことだ」
「どれどれ」
叔父は俺が見ていた招待状を強引に奪い取った。
「あっ、本当だ。俺達なら解るけど、似合わねえ」
木暮は腹を抱えて笑い出した。
「そう言えば叔父さん。女装したことあったね」
「えっ、何時だ?」
「ほら、水村さんの……。ま、あの時は俺だけが女装する羽目になったけど」
俺はそう言いながら考えた。
結局、水村さんは自首してくれなかったなと。
「あ、水村さんなら引っ越したよ。瑞穂によろしくって伝言されていたんだ。今回のこともあって、すっかり忘れていた」
「えっ、そうなの?」
「あっ、水村さんって例の?」
「そうだよ。俺も叔父さんも、罪状通りに和也さんが警察官を殺した真犯人だと思いたかったんだ」
「完全犯罪だな? って瑞穂は言っていたけど結局、その通りだったな」
「いいや、きっと自首してくれるさ」
俺は強気だった。
「瑞穂の女装はあの時が最初だったな」
「だって、叔父さんがワンピースを着ようとしていたから見るにみかねてだ」
「瑞穂のお陰で真相は把握出来たけど……」
「だったら俺も手伝う」
木暮が手を出して三人の手を組ませた。
その行為が嬉しくて思わず涙腺が弱くなった。
その時、俺達は同士と言う絆で結ばれている。そう感じた。
結局叔父も女装することになった。
それはそれは抱腹絶倒の女子会になるはずだった。
聞いた話によると、男性も女装さえすれば会場には入れるそうだ。
でもカフェに入る前に事は起こった。
それは突然だった。
みずほのコンパクトが熱を帯び、それと同時にワクワクし始めた。
原因不明の挙動不審状態に俺は陥ったのだ。
何かに締め付けられているような感覚で、仕方なく胸を抑えた。
その時、着ていたワンピースのせいだと気付いた。
(もしかしたら叔母さんが……)
そう思いながら周りを見回すと、見知った顔に出会した。
それは叔父が長年探していたラジオと呼ばれていた人だった。
(この人は叔母さんを殺した犯人じゃない)
俺の深部が反応した。
叔母さんのワンピースがその人を懐かしがっていたんだ。
だからワクワクしていたんだ。
(自分を殺した容疑者だとされた人なんだよ。もし本当に殺られていたのならこんな風には感じられないはずだ)
俺は叔父にそっと目配せをして耳打ちした。
勿論、俺の霊感が真犯人ではないと告げた。とは言っておいた。
叔父は目を白黒させながらその人を見ていた。
ラジオと呼ばれたその人は、目の前にいる女性が叔父だと気付くはずもなく立ち去っていた。
俺はホッとしていた。
女装なんて本当はイヤでイヤで堪らなかったんだ。
でもそのお陰で、叔父が誤解をしていたと指摘出来たのだ。
二人の関係を修復出来ないとは思っているけど、少しでも心が軽くなったのではないのかと感じていた。
結局、女子会は大成功のうちに幕を下ろした。
MAIさんが何故女装した人も良しとしたのか?
それはクリスマスイヴに、家族立ち合いの元で結婚式を挙げるためだった。
お相手は勿論、あのロックミュージシャンだ。
「やっぱりロック好きだね」
「それも、相当のパンクだな」
叔父の目配せの先には、俺の両親もいた。
MAIさんはヘアーメイクアーチストの力をフルに発揮して、其処にいた男性全員をビジュアル系に仕立てたのだ。
でも父はヘビメタに相当近かったのだ。
「義兄貴の格好……」
自分のことは棚に上げて、叔父は堪らずに笑い出した。
「お前の親とは思えないほどのゴツさだな」
「うん。ねぇ叔父さん知ってる。母はそのゴツさ、じゃぁない男らしさに惚れたんだって」
俺は母の秘密を暴露していた。
「勿論だ。あの頃、サッカーのエースを目指して猛特訓をしていた姿に……あっ」
「えっ!?」
そうだったのか?
だから俺に教えてくれたのかな?
父は何も語らず黙々とボールを蹴ってくれていた。
(そうか? だから俺のそんな姿にみずほも惚れてくれたのか?)
その途端に胸が張り裂けそうになった。
恋人になって以来、初めてみずほの居ないクリスマス……
その哀しさにこれから押し潰されそうになるはずだからだ。
又クローゼットの中で泣く羽目になる。
それは俺の精一杯の親孝行だ。
叔父の真似をするつもりはないけれど、心配を掛けたくないんだ。
でも何故か俺は叔父の発言が気になっていた。
あの、『あっ』が。
「なぁ瑞穂。さっきの発言は撤回させてくれ。義兄貴が……」
「あっ、サッカー部のエースになるために頑張っていたってこと?」
俺の質問に叔父は頷いた。
「それもあるけど、瑞穂に何時も言っていたろ?」
「あっー。『サッカーなんか辞めて仕事を手伝ってくれ』ってこと?」
「義兄貴も同じだったけど、やはり手伝ってほしいと思って……」
「言っておきますが、俺もサッカーのエースを目指して猛特訓 しているよ」
「それは承知の上です」
「あのー、誰か忘れていませんか? 俺なら暇しているよ」
抜群のタイミングで木暮が言った。
ストーカーはマネージャーだった。
木暮敦士の時も、原田守の時も。
原田守は木暮敦士がスキンヘッドで殺された事実を知っていた。
何故なら彼はあの現場を見ていたからだ。
ライブイベントパフォーマンスで、あのデパートにギタリストとして参加していたからだ。
だから原田守は自分がスキンヘッドになっていると気付いた時震え上がったのだ。
でも彼は犯人がマネージャーだと知らないはずだ。
もしかしたらMAIさんだと考えたのかも知れない。
だから敢えて、あの写真を示して彼女だと言ったのかも知れない。
MAIさんやみずほは別として、女性は怖いと思った。
でも何時かは俺も恋をしたい。
みずほのことを忘れるつもりはないけれど、いつまでもウジウジしていたらみずほが悲しむと思ったんだ。
「結局振り出しか?」
叔父が染々呟いた。
「さっきの人はラジオ。無銭飲食の隠語なんだ」
「瑞穂から聞いているけど、でもその頃だったら無線よりトランシーバーが普通だろう?」
木暮の発言に叔父は笑い出した。
「お前達似てるな。流石相棒だ」
叔父は更に笑った。
「暴走族だと言うだけで店主に通報されたんだって。でも違った。スリに遭っていたんだ。店の脇から現金を抜かれた財布が見つかったんで難を逃れたそうだ」
「アイツが服役した事件の捜査だっていい加減なものだった。ホンボシは初犯だってことで執行猶予になったけど、アイツは罪を認めなかったから実刑だった。本当に無実だ。でも俺には何も出来なかった」
今度は泣き出した。
無理もない。
だって、奥さんを殺したのがその人だと思い込んでいたからだ。
「叔父さんはその人が事件現場に居なかったことを知ってるんだって、それなのに寄って集ってアイツを共犯に仕立て上げたんだよ。ホンボシの自供だけで……」
俺の言葉を聞いて、叔父さんが握り拳を左の手のひらで包んだ。
「こうやって、やっと自分を抑えている。叔父さんの痛みはみずほを失った俺には解る気がするんだ」
「瑞穂……」
今度は木暮も泣き出した。
俺達は其々、大切な人を亡くしている。
だから尚一層深い絆で結ばれていると感じた。
「出所した後でアイツは奥さんの行方を探した。でも見つけ出すことは出来なかったらしい。だから怒りの矛先は庇ってくれなかった俺に向かったんだ」
「叔父さんは長年、奥さんを殺した犯人だと思っていたんだ。だから嬉しいんだ。俺の霊感はこの日のためではなかったのでは俺は思ってな」
俺は力説していた。
「熊谷のアパートには思い出がいっぱい詰まっている。だから其処に居るんだよ」
「本当はアイツを信じていたんだ。だから嬉しい。瑞穂の霊感は正しいと思う。彼女はアイツを本当に心配していたからな。だから毒牙にかかった時、怒りが収められなかったんだ」
叔父は辛そうに言った。
俺達はそれ以上聞けなくなった。
叔父は心の奥底では否定しながらも、真犯人だと思っていたのだ。
俺はみずほ死によって霊感を授けられた。
それはきっとこのためではなかったのだろうか?
みずほはきっと、事件の真相を……
ラジオと呼ばれた人が真犯人じゃないって伝えたかったのではないのだろうか?
ふと、俺は思った。
「叔父さん。あの人が真犯人じゃなくて良かったね。今日はクリスマスイヴだからもう帰るけど……」
本当は叔父とずっと居たい。
同じ痛みを少しでも紛らわせることが出来るかも知れないから……
でもサッカーだけは辞められないんだ。
大手でも就職活動はしていた。でも内定をもらえなかったのだ。
最初の仕事は売れない歌手の施設巡りの同行だった。
スーパー銭湯内にある小さなステージでのカラオケ大会や、老人ホームなどでのコンサート。それは憧れていた華やかな世界とはまるっきり違っていた。
夢は破れたと思っていた。そんな時、訪れた施設で木暮敦士と出会ったのだ。
一目惚れだった。木暮敦士にマネージャーは恋をしてしまったのだ。だから恋心を隠して木暮敦士に接近し、所属していたプロダクションへ誘ったのだ。
原田学を一緒に勧誘したのは下心を見抜かれなくするためだった。
でもマネージャーは原田学のギタリストとしての才能に着目して、ロックバンドとして売り出すことを社長に進言したのだった。
早速ライブ活動をすることにした。
練習場所は専門学校時代の仲間が働いているスタジオだった。
マネージャーの力で安くしてもらった訳でもないのに、低料金だったからプロダクションとしては両手を上げて喜んだようだ。
だからマネージャーは少しずつ自分の意見も言えるようになったのだ。
CDが売れない時代にヒットした楽曲は着うたやカラオケにもなった。
木暮敦士が亡くなった時にはカラオケランキングトップにも輝いた。
マネージャーは悲しみの中に栄光を掴んだのだった。
傍に原田学が居てくれたことも一因だったに違いなかった。
原田学の優しさがマネージャーを癒し、木暮敦士を手に掛けてしまった悪夢の事件を遠退けてくれたのだろう。
ボンドー原っぱの恋人はやはりマネージャーだったに違いない。
木暮敦士亡き後、マネージャーは原田学の誠実な態度に救われたのだ。
意気消沈しているマネージャーを原田学はケアしてくれたのだ。
親友だった木暮敦士の死は原田学自身でも辛いはずなのに、彼は優しかった。
その人柄に惚れ込んでしまったのだった。
木暮敦士を殺した犯人がマネージャーだと夢にも思わない原田学。
だから付いていく決意をしたのだった。
マネージャーは原田学のギターテクニックを売り出そうとしていた。
木暮敦士のいたロックグループが売れたのは、バックに確かな技術のギタリストがいたからなのだ。
マネージャーはその事実を知っていた。
それでも、木暮敦士に賭けてしまったのだった。
その事実を反省し、気持ちを新たに他のメンバーのために立ち上がったのだ。
それが自分の不注意から死に追いやってしまった木暮敦士への追悼でもあったのだ。
でも社長の方針でコミカルなバンドを目指すことになってしまったのだった。
ボンドー原っぱと言う名前にマネージャーは抵抗があった。
だから必死に止めようとしたのだ。
でも覆らなかった。
物の試しにと出場した視聴者参加型テレビ番組で大ウケしてしまったからだった。
社長はそれで気を良くして、本格的に売り出したのだ。
そんな時MAIさんに彼氏が出来たことを知ったのだ。
未だに自分が殺した木暮敦士のことが忘れられないマネージャー。
又ストーカーのようにMAIさんを付け回すようになったのだった。マネージャーは自分に見せ付けるためにスキンヘッドにしたことを知っていた。
それ故殺してしまったのだと恨んでいたのだ。だから尚更付け回していたのだった。
MAIさんと隣り合わせたカラオケルームで、マネージャーは新恋人の歌声を聴いたのだ。
『欲しい』と思った。
心血を注げる相手に又出逢えた奇跡に震えた。
その途端、マネージャーの心の中にはもう原田学は居なくなっていた。
その代わりに、邪魔な存在としてその大半を占めるようになっていったのだ。
ボンドー原っぱなんて奇妙な名前の原田学は恋人でも何でもなくなっていたのだった。
MAIさんの実家が美容院だと知っていたマネージャーは、其処が居抜きで売りに出されている情報を得て利用することにした。
だから原田学を其処に移動させようとしたのだ。
方法は車椅子だった。
マネージャーと原田学が出会ったのは介護施設だ。たまには車椅子移動も頼まれるから扱いには馴れていたのだ。
スタジオで原田学は眠らされていた。
マネージャーは用意したドリンクの中に睡眠薬を混入した。
社長から叱責された原田学はそれを一気飲みしてしまったのだった。
それは何時もドリンクではなく、アルコールだった。
だから原田学は全く気付かない内に故郷まで連れて来られたのだ。
マネージャーは見よう見まねで原田学の頭をスキンヘッドにしたのだ。
そして行動を監視した。
イワキ探偵事務所を訪ねた時には驚いた。
でもその前に携帯に保存してあった画像は全て消したから安心していたのだ。
まさか、木暮敦士が恋人だったMAIさんの画像を名刺に入れていたとも思わずに……
『すいません遅くなりまして。木暮を殺したの犯人が逮捕されたと聞きまして……』
あの時、犯人しか知り得ない事柄を言った。刑事が少し首を傾げたので気になって聞いてみたら、警察は連続殺人だとは言っていなかったのだ。
原田学殺害の罪を被せることさえ出来れば……
殺人が発覚した時、マネージャーはMAIさんを逮捕させようと目論んだ。
だからボンドー原っぱの恋人だと噂を流したのだ。
それはアマチュアロックバンドのボーカルを獲得する手段でもあったのだ。
木暮敦士が死んだのは、MAIさんがあれを買ったからだと思っていた。
愛する人を殺してしまったのは、MAIさんが悪巧みをしたせいだと逆恨みしたのだ。
原田学の葬儀の日、ゴールドスカルのペンダントヘッドを彼に渡したのはマネージャーだった。
マネージャーはMAIさんの反響を見たかったのだ。
ゴールドスカルのペンダントヘッドは、きっと木暮敦士との思い出に繋がる。
そうなれば、彼はMAIさんから離れるに違いないと踏んだのだ。
きっと二人は別れる。
マネージャーはそう思い込んでいた。
でもマネージャーはもう一つミスをおかした。
俺に霊感があると知らないマネージャーは原田学の首にあのゴールドスカルのペンダントヘッドを掛けたのだ。
もっとも、いきなりのスキンヘッドに驚いた原田学が木暮の兄貴の携帯に電話するとは思ってもいなかったのだ。
折りさえあれば何時でも殺害しようと、マネージャーは原田学の後を付けた。
でも原田学が向かった先はバス停でも駅でもなかった。
原田学が着いた先はイワキ探偵事務所だったのだ。
木暮の兄貴の携帯電話に残った映像。
パソコンに保存されていたボンドー原っぱが隠し撮りした映像。
それらを見比べている内に俺は何か違和感を覚えた。
俺はどうして彼女に会いたいと懇願した。
「あのペンダントヘッドは私が買ってしまっておいた物に間違いありません」
MAIさんは俺の前でそう言った。
そんなことを聞きたくて刑事に伝言した訳ではない。
俺はただ、彼女を助けてやりたかったのだ。
俺の霊感全てを使って、木暮敦士がMAIさんに伝えたかったことを代弁したかったのだ。
MAIさんは道端で男性の売っていたゴールドスカルのペンダントヘッドを見つけた。
いや、魅入られたと言うのが正解かも知れない。
それは握り拳位い。
流れた胎児の大きさだったのだ。
全身が震える。
ゴールドスカルから目が離せない。
MAIさんはゴールドスカルが流れた胎児の生まれ変りのように感じていたのだ。
MAIさんは遂にそれを愛しそうに掌に乗せたのだ。
我が子が戻ってきた。
MAIさんはそう思ったのだ。
「でも木暮には内緒にしておきたかったの。彼は私が妊娠した事実も知らなかったから……」
「それを木暮の兄貴が見つけて、プレゼントだと思ってしまったのか?」
「だと思います」
辛そうにMAIさんは言った。
ストーカーはマネージャーだった。木暮敦士の時も、原田学の時も。
原田学は木暮敦士がスキンヘッドで殺された事実を知っていた。
何故なら彼はあの現場を見ていたからだ。
ライブイベントパフォーマンスで、あのデパートにギタリストとして参加していたからだ。
だから原田学は自分がスキンヘッドになっていると気付いた時震え上がったのだろう。
その事実を知らされた彼氏は押し黙ってしまった。
もしかしたら、ラブデスゲームの被害者になるかも知れなかったからだ。
自分が好きになった男の気持ちを掴むためには手段を選ばない。
彼女もきっと邪悪になっていたのだろう。
MAIさんやみずほは別として、女性は怖いと思った。
でも何時かは俺も恋をしたい。
みずほのことを忘れるつもりはないけれど、いつまでもウジウジしていたらみずほが悲しむと思ったんだ。
「義姉貴の彼、何て言ってた?」
木暮はMAIさんの彼のことを聞きたいらしい。
秘密厳守なんだけど、叔父の許可はもらっていた。
「あのマネージャーからスキンヘッドを勧められた時、あのペンダントヘッドも託されたそうだ。『彼女の気持ちを確かめるには、これをするのが一番よ』そう言ってたそうだ」
「それじゃあ……」
「うん。だから事件の全容を知った時総毛立ったんだって、スキンヘッドだけどな」
「自分が好きになった男の気持ちを掴むためには手段を選ばない女か」
「そんな彼女にマネージメントを頼もうとしていたのだから……」
俺は染々と呟いた。
街はクリスマスツリーが輝いている。
駅前広場に飾り付けられたイルミネーションが、急ぎ足の人も楽しませている。
俺に新しい恋人でも出来たらきっと二人で……
何て思いながらそんな風景を木暮と見ていた。
「さあ、早く行こうよ」
木暮が急かす。
そうなんだ。今日は少し早目のクリスマス。
事件も解決したし、依頼人だった原田守の母親にも報告出来たからだ。
本物のクリスマスは其々の家族とって言うことで今日に決まったのだ。
本番までまだかなりあるけど暇な時にってことなのだ。
ま、年がら年中似たようなものだけどね。
でも一つ困ったことが起きた。
すっかり女装に木暮が嵌まってしまったのだ。
「今後はもっと上手くやるから又手伝わせてくれ」
木暮がはそう言いながら叔父にウインクした。
(えっー!? もしかしたら俺の相棒? やだ、益々サッカーが出来なくなる。あぁ、俺の夢が……)
「なぁ、また女子会に潜入しようよ」
木暮が俺の耳元で囁く。
「でも学校に知れたら大変だぞ」
俺はさも知り尽くしたように言ってやった。
木暮を見ると、相変わらず叔母さんのワンピースに目を輝かせていた。
「女装なんて、仕事だけで充分だ」
俺はそう言いながらも楽しそうな木暮とワンピースを見ていた。
(そうだよ。浮かれている場合じゃなかった。叔母さんの敵討ちが先決だったんだ)
形見のワンピースにそっと触れる。
(叔母さん待ってて、必ず叔父さんと一緒に犯人を探して出してみせるから)
そっと叔父を見る。
優しそうな眼差しが、余計に悲しく映る。
その途端。
心がジンジンと疼き、新たな闘志に掻き乱さられていく。
俺は改めて、事件解決を誓っていた。
そんなある日。
MAIさんから女子会への招待状がイワキ探偵事務所に届いた。
MAIさんは俺達を女装をさせて楽しもうとしていたのだ。
ま、木暮はすっかりうつつを抜かせていたけどね。
「今後はもっと上手くやるから、なあ瑞穂一緒に行こうよー」
「お前解っているのか? 主催するのはMAIさんなんだそ。お前の兄貴の奥さんだった人だぞ」
「うん。解ってる。それが何だって言うんだ」
木暮はすかっり我を忘れて、女装出来る喜びに浮かれていた。
「瑞穂の叔父様、お願いしますね」
木暮はそう言いながら叔父にウインクした。
「又お仕事お手伝い致しますので……」
その発言にドキンとした。
それは俺のエースになるという夢が遠退くことを意味していた。
「なぁ、また女装しようよ」
木暮が俺の耳元で囁く。
「やだ。絶対にやだ」
MAIさんに弄ばれことが解っていた俺は突っぱねようとあれこれ考えていた。
(きっとからかわれる)
そう思いつつ招待状を良く見てみた。
「あれっ、これ叔父さんも一緒に。ってことだ」
「どれどれ」
叔父は俺が見ていた招待状を強引に奪い取った。
「あっ、本当だ。俺達なら解るけど、似合わねえ」
木暮は腹を抱えて笑い出した。
「そう言えば叔父さん。女装したことあったね」
「えっ、何時だ?」
「ほら、水村さんの……。ま、あの時は俺だけが女装する羽目になったけど」
俺はそう言いながら考えた。
結局、水村さんは自首してくれなかったなと。
「あ、水村さんなら引っ越したよ。瑞穂によろしくって伝言されていたんだ。今回のこともあって、すっかり忘れていた」
「えっ、そうなの?」
「あっ、水村さんって例の?」
「そうだよ。俺も叔父さんも、罪状通りに和也さんが警察官を殺した真犯人だと思いたかったんだ」
「完全犯罪だな? って瑞穂は言っていたけど結局、その通りだったな」
「いいや、きっと自首してくれるさ」
俺は強気だった。
「瑞穂の女装はあの時が最初だったな」
「だって、叔父さんがワンピースを着ようとしていたから見るにみかねてだ」
「瑞穂のお陰で真相は把握出来たけど……」
「だったら俺も手伝う」
木暮が手を出して三人の手を組ませた。
その行為が嬉しくて思わず涙腺が弱くなった。
その時、俺達は同士と言う絆で結ばれている。そう感じた。
結局叔父も女装することになった。
それはそれは抱腹絶倒の女子会になるはずだった。
聞いた話によると、男性も女装さえすれば会場には入れるそうだ。
でもカフェに入る前に事は起こった。
それは突然だった。
みずほのコンパクトが熱を帯び、それと同時にワクワクし始めた。
原因不明の挙動不審状態に俺は陥ったのだ。
何かに締め付けられているような感覚で、仕方なく胸を抑えた。
その時、着ていたワンピースのせいだと気付いた。
(もしかしたら叔母さんが……)
そう思いながら周りを見回すと、見知った顔に出会した。
それは叔父が長年探していたラジオと呼ばれていた人だった。
(この人は叔母さんを殺した犯人じゃない)
俺の深部が反応した。
叔母さんのワンピースがその人を懐かしがっていたんだ。
だからワクワクしていたんだ。
(自分を殺した容疑者だとされた人なんだよ。もし本当に殺られていたのならこんな風には感じられないはずだ)
俺は叔父にそっと目配せをして耳打ちした。
勿論、俺の霊感が真犯人ではないと告げた。とは言っておいた。
叔父は目を白黒させながらその人を見ていた。
ラジオと呼ばれたその人は、目の前にいる女性が叔父だと気付くはずもなく立ち去っていた。
俺はホッとしていた。
女装なんて本当はイヤでイヤで堪らなかったんだ。
でもそのお陰で、叔父が誤解をしていたと指摘出来たのだ。
二人の関係を修復出来ないとは思っているけど、少しでも心が軽くなったのではないのかと感じていた。
結局、女子会は大成功のうちに幕を下ろした。
MAIさんが何故女装した人も良しとしたのか?
それはクリスマスイヴに、家族立ち合いの元で結婚式を挙げるためだった。
お相手は勿論、あのロックミュージシャンだ。
「やっぱりロック好きだね」
「それも、相当のパンクだな」
叔父の目配せの先には、俺の両親もいた。
MAIさんはヘアーメイクアーチストの力をフルに発揮して、其処にいた男性全員をビジュアル系に仕立てたのだ。
でも父はヘビメタに相当近かったのだ。
「義兄貴の格好……」
自分のことは棚に上げて、叔父は堪らずに笑い出した。
「お前の親とは思えないほどのゴツさだな」
「うん。ねぇ叔父さん知ってる。母はそのゴツさ、じゃぁない男らしさに惚れたんだって」
俺は母の秘密を暴露していた。
「勿論だ。あの頃、サッカーのエースを目指して猛特訓をしていた姿に……あっ」
「えっ!?」
そうだったのか?
だから俺に教えてくれたのかな?
父は何も語らず黙々とボールを蹴ってくれていた。
(そうか? だから俺のそんな姿にみずほも惚れてくれたのか?)
その途端に胸が張り裂けそうになった。
恋人になって以来、初めてみずほの居ないクリスマス……
その哀しさにこれから押し潰されそうになるはずだからだ。
又クローゼットの中で泣く羽目になる。
それは俺の精一杯の親孝行だ。
叔父の真似をするつもりはないけれど、心配を掛けたくないんだ。
でも何故か俺は叔父の発言が気になっていた。
あの、『あっ』が。
「なぁ瑞穂。さっきの発言は撤回させてくれ。義兄貴が……」
「あっ、サッカー部のエースになるために頑張っていたってこと?」
俺の質問に叔父は頷いた。
「それもあるけど、瑞穂に何時も言っていたろ?」
「あっー。『サッカーなんか辞めて仕事を手伝ってくれ』ってこと?」
「義兄貴も同じだったけど、やはり手伝ってほしいと思って……」
「言っておきますが、俺もサッカーのエースを目指して猛特訓 しているよ」
「それは承知の上です」
「あのー、誰か忘れていませんか? 俺なら暇しているよ」
抜群のタイミングで木暮が言った。
ストーカーはマネージャーだった。
木暮敦士の時も、原田守の時も。
原田守は木暮敦士がスキンヘッドで殺された事実を知っていた。
何故なら彼はあの現場を見ていたからだ。
ライブイベントパフォーマンスで、あのデパートにギタリストとして参加していたからだ。
だから原田守は自分がスキンヘッドになっていると気付いた時震え上がったのだ。
でも彼は犯人がマネージャーだと知らないはずだ。
もしかしたらMAIさんだと考えたのかも知れない。
だから敢えて、あの写真を示して彼女だと言ったのかも知れない。
MAIさんやみずほは別として、女性は怖いと思った。
でも何時かは俺も恋をしたい。
みずほのことを忘れるつもりはないけれど、いつまでもウジウジしていたらみずほが悲しむと思ったんだ。
「結局振り出しか?」
叔父が染々呟いた。
「さっきの人はラジオ。無銭飲食の隠語なんだ」
「瑞穂から聞いているけど、でもその頃だったら無線よりトランシーバーが普通だろう?」
木暮の発言に叔父は笑い出した。
「お前達似てるな。流石相棒だ」
叔父は更に笑った。
「暴走族だと言うだけで店主に通報されたんだって。でも違った。スリに遭っていたんだ。店の脇から現金を抜かれた財布が見つかったんで難を逃れたそうだ」
「アイツが服役した事件の捜査だっていい加減なものだった。ホンボシは初犯だってことで執行猶予になったけど、アイツは罪を認めなかったから実刑だった。本当に無実だ。でも俺には何も出来なかった」
今度は泣き出した。
無理もない。
だって、奥さんを殺したのがその人だと思い込んでいたからだ。
「叔父さんはその人が事件現場に居なかったことを知ってるんだって、それなのに寄って集ってアイツを共犯に仕立て上げたんだよ。ホンボシの自供だけで……」
俺の言葉を聞いて、叔父さんが握り拳を左の手のひらで包んだ。
「こうやって、やっと自分を抑えている。叔父さんの痛みはみずほを失った俺には解る気がするんだ」
「瑞穂……」
今度は木暮も泣き出した。
俺達は其々、大切な人を亡くしている。
だから尚一層深い絆で結ばれていると感じた。
「出所した後でアイツは奥さんの行方を探した。でも見つけ出すことは出来なかったらしい。だから怒りの矛先は庇ってくれなかった俺に向かったんだ」
「叔父さんは長年、奥さんを殺した犯人だと思っていたんだ。だから嬉しいんだ。俺の霊感はこの日のためではなかったのでは俺は思ってな」
俺は力説していた。
「熊谷のアパートには思い出がいっぱい詰まっている。だから其処に居るんだよ」
「本当はアイツを信じていたんだ。だから嬉しい。瑞穂の霊感は正しいと思う。彼女はアイツを本当に心配していたからな。だから毒牙にかかった時、怒りが収められなかったんだ」
叔父は辛そうに言った。
俺達はそれ以上聞けなくなった。
叔父は心の奥底では否定しながらも、真犯人だと思っていたのだ。
俺はみずほ死によって霊感を授けられた。
それはきっとこのためではなかったのだろうか?
みずほはきっと、事件の真相を……
ラジオと呼ばれた人が真犯人じゃないって伝えたかったのではないのだろうか?
ふと、俺は思った。
「叔父さん。あの人が真犯人じゃなくて良かったね。今日はクリスマスイヴだからもう帰るけど……」
本当は叔父とずっと居たい。
同じ痛みを少しでも紛らわせることが出来るかも知れないから……
でもサッカーだけは辞められないんだ。