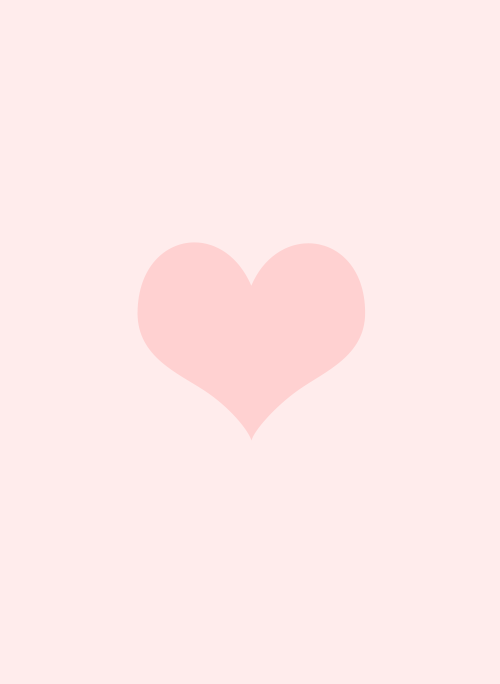ソバカス隊長と暗闇の蜜蜂
カボチャ灯篭と蝙蝠大佐
「ノル、その大きなカボチャはどうしたの?」
台所で夕食の準備をしているノルディのところへやってきたライマーは、台の上にデーンと鎮座している大きなオレンジのカボチャを見つけて妻にそう聞いた。
「もうすぐ、退魔祭ですから」
白いシチューの鍋をかきまぜながら、ノルディは夫へと視線を向けて答えた。ああなるほどと、ライマーは秋の祭りを思い出す。
子供たちが悪霊に取り憑かれて病気にや怪我をしないように、年に一度悪霊祓いの日がある。それが退魔祭だ。大昔の同じ季節の頃、子供の間だけで流行った病があり、多くの子供たちが亡くなった。それを悼んだ神殿が、二度と同じことが起きないようにとこの祭りを始めたのだ。
大人とちがって子供は純粋だから悪霊に狙われると思われたため、この日だけは子供たちは悪霊の姿に仮装して、奴らの目から身を隠す。その仮装のまま町を練り歩き、徘徊する悪霊の代わりに各家庭を訪問する。
本物ではなく子供の悪霊に来て欲しい家は、家の前にカボチャで作った灯篭を出しておく。勿論、本物の悪霊に来て欲しい家なんかあるはずはないので、よほど事情がない限り、どこの家でもカボチャの灯篭を出すのだが。そしてやってきた子供のいたずらから家族を守るために、お菓子で退散してもらうのだ。
子供の頃に退魔祭に参加した記憶はあっても、軍に入隊して独身の間、官舎住まいだったライマーにとってそれは、すっかり無縁の行事と化していた。結婚して一戸建ての家を買い、こうして妻と暮らすようになったいま、確かにカボチャの灯篭を置かないのは変な話だろう。
特にノルディは、神殿で暮らしていた。ただの花見であるマンデル祭ならともかく、宗教色のある祭りをないがしろにするはずがなかった。
「そうか、退魔祭か……鉱山に住んでた時は楽しかったなあ」
自分が宗教に関してはいまひとつ熱心でないことがバレそうで、ライマーははははと笑いながら祭りを忘れていたことをごまかした。
「どんな風だったんですか?」
小皿にシチューをよそったノルディが、小皿と共に言葉を夫へと向ける。どうやら味見をして欲しいらしい。喜んでと、まだ湯気をあげる小皿を彼は受け取った。
「みんな貧乏でね、いい布なんか手に入らないから、山に入って木の枝とか花とか草とかキノコとか取ってくるんだよ。あと、鉱山の中から石なんかね」
それらの雑多なガラクタを、紐で頭に縛り付けたり、服に縫い付けたりするのだ。木のオバケみたいな子が出来上がったり、花だらけの女の子がいたりとみんな工夫をこらしていた。
「あ……あなたは、どんな仮装をしたんですか?」
シチューの皿に口をつけて、「んー、うまい」と笑顔で評したライマーに、味の結果よりもそっちの方が気になるとばかりにノルディが食いついてくる。
「一番傑作だったのが、石をいっぱい服にくくりつけて、石のオバケを作った時なんだけどね……」
小皿を返しつつ、ライマーはその時の記憶を呼び起こして苦笑いした。
「あんまり石をぶらさげすぎて、歩いている最中に服が重みに耐え切れずにビリビリ……服が一着ダメになって、あの時はおばあちゃんに悪いことをしたよ。それ以来、石はダメって言われたんだよな」
失敗談を語っている途中からもう、ノルディは笑い出していた。自分のマヌケな記憶も、こうして妻の笑顔に変換されるなら、何という有効活用だろうかと彼は思った。
「ノルはどんな仮装したんだい?」
笑っているばかりの妻を見ているのも楽しいが、彼女の昔の話も聞いてみたいとライマーは話を返した。小皿は素直に受け取ってくれた彼女だったが、この言葉には少し恥ずかしそうだった。
「母が……その、黒い服に刺繍をしてくれたんです。オレンジのカボチャの灯篭の刺繍。あんまりそれが素敵で、退魔祭じゃない時に着ようとして怒られました……」
ライマーが失敗談を話したように、彼女もまた自分の失敗談を話してくれた。しかし、恥ずかしさの中にライマーは寂しさのようなものを感じた。
「本当にお気に入りだったんです。でも、すぐ大きくなっちゃって……二年もしたら着られなくなって残念でした」
母との思い出の品であり、子供の頃の幸せな記憶であるその服のことは、彼女の中ではかけがえの無いものなのだろう。
ライマーは、うーんと考え込んだ。彼に、カボチャの刺繍は出来そうにない。何か他に、妻の幸せに寄与する方法が何かないかと思った。
「そうだ……そのカボチャの灯篭を私が作ろう」
「え?」
ライマーの中ではカボチャでつながっている話も、ノルディにしてみれば唐突だったのだろう。母の記憶から戻ってきたばかりということもあり、彼女はきょとんと夫を見た。
「私がカボチャの灯篭を作るよ。作るのは初めてだけど……まあ、何とかなるんじゃないかな」
ライマーは、ノルディの母にはなれない。しかし、彼は唯一無二の夫である。新しい退魔祭の記憶を増やしていくことは出来る。そのためなら、カボチャのひとつやふたつくりぬいて見せようと思った。
「え? 初めて? だ、大丈夫ですか?」
ノルディは違うところが気になったらしく、しきりと心配を始めた。神殿育ちの彼女からすれば、灯篭を作るのは毎年の行事なので慣れているのだろう。
「大丈夫大丈夫、任せなさい」
にこにこと笑いながら、ライマーはカボチャの前まで歩み寄ってその大きな身をペチペチと叩いたのだった。
そして──退魔祭当日。
「ズューセス オーダー ザオレス!(甘いものをくれないなら酸っぱいものをあげるぞー)」
彼の家に、最初の悪霊がやってくる。せっかくの妻との祭りということもあって、ライマー自身もちゃっかり休みを取っていた。
一番乗りは誰かと思ったら、ライマーの異母弟妹だった。白いシーツをかぶっただけの手抜きオバケは最初誰か分からなかったが、その横に黒い耳と尻尾、顔にヒゲまで描いた異母妹のニーナがいたので、ライマーはオバケの正体が分かった。
「カミルかぁ、まだ仮装やってるんだな」
黒猫の頭を撫でた後、白いオバケの頭も撫でようとしたら、そのシーツがばさっと取り払われて不満そうな黒髪の異母弟の顔が出てくる。
「もう子供じゃないのに母さんが悪霊に取り憑かれるってうるさくて……恥ずかしいから、一応かぶってきただけだよ」
そろそろ学校を卒業して働き出す年だ。仮装も卒業したいようだが、まだあの義母は許してくれないのだろう。
「カミルくんニーナちゃん、いらっしゃい」
奥から慌てて出てきたノルディの手にあるのはキャンディーの袋。それと、ほくほくのカボチャパイ。甘いものはまだ卒業出来ないのか、ニーナだけでなくカミルの目も輝いたのをライマーは見逃さなかった。
「カボチャのにおいーおいしそう」
黒猫ニーナがパイの匂いを大きく吸い込んでそう言った次の時、カミルが「あー」っと奇妙な声をあげた。
「あのさ、兄さん」
「何かね、弟よ」
「表のカボチャの灯篭……誰が作ったの?」
その質問の次の瞬間。
ぷふっと──ノルディが噴き出した。慌ててその口を押さえて後ろを向くが、もう遅い。
「兄さんなの、あれ!?」
「何でさかさまなの、あれ!」
弟妹二人がかりで、ライマーはカボチャの灯篭の出来をつっこまれることになる。
「いやー、カッコイイのを作ろうとしたんだけどねぇ」
彼は困った笑いを浮かべながら頭をかく。
最初にライマーはカボチャの右目をくりぬいた。そこまではよかった。左目をくりぬいたときに、右目とのバランスが非常におかしいことに気づいて、右目を直したら、今度は左目がおかしい気がして左目を、そうしたらまた右目が、という無限回廊に突入してしまったのである。
結局、両目はどんどん大きくなり、ついには目の間の壁が耐え切れずに崩壊した。そうなると、カボチャの上部はぽっかりひとつの大きな穴が開いただけの存在になる。
やむなく、ライマーはその大きく開きすぎた部分を口にすべく、カボチャをひっくり返した。そして今度は、多少のいびつさを我慢して目をふたつ、くり抜いてやめたのだった。
目を作るはずだった場所のため、口はとりあえず大きいだけの歪んだ形をしている上に、カボチャの上下が逆さまという灯篭は、この町広しと言えどもライマー宅だけだろう。
おかげで妻と異母弟妹だけでなく、次々とやってくる子供たちにまで笑われる羽目となったライマーだった。
しかし、これは悪いことばかりではなかった。それから毎年退魔祭が来る度に、彼の妻であるノルディはカボチャを見るとぷっと笑うようになったのだ。
それこそが、ライマーが新しく彼女に残した楽しい退魔祭の記憶である。
そんな妻の姿が嬉しくて、トット家のカボチャの灯篭は毎年必ず逆さまに作られることとなったのだった。
『カボチャ灯篭と蝙蝠大佐 終』
台所で夕食の準備をしているノルディのところへやってきたライマーは、台の上にデーンと鎮座している大きなオレンジのカボチャを見つけて妻にそう聞いた。
「もうすぐ、退魔祭ですから」
白いシチューの鍋をかきまぜながら、ノルディは夫へと視線を向けて答えた。ああなるほどと、ライマーは秋の祭りを思い出す。
子供たちが悪霊に取り憑かれて病気にや怪我をしないように、年に一度悪霊祓いの日がある。それが退魔祭だ。大昔の同じ季節の頃、子供の間だけで流行った病があり、多くの子供たちが亡くなった。それを悼んだ神殿が、二度と同じことが起きないようにとこの祭りを始めたのだ。
大人とちがって子供は純粋だから悪霊に狙われると思われたため、この日だけは子供たちは悪霊の姿に仮装して、奴らの目から身を隠す。その仮装のまま町を練り歩き、徘徊する悪霊の代わりに各家庭を訪問する。
本物ではなく子供の悪霊に来て欲しい家は、家の前にカボチャで作った灯篭を出しておく。勿論、本物の悪霊に来て欲しい家なんかあるはずはないので、よほど事情がない限り、どこの家でもカボチャの灯篭を出すのだが。そしてやってきた子供のいたずらから家族を守るために、お菓子で退散してもらうのだ。
子供の頃に退魔祭に参加した記憶はあっても、軍に入隊して独身の間、官舎住まいだったライマーにとってそれは、すっかり無縁の行事と化していた。結婚して一戸建ての家を買い、こうして妻と暮らすようになったいま、確かにカボチャの灯篭を置かないのは変な話だろう。
特にノルディは、神殿で暮らしていた。ただの花見であるマンデル祭ならともかく、宗教色のある祭りをないがしろにするはずがなかった。
「そうか、退魔祭か……鉱山に住んでた時は楽しかったなあ」
自分が宗教に関してはいまひとつ熱心でないことがバレそうで、ライマーははははと笑いながら祭りを忘れていたことをごまかした。
「どんな風だったんですか?」
小皿にシチューをよそったノルディが、小皿と共に言葉を夫へと向ける。どうやら味見をして欲しいらしい。喜んでと、まだ湯気をあげる小皿を彼は受け取った。
「みんな貧乏でね、いい布なんか手に入らないから、山に入って木の枝とか花とか草とかキノコとか取ってくるんだよ。あと、鉱山の中から石なんかね」
それらの雑多なガラクタを、紐で頭に縛り付けたり、服に縫い付けたりするのだ。木のオバケみたいな子が出来上がったり、花だらけの女の子がいたりとみんな工夫をこらしていた。
「あ……あなたは、どんな仮装をしたんですか?」
シチューの皿に口をつけて、「んー、うまい」と笑顔で評したライマーに、味の結果よりもそっちの方が気になるとばかりにノルディが食いついてくる。
「一番傑作だったのが、石をいっぱい服にくくりつけて、石のオバケを作った時なんだけどね……」
小皿を返しつつ、ライマーはその時の記憶を呼び起こして苦笑いした。
「あんまり石をぶらさげすぎて、歩いている最中に服が重みに耐え切れずにビリビリ……服が一着ダメになって、あの時はおばあちゃんに悪いことをしたよ。それ以来、石はダメって言われたんだよな」
失敗談を語っている途中からもう、ノルディは笑い出していた。自分のマヌケな記憶も、こうして妻の笑顔に変換されるなら、何という有効活用だろうかと彼は思った。
「ノルはどんな仮装したんだい?」
笑っているばかりの妻を見ているのも楽しいが、彼女の昔の話も聞いてみたいとライマーは話を返した。小皿は素直に受け取ってくれた彼女だったが、この言葉には少し恥ずかしそうだった。
「母が……その、黒い服に刺繍をしてくれたんです。オレンジのカボチャの灯篭の刺繍。あんまりそれが素敵で、退魔祭じゃない時に着ようとして怒られました……」
ライマーが失敗談を話したように、彼女もまた自分の失敗談を話してくれた。しかし、恥ずかしさの中にライマーは寂しさのようなものを感じた。
「本当にお気に入りだったんです。でも、すぐ大きくなっちゃって……二年もしたら着られなくなって残念でした」
母との思い出の品であり、子供の頃の幸せな記憶であるその服のことは、彼女の中ではかけがえの無いものなのだろう。
ライマーは、うーんと考え込んだ。彼に、カボチャの刺繍は出来そうにない。何か他に、妻の幸せに寄与する方法が何かないかと思った。
「そうだ……そのカボチャの灯篭を私が作ろう」
「え?」
ライマーの中ではカボチャでつながっている話も、ノルディにしてみれば唐突だったのだろう。母の記憶から戻ってきたばかりということもあり、彼女はきょとんと夫を見た。
「私がカボチャの灯篭を作るよ。作るのは初めてだけど……まあ、何とかなるんじゃないかな」
ライマーは、ノルディの母にはなれない。しかし、彼は唯一無二の夫である。新しい退魔祭の記憶を増やしていくことは出来る。そのためなら、カボチャのひとつやふたつくりぬいて見せようと思った。
「え? 初めて? だ、大丈夫ですか?」
ノルディは違うところが気になったらしく、しきりと心配を始めた。神殿育ちの彼女からすれば、灯篭を作るのは毎年の行事なので慣れているのだろう。
「大丈夫大丈夫、任せなさい」
にこにこと笑いながら、ライマーはカボチャの前まで歩み寄ってその大きな身をペチペチと叩いたのだった。
そして──退魔祭当日。
「ズューセス オーダー ザオレス!(甘いものをくれないなら酸っぱいものをあげるぞー)」
彼の家に、最初の悪霊がやってくる。せっかくの妻との祭りということもあって、ライマー自身もちゃっかり休みを取っていた。
一番乗りは誰かと思ったら、ライマーの異母弟妹だった。白いシーツをかぶっただけの手抜きオバケは最初誰か分からなかったが、その横に黒い耳と尻尾、顔にヒゲまで描いた異母妹のニーナがいたので、ライマーはオバケの正体が分かった。
「カミルかぁ、まだ仮装やってるんだな」
黒猫の頭を撫でた後、白いオバケの頭も撫でようとしたら、そのシーツがばさっと取り払われて不満そうな黒髪の異母弟の顔が出てくる。
「もう子供じゃないのに母さんが悪霊に取り憑かれるってうるさくて……恥ずかしいから、一応かぶってきただけだよ」
そろそろ学校を卒業して働き出す年だ。仮装も卒業したいようだが、まだあの義母は許してくれないのだろう。
「カミルくんニーナちゃん、いらっしゃい」
奥から慌てて出てきたノルディの手にあるのはキャンディーの袋。それと、ほくほくのカボチャパイ。甘いものはまだ卒業出来ないのか、ニーナだけでなくカミルの目も輝いたのをライマーは見逃さなかった。
「カボチャのにおいーおいしそう」
黒猫ニーナがパイの匂いを大きく吸い込んでそう言った次の時、カミルが「あー」っと奇妙な声をあげた。
「あのさ、兄さん」
「何かね、弟よ」
「表のカボチャの灯篭……誰が作ったの?」
その質問の次の瞬間。
ぷふっと──ノルディが噴き出した。慌ててその口を押さえて後ろを向くが、もう遅い。
「兄さんなの、あれ!?」
「何でさかさまなの、あれ!」
弟妹二人がかりで、ライマーはカボチャの灯篭の出来をつっこまれることになる。
「いやー、カッコイイのを作ろうとしたんだけどねぇ」
彼は困った笑いを浮かべながら頭をかく。
最初にライマーはカボチャの右目をくりぬいた。そこまではよかった。左目をくりぬいたときに、右目とのバランスが非常におかしいことに気づいて、右目を直したら、今度は左目がおかしい気がして左目を、そうしたらまた右目が、という無限回廊に突入してしまったのである。
結局、両目はどんどん大きくなり、ついには目の間の壁が耐え切れずに崩壊した。そうなると、カボチャの上部はぽっかりひとつの大きな穴が開いただけの存在になる。
やむなく、ライマーはその大きく開きすぎた部分を口にすべく、カボチャをひっくり返した。そして今度は、多少のいびつさを我慢して目をふたつ、くり抜いてやめたのだった。
目を作るはずだった場所のため、口はとりあえず大きいだけの歪んだ形をしている上に、カボチャの上下が逆さまという灯篭は、この町広しと言えどもライマー宅だけだろう。
おかげで妻と異母弟妹だけでなく、次々とやってくる子供たちにまで笑われる羽目となったライマーだった。
しかし、これは悪いことばかりではなかった。それから毎年退魔祭が来る度に、彼の妻であるノルディはカボチャを見るとぷっと笑うようになったのだ。
それこそが、ライマーが新しく彼女に残した楽しい退魔祭の記憶である。
そんな妻の姿が嬉しくて、トット家のカボチャの灯篭は毎年必ず逆さまに作られることとなったのだった。
『カボチャ灯篭と蝙蝠大佐 終』