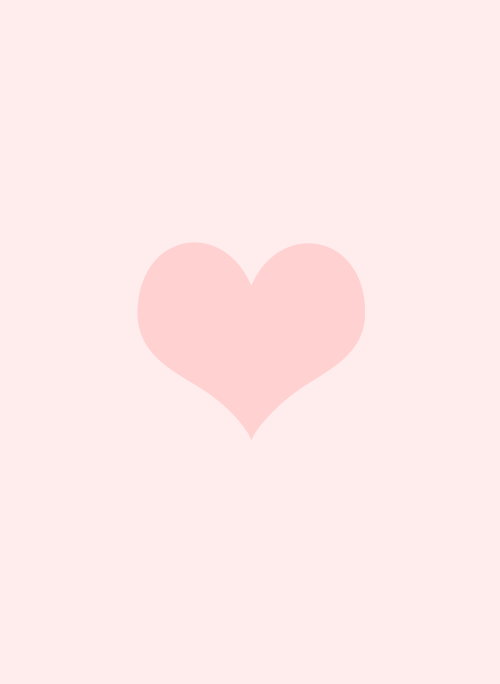とわのゆめ
これは夢だ。
――と瞬時にわかってしまう感覚は、ネタバレのようで好きじゃない。
見渡すと、学校の廊下。左右に伸びているそれは果てがなく、目の前の教室には3-3のプレートがかかっている。
ここは――、高校か。
やけに懐かしい夢を見るな、なんて感傷に浸ってしまった。高三ともなれば十年ほど前になる。大学に進学して、会社勤めになって、といった濃い思い出に上書きされた、それもまた濃い青春。覚えていることとすれば、学校祭くらいだろう。
がらがら、とこれもまた懐かしい音を立て教室に入る。規則的に並べられた机と椅子。それだけだ。黒板に何かが書いてあるわけでもなく、誰かが座っているわけでもない。言うなれば早朝の教室を彷彿させる、世界に誰もいなくなったと錯覚する独特な雰囲気。
どうしたものかと困惑しつつ、一つの席に腰掛ける。
「なんでそこに座ったの?」
背後から声をかけられた。急なそれにびくりと肩を震わせる。驚いた理由はそれだけではない。聞き覚えのある、優しい声音。
振り返ると、大人しい笑みを浮かべた髪の長い少女。仄かにグレープフルーツの匂い。
「S……」
「久しぶりだね、Rくん」
高校生活、俺が覚えているのは学校祭くらいだ。特別な行事だから頭に強く残っている。
もう一つ、忘れたくても忘れられない存在がある。
Sは高校のときの同級生だ。まあまあ、仲も良かった。
俺は彼女に恋をしていた。
ある意味、対極の存在だと思ってた。
彼女の周りにはいつも笑顔が溢れている。笑いを取るわけでもなく、会話の中で自然と顔が綻ぶような、そんな雰囲気だ。男女隔たりなく接し、誰かと行動するのが常だった。面倒が嫌いな自分としては考えられないことだ。だからこれといって関わらない。クラスメイトという接点だけが辛うじて繋いでいる。あとはひたすら続く交わらない平行線。
話すようになったのは本当に偶然だ。くじ引きだか何だかで隣の席になって、それから一度話しかけられて、といった具合。初めて話して、イメージとは少し違う、ちょっとズレている部分があったり突拍子がなかったりと意外な面を度々見せられて、惹かれていった。彼女は先刻言ったとおり所謂クラスの中心で、高嶺の花と言って過言は無い存在。そんな彼女と友達もいない一匹狼が話す、という構図に興味を持ってついてまわるやつもいたが、次第に違和のない日常になってそれもなくなった。なくなってもお構いなしだった。彼女にはいつもグレープフルーツのような甘酸っぱい香りが漂っていて、これが恋なのかな、なんて柄でもないことを俺は考えていた。
彼女は俺に纒わり付く。一度ついた匂いは取れない。
忘れたい、どうしても忘れられない。
「久しぶりだね、Rくん」
そう言って淡く微笑む少女はあの頃から何も変わらない。俺の記憶と違いない紛れもなくSだった。
まあ、自分の夢の中だから当然なのだけれど。
なんて心で詰る。分かりやすく動揺している。かつての想い人が突如目の前に現れたからだろうか。
「おぅ……、久しぶり」
そう言うと自分の前の席に腰掛ける。椅子をこちらに向け、少し見上げるようにしてもう一度言った。
「なんでそこに座ったの?」
意味なんてない。ただどこかに座ろうと思って、偶々。
言い淀み、視線を彷徨わせる。
「当てよっか。ここ、私と隣だったときの席だよ」
そうだったっけか。だとしたら相当焦がれている。言われてみればこの席から見る黒板は何となく見なれている気も、左を向けば彼女がいたような気もする。
逡巡して返事をせずにいると、焦れたのかまた口を開く。
「だから座ったの」
「……かもな」
「照れてんでしょ」
「さあ」
何だか落ち着かない気持ちになって、短く返した。
「背伸びた?なんか視線合わない」
そりゃあ十年も経ったら、と思い、伏せていた目を上げて気付いた。
彼女はあの頃のまま、セーラー服に身を包んでいる。
「まあ、もう二十七だし。てかなんでお前は制服なんだよ」
「だってRくんの中の私はこの頃のままでしょ。だから私か高校生のまま」
あの頃と変わらない、若干よれているセーラー。姉からのお下がりだと言っていた気がする。そういうどうでもいいことすら、忘れられずにいる。
「同窓会で会ったのに。Rくんはその時のこと、もう忘れようとしてる」
そうだ。最後に彼女と会ったのは二十歳になって少し経ったとき。同窓会で再会した。
「ねえ、あのとき私が言ったこと覚えてる?」
忘れるわけがない。強く、刻まれている。
彼女は俺に親しげに話しかけてくれた。
今までの人生で唯一愛した女性だ。
でも、俺が彼女に恋するなんて烏滸がましいと思った。
一匹狼と高嶺の花だ。
どうして俺と仲良くする?
独りぼっちの俺に同情してるのか?
裏があるのか?
本当は俺のことからかってるのか?
俺は彼女から逃げた。
避けて、しつこいと突っぱねた。
賢い選択だったと思う。
後悔はなかった。
同窓会には行かないつもりだった。友達もいないし、唯一仲がよかった彼女のことは自ら突き放した。行く動機がなかった。
でも、もしかしたら、なんて勝手な妄想が膨らんで少しだけ顔を出してみた。
みんなは俺の事を案外覚えていた。親しいわけではなくとも卒業してから三年と経ってないからか楽しく過ごせた。そんな中、酸っぱい匂いが俺の鼻孔をつついて俺の隣に座った。高校の座席と一緒の左隣。
薬指にリングが嵌められていた。
まだ婚約段階だから籍は入れてないんだけどね。
彼が、同窓会なら牽制した方がいいだろって言うの。
Rくんには一番に言いたかったんだ。
あの頃、Rくんは私が嫌いだったのかな。
でも、私は好きだったんだよ。
本気で、好きだったんだ。
「……覚えてるよ」
身の程を弁えた選択だったはずが自ら幸福の選択肢を捨てていたのだ。ショックでたまらなくなった。
君はもう、俺を見ることはない。
「後悔したんだ、強く。自分の選択を恨んだ」
「この辛い十年と後悔、忘れちゃ駄目だよ」
彼女が不意に手を伸ばす。俺の瞼の上に重ねた。
「目を瞑って、ゆっくり深呼吸」
急に何を始めたのか理解できないまま言われた通りにする。息を深く吸い込んだからか、より強く柑橘の匂いがした。
「そう。そのまま、この幻想とお別れして。次は悔いなく生きてね」
「十年間の、永遠の夢から覚めて」
「あ、おはよう」
騒々しさに目を覚ます。弛緩した身体を叱咤して上体を起こせば、そう声をかけられた。
声のする方――、左を向けば長い黒髪を垂らした少女と目が合う。瞬きをすれば、彼女はふふっと笑った。
「もうすぐ一限始まるよ。さすがに授業は起きたら?」
鼻先を擽る、グレープフルーツの匂い。
「……はよ。授業になったら声かけて」
「はいはい」
眠いわけではないがもう一度机に突っ伏した。
妙な気分だ。永い夢から覚めた今、なんだかふわふわとしていて何でも出来そうな気がする。
悔いのないように生きよう。
「……あんさ、S」
「ん?」
「好き」
――と瞬時にわかってしまう感覚は、ネタバレのようで好きじゃない。
見渡すと、学校の廊下。左右に伸びているそれは果てがなく、目の前の教室には3-3のプレートがかかっている。
ここは――、高校か。
やけに懐かしい夢を見るな、なんて感傷に浸ってしまった。高三ともなれば十年ほど前になる。大学に進学して、会社勤めになって、といった濃い思い出に上書きされた、それもまた濃い青春。覚えていることとすれば、学校祭くらいだろう。
がらがら、とこれもまた懐かしい音を立て教室に入る。規則的に並べられた机と椅子。それだけだ。黒板に何かが書いてあるわけでもなく、誰かが座っているわけでもない。言うなれば早朝の教室を彷彿させる、世界に誰もいなくなったと錯覚する独特な雰囲気。
どうしたものかと困惑しつつ、一つの席に腰掛ける。
「なんでそこに座ったの?」
背後から声をかけられた。急なそれにびくりと肩を震わせる。驚いた理由はそれだけではない。聞き覚えのある、優しい声音。
振り返ると、大人しい笑みを浮かべた髪の長い少女。仄かにグレープフルーツの匂い。
「S……」
「久しぶりだね、Rくん」
高校生活、俺が覚えているのは学校祭くらいだ。特別な行事だから頭に強く残っている。
もう一つ、忘れたくても忘れられない存在がある。
Sは高校のときの同級生だ。まあまあ、仲も良かった。
俺は彼女に恋をしていた。
ある意味、対極の存在だと思ってた。
彼女の周りにはいつも笑顔が溢れている。笑いを取るわけでもなく、会話の中で自然と顔が綻ぶような、そんな雰囲気だ。男女隔たりなく接し、誰かと行動するのが常だった。面倒が嫌いな自分としては考えられないことだ。だからこれといって関わらない。クラスメイトという接点だけが辛うじて繋いでいる。あとはひたすら続く交わらない平行線。
話すようになったのは本当に偶然だ。くじ引きだか何だかで隣の席になって、それから一度話しかけられて、といった具合。初めて話して、イメージとは少し違う、ちょっとズレている部分があったり突拍子がなかったりと意外な面を度々見せられて、惹かれていった。彼女は先刻言ったとおり所謂クラスの中心で、高嶺の花と言って過言は無い存在。そんな彼女と友達もいない一匹狼が話す、という構図に興味を持ってついてまわるやつもいたが、次第に違和のない日常になってそれもなくなった。なくなってもお構いなしだった。彼女にはいつもグレープフルーツのような甘酸っぱい香りが漂っていて、これが恋なのかな、なんて柄でもないことを俺は考えていた。
彼女は俺に纒わり付く。一度ついた匂いは取れない。
忘れたい、どうしても忘れられない。
「久しぶりだね、Rくん」
そう言って淡く微笑む少女はあの頃から何も変わらない。俺の記憶と違いない紛れもなくSだった。
まあ、自分の夢の中だから当然なのだけれど。
なんて心で詰る。分かりやすく動揺している。かつての想い人が突如目の前に現れたからだろうか。
「おぅ……、久しぶり」
そう言うと自分の前の席に腰掛ける。椅子をこちらに向け、少し見上げるようにしてもう一度言った。
「なんでそこに座ったの?」
意味なんてない。ただどこかに座ろうと思って、偶々。
言い淀み、視線を彷徨わせる。
「当てよっか。ここ、私と隣だったときの席だよ」
そうだったっけか。だとしたら相当焦がれている。言われてみればこの席から見る黒板は何となく見なれている気も、左を向けば彼女がいたような気もする。
逡巡して返事をせずにいると、焦れたのかまた口を開く。
「だから座ったの」
「……かもな」
「照れてんでしょ」
「さあ」
何だか落ち着かない気持ちになって、短く返した。
「背伸びた?なんか視線合わない」
そりゃあ十年も経ったら、と思い、伏せていた目を上げて気付いた。
彼女はあの頃のまま、セーラー服に身を包んでいる。
「まあ、もう二十七だし。てかなんでお前は制服なんだよ」
「だってRくんの中の私はこの頃のままでしょ。だから私か高校生のまま」
あの頃と変わらない、若干よれているセーラー。姉からのお下がりだと言っていた気がする。そういうどうでもいいことすら、忘れられずにいる。
「同窓会で会ったのに。Rくんはその時のこと、もう忘れようとしてる」
そうだ。最後に彼女と会ったのは二十歳になって少し経ったとき。同窓会で再会した。
「ねえ、あのとき私が言ったこと覚えてる?」
忘れるわけがない。強く、刻まれている。
彼女は俺に親しげに話しかけてくれた。
今までの人生で唯一愛した女性だ。
でも、俺が彼女に恋するなんて烏滸がましいと思った。
一匹狼と高嶺の花だ。
どうして俺と仲良くする?
独りぼっちの俺に同情してるのか?
裏があるのか?
本当は俺のことからかってるのか?
俺は彼女から逃げた。
避けて、しつこいと突っぱねた。
賢い選択だったと思う。
後悔はなかった。
同窓会には行かないつもりだった。友達もいないし、唯一仲がよかった彼女のことは自ら突き放した。行く動機がなかった。
でも、もしかしたら、なんて勝手な妄想が膨らんで少しだけ顔を出してみた。
みんなは俺の事を案外覚えていた。親しいわけではなくとも卒業してから三年と経ってないからか楽しく過ごせた。そんな中、酸っぱい匂いが俺の鼻孔をつついて俺の隣に座った。高校の座席と一緒の左隣。
薬指にリングが嵌められていた。
まだ婚約段階だから籍は入れてないんだけどね。
彼が、同窓会なら牽制した方がいいだろって言うの。
Rくんには一番に言いたかったんだ。
あの頃、Rくんは私が嫌いだったのかな。
でも、私は好きだったんだよ。
本気で、好きだったんだ。
「……覚えてるよ」
身の程を弁えた選択だったはずが自ら幸福の選択肢を捨てていたのだ。ショックでたまらなくなった。
君はもう、俺を見ることはない。
「後悔したんだ、強く。自分の選択を恨んだ」
「この辛い十年と後悔、忘れちゃ駄目だよ」
彼女が不意に手を伸ばす。俺の瞼の上に重ねた。
「目を瞑って、ゆっくり深呼吸」
急に何を始めたのか理解できないまま言われた通りにする。息を深く吸い込んだからか、より強く柑橘の匂いがした。
「そう。そのまま、この幻想とお別れして。次は悔いなく生きてね」
「十年間の、永遠の夢から覚めて」
「あ、おはよう」
騒々しさに目を覚ます。弛緩した身体を叱咤して上体を起こせば、そう声をかけられた。
声のする方――、左を向けば長い黒髪を垂らした少女と目が合う。瞬きをすれば、彼女はふふっと笑った。
「もうすぐ一限始まるよ。さすがに授業は起きたら?」
鼻先を擽る、グレープフルーツの匂い。
「……はよ。授業になったら声かけて」
「はいはい」
眠いわけではないがもう一度机に突っ伏した。
妙な気分だ。永い夢から覚めた今、なんだかふわふわとしていて何でも出来そうな気がする。
悔いのないように生きよう。
「……あんさ、S」
「ん?」
「好き」