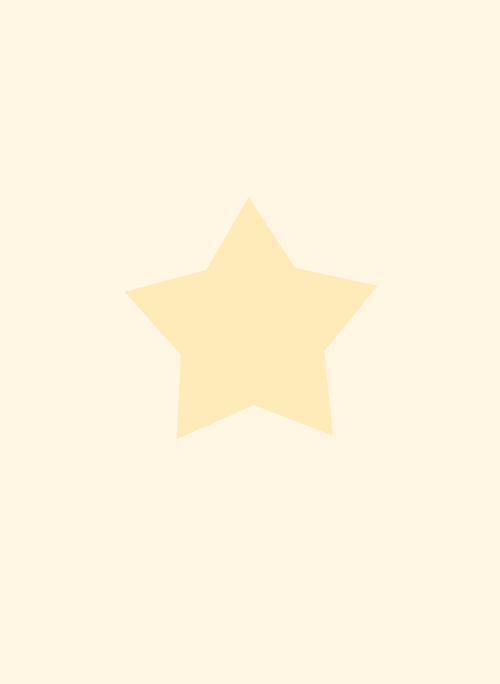Old memories
Old memories
「Old memories」 椎名のん
―♪
好きだった
大好きだった
愛していた
真夏の太陽が照らす空の下で恋をした
愛しい
願うならば、会いたい
ずっと一緒にいたかった
我を忘れるぐらい、恋をしていた
―🌸
第1章――「想い出」
蝉の鳴き声が響き渡る。太陽の日差しが眩しい。向日葵が満開に咲いている。小さな子供が虫取りに夢中になっている。シャボン玉を飛ばしている子供もいたりする。漁港も人で溢れてる。光が丘海岸の海は静かに音を立てている。今年も夏が来た。愛媛県のA島は本当に暑い。真夏の暑さだ。そして、そこの島に、1人の男がいた。山村健太、37歳。独身。健太は、部屋から海を見ながら、煙草を吸っていた。メビウスの煙草の煙が、部屋の宙をまいた。
「・・・・・今年もきたか」
健太は、毎年夏が来ると、複雑な気持ちになっていた。健太は煙草を灰皿に押し付け、そして、スマホで音楽を流した。17年前に死んだ、亡き恋人が好きだった音楽を流しながら、煙草を吸っていた。健太は思い出していた。亡き恋人のことを。いつまでも忘れれない女のことを。夏海を。健太は、思い出しながら、音楽を流していた。
「・・・・・は~、・・・・・・あいつ・・・・。」
健太は、光が丘海岸の海を見ながら、17年前に、死んだ亡き恋人が好きだった音楽を流しながら、煙草を吸っていた。夜、健太は、部屋で友達の達也と酒を飲んでいた。達也も煙草を吸っていた。達也は、アイコスを吸っていた。
「けんちゃん」
「ん」
「今年も来たな、夏。」
「・・・・・・・あー。そうやな」
さざ波が聞こえる夜10時。健太は立ち上がった。そして、窓から見える海を見た。健太は、亡き恋人とのことを、たくさん思い出していた。死んだ恋人とのことを思い出していた。達也は、いびきをかきながら寝ていた。健太は、煙草の箱から1本紙煙草を取り出し、ライターで煙草の先端に火を付け、そして吸い始めた。健太は、海を見るたびに切ない気持ちになっていた。その日の夜、健太は夢を見た。凄く凄く愛していた人、その女はセーラー服を着ていた。そして、笑顔で海を見ていた。そして、名前を呼ばれた。
「けんた」
―はっ
健太は夢にうなされながら、夜中の3時に目覚めた。額から汗が流れていた。健太は息切れをしながら、再度寝始めた。ずっと、何年も忘れることが出来ない、死んだ恋人・夏海の夢を、ここ最近、何度も見ていた。健太は、‘夏海’が近くにいる気がした。健太は、走馬灯のように、‘夏海’が死んだときのことを思い出していた。健太は思い出すと辛くなり、テーブルの上に置いてある、ライターと煙草を取り出し、煙草の先端に火を付け、吸い始めた。
もう、思い出したくなかった。‘夏海’との日々を思い出したくなかった。‘夏海’は、17歳の時に、早くしてこの世を去った。‘夏海’との思い出の場所、光が丘海岸は、いつまでも色あせることなく、波が音を立てていた。健太は、煙草の吸殻を灰皿に押し付け、再度寝た。
第2章――「夕暮れの空」
翌日、空は晴天だった。健太は、夏海の命日の前の日、小さい頃からの知り合いで、今は一児の母になっている、木原咲に会った。健太は咲と海の見える喫茶店で、お互いコーヒーを飲んでいた。
「健太」
「ん?」
咲は黒髪のロングで、華奢な体系で、そして咲も、健太と同じヘビースモーカー。
咲の傍には、ピンク色のアイコスが置かれていた。
「健太・・・・明日やね・・・・。」
「それさ―、昨日達也にも同じこと言われた。」
「有村も?」
「・・・・・・・・明日、花添えてくるわ」
健太は、煙草を1本吸い始めた。喫煙がOKな席だった。咲は、切なそうな目をしていた。
「けんた」
「ん?」
「今でも・・・・・・・なつみちゃんのこと・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・・あー、そうやな」
2人の間でちょっとした沈黙が流れ、煙草の匂いが辺りを充満した。太陽の日差しが窓に差し込み、店の冷房の風が、頬にヒヤッとした。そして、次の日の朝、健太は、夏海の家に行った。2037年 某8月。夏海の命日。健太は、夏海の遺影の前で手を合わせた。健太は、向日葵の花を、遺影の近くに添えた。21年。あれから21年経ったことが、健太は信じられなかった。健太は、夏海の部屋を見た。勉強机、スマホ、ギター、服。夏海の母の真由子は、自分の娘が使っていた部屋をそのままにしていた。そして、健太は、勉強机に飾られている1つの写真盾を見た。夏海は、自分との2ショットを飾っていた。自分は歳をとり、夏海は老けない。その事実を未だに受け止めきれなかった。夏海は、苦しんで死んだ。17という若さだった。
「健太、ありがとう・・・・。」
「・・・・・・・・・・・うん。あ、おばちゃん、ちょいベランダで煙草吸っていい?」
「ええで」
健太は、ベランダに出た。煙草の箱から1本取り出し、ライターで煙草の先端に火を付け、吸い始めた。煙は宙を巻いた。ベランダから見る島の海は、色あせることなく、いつまでも輝いていた。すると電話がかかってきた。友達の有村達也からだった。
「もしもーし」
「けんちゃん、やほ―。けんちゃん、特に用はないんやけど―・・・・・・・明日、
なっちゃんの誕生日や―ん」
「ああ、そうやな」
「家来る?愛が、ご飯作るで~」
「・・・・・・・・・・・時間あったら行くわ」
健太は、川村家のベランダから見える、光が丘海岸を見た。茜色に染まった空は健太の心を悲しくさせた。健太は、なんで夏海がこの世にいないのか、信じられなかった。本当に信じられなかった。そして、健太の職業は高校教師。健太は、明日は夏海の誕生日だが、普通に部活の日だ。健太は、明日の部活の計画を立て、夏海の誕生日と思うと、辛い気持ちになっていたが、部活の時は部活に集中と思った。光が丘海岸の波は、静かに音を立てていた。
第3章――「告白」
次の日。真夏の暑い日に某高校のバスケ部が、体育館で猛練習をしていた。
「そこ早く!」
「何してんや!」
健太は、そこの高校の男子バスケ部の監督をしていた。健太は、熱血で教育熱心だと有名だった。山村健太、37歳。男子バスケ部副顧問兼コーチ。女子生徒からはイケメンだと評判だ。休憩時間、選手たちが体育館で弁当に、ローソンの菓子パンに、食べ始めた。すると、軽音部のバンドが、文化祭の練習で体育館のステージを使い始めた。そのバンドのボーカルに、達也と愛の娘の、高校1年の有村夏希。軽音部所属。文系志望。夏希は、綺麗な顔をしていて、色白で、男子生徒から一目置かれている。その中の1人、藤沢翔は、夏希に惚れていた。
「あ~~~♪じゃやりますかー!」
そのバンドは、演奏し始めた。
「有村って綺麗よなー」
「可愛い」
「細い」
「色白」
「美人」
すると、翔が乱暴なことを言い出した。
「どこが?あいつ、ブスやん(笑)」
翔のその言葉に、健太が突っ込んだ。
「藤沢、夏希に惚れとんやろ?」
「は?惚れてねーし、あんなガサツ女・・・・・・」
「顔、少し赤いで(笑)」
「も~監督・・・・・・・。」
夏希は本当に綺麗な声をしていた。少し低いハスキーな歌声を夏希はしていた。そのバンドのステージ練習が少し終わった頃、夏希がバスケ部の連中のところに来た。夏希は、健太の顔を見た。
「あ、おじ・・・・あ、山村先生、翔殴ってもいいですか?」
「は?なんでや」
「翔、ノート返してや」
「あ、忘れた。」
すると、健太が翔の頭をげんこつした。
「あほか、勉強せんといけんやん」
「いって~~。監督もっと手加減してや~」
すると、夏希が翔の前にしゃがみこんだ。
「翔」
翔はドキドキしていた。夏希の大きな目、そして・・・・胸。
「翔」
「ん?」
「何、この擦り傷~」
夏希は、右頬にうっすら出来ている、翔の頬の擦り傷を触った。翔は、夏希の右手首を掴んだ。夏希の頬が少し赤くなった。夏希はそれを隠そうと左手で隠そうとしたが、無理だった。翔が夏希の目を真剣に見た。いや、見つめたと言い直した方がいいかもしれない。
「夏希」
「ん?」
夏海は本当に綺麗な顔をしていた。翔はドキドキしていた。夏希がどんどん綺麗になっていくことに。時々、夏希が至近距離にいる時、キスしそうになる自分がいた。でも、夏希は本当に綺麗で、そんな簡単に夏希に手を出せないほど、翔は夏希のことを大切に思っていた。ドキドキしていた。翔は夏希に恋焦がれていた。夏希の顔が至近距離にある。金木犀の匂いがした。
「あのさ」
「うん」
「お前ら、付き合っとん?」
健太が2人に言った。
「は?なんでや。」
「山村先生、翔とは、ただの幼馴染よ。」
―けんたとは、ただの幼馴染よ
健太は、夏希がふと、大昔惚れた女に重なった。
‘けんた、私さ―、長くないんよ’
‘私が死んでも、忘れないでね’
大昔、真夏の暑い中、病室で命を絶った恋人・夏海のことを健太は思い出した。
―来年、光が丘海岸の桜、一緒に見よう
―健太、好き
―健太の隣で笑ってたいな
―生きて・・・・・生きて
健太の目が潤んでいた。健太は、手で目頭を拭った。17で命を落とした女のことを・・・・。健太は、その場であぐらをかいた。そして、バスケ部員たちを見た。
「・・・・・あのさ」
「ん?」
「お前らに、話す時が来たか・・・・」
「何を、すか?」
すると、健太は、一呼吸置いてから、ゆっくりと話し出した。
「俺の幼馴染に夏海という子がいたんだ」
「夏海??」
「夏の海と書いて、夏海。」
健太は、落ち着いて話し出していた。もう覚悟は決めていた。
「夏海、明るくて、いつでも笑っとるような奴で、笑顔で、教室でよくギターを弾きよったな。夏になると、教室から海を見ながら、‘死んだら海になりたい’って言うような女やった。誰に対しても明るくて、笑顔で、ニコニコしよって、そんな夏海のことを、俺は・・・・・・・・・・。でも」
「でも?」
健太は落ち着いていた。
「17歳の時に、病気で死んだ。」
「え・・・・・・・・・・」
すると、健太が、近くにあった、バスケットボールを持った。そして、そのボールを撫でるよう触った。高校の近くには海がある。健太は、その海を切なそうな目で見た。
「ほんま、好きやった。あいつに何かしてあげれたかな・・・・」
健太の心には、‘夏海’がいつまでもいた。永遠に消えることのない、淡い恋心。健太は、夏海と笑い合った日々を、昨日のことのように思い出していた。健太は、体育館の傍に植えられている向日葵をふと見た。向日葵を見ていると、あの夏を思い出してしまい、正直辛かった。夏海、夏海に会いたいとものすごく思った。
「あれは、21年前・・・・・・・。」
第4章――「21年前」
本気で愛していた。でも、あいつは、17で死んだ――――・・・・・・・。
いつまでも忘れられない女のことを、俺は愛していた。
健太は、今でも夏海に会いたいと思う。ものすごく夏海に会いたいと思う。夏海がこの世にいないことが、信じられなかった。夏海が近くにいない。傍で笑ってた夏海がこの世にいない。健太は、夏海の死を受け入れるのにどれくらい時間がかかっただろう。でも、夏海は17で命を落とした。健太は、夏海が死んだときの顔も覚えている。脳裏に蘇る。夏海が亡くなった時のことを思い出すだけで、苦しくて、苦しくて、だから、煙草を吸って、夏海を、夏海の存在自体を忘れようとしていた。けど、そんなことしても、夏海のことは忘れられなかった。夏海は、海が好きな女の子だった。
夏海は、健太と同じで、海沿いの街に住んでいた。川村夏海、夏海と健太は小さい頃からの幼馴染だった。2人はいつでも一緒にいた。どんな時も一緒にいた。高校2年の春に付き合い、夏海は、真夏の太陽の日差しが降り注ぐ病室の中で、命を落とした。夏海は、どんな時も明るかった。夏海は夢の中にいた。夏海は亡き父親の夢を見ていた。夏海は、夢の中で亡き父と夕暮れに染まった海を見ていた。和樹は、綺麗な顔をしていた。シュッとした顔立ちをしていて、夏海の顔をじっと見た。和樹は笑っていた。和樹は、夏海の右頬を触った。和樹は、少し健太に似ていた。ワイルドな感じだった。
「夏海」
「お父ちゃん?」
「生きろよ」
そこで夢は終わった。目覚めると、朝になっていた。‘ほんまにリアルな夢やん’と夏海は思った。右頬の感触が残っていた。夢がリアルすぎて、少しビックリしていた。夏海は、朝の5時半に起きた。そして布団を押しのけ、遠くからだが窓から見える海を見た。夏海は、自分が今日も生きていることに感謝した。天国にいる父親・和樹に心の中で、‘お父ちゃん、今日も良い日になるよ’と問いかけた。夏海の父親、和樹は、おとなしく、ワイルドで、芯が熱い男だったと、前に、母の真由子から聞いたことがあった。
「お母ちゃん、朝やで~~」
「・・・・な・・・っちゃん・・・朝早いね~~お母ちゃんまだ眠いよ~~」
母の真由子は、本当に眠そうだった。
「焼けん~~~。あ――――」
「どしたんよーーー(笑)」
夏海は、フレンチトーストが焼けなくて悪戦苦闘していた。そして、夏海は、焦げ焦げのフレンチトーストを母親と2人で食べることになった。
「まっっずーーーー!」
「なっちゃん、大丈夫。蜂蜜掛けたら食べれる」
母親の真由子。34歳。肝っ玉母ちゃん。昼はスーパー、夜はスナックで働いている。真由子は、ラッキーストライクの煙草の箱から1本取り出し、ライターで煙草の先端部分を付け、吸い始めた。
「なっちゃん」
「ん?」
「健太、最近、元気?」
「元気元気、相変わらず、バスケ馬鹿よ」
「ははは(笑)」
そして、真由子は、洗面所の前でメイクをし出した。
「なっちゃん、お母ちゃんさーー」
「ん?」
「駅前に‘ひかりがおか’っていう、最近出来た新しい居酒屋のお店あるや―ん」
「うん」
「週一、そこで働くことにした」
夏海は、パンを落としそうになった。‘母ちゃん働きすぎやろ’って内心思ったが、言えなかった。夏海は、反対することなく、
「がんば」
と、一言言い、焦げ焦げのフレンチトーストにかぶりついた。真由子は、赤い口紅を付け、髪を巻いて、黒のワンピースを着て、また、ベランダで煙草をふかした。部屋は、ラッキーストライクの煙草の臭いがすごくした。ふと、真由子を見ると、真由子の後ろ姿は時折悲しく見えた。夏海のお父ちゃん、死んだ和樹のことを思い出しとんかな?と夏海は、思った。母の長い髪の毛が、春の風になびいた。そして、真由子が、部屋の中に入ってきた。
「お母ちゃん、私、大丈夫かな―料理が下手なんじゃ、お嫁に行けないわ~」
もう一度打つ。川村夏海、16歳。今日から高校2年生になる。夏海は、母親の真由子と2人暮らし。夏海は、数学化学、理数系が本当に苦手で、高校1年の時の調理実習の生姜焼きの調味料に、焼く前だからよかったのだが、大さじ8杯の砂糖を、銀の四角い入れ物のなかに入れた。夏海はそれ以来自信をなくした。料理を。
「なっちゃん、あんた、愛嬌とかほんまええんやから~。」
「お母ちゃん、ほんま?」
夏海は立ち直った。夏海は本当に立ち直りが早い。いわゆるポジティブ人間。どんなに辛いことがあっても一瞬で立ち直る。夏海は焦げ焦げのフレンチトーストを食べた後、洗面台で歯磨きをし、そして、前髪をアイロンしはじめた。
「あっつ――――――――」
夏海は前髪をアイロンしている時に、低温やけどをした。
「なっちゃん、8時になりよるで~」
「あっつ」
夏海は、またも洗面台で、前髪をアイロンでストレートにするのに悪戦苦闘していた。遂に真由子は、声を強くした。
「なっちゃん、急がんと!」
「あ、はいっ」
―❤
夏海は小さい頃から不思議や、謎、変、変わっとると言われてきた。夏海は本当に変人で、何考えとんか分らんと、よく人に言われてきた。夏海は、黒のリュックを背負い、そして、玄関を飛び出した。階段をおり、そして自転車置き場に行った。夏海は、自転車に乗り、こぎ出した。まず、アパートから坂道になっている坂をおり、そして、坂を下りたとこにあるローソンを曲がり、そこから田んぼばかり続く道を自転車でこぐ。青い空が広がり、春の風が気持ちよかった。夏海の天然パーマの髪が揺れた。そして、学校までもうすぐのとこにガードレールがある。ガードレールからは、光り輝く青い海が見える。海からの潮の匂いが鼻をくすぐる。ガードレールの板は、寂れているが、夏海は、朝の登校、そして夕方の帰り道、光が丘海岸の海を見て‘今日も頑張ろう’と思うことが日課になっていた。そして、夏海は、あいみょんの‘裸の心’をガードレールを自転車で下りながら歌っていた。
「この~恋が~~み~のりますよ――に――」
夏海はあいみょんが本当に好きだ。あいみょんのCDの発売日はほんまに必ずチェックしているし、雑誌も必ず買っている。あいみょんが出ているテレビも必ずチェックしている。夏海は初めてアルバイトでもらった給料で、あいみょんのCDを買った。1000何円もするCDだ。本当に欲しかったあいみょんのCDを、自分で働いたお金で初めて買ったときは、ものすごく嬉しい気持ちになった。
ガードレールを下りたところに、小さい頃から馴染の駄菓子屋さんがある。そこには、もう90近い、高齢の夫婦が住んでいた。
「お―なっちゃん」
「おじいちゃん、学校行ってきま―す!」
夏海は、満面の笑みで、駄菓子屋の出たとこを掃除している、タカさんに言った。
夏海は、そのまま自転車をこいだ。夏海が住んでいるのは、愛媛県のA島。人口、2000人。夏海は、光が丘海岸の波の音を感じながら、海沿いのガードレールの道を、自転車でこいでいた。すると、道の途中で、健太に会った。
「おーす、健太」
「あ、川村やん。」
「今日から高校2年やねーーー!」
「ほやな」
夏海は自転車からおり、健太の隣で歩き始めた。
「けんた」
「ん?」
「呼んだだけや(笑)」
「なんや(笑)」
すると、健太が話し出した。
「川村」
「ん?」
「貧乳―、ばーか」
「は?今からお胸も大きくなるんですー」
「やって、お前、まじ、胸ちっせー」
健太が、変態発言を夏海にした。2人は喧嘩?をしながら、高校までの道を歩いた。
「健太のばーか」
「ばかとは、なんぞ(笑)」
「やって、さっき、貧乳っていったやん」
「やって、ほんまに貧乳やもん―――」
「ばかやろ――」
「ははは(笑)」
そんなくだらない会話をしている間に、高校に着いた。健太とは、今年も同じ
クラスだった。
「今年も川村と一緒かー」
「え、嫌?」
「嫌やない」
すると、夏海は後ろから幼馴染で親友の愛に抱きしめられた。
「なっちゃーん~~~~~~~~~❤今年も一緒よ―――――――――❤」
夏海は、愛を抱きしめた。
「え、やった――――――――――――❤愛ちゃん、たくさん話そ――ね❤」
「早弁もたくさんしよ――――ね(^^♪)」
夏海と愛が騒いでいる時に、幼馴染の達也が来た。
「おめーら、俺のことも忘れんなよ~~~~~~。」
「え、たっつんも、A組?」
「ほやけど、悪いか?」
「え、達也、俺もAやぞ」
「え」
「え」
「「しゃ――――――――――――――――――!」」
健太と達也の声が廊下に響き渡った。そして、高校2年の季節が始まった。夏海と、健太は、席が一番後ろの、隣どうしになった。
「よろしく」
「寝よったら、起こすわ」
「起こすな、ばーか」
本当に幸せな日々だった。夏海は、こっそり、健太の横顔を見ていた。
居眠りしている健太
大あくびしている健太
友達と、談笑している健太
一生懸命、勉強している健太
どの健太も、本当に愛しくてたまらなかった。そして、夏海は、街から3駅離れた町の駅のドトールで、アルバイトをしていた。
「いらっしゃいませ――。メニューはお決まりでしょうか?」
夏海は、笑顔で、接客業をしていた。そして、そこのお店で出会った同い年の女、
木原咲と仲がよかった。咲は、健太の古くからの知りあいだった。夏海は、咲と、バイトの控室で談笑していた。
「夏海、思ったんやけど。」
「ん?」
「彼氏、おらんの?」
「は?おらんわ////」
咲は、顔をにやつかせながら、夏海に、たくさん話をした。
「あれは、幼馴染の、健太は?」
「健太?」
夏海の頬は少し赤かった。そして、夏海は、両手で顔を隠した。
「咲ちゃん」
「ん?」
夏海は、本当に、健太のことが好きだった。健太の1番なれたらな―とも思っていた。夏海は、健太のことを想うと、胸が高鳴ってしょうがなかった。そして、次の日の、放課後。時間は夕方の時間帯、テスト期間もあって、運動部は部活が休みだった。
「川村」
「ん?」
「一緒に帰んね――か?」
「ええよ、帰ろ――」
夏海と健太は、肩を並べて帰った。健太は、夏海の頭1個分、背が高かった。A島は、この日は、天気がよく晴れていて、遠くのほうで、鴎の鳴き声が聞こえた。夏海と、健太は、桜並木を歩き、そして、通学路にもなっている、海沿いのガードレールを歩いた。空は、辺り一面に、青空が広がっていた。
―第5章「好きだ」
「川村、彼氏いんのかよ」
歩いている時、健太が聞いてきた。
「え・・・・・・・・・おらんよ――(笑)何言いよるん(笑)」
すると、健太が率直な質問をしてきた。
「川村、あのさ、俺がいきなりお前のことを抱きしめたら、どうする?」
「え・・・・・・・・」
夏海は、健太の方を見た。
「もし俺が、お前にキスしたら、川村、どうする?」
夏海は、頬が熱くなった。夏海は話題を変えた。
「健太~、明日、数学のミニテストやーん。勉強した?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・、貧乳のくせに」
「まじムカつく、死ね」
「死ねってなんぞ、ばーか」
2人は大人げない会話をしていた。夏海は、ふと自分の胸の方を見た。‘健太はおっぱい大きい子が好きなんかな?’と思った。すると夏海は、健太の後ろからの視線を感じた。健太からの視線を強く感じた。夏海の心臓がとくとくと高鳴った。後ろを見ると、健太が真剣な目で夏海を見ていた。夏海は、前へと視線を戻した。すると、健太が夏海の左手首を後ろから掴んだ。夏海はびっくりした。
静かな沈黙が流れた。夏海は健太の方を再度振り返った。健太の頬が少し赤かった。
(健太・・・・・・・・・?)
すると、後ろから健太が夏海を抱きしめた。夏海は、何が起こっているのか分からなかった。健太の腕は力強かった。夏海は、健太の温もりを感じた。
「ちょ、健太・・・・・・・・?」
健太は、本当に力強く、健太から離れようとしたが、抵抗出来なかった。
健太の頬が赤かった。健太は、夏海を自分の身体から話し、一言言った。
「並んで歩こう・・・・・・・」
海沿いのガードレールを2人で歩くのは久しぶりだった。高校2年の春のことだった。夏海はふと健太を見た。健太の横顔は凛としていて綺麗だった。2人の身体の距離が近くなった。夏海は、今にも心臓の音が健太にバレルんやないかと思って、心臓の鼓動が収まらなかった。夏海の頬が少し熱くなった。そして、2人の手が当たった。
「あ、ごめん・・・・っ」
夏海が手を心臓のとこにもっていこうとしたその時、健太が、夏海の右手を握った。夏海は、‘え?’と思った。夏海の心臓の鼓動は増すばかりだった。ドクンドクンと心臓が音を立てていた。
「な――」
「ん?」
すると、健太が夏海の顔を見た。健太が切なそうな顔で夏海を見た。健太は、夏海の唇を触った。柔らかくてぷっくらしている唇をそっと触った。すると、健太が顔を近づけた。2人の顔の距離は近かった。
「好きだ。ずっと好きだった。」
そう言うと、健太は夏海にキスをした。高校2年生の春のことだった。お互い、初めてのファーストキスだった。夏海は、目を閉じた。
6章―――「両想い」
あれから何秒経っただろう。健太が唇を離した。夏海は恥ずかしすぎて健太の顔を見れなかった。
「好きだ・・・・・」
健太は夏海を思いっきり抱きしめた。健太の腕は力強かった。健太の吐息、心臓の鼓動、体温。夏海は全てを感じ取った。淡い、高校2年の春のことだった。夏海は、返事が出来ずに、ただ、健太を避けてしまう日々が続いた。
健太のことが好きやのに
健太のことが好きやのに
幼馴染の関係が壊れるんが怖い、とばかり思ってしまい、
学校でも、健太を避けていた。そんなことを考えているうちに、季節は6月になった。6月某日、放課後教室で勉強していると、健太の先輩の、有馬さんが教室に入ってきた。
「有馬さん」
「お、なっちゃんやん」
高校2年の初夏。教室で勉強している時に、練習着で汗だくの有馬が教室に来た。
「てか、有馬さん、入る教室間違えてません?(笑)」
「間違えた(笑)はは(笑)」
「・・・・・・・・・有馬さん、健太頑張ってますか?」
すると、有馬は、夏海の教室机にもたれかかった。
「あいつな・・・・」
有馬は、少し険しそうな顔をした。
「あいつ・・・予選の準決勝でシュート外したこと、すげ―気にしてたんだよ。先輩たちの夢を壊してすみませんって・・・・前に泣きながら誤ってきて・・・。健太、でも、毎朝、シュート練習しよって・・・・・・。あいつは強くなるよ。俺も、大学でも
バスケしようと思うし、今日は、ちょい、受験勉強の合間をぬって、練習―」
夏海は、なるほど、と思った。最近、健太の元気がなく、どうしたのかと思ったが、
立ち直ったんならよかった、と思った。
「・・・・・・・・・健太、ほんまにバスケ好きですもんね」
すると、有馬は、夏海を見て、白い歯を出した。
「なっちゃんのこともな」
「え、え?」
「何、そんなびっくりしてんだよ。バスケ部で噂になってんぞ―。健太となっちゃんが両想いって❤ヒューヒュー❤」
夏海の頬が、林檎みたいに赤く染まっていった。
そして、夏海は、有馬の顔をじっと見た。
「あいつ、めっちゃ俺に、電話とかで、‘夏海のことがすげ―好きやから、有馬、惚れんでな’とか‘夏海が今日髪結んどって可愛かった’とか、あいつ、ほんまに、なっちゃんのこと、すげ―想っとる」
夕暮れに染まる教室で、夏海の心臓は高鳴った。すると、有馬が夏海の頭をポンッと触った。有馬は、クスッと子供のような無邪気な顔を見せた。
「なっちゃん」
「どうされました?」
「健太のこと好きか?」
夏海の頬が少し赤く染まった。すると、夏海が顔を下に向けた。
「・・・・・・好きなんか、健太のこと」
「え、好きやないです」
すると、有馬がからかった。
「ほんま?健太の奴、部活の休憩時間の時とか、達也に、むっちゃ、なっちゃんの話してたで。なっちゃん、ほんまに愛されてんな」
すると、有馬は、タオルを頭に被って、教室を出ていった。すると、教室の外から、有馬は夏海を見た。
「なっちゃん」
「も―、なんですか。」
「健太の気持ち、確かめてみたら?」
すると、有馬は、向こうの方へと、走っていった。そして、夏海は、ギタ―を教室の床に置いて、壁にもたれかかった。その時、軽音部のバンドが、あいみょんの
「3636」を練習していた。夏海は、目を瞑って、そして、あいみょんの「3636」を口ずさんだ。夏海は、軽音部の音を聴いていたら、いてもたってもいられなくなり、ギタ―で曲を作り始めた。
「――――――――♪」
夏海は、教室から見える海を見ながら、歌っていた。そして、遠くの方で、バスケ部の集団が、夏海の綺麗な歌声を聴いていた。ふと、健太が言った。
「夏海の歌声、好きやな」
すると、達也が健太を茶化した。
「けんちゃん、付き合ったらええやん――も―――❤」
すると、健太の頬が少し赤く染まり、健太は、口元を右手で隠した。すると、達也が健太ににやにやしながら言った。
「なっちゃんとキス出来たら最高やろ?」
「は?」
健太の顔がますます赤くなった。すると、バスケ部員が茶化しだした。
「健太さん、しちゃえ~」
「愛しの‘なっちゃん’とキス」
「青春やね――――❤」
健太は、照れ隠しなのか、‘うっせ―’と言った。
「おい、お前ら、練習再開するぞ」
「「うすっ」」
男子バスケ部が、練習を再開した。夕方の6時半を回っていた。夜8時、夏海はまたも、教室にいた。この前、カメラのキタムラで現像した、高校入学する前の春に、幼馴染4人で、春休みにディズニーランドに行った写真を、机の上に並べ、そして眺めていた。夏海は、スマホを取り出し、マイヘアーイズバッドの‘卒業’を、音楽アプリで流した。すると、健太からLINEが来た。
‘川村’
‘ん?’
‘教室おる?’
‘おるよ’
‘一緒に帰ろうぜ――’
夏海は、珍しいと思った。健太からお誘いのLINEが来ることは滅多になかった。
‘どしたん急に?’
‘いいから’
夏海は健太と一緒に帰ることになった。ギターケースを背負い、そして、夏海は気持ちを落ち着かせた。夏海は、健太が教室に来るのを待っていた。そして、健太が、教室に来た。
「うす」
「あ・・・・・・おひさ」
2人がまともに話すのは、2か月ぶりだった。そして、健太は、夏海の、
天然パーマの髪の毛を、そっと、右手で触った。
「・・・・・・・・・夏海」
「ん?」
すると、健太が、夏海を抱きしめた。
「好きだ・・・・・・・・・・。夏海と一緒にいたい。」
夏海の心臓の鼓動は、半端なかった。そして、夏海は、抱きしめかえした。
「・・・・私も、健太と一緒にいたい。好き。」
高校2年の6月某日、2人は付き合った。本当に幸せなことだった。
第7章―――「初体験」
―あの日の夜を忘れない。あの日の夜、夏海の肌に触れた。心臓の鼓動が半端なかった。ベットの上で夏海を抱きしめた時、夏海がすこし震えていた。夏海の温もりを感じた。夏海の温もりに触れた夜、夏海の頬は赤かった。夏海が‘女’の顔をしていた。そして、夏海は泣いた。
「ねー、健太」
「ん?」
「キスする?」
「ん、なんて?」
「やけん、き、す!」
夏海と健太は、商店街を歩いていた。健太の頬が少し赤くなった。そして、健太は、夏海の左手を、握った。
「おまえ、手、ちっせーな」
光が丘商店街は、出口のところに本屋さんがある。夏海は、内容が少しエロい漫画を読んでいた。
「・・・・・えっろ」
「お前、何見よんぞ」
「えろい漫画」
「アホ」
夏海は、ちょい官能的な内容の漫画を立ち読みしていて、健太に頭をチョップされた。夏海は、下をペロッと出した。
「健太」
「ん?」
夕暮れの商店街、夏海は健太と一緒に帰っていた。健太は自動販売機で買った、ブラックコーヒーを飲んでいた。夏海の頬が少し赤くなっていた。
「・・・・・・・」
「何その顔」
「チューしよ」
健太は、コーヒーを少し吹き出した。
「んん?なんて?」
健太はわざと、聞こえていないふりをしていた。でも、内心すごく嬉しかった。
「やけん、キスしよ」
「いいよ」
周りには誰もいなかった。健太は夏海に顔を近づけ、2人は唇を重ねた。すると、健太が舌を入れてきた。夏海は、健太から離れた。
「・・・・けんた?」
「ごめん、無意識・・・・」
健太が前をすたすたと歩き始めた。健太は最近自分が変だと思ってきた。夏海が近くにいると、変な気持ちになってしまう自分がいた。キスの最中に舌を入れるとか、ほんま変人やん、、、とも思った。中学の時、保健体育の性教育で、男女の性について勉強した。そん時はあまり深く考えなかったが、いざ好きな子を前にすると、すごく変ないやらしい気持ちになってしまう。いつか、自分の行動で夏海を傷付けてしまうんやないかと思ってしまうこともあった。すると、夏海が後ろから抱き着いてきた。夏海の胸の感触が背中にあたった。‘あ、、、、’と健太は理性をなくしそうだった。本当に健太は理性をなくしそうだった。
「・・・・・甘えんぼさん。」
「健太・・・・・・・」
夏海は更に強く抱きしめてきた。
「てか、お前、胸大きくなった?」
「何なん、ばか・・・・・・」
「・・・・・・ほんま、俺がどんだけ我慢してんだと思ってんだよ(ボソッ)」
「ん?なんか言った?」
健太は、ドキドキしていた。夏海のふとした時の女の顔、金木犀の香り、胸の感触、ほんと、全てにドキドキしていた。
「夏海」
「ん」
すると、健太がキスをした。今度は、少し大人な、甘いキスだった。夏海の呼吸が乱れた。
「は・・・・っ・・・・・はっ・・・・・・けんた?」
健太の頬が少し赤くなった。
「俺の家来る?」
高校2年の7月、夏海は健太の部屋にいた。
「健太、キスしていい?」
夏海は、部屋で健太にキスをした。そして、2人は深くキスをし合った。健太は、
男の子の顔をしていた。2人は、何度も何度もキスを交わした。すると、健太が
乱暴に夏海に言った。
「好きだ、大好きだ、大好きなんだよ、お前の事、大事にしたい。なんで俺の気持ち分かんねーんだよ。俺がどんだけ我慢してんだと思ってんだよ・・・・・・・」
健太が、夏海を抱きしめた。そして、健太は夏海に力強くキスをした。夏海は、呼吸が上手く出来なかった。健太が夏海の制服の中に手を入れた。健太は、夏海の首筋にキスをした。夏海の身体は細かった。夏海が少し震えていた。
「け・・・・・・ん・・・た」
「好きだよ」
健太と目があった瞬間、健太が舌を入れてきた。そして、健太は夏海の制服の中へと手を伸ばしてきた。
「けんた・・・・・・っっ」
「・・・・・・夏海、ごめん。」
「健太、好きだよ。」
夏海が健太にキスをした。夏海の頬は、赤く染まっていた。
「な・・・なつみ?」
夏海は健太の目をじっと見た。健太の頬は赤く、真剣な表情だった。2人は何回も唇を重ねた。夏海は、健太の鼓動、真剣な目、手を強く握り返してくれるとこ、全てにドキドキしていた。健太は夏海をベッドの上にゆっくりと押し倒した。そして、健太は夏海の両手を握り、キスをした。唇・頬・そして、夏海の華奢な首筋にもキスをした。健太の身体は力強かった。健太が震えながら、夏海の両頬を触った。健太は理性をなくしかけていた。夏海の心臓がバクバクと鳴った。すると、健太が、夏海の太ももあたりをさぐっっていた。
「夏海・・・・好きだ」
再度、健太は夏海にキスをし、夏海の柔らかい、ふっくらとした唇にもキスをした。外では、海のさざ波が、優しい柔らかな音を立てていた。夏海の頬が林檎のように赤く染まっていた。健太は真剣な眼差しで、男の子の顔をしていた。
「好きだ・・・・・っ」
「はっ、はっ・・・・・けんた・・・・っ」
健太がすごく恥ずかしそうだった。健太は、深く深く夏海にキスをした。すると、健太がキスの最中に舌を入れてきた。夏海は、息が出来なかった。健太は、夏海の着ている制服のボタンをはずし、タンクトップの状態にした。健太が夏海の首筋にキスをした。
「あ・・・・・っっ」
夏海は、感じていた。健太の睫毛から汗の雫がぽたっと、夏海の頬に落ちた。健太の頬が本当に赤かった。
「夏海、優しくするから」
「・・・・・うん」
健太は、夏海の下をさぐった。太もも、そして、夏海の足をなぞるように探った。健太は、夏海の唇、お腹、太ももと、全身にキスをしていった。夜の街は静かだった。静かな夜の海のさざ波の音と、ひぐらしの鳴く声が2人を包んだ。6歳の時に2人は出会い、そして高校2年の初夏に恋人になった。そして、2人は‘初めて’を経験した。健太は、夏海のタンクトップを脱がし、そして、夏海の付けている白のブラジャーをはずそうとホックのとこに手を伸ばした時、手が震えた。あまりにも、心臓がバクバクしていた。
「健太」
「ん」
「ゆっくりでいいよ」
夏海が少し笑った。健太はゆっくりとブラジャーのホックを外した。健太は夏海の胸を直視した。そして、健太は夏海に言った。
「夏海、綺麗だ・・・・・・・・」
2人はつよく抱き合った。薄明りの部屋の中で、2人は愛し合った。
「あ・・・・・・っ」
健太は優しかった。夏海は、健太にキスをした。
「健太・・・・・・。」
「ん」
「もう一回キスしよう」
夏海の身体は細かった。外からさざ波が聞こえる。1つの空間に2人だけがいるようだった。健太は、夏海の首筋に埋もれるようにキスをした。夏海は健太の鼓動を強く感じた。健太は、夏海の両手を更に強く握り、そして、再度キスをした。
2人は唇を重ねた。2人は強く強く抱き合った。夏海の身体は柔らかかった。
夏海は感じていた。健太の温もり、力強さ、強く手を握ってくるとこ、全てがたまらなく愛しかった。そして、2人は繋がった。健太は夏海の温もり、夏海は健太の温もりを強く感じていた。
「け・・・・・・んた」
健太は夏海にキスをした。健太の汗が夏海の白い肌に落ちた。夏海の身体の中で、少し痛みが走った。夏海は、その痛さが走った時、健太を更に強く抱きしめた。そして、健太は、切なそうに言った。
「夏海、愛してる」
と言い、夏海の唇にそっとキスをした。夏海は、健太の温もりを感じていた。健太の腕は力強かった。幸せすぎたから。夏海が、ベットのシーツを掴み、そして、後ろからも健太は、夏海の手を握った。2人は愛を感じていた。健太の汗が、ぽたっと、夏海の手に落ちた。繋がれることが本当に幸せだった。健太と繋がれることが本当に幸せすぎたから。だから、‘この夜が、最初で最後’と思った。本当にこの夜が最初で最後だった。2人は抱き合った。深く深く抱き合った。次の日の朝、夏海は目覚めた。横では、健太が眠っていた。ベッドの横のテーブルには、コンドームの箱と、殻の入れ物が置かれていた。昨夜、健太は夏海に何度もキスをし、そして、ぎこちない手つきで、夏海の頬を触り、ゆっくりと2人は繋がった。そして、今朝。朝の海は黄金色に輝いていた。
(健太、愛してる)
―8章「二人の絆」
―あいつに会いたいよ。強くそう思う。
「お・・・・っ」
「ん?」
「おはよ」
夏海は、健太の部屋で制服に着替えていた。夏海の頬は少し赤かった。
「夏海」
「どし・・・・・・」
―チュッ
健太は半分身体を起こして、夏海にキスをした。夏海は不意打ちのキスに、すごくドキドキした。今にも心臓が飛び出そうだった。
「・・・・・・・まだ、健太とのキスに慣れない・・・・・・・・・です」
「・・・・・・・え、ほんまに?夏海・・・・・・・オレも・・・・・・・・」
すると、健太は、夏海にキスをし出した。舌も入れ合う、少し激しいキスをした。すると、健太が話し出した。
「夏海、好きだ~」
健太は、ベットの上で夏海を抱きしめた。夏海は、身体を起こして、白のレースのブラジャーを付けた。すると、視線が感じたので、後ろを向くと、健太が凝視していた。
「健太、変態やん//」
「ええやん、別に・・・・・・///」
健太は、壁の方を向いた。健太の耳は赤かった。
そして2人は、家を出て、朝の海沿いを散歩した。朝の漁港は、本当に綺麗だった。
「夏海」
「ん?」
健太は夏海にキスをした。夏海の頬が少し赤くなった。
「けんた~~~~、いつからそんなに、激しい人になったん?」
「え、いつからやろー、夏海、もっとエロいキスする?」
「えっろ、、、、w」
―ははは
二人は笑い合った。
2人は海沿いを散歩した後、光が丘商店街も散歩した。朝だからなのか、どこのお店も閉まっていた。ゆういつ開いているのが、ローソンだった。夏海と健太は、そこで、コーヒーを2つ買った。2人で飲みながら商店街を歩いた。2人は肩を寄せ合いながら歩いていた。朝の陽ざしが眩しかった。遠くで小鳥の鳴き声が聞こえる。商店街の店のシャッターが上がる音も聞こえる。
「なー、夏海」
「ん?」
「俺、夏海と・・・・・・・・・ずっと一緒にいたい」
夏海は、健太の想いにびっくりした。それは、夏海も一緒だった。
「うん、私も・・・・・・」
―健太と初めての夜を迎えた。
好きな人と触れ合える喜びを初めて知った。
健太、大好きだよ。
大好き。
大好き。
大好き。
健太、ずっと一緒にいようね。
第9章―――「ALS」
「はーは―――・・・・」
「なっちゃん、大丈夫?」
ここ最近、夏海の体調が悪い日々が続いた。夏海は、すぐこけたり、箸が上手くもてなかったり、身体が思うように動かせない日々が続いた。母の真由子の勧めもあって、町の大きな病院で受診したところ、病気が発覚した。
「夏海さんの病名はALS。筋萎縮性側索硬化症という病気です。」
「え・・・・・・・」
夏海も、そして、真由子も言葉を失った。夏海は、まだ、17歳だった。そして、医師の中屋は、言葉を続けた。
「体を動かすのに必要な筋肉が徐々にやせていき、力が弱くなって思うように動かせなくなる病気です。筋力の低下が主な症状ですが、筋萎縮性側索硬化症は筋肉の病気ではなく、筋肉を動かしている脳神経がダメージを受けることで発症します。脳から筋肉に指令が伝わらなくなることで手足や喉、舌の筋肉や呼吸筋が徐々にやせていきます。夏海さんの年齢で発症することも珍しくないです。」
夏海の頭の中は真っ白だった。そして、中屋に聞いた。
「中屋医師。」
「はい」
「私は・・・・・・元気になれますか?」
診察室が一瞬の沈黙に包まれた。そして、中屋は、言葉を発した。
「筋肉がやせると体を上手く動かすことができず、呼吸筋が弱まると呼吸困難に陥り人工呼吸器が必要になります。一般的に症状の進行は速く、人工呼吸器を使用しなければ発症から2~5年で死に至ることが多いといわれていますが、個人差は非常に大きく10年以上かけてゆっくり進行する場合もあります。夏海さん、呼吸器を使用しない選択をするとなると・・・・・・・もって1年・・・・・・」
夏海の目からは赤くなっていた。夏海は、早すぎる選択をしなければならなくなった。早すぎた。17歳だった。そして、中屋は、言葉を続けた。
「ALSは手足の筋力低下から始まることが一般的です。手の筋力が低下するとペットボトルの蓋が開けにくい、髪を洗うときに腕を挙げにくいなどの症状がみられ、足の筋力が低下すると階段の昇り降りが難しくなったり、椅子から立ち上がりにくくなったりします。夏海さん、これからのこと、お母様とも、よく話あっていきましょうね・・・・・・・・・・。」
夏海と真由子は病室を出た。夏海は、真由子に支えてもらいながら、歩行が不安定な状態で歩いた。そして、夏海は、真由子に言った。
「母ちゃん」
「ん?」
「ごめんね・・・・・・・・・。私、長く生きれないかも・・・・・・・。」
真由子は、泣くのを堪えた。夏海は、足を引きずるように歩いていた。夏海は、自分の未来が見えなくなった。
―私は。ALSという病気になった。
呼吸器を付けなければ、もって1年・・・・・・・。
神様、いじわるしないでくださいー。涙
私、もっと、生きたいよ。
したいこと、たくさんあるよ。
死にたくないよ。生きたいよ。死にたくないよ。私は、18ぐらいで死ぬ・・・・・。
苦しい。辛い。
第10章―――「辛い選択」
夏海は、次の日から、学校を休んだ。
〈夏海、大丈夫?〉
健太から、心配のLINEが来た。夏海は、そのLINEに返信するのも億劫だった。夏海は、怖かった。自分の身体がどんどん動かせなくなるのが、怖かった。夏海は、ふらふらになりながら立ち上がり、食卓のテーブルの椅子に座った。そして、傍に置いてあった、1枚のメモ用紙に文字を書いてみた。
―けんた、好き
と書いた。でも、手が思うように動かせずに、ふらふらになりながら書いた。夏海は、これから、どのように自分は生きていけばいいのか、分からなくなった。すると、電話がかかってきた。健太からだった。
―あ、夏海、どしたんお前?
―あ・・・・けん・・・た?
―お前、風邪?夏海、なんか持っていこうか?ゼリーとか
―い・・・いよ、だ・・・いじょ・・・・・う・・・ぶ
―あー、おけおけ
―け・・・・んた
―ん?
夏海は、意識が遠のいていく寸前だった。
―わ・・・・たし
―うん
夏海は、言った。
―け・・・・・ん・・た・・・・・が・・・・す・・・・き
〈健太が好き〉
そして、そこで、夏海は椅子から床に倒れた。夏海の意識はどんどん遠のいていった。
―夏海、おい、夏海・・・・・・!?
―・・・・・・け・・・・ん・・・た
そこで、夏海の意識が途切れた。気づいたら、夏海は、病院の病室のベットの上にいた。
「なっちゃん・・・・・・・・」
「か・・・・あ・・・・ち・・・・・・ゃ・・・ん」
夏海は、ALSの症状が、ますます進んでいた。その後、中屋医師が来た。
「夏海さん、運動、コミュニケーション、嚥下、呼吸の4つの障害のうち、最初にあらわれる症状は人によって異なりますが、最初の症状がどれであっても、症状が進むとともに、これら4つの症状がすべてあらわれるようになります。患者さんによって病気の進行の速さは違いますが、運動障害が最初にあらわれる患者さんの場合、次第に手足がやせていき、歩いたり動いたりすることが困難になります。夏海さんは、運動障害が出ています。さらに症状が進むと、食べ物を飲み込むこと、ことばを発することが困難になります。顔の筋肉の力が弱くなってくると、よだれが出たりします。食べ物を飲み込みにくくなったら、チューブを通して栄養をとる場合もあります。 次第に全身の筋肉の力が弱くなり、自力では起き上がれなくなります。しかし、意識や五感は最後まで正常で、知能の働きも変わりません。」
夏海の目からは涙が溢れてきた。そして、夏海は1枚の紙に書いた。
―せんせい、こきゅうきはつけません
医師の中屋、そして、真由子は驚きを隠せなかった。そして、夏海は、もう1枚、紙に書いた。
―けんたとけっこんしたい
夏海は、あと、1年しか生きられない。真由子は、病室の外に出て、泣いた。外は晴れていた。
第11章―――「小さい頃の約束」
―お前、名前は?
―かわむらなつみ
―へー、ええ名前やん。なつみ、なつみ、なつみ。よし、覚えた。よろしくな。なつみ。
―あの、名前は?
―けんた。やまむらけんた。
―けんた、けんた、けんた。なつみも、おぼえた。
2人の出会いは、光が丘海岸の花壇だった。夏の暑い日、2人は、出会った。
―なつみ
―ん?
―ええ笑顔やな。よろしくな。
2人は手を握り合った。そして、そこで、夏海は目が覚めた。夏海は、点滴に繋がれていた。夏海は、病室の外の光が丘海岸を見た。今日は少し、雨の日だった。
「・・・・・・・・・・・」
夏海は、生きている意味が分からなくなっていた。夏海は、ただ、病室の天井を見ることしか出来なかった。
―ぽつん、ぽつん
雨の音色が、夏海の心を少し悲しくさせた。夏海は、もう、このまま死んでもいいと思っていた。すると、ドアのノックが聞こえた。
―入ってもいいですか?
入ってきた人物は、愛だった。
「あ・・・・・・・い・・・・・ちゃ・・・・・・・ん」
「なっちゃん、やほ~」
愛は、ベットの近くの椅子に座った。
「なっちゃん、調子はどう?」
すると、夏海は、紙に書いた
―あんまりかな・・・・・・
すると、愛は、スマホで1枚の写真を見せてくれた。スポーツ大会で、健太がバスケのシュートを決めた時の写真だった。
「健太、シュート決めたよ。ほんで、周りの子たちと、めっちゃ、喜こんどった・・・・・!」
夏海の目が少し赤くなった。夏海は、そのスマホの写真を、じっと見た。
健太に会いたい、と強く思った。夏海は、紙に書いた。
―けんたに、あいたい
愛は、その紙のメッセージを見ると、愛は、夏海の頭をポンポンとした。そして、愛は、言葉を続けた。
「山村さ・・・・・・・・・ずっと、なっちゃんの席ばかり見よんよね・・・・・・・。切なそうな目で、ずっと・・・・・・なっちゃんの方の席を見よる。すごい、なっちゃんに会いたそう・・・・・。」
雨は止むことなく、ポツンポツンと音を立てていた。そして、夜、夏海は、夢を見ていた。
―なつみ
―ん?
夢の中の場所は、光が丘海岸。夏海と健太、お互い高校の夏の制服姿。
そして、健太は、夢の中で言葉を続けた。
「俺、夏海がおらんと、生きていけんかも・・・・・・。夏海って、ほんま、綺麗で、心も優しくて、純粋で、真っすぐで、頑張り屋さんで・・・・・・・俺、前に、夏海が教室で泣きよった時、‘こいつのこと守れるんは俺しかおらん’って強く思ってさー。夏海、俺、夏海が好きだよ。」
夏海は目覚めた時、その夢の中の言葉が、健太の本当の想いのような気がしてならなかった。夏海の目からは、1粒の涙が流れ落ちた。
第12章―――「17歳の誕生日」
ーねー、ママ
―ん?
3歳の誕生日の時、夏海は、母の真由子に聞いた。
―なんで、なつみには、パパがいないんー?
―・・・・・・パパはね、遠くの方にいるんよ。いつか、なっちゃんのことを、迎えに来るよー。🐎
―うれちー♡パパ、むかえにこんかなー?
夏海は、17歳の誕生日の日を迎えた。母の真由子と祖母の夏が病室に来た。真由子が、1本の向日葵を、瓶で飾ってくれた。
「おめでとう・・・・。」
真由子が、笑顔で、そう言ってくれた。祖母の夏も、‘夏海、17歳の誕生日おめでとう’と言ってくれた。夏海は、白い紙に
―ありがとう
と、そう書いた。すると、真由子が、夏海の目を見て、言った。
「なっちゃん、健太!健太が、昼頃、病室に来るよー。♡」
夏海の心臓の鼓動が、とくんとくん、と鳴っていた。夏海は、紙に、
―うれしい、けんた、はやくこんかな
と書いた。夏海も、恋する乙女だった。夏海は、健太が病室に来るのが楽しみだった。昼頃、病室のノックがなった。‘入りまーす’と、声がした。すると、健太と、もう1人、達也が病室に入ってきた。
「夏海・・・・・・・・・・」
すると、夏海が、紙に書いた。
―けんた、あいたかった
健太の頬が少し赤くなった。そして、隣で達也がからかった。
「けんちゃん~会いたかった、ってー♡よかったなー♡」
すると、夏海は、もう1枚、紙に書いた。
―たっつんも、きてくれて、ありがとう
すると、達也は、はにかんだ。
「ええでー(^_-)-☆」
すると、健太が、ベットの上にいる夏海を抱きしめた。
「・・・・誕生日おめでとう。」
その一言だけだったが、夏海の心臓の鼓動が半端なかった。すると、健太は、自分の行動にハッと気が付き、夏海を自分の身体から、そっと離した。すると、達也がからかってきた。
「けんちゃん、そのまま、キスもしちゃえよ♡」
健太は、照れ隠しなのか、口を自分の手で隠した。
「うっせーな////」
健太は、そう言いながら、ショルダーバックから、何かを取りだした。小さな紙の入れ物だった。
「これ、俺と思って、付けてくれたら・・・・・」
夏海は、その紙袋を、ゆっくりと開けた。ハートのネックレスだった。健太は、照れながら話をした。
「俺・・・・・・・お前がおらんと寂しいんだよ。まー、それ、俺と思ってくれたら」
「なっちゃん、けんちゃん、ほんまに寂しそうでさー。弁当の時とか、学校帰りとか、‘なつみがおらんと寂しい’って、めっちゃ、言いよるで♡なっちゃん、愛されてんな♡」
すると、健太は耳まで赤くしながら、言った。
「お前、言わんでええけん///」
すると、夏海は、紙に書いた。
―けんた、なつみのこと、すき?
すると、健太が、顔を赤くして、言った。達也はにやにやしていた。健太は、夏海の耳元で言った。
「・・・・・・・・好きやし、アホ。大好きだよ、夏海・・・・・・・。」
「俺、病室出とくわ♡」
達也は、気を使ってくれたのか、病室を出た。病室には、夏海と健太、2人だけの空間になった。
「・・・・・・・・夏海」
「・・・・ん?」
すると、健太は、夏海にキスをした。不意打ちのキスだった。健太のキスは、優しかった。唇を離した後、健太は一言言った。
「・・・・・・・俺、最近、おかしいわ・・・・・・・///」
そして、健太は、病室を出た。夏海の心臓の鼓動がおさまらなかった。夏海は、自分の頬を触った。頬は熱かった。夏海は、幸せな、17歳の誕生日を迎えた。
―幸せな誕生日。
病室に、健太とたっつんが来た。
健太がハートのネックレスをプレゼントしてくれた。
ほんで、好きって言ってくれた。
キスもしてくれた。
ほんと、今死んでもいいくらい、幸せな誕生日やった・・・・♡
けんた、好き。
大好き。♡ずっと、一緒にいようね・・・・・・・。♡
でも、なつみ、あと1年・・・・・・・涙
第13章―――「好き」
「ごほっ・・・・・・・ごほっ・・・・」
「なっちゃん?」
9月になった。夏海は、食べ物が上手く、呑み込めなくなっていた。夏海は、嚥下障害が出てきていた。夏海は、自分の首あたりを触った。夏海は、辛かった。苦しかった。夏海は、窓の外を見た。光が丘海岸の海は、太陽の光に当たって綺麗だった。夏海は、いつからか、こう思うようになった。
―死んだら海になりたい
17歳。人生あと100年。でも夏海は1年・・・・。夏海は、病院のテーブルの上に置いてある、健太との2ショットを見た。夏海は、思った。自分が死んで、健太が、他の子と付き合って結婚をする。夏海は、その方が、健太も幸せなんやないかと、ここ最近、思うようになっていた。夏海は、ふと、高校1年の夏、健太と付き合う前のことを思い出していた。
―川村
―ん?
―川村の好きな異性のタイプは?
―え、なんでそんなこと聞くん・・・・?
―ええやん//言えって・・・・・・///
―言わん、ばーか
―は?なんでや
―・・・・じゃー、健太の好きなタイプは?
―俺は・・・・・・・好きになった人がタイプ
―え、ほんま?
光が丘海岸で、そんな会話を、健太としていた。そして、お互いの将来のことも話した。
―俺、将来の夢、高校教師。
―へー、ええやん
―夏海は?
―私の夢は
―うん
―普通に暮らすこと
―なんや、それ(笑)
―1つ言うと
―うん
―好きな人のお嫁さん
―・・・・・・ほー、てかお前、好きな人おるん?
―内緒♡
夏海は、高校1年の夏、光が丘海岸で、健太とそんな会話をしたことを思い出した。夏海は、‘本当に幸せやったな’と、強く思った。夏海は、ハートのペンダントを触った。健太といつでも、一緒にいる気がした。夏海は、そのまま眠りについた。
第14章―――「想い出」
―好きだ
―夏海、可愛いな
―ずっと、一緒におりたいわい
―大きくなったら、結婚しよう
夏海は、ここ最近、思い出に浸っていた。夏海は、車いすに乗って、真由子に車いすを押してもらいながら、病院の周辺を散歩していた。
「か・・・・・あ・・・・ちゃ・・・・・・ん」
「ん?どした、なっちゃん?」
「・・・え・・・・・え・・・・・・てん・・・・・き・・・・や・・・・・ね」
17歳。季節は秋。天気は晴れていた。すると、真由子が話し始めた。
「なっちゃん・・・・・・なっちゃんが生まれた時も、こんな天気やったよ。なっちゃんが生まれた時、ほんとうに嬉しかった。」
「・・・・・・・・・・・・」
夏海は、気持ちが苦しかった。自分が死んだあと、母は?と思った。そして、夏海は、病院の花壇に咲いてある秋桜を見た。赤・ピンク・桃色、たくさんの色の秋桜が満開に咲いていた。なぜだろう、夏海は、その時、健太の顔が思い浮かんだ。
―夏海
夏海と呼ぶ健太が愛しい。恋しい。好き。夏海は、どんどん身体が弱っていき、死んでしまうことが怖くてたまらなかった。夏海は、母の真由子の顔を見て、言った。
「か・・・・あ・・・ちゃ・・・・ん」
「ん?」
「こわ・・・・・い」
「ん?どした?」
「し・・・ん・・・で・・・しま・・・・・・・・う・・・・の・・・が・・・こわ・・・・・・い」
真由子はその時、夏海の本当の思いを知ったような気がした。真由子は、車いすに乗っている夏海を抱きしめた。
「・・・・なっちゃん、ごめんね・・・・・・。なっちゃんを丈夫に産んであげれんで・・・・。母ちゃん、ずっと、後悔しとった・・・・・・・。なっちゃん、生まれてきてくれて、ありがとう。母ちゃん、なっちゃんを支えていくけんね・・・・・。」
母の真由子は、声を震わしながら、夏海に言った。夏海は、母の温もりを覚えておこう、そう心に決めた。
―母ちゃんは18で私を産んだ。
母ちゃんからたくさんの愛をもらった。
母ちゃんは強い
母ちゃんは明るい
母ちゃんは、心強い
母ちゃんは優しい
母ちゃん、私を、産んでくれてありがとう。
ALSになってごめんね。
母ちゃん、私、生きるよ。
―そんな真由子にも、過去の辛い出来事を、思い出すこともあった。
第15章―――「和樹」
ある時、真由子が病室で、夏海に和樹の話をした。夕方の時間帯のことだった。
―和樹、好きよ
生きててほしかった。死んでほしくなかった。和樹は、夏海が生まれた数日後に交通事故で、この世を去った。真由子は、18でシングルマザーになり、夏海を今まで育ててきた。真由子は思う、和樹が生きてたら、どんな家庭になってただろう。和樹がこの世にいないことが信じられなかった。大村和樹。和樹。真由子と同い年の男の子で夏海の亡き父親。和樹は、17年前、交通事故でこの世を去った。‘真由子’。真由子と呼んでくれる和樹の声が今でも脳裏に響く。真由子は和樹のことがいつまでも忘れられないでいた。和樹はレコード店の息子だった。会いたいと思っても、もう会えない。真由子は天国にいる和樹を、いつまでも想っていた。ずっとずっと、和樹のことを想っていた。和樹はこの世にいない。天国にいる。真由子は、ゆっくりと、自分の過去を夏海に話し始めた。
「母ちゃん・・・・・他は失ってもいいから、この人と一緒におりたい。そう想ったんは、和樹が初めてやった。」
真由子が和樹と出会ったのは、15年以上前の肌寒い高校1年の4月のことやった。真由子は和樹との日々を忘れたことがなかった。ガラケーの画面は、和樹との2ショットに、真由子はしていた。和樹は、優しい男だった。人からも好かれ、怒らない。本当に優しい男だった。真由子は、15歳の春に、和樹に恋をした。
「真由子、帰ろー」
「帰ろうか~」
真由子は、黒髪のロングで、目が大きくて、華奢で、綺麗な顔をしている。なので、他のクラスの人からも一目置かれていた。でも、真由子は恋はしないと決めていた。それは、生き別れた父親が最低な男だったから。恋なんかしたくないと思っていた。真由子は、生き別れた父親を憎んでいた。そのこともあって、人を好きになることが分からなかった。小さい頃に父親に殴られたあざが今でも残っている。真由子は、母の夏を殴り、蹴り、暴力でストレスを解消しようとしていた父親が本当に憎かった。父親の顔も思い出したくないくらい、父親が憎かった。この日の天気は雨だった。
―ポツン、ポツン
雨は、静かに音を立てていた。そして、真由子は、バス停で運命の出会いをした。真由子は、途中の道で里沙と別れ、バス停へと向かった。真由子は、バス停に着いた。すると、背の高い男の子が隣にいた。同じ高校の人だろうか。その男が、後に恋人となる、大村和樹だった
「雨、やまんかなー(ボソッ)」
真由子は、そう呟いた。すると、和樹は、真由子の顔を見た。真由子も和樹の顔を見た。
「あの・・・・・・・川村、よな・・・・・?美人で有名な川村よな・・・・?」
「なんですか、いきなり(笑)」
「いや・・・・・・・お前、ほんと、綺麗な顔しとるな・・・・・。」
〈初対面の人に、お前・・・・・?〉
夏海は、最初は和樹のことを警戒していた。すると、和樹は話だした。
「真由子・・・・・・かわむら、まゆこ・・・・・・・川村真由子。真由子、真由子、真由子。綺麗な名前やな。ええやん。」
「え、なに?私、自分の名前なんか気にいってないけど」
「なんでそんなに冷たいん~」
「やって、話したことない人やもん。あんた、私と同じ高校やろ?何年生?」
「1年生」
「へー、え?1年???」
すると、和樹は、またも真由子に質問をした。
「何年何組?」
「1年A組」
「え、俺、B組なんやけど(笑)」
「ははははっ(笑)」
すると、和樹は、真由子の少し雨で濡れた髪をそっと触った。
「・・・・・・・風邪ひくなよ」
―どきっ
真由子の心臓の鼓動が鳴り始めた。あまりにも、不意打ちの出来事だった。そして、2人は、名前を言い合った。
「名前は?」
「俺、大村和樹」
「知っとると思うけどー、私、川村真由子」
「和樹」
「真由子」
5月の寒い雨の日。バス停で、真由子と和樹は出会った。
その日の夜、真由子は携帯で、友達の椎名里沙にメールを打っていた。
‘真由子、数学教えて~’
‘嫌よ’
‘は?’
‘嘘よ。里沙さん☆’
‘ありがと♡’
真由子は、今朝のバス停で出会った人、和樹のことが頭から離れなかった。和樹は、本当に、物静かな男の子だった。夏海は、布団の上で、天井を見ながら、和樹の顔を思い出していた。恋は始まっていた。
そして、数日経った頃、真由子は里沙と学校の廊下を歩いていた。
「真由子・・・・」
「真由子」
「どしたん、里沙ちゃん」
「ほんま、あんたのその美貌は誰遺伝?夏おばちゃん?」
「も―、美貌美貌、ほんまうっさいわ~~」
「え、照れとる?」
「里沙ちゃん、うざ(笑)」
「照れた真由子も可愛い」
川村真由子。15歳。容姿端麗。でも勉強は出来ない。特に苦手なのが数学。そして真由子は放課後、里沙と一緒に中間テストに向けての勉強をしていた。真由子は、勉強に全然集中出来なかった。
「真由子」
「どうされました?里沙先生」
「まじ、赤点取っても知らんよ~~。あんた、軽音部の顧問の先生に言われとんやろ?赤点4つ取ったら部活くんな―みたいなこと言われとんやろ?ほんま、ずっ―とぼ―っとして~~。まじ知らんよ」
真由子は、言い返した。
「いいも―んだ」
「も―」
真由子と里沙は言い合いをしていた。すると、男子バスケ部の連中が廊下を歩いていた。ふと、真由子は、廊下を見た。すると、和樹と目があった。
「あ、川村やん~」
「やほー」
真由子は小さく、教室の中から、和樹に手を振った。和樹は少し照れ臭そうにしながら、手を振ってくれた。すると、バスケ部の連中が、和樹をからかった。
「え、お前、いつから川村と知り合いなん?」
「あんな美人と・・・・・・」
「ええなー♡大村♡」
そんな光景を、真由子は微笑ましく見ていた。すると、里沙が、突っ込んできた。
「真由子、いつから彼氏が~♡」
「は?彼氏やないしー//」
「ははは(笑)」
光が丘海岸の海は静かに音を立て、空は夕暮れに染まっていた。
⏰
―6月、真由子は、里沙の部屋で勉強会をしていた。
「雨・・・・・。」
「真由子、雨って気分下がるよね―――。もーっ、嫌になっちゃうう。」
6月、梅雨。真由子は、里沙の部屋に遊びに来ていた。真由子は、ふとため息をついた。
「里沙ちゃん・・・・」
「どした、真由子?」
「いや・・・なんでもない。」
その日の夕方、天気はいつのまにか晴れていた。空には、夕焼け空が一面に広がっていた。真由子は、帰り道にある、レコード屋さんに少し寄った。そして、店の中を見ると、和樹がレコードを聴いていた。真由子は、和樹の凛とした横顔を、じっと見た。すると、和樹が真由子のいる方向を見た。
「あ、川村?」
「・・・・あ・・・こんにちは。大村君」
「タメでいいよ。てか、あんた、なんでここにいんの?ここ、俺ん家だぞ」
「え、大村君の家なん?」
「正確に言えば―、じいちゃんばあちゃんの店=家」
真由子は、和樹の顔をじっと見た。和樹は、大きな猫みたいな鋭い目に、シュッとした顔立ちに、端正な顔立ちをしていた。真由子は思わず言葉に出してしまった。
「大村君、綺麗な横顔しとるね」
「何言ってんだよ。アホかお前は。・・・・川村、お前さ・・・・・まじで綺麗だよな」
「え」
和樹の思わぬ言葉に、思わず胸が高鳴った。真由子は、和樹の顔を、一瞬直視したが、逸らした。
「きも」
真由子は、笑った。すると、和樹が、ぶっきらぼうに言った。
「ほんまに、綺麗だよ」
「大村くん、私、ほんま、ほんまにコンプレックスだらけよ。小さい頃ね・・・・・今は一緒に暮らしとらんけど、お父さんに、‘ブス’とか‘キモイんだよ’とか、死ね’とか、‘ぶつぶつ顔’とか言われてさ・・・・。大村くん、だから、私ほんまに綺麗やないの。」
すると、和樹が、真由子の肩をガシッと掴んだ。
「川村、しんどそうやで」
「あ・・・・ごめんね」
「川村・・・・俺がそんな不安、吹き飛ばしてやる」
真由子の頬は少し赤くなった。至近距離で見ると、和樹の顔立ちは、本当に綺麗だった。真由子は、こくんと頷いた。
「ありがとう・・・・。」
真由子は、店の外にある、椅子に座った。足をぶらぶらさせた。和樹が、店の中から出てきた。
「ほらよ」
和樹は、小さいペットボトルのウーロン茶を渡してきた。和樹は、真顔で、真由子の隣に座った。
「あのさ」
「どした?」
「あ・・・嫌やったらいいんやけど、‘真由子’って呼んでもいい?」
真由子の心臓は高鳴った。和樹の頬が少し赤かった。真由子は、和樹の額をチョップした。
「ええよ」
「え、いいん?」
「真由子って呼んでえーよ」
「おけおけ、ほんなら、真由子って、呼ぶわ」
「ふふ(笑)分かった」
この日、空は、茜色だった。2人の時間がいつまでも続くような気がした。それから、2人は、携帯電話でよく話したりもした。夜中の12時になっても、真由子と和樹は、話をした。そして、教室で勉強もしたりした。和樹は数学&科学が得意だった。真由子は、勉強会をするたびに、‘和樹の手って大きいなー’と思いながら、密かにドキドキしていた。そして、高校1年の10月に、和樹は、教室で真由子に告白した。
「好きや、真由子が好きや」
真剣な告白だった。真由子も和樹に‘好きよ’と言った。真由子と和樹は思いが通じ合った。そして、高校2年の8月、和樹の部屋で、初体験をした。
「は、は・・・・・・・・・・和樹・・・・・・っ」
和樹は、真由子の両手を握り、そして、明かりがあまり灯っていない、薄暗い部屋で、2人は身体を重ねた。和樹は、真由子を抱きしめた。これが、和樹との、最初で最後の夜だった。真由子の中で痛みが走った。SEXがこんなに痛くて、こんなに幸せなことなんだと、真由子は知らなかった。そして、真由子の中で新しい命が宿ったことは、後の話・・・・・。
―👪
「・・・・はあ・・はあ」
「真由子、大丈夫?」
真由子は、高校2年の冬、授業中に体調が悪くなり、そして、トイレで嘔吐することが多くなった。真由子は、和樹になかなか話せだせずにいた。そして、養護教諭の田村亜希子先生に言われた。
「川村さん、あなた妊娠している可能性があるわ。」
真由子の心臓はドクンと鳴った。そして、その日の朝、学校を休み、、母の夏に産婦人科に連れていかれた。
「真由子、しっかりね」
病院で検査を受けた。すると、そこのクリニックの助産師の七宮さや先生に告げられた。
「真由子さん、あなた妊娠しているわ。お腹の赤ちゃん・・・2か月に入ってる」
真由子は、嬉しいはずだが・・・・涙が出た。和樹の子供を妊娠。しかも17で・・・。
高校2年の冬、和樹と公園で会った。
「和樹」
「どしたんだよ、そんな深刻そうな顔して・・・・」
真由子は、カバンからお腹の赤ちゃんのエコー写真を取り出した。
「ん?」
真由子は額に汗をかいていた。そして、ゆっくりと告げた。
「和樹の子供・・・・・赤ちゃんが出来た・・・・。妊娠2か月。」
すると、和樹は・・・・・初めて真由子の前で泣いた。真由子は、びっくりした。そして、なんて美しい涙なんやと思った。
「真由子」
「ん?」
和樹は、細くて真っ白な真由子の手を握った。そして、泣きながら言った。
「俺さ・・・・・小さい頃親父に暴力受けて・・・・母親は、俺を捨てて、他の男を選んだ・・・。真由子、‘3人’で幸せになろうな」
その日の帰り、真由子は和樹と、夕暮れに染まった光が丘海岸を歩いた。夕暮れに染まる光が丘海岸は本当に綺麗で、そして遠くの方で、鳥が飛んでいた。和樹は、真由子のお腹を触った。
「名前、どうするか・・・・・」
「性別は、まだ分からんらしいんやけどね―」
和樹は、目を細めた後、空を見ながら言った。
「真子、和美、和子、和彦、和也、真美、勝、真紀、真奈、う―んっ、いまいちピンとこね――」
「和樹、お腹の赤ちゃん、もしかしたら、来年の夏に産まれるかも」
和樹は、真由子の肩を組んだ。そして、真由子の顔をジッと見た。
「じゃ、‘夏’に産まれるとして・・・・光が丘海岸の‘海’を取って・・・‘夏海’・・・・」
「え、いいやん」
「早く生まれて来いよ・・・・夏海」
その1年後、真由子は産婦人科で、18という若さで、夏海を産んだ。
「女の子ですよーーー」
時計の時刻は、夜の8時を回っていた。真由子の目からは大粒の涙が流れていた。その3日後、和樹が大型トラックに跳ねられて、この世を去った。飲酒運転のトラックだった。和樹は、18歳だった。真由子は、部屋に引きこもった。
「・・・・・・」
「食べ物置いとくね」
真由子は、夏海を産み、そして和樹を亡くした。最愛の人を亡くした。真由子は、なんで生きているのだろう、なんで自分だけ生きているのだろうと思った。真由子は、部屋から見える、光が丘海岸を見た。あんなに好きだった光が丘海岸が、今は真っ黒に見えた。もう、死んでしまおうかと思った。
―和樹がいないと生きていけない
―私は、死んだ方がええんや。
「和樹・・・・・」
真由子は生きる希望をなくしていた。すると、携帯電話の着信音が鳴った。和樹との思い出の曲、大塚愛の‘恋愛写真’を、着信音にしていた。真由子は、携帯電話を、ベッドに投げつけた。そして、声が枯れるまで、泣いた・・・・・。すると、勉強机から、1枚の写真が床にひらっと落ちた。和樹と馴染の、かき氷屋さんで撮った写真だった。その裏に・・・・・和樹の最期のメッセージが、マジックで書かれていた。
‘真由子、ほんまに好きだ。大好きだ。真由子の笑顔が好きだ。真由子の横顔が好きだ。真由子の髪が好きだ。真由子の、よく笑うとこが好きだ。真由子のドジなとこが好きだ。真由子、お腹の赤ちゃん、絶対お前に似るやろな。馬鹿なとこがな。真由子、3人で幸せに暮らしていこうな。真由子、俺と、出会ってくれてありがとう。愛してる。’
真由子は、そのメッセージを初めて見た。真由子は、本当に幸せだった。こんな思い初めてだった。和樹、会いたい、会いたい。何度そう思っても、叶わない思いだった。真由子の目から大粒の涙が溢れだした。
「・・・・・・・・っ、か・・・・・・ず・・・・・き・・・・・あーーーーっ・・・・・・っっ」
真由子は、過呼吸になりながら泣いた。そして、和樹との永遠の別れとなった。
―
「・・・・・・なっちゃん」
真由子は、夏海の手を握った。
「生まれてきてくれて、ありがとう。」
真由子は、目を赤くし、そして涙を流しながら、夏海に言った。夏海の目からは、1粒の涙が、零れ落ちた。
―生きたい
生きたい
生きたい
死にたくない
私は・・・・・・・・生きたい。
まだまだしたいことたくさんある。生きたい。
生きたい・・・・・・・・・・。
第18章―――「命」
17歳。季節は冬になった。夏海は、身体のあちこちで悲鳴をあげていた。
ご飯を上手く食べれない、そして、手が動かせない。足も動かない。口も上手く
動かせれない。夏海は、そんな自分が嫌でたまらなかった。母の真由子も、毎日のように病室に来てくれていた。夏海は、身体が自由に動かすことが出来ずに、イライラしていた。
「か・・・・あ・・・・ちゃ・・・ん」
「ん?」
夏海は、母に当たってしまった。昼頃のことだった。
「も・・・・・・・・う・・・・・こな・・・・・いで」
「え、なんで?」
真由子は、驚きを隠せなかった。そして、夏海は、机の上に置いてある、写真盾、ものを、床になげつけた。
「・・・・・・・わかった、ゆっくり休み。」
真由子は、動揺を隠せず、床に散乱している、写真盾と物を、机の上に置き、病室を後にした。
「・・・・・・・・うっ・・・う」
夏海は、ただ1人、病室で泣いていた。その2時間後、1人の来訪者が病室の中に入ってきた。
「失礼します」
夏海は、見たことのない人物だった。その人物は、髪の毛が短く、目がぱっちりで、小柄で華奢な方で、オレンジ色の服に黒のスカートに、ブーツを履いていた。夏海は紙に書いた。
―どなたですか?
すると、その人物は、夏海の耳元で言った。
「椎名里沙(しいなりさ)。夏海ちゃんのママ、真由子の高校の時からの友達よー。」
椎名里沙。真由子の高校の時からの友達。里沙は、ミニ椅子に座った。
「あれ、真由子は?」
「か・・・・・・あ・・・・ちゃ・・・ん・・・・・か・・・・え・・・りま・・・・し・・・た」
「えー、まじ?真由子に会いたかったなー」
夏海は、里沙は本当に綺麗な人だと思った。里沙は、夏海の目を見て、話し始めた。
「夏海ちゃん、赤ちゃんやった頃に、1回会ったかな・・・・・?確か、‘かずき’もおったような・・・・・・。」
「と・・・・・う・・・ちゃ・・・・ん?」
すると、里沙はまたも、ニコニコしながら話し出した。
「そ、和樹。大村和樹。和樹さー、イケメンやったんよ。優しい男でさー、ほんまに、真由子とラブラブで、真由子が学園のマドンナみたいな感じで、和樹は・・・。
真由子って、羨ましいくらい綺麗やーん。ほんと、あの子綺麗やーん。和樹、そんな真由子にぞっこんやったんよー♡‘まゆこ、まゆこ’って、いっつも真由子のこと、そう呼びよったなー♡和樹。」
すると、里沙が表情を変えた。
「でも、高校2年の冬、真由子、お腹に夏海ちゃんがおるって分かった時、真由子と和樹ね・・・・・・・朝一の始発の電車に乗って、東京までいって駆け落ちしたの。」
え?と夏海は思った。
―18年前
和樹と、真由子は、冬の寒い東京行の電車の中で、肩を寄せ合っていた。
「和樹、寒いね」
「そやな・・・・・・、真由子、お腹の赤ん坊は?」
「動っきょる、動っきょる。」
そして、東京駅に着いた。冬の東京は寒かった。真由子と和樹は、少ないお金と、切符を持って、品川駅を歩いていた。2人は、肩を寄せ合って歩いていた。
「・・・・・・真由子、お腹の赤ん坊は?」
「・・・・・あ、動いた」
和樹は、真由子のお腹を触った。お腹の赤ちゃんは、ぽこっと、真由子のお腹を蹴った。真由子はこの時、妊娠3か月。新たな命がいた。
「真由子、東京って広いねー。」
2人は、品川から渋谷まで電車で乗り、夕方の時間帯に、渋谷の街を歩いた。すると、後ろから2人の警察官に声をかけられた。
「ちょっとすみません・・・・・・大村和樹くんと、川村真由子さん?」
「はい・・・・そうです。」
和樹は真由子の手を握った。力強く、握った。そして、2人は、渋谷警察署まで連行された。2人は事情を話し、愛媛の実家へと帰された。
「真由子、なんで、和樹君と駆け落ちしたん~~~~?あんた、アホちゃう?バカ、あほんだら!」
川村家と、大村家。川村家の家に、大村家もいた。和樹は、話しだした。
「夏さん」
「なんや、人の娘、妊娠させておいてなー、お前、なんぞ!」
「母ちゃん、うるさい」
「は?こんな状況で落ち着ける母親がどこにおるんや!」
「・・・・・・・・俺、働きます。ほんで、真由子と結婚したいです。真由子と生きていきたいです。真由子の傍にいたいです。俺、もう、逃げません。真由子と、生きていきます。」
真由子の目が赤くなっていた。夏は、最初は怒りを露わにしていたが、和樹の真剣な思いを聞き、‘それなら’と言い、両家の承諾を得た。夕方の時間帯、2人は、A島の漁港のあたりを歩いた。
「和樹」
「ん?」
「うちも、和樹と生きていきたい。一緒に生きていきたい。」
すると、和樹は、真由子を抱きしめた。
「・・・・・・・・ずっと、一緒や・・・・」
和樹は、真由子の頭をぽん、ぽんとしながら、真由子を抱きしめた。A島の夕日は、本当に綺麗だった。
―♪
「真由子、辛かったみたいやけど、夏海ちゃんは絶対産む!そう言いよった。」
「か・・・・あ・・・・ちゃ・・・・・ん・・・。」
里沙は、夏海の両手を握った。
「夏海ちゃん、彼氏は?」
「・・・・・・・・いま・・・・・す」
夏海は、1枚の紙に書いた。
―やまむらけんたです。
里沙は、目を輝かせた。
「けんたくんかー、どんな男の子?」
夏海は、またも紙に書いた。
―ばすけばかです。アホです。ばかです。でもやさしいです。
すると、里沙は、夏海の頭をぽんぽんとした。
「いいね、そんな男の子が夏海ちゃんの彼氏で、会ってみたいわい。♡」
その後、里沙は、病室を後にした。夏海は、里沙が帰った後、なんとも言えない気持ちに包まれた。椎名里沙、母の友達。里沙さんは不思議な人やん、と夏海は思った。
―里沙さん
不思議な人・・・・。
母ちゃん・・・・・・駆け落ちしたんや・・・・・。
はー。なんとも言えない気持ち・・・・・・・・・・・。
次の日、健太が病室に来た。
「夏海」
「・・・・・ん?」
「なんか、辛そうやで。なんかあったやろ・・・・・。」
夏海は、1枚の紙に書いた。
―なんで、わかったん?
すると、健太が険しそうな顔をした。
「話してみ・・・・聞くけん。」
健太は、夏海の左手をぎゅっと握った。夏海は、身振り手振り使いながら、話し出した。
「け・・・・・ん・・・・た」
夏海は、上手く言葉が回らなかったので、紙に自分の思いを書くことにした。
―かけおちってしっとる?
健太の顔に?のマークが浮かんだ。すると、健太は話し出した。
「知っとるよ。男女が駆け落ちすることやろ?」
すると夏海は、またも紙に、書き出した。
―かあちゃん、17のときに、とおちゃんと、とうきょうまでかけおちしたらしい・・・・
「え・・・・真由子さんが?」
光が丘海岸の海は、静かだった。外は夕暮れに染まっていた。
「夏海」
「・・・・・・ん?」
「確か・・・・・・真由子さんは夏海を17で妊娠したんよな?・・・・・・・俺が、和樹さんやったら、周囲に反対されたら、駆け落ちする覚悟で、好きな女と一緒になるかもな・・・・・」
「・・・・・・・け・・・・んた・・・・・も?」
夏海は、またも、紙に書いた。
―けんた、なつみがもし、にんしんしたら、いっしょにかけおちしとった?
「・・・あー、俺も、和樹さんの気持ち分るな・・・・・・。」
窓に夕日が差し込んでいた。遠くの方で鴎が飛んでいた。飛行機雲が空に浮かんでいた。すると、健太が夏海の顔をじっと見た。そして、健太は、夏海を抱きしめた。
「あの夜・・・・・・・お前の肌に触れた時、心臓の鼓動が、半端なくてさー・・・・・
お前のこと、すげー好きやと思った。夏海を・・・・・一生大事にしたいと思った。夏海・・・・・・・。」
夏海の目は赤くなっていた。そして、健太は、夏海にキスをした。夏海の唇は柔らかかった。深く、奥深く、キスをした。
―好き、好き、大好き
その想いだけやった。
けんた、あなたと過ごした日々。あなたとしたキス。
一生忘れません。
I love you. けんた。
愛してる。ずっと。
第19章―――「花火」
あれから何分経っただろう。健太はキスを辞めようとしなかった。
「・・・・・・・・はー、俺、ダメや。・・・・・・・夏海」
健太は、再度、またキスをした。夏海の頬が赤かった。健太も、耳まで赤くなっていた。すると、健太は、冷静を取り戻したのか、キスをやめた。
「ごめん、夏海・・・・・・・・・・何度も思い出すんだよ。あの夜のことを・・・・・・。」
「け・・・・・・ん・・・・・た」
「ん?」
夏海は、紙に書いた。
―もういっかい、きすしていいよ
健太の頬が赤かった。そして、2人は、またもキスをした。すると、花火の音がした。部屋の中から見ると、花火が打ち上げられていた。
「・・・・・・あ・・・・・・・き・・・・・れ・・・・い・・・・や・・・・・・・ね」
夏海は、健太と手を握り合った。健太の手は大きかった。そして、温かかった。
「夏海」
「ん?」
「俺・・・・・・・お前がおらんと、生きていけんわ」
―え、なんで?
健太は、ベットの上で夏海を抱きしめた。
「俺、ずっと、夏海を見よった。夏海が笑いよるとこ、授業中寝よるとこ、高橋と、馬鹿みたいに笑いよるとこ、大きい口開けて、楽しそうに歌うところ、好きなものを美味しそうに食べるとこ、頑張り屋さんなとこ・・・・・純粋なとこ、笑顔が可愛いとこ・・・・・俺のことを、好きでいてくれるとこ。夏海、このまま夏海と、どっか違うとこいけたらな・・・・・・・。」
健太の抱きしめる腕の力が更に強くなった。
「け・・・・・ん・・・・た」
―けんた、私もよ
愛媛県、A島。夜の花火が何発も打ち上げられる中、2人はまたも、唇を重ねた。花火の音が、2人の悲しい運命を消してくれているような気がした。夏海の付けているハートのネックレスが、風で少し揺れた。
―けんた、けんた、けんた。
あんなにハッキリ、‘けんた’と言いよったけど、
声があまりでなくなってしまった・・・・・。
けんた、けんた、けんた。
あなたの名前をいつか呼べなくなる日がくると思うと、
私、辛い。苦しい。あなたの名前を、いつまでも、呼んでいたい。
‘けんた’。愛してる。
第20章―――「クリスマス」
季節は12月になった。夏海の症状は更に悪化していた。声も出せなくなってきていた。病室には、愛が来ていた。
「なっちゃん」
「ん?」
「クリスマスさー、ここで皆でパーティーしようかって話になっとってー、どう?」
夏海は、紙に書いた。
―いいよ♡
後日、愛、達也、健太、愛の弟の陸、そして、健太の弟の優太も来ることになった。そして、夏海は、あることを考えていた。健太に向けてラブレターを執筆しようと考えていた。母の真由子にパソコンを持ってきてもらい、病室で、ゆっくり、パソコンのワードでラブレターを執筆していた。
―♡
山村健太様
最近、本当に寒くなりましたね。健太は、どのようにお過ごしでしょうか?病室から光が丘海岸の海を見るたびに、健太と、A島で過ごした日々が蘇ります。あれは5歳の頃、光が丘海岸で健太と初めて話しましたね。ほんと、口の悪い男の子やと思ったわい(笑)健太、でも、そこから健太のたくさんの一面を知って、健太からたくさんのことを教えてもらい、夏海の人生は、日々、充実しておりました。健太と出会って、10年以上経つんやね・・・・・・。健太、健太に初めて抱きしめられた時、あれは、14歳でしたね。私は、心臓が爆発するかと思いました。それぐらい、どんどんかっこよくなっていく健太に、夏海は恋焦がれていました。健太、あなたの横でずっと笑っていたい。ずっと、あなたの横にいたい。健太、こんなにも、人を好きになったのは、あなたが初めてです。健太、愛してる。
―♡
夏海がラブレターを打ち終えたのは、夜の10時頃だった。クリスマスの数日前のことだった。夏海は、なぜだろう。そのラブレターを見ていると、涙が溢れてきた。数か月後には、自分は命を落として、あの世にいると思うと、いたたまれなくなった。夏海は、日々を、一生懸命生きていた。
―夏海
―ん?
―ばーか
―は、あーほ
―なんや(笑)
―それ、こっちのセリフや(笑)
―てか、また、松山市行く?
―え、ええやん~。行こうで。電車代はもちろん、健太のおごりね(笑)
―は、奢るか、ばーか(笑)
―ははは(笑)ま、健太、松山市行こう~~~
こんなくだらない会話が、こんなにも夏海にとって大切なものになると思わなかった・・・・・。
―なー
―ん?
―キスする?
―なんでや///
―キスしようや
―恥ずかしいやん~///
―しよ、ちゅ♡
―健太、甘えんぼさんなんやけーん
―甘えんぼで結構
―ははは(笑)
夏海は、病室の窓から光が丘海岸を見ていた。なぜだろう、涙を止めることが出来なかった。ぽた、ぽた、と、とめどなく、涙が溢れた。
―私は、あと、数か月の命。
この命を、簡単に捨てれない。
精一杯、生きる。
生きる、生きる、生きる。
死にたくない。生きたい。
けんた、私、健太が好きや~~。
大好きや~~~。
でも、私は、あと数か月の命・・・・・・・。
そして、クリスマスパーティー当日の日が来た。
「メリクリ~」
クリスマスパーティーは、夏海にとって、一生の想い出になった。そして、みんなで、集合写真も撮った。夏海の青春の1Pに刻まれた。
第21章―――「龍一くん」
年が明けた。夏海の体は、ますます動かせなくなっていた。夏海は、話すこともほぼできなくなってきていた。
「なっちゃん」
「・・・・・・・ど・・・し・・・た?」
「龍一くん覚えとる?」
「・・・・・・・う・・・・・ん」
篠崎龍一。通称「りゅういちくん」。夏海の同級生で、松山市に住んでいる男の子。
「りゅういちくんが、明日、ここに来てもいい?」
夏海は驚きを隠せなかった。まさかの、龍一がここに来るとは思わなかった。
「・・・・・・・・・・なっちゃん、わけを話すと、母ちゃん、龍一の母の真美と頻繁に連絡取り合いよってね、真美が、なっちゃんの容態をものすごく心配して、ほんで、龍一もそのことを知ったらしくて、ほやけん、明日、篠崎親子、来るよ」
夏海は、なんとも言えない気持ちになっていた。
―夏海ちゃん
―ん?
―俺の事、どう思っとん?
―え、私が、龍一くんのことを?
―そうそう
あれは、14歳の夏のことだった。2人でアイス食べながら海を見ていた時のことだった。
―うちは・・・・
―俺は好きや
―え・・・・・・・
―俺は、夏海ちゃんが好きや
このことは、健太にも話せていなかった。そして、次の日、龍一と、母の真美がお見舞いに来た。
「やほー、夏海ちゃん」
龍一は、坊主頭に、黒のジャケットを着ていた。夏海は、紙に書いた。
―りゅういちくん、げんき?
すると、りゅういちは、夏海の頭をポンとした。
「元気やぞ」
それから、夏海は、龍一と思い出話をした。話の中で、14歳の時の話になった。
「り・・・・・・ゅう・・・・・く・・・・・・ん」
「ん?どした?」
夏海は、紙に書いた。
―14のとき、わたしのことすきやった?
一瞬の沈黙が流れた。そして龍一は、真剣な表情をして言った。
「今もや」
夏海はびっくりした。すると、龍一は言葉を続けた。
「夏海ちゃん・・・・・・・・俺、ずっと・・・・・・・・・」
すると、龍一は、我慢したのか、話すのをやめた。すると、病室のドアのノックが聞こえ、1人の人物が入ってきた。
「夏海―」
すると、健太は、目玉を大きくした。
「え、えーと・・・・・・篠崎、よな?」
「うん、ほやけど」
夏海は健太に話した。
「け・・・・・・・・ん・・・・・た」
「ん?」
すると、龍一が、夏海の付けているネックレスを見た。
「夏海ちゃんの付けとるこれって、誰かからもらったん?」
すると、夏海は、左手の指で、健太の方を指した。
「お前、指さすなよ(笑)」
夏海はふふっと笑顔になって笑った。すると、龍一は、鋭いことを言った。
「あー、もしや・・・・・・・2人付き合っとん?」
健太の頬が少し赤くなった。
「・・・そや、悪いか?///」
すると、龍一は、天然発言をした。
「付き合っとるということはー、2人はキスもしとるってこと?」
夏海の顔が赤くなった。健太も頬を赤くした。
「・・・・・・・・キスした。///」
すると、龍一は、言葉を続けた。
「山村が惚れるんも分かるよ。やって、夏海ちゃん、可愛いもん。優しいし。純粋やし。夏海ちゃん、真っすぐやし、ほんま、分かる。」
龍一は、真顔でそう言った。窓の外は、雪が降っており、光が丘海岸の海も、白く、染まっていた。すると、龍一は、言った。
「山村」
「ん?」
龍一は、健太の耳元で言った。
「幸せにしろよ。こんな綺麗な女、おらん」
そして、龍一は、‘夏海ちゃんバイバイ~’と言い、病室を後にした。病室には、健太と夏海、2人きりになった。そして、健太はミニ椅子に座り、話し出した。
「・・・・・・・手、ちっちぇーな」
健太は、夏海の手を触った。そして、夏海の顔を見て、2人はお互いを見つめあった後、唇を静かに重ねた。真っ白な雪が降る中、2人は静かに唇を重ねた。そして、唇を離した後、健太は、静かにこう、呟いた。
「・・・・・・夏海と家庭作って、子供が生まれて、そんな未来が来たらええな・・・・。」
健太は、夏海をそっと抱きしめた。夏海の命はあと数か月。身体の機能も低下している。いつか呼吸も止まる。夏海は、健太に抱きしめられながら、静かに泣いた。雪は止むことなく、静かに、ひっそりと、降り続けた。
―りゅうくん、野球頑張ってほしいなー
けんた、けんた。生きて。
けんた生きて
生きて
生きて
私が死んでも
生きて。生きて。生きて。
第22章―――「山村夏海」
高校3年の春になった。夏海は、身体があまり自由に動かせなくなっていた。夏海は、ほぼ毎日、ベットの上で過ごしていた。光が丘海岸の近くの木々は桜が咲いていた。夏海は、‘死ぬ’ということに対して恐怖心を抱きながら、毎日を過ごしていた。夏海は、病室から、満開の桜の木を見ていた。そして、病室に、愛と、達也が来た。
「・・・・・や・・・・・・・・ほ」
「なっちゃん、大丈夫・・・・・・・?」
すると、夏海は辛そうな表情をした。すると、愛が手を握った。
「なっちゃん、聞いて。」
「ん?」
「私・・・・・・・有村と付き合ったよ」
夏海は、目を更に大きくした。そして、達也も話した。
「今年の2月に、愛に告白して、付き合うことになった。ほんと、けんちゃんの気持ちがわかるよ。好きな子に告白するって、こんなに緊張するんやって、愛に告白して思ったもん」
「・・・・・・・達也が、‘高橋が好きや。大好きや。幸せにしたい。’って言ってくるけん、それに答えんといけんな、って思って、達也と付き合うことになったよ。」
夏海の顔が緩んでいた。そして、夏海は紙に書いた。
―おめでとう。しあわせに。
愛は少し涙目になった。
「・・・・ありがとう。なっちゃん、なっちゃんも幸せにね・・・・・・」
達也は、愛の背中をさすった。ピンク色の桜の木は、風によって、舞い散った。
光が丘海岸の海は、静かだった。そして、夜、夏海はパソコンのワードに、自分の胸中を打った。
―🌸
私は、ほんと、あと数か月の命やと思う。
ご飯も食べれん
身体も自由に動かせれん
顔の筋肉も動かない
筋力も低下している
不安でしかない。人生前向きに生きようって思っても、ほんま、不安でしかない。
私は、生きてていいいのだろうか。このまま死んでしまった方が楽なのかもしれんと思ったこともあった。前、健太が、17歳の誕生日の時に、ハートのネックレスをプレゼントしてくれた時、‘このまま死んでもいいくらい幸せ’そう思った。
健太と唇を重ねた時、本当に幸せだと感じた。
生きたい
生きたい
そう思っても、私は死んでしまう。
死ぬ運命・・・・・・。私の人生は・・・・・・・・。
でも、私は、日々の人生を、1歩1歩生きたい、そう強く思う。
その日、夏海は眠りについた。
―なつみ
―ん?
夏海は夢を見ていた。夢の中でだが、光が丘海岸で、健太が夏海にキスをしていた。
「・・・・・・愛してる」
そして、夢の中で、再度2人はキスをした。そこで夢は終わった。その日の朝、夏海は、病室に置いてある思い出の写真を見た。高1の文化祭の写真、健太と初めてデートした時の写真。全てが懐かしく、愛おしかった。夏海は、健太と初めてデートした時のことを思い出した。
―けんた、歩くん早いよー
―え、普通に歩きよるけど
―いや、早い早い
―てか、タピオカ飲む?
―健太のおごりね~
―はいはい
健太との初デートは、愛媛県 松山市の、大街道だった。夏海は、その時、健太の手をそっと握った。健太も、握り返した。2人は、少しの間、無言で手を繋ぎながら歩いた。夏海の目からは涙が溢れた。夏海は、涙を流しながら、その写真たちを見ていた。夏海の命は、あと、わずかだった。
第23章―――「17歳、高校3年の6月」
―死にたくない。
そう、強く思ってきた。
死にたくない。
でも、私は、死んでしまう。
あと、数か月の命・・・・・・。
6月になった。夏海は、身体を動かすことも、話すことも出来なくなっていた。夏海は、ほぼ、植物状態になっていた。真由子は、その日病室に来ていた健太に、話した。
「お医者さんが言うには・・・・・・・・あと2~3か月しか生きられないって・・・・・・・」
健太は、なんで?と思った。なんで恋人が、あと2~3か月の命なのか、分からなかった。健太は、病室の中に入った。夏海は、植物状態に陥っていた。
「なつみ・・・・・・・・」
その日、帰り際、健太は有村家に行った。
「達也・・・・・・・夏海、あと、2~3か月の命やって・・・・・・。」
「え、嘘やん・・・・・・・」
達也の部屋で、健太は達也と話をしていた。
「けんちゃん、大丈夫・・・・・・・・・?」
「・・・・・・・・・夏海、死んでほしくないな・・・・・・・俺、ほんま、夏海が好きやもん。
死んでほしくない
死んでほしくない
死んでほしくない・・・・・・。
ずっと、生きててほしい。
今日、夏海の病室行って、夏海が植物状態で、ベットの上におるとこ見て、
自分が、ほんま、情けないと思った・・・・・・。
夏海、生きててほしい。
ずっと、俺の傍にいてほしい。
俺の横で笑っててほしい。
また、‘けんた’って呼んでほしい。
・・・・・・・・・夏海が、好きなんだよ・・・・・・。」
健太は、久しぶりに、泣いていた。達也も、横で泣いていた。17歳の女の子の命が絶とうとしていた。光が丘海岸の海は、静かだった。空は赤色に染まっていた。風は静かに吹いていた。達也は言葉を発した。
「なっちゃん、死んでほしくないな・・・・・・。生きてほしい・・・・・・。」
健太の涙は更に溢れだした。
「・・・・・・・・・夏海。夏海が、好きやのに、何も出来ん自分が嫌や・・・・・・。
夏海が好きや
夏海が好きや
夏海の笑顔がもう1回見たい。もう、辛い・・・・・・・・・・・。」
2人は、何分も泣き続けた。
―夏海、好きや、好きや
大好きや
夏海が植物状態になっとって、俺は、夏海の死を受け入れないといけない
時が来ると思うと、辛くてたまらなかった。
夏海、夏海の笑顔がもう1回見たい。
夏海と、もう1回話がしたい。
夏海に、‘愛してる’と、言いたい。
―?章「2人の愛」
―夏海、好きだ
―けんた、好き
—こんな幸せなことってあっていいんかな?
夏海は、食べることも、話すことも、出来なくなっていた。健太は、学校終わり、夏海のいる、病室に来ていた。健太は、ミニ椅子に座り、植物状態の夏海に、色んな話をした。
「夏海、また、松山市に行きたいな。俺らが初めてデートしたん、松山市の大街道やったよな?あん時、夏海、めっちゃはしゃぎよったよな・・・・・・」
健太は、一言一言、話した。
「夏海、あん時、お洒落しとって、可愛いな―って思いよった。」
健太は、夏海の左手の上に自分の左手を重ねた。
「夏海、また、松山市行こ。てか、ディズニーランドも行こうや。ユニバとかさ。夏海と、これからもたくさんのことがしたいよ・・・・・・・・・・。」
光が丘海岸の海は静かに音を立てていた。健太は、夏海の目を見た。夏海の目からは、1粒の涙が落ちていた。そして、健太は、言葉を続けた。
「夏海、愛してる・・・・・・・・・。いつまでも。ずっと、ずっと、夏海を、愛してる」
夏海の目からは、またも、涙が流れ落ちていた。健太の目も赤かった。そして、健太は言葉を続けた。
「もし、俺らが結婚しとったら、ここの島に住んで、俺が高校教師で、夏海が、パン屋とかで働いて、ほんで、子供は2人で、1人が男の子、もう1人が女の子。そんな未来も来たらええのに・・・・・・・って、ずっと思いよった。ずっと・・・・・・・ずっと・・・・・」
2人の叶わない、未来だった。
―けんた
―ん?
―もう1回キスしよ
―ええよ
—・・・・あはは、歯があたった(笑)
―ははは(笑)
2人は愛し合っていた。死ぬ運命・・・・・・・・・。夏海の死は、間近にせまっていた。
―夏海、夏海、夏海。
生きててほしい。夏海の笑顔をずっと見ていたい。生きててほしい。
生きててほしい。
生きててほしい。
夏海、夏海と色んなとこに行きたい。
夏海・・・・・・。
第24章―――「生きるか死ぬか」
夏になった。夏海の体力は完全に落ちていた。夏海は、病気の後遺症で、あまり話せなくなっていた。手も、自由に動かせなくなっていた。夏海は、病室のベッドの上から、海を見ていた。夏海は、‘死ぬ’恐怖と闘っていた。病気と闘っていた。死が間近に来ていた。怖かった。怖かった。健太は夏海の病室へと来ていた。すると、夏海は、病室の窓の外を見た。健太は、夏海を見た。夏海はやせ細り、焼けて健康的だった肌が、真っ白になっていた。そして、なつみは、健太を見た。
「け・・・・んた」
「ん?」
その時夏海は、健太をじっと見た。夏海は、涙を流した。
「い・・・つま・・・・・で・・・・も・・・あ・・・・・・いし・・・・・・・・て・・・・・・る」
―いつまでも、愛してる
健太は苦しくなった。‘紗希ちゃんと幸せに’健太がそれは、夏海の永遠の別れの言葉でもあるように思えた。大声出して笑っていた夏海、鼻歌歌いながら帰っていた夏海、どんなときも明るく元気だった夏海・・・。健太は何もしてやれない自分に腹が立った。健太は、何も言葉を発することが出来なかった。
その日の夜、夏海は夢を見た。亡き父親の和樹が夏海の夢に出てきた。
「夏海、死ぬな、生きろ。夏海、まだ17歳やろ?ほんま死んだらいかん。お前、まだまだしたいことたくさんあるやろ?夏海、お父さんのお願い・・・・死ぬな・・・。生きろ・・・・・夏海、真由子を1人にするな、夏海、お願いやけん、死ぬな、生きろ」
「お父ちゃん・・・・・・直接、会いたかったな。」
「夏海・・・・・・。」
夢の中で和樹が、夏海の前で俯いた。そして、和樹は夏海を抱きしめた。
「生きたな・・・・・。お父ちゃんと、行こう」
「・・・・・・・・うん。‘お父ちゃん’。お母ちゃんを愛してくれてありがとう。」
2人は、天気が晴れの、外国の映画に出てきそうな、山の中にある、お花畑にいた。夏海は、セーラー服姿のまま、そのお花畑をあるいた。向日葵、ガーネット、百合の花、たくさんの花がお花畑に咲いていた。その中でも、向日葵がひと際大きくさいていた。
「お父ちゃん、見てみて!」
「ん?お、綺麗な向日葵やな」
夏海は、ずいぶん前の話だが、光が丘海岸に咲いている向日葵を、小学生の時に、健太と一緒に見て、笑い合ったことを思い出した。すると、夏海の目から涙が溢れてきた。
「・・・・・え、あれ、なんで私泣いとんやろ・・・・・・。」
すると、和樹がそっと、夏海を抱きしめた。周りには、たくさんの花が咲いており、向日葵も満開に咲いていた。夏海の涙は止まるこはなかった。
「お父ちゃん・・・・。」
「夏海は悪ない。まったく悪ない。もう、苦しまんでええ・・・・・。」
和樹も泣いていた。空は晴れていた。
―次の日の朝、夏海の病状が悪化した。
第25章―――「最期」
空は晴れていた。看護師が朝、夏海の病室に行った。
「川村さん、バイタルはかりますね」
夏海が目を瞑っていた。看護師は、夏海の容態が悪いことに気が付いた。夏海は、呼吸は浅かった。
―
真由子が病室の外で泣いていた。‘なっちゃん、なっちゃん・・・・・・’と何度も泣きながら言っていた。主治医の中屋、そして、看護師4人が病室の中にいた。夏海の心拍数が、120、110、100、90、85と下がってきていた。夏海は呼吸器に繋がれていた。
「意識戻らないです」
「血圧下がってます」
「ALDを」
中屋は、懸命に心臓マッサージをしていた。
「夏海ちゃん、頑張れ」
夏海の心拍数はどんどん下がってきていた。
夏海の意識が戻らない。顔も青ざめていた。
主治医の中屋は、心臓マッサージをしていた。夏海の意識が戻らない。血圧もどんどん下がっていく。夏海が死んでしまう。傍で、祖母の夏と、母親の真由子が血相を悪くして、夏海を見ていた。
「はーはーー・・・・。」
血圧が、80、90、と戻ってきた。すると、健太と愛と、達也が走ってきた。
「夏海は・・・・!?」
健太は、病室の中で、心臓マッサージをされている夏海を見た。夏海の顔は青ざめていた。夏海の脳裏には、健太の顔が浮かんだ。夏海は、力を振り絞って最期に言った。力を振り絞って言った。
「けんた・・・――けんた・・・――」
と言った。力を振り縛って、最愛の人の名前を、夏海は最期、言った。それが、夏海の最期の言葉だった。血圧がそれからどんどん下がり、脈も下がった。そして、夏海は、17歳という若さで病室で息を引き取った。
― 川村夏海 享年17歳
夏海は、静かに息を引き取った。早すぎる死だった。
「午前・・・12時15分・・・」
真由子は、夏海の傍に倒れこんだ。
―お母ちゃん
―このぬいぐるみ、お母ちゃんと思って、いい子にしててね
中屋医師がそう静かに告げた。夏海は天国へと旅立った。亡き父の和樹のいる天国へと旅立った。
「・・・・・・・なっちゃん、なっちゃん―――――――――あ~~~っ・・・・」
真由子が夏海の傍で泣き崩れた。愛が、大粒の涙を流していた。その後ろで、健太は泣かなかった。ただ、夏海の‘死’を受け止めるしかなかった。最愛の人の死を目の前で見てしまった。健太は泣かなかった。泣かなかった。
―お父ちゃん
―夏海、てかお前、真由子に似とるな~
―ふふ
夏海は、温かい日差しが降り注ぐ病室の中で永遠に眠った。あまりにも、早すぎる死だった。外は晴れていた。
第25章―――「想い出」
―けんた
―なつみ
年月は、どんどん流れていく。2人は愛し合っていた。健太は、出会った時から、夏海に恋をしていた。夏海の笑顔、夏海。夏海に恋をしていた。自分の気持ちに嘘付けない。それぐらい、夏海に恋をしていた。夏海とキスした時、本当に幸せな気持ちになった。夏海を抱きしめた時、ずっと一緒にいたい、そう強く思った。夏海が好きだった。我を忘れるくらい、夏海を愛していた。15歳、高校1年生の夏。2人で光が丘海岸の夕焼けを見た時、うっすら気づいていた。健太は自分の気持ちに。夏海に惹かれてることに。夏海の笑った顔を見た時、思わずキスしそうになった。
夏海と触れ合った夜、すごく震えた。好きな人と触れ合える幸せを感じた。夏海、死んでほしくなかった、生きててほしかった。夏海の小さな手を、もう一度握りたい。夏海に触れたい。夏海を抱きしめたい。健太は、心の底から‘川村夏海’を愛していた。
夏海の葬儀は、光が丘海岸の海の近くの葬儀場で行われた。
「なっちゃん・・・」
「早すぎるよ・・・」
「まだ、若いのに」
「ALSやったんやろ・・・」
「これからって時に・・・・・」
健太は、夏海の遺影を見た。高校の入学式の写真だった。遺影の夏海は、笑顔だった。たくさんの花と、スナック菓子と、人形が供えられていた。そして、写真は、夏海と健太の2ショットも置かれていた。健太は、それらを見て、夏海がこの世にいない、その事実が本当に信じられなかった。すると、隣に達也が来た。達也の目も赤かった。
「健ちゃん、大丈夫・・・・?」
「・・・・・・・・・・・ほんと、夏海のこと、好きやな・・・・・・」
健太の目が赤かった。健太は、火葬場までは行けなかった。骨になる夏海を見たくなかった。健太は、光が丘海岸に行った。空は、茜色に染まっていた。健太は、スマホで、生前の夏海の動画を見ていた。
〈美味しい~、健太、このパフェ美味しいねーーーーーー〉
〈健太、私可愛い?着物着たよー〉
〈勉強しなさいよー、健太~~~~~(笑)〉
健太は、涙が溢れてきていた。健太は、泣いた。泣いた。健太は、その動画を見ると、夏海が確かに生きていたんだと、強く思った。そして、亡くなる2週間前の動画を見た。
〈夏海、外晴れとるな~〉
〈あ・・・・・・そ・・・そうやね〉
〈はは。夏海、来年の夏も、光が丘海岸の向日葵見ような〉
〈や・・・・・や・・・くそ・・・・・く・・・や・・・・で〉
最期の動画の夏海は、かすかながら、微笑んでいた。その動画で、健太の涙腺がさらに緩み、泣き止むことは出来なかった。そして、夏海の最期のLINEは、
―生きたい
だった。健太は、‘何も出来なかった’、そんな自分を恨んだ。光が丘海岸の空は、茜色に染まっていた。夏海は17歳という若さで死んだ。
第26章―――「遺書」
健太は、川村家に来ていた。夏海の葬儀から数日経った頃だった。健太は夏海の遺影の前で手を合わせた。そして、1本の向日葵の花を夏海の遺影の傍に置いた。
「健太」
「どした、真由子ちゃん」
真由子は、ふと、1枚の封筒を渡してきた。
「なっちゃんの手紙・・・これ、なっちゃんの遺書」
真由子はそう言うと、リビングを後にし、ベランダに出た。そして、煙草を吸い始めた。真由子の煙草の煙が、中を巻いた。
「・・・・・」
健太はその封筒を見た。持つ手が震えた。封筒には、‘遺書’と書かれていた。夏海の字だった。健太は、手を振るわせながら、封筒を開け、中身を見ると、紙が入っていた。健太はその紙を取り出した。健太は、夏海が生前に書いたであろう、遺書を見た。
ー
健太へ
健太、やほ。健太、私、健太にありがとうの気持ち、何も伝えてなかった気がする・・・・。健太、私、手紙を見る頃には、夏海はあの世にいるよ。健太、私、ALSという病気になり、ほんで、お医者さんに、持って1年って言われちゃった。確かに、上手く物を持てなかったり、身体が重かったり、すぐこけたり、上手くご飯が食べれなかったり・・・・。健太、覚えとる?5歳の頃に私たちは出会ったよね?砂場で1人で遊んびょる時に、1人でおった私に健太が私に話しかけてくれたよね?健太の第一印象は‘口の悪い男の子’でした。でも、健太が私の世界を広げてくれたね。それから、たっつんに出会って、愛ちゃん、ほんで、島の人達に出会って・・・・・。健太、私は、健太に出会ったこと、これっぽちも後悔してない。私を、愛してくれてありがとう。健太と結婚して、幸せな家庭を築きたかったな―。ほんで、子供産んで、笑顔溢れる日々を過ごしたい、夢ありました。健太、日々を大切に生きてね。健太、愛してる。健太、ずっと、ずっと、ありがとう。
夏海
健太の目からは、大粒の涙が溢れていた。健太は、夏海の遺影を見た。遺影の中で夏海は笑っていた。健太は、思う。夏海の声が好きだ、夏海の横顔が好きだ、夏海の髪の毛が好きだ、夏海の細い指が好きだ、夏海の笑った顔が好きだ、夏海が好きだ。外は晴れていた。夕焼けの日差しが、窓に反射した。真由子は、まだ紙煙草を吸っていた。健太は、ただ、泣いていた。いつまでも泣いていた。夏海が、好きだ・・・・・・。大好きだ。でも、夏海は、もう、戻ってこない。夏海は今、空の上にいる。もう会えない。達也は、夏海の遺影を見た。目がぼやける。もう、夏海に会えない、そのことが信じれなかった。健太の目から大粒の涙が溢れだした。
―健太
―健太、遊ぼ~。明日、13時に駅前集合ね。
―最近・・・・・手が動かせない。
―健太・・・・・別れよ。
―健太・・・・私、もう長くないかも。
―ごめんね
―健太、海っていいね。ほんま、綺麗
―健太と、ずっと一緒にいたい。
―健太・・・・ずっと、愛してる。
「な・・・・つっ・・・・・み・・・・・」
健太は涙を止めることが出来なかった。真由子は、そんな健太の姿をじっと見守っていた。真由子も静かに泣いた。健太は、最愛の恋人を亡くした・・・・・。あれは17歳の時のことだった。
―それから21年の月日が流れた。
―18歳
月日が流れ、健太は高校を卒業した。
「健太くん、卒業しないで―」
「頑張れよ―。シュート練習、頑張れよ~~~」
健太は体育館で達也、そして同期の人らとワイワイはしゃいでいた。
「え、たつや、お前高橋と付き合っとん?」
「いいやんか―。ラブラブですよ。愛と」
健太は、達也をいじった。
「愛、、、、(笑)あはははは(笑)」
健太は笑った。達也が口をとがらせた。
「けんちゃんやってさ―。なっちゃんのこと‘夏海’って言いよったやん―。ばーか。」
バスケ部の連中が笑った。健太は光が丘高校を卒業し、東京の大学へ進学した。
―20歳
「けーんた」
「なんだよ、有馬」
渋谷のハチ公前で、有馬と待ち合わせした。健太は、紙煙草の箱とライターを持っていた。
「え、健太、お前」
「てか、おめえも吸っとんやろ?有馬のヘビースモーカ~~~~」
「ははは。相変わらず口悪いとこは変わってねーな」
そして、健太は、愛媛に戻り、高校教師になった。
「川村健太です。松山のA島出身です。担当科目は保健体育です。」
日々は流れていった。
最終章―――「いつまでも、愛してる」
―健太・・・・・・好き・・・。
―健太、私、死んだら海になりたい。
―生まれ変わっても、健太の幼馴染で、ほんで、彼女になりたい
人はいつか死ぬ。あいつと過ごした日々を今でも思い出す。生きててほしかった。死んでほしくなかった。あいつは真夏の晴れた日に、死んだ。でも、思うんだ。夏海、夏海がいつまでも近くで見守ってくれてる気がする。夏海が生きてる気がする。でも、あいつは17で死んだ。海になったんだ。俺は、夏海の死を受け止められずに、日々を生きてきた。
季節は、あっという間に過ぎてゆく。時が過ぎるのは早い。時間はあっという間に過ぎる。健太は37歳。・・・でも夏海は17歳のまま。夏海の笑顔が好きだった。夏海と一緒にいるだけでも幸せだった。
―
あれから21年。あれから21年経った。人口減少で島の人口も減った。健太と夏海がよく行った駄菓子屋の高齢の夫婦もいなくなった。子供の数が減って、小学校2校のうち、1校が閉校した。閉まった店も何件もある。島でゆういつのゲームセンターも閉店した。健太と夏海が高校の学校帰りに寄ったファミマも閉まった。街の商店街、海、公園。商店街とかは、寂れてきていた。街の風景も変わった。だが、健太の淡い切ない恋心は、いつまでも変わらなかった。健太は夏海に夢中だった。夏海のことが好きで好きで大好きで、夏海のことを変に避けてしまう時もあった。でも、自分の気持ちに正直になった時、‘あ―俺は、夏海のことが本気で好きなんだ’と、自分の小さな恋心に気づいてしまった。本気で健太は、夏海を愛していた。16の夏、初めて夏海に触れた夜、あの夜、夏海の涙を見て、‘ほんと好きだ’と強く思った。夏海の白い肌に触れた時、震えた。好きな子と1つになるって、ほんまに幸せなことなんやな、って思った。そして、夏海の病気が発覚した時、夏海は辛いはずやのに笑顔で‘健太、私は大丈夫やけん’と、目を真っ赤にして笑顔でそう言っている夏海を見て、何も助けてあげれない自分を憎んだ時もあった。夏海の病気がどんどん悪化して、夏海の病状が悪い時も、夏海は笑顔だった。そして、夏海が亡くなった時、ただ、夏海の死に顔を、じっと見る事しか出来なかった。健太は、泣くことなく、ただ、夏海の死に顔を、じっと見ていた。健太は、夏海の死をいつまでも引きずっていた。夏海が死んだときのことが走馬灯に蘇り、煙草を吸って忘れようとしたこともあった。
「夏海・・・俺は夏海に恋焦がれていた」
前に進めないでいた。バスケ部の部員たちは泣いていた。夏希は目を真っ赤にして、大粒の涙を流していた。外の日が沈んできていた。あれから何時間経っただろう。健太は一呼吸置いた。
「死んでほしくなかった。もう一度、夏海と話したいよ・・・。」
すると翔が言った。
「夏海さん、絶対幸せだったっすよ。山村監督と一緒に過ごして、絶対幸せだったすよ。」
夏海は17歳で命を落とした。延命治療を決断したが、静かに病室で息を引き取った。健太は夏海のその時の顔も未だに頭に残っている。夏海が好きだった。本気で好きだった。だけど、夏海は天国へ旅立った。健太は夏海のことをバスケ部員たちに話すのは初めてだった。恋をすること、恋をして、そして傷ついたこと、夏海に夢中だったこと。
「病気やのに、それを表に出さんと、最期まで生き抜いた人やったんやな。夏海さん・・」
夏希の顔が涙でぬれていた。体育館は、男子バスケ部だけになっていた。他の部活の部員たちは帰ったのだろう。すると、健太が手を叩きながら話し出した。
「今日は解散!」
男子バスケ部員たちが、体育館を後にした。そして健太は、学校内にある職員室へと戻った。健太は決して忘れなかった。健太は2階から見える大きな夕焼けを見た。健太は、毎日その夕焼けを見るたびに、夏海の笑顔を思い出していた。本当に辛かった。苦しかった。自分だけなんで生きとんやろ、と思ったこともあった。高校時代、夏海が他の男と話している時、すごくモヤモヤした。そして、教室で、泣いている夏海を見て、自分の小さな恋心に気づいてしまった。夏海が他の男を思って泣いている、それが健太は苦しかった。健太は職員室で帰りの準備をし、駐車場に止めてある愛車のレトロな車に乗り、煙草のケースから1本取り出し、マールボロを吸い始めた。マールボロの煙の臭いが鼻を突く。学校の駐車場は丘の下にあり、海がよく見える。健太は、車の中から見える、海を見た。小さな子供と、そのお母さん。小学生。高校生のカップル。それに海を背景にして写真を撮りよるであろう、女の子2人組。健太はその光景を、自分の思い出と重ね合わせながら見ていた。懐かしくなった。健太は、煙草の吸殻を灰皿に置き、そして2本目も吸い始めた。ふとあごの方を触ると、ひげが少し伸びていた。最近心に余裕がなくて、教師をやめようか悩んでいたため、ひげをそることすら、間もならなかった。光が丘海岸の海は相変わらず、何年たっても綺麗だった。聳え立つ夕焼けが、健太の心を癒した。夏海の笑顔を思い出していた。
‘夏海、夕焼け好きやったな~’
みたいなことを思い出しながら、マールボロの煙草をまた吸った。煙草を吸うことで、夏海が死んだ時のことを忘れれる気がした。人の死ってこんなにも辛いんだと思った。最近、母の絵里奈に注意される。‘煙草の吸いすぎ’だと。健太は、今でも夏海が死んだ時のことを走馬灯のように思い出す。思い出したくなかった。夏海はALSという病気になり、この世を去った。健太の目がうっすら赤くなった。そして、学校の自動販売機で買った、缶コーヒーを一口飲んだ。すると、1件のLINEが来た。咲からだった。咲のLINEのトプ画は、息子の翔一の写真だった。笑顔の可愛らしい、男の子だった。
‘健太、今暇?’
‘うん’
‘もしよかったら、飲まない?’
‘は?’
‘駅の近くの居酒屋で待ってる’
咲のLINEは相変わらずあっさりしていた。健太は今?と思いながらも、咲のおる居酒屋へと向かった。健太は、ファミマで1回車を止め、ファミマの中に入り、マールボロの煙草を1箱買った。そのファミマの店員さんは、ギャル要素が満載の、17~18ぐらいの女の子で、すっごい嫌そうな顔をされた。‘俺、そこまで臭いか?’と内心苛立ちながら、店を後にした。そして、健太は新品のマールボロの煙草を1本取り出し、吸い始めた。煙草を吸ってるときは、過去のことを忘れれる気がした。健太にとって、煙草は必須になっていた。そして、健太は、地元の駅の近くの居酒屋へと向かった。健太は、夏海が大好きだった、椎名林檎の同じ夜という曲を車の中で流しながら、車を走らせていた。10何年前、夏海にすすめられた曲だ。椎名林檎の、切ない歌声が、心に染み、そして病室で呼吸器に繋がれていた夏海を思い出していた。夏海は、苦しかっただろう、どんだけしんどかっただろう、そう思うと、なぜか涙が出てきた。椎名林檎の切ない歌声が心に染み、車の中で充満する煙草の臭いが、健太の心を悲しくさせた。健太は、居酒屋近くの駐車場に車を止め、咲のいる居酒屋へと向かった。そこの居酒屋は何年も営業しているところであり、店の外観は寂れていた。店内に入ると、咲が煙草をカウンターの席で吸っていた。
夕方17時。健太は学校帰りに、今は高校教師で、一児の母親になっている、咲に会っていた。
相変わらず咲は美人になっていた。健太と咲は、地元の居酒屋に来ていた。そこは禁煙じゃないところであり、咲はたばこを吸い始めた。健太はびっくりして目を丸くした。
「え、お前煙草吸うん?」
「吸うで」
咲は、煙草を右手に持ち、そして、焼き鳥を食い始めた。
「ここの焼き鳥美味しいよね」
「咲が煙草吸うとか衝撃なんやけど」
「は?」
咲は、煙草の煙を、健太の方に吐いた。
「くっさ―――。お前な――」
「あ―――ここの焼き鳥ほんま美味しい。おっちゃん、お代わり~~~」
咲は、本当に細い体をしている。でも、よく食べる。すると、咲は、健太の顔をじっと見た。咲は煙草の吸殻を灰皿に置き、そして、ラッキーストライクの煙草のケースから1本取り出し、ライターの火をつけて、またも吸い始めた。その姿が、なぜか悲しく見えた。
「健太、あのさ」
「健太・・・・今日夏海ちゃんの誕生日やない?」
「そうだよ。あいつ、生きとったら・・・・37歳。」
「この後、行くんやろ?」
山村健太、37歳。高校教師。バスケ部副顧問。健太は、有村家へと向かった。健太は、一階建ての有村家の玄関のインターフォンを押した。
「あ、おじちゃん?」
「あ、夏希?お父ちゃんおるか?」
有村達也。そして、有村愛。旧姓・高橋愛は、23歳の時に、結婚をし、そして、次の日の年に、愛は長女の夏希を出産した。
「お、けんちゃんやん」
「うっす、達也」
「あ、山村やん~どうぞどうぞ―。今日、なっちゃんの誕生日やし、みんなで祝おう~」
「達也・・・・・お前ビール結構飲んどるやろ~~~。」
達也は健太の肩を組んだ。そして、夏希はその後ろを歩いた。久しぶりの、幼馴染‘4人’での集まりだった。健太は、有村家のリビングに入ったとこにある、高校生の時の幼馴染4人の写真と、夏海単体の写真を見た。写真での夏海は、ものすごく笑顔だった。まるで、太陽に照らされた満開の向日葵のような笑顔だった。健太はダイニングテーブルの椅子に座った。
「高橋」
「ん?」
健太は、カバンの中に入れてある煙草の入れ物を取り出した。
「有村家は煙草禁止?」
すると、愛は険しそうな顔をした。そして、健太の頭をチョップした。
「吸うなら外で吸ってください!」
「は―い(笑)」
「てか、料理出来たんやけど」
愛は、肉サラダに、シューマイに、唐揚げに、餃子にたくさん料理を振舞った。達也は酔っぱらっていた。
「愛、けんちゃんにたくさん食べさせてな~~~」
「OK」
「はは」
すると健太のスマホの着信音が鳴った。有馬からだった。
「ん、有馬?」
「健太~~~、今どこ?」
有馬は酒で酔っぱらっているようだった。
「なんぞお前。かけてくんなよ気持ちワリい」
「おじちゃん口わっる――――――――――」
夏希が横で爆笑していた。達也と愛も笑った。相変わらずの、健太と有馬のやり取りだった。健太は、電話のスピーカーをオンにし、タバコをカバンから取り出した。
「山村、中で吸ったらいかんで~~~」
「わーってるよ」
すると、有馬が大声で話し始めた。
「え、健太タバコ吸ってんの?」
健太が笑い始めた。
「そやけど」
「なんぞ、有馬」
「健太、今から有村家に向かうわ」
「え、くんな―。めんどいやん」
「腹立つな」
愛が、聞こえるように言った。
「有馬さん、今日、なっちゃんの命日」
「愛ちゃんやん。相変わらずたっつんとラブラブか?」
達也が、少しビールを吹き出した。
「ええ。相変わらず」
「はは」
「てか、今日なっちゃんの命日。有馬さん、まさか忘れてませんよね?」
「忘れとるわけね―よ。なっちゃんの37歳の誕生日やろ?」
すると、健太が言った。
「夏海の37歳か―、生きとったらあいつ、何しよったかな?」
「保育士」
「いや、なっちゃん歌手やない?」
「幼稚園の先生」
すると、達也が、健太の肩を組んだ。
「けんちゃんのお嫁さんで、専業主婦」
健太の頬が少し赤くなった。健太は達也の頭をバシッと叩いた。
「うぜえ」
「けんちゃん、でもそうなっとるやろ~~」
「なっちゃんと山村、いつか結婚するやろな―って思いよったで」
健太は両手で顔を隠した。健太の耳が少し赤くなっていた。
「なっちゃんのウエディングドレス姿、絶対綺麗やったろうに」
「なっちゃん、絶対ニコニコしながら協会のバージンロード歩いたと思う」
「間違いない。夏海、ここにいたら・・・。」
健太が目を細めて、夏海の写真を見た。健太は、夏海と結婚して、夏海が子供を授かり、家庭を持っていたらどんな人生を歩んでいたのかと思った。健太は、写真の中で満面の笑みで笑っている夏海が、もうこの世にいないかと思うと、胸が苦しくなった。
愛は、健太が家を出た後、傍に飾ってある、4人での2ショットを見た。中学3年の時の修学旅行の時の写真だ。夏海は笑っていた。夏海だけ歳をとらない。そのことが信じれなかった。
「・・・・・・・・・生きよう」
愛、そして達也。2人とも夏海の死を受け入れるときがきた。
―ガチャ
夏海が死んで、21年という月日が流れた。健太は、夏海のことをいつまでも忘れれないでいた。健太は有村家の玄関のドアを開け、そして、近くの公園へとッ向かった。空は赤く染まっていた。健太は、ベンチに座った。
―は~
健太は思いだしていた。夏海との日々を、夏海と生きた日々を。有村家の家の外で煙草を吸い始めた。マールボロの煙の臭いが鼻に突き刺さった。咲はラッキーストライクを吸いよったな~と思いながら煙草を吸っていた。健太が煙草を吸い始めたのは20歳のころだった。そして、辺り一面に広がる、真っ赤な空を見た。ふと泣きそうになった。
―夏海は、この世にいない
―夏海は17で死んだ
―夏海の、笑顔が好きやった
―夏海に会いたい
夏海がこの世にいない。健太はその事実を受け止めきるには時間がかかった。健太は、煙草を吸い始めた。マールボロの臭いが鼻を突いた。この町の空は、何年経っても、相変わらず色褪せなかった。真っ赤に染まった空が健太の心を悲しくさせた。健太は、ふと、泣きそうになった。健太の心には、ずっと、夏海がいた。そして、健太は夏海が好きだった音楽を流した。夏海が、よく聴いていた曲だ。健太は、煙草を吸った。煙草の煙が宙をまいた。なんで、夏海がこの世にいないのか、受け止めるに時間がかかった。すると
―健太
(え・・・・)
ふと、声のした方を向くと、高校生ぐらいのカップルが並んで帰っていた。彼女の方は、よく話す感じの笑顔溢れる子で、彼氏の方は、多分バスケ部で、そして、バスケ部のショルダーバックを肩にかけていた。
「ばーか」
「お前にばかって言われたくないし」
「そういうとこも、可愛いで」
「もう」
空は、茜色に染まっていた。健太は、またも煙草を吸い始めた。健太は、ふっと、ため息をついた。夏海は、いつまでも皆の心の中で生きてる、そう思った。川村家の玄関には、夏海が生前付けていた、ハートのネックレスが飾られている。健太は、今でも空の上にいる、夏海を想っている。そして、いつまでも、ずっと、健太は夏海を想い続けるだろう。今日も、健太は、夏海と生きた日々を頭の脳裏に焼き付けながら生きていた。空は、綺麗だった。茜色に染まった空は、健太の気持ちを明るくさせた。
―夏海、いつまでも、愛してるー
夏海と、健太。2人の愛は、いつまでも変わらずに、永遠に続くのであった。
—この小説を執筆するにあたって、コメントします。
皆、それぞれの人生を生きています。
この物語は、2021年ごろから考えていました。
私は、愛媛県で生まれ育ちました。
18歳まで愛媛で過ごし、悩んだり苦しんだりしたことも
ありました。でも、幸せだったこともたくさんあります。
皆様、これからの人生で悩むこともたくさんあると思います。
でも、近くには絶対、自分のことを必要としてくれている人、
見てくれている人、自分のことを愛してくれている人がいることを
忘れないでください。最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
皆様、それぞれの人生が輝きますように、と、ここに
記させて頂きます。誠に、ありがとうございました。
令和5年 12月31日 椎名のん
―♪
好きだった
大好きだった
愛していた
真夏の太陽が照らす空の下で恋をした
愛しい
願うならば、会いたい
ずっと一緒にいたかった
我を忘れるぐらい、恋をしていた
―🌸
第1章――「想い出」
蝉の鳴き声が響き渡る。太陽の日差しが眩しい。向日葵が満開に咲いている。小さな子供が虫取りに夢中になっている。シャボン玉を飛ばしている子供もいたりする。漁港も人で溢れてる。光が丘海岸の海は静かに音を立てている。今年も夏が来た。愛媛県のA島は本当に暑い。真夏の暑さだ。そして、そこの島に、1人の男がいた。山村健太、37歳。独身。健太は、部屋から海を見ながら、煙草を吸っていた。メビウスの煙草の煙が、部屋の宙をまいた。
「・・・・・今年もきたか」
健太は、毎年夏が来ると、複雑な気持ちになっていた。健太は煙草を灰皿に押し付け、そして、スマホで音楽を流した。17年前に死んだ、亡き恋人が好きだった音楽を流しながら、煙草を吸っていた。健太は思い出していた。亡き恋人のことを。いつまでも忘れれない女のことを。夏海を。健太は、思い出しながら、音楽を流していた。
「・・・・・は~、・・・・・・あいつ・・・・。」
健太は、光が丘海岸の海を見ながら、17年前に、死んだ亡き恋人が好きだった音楽を流しながら、煙草を吸っていた。夜、健太は、部屋で友達の達也と酒を飲んでいた。達也も煙草を吸っていた。達也は、アイコスを吸っていた。
「けんちゃん」
「ん」
「今年も来たな、夏。」
「・・・・・・・あー。そうやな」
さざ波が聞こえる夜10時。健太は立ち上がった。そして、窓から見える海を見た。健太は、亡き恋人とのことを、たくさん思い出していた。死んだ恋人とのことを思い出していた。達也は、いびきをかきながら寝ていた。健太は、煙草の箱から1本紙煙草を取り出し、ライターで煙草の先端に火を付け、そして吸い始めた。健太は、海を見るたびに切ない気持ちになっていた。その日の夜、健太は夢を見た。凄く凄く愛していた人、その女はセーラー服を着ていた。そして、笑顔で海を見ていた。そして、名前を呼ばれた。
「けんた」
―はっ
健太は夢にうなされながら、夜中の3時に目覚めた。額から汗が流れていた。健太は息切れをしながら、再度寝始めた。ずっと、何年も忘れることが出来ない、死んだ恋人・夏海の夢を、ここ最近、何度も見ていた。健太は、‘夏海’が近くにいる気がした。健太は、走馬灯のように、‘夏海’が死んだときのことを思い出していた。健太は思い出すと辛くなり、テーブルの上に置いてある、ライターと煙草を取り出し、煙草の先端に火を付け、吸い始めた。
もう、思い出したくなかった。‘夏海’との日々を思い出したくなかった。‘夏海’は、17歳の時に、早くしてこの世を去った。‘夏海’との思い出の場所、光が丘海岸は、いつまでも色あせることなく、波が音を立てていた。健太は、煙草の吸殻を灰皿に押し付け、再度寝た。
第2章――「夕暮れの空」
翌日、空は晴天だった。健太は、夏海の命日の前の日、小さい頃からの知り合いで、今は一児の母になっている、木原咲に会った。健太は咲と海の見える喫茶店で、お互いコーヒーを飲んでいた。
「健太」
「ん?」
咲は黒髪のロングで、華奢な体系で、そして咲も、健太と同じヘビースモーカー。
咲の傍には、ピンク色のアイコスが置かれていた。
「健太・・・・明日やね・・・・。」
「それさ―、昨日達也にも同じこと言われた。」
「有村も?」
「・・・・・・・・明日、花添えてくるわ」
健太は、煙草を1本吸い始めた。喫煙がOKな席だった。咲は、切なそうな目をしていた。
「けんた」
「ん?」
「今でも・・・・・・・なつみちゃんのこと・・・・・・・・・。」
「・・・・・・・・・・・あー、そうやな」
2人の間でちょっとした沈黙が流れ、煙草の匂いが辺りを充満した。太陽の日差しが窓に差し込み、店の冷房の風が、頬にヒヤッとした。そして、次の日の朝、健太は、夏海の家に行った。2037年 某8月。夏海の命日。健太は、夏海の遺影の前で手を合わせた。健太は、向日葵の花を、遺影の近くに添えた。21年。あれから21年経ったことが、健太は信じられなかった。健太は、夏海の部屋を見た。勉強机、スマホ、ギター、服。夏海の母の真由子は、自分の娘が使っていた部屋をそのままにしていた。そして、健太は、勉強机に飾られている1つの写真盾を見た。夏海は、自分との2ショットを飾っていた。自分は歳をとり、夏海は老けない。その事実を未だに受け止めきれなかった。夏海は、苦しんで死んだ。17という若さだった。
「健太、ありがとう・・・・。」
「・・・・・・・・・・・うん。あ、おばちゃん、ちょいベランダで煙草吸っていい?」
「ええで」
健太は、ベランダに出た。煙草の箱から1本取り出し、ライターで煙草の先端に火を付け、吸い始めた。煙は宙を巻いた。ベランダから見る島の海は、色あせることなく、いつまでも輝いていた。すると電話がかかってきた。友達の有村達也からだった。
「もしもーし」
「けんちゃん、やほ―。けんちゃん、特に用はないんやけど―・・・・・・・明日、
なっちゃんの誕生日や―ん」
「ああ、そうやな」
「家来る?愛が、ご飯作るで~」
「・・・・・・・・・・・時間あったら行くわ」
健太は、川村家のベランダから見える、光が丘海岸を見た。茜色に染まった空は健太の心を悲しくさせた。健太は、なんで夏海がこの世にいないのか、信じられなかった。本当に信じられなかった。そして、健太の職業は高校教師。健太は、明日は夏海の誕生日だが、普通に部活の日だ。健太は、明日の部活の計画を立て、夏海の誕生日と思うと、辛い気持ちになっていたが、部活の時は部活に集中と思った。光が丘海岸の波は、静かに音を立てていた。
第3章――「告白」
次の日。真夏の暑い日に某高校のバスケ部が、体育館で猛練習をしていた。
「そこ早く!」
「何してんや!」
健太は、そこの高校の男子バスケ部の監督をしていた。健太は、熱血で教育熱心だと有名だった。山村健太、37歳。男子バスケ部副顧問兼コーチ。女子生徒からはイケメンだと評判だ。休憩時間、選手たちが体育館で弁当に、ローソンの菓子パンに、食べ始めた。すると、軽音部のバンドが、文化祭の練習で体育館のステージを使い始めた。そのバンドのボーカルに、達也と愛の娘の、高校1年の有村夏希。軽音部所属。文系志望。夏希は、綺麗な顔をしていて、色白で、男子生徒から一目置かれている。その中の1人、藤沢翔は、夏希に惚れていた。
「あ~~~♪じゃやりますかー!」
そのバンドは、演奏し始めた。
「有村って綺麗よなー」
「可愛い」
「細い」
「色白」
「美人」
すると、翔が乱暴なことを言い出した。
「どこが?あいつ、ブスやん(笑)」
翔のその言葉に、健太が突っ込んだ。
「藤沢、夏希に惚れとんやろ?」
「は?惚れてねーし、あんなガサツ女・・・・・・」
「顔、少し赤いで(笑)」
「も~監督・・・・・・・。」
夏希は本当に綺麗な声をしていた。少し低いハスキーな歌声を夏希はしていた。そのバンドのステージ練習が少し終わった頃、夏希がバスケ部の連中のところに来た。夏希は、健太の顔を見た。
「あ、おじ・・・・あ、山村先生、翔殴ってもいいですか?」
「は?なんでや」
「翔、ノート返してや」
「あ、忘れた。」
すると、健太が翔の頭をげんこつした。
「あほか、勉強せんといけんやん」
「いって~~。監督もっと手加減してや~」
すると、夏希が翔の前にしゃがみこんだ。
「翔」
翔はドキドキしていた。夏希の大きな目、そして・・・・胸。
「翔」
「ん?」
「何、この擦り傷~」
夏希は、右頬にうっすら出来ている、翔の頬の擦り傷を触った。翔は、夏希の右手首を掴んだ。夏希の頬が少し赤くなった。夏希はそれを隠そうと左手で隠そうとしたが、無理だった。翔が夏希の目を真剣に見た。いや、見つめたと言い直した方がいいかもしれない。
「夏希」
「ん?」
夏海は本当に綺麗な顔をしていた。翔はドキドキしていた。夏希がどんどん綺麗になっていくことに。時々、夏希が至近距離にいる時、キスしそうになる自分がいた。でも、夏希は本当に綺麗で、そんな簡単に夏希に手を出せないほど、翔は夏希のことを大切に思っていた。ドキドキしていた。翔は夏希に恋焦がれていた。夏希の顔が至近距離にある。金木犀の匂いがした。
「あのさ」
「うん」
「お前ら、付き合っとん?」
健太が2人に言った。
「は?なんでや。」
「山村先生、翔とは、ただの幼馴染よ。」
―けんたとは、ただの幼馴染よ
健太は、夏希がふと、大昔惚れた女に重なった。
‘けんた、私さ―、長くないんよ’
‘私が死んでも、忘れないでね’
大昔、真夏の暑い中、病室で命を絶った恋人・夏海のことを健太は思い出した。
―来年、光が丘海岸の桜、一緒に見よう
―健太、好き
―健太の隣で笑ってたいな
―生きて・・・・・生きて
健太の目が潤んでいた。健太は、手で目頭を拭った。17で命を落とした女のことを・・・・。健太は、その場であぐらをかいた。そして、バスケ部員たちを見た。
「・・・・・あのさ」
「ん?」
「お前らに、話す時が来たか・・・・」
「何を、すか?」
すると、健太は、一呼吸置いてから、ゆっくりと話し出した。
「俺の幼馴染に夏海という子がいたんだ」
「夏海??」
「夏の海と書いて、夏海。」
健太は、落ち着いて話し出していた。もう覚悟は決めていた。
「夏海、明るくて、いつでも笑っとるような奴で、笑顔で、教室でよくギターを弾きよったな。夏になると、教室から海を見ながら、‘死んだら海になりたい’って言うような女やった。誰に対しても明るくて、笑顔で、ニコニコしよって、そんな夏海のことを、俺は・・・・・・・・・・。でも」
「でも?」
健太は落ち着いていた。
「17歳の時に、病気で死んだ。」
「え・・・・・・・・・・」
すると、健太が、近くにあった、バスケットボールを持った。そして、そのボールを撫でるよう触った。高校の近くには海がある。健太は、その海を切なそうな目で見た。
「ほんま、好きやった。あいつに何かしてあげれたかな・・・・」
健太の心には、‘夏海’がいつまでもいた。永遠に消えることのない、淡い恋心。健太は、夏海と笑い合った日々を、昨日のことのように思い出していた。健太は、体育館の傍に植えられている向日葵をふと見た。向日葵を見ていると、あの夏を思い出してしまい、正直辛かった。夏海、夏海に会いたいとものすごく思った。
「あれは、21年前・・・・・・・。」
第4章――「21年前」
本気で愛していた。でも、あいつは、17で死んだ――――・・・・・・・。
いつまでも忘れられない女のことを、俺は愛していた。
健太は、今でも夏海に会いたいと思う。ものすごく夏海に会いたいと思う。夏海がこの世にいないことが、信じられなかった。夏海が近くにいない。傍で笑ってた夏海がこの世にいない。健太は、夏海の死を受け入れるのにどれくらい時間がかかっただろう。でも、夏海は17で命を落とした。健太は、夏海が死んだときの顔も覚えている。脳裏に蘇る。夏海が亡くなった時のことを思い出すだけで、苦しくて、苦しくて、だから、煙草を吸って、夏海を、夏海の存在自体を忘れようとしていた。けど、そんなことしても、夏海のことは忘れられなかった。夏海は、海が好きな女の子だった。
夏海は、健太と同じで、海沿いの街に住んでいた。川村夏海、夏海と健太は小さい頃からの幼馴染だった。2人はいつでも一緒にいた。どんな時も一緒にいた。高校2年の春に付き合い、夏海は、真夏の太陽の日差しが降り注ぐ病室の中で、命を落とした。夏海は、どんな時も明るかった。夏海は夢の中にいた。夏海は亡き父親の夢を見ていた。夏海は、夢の中で亡き父と夕暮れに染まった海を見ていた。和樹は、綺麗な顔をしていた。シュッとした顔立ちをしていて、夏海の顔をじっと見た。和樹は笑っていた。和樹は、夏海の右頬を触った。和樹は、少し健太に似ていた。ワイルドな感じだった。
「夏海」
「お父ちゃん?」
「生きろよ」
そこで夢は終わった。目覚めると、朝になっていた。‘ほんまにリアルな夢やん’と夏海は思った。右頬の感触が残っていた。夢がリアルすぎて、少しビックリしていた。夏海は、朝の5時半に起きた。そして布団を押しのけ、遠くからだが窓から見える海を見た。夏海は、自分が今日も生きていることに感謝した。天国にいる父親・和樹に心の中で、‘お父ちゃん、今日も良い日になるよ’と問いかけた。夏海の父親、和樹は、おとなしく、ワイルドで、芯が熱い男だったと、前に、母の真由子から聞いたことがあった。
「お母ちゃん、朝やで~~」
「・・・・な・・・っちゃん・・・朝早いね~~お母ちゃんまだ眠いよ~~」
母の真由子は、本当に眠そうだった。
「焼けん~~~。あ――――」
「どしたんよーーー(笑)」
夏海は、フレンチトーストが焼けなくて悪戦苦闘していた。そして、夏海は、焦げ焦げのフレンチトーストを母親と2人で食べることになった。
「まっっずーーーー!」
「なっちゃん、大丈夫。蜂蜜掛けたら食べれる」
母親の真由子。34歳。肝っ玉母ちゃん。昼はスーパー、夜はスナックで働いている。真由子は、ラッキーストライクの煙草の箱から1本取り出し、ライターで煙草の先端部分を付け、吸い始めた。
「なっちゃん」
「ん?」
「健太、最近、元気?」
「元気元気、相変わらず、バスケ馬鹿よ」
「ははは(笑)」
そして、真由子は、洗面所の前でメイクをし出した。
「なっちゃん、お母ちゃんさーー」
「ん?」
「駅前に‘ひかりがおか’っていう、最近出来た新しい居酒屋のお店あるや―ん」
「うん」
「週一、そこで働くことにした」
夏海は、パンを落としそうになった。‘母ちゃん働きすぎやろ’って内心思ったが、言えなかった。夏海は、反対することなく、
「がんば」
と、一言言い、焦げ焦げのフレンチトーストにかぶりついた。真由子は、赤い口紅を付け、髪を巻いて、黒のワンピースを着て、また、ベランダで煙草をふかした。部屋は、ラッキーストライクの煙草の臭いがすごくした。ふと、真由子を見ると、真由子の後ろ姿は時折悲しく見えた。夏海のお父ちゃん、死んだ和樹のことを思い出しとんかな?と夏海は、思った。母の長い髪の毛が、春の風になびいた。そして、真由子が、部屋の中に入ってきた。
「お母ちゃん、私、大丈夫かな―料理が下手なんじゃ、お嫁に行けないわ~」
もう一度打つ。川村夏海、16歳。今日から高校2年生になる。夏海は、母親の真由子と2人暮らし。夏海は、数学化学、理数系が本当に苦手で、高校1年の時の調理実習の生姜焼きの調味料に、焼く前だからよかったのだが、大さじ8杯の砂糖を、銀の四角い入れ物のなかに入れた。夏海はそれ以来自信をなくした。料理を。
「なっちゃん、あんた、愛嬌とかほんまええんやから~。」
「お母ちゃん、ほんま?」
夏海は立ち直った。夏海は本当に立ち直りが早い。いわゆるポジティブ人間。どんなに辛いことがあっても一瞬で立ち直る。夏海は焦げ焦げのフレンチトーストを食べた後、洗面台で歯磨きをし、そして、前髪をアイロンしはじめた。
「あっつ――――――――」
夏海は前髪をアイロンしている時に、低温やけどをした。
「なっちゃん、8時になりよるで~」
「あっつ」
夏海は、またも洗面台で、前髪をアイロンでストレートにするのに悪戦苦闘していた。遂に真由子は、声を強くした。
「なっちゃん、急がんと!」
「あ、はいっ」
―❤
夏海は小さい頃から不思議や、謎、変、変わっとると言われてきた。夏海は本当に変人で、何考えとんか分らんと、よく人に言われてきた。夏海は、黒のリュックを背負い、そして、玄関を飛び出した。階段をおり、そして自転車置き場に行った。夏海は、自転車に乗り、こぎ出した。まず、アパートから坂道になっている坂をおり、そして、坂を下りたとこにあるローソンを曲がり、そこから田んぼばかり続く道を自転車でこぐ。青い空が広がり、春の風が気持ちよかった。夏海の天然パーマの髪が揺れた。そして、学校までもうすぐのとこにガードレールがある。ガードレールからは、光り輝く青い海が見える。海からの潮の匂いが鼻をくすぐる。ガードレールの板は、寂れているが、夏海は、朝の登校、そして夕方の帰り道、光が丘海岸の海を見て‘今日も頑張ろう’と思うことが日課になっていた。そして、夏海は、あいみょんの‘裸の心’をガードレールを自転車で下りながら歌っていた。
「この~恋が~~み~のりますよ――に――」
夏海はあいみょんが本当に好きだ。あいみょんのCDの発売日はほんまに必ずチェックしているし、雑誌も必ず買っている。あいみょんが出ているテレビも必ずチェックしている。夏海は初めてアルバイトでもらった給料で、あいみょんのCDを買った。1000何円もするCDだ。本当に欲しかったあいみょんのCDを、自分で働いたお金で初めて買ったときは、ものすごく嬉しい気持ちになった。
ガードレールを下りたところに、小さい頃から馴染の駄菓子屋さんがある。そこには、もう90近い、高齢の夫婦が住んでいた。
「お―なっちゃん」
「おじいちゃん、学校行ってきま―す!」
夏海は、満面の笑みで、駄菓子屋の出たとこを掃除している、タカさんに言った。
夏海は、そのまま自転車をこいだ。夏海が住んでいるのは、愛媛県のA島。人口、2000人。夏海は、光が丘海岸の波の音を感じながら、海沿いのガードレールの道を、自転車でこいでいた。すると、道の途中で、健太に会った。
「おーす、健太」
「あ、川村やん。」
「今日から高校2年やねーーー!」
「ほやな」
夏海は自転車からおり、健太の隣で歩き始めた。
「けんた」
「ん?」
「呼んだだけや(笑)」
「なんや(笑)」
すると、健太が話し出した。
「川村」
「ん?」
「貧乳―、ばーか」
「は?今からお胸も大きくなるんですー」
「やって、お前、まじ、胸ちっせー」
健太が、変態発言を夏海にした。2人は喧嘩?をしながら、高校までの道を歩いた。
「健太のばーか」
「ばかとは、なんぞ(笑)」
「やって、さっき、貧乳っていったやん」
「やって、ほんまに貧乳やもん―――」
「ばかやろ――」
「ははは(笑)」
そんなくだらない会話をしている間に、高校に着いた。健太とは、今年も同じ
クラスだった。
「今年も川村と一緒かー」
「え、嫌?」
「嫌やない」
すると、夏海は後ろから幼馴染で親友の愛に抱きしめられた。
「なっちゃーん~~~~~~~~~❤今年も一緒よ―――――――――❤」
夏海は、愛を抱きしめた。
「え、やった――――――――――――❤愛ちゃん、たくさん話そ――ね❤」
「早弁もたくさんしよ――――ね(^^♪)」
夏海と愛が騒いでいる時に、幼馴染の達也が来た。
「おめーら、俺のことも忘れんなよ~~~~~~。」
「え、たっつんも、A組?」
「ほやけど、悪いか?」
「え、達也、俺もAやぞ」
「え」
「え」
「「しゃ――――――――――――――――――!」」
健太と達也の声が廊下に響き渡った。そして、高校2年の季節が始まった。夏海と、健太は、席が一番後ろの、隣どうしになった。
「よろしく」
「寝よったら、起こすわ」
「起こすな、ばーか」
本当に幸せな日々だった。夏海は、こっそり、健太の横顔を見ていた。
居眠りしている健太
大あくびしている健太
友達と、談笑している健太
一生懸命、勉強している健太
どの健太も、本当に愛しくてたまらなかった。そして、夏海は、街から3駅離れた町の駅のドトールで、アルバイトをしていた。
「いらっしゃいませ――。メニューはお決まりでしょうか?」
夏海は、笑顔で、接客業をしていた。そして、そこのお店で出会った同い年の女、
木原咲と仲がよかった。咲は、健太の古くからの知りあいだった。夏海は、咲と、バイトの控室で談笑していた。
「夏海、思ったんやけど。」
「ん?」
「彼氏、おらんの?」
「は?おらんわ////」
咲は、顔をにやつかせながら、夏海に、たくさん話をした。
「あれは、幼馴染の、健太は?」
「健太?」
夏海の頬は少し赤かった。そして、夏海は、両手で顔を隠した。
「咲ちゃん」
「ん?」
夏海は、本当に、健太のことが好きだった。健太の1番なれたらな―とも思っていた。夏海は、健太のことを想うと、胸が高鳴ってしょうがなかった。そして、次の日の、放課後。時間は夕方の時間帯、テスト期間もあって、運動部は部活が休みだった。
「川村」
「ん?」
「一緒に帰んね――か?」
「ええよ、帰ろ――」
夏海と健太は、肩を並べて帰った。健太は、夏海の頭1個分、背が高かった。A島は、この日は、天気がよく晴れていて、遠くのほうで、鴎の鳴き声が聞こえた。夏海と、健太は、桜並木を歩き、そして、通学路にもなっている、海沿いのガードレールを歩いた。空は、辺り一面に、青空が広がっていた。
―第5章「好きだ」
「川村、彼氏いんのかよ」
歩いている時、健太が聞いてきた。
「え・・・・・・・・・おらんよ――(笑)何言いよるん(笑)」
すると、健太が率直な質問をしてきた。
「川村、あのさ、俺がいきなりお前のことを抱きしめたら、どうする?」
「え・・・・・・・・」
夏海は、健太の方を見た。
「もし俺が、お前にキスしたら、川村、どうする?」
夏海は、頬が熱くなった。夏海は話題を変えた。
「健太~、明日、数学のミニテストやーん。勉強した?」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・、貧乳のくせに」
「まじムカつく、死ね」
「死ねってなんぞ、ばーか」
2人は大人げない会話をしていた。夏海は、ふと自分の胸の方を見た。‘健太はおっぱい大きい子が好きなんかな?’と思った。すると夏海は、健太の後ろからの視線を感じた。健太からの視線を強く感じた。夏海の心臓がとくとくと高鳴った。後ろを見ると、健太が真剣な目で夏海を見ていた。夏海は、前へと視線を戻した。すると、健太が夏海の左手首を後ろから掴んだ。夏海はびっくりした。
静かな沈黙が流れた。夏海は健太の方を再度振り返った。健太の頬が少し赤かった。
(健太・・・・・・・・・?)
すると、後ろから健太が夏海を抱きしめた。夏海は、何が起こっているのか分からなかった。健太の腕は力強かった。夏海は、健太の温もりを感じた。
「ちょ、健太・・・・・・・・?」
健太は、本当に力強く、健太から離れようとしたが、抵抗出来なかった。
健太の頬が赤かった。健太は、夏海を自分の身体から話し、一言言った。
「並んで歩こう・・・・・・・」
海沿いのガードレールを2人で歩くのは久しぶりだった。高校2年の春のことだった。夏海はふと健太を見た。健太の横顔は凛としていて綺麗だった。2人の身体の距離が近くなった。夏海は、今にも心臓の音が健太にバレルんやないかと思って、心臓の鼓動が収まらなかった。夏海の頬が少し熱くなった。そして、2人の手が当たった。
「あ、ごめん・・・・っ」
夏海が手を心臓のとこにもっていこうとしたその時、健太が、夏海の右手を握った。夏海は、‘え?’と思った。夏海の心臓の鼓動は増すばかりだった。ドクンドクンと心臓が音を立てていた。
「な――」
「ん?」
すると、健太が夏海の顔を見た。健太が切なそうな顔で夏海を見た。健太は、夏海の唇を触った。柔らかくてぷっくらしている唇をそっと触った。すると、健太が顔を近づけた。2人の顔の距離は近かった。
「好きだ。ずっと好きだった。」
そう言うと、健太は夏海にキスをした。高校2年生の春のことだった。お互い、初めてのファーストキスだった。夏海は、目を閉じた。
6章―――「両想い」
あれから何秒経っただろう。健太が唇を離した。夏海は恥ずかしすぎて健太の顔を見れなかった。
「好きだ・・・・・」
健太は夏海を思いっきり抱きしめた。健太の腕は力強かった。健太の吐息、心臓の鼓動、体温。夏海は全てを感じ取った。淡い、高校2年の春のことだった。夏海は、返事が出来ずに、ただ、健太を避けてしまう日々が続いた。
健太のことが好きやのに
健太のことが好きやのに
幼馴染の関係が壊れるんが怖い、とばかり思ってしまい、
学校でも、健太を避けていた。そんなことを考えているうちに、季節は6月になった。6月某日、放課後教室で勉強していると、健太の先輩の、有馬さんが教室に入ってきた。
「有馬さん」
「お、なっちゃんやん」
高校2年の初夏。教室で勉強している時に、練習着で汗だくの有馬が教室に来た。
「てか、有馬さん、入る教室間違えてません?(笑)」
「間違えた(笑)はは(笑)」
「・・・・・・・・・有馬さん、健太頑張ってますか?」
すると、有馬は、夏海の教室机にもたれかかった。
「あいつな・・・・」
有馬は、少し険しそうな顔をした。
「あいつ・・・予選の準決勝でシュート外したこと、すげ―気にしてたんだよ。先輩たちの夢を壊してすみませんって・・・・前に泣きながら誤ってきて・・・。健太、でも、毎朝、シュート練習しよって・・・・・・。あいつは強くなるよ。俺も、大学でも
バスケしようと思うし、今日は、ちょい、受験勉強の合間をぬって、練習―」
夏海は、なるほど、と思った。最近、健太の元気がなく、どうしたのかと思ったが、
立ち直ったんならよかった、と思った。
「・・・・・・・・・健太、ほんまにバスケ好きですもんね」
すると、有馬は、夏海を見て、白い歯を出した。
「なっちゃんのこともな」
「え、え?」
「何、そんなびっくりしてんだよ。バスケ部で噂になってんぞ―。健太となっちゃんが両想いって❤ヒューヒュー❤」
夏海の頬が、林檎みたいに赤く染まっていった。
そして、夏海は、有馬の顔をじっと見た。
「あいつ、めっちゃ俺に、電話とかで、‘夏海のことがすげ―好きやから、有馬、惚れんでな’とか‘夏海が今日髪結んどって可愛かった’とか、あいつ、ほんまに、なっちゃんのこと、すげ―想っとる」
夕暮れに染まる教室で、夏海の心臓は高鳴った。すると、有馬が夏海の頭をポンッと触った。有馬は、クスッと子供のような無邪気な顔を見せた。
「なっちゃん」
「どうされました?」
「健太のこと好きか?」
夏海の頬が少し赤く染まった。すると、夏海が顔を下に向けた。
「・・・・・・好きなんか、健太のこと」
「え、好きやないです」
すると、有馬がからかった。
「ほんま?健太の奴、部活の休憩時間の時とか、達也に、むっちゃ、なっちゃんの話してたで。なっちゃん、ほんまに愛されてんな」
すると、有馬は、タオルを頭に被って、教室を出ていった。すると、教室の外から、有馬は夏海を見た。
「なっちゃん」
「も―、なんですか。」
「健太の気持ち、確かめてみたら?」
すると、有馬は、向こうの方へと、走っていった。そして、夏海は、ギタ―を教室の床に置いて、壁にもたれかかった。その時、軽音部のバンドが、あいみょんの
「3636」を練習していた。夏海は、目を瞑って、そして、あいみょんの「3636」を口ずさんだ。夏海は、軽音部の音を聴いていたら、いてもたってもいられなくなり、ギタ―で曲を作り始めた。
「――――――――♪」
夏海は、教室から見える海を見ながら、歌っていた。そして、遠くの方で、バスケ部の集団が、夏海の綺麗な歌声を聴いていた。ふと、健太が言った。
「夏海の歌声、好きやな」
すると、達也が健太を茶化した。
「けんちゃん、付き合ったらええやん――も―――❤」
すると、健太の頬が少し赤く染まり、健太は、口元を右手で隠した。すると、達也が健太ににやにやしながら言った。
「なっちゃんとキス出来たら最高やろ?」
「は?」
健太の顔がますます赤くなった。すると、バスケ部員が茶化しだした。
「健太さん、しちゃえ~」
「愛しの‘なっちゃん’とキス」
「青春やね――――❤」
健太は、照れ隠しなのか、‘うっせ―’と言った。
「おい、お前ら、練習再開するぞ」
「「うすっ」」
男子バスケ部が、練習を再開した。夕方の6時半を回っていた。夜8時、夏海はまたも、教室にいた。この前、カメラのキタムラで現像した、高校入学する前の春に、幼馴染4人で、春休みにディズニーランドに行った写真を、机の上に並べ、そして眺めていた。夏海は、スマホを取り出し、マイヘアーイズバッドの‘卒業’を、音楽アプリで流した。すると、健太からLINEが来た。
‘川村’
‘ん?’
‘教室おる?’
‘おるよ’
‘一緒に帰ろうぜ――’
夏海は、珍しいと思った。健太からお誘いのLINEが来ることは滅多になかった。
‘どしたん急に?’
‘いいから’
夏海は健太と一緒に帰ることになった。ギターケースを背負い、そして、夏海は気持ちを落ち着かせた。夏海は、健太が教室に来るのを待っていた。そして、健太が、教室に来た。
「うす」
「あ・・・・・・おひさ」
2人がまともに話すのは、2か月ぶりだった。そして、健太は、夏海の、
天然パーマの髪の毛を、そっと、右手で触った。
「・・・・・・・・・夏海」
「ん?」
すると、健太が、夏海を抱きしめた。
「好きだ・・・・・・・・・・。夏海と一緒にいたい。」
夏海の心臓の鼓動は、半端なかった。そして、夏海は、抱きしめかえした。
「・・・・私も、健太と一緒にいたい。好き。」
高校2年の6月某日、2人は付き合った。本当に幸せなことだった。
第7章―――「初体験」
―あの日の夜を忘れない。あの日の夜、夏海の肌に触れた。心臓の鼓動が半端なかった。ベットの上で夏海を抱きしめた時、夏海がすこし震えていた。夏海の温もりを感じた。夏海の温もりに触れた夜、夏海の頬は赤かった。夏海が‘女’の顔をしていた。そして、夏海は泣いた。
「ねー、健太」
「ん?」
「キスする?」
「ん、なんて?」
「やけん、き、す!」
夏海と健太は、商店街を歩いていた。健太の頬が少し赤くなった。そして、健太は、夏海の左手を、握った。
「おまえ、手、ちっせーな」
光が丘商店街は、出口のところに本屋さんがある。夏海は、内容が少しエロい漫画を読んでいた。
「・・・・・えっろ」
「お前、何見よんぞ」
「えろい漫画」
「アホ」
夏海は、ちょい官能的な内容の漫画を立ち読みしていて、健太に頭をチョップされた。夏海は、下をペロッと出した。
「健太」
「ん?」
夕暮れの商店街、夏海は健太と一緒に帰っていた。健太は自動販売機で買った、ブラックコーヒーを飲んでいた。夏海の頬が少し赤くなっていた。
「・・・・・・・」
「何その顔」
「チューしよ」
健太は、コーヒーを少し吹き出した。
「んん?なんて?」
健太はわざと、聞こえていないふりをしていた。でも、内心すごく嬉しかった。
「やけん、キスしよ」
「いいよ」
周りには誰もいなかった。健太は夏海に顔を近づけ、2人は唇を重ねた。すると、健太が舌を入れてきた。夏海は、健太から離れた。
「・・・・けんた?」
「ごめん、無意識・・・・」
健太が前をすたすたと歩き始めた。健太は最近自分が変だと思ってきた。夏海が近くにいると、変な気持ちになってしまう自分がいた。キスの最中に舌を入れるとか、ほんま変人やん、、、とも思った。中学の時、保健体育の性教育で、男女の性について勉強した。そん時はあまり深く考えなかったが、いざ好きな子を前にすると、すごく変ないやらしい気持ちになってしまう。いつか、自分の行動で夏海を傷付けてしまうんやないかと思ってしまうこともあった。すると、夏海が後ろから抱き着いてきた。夏海の胸の感触が背中にあたった。‘あ、、、、’と健太は理性をなくしそうだった。本当に健太は理性をなくしそうだった。
「・・・・・甘えんぼさん。」
「健太・・・・・・・」
夏海は更に強く抱きしめてきた。
「てか、お前、胸大きくなった?」
「何なん、ばか・・・・・・」
「・・・・・・ほんま、俺がどんだけ我慢してんだと思ってんだよ(ボソッ)」
「ん?なんか言った?」
健太は、ドキドキしていた。夏海のふとした時の女の顔、金木犀の香り、胸の感触、ほんと、全てにドキドキしていた。
「夏海」
「ん」
すると、健太がキスをした。今度は、少し大人な、甘いキスだった。夏海の呼吸が乱れた。
「は・・・・っ・・・・・はっ・・・・・・けんた?」
健太の頬が少し赤くなった。
「俺の家来る?」
高校2年の7月、夏海は健太の部屋にいた。
「健太、キスしていい?」
夏海は、部屋で健太にキスをした。そして、2人は深くキスをし合った。健太は、
男の子の顔をしていた。2人は、何度も何度もキスを交わした。すると、健太が
乱暴に夏海に言った。
「好きだ、大好きだ、大好きなんだよ、お前の事、大事にしたい。なんで俺の気持ち分かんねーんだよ。俺がどんだけ我慢してんだと思ってんだよ・・・・・・・」
健太が、夏海を抱きしめた。そして、健太は夏海に力強くキスをした。夏海は、呼吸が上手く出来なかった。健太が夏海の制服の中に手を入れた。健太は、夏海の首筋にキスをした。夏海の身体は細かった。夏海が少し震えていた。
「け・・・・・・ん・・・た」
「好きだよ」
健太と目があった瞬間、健太が舌を入れてきた。そして、健太は夏海の制服の中へと手を伸ばしてきた。
「けんた・・・・・・っっ」
「・・・・・・夏海、ごめん。」
「健太、好きだよ。」
夏海が健太にキスをした。夏海の頬は、赤く染まっていた。
「な・・・なつみ?」
夏海は健太の目をじっと見た。健太の頬は赤く、真剣な表情だった。2人は何回も唇を重ねた。夏海は、健太の鼓動、真剣な目、手を強く握り返してくれるとこ、全てにドキドキしていた。健太は夏海をベッドの上にゆっくりと押し倒した。そして、健太は夏海の両手を握り、キスをした。唇・頬・そして、夏海の華奢な首筋にもキスをした。健太の身体は力強かった。健太が震えながら、夏海の両頬を触った。健太は理性をなくしかけていた。夏海の心臓がバクバクと鳴った。すると、健太が、夏海の太ももあたりをさぐっっていた。
「夏海・・・・好きだ」
再度、健太は夏海にキスをし、夏海の柔らかい、ふっくらとした唇にもキスをした。外では、海のさざ波が、優しい柔らかな音を立てていた。夏海の頬が林檎のように赤く染まっていた。健太は真剣な眼差しで、男の子の顔をしていた。
「好きだ・・・・・っ」
「はっ、はっ・・・・・けんた・・・・っ」
健太がすごく恥ずかしそうだった。健太は、深く深く夏海にキスをした。すると、健太がキスの最中に舌を入れてきた。夏海は、息が出来なかった。健太は、夏海の着ている制服のボタンをはずし、タンクトップの状態にした。健太が夏海の首筋にキスをした。
「あ・・・・・っっ」
夏海は、感じていた。健太の睫毛から汗の雫がぽたっと、夏海の頬に落ちた。健太の頬が本当に赤かった。
「夏海、優しくするから」
「・・・・・うん」
健太は、夏海の下をさぐった。太もも、そして、夏海の足をなぞるように探った。健太は、夏海の唇、お腹、太ももと、全身にキスをしていった。夜の街は静かだった。静かな夜の海のさざ波の音と、ひぐらしの鳴く声が2人を包んだ。6歳の時に2人は出会い、そして高校2年の初夏に恋人になった。そして、2人は‘初めて’を経験した。健太は、夏海のタンクトップを脱がし、そして、夏海の付けている白のブラジャーをはずそうとホックのとこに手を伸ばした時、手が震えた。あまりにも、心臓がバクバクしていた。
「健太」
「ん」
「ゆっくりでいいよ」
夏海が少し笑った。健太はゆっくりとブラジャーのホックを外した。健太は夏海の胸を直視した。そして、健太は夏海に言った。
「夏海、綺麗だ・・・・・・・・」
2人はつよく抱き合った。薄明りの部屋の中で、2人は愛し合った。
「あ・・・・・・っ」
健太は優しかった。夏海は、健太にキスをした。
「健太・・・・・・。」
「ん」
「もう一回キスしよう」
夏海の身体は細かった。外からさざ波が聞こえる。1つの空間に2人だけがいるようだった。健太は、夏海の首筋に埋もれるようにキスをした。夏海は健太の鼓動を強く感じた。健太は、夏海の両手を更に強く握り、そして、再度キスをした。
2人は唇を重ねた。2人は強く強く抱き合った。夏海の身体は柔らかかった。
夏海は感じていた。健太の温もり、力強さ、強く手を握ってくるとこ、全てがたまらなく愛しかった。そして、2人は繋がった。健太は夏海の温もり、夏海は健太の温もりを強く感じていた。
「け・・・・・・んた」
健太は夏海にキスをした。健太の汗が夏海の白い肌に落ちた。夏海の身体の中で、少し痛みが走った。夏海は、その痛さが走った時、健太を更に強く抱きしめた。そして、健太は、切なそうに言った。
「夏海、愛してる」
と言い、夏海の唇にそっとキスをした。夏海は、健太の温もりを感じていた。健太の腕は力強かった。幸せすぎたから。夏海が、ベットのシーツを掴み、そして、後ろからも健太は、夏海の手を握った。2人は愛を感じていた。健太の汗が、ぽたっと、夏海の手に落ちた。繋がれることが本当に幸せだった。健太と繋がれることが本当に幸せすぎたから。だから、‘この夜が、最初で最後’と思った。本当にこの夜が最初で最後だった。2人は抱き合った。深く深く抱き合った。次の日の朝、夏海は目覚めた。横では、健太が眠っていた。ベッドの横のテーブルには、コンドームの箱と、殻の入れ物が置かれていた。昨夜、健太は夏海に何度もキスをし、そして、ぎこちない手つきで、夏海の頬を触り、ゆっくりと2人は繋がった。そして、今朝。朝の海は黄金色に輝いていた。
(健太、愛してる)
―8章「二人の絆」
―あいつに会いたいよ。強くそう思う。
「お・・・・っ」
「ん?」
「おはよ」
夏海は、健太の部屋で制服に着替えていた。夏海の頬は少し赤かった。
「夏海」
「どし・・・・・・」
―チュッ
健太は半分身体を起こして、夏海にキスをした。夏海は不意打ちのキスに、すごくドキドキした。今にも心臓が飛び出そうだった。
「・・・・・・・まだ、健太とのキスに慣れない・・・・・・・・・です」
「・・・・・・・え、ほんまに?夏海・・・・・・・オレも・・・・・・・・」
すると、健太は、夏海にキスをし出した。舌も入れ合う、少し激しいキスをした。すると、健太が話し出した。
「夏海、好きだ~」
健太は、ベットの上で夏海を抱きしめた。夏海は、身体を起こして、白のレースのブラジャーを付けた。すると、視線が感じたので、後ろを向くと、健太が凝視していた。
「健太、変態やん//」
「ええやん、別に・・・・・・///」
健太は、壁の方を向いた。健太の耳は赤かった。
そして2人は、家を出て、朝の海沿いを散歩した。朝の漁港は、本当に綺麗だった。
「夏海」
「ん?」
健太は夏海にキスをした。夏海の頬が少し赤くなった。
「けんた~~~~、いつからそんなに、激しい人になったん?」
「え、いつからやろー、夏海、もっとエロいキスする?」
「えっろ、、、、w」
―ははは
二人は笑い合った。
2人は海沿いを散歩した後、光が丘商店街も散歩した。朝だからなのか、どこのお店も閉まっていた。ゆういつ開いているのが、ローソンだった。夏海と健太は、そこで、コーヒーを2つ買った。2人で飲みながら商店街を歩いた。2人は肩を寄せ合いながら歩いていた。朝の陽ざしが眩しかった。遠くで小鳥の鳴き声が聞こえる。商店街の店のシャッターが上がる音も聞こえる。
「なー、夏海」
「ん?」
「俺、夏海と・・・・・・・・・ずっと一緒にいたい」
夏海は、健太の想いにびっくりした。それは、夏海も一緒だった。
「うん、私も・・・・・・」
―健太と初めての夜を迎えた。
好きな人と触れ合える喜びを初めて知った。
健太、大好きだよ。
大好き。
大好き。
大好き。
健太、ずっと一緒にいようね。
第9章―――「ALS」
「はーは―――・・・・」
「なっちゃん、大丈夫?」
ここ最近、夏海の体調が悪い日々が続いた。夏海は、すぐこけたり、箸が上手くもてなかったり、身体が思うように動かせない日々が続いた。母の真由子の勧めもあって、町の大きな病院で受診したところ、病気が発覚した。
「夏海さんの病名はALS。筋萎縮性側索硬化症という病気です。」
「え・・・・・・・」
夏海も、そして、真由子も言葉を失った。夏海は、まだ、17歳だった。そして、医師の中屋は、言葉を続けた。
「体を動かすのに必要な筋肉が徐々にやせていき、力が弱くなって思うように動かせなくなる病気です。筋力の低下が主な症状ですが、筋萎縮性側索硬化症は筋肉の病気ではなく、筋肉を動かしている脳神経がダメージを受けることで発症します。脳から筋肉に指令が伝わらなくなることで手足や喉、舌の筋肉や呼吸筋が徐々にやせていきます。夏海さんの年齢で発症することも珍しくないです。」
夏海の頭の中は真っ白だった。そして、中屋に聞いた。
「中屋医師。」
「はい」
「私は・・・・・・元気になれますか?」
診察室が一瞬の沈黙に包まれた。そして、中屋は、言葉を発した。
「筋肉がやせると体を上手く動かすことができず、呼吸筋が弱まると呼吸困難に陥り人工呼吸器が必要になります。一般的に症状の進行は速く、人工呼吸器を使用しなければ発症から2~5年で死に至ることが多いといわれていますが、個人差は非常に大きく10年以上かけてゆっくり進行する場合もあります。夏海さん、呼吸器を使用しない選択をするとなると・・・・・・・もって1年・・・・・・」
夏海の目からは赤くなっていた。夏海は、早すぎる選択をしなければならなくなった。早すぎた。17歳だった。そして、中屋は、言葉を続けた。
「ALSは手足の筋力低下から始まることが一般的です。手の筋力が低下するとペットボトルの蓋が開けにくい、髪を洗うときに腕を挙げにくいなどの症状がみられ、足の筋力が低下すると階段の昇り降りが難しくなったり、椅子から立ち上がりにくくなったりします。夏海さん、これからのこと、お母様とも、よく話あっていきましょうね・・・・・・・・・・。」
夏海と真由子は病室を出た。夏海は、真由子に支えてもらいながら、歩行が不安定な状態で歩いた。そして、夏海は、真由子に言った。
「母ちゃん」
「ん?」
「ごめんね・・・・・・・・・。私、長く生きれないかも・・・・・・・。」
真由子は、泣くのを堪えた。夏海は、足を引きずるように歩いていた。夏海は、自分の未来が見えなくなった。
―私は。ALSという病気になった。
呼吸器を付けなければ、もって1年・・・・・・・。
神様、いじわるしないでくださいー。涙
私、もっと、生きたいよ。
したいこと、たくさんあるよ。
死にたくないよ。生きたいよ。死にたくないよ。私は、18ぐらいで死ぬ・・・・・。
苦しい。辛い。
第10章―――「辛い選択」
夏海は、次の日から、学校を休んだ。
〈夏海、大丈夫?〉
健太から、心配のLINEが来た。夏海は、そのLINEに返信するのも億劫だった。夏海は、怖かった。自分の身体がどんどん動かせなくなるのが、怖かった。夏海は、ふらふらになりながら立ち上がり、食卓のテーブルの椅子に座った。そして、傍に置いてあった、1枚のメモ用紙に文字を書いてみた。
―けんた、好き
と書いた。でも、手が思うように動かせずに、ふらふらになりながら書いた。夏海は、これから、どのように自分は生きていけばいいのか、分からなくなった。すると、電話がかかってきた。健太からだった。
―あ、夏海、どしたんお前?
―あ・・・・けん・・・た?
―お前、風邪?夏海、なんか持っていこうか?ゼリーとか
―い・・・いよ、だ・・・いじょ・・・・・う・・・ぶ
―あー、おけおけ
―け・・・・んた
―ん?
夏海は、意識が遠のいていく寸前だった。
―わ・・・・たし
―うん
夏海は、言った。
―け・・・・・ん・・た・・・・・が・・・・す・・・・き
〈健太が好き〉
そして、そこで、夏海は椅子から床に倒れた。夏海の意識はどんどん遠のいていった。
―夏海、おい、夏海・・・・・・!?
―・・・・・・け・・・・ん・・・た
そこで、夏海の意識が途切れた。気づいたら、夏海は、病院の病室のベットの上にいた。
「なっちゃん・・・・・・・・」
「か・・・・あ・・・・ち・・・・・・ゃ・・・ん」
夏海は、ALSの症状が、ますます進んでいた。その後、中屋医師が来た。
「夏海さん、運動、コミュニケーション、嚥下、呼吸の4つの障害のうち、最初にあらわれる症状は人によって異なりますが、最初の症状がどれであっても、症状が進むとともに、これら4つの症状がすべてあらわれるようになります。患者さんによって病気の進行の速さは違いますが、運動障害が最初にあらわれる患者さんの場合、次第に手足がやせていき、歩いたり動いたりすることが困難になります。夏海さんは、運動障害が出ています。さらに症状が進むと、食べ物を飲み込むこと、ことばを発することが困難になります。顔の筋肉の力が弱くなってくると、よだれが出たりします。食べ物を飲み込みにくくなったら、チューブを通して栄養をとる場合もあります。 次第に全身の筋肉の力が弱くなり、自力では起き上がれなくなります。しかし、意識や五感は最後まで正常で、知能の働きも変わりません。」
夏海の目からは涙が溢れてきた。そして、夏海は1枚の紙に書いた。
―せんせい、こきゅうきはつけません
医師の中屋、そして、真由子は驚きを隠せなかった。そして、夏海は、もう1枚、紙に書いた。
―けんたとけっこんしたい
夏海は、あと、1年しか生きられない。真由子は、病室の外に出て、泣いた。外は晴れていた。
第11章―――「小さい頃の約束」
―お前、名前は?
―かわむらなつみ
―へー、ええ名前やん。なつみ、なつみ、なつみ。よし、覚えた。よろしくな。なつみ。
―あの、名前は?
―けんた。やまむらけんた。
―けんた、けんた、けんた。なつみも、おぼえた。
2人の出会いは、光が丘海岸の花壇だった。夏の暑い日、2人は、出会った。
―なつみ
―ん?
―ええ笑顔やな。よろしくな。
2人は手を握り合った。そして、そこで、夏海は目が覚めた。夏海は、点滴に繋がれていた。夏海は、病室の外の光が丘海岸を見た。今日は少し、雨の日だった。
「・・・・・・・・・・・」
夏海は、生きている意味が分からなくなっていた。夏海は、ただ、病室の天井を見ることしか出来なかった。
―ぽつん、ぽつん
雨の音色が、夏海の心を少し悲しくさせた。夏海は、もう、このまま死んでもいいと思っていた。すると、ドアのノックが聞こえた。
―入ってもいいですか?
入ってきた人物は、愛だった。
「あ・・・・・・・い・・・・・ちゃ・・・・・・・ん」
「なっちゃん、やほ~」
愛は、ベットの近くの椅子に座った。
「なっちゃん、調子はどう?」
すると、夏海は、紙に書いた
―あんまりかな・・・・・・
すると、愛は、スマホで1枚の写真を見せてくれた。スポーツ大会で、健太がバスケのシュートを決めた時の写真だった。
「健太、シュート決めたよ。ほんで、周りの子たちと、めっちゃ、喜こんどった・・・・・!」
夏海の目が少し赤くなった。夏海は、そのスマホの写真を、じっと見た。
健太に会いたい、と強く思った。夏海は、紙に書いた。
―けんたに、あいたい
愛は、その紙のメッセージを見ると、愛は、夏海の頭をポンポンとした。そして、愛は、言葉を続けた。
「山村さ・・・・・・・・・ずっと、なっちゃんの席ばかり見よんよね・・・・・・・。切なそうな目で、ずっと・・・・・・なっちゃんの方の席を見よる。すごい、なっちゃんに会いたそう・・・・・。」
雨は止むことなく、ポツンポツンと音を立てていた。そして、夜、夏海は、夢を見ていた。
―なつみ
―ん?
夢の中の場所は、光が丘海岸。夏海と健太、お互い高校の夏の制服姿。
そして、健太は、夢の中で言葉を続けた。
「俺、夏海がおらんと、生きていけんかも・・・・・・。夏海って、ほんま、綺麗で、心も優しくて、純粋で、真っすぐで、頑張り屋さんで・・・・・・・俺、前に、夏海が教室で泣きよった時、‘こいつのこと守れるんは俺しかおらん’って強く思ってさー。夏海、俺、夏海が好きだよ。」
夏海は目覚めた時、その夢の中の言葉が、健太の本当の想いのような気がしてならなかった。夏海の目からは、1粒の涙が流れ落ちた。
第12章―――「17歳の誕生日」
ーねー、ママ
―ん?
3歳の誕生日の時、夏海は、母の真由子に聞いた。
―なんで、なつみには、パパがいないんー?
―・・・・・・パパはね、遠くの方にいるんよ。いつか、なっちゃんのことを、迎えに来るよー。🐎
―うれちー♡パパ、むかえにこんかなー?
夏海は、17歳の誕生日の日を迎えた。母の真由子と祖母の夏が病室に来た。真由子が、1本の向日葵を、瓶で飾ってくれた。
「おめでとう・・・・。」
真由子が、笑顔で、そう言ってくれた。祖母の夏も、‘夏海、17歳の誕生日おめでとう’と言ってくれた。夏海は、白い紙に
―ありがとう
と、そう書いた。すると、真由子が、夏海の目を見て、言った。
「なっちゃん、健太!健太が、昼頃、病室に来るよー。♡」
夏海の心臓の鼓動が、とくんとくん、と鳴っていた。夏海は、紙に、
―うれしい、けんた、はやくこんかな
と書いた。夏海も、恋する乙女だった。夏海は、健太が病室に来るのが楽しみだった。昼頃、病室のノックがなった。‘入りまーす’と、声がした。すると、健太と、もう1人、達也が病室に入ってきた。
「夏海・・・・・・・・・・」
すると、夏海が、紙に書いた。
―けんた、あいたかった
健太の頬が少し赤くなった。そして、隣で達也がからかった。
「けんちゃん~会いたかった、ってー♡よかったなー♡」
すると、夏海は、もう1枚、紙に書いた。
―たっつんも、きてくれて、ありがとう
すると、達也は、はにかんだ。
「ええでー(^_-)-☆」
すると、健太が、ベットの上にいる夏海を抱きしめた。
「・・・・誕生日おめでとう。」
その一言だけだったが、夏海の心臓の鼓動が半端なかった。すると、健太は、自分の行動にハッと気が付き、夏海を自分の身体から、そっと離した。すると、達也がからかってきた。
「けんちゃん、そのまま、キスもしちゃえよ♡」
健太は、照れ隠しなのか、口を自分の手で隠した。
「うっせーな////」
健太は、そう言いながら、ショルダーバックから、何かを取りだした。小さな紙の入れ物だった。
「これ、俺と思って、付けてくれたら・・・・・」
夏海は、その紙袋を、ゆっくりと開けた。ハートのネックレスだった。健太は、照れながら話をした。
「俺・・・・・・・お前がおらんと寂しいんだよ。まー、それ、俺と思ってくれたら」
「なっちゃん、けんちゃん、ほんまに寂しそうでさー。弁当の時とか、学校帰りとか、‘なつみがおらんと寂しい’って、めっちゃ、言いよるで♡なっちゃん、愛されてんな♡」
すると、健太は耳まで赤くしながら、言った。
「お前、言わんでええけん///」
すると、夏海は、紙に書いた。
―けんた、なつみのこと、すき?
すると、健太が、顔を赤くして、言った。達也はにやにやしていた。健太は、夏海の耳元で言った。
「・・・・・・・・好きやし、アホ。大好きだよ、夏海・・・・・・・。」
「俺、病室出とくわ♡」
達也は、気を使ってくれたのか、病室を出た。病室には、夏海と健太、2人だけの空間になった。
「・・・・・・・・夏海」
「・・・・ん?」
すると、健太は、夏海にキスをした。不意打ちのキスだった。健太のキスは、優しかった。唇を離した後、健太は一言言った。
「・・・・・・・俺、最近、おかしいわ・・・・・・・///」
そして、健太は、病室を出た。夏海の心臓の鼓動がおさまらなかった。夏海は、自分の頬を触った。頬は熱かった。夏海は、幸せな、17歳の誕生日を迎えた。
―幸せな誕生日。
病室に、健太とたっつんが来た。
健太がハートのネックレスをプレゼントしてくれた。
ほんで、好きって言ってくれた。
キスもしてくれた。
ほんと、今死んでもいいくらい、幸せな誕生日やった・・・・♡
けんた、好き。
大好き。♡ずっと、一緒にいようね・・・・・・・。♡
でも、なつみ、あと1年・・・・・・・涙
第13章―――「好き」
「ごほっ・・・・・・・ごほっ・・・・」
「なっちゃん?」
9月になった。夏海は、食べ物が上手く、呑み込めなくなっていた。夏海は、嚥下障害が出てきていた。夏海は、自分の首あたりを触った。夏海は、辛かった。苦しかった。夏海は、窓の外を見た。光が丘海岸の海は、太陽の光に当たって綺麗だった。夏海は、いつからか、こう思うようになった。
―死んだら海になりたい
17歳。人生あと100年。でも夏海は1年・・・・。夏海は、病院のテーブルの上に置いてある、健太との2ショットを見た。夏海は、思った。自分が死んで、健太が、他の子と付き合って結婚をする。夏海は、その方が、健太も幸せなんやないかと、ここ最近、思うようになっていた。夏海は、ふと、高校1年の夏、健太と付き合う前のことを思い出していた。
―川村
―ん?
―川村の好きな異性のタイプは?
―え、なんでそんなこと聞くん・・・・?
―ええやん//言えって・・・・・・///
―言わん、ばーか
―は?なんでや
―・・・・じゃー、健太の好きなタイプは?
―俺は・・・・・・・好きになった人がタイプ
―え、ほんま?
光が丘海岸で、そんな会話を、健太としていた。そして、お互いの将来のことも話した。
―俺、将来の夢、高校教師。
―へー、ええやん
―夏海は?
―私の夢は
―うん
―普通に暮らすこと
―なんや、それ(笑)
―1つ言うと
―うん
―好きな人のお嫁さん
―・・・・・・ほー、てかお前、好きな人おるん?
―内緒♡
夏海は、高校1年の夏、光が丘海岸で、健太とそんな会話をしたことを思い出した。夏海は、‘本当に幸せやったな’と、強く思った。夏海は、ハートのペンダントを触った。健太といつでも、一緒にいる気がした。夏海は、そのまま眠りについた。
第14章―――「想い出」
―好きだ
―夏海、可愛いな
―ずっと、一緒におりたいわい
―大きくなったら、結婚しよう
夏海は、ここ最近、思い出に浸っていた。夏海は、車いすに乗って、真由子に車いすを押してもらいながら、病院の周辺を散歩していた。
「か・・・・・あ・・・・ちゃ・・・・・・ん」
「ん?どした、なっちゃん?」
「・・・え・・・・・え・・・・・・てん・・・・・き・・・・や・・・・・ね」
17歳。季節は秋。天気は晴れていた。すると、真由子が話し始めた。
「なっちゃん・・・・・・なっちゃんが生まれた時も、こんな天気やったよ。なっちゃんが生まれた時、ほんとうに嬉しかった。」
「・・・・・・・・・・・・」
夏海は、気持ちが苦しかった。自分が死んだあと、母は?と思った。そして、夏海は、病院の花壇に咲いてある秋桜を見た。赤・ピンク・桃色、たくさんの色の秋桜が満開に咲いていた。なぜだろう、夏海は、その時、健太の顔が思い浮かんだ。
―夏海
夏海と呼ぶ健太が愛しい。恋しい。好き。夏海は、どんどん身体が弱っていき、死んでしまうことが怖くてたまらなかった。夏海は、母の真由子の顔を見て、言った。
「か・・・・あ・・・ちゃ・・・・ん」
「ん?」
「こわ・・・・・い」
「ん?どした?」
「し・・・ん・・・で・・・しま・・・・・・・・う・・・・の・・・が・・・こわ・・・・・・い」
真由子はその時、夏海の本当の思いを知ったような気がした。真由子は、車いすに乗っている夏海を抱きしめた。
「・・・・なっちゃん、ごめんね・・・・・・。なっちゃんを丈夫に産んであげれんで・・・・。母ちゃん、ずっと、後悔しとった・・・・・・・。なっちゃん、生まれてきてくれて、ありがとう。母ちゃん、なっちゃんを支えていくけんね・・・・・。」
母の真由子は、声を震わしながら、夏海に言った。夏海は、母の温もりを覚えておこう、そう心に決めた。
―母ちゃんは18で私を産んだ。
母ちゃんからたくさんの愛をもらった。
母ちゃんは強い
母ちゃんは明るい
母ちゃんは、心強い
母ちゃんは優しい
母ちゃん、私を、産んでくれてありがとう。
ALSになってごめんね。
母ちゃん、私、生きるよ。
―そんな真由子にも、過去の辛い出来事を、思い出すこともあった。
第15章―――「和樹」
ある時、真由子が病室で、夏海に和樹の話をした。夕方の時間帯のことだった。
―和樹、好きよ
生きててほしかった。死んでほしくなかった。和樹は、夏海が生まれた数日後に交通事故で、この世を去った。真由子は、18でシングルマザーになり、夏海を今まで育ててきた。真由子は思う、和樹が生きてたら、どんな家庭になってただろう。和樹がこの世にいないことが信じられなかった。大村和樹。和樹。真由子と同い年の男の子で夏海の亡き父親。和樹は、17年前、交通事故でこの世を去った。‘真由子’。真由子と呼んでくれる和樹の声が今でも脳裏に響く。真由子は和樹のことがいつまでも忘れられないでいた。和樹はレコード店の息子だった。会いたいと思っても、もう会えない。真由子は天国にいる和樹を、いつまでも想っていた。ずっとずっと、和樹のことを想っていた。和樹はこの世にいない。天国にいる。真由子は、ゆっくりと、自分の過去を夏海に話し始めた。
「母ちゃん・・・・・他は失ってもいいから、この人と一緒におりたい。そう想ったんは、和樹が初めてやった。」
真由子が和樹と出会ったのは、15年以上前の肌寒い高校1年の4月のことやった。真由子は和樹との日々を忘れたことがなかった。ガラケーの画面は、和樹との2ショットに、真由子はしていた。和樹は、優しい男だった。人からも好かれ、怒らない。本当に優しい男だった。真由子は、15歳の春に、和樹に恋をした。
「真由子、帰ろー」
「帰ろうか~」
真由子は、黒髪のロングで、目が大きくて、華奢で、綺麗な顔をしている。なので、他のクラスの人からも一目置かれていた。でも、真由子は恋はしないと決めていた。それは、生き別れた父親が最低な男だったから。恋なんかしたくないと思っていた。真由子は、生き別れた父親を憎んでいた。そのこともあって、人を好きになることが分からなかった。小さい頃に父親に殴られたあざが今でも残っている。真由子は、母の夏を殴り、蹴り、暴力でストレスを解消しようとしていた父親が本当に憎かった。父親の顔も思い出したくないくらい、父親が憎かった。この日の天気は雨だった。
―ポツン、ポツン
雨は、静かに音を立てていた。そして、真由子は、バス停で運命の出会いをした。真由子は、途中の道で里沙と別れ、バス停へと向かった。真由子は、バス停に着いた。すると、背の高い男の子が隣にいた。同じ高校の人だろうか。その男が、後に恋人となる、大村和樹だった
「雨、やまんかなー(ボソッ)」
真由子は、そう呟いた。すると、和樹は、真由子の顔を見た。真由子も和樹の顔を見た。
「あの・・・・・・・川村、よな・・・・・?美人で有名な川村よな・・・・?」
「なんですか、いきなり(笑)」
「いや・・・・・・・お前、ほんと、綺麗な顔しとるな・・・・・。」
〈初対面の人に、お前・・・・・?〉
夏海は、最初は和樹のことを警戒していた。すると、和樹は話だした。
「真由子・・・・・・かわむら、まゆこ・・・・・・・川村真由子。真由子、真由子、真由子。綺麗な名前やな。ええやん。」
「え、なに?私、自分の名前なんか気にいってないけど」
「なんでそんなに冷たいん~」
「やって、話したことない人やもん。あんた、私と同じ高校やろ?何年生?」
「1年生」
「へー、え?1年???」
すると、和樹は、またも真由子に質問をした。
「何年何組?」
「1年A組」
「え、俺、B組なんやけど(笑)」
「ははははっ(笑)」
すると、和樹は、真由子の少し雨で濡れた髪をそっと触った。
「・・・・・・・風邪ひくなよ」
―どきっ
真由子の心臓の鼓動が鳴り始めた。あまりにも、不意打ちの出来事だった。そして、2人は、名前を言い合った。
「名前は?」
「俺、大村和樹」
「知っとると思うけどー、私、川村真由子」
「和樹」
「真由子」
5月の寒い雨の日。バス停で、真由子と和樹は出会った。
その日の夜、真由子は携帯で、友達の椎名里沙にメールを打っていた。
‘真由子、数学教えて~’
‘嫌よ’
‘は?’
‘嘘よ。里沙さん☆’
‘ありがと♡’
真由子は、今朝のバス停で出会った人、和樹のことが頭から離れなかった。和樹は、本当に、物静かな男の子だった。夏海は、布団の上で、天井を見ながら、和樹の顔を思い出していた。恋は始まっていた。
そして、数日経った頃、真由子は里沙と学校の廊下を歩いていた。
「真由子・・・・」
「真由子」
「どしたん、里沙ちゃん」
「ほんま、あんたのその美貌は誰遺伝?夏おばちゃん?」
「も―、美貌美貌、ほんまうっさいわ~~」
「え、照れとる?」
「里沙ちゃん、うざ(笑)」
「照れた真由子も可愛い」
川村真由子。15歳。容姿端麗。でも勉強は出来ない。特に苦手なのが数学。そして真由子は放課後、里沙と一緒に中間テストに向けての勉強をしていた。真由子は、勉強に全然集中出来なかった。
「真由子」
「どうされました?里沙先生」
「まじ、赤点取っても知らんよ~~。あんた、軽音部の顧問の先生に言われとんやろ?赤点4つ取ったら部活くんな―みたいなこと言われとんやろ?ほんま、ずっ―とぼ―っとして~~。まじ知らんよ」
真由子は、言い返した。
「いいも―んだ」
「も―」
真由子と里沙は言い合いをしていた。すると、男子バスケ部の連中が廊下を歩いていた。ふと、真由子は、廊下を見た。すると、和樹と目があった。
「あ、川村やん~」
「やほー」
真由子は小さく、教室の中から、和樹に手を振った。和樹は少し照れ臭そうにしながら、手を振ってくれた。すると、バスケ部の連中が、和樹をからかった。
「え、お前、いつから川村と知り合いなん?」
「あんな美人と・・・・・・」
「ええなー♡大村♡」
そんな光景を、真由子は微笑ましく見ていた。すると、里沙が、突っ込んできた。
「真由子、いつから彼氏が~♡」
「は?彼氏やないしー//」
「ははは(笑)」
光が丘海岸の海は静かに音を立て、空は夕暮れに染まっていた。
⏰
―6月、真由子は、里沙の部屋で勉強会をしていた。
「雨・・・・・。」
「真由子、雨って気分下がるよね―――。もーっ、嫌になっちゃうう。」
6月、梅雨。真由子は、里沙の部屋に遊びに来ていた。真由子は、ふとため息をついた。
「里沙ちゃん・・・・」
「どした、真由子?」
「いや・・・なんでもない。」
その日の夕方、天気はいつのまにか晴れていた。空には、夕焼け空が一面に広がっていた。真由子は、帰り道にある、レコード屋さんに少し寄った。そして、店の中を見ると、和樹がレコードを聴いていた。真由子は、和樹の凛とした横顔を、じっと見た。すると、和樹が真由子のいる方向を見た。
「あ、川村?」
「・・・・あ・・・こんにちは。大村君」
「タメでいいよ。てか、あんた、なんでここにいんの?ここ、俺ん家だぞ」
「え、大村君の家なん?」
「正確に言えば―、じいちゃんばあちゃんの店=家」
真由子は、和樹の顔をじっと見た。和樹は、大きな猫みたいな鋭い目に、シュッとした顔立ちに、端正な顔立ちをしていた。真由子は思わず言葉に出してしまった。
「大村君、綺麗な横顔しとるね」
「何言ってんだよ。アホかお前は。・・・・川村、お前さ・・・・・まじで綺麗だよな」
「え」
和樹の思わぬ言葉に、思わず胸が高鳴った。真由子は、和樹の顔を、一瞬直視したが、逸らした。
「きも」
真由子は、笑った。すると、和樹が、ぶっきらぼうに言った。
「ほんまに、綺麗だよ」
「大村くん、私、ほんま、ほんまにコンプレックスだらけよ。小さい頃ね・・・・・今は一緒に暮らしとらんけど、お父さんに、‘ブス’とか‘キモイんだよ’とか、死ね’とか、‘ぶつぶつ顔’とか言われてさ・・・・。大村くん、だから、私ほんまに綺麗やないの。」
すると、和樹が、真由子の肩をガシッと掴んだ。
「川村、しんどそうやで」
「あ・・・・ごめんね」
「川村・・・・俺がそんな不安、吹き飛ばしてやる」
真由子の頬は少し赤くなった。至近距離で見ると、和樹の顔立ちは、本当に綺麗だった。真由子は、こくんと頷いた。
「ありがとう・・・・。」
真由子は、店の外にある、椅子に座った。足をぶらぶらさせた。和樹が、店の中から出てきた。
「ほらよ」
和樹は、小さいペットボトルのウーロン茶を渡してきた。和樹は、真顔で、真由子の隣に座った。
「あのさ」
「どした?」
「あ・・・嫌やったらいいんやけど、‘真由子’って呼んでもいい?」
真由子の心臓は高鳴った。和樹の頬が少し赤かった。真由子は、和樹の額をチョップした。
「ええよ」
「え、いいん?」
「真由子って呼んでえーよ」
「おけおけ、ほんなら、真由子って、呼ぶわ」
「ふふ(笑)分かった」
この日、空は、茜色だった。2人の時間がいつまでも続くような気がした。それから、2人は、携帯電話でよく話したりもした。夜中の12時になっても、真由子と和樹は、話をした。そして、教室で勉強もしたりした。和樹は数学&科学が得意だった。真由子は、勉強会をするたびに、‘和樹の手って大きいなー’と思いながら、密かにドキドキしていた。そして、高校1年の10月に、和樹は、教室で真由子に告白した。
「好きや、真由子が好きや」
真剣な告白だった。真由子も和樹に‘好きよ’と言った。真由子と和樹は思いが通じ合った。そして、高校2年の8月、和樹の部屋で、初体験をした。
「は、は・・・・・・・・・・和樹・・・・・・っ」
和樹は、真由子の両手を握り、そして、明かりがあまり灯っていない、薄暗い部屋で、2人は身体を重ねた。和樹は、真由子を抱きしめた。これが、和樹との、最初で最後の夜だった。真由子の中で痛みが走った。SEXがこんなに痛くて、こんなに幸せなことなんだと、真由子は知らなかった。そして、真由子の中で新しい命が宿ったことは、後の話・・・・・。
―👪
「・・・・はあ・・はあ」
「真由子、大丈夫?」
真由子は、高校2年の冬、授業中に体調が悪くなり、そして、トイレで嘔吐することが多くなった。真由子は、和樹になかなか話せだせずにいた。そして、養護教諭の田村亜希子先生に言われた。
「川村さん、あなた妊娠している可能性があるわ。」
真由子の心臓はドクンと鳴った。そして、その日の朝、学校を休み、、母の夏に産婦人科に連れていかれた。
「真由子、しっかりね」
病院で検査を受けた。すると、そこのクリニックの助産師の七宮さや先生に告げられた。
「真由子さん、あなた妊娠しているわ。お腹の赤ちゃん・・・2か月に入ってる」
真由子は、嬉しいはずだが・・・・涙が出た。和樹の子供を妊娠。しかも17で・・・。
高校2年の冬、和樹と公園で会った。
「和樹」
「どしたんだよ、そんな深刻そうな顔して・・・・」
真由子は、カバンからお腹の赤ちゃんのエコー写真を取り出した。
「ん?」
真由子は額に汗をかいていた。そして、ゆっくりと告げた。
「和樹の子供・・・・・赤ちゃんが出来た・・・・。妊娠2か月。」
すると、和樹は・・・・・初めて真由子の前で泣いた。真由子は、びっくりした。そして、なんて美しい涙なんやと思った。
「真由子」
「ん?」
和樹は、細くて真っ白な真由子の手を握った。そして、泣きながら言った。
「俺さ・・・・・小さい頃親父に暴力受けて・・・・母親は、俺を捨てて、他の男を選んだ・・・。真由子、‘3人’で幸せになろうな」
その日の帰り、真由子は和樹と、夕暮れに染まった光が丘海岸を歩いた。夕暮れに染まる光が丘海岸は本当に綺麗で、そして遠くの方で、鳥が飛んでいた。和樹は、真由子のお腹を触った。
「名前、どうするか・・・・・」
「性別は、まだ分からんらしいんやけどね―」
和樹は、目を細めた後、空を見ながら言った。
「真子、和美、和子、和彦、和也、真美、勝、真紀、真奈、う―んっ、いまいちピンとこね――」
「和樹、お腹の赤ちゃん、もしかしたら、来年の夏に産まれるかも」
和樹は、真由子の肩を組んだ。そして、真由子の顔をジッと見た。
「じゃ、‘夏’に産まれるとして・・・・光が丘海岸の‘海’を取って・・・‘夏海’・・・・」
「え、いいやん」
「早く生まれて来いよ・・・・夏海」
その1年後、真由子は産婦人科で、18という若さで、夏海を産んだ。
「女の子ですよーーー」
時計の時刻は、夜の8時を回っていた。真由子の目からは大粒の涙が流れていた。その3日後、和樹が大型トラックに跳ねられて、この世を去った。飲酒運転のトラックだった。和樹は、18歳だった。真由子は、部屋に引きこもった。
「・・・・・・」
「食べ物置いとくね」
真由子は、夏海を産み、そして和樹を亡くした。最愛の人を亡くした。真由子は、なんで生きているのだろう、なんで自分だけ生きているのだろうと思った。真由子は、部屋から見える、光が丘海岸を見た。あんなに好きだった光が丘海岸が、今は真っ黒に見えた。もう、死んでしまおうかと思った。
―和樹がいないと生きていけない
―私は、死んだ方がええんや。
「和樹・・・・・」
真由子は生きる希望をなくしていた。すると、携帯電話の着信音が鳴った。和樹との思い出の曲、大塚愛の‘恋愛写真’を、着信音にしていた。真由子は、携帯電話を、ベッドに投げつけた。そして、声が枯れるまで、泣いた・・・・・。すると、勉強机から、1枚の写真が床にひらっと落ちた。和樹と馴染の、かき氷屋さんで撮った写真だった。その裏に・・・・・和樹の最期のメッセージが、マジックで書かれていた。
‘真由子、ほんまに好きだ。大好きだ。真由子の笑顔が好きだ。真由子の横顔が好きだ。真由子の髪が好きだ。真由子の、よく笑うとこが好きだ。真由子のドジなとこが好きだ。真由子、お腹の赤ちゃん、絶対お前に似るやろな。馬鹿なとこがな。真由子、3人で幸せに暮らしていこうな。真由子、俺と、出会ってくれてありがとう。愛してる。’
真由子は、そのメッセージを初めて見た。真由子は、本当に幸せだった。こんな思い初めてだった。和樹、会いたい、会いたい。何度そう思っても、叶わない思いだった。真由子の目から大粒の涙が溢れだした。
「・・・・・・・・っ、か・・・・・・ず・・・・・き・・・・・あーーーーっ・・・・・・っっ」
真由子は、過呼吸になりながら泣いた。そして、和樹との永遠の別れとなった。
―
「・・・・・・なっちゃん」
真由子は、夏海の手を握った。
「生まれてきてくれて、ありがとう。」
真由子は、目を赤くし、そして涙を流しながら、夏海に言った。夏海の目からは、1粒の涙が、零れ落ちた。
―生きたい
生きたい
生きたい
死にたくない
私は・・・・・・・・生きたい。
まだまだしたいことたくさんある。生きたい。
生きたい・・・・・・・・・・。
第18章―――「命」
17歳。季節は冬になった。夏海は、身体のあちこちで悲鳴をあげていた。
ご飯を上手く食べれない、そして、手が動かせない。足も動かない。口も上手く
動かせれない。夏海は、そんな自分が嫌でたまらなかった。母の真由子も、毎日のように病室に来てくれていた。夏海は、身体が自由に動かすことが出来ずに、イライラしていた。
「か・・・・あ・・・・ちゃ・・・ん」
「ん?」
夏海は、母に当たってしまった。昼頃のことだった。
「も・・・・・・・・う・・・・・こな・・・・・いで」
「え、なんで?」
真由子は、驚きを隠せなかった。そして、夏海は、机の上に置いてある、写真盾、ものを、床になげつけた。
「・・・・・・・わかった、ゆっくり休み。」
真由子は、動揺を隠せず、床に散乱している、写真盾と物を、机の上に置き、病室を後にした。
「・・・・・・・・うっ・・・う」
夏海は、ただ1人、病室で泣いていた。その2時間後、1人の来訪者が病室の中に入ってきた。
「失礼します」
夏海は、見たことのない人物だった。その人物は、髪の毛が短く、目がぱっちりで、小柄で華奢な方で、オレンジ色の服に黒のスカートに、ブーツを履いていた。夏海は紙に書いた。
―どなたですか?
すると、その人物は、夏海の耳元で言った。
「椎名里沙(しいなりさ)。夏海ちゃんのママ、真由子の高校の時からの友達よー。」
椎名里沙。真由子の高校の時からの友達。里沙は、ミニ椅子に座った。
「あれ、真由子は?」
「か・・・・・・あ・・・・ちゃ・・・ん・・・・・か・・・・え・・・りま・・・・し・・・た」
「えー、まじ?真由子に会いたかったなー」
夏海は、里沙は本当に綺麗な人だと思った。里沙は、夏海の目を見て、話し始めた。
「夏海ちゃん、赤ちゃんやった頃に、1回会ったかな・・・・・?確か、‘かずき’もおったような・・・・・・。」
「と・・・・・う・・・ちゃ・・・・ん?」
すると、里沙はまたも、ニコニコしながら話し出した。
「そ、和樹。大村和樹。和樹さー、イケメンやったんよ。優しい男でさー、ほんまに、真由子とラブラブで、真由子が学園のマドンナみたいな感じで、和樹は・・・。
真由子って、羨ましいくらい綺麗やーん。ほんと、あの子綺麗やーん。和樹、そんな真由子にぞっこんやったんよー♡‘まゆこ、まゆこ’って、いっつも真由子のこと、そう呼びよったなー♡和樹。」
すると、里沙が表情を変えた。
「でも、高校2年の冬、真由子、お腹に夏海ちゃんがおるって分かった時、真由子と和樹ね・・・・・・・朝一の始発の電車に乗って、東京までいって駆け落ちしたの。」
え?と夏海は思った。
―18年前
和樹と、真由子は、冬の寒い東京行の電車の中で、肩を寄せ合っていた。
「和樹、寒いね」
「そやな・・・・・・、真由子、お腹の赤ん坊は?」
「動っきょる、動っきょる。」
そして、東京駅に着いた。冬の東京は寒かった。真由子と和樹は、少ないお金と、切符を持って、品川駅を歩いていた。2人は、肩を寄せ合って歩いていた。
「・・・・・・真由子、お腹の赤ん坊は?」
「・・・・・あ、動いた」
和樹は、真由子のお腹を触った。お腹の赤ちゃんは、ぽこっと、真由子のお腹を蹴った。真由子はこの時、妊娠3か月。新たな命がいた。
「真由子、東京って広いねー。」
2人は、品川から渋谷まで電車で乗り、夕方の時間帯に、渋谷の街を歩いた。すると、後ろから2人の警察官に声をかけられた。
「ちょっとすみません・・・・・・大村和樹くんと、川村真由子さん?」
「はい・・・・そうです。」
和樹は真由子の手を握った。力強く、握った。そして、2人は、渋谷警察署まで連行された。2人は事情を話し、愛媛の実家へと帰された。
「真由子、なんで、和樹君と駆け落ちしたん~~~~?あんた、アホちゃう?バカ、あほんだら!」
川村家と、大村家。川村家の家に、大村家もいた。和樹は、話しだした。
「夏さん」
「なんや、人の娘、妊娠させておいてなー、お前、なんぞ!」
「母ちゃん、うるさい」
「は?こんな状況で落ち着ける母親がどこにおるんや!」
「・・・・・・・・俺、働きます。ほんで、真由子と結婚したいです。真由子と生きていきたいです。真由子の傍にいたいです。俺、もう、逃げません。真由子と、生きていきます。」
真由子の目が赤くなっていた。夏は、最初は怒りを露わにしていたが、和樹の真剣な思いを聞き、‘それなら’と言い、両家の承諾を得た。夕方の時間帯、2人は、A島の漁港のあたりを歩いた。
「和樹」
「ん?」
「うちも、和樹と生きていきたい。一緒に生きていきたい。」
すると、和樹は、真由子を抱きしめた。
「・・・・・・・・ずっと、一緒や・・・・」
和樹は、真由子の頭をぽん、ぽんとしながら、真由子を抱きしめた。A島の夕日は、本当に綺麗だった。
―♪
「真由子、辛かったみたいやけど、夏海ちゃんは絶対産む!そう言いよった。」
「か・・・・あ・・・・ちゃ・・・・・ん・・・。」
里沙は、夏海の両手を握った。
「夏海ちゃん、彼氏は?」
「・・・・・・・・いま・・・・・す」
夏海は、1枚の紙に書いた。
―やまむらけんたです。
里沙は、目を輝かせた。
「けんたくんかー、どんな男の子?」
夏海は、またも紙に書いた。
―ばすけばかです。アホです。ばかです。でもやさしいです。
すると、里沙は、夏海の頭をぽんぽんとした。
「いいね、そんな男の子が夏海ちゃんの彼氏で、会ってみたいわい。♡」
その後、里沙は、病室を後にした。夏海は、里沙が帰った後、なんとも言えない気持ちに包まれた。椎名里沙、母の友達。里沙さんは不思議な人やん、と夏海は思った。
―里沙さん
不思議な人・・・・。
母ちゃん・・・・・・駆け落ちしたんや・・・・・。
はー。なんとも言えない気持ち・・・・・・・・・・・。
次の日、健太が病室に来た。
「夏海」
「・・・・・ん?」
「なんか、辛そうやで。なんかあったやろ・・・・・。」
夏海は、1枚の紙に書いた。
―なんで、わかったん?
すると、健太が険しそうな顔をした。
「話してみ・・・・聞くけん。」
健太は、夏海の左手をぎゅっと握った。夏海は、身振り手振り使いながら、話し出した。
「け・・・・・ん・・・・た」
夏海は、上手く言葉が回らなかったので、紙に自分の思いを書くことにした。
―かけおちってしっとる?
健太の顔に?のマークが浮かんだ。すると、健太は話し出した。
「知っとるよ。男女が駆け落ちすることやろ?」
すると夏海は、またも紙に、書き出した。
―かあちゃん、17のときに、とおちゃんと、とうきょうまでかけおちしたらしい・・・・
「え・・・・真由子さんが?」
光が丘海岸の海は、静かだった。外は夕暮れに染まっていた。
「夏海」
「・・・・・・ん?」
「確か・・・・・・真由子さんは夏海を17で妊娠したんよな?・・・・・・・俺が、和樹さんやったら、周囲に反対されたら、駆け落ちする覚悟で、好きな女と一緒になるかもな・・・・・」
「・・・・・・・け・・・・んた・・・・・も?」
夏海は、またも、紙に書いた。
―けんた、なつみがもし、にんしんしたら、いっしょにかけおちしとった?
「・・・あー、俺も、和樹さんの気持ち分るな・・・・・・。」
窓に夕日が差し込んでいた。遠くの方で鴎が飛んでいた。飛行機雲が空に浮かんでいた。すると、健太が夏海の顔をじっと見た。そして、健太は、夏海を抱きしめた。
「あの夜・・・・・・・お前の肌に触れた時、心臓の鼓動が、半端なくてさー・・・・・
お前のこと、すげー好きやと思った。夏海を・・・・・一生大事にしたいと思った。夏海・・・・・・・。」
夏海の目は赤くなっていた。そして、健太は、夏海にキスをした。夏海の唇は柔らかかった。深く、奥深く、キスをした。
―好き、好き、大好き
その想いだけやった。
けんた、あなたと過ごした日々。あなたとしたキス。
一生忘れません。
I love you. けんた。
愛してる。ずっと。
第19章―――「花火」
あれから何分経っただろう。健太はキスを辞めようとしなかった。
「・・・・・・・・はー、俺、ダメや。・・・・・・・夏海」
健太は、再度、またキスをした。夏海の頬が赤かった。健太も、耳まで赤くなっていた。すると、健太は、冷静を取り戻したのか、キスをやめた。
「ごめん、夏海・・・・・・・・・・何度も思い出すんだよ。あの夜のことを・・・・・・。」
「け・・・・・・ん・・・・・た」
「ん?」
夏海は、紙に書いた。
―もういっかい、きすしていいよ
健太の頬が赤かった。そして、2人は、またもキスをした。すると、花火の音がした。部屋の中から見ると、花火が打ち上げられていた。
「・・・・・・あ・・・・・・・き・・・・・れ・・・・い・・・・や・・・・・・・ね」
夏海は、健太と手を握り合った。健太の手は大きかった。そして、温かかった。
「夏海」
「ん?」
「俺・・・・・・・お前がおらんと、生きていけんわ」
―え、なんで?
健太は、ベットの上で夏海を抱きしめた。
「俺、ずっと、夏海を見よった。夏海が笑いよるとこ、授業中寝よるとこ、高橋と、馬鹿みたいに笑いよるとこ、大きい口開けて、楽しそうに歌うところ、好きなものを美味しそうに食べるとこ、頑張り屋さんなとこ・・・・・純粋なとこ、笑顔が可愛いとこ・・・・・俺のことを、好きでいてくれるとこ。夏海、このまま夏海と、どっか違うとこいけたらな・・・・・・・。」
健太の抱きしめる腕の力が更に強くなった。
「け・・・・・ん・・・・た」
―けんた、私もよ
愛媛県、A島。夜の花火が何発も打ち上げられる中、2人はまたも、唇を重ねた。花火の音が、2人の悲しい運命を消してくれているような気がした。夏海の付けているハートのネックレスが、風で少し揺れた。
―けんた、けんた、けんた。
あんなにハッキリ、‘けんた’と言いよったけど、
声があまりでなくなってしまった・・・・・。
けんた、けんた、けんた。
あなたの名前をいつか呼べなくなる日がくると思うと、
私、辛い。苦しい。あなたの名前を、いつまでも、呼んでいたい。
‘けんた’。愛してる。
第20章―――「クリスマス」
季節は12月になった。夏海の症状は更に悪化していた。声も出せなくなってきていた。病室には、愛が来ていた。
「なっちゃん」
「ん?」
「クリスマスさー、ここで皆でパーティーしようかって話になっとってー、どう?」
夏海は、紙に書いた。
―いいよ♡
後日、愛、達也、健太、愛の弟の陸、そして、健太の弟の優太も来ることになった。そして、夏海は、あることを考えていた。健太に向けてラブレターを執筆しようと考えていた。母の真由子にパソコンを持ってきてもらい、病室で、ゆっくり、パソコンのワードでラブレターを執筆していた。
―♡
山村健太様
最近、本当に寒くなりましたね。健太は、どのようにお過ごしでしょうか?病室から光が丘海岸の海を見るたびに、健太と、A島で過ごした日々が蘇ります。あれは5歳の頃、光が丘海岸で健太と初めて話しましたね。ほんと、口の悪い男の子やと思ったわい(笑)健太、でも、そこから健太のたくさんの一面を知って、健太からたくさんのことを教えてもらい、夏海の人生は、日々、充実しておりました。健太と出会って、10年以上経つんやね・・・・・・。健太、健太に初めて抱きしめられた時、あれは、14歳でしたね。私は、心臓が爆発するかと思いました。それぐらい、どんどんかっこよくなっていく健太に、夏海は恋焦がれていました。健太、あなたの横でずっと笑っていたい。ずっと、あなたの横にいたい。健太、こんなにも、人を好きになったのは、あなたが初めてです。健太、愛してる。
―♡
夏海がラブレターを打ち終えたのは、夜の10時頃だった。クリスマスの数日前のことだった。夏海は、なぜだろう。そのラブレターを見ていると、涙が溢れてきた。数か月後には、自分は命を落として、あの世にいると思うと、いたたまれなくなった。夏海は、日々を、一生懸命生きていた。
―夏海
―ん?
―ばーか
―は、あーほ
―なんや(笑)
―それ、こっちのセリフや(笑)
―てか、また、松山市行く?
―え、ええやん~。行こうで。電車代はもちろん、健太のおごりね(笑)
―は、奢るか、ばーか(笑)
―ははは(笑)ま、健太、松山市行こう~~~
こんなくだらない会話が、こんなにも夏海にとって大切なものになると思わなかった・・・・・。
―なー
―ん?
―キスする?
―なんでや///
―キスしようや
―恥ずかしいやん~///
―しよ、ちゅ♡
―健太、甘えんぼさんなんやけーん
―甘えんぼで結構
―ははは(笑)
夏海は、病室の窓から光が丘海岸を見ていた。なぜだろう、涙を止めることが出来なかった。ぽた、ぽた、と、とめどなく、涙が溢れた。
―私は、あと、数か月の命。
この命を、簡単に捨てれない。
精一杯、生きる。
生きる、生きる、生きる。
死にたくない。生きたい。
けんた、私、健太が好きや~~。
大好きや~~~。
でも、私は、あと数か月の命・・・・・・・。
そして、クリスマスパーティー当日の日が来た。
「メリクリ~」
クリスマスパーティーは、夏海にとって、一生の想い出になった。そして、みんなで、集合写真も撮った。夏海の青春の1Pに刻まれた。
第21章―――「龍一くん」
年が明けた。夏海の体は、ますます動かせなくなっていた。夏海は、話すこともほぼできなくなってきていた。
「なっちゃん」
「・・・・・・・ど・・・し・・・た?」
「龍一くん覚えとる?」
「・・・・・・・う・・・・・ん」
篠崎龍一。通称「りゅういちくん」。夏海の同級生で、松山市に住んでいる男の子。
「りゅういちくんが、明日、ここに来てもいい?」
夏海は驚きを隠せなかった。まさかの、龍一がここに来るとは思わなかった。
「・・・・・・・・・・なっちゃん、わけを話すと、母ちゃん、龍一の母の真美と頻繁に連絡取り合いよってね、真美が、なっちゃんの容態をものすごく心配して、ほんで、龍一もそのことを知ったらしくて、ほやけん、明日、篠崎親子、来るよ」
夏海は、なんとも言えない気持ちになっていた。
―夏海ちゃん
―ん?
―俺の事、どう思っとん?
―え、私が、龍一くんのことを?
―そうそう
あれは、14歳の夏のことだった。2人でアイス食べながら海を見ていた時のことだった。
―うちは・・・・
―俺は好きや
―え・・・・・・・
―俺は、夏海ちゃんが好きや
このことは、健太にも話せていなかった。そして、次の日、龍一と、母の真美がお見舞いに来た。
「やほー、夏海ちゃん」
龍一は、坊主頭に、黒のジャケットを着ていた。夏海は、紙に書いた。
―りゅういちくん、げんき?
すると、りゅういちは、夏海の頭をポンとした。
「元気やぞ」
それから、夏海は、龍一と思い出話をした。話の中で、14歳の時の話になった。
「り・・・・・・ゅう・・・・・く・・・・・・ん」
「ん?どした?」
夏海は、紙に書いた。
―14のとき、わたしのことすきやった?
一瞬の沈黙が流れた。そして龍一は、真剣な表情をして言った。
「今もや」
夏海はびっくりした。すると、龍一は言葉を続けた。
「夏海ちゃん・・・・・・・・俺、ずっと・・・・・・・・・」
すると、龍一は、我慢したのか、話すのをやめた。すると、病室のドアのノックが聞こえ、1人の人物が入ってきた。
「夏海―」
すると、健太は、目玉を大きくした。
「え、えーと・・・・・・篠崎、よな?」
「うん、ほやけど」
夏海は健太に話した。
「け・・・・・・・・ん・・・・・た」
「ん?」
すると、龍一が、夏海の付けているネックレスを見た。
「夏海ちゃんの付けとるこれって、誰かからもらったん?」
すると、夏海は、左手の指で、健太の方を指した。
「お前、指さすなよ(笑)」
夏海はふふっと笑顔になって笑った。すると、龍一は、鋭いことを言った。
「あー、もしや・・・・・・・2人付き合っとん?」
健太の頬が少し赤くなった。
「・・・そや、悪いか?///」
すると、龍一は、天然発言をした。
「付き合っとるということはー、2人はキスもしとるってこと?」
夏海の顔が赤くなった。健太も頬を赤くした。
「・・・・・・・・キスした。///」
すると、龍一は、言葉を続けた。
「山村が惚れるんも分かるよ。やって、夏海ちゃん、可愛いもん。優しいし。純粋やし。夏海ちゃん、真っすぐやし、ほんま、分かる。」
龍一は、真顔でそう言った。窓の外は、雪が降っており、光が丘海岸の海も、白く、染まっていた。すると、龍一は、言った。
「山村」
「ん?」
龍一は、健太の耳元で言った。
「幸せにしろよ。こんな綺麗な女、おらん」
そして、龍一は、‘夏海ちゃんバイバイ~’と言い、病室を後にした。病室には、健太と夏海、2人きりになった。そして、健太はミニ椅子に座り、話し出した。
「・・・・・・・手、ちっちぇーな」
健太は、夏海の手を触った。そして、夏海の顔を見て、2人はお互いを見つめあった後、唇を静かに重ねた。真っ白な雪が降る中、2人は静かに唇を重ねた。そして、唇を離した後、健太は、静かにこう、呟いた。
「・・・・・・夏海と家庭作って、子供が生まれて、そんな未来が来たらええな・・・・。」
健太は、夏海をそっと抱きしめた。夏海の命はあと数か月。身体の機能も低下している。いつか呼吸も止まる。夏海は、健太に抱きしめられながら、静かに泣いた。雪は止むことなく、静かに、ひっそりと、降り続けた。
―りゅうくん、野球頑張ってほしいなー
けんた、けんた。生きて。
けんた生きて
生きて
生きて
私が死んでも
生きて。生きて。生きて。
第22章―――「山村夏海」
高校3年の春になった。夏海は、身体があまり自由に動かせなくなっていた。夏海は、ほぼ毎日、ベットの上で過ごしていた。光が丘海岸の近くの木々は桜が咲いていた。夏海は、‘死ぬ’ということに対して恐怖心を抱きながら、毎日を過ごしていた。夏海は、病室から、満開の桜の木を見ていた。そして、病室に、愛と、達也が来た。
「・・・・・や・・・・・・・・ほ」
「なっちゃん、大丈夫・・・・・・・?」
すると、夏海は辛そうな表情をした。すると、愛が手を握った。
「なっちゃん、聞いて。」
「ん?」
「私・・・・・・・有村と付き合ったよ」
夏海は、目を更に大きくした。そして、達也も話した。
「今年の2月に、愛に告白して、付き合うことになった。ほんと、けんちゃんの気持ちがわかるよ。好きな子に告白するって、こんなに緊張するんやって、愛に告白して思ったもん」
「・・・・・・・達也が、‘高橋が好きや。大好きや。幸せにしたい。’って言ってくるけん、それに答えんといけんな、って思って、達也と付き合うことになったよ。」
夏海の顔が緩んでいた。そして、夏海は紙に書いた。
―おめでとう。しあわせに。
愛は少し涙目になった。
「・・・・ありがとう。なっちゃん、なっちゃんも幸せにね・・・・・・」
達也は、愛の背中をさすった。ピンク色の桜の木は、風によって、舞い散った。
光が丘海岸の海は、静かだった。そして、夜、夏海はパソコンのワードに、自分の胸中を打った。
―🌸
私は、ほんと、あと数か月の命やと思う。
ご飯も食べれん
身体も自由に動かせれん
顔の筋肉も動かない
筋力も低下している
不安でしかない。人生前向きに生きようって思っても、ほんま、不安でしかない。
私は、生きてていいいのだろうか。このまま死んでしまった方が楽なのかもしれんと思ったこともあった。前、健太が、17歳の誕生日の時に、ハートのネックレスをプレゼントしてくれた時、‘このまま死んでもいいくらい幸せ’そう思った。
健太と唇を重ねた時、本当に幸せだと感じた。
生きたい
生きたい
そう思っても、私は死んでしまう。
死ぬ運命・・・・・・。私の人生は・・・・・・・・。
でも、私は、日々の人生を、1歩1歩生きたい、そう強く思う。
その日、夏海は眠りについた。
―なつみ
―ん?
夏海は夢を見ていた。夢の中でだが、光が丘海岸で、健太が夏海にキスをしていた。
「・・・・・・愛してる」
そして、夢の中で、再度2人はキスをした。そこで夢は終わった。その日の朝、夏海は、病室に置いてある思い出の写真を見た。高1の文化祭の写真、健太と初めてデートした時の写真。全てが懐かしく、愛おしかった。夏海は、健太と初めてデートした時のことを思い出した。
―けんた、歩くん早いよー
―え、普通に歩きよるけど
―いや、早い早い
―てか、タピオカ飲む?
―健太のおごりね~
―はいはい
健太との初デートは、愛媛県 松山市の、大街道だった。夏海は、その時、健太の手をそっと握った。健太も、握り返した。2人は、少しの間、無言で手を繋ぎながら歩いた。夏海の目からは涙が溢れた。夏海は、涙を流しながら、その写真たちを見ていた。夏海の命は、あと、わずかだった。
第23章―――「17歳、高校3年の6月」
―死にたくない。
そう、強く思ってきた。
死にたくない。
でも、私は、死んでしまう。
あと、数か月の命・・・・・・。
6月になった。夏海は、身体を動かすことも、話すことも出来なくなっていた。夏海は、ほぼ、植物状態になっていた。真由子は、その日病室に来ていた健太に、話した。
「お医者さんが言うには・・・・・・・・あと2~3か月しか生きられないって・・・・・・・」
健太は、なんで?と思った。なんで恋人が、あと2~3か月の命なのか、分からなかった。健太は、病室の中に入った。夏海は、植物状態に陥っていた。
「なつみ・・・・・・・・」
その日、帰り際、健太は有村家に行った。
「達也・・・・・・・夏海、あと、2~3か月の命やって・・・・・・。」
「え、嘘やん・・・・・・・」
達也の部屋で、健太は達也と話をしていた。
「けんちゃん、大丈夫・・・・・・・・・?」
「・・・・・・・・・夏海、死んでほしくないな・・・・・・・俺、ほんま、夏海が好きやもん。
死んでほしくない
死んでほしくない
死んでほしくない・・・・・・。
ずっと、生きててほしい。
今日、夏海の病室行って、夏海が植物状態で、ベットの上におるとこ見て、
自分が、ほんま、情けないと思った・・・・・・。
夏海、生きててほしい。
ずっと、俺の傍にいてほしい。
俺の横で笑っててほしい。
また、‘けんた’って呼んでほしい。
・・・・・・・・・夏海が、好きなんだよ・・・・・・。」
健太は、久しぶりに、泣いていた。達也も、横で泣いていた。17歳の女の子の命が絶とうとしていた。光が丘海岸の海は、静かだった。空は赤色に染まっていた。風は静かに吹いていた。達也は言葉を発した。
「なっちゃん、死んでほしくないな・・・・・・。生きてほしい・・・・・・。」
健太の涙は更に溢れだした。
「・・・・・・・・・夏海。夏海が、好きやのに、何も出来ん自分が嫌や・・・・・・。
夏海が好きや
夏海が好きや
夏海の笑顔がもう1回見たい。もう、辛い・・・・・・・・・・・。」
2人は、何分も泣き続けた。
―夏海、好きや、好きや
大好きや
夏海が植物状態になっとって、俺は、夏海の死を受け入れないといけない
時が来ると思うと、辛くてたまらなかった。
夏海、夏海の笑顔がもう1回見たい。
夏海と、もう1回話がしたい。
夏海に、‘愛してる’と、言いたい。
―?章「2人の愛」
―夏海、好きだ
―けんた、好き
—こんな幸せなことってあっていいんかな?
夏海は、食べることも、話すことも、出来なくなっていた。健太は、学校終わり、夏海のいる、病室に来ていた。健太は、ミニ椅子に座り、植物状態の夏海に、色んな話をした。
「夏海、また、松山市に行きたいな。俺らが初めてデートしたん、松山市の大街道やったよな?あん時、夏海、めっちゃはしゃぎよったよな・・・・・・」
健太は、一言一言、話した。
「夏海、あん時、お洒落しとって、可愛いな―って思いよった。」
健太は、夏海の左手の上に自分の左手を重ねた。
「夏海、また、松山市行こ。てか、ディズニーランドも行こうや。ユニバとかさ。夏海と、これからもたくさんのことがしたいよ・・・・・・・・・・。」
光が丘海岸の海は静かに音を立てていた。健太は、夏海の目を見た。夏海の目からは、1粒の涙が落ちていた。そして、健太は、言葉を続けた。
「夏海、愛してる・・・・・・・・・。いつまでも。ずっと、ずっと、夏海を、愛してる」
夏海の目からは、またも、涙が流れ落ちていた。健太の目も赤かった。そして、健太は言葉を続けた。
「もし、俺らが結婚しとったら、ここの島に住んで、俺が高校教師で、夏海が、パン屋とかで働いて、ほんで、子供は2人で、1人が男の子、もう1人が女の子。そんな未来も来たらええのに・・・・・・・って、ずっと思いよった。ずっと・・・・・・・ずっと・・・・・」
2人の叶わない、未来だった。
―けんた
―ん?
―もう1回キスしよ
―ええよ
—・・・・あはは、歯があたった(笑)
―ははは(笑)
2人は愛し合っていた。死ぬ運命・・・・・・・・・。夏海の死は、間近にせまっていた。
―夏海、夏海、夏海。
生きててほしい。夏海の笑顔をずっと見ていたい。生きててほしい。
生きててほしい。
生きててほしい。
夏海、夏海と色んなとこに行きたい。
夏海・・・・・・。
第24章―――「生きるか死ぬか」
夏になった。夏海の体力は完全に落ちていた。夏海は、病気の後遺症で、あまり話せなくなっていた。手も、自由に動かせなくなっていた。夏海は、病室のベッドの上から、海を見ていた。夏海は、‘死ぬ’恐怖と闘っていた。病気と闘っていた。死が間近に来ていた。怖かった。怖かった。健太は夏海の病室へと来ていた。すると、夏海は、病室の窓の外を見た。健太は、夏海を見た。夏海はやせ細り、焼けて健康的だった肌が、真っ白になっていた。そして、なつみは、健太を見た。
「け・・・・んた」
「ん?」
その時夏海は、健太をじっと見た。夏海は、涙を流した。
「い・・・つま・・・・・で・・・・も・・・あ・・・・・・いし・・・・・・・・て・・・・・・る」
―いつまでも、愛してる
健太は苦しくなった。‘紗希ちゃんと幸せに’健太がそれは、夏海の永遠の別れの言葉でもあるように思えた。大声出して笑っていた夏海、鼻歌歌いながら帰っていた夏海、どんなときも明るく元気だった夏海・・・。健太は何もしてやれない自分に腹が立った。健太は、何も言葉を発することが出来なかった。
その日の夜、夏海は夢を見た。亡き父親の和樹が夏海の夢に出てきた。
「夏海、死ぬな、生きろ。夏海、まだ17歳やろ?ほんま死んだらいかん。お前、まだまだしたいことたくさんあるやろ?夏海、お父さんのお願い・・・・死ぬな・・・。生きろ・・・・・夏海、真由子を1人にするな、夏海、お願いやけん、死ぬな、生きろ」
「お父ちゃん・・・・・・直接、会いたかったな。」
「夏海・・・・・・。」
夢の中で和樹が、夏海の前で俯いた。そして、和樹は夏海を抱きしめた。
「生きたな・・・・・。お父ちゃんと、行こう」
「・・・・・・・・うん。‘お父ちゃん’。お母ちゃんを愛してくれてありがとう。」
2人は、天気が晴れの、外国の映画に出てきそうな、山の中にある、お花畑にいた。夏海は、セーラー服姿のまま、そのお花畑をあるいた。向日葵、ガーネット、百合の花、たくさんの花がお花畑に咲いていた。その中でも、向日葵がひと際大きくさいていた。
「お父ちゃん、見てみて!」
「ん?お、綺麗な向日葵やな」
夏海は、ずいぶん前の話だが、光が丘海岸に咲いている向日葵を、小学生の時に、健太と一緒に見て、笑い合ったことを思い出した。すると、夏海の目から涙が溢れてきた。
「・・・・・え、あれ、なんで私泣いとんやろ・・・・・・。」
すると、和樹がそっと、夏海を抱きしめた。周りには、たくさんの花が咲いており、向日葵も満開に咲いていた。夏海の涙は止まるこはなかった。
「お父ちゃん・・・・。」
「夏海は悪ない。まったく悪ない。もう、苦しまんでええ・・・・・。」
和樹も泣いていた。空は晴れていた。
―次の日の朝、夏海の病状が悪化した。
第25章―――「最期」
空は晴れていた。看護師が朝、夏海の病室に行った。
「川村さん、バイタルはかりますね」
夏海が目を瞑っていた。看護師は、夏海の容態が悪いことに気が付いた。夏海は、呼吸は浅かった。
―
真由子が病室の外で泣いていた。‘なっちゃん、なっちゃん・・・・・・’と何度も泣きながら言っていた。主治医の中屋、そして、看護師4人が病室の中にいた。夏海の心拍数が、120、110、100、90、85と下がってきていた。夏海は呼吸器に繋がれていた。
「意識戻らないです」
「血圧下がってます」
「ALDを」
中屋は、懸命に心臓マッサージをしていた。
「夏海ちゃん、頑張れ」
夏海の心拍数はどんどん下がってきていた。
夏海の意識が戻らない。顔も青ざめていた。
主治医の中屋は、心臓マッサージをしていた。夏海の意識が戻らない。血圧もどんどん下がっていく。夏海が死んでしまう。傍で、祖母の夏と、母親の真由子が血相を悪くして、夏海を見ていた。
「はーはーー・・・・。」
血圧が、80、90、と戻ってきた。すると、健太と愛と、達也が走ってきた。
「夏海は・・・・!?」
健太は、病室の中で、心臓マッサージをされている夏海を見た。夏海の顔は青ざめていた。夏海の脳裏には、健太の顔が浮かんだ。夏海は、力を振り絞って最期に言った。力を振り絞って言った。
「けんた・・・――けんた・・・――」
と言った。力を振り縛って、最愛の人の名前を、夏海は最期、言った。それが、夏海の最期の言葉だった。血圧がそれからどんどん下がり、脈も下がった。そして、夏海は、17歳という若さで病室で息を引き取った。
― 川村夏海 享年17歳
夏海は、静かに息を引き取った。早すぎる死だった。
「午前・・・12時15分・・・」
真由子は、夏海の傍に倒れこんだ。
―お母ちゃん
―このぬいぐるみ、お母ちゃんと思って、いい子にしててね
中屋医師がそう静かに告げた。夏海は天国へと旅立った。亡き父の和樹のいる天国へと旅立った。
「・・・・・・・なっちゃん、なっちゃん―――――――――あ~~~っ・・・・」
真由子が夏海の傍で泣き崩れた。愛が、大粒の涙を流していた。その後ろで、健太は泣かなかった。ただ、夏海の‘死’を受け止めるしかなかった。最愛の人の死を目の前で見てしまった。健太は泣かなかった。泣かなかった。
―お父ちゃん
―夏海、てかお前、真由子に似とるな~
―ふふ
夏海は、温かい日差しが降り注ぐ病室の中で永遠に眠った。あまりにも、早すぎる死だった。外は晴れていた。
第25章―――「想い出」
―けんた
―なつみ
年月は、どんどん流れていく。2人は愛し合っていた。健太は、出会った時から、夏海に恋をしていた。夏海の笑顔、夏海。夏海に恋をしていた。自分の気持ちに嘘付けない。それぐらい、夏海に恋をしていた。夏海とキスした時、本当に幸せな気持ちになった。夏海を抱きしめた時、ずっと一緒にいたい、そう強く思った。夏海が好きだった。我を忘れるくらい、夏海を愛していた。15歳、高校1年生の夏。2人で光が丘海岸の夕焼けを見た時、うっすら気づいていた。健太は自分の気持ちに。夏海に惹かれてることに。夏海の笑った顔を見た時、思わずキスしそうになった。
夏海と触れ合った夜、すごく震えた。好きな人と触れ合える幸せを感じた。夏海、死んでほしくなかった、生きててほしかった。夏海の小さな手を、もう一度握りたい。夏海に触れたい。夏海を抱きしめたい。健太は、心の底から‘川村夏海’を愛していた。
夏海の葬儀は、光が丘海岸の海の近くの葬儀場で行われた。
「なっちゃん・・・」
「早すぎるよ・・・」
「まだ、若いのに」
「ALSやったんやろ・・・」
「これからって時に・・・・・」
健太は、夏海の遺影を見た。高校の入学式の写真だった。遺影の夏海は、笑顔だった。たくさんの花と、スナック菓子と、人形が供えられていた。そして、写真は、夏海と健太の2ショットも置かれていた。健太は、それらを見て、夏海がこの世にいない、その事実が本当に信じられなかった。すると、隣に達也が来た。達也の目も赤かった。
「健ちゃん、大丈夫・・・・?」
「・・・・・・・・・・・ほんと、夏海のこと、好きやな・・・・・・」
健太の目が赤かった。健太は、火葬場までは行けなかった。骨になる夏海を見たくなかった。健太は、光が丘海岸に行った。空は、茜色に染まっていた。健太は、スマホで、生前の夏海の動画を見ていた。
〈美味しい~、健太、このパフェ美味しいねーーーーーー〉
〈健太、私可愛い?着物着たよー〉
〈勉強しなさいよー、健太~~~~~(笑)〉
健太は、涙が溢れてきていた。健太は、泣いた。泣いた。健太は、その動画を見ると、夏海が確かに生きていたんだと、強く思った。そして、亡くなる2週間前の動画を見た。
〈夏海、外晴れとるな~〉
〈あ・・・・・・そ・・・そうやね〉
〈はは。夏海、来年の夏も、光が丘海岸の向日葵見ような〉
〈や・・・・・や・・・くそ・・・・・く・・・や・・・・で〉
最期の動画の夏海は、かすかながら、微笑んでいた。その動画で、健太の涙腺がさらに緩み、泣き止むことは出来なかった。そして、夏海の最期のLINEは、
―生きたい
だった。健太は、‘何も出来なかった’、そんな自分を恨んだ。光が丘海岸の空は、茜色に染まっていた。夏海は17歳という若さで死んだ。
第26章―――「遺書」
健太は、川村家に来ていた。夏海の葬儀から数日経った頃だった。健太は夏海の遺影の前で手を合わせた。そして、1本の向日葵の花を夏海の遺影の傍に置いた。
「健太」
「どした、真由子ちゃん」
真由子は、ふと、1枚の封筒を渡してきた。
「なっちゃんの手紙・・・これ、なっちゃんの遺書」
真由子はそう言うと、リビングを後にし、ベランダに出た。そして、煙草を吸い始めた。真由子の煙草の煙が、中を巻いた。
「・・・・・」
健太はその封筒を見た。持つ手が震えた。封筒には、‘遺書’と書かれていた。夏海の字だった。健太は、手を振るわせながら、封筒を開け、中身を見ると、紙が入っていた。健太はその紙を取り出した。健太は、夏海が生前に書いたであろう、遺書を見た。
ー
健太へ
健太、やほ。健太、私、健太にありがとうの気持ち、何も伝えてなかった気がする・・・・。健太、私、手紙を見る頃には、夏海はあの世にいるよ。健太、私、ALSという病気になり、ほんで、お医者さんに、持って1年って言われちゃった。確かに、上手く物を持てなかったり、身体が重かったり、すぐこけたり、上手くご飯が食べれなかったり・・・・。健太、覚えとる?5歳の頃に私たちは出会ったよね?砂場で1人で遊んびょる時に、1人でおった私に健太が私に話しかけてくれたよね?健太の第一印象は‘口の悪い男の子’でした。でも、健太が私の世界を広げてくれたね。それから、たっつんに出会って、愛ちゃん、ほんで、島の人達に出会って・・・・・。健太、私は、健太に出会ったこと、これっぽちも後悔してない。私を、愛してくれてありがとう。健太と結婚して、幸せな家庭を築きたかったな―。ほんで、子供産んで、笑顔溢れる日々を過ごしたい、夢ありました。健太、日々を大切に生きてね。健太、愛してる。健太、ずっと、ずっと、ありがとう。
夏海
健太の目からは、大粒の涙が溢れていた。健太は、夏海の遺影を見た。遺影の中で夏海は笑っていた。健太は、思う。夏海の声が好きだ、夏海の横顔が好きだ、夏海の髪の毛が好きだ、夏海の細い指が好きだ、夏海の笑った顔が好きだ、夏海が好きだ。外は晴れていた。夕焼けの日差しが、窓に反射した。真由子は、まだ紙煙草を吸っていた。健太は、ただ、泣いていた。いつまでも泣いていた。夏海が、好きだ・・・・・・。大好きだ。でも、夏海は、もう、戻ってこない。夏海は今、空の上にいる。もう会えない。達也は、夏海の遺影を見た。目がぼやける。もう、夏海に会えない、そのことが信じれなかった。健太の目から大粒の涙が溢れだした。
―健太
―健太、遊ぼ~。明日、13時に駅前集合ね。
―最近・・・・・手が動かせない。
―健太・・・・・別れよ。
―健太・・・・私、もう長くないかも。
―ごめんね
―健太、海っていいね。ほんま、綺麗
―健太と、ずっと一緒にいたい。
―健太・・・・ずっと、愛してる。
「な・・・・つっ・・・・・み・・・・・」
健太は涙を止めることが出来なかった。真由子は、そんな健太の姿をじっと見守っていた。真由子も静かに泣いた。健太は、最愛の恋人を亡くした・・・・・。あれは17歳の時のことだった。
―それから21年の月日が流れた。
―18歳
月日が流れ、健太は高校を卒業した。
「健太くん、卒業しないで―」
「頑張れよ―。シュート練習、頑張れよ~~~」
健太は体育館で達也、そして同期の人らとワイワイはしゃいでいた。
「え、たつや、お前高橋と付き合っとん?」
「いいやんか―。ラブラブですよ。愛と」
健太は、達也をいじった。
「愛、、、、(笑)あはははは(笑)」
健太は笑った。達也が口をとがらせた。
「けんちゃんやってさ―。なっちゃんのこと‘夏海’って言いよったやん―。ばーか。」
バスケ部の連中が笑った。健太は光が丘高校を卒業し、東京の大学へ進学した。
―20歳
「けーんた」
「なんだよ、有馬」
渋谷のハチ公前で、有馬と待ち合わせした。健太は、紙煙草の箱とライターを持っていた。
「え、健太、お前」
「てか、おめえも吸っとんやろ?有馬のヘビースモーカ~~~~」
「ははは。相変わらず口悪いとこは変わってねーな」
そして、健太は、愛媛に戻り、高校教師になった。
「川村健太です。松山のA島出身です。担当科目は保健体育です。」
日々は流れていった。
最終章―――「いつまでも、愛してる」
―健太・・・・・・好き・・・。
―健太、私、死んだら海になりたい。
―生まれ変わっても、健太の幼馴染で、ほんで、彼女になりたい
人はいつか死ぬ。あいつと過ごした日々を今でも思い出す。生きててほしかった。死んでほしくなかった。あいつは真夏の晴れた日に、死んだ。でも、思うんだ。夏海、夏海がいつまでも近くで見守ってくれてる気がする。夏海が生きてる気がする。でも、あいつは17で死んだ。海になったんだ。俺は、夏海の死を受け止められずに、日々を生きてきた。
季節は、あっという間に過ぎてゆく。時が過ぎるのは早い。時間はあっという間に過ぎる。健太は37歳。・・・でも夏海は17歳のまま。夏海の笑顔が好きだった。夏海と一緒にいるだけでも幸せだった。
―
あれから21年。あれから21年経った。人口減少で島の人口も減った。健太と夏海がよく行った駄菓子屋の高齢の夫婦もいなくなった。子供の数が減って、小学校2校のうち、1校が閉校した。閉まった店も何件もある。島でゆういつのゲームセンターも閉店した。健太と夏海が高校の学校帰りに寄ったファミマも閉まった。街の商店街、海、公園。商店街とかは、寂れてきていた。街の風景も変わった。だが、健太の淡い切ない恋心は、いつまでも変わらなかった。健太は夏海に夢中だった。夏海のことが好きで好きで大好きで、夏海のことを変に避けてしまう時もあった。でも、自分の気持ちに正直になった時、‘あ―俺は、夏海のことが本気で好きなんだ’と、自分の小さな恋心に気づいてしまった。本気で健太は、夏海を愛していた。16の夏、初めて夏海に触れた夜、あの夜、夏海の涙を見て、‘ほんと好きだ’と強く思った。夏海の白い肌に触れた時、震えた。好きな子と1つになるって、ほんまに幸せなことなんやな、って思った。そして、夏海の病気が発覚した時、夏海は辛いはずやのに笑顔で‘健太、私は大丈夫やけん’と、目を真っ赤にして笑顔でそう言っている夏海を見て、何も助けてあげれない自分を憎んだ時もあった。夏海の病気がどんどん悪化して、夏海の病状が悪い時も、夏海は笑顔だった。そして、夏海が亡くなった時、ただ、夏海の死に顔を、じっと見る事しか出来なかった。健太は、泣くことなく、ただ、夏海の死に顔を、じっと見ていた。健太は、夏海の死をいつまでも引きずっていた。夏海が死んだときのことが走馬灯に蘇り、煙草を吸って忘れようとしたこともあった。
「夏海・・・俺は夏海に恋焦がれていた」
前に進めないでいた。バスケ部の部員たちは泣いていた。夏希は目を真っ赤にして、大粒の涙を流していた。外の日が沈んできていた。あれから何時間経っただろう。健太は一呼吸置いた。
「死んでほしくなかった。もう一度、夏海と話したいよ・・・。」
すると翔が言った。
「夏海さん、絶対幸せだったっすよ。山村監督と一緒に過ごして、絶対幸せだったすよ。」
夏海は17歳で命を落とした。延命治療を決断したが、静かに病室で息を引き取った。健太は夏海のその時の顔も未だに頭に残っている。夏海が好きだった。本気で好きだった。だけど、夏海は天国へ旅立った。健太は夏海のことをバスケ部員たちに話すのは初めてだった。恋をすること、恋をして、そして傷ついたこと、夏海に夢中だったこと。
「病気やのに、それを表に出さんと、最期まで生き抜いた人やったんやな。夏海さん・・」
夏希の顔が涙でぬれていた。体育館は、男子バスケ部だけになっていた。他の部活の部員たちは帰ったのだろう。すると、健太が手を叩きながら話し出した。
「今日は解散!」
男子バスケ部員たちが、体育館を後にした。そして健太は、学校内にある職員室へと戻った。健太は決して忘れなかった。健太は2階から見える大きな夕焼けを見た。健太は、毎日その夕焼けを見るたびに、夏海の笑顔を思い出していた。本当に辛かった。苦しかった。自分だけなんで生きとんやろ、と思ったこともあった。高校時代、夏海が他の男と話している時、すごくモヤモヤした。そして、教室で、泣いている夏海を見て、自分の小さな恋心に気づいてしまった。夏海が他の男を思って泣いている、それが健太は苦しかった。健太は職員室で帰りの準備をし、駐車場に止めてある愛車のレトロな車に乗り、煙草のケースから1本取り出し、マールボロを吸い始めた。マールボロの煙の臭いが鼻を突く。学校の駐車場は丘の下にあり、海がよく見える。健太は、車の中から見える、海を見た。小さな子供と、そのお母さん。小学生。高校生のカップル。それに海を背景にして写真を撮りよるであろう、女の子2人組。健太はその光景を、自分の思い出と重ね合わせながら見ていた。懐かしくなった。健太は、煙草の吸殻を灰皿に置き、そして2本目も吸い始めた。ふとあごの方を触ると、ひげが少し伸びていた。最近心に余裕がなくて、教師をやめようか悩んでいたため、ひげをそることすら、間もならなかった。光が丘海岸の海は相変わらず、何年たっても綺麗だった。聳え立つ夕焼けが、健太の心を癒した。夏海の笑顔を思い出していた。
‘夏海、夕焼け好きやったな~’
みたいなことを思い出しながら、マールボロの煙草をまた吸った。煙草を吸うことで、夏海が死んだ時のことを忘れれる気がした。人の死ってこんなにも辛いんだと思った。最近、母の絵里奈に注意される。‘煙草の吸いすぎ’だと。健太は、今でも夏海が死んだ時のことを走馬灯のように思い出す。思い出したくなかった。夏海はALSという病気になり、この世を去った。健太の目がうっすら赤くなった。そして、学校の自動販売機で買った、缶コーヒーを一口飲んだ。すると、1件のLINEが来た。咲からだった。咲のLINEのトプ画は、息子の翔一の写真だった。笑顔の可愛らしい、男の子だった。
‘健太、今暇?’
‘うん’
‘もしよかったら、飲まない?’
‘は?’
‘駅の近くの居酒屋で待ってる’
咲のLINEは相変わらずあっさりしていた。健太は今?と思いながらも、咲のおる居酒屋へと向かった。健太は、ファミマで1回車を止め、ファミマの中に入り、マールボロの煙草を1箱買った。そのファミマの店員さんは、ギャル要素が満載の、17~18ぐらいの女の子で、すっごい嫌そうな顔をされた。‘俺、そこまで臭いか?’と内心苛立ちながら、店を後にした。そして、健太は新品のマールボロの煙草を1本取り出し、吸い始めた。煙草を吸ってるときは、過去のことを忘れれる気がした。健太にとって、煙草は必須になっていた。そして、健太は、地元の駅の近くの居酒屋へと向かった。健太は、夏海が大好きだった、椎名林檎の同じ夜という曲を車の中で流しながら、車を走らせていた。10何年前、夏海にすすめられた曲だ。椎名林檎の、切ない歌声が、心に染み、そして病室で呼吸器に繋がれていた夏海を思い出していた。夏海は、苦しかっただろう、どんだけしんどかっただろう、そう思うと、なぜか涙が出てきた。椎名林檎の切ない歌声が心に染み、車の中で充満する煙草の臭いが、健太の心を悲しくさせた。健太は、居酒屋近くの駐車場に車を止め、咲のいる居酒屋へと向かった。そこの居酒屋は何年も営業しているところであり、店の外観は寂れていた。店内に入ると、咲が煙草をカウンターの席で吸っていた。
夕方17時。健太は学校帰りに、今は高校教師で、一児の母親になっている、咲に会っていた。
相変わらず咲は美人になっていた。健太と咲は、地元の居酒屋に来ていた。そこは禁煙じゃないところであり、咲はたばこを吸い始めた。健太はびっくりして目を丸くした。
「え、お前煙草吸うん?」
「吸うで」
咲は、煙草を右手に持ち、そして、焼き鳥を食い始めた。
「ここの焼き鳥美味しいよね」
「咲が煙草吸うとか衝撃なんやけど」
「は?」
咲は、煙草の煙を、健太の方に吐いた。
「くっさ―――。お前な――」
「あ―――ここの焼き鳥ほんま美味しい。おっちゃん、お代わり~~~」
咲は、本当に細い体をしている。でも、よく食べる。すると、咲は、健太の顔をじっと見た。咲は煙草の吸殻を灰皿に置き、そして、ラッキーストライクの煙草のケースから1本取り出し、ライターの火をつけて、またも吸い始めた。その姿が、なぜか悲しく見えた。
「健太、あのさ」
「健太・・・・今日夏海ちゃんの誕生日やない?」
「そうだよ。あいつ、生きとったら・・・・37歳。」
「この後、行くんやろ?」
山村健太、37歳。高校教師。バスケ部副顧問。健太は、有村家へと向かった。健太は、一階建ての有村家の玄関のインターフォンを押した。
「あ、おじちゃん?」
「あ、夏希?お父ちゃんおるか?」
有村達也。そして、有村愛。旧姓・高橋愛は、23歳の時に、結婚をし、そして、次の日の年に、愛は長女の夏希を出産した。
「お、けんちゃんやん」
「うっす、達也」
「あ、山村やん~どうぞどうぞ―。今日、なっちゃんの誕生日やし、みんなで祝おう~」
「達也・・・・・お前ビール結構飲んどるやろ~~~。」
達也は健太の肩を組んだ。そして、夏希はその後ろを歩いた。久しぶりの、幼馴染‘4人’での集まりだった。健太は、有村家のリビングに入ったとこにある、高校生の時の幼馴染4人の写真と、夏海単体の写真を見た。写真での夏海は、ものすごく笑顔だった。まるで、太陽に照らされた満開の向日葵のような笑顔だった。健太はダイニングテーブルの椅子に座った。
「高橋」
「ん?」
健太は、カバンの中に入れてある煙草の入れ物を取り出した。
「有村家は煙草禁止?」
すると、愛は険しそうな顔をした。そして、健太の頭をチョップした。
「吸うなら外で吸ってください!」
「は―い(笑)」
「てか、料理出来たんやけど」
愛は、肉サラダに、シューマイに、唐揚げに、餃子にたくさん料理を振舞った。達也は酔っぱらっていた。
「愛、けんちゃんにたくさん食べさせてな~~~」
「OK」
「はは」
すると健太のスマホの着信音が鳴った。有馬からだった。
「ん、有馬?」
「健太~~~、今どこ?」
有馬は酒で酔っぱらっているようだった。
「なんぞお前。かけてくんなよ気持ちワリい」
「おじちゃん口わっる――――――――――」
夏希が横で爆笑していた。達也と愛も笑った。相変わらずの、健太と有馬のやり取りだった。健太は、電話のスピーカーをオンにし、タバコをカバンから取り出した。
「山村、中で吸ったらいかんで~~~」
「わーってるよ」
すると、有馬が大声で話し始めた。
「え、健太タバコ吸ってんの?」
健太が笑い始めた。
「そやけど」
「なんぞ、有馬」
「健太、今から有村家に向かうわ」
「え、くんな―。めんどいやん」
「腹立つな」
愛が、聞こえるように言った。
「有馬さん、今日、なっちゃんの命日」
「愛ちゃんやん。相変わらずたっつんとラブラブか?」
達也が、少しビールを吹き出した。
「ええ。相変わらず」
「はは」
「てか、今日なっちゃんの命日。有馬さん、まさか忘れてませんよね?」
「忘れとるわけね―よ。なっちゃんの37歳の誕生日やろ?」
すると、健太が言った。
「夏海の37歳か―、生きとったらあいつ、何しよったかな?」
「保育士」
「いや、なっちゃん歌手やない?」
「幼稚園の先生」
すると、達也が、健太の肩を組んだ。
「けんちゃんのお嫁さんで、専業主婦」
健太の頬が少し赤くなった。健太は達也の頭をバシッと叩いた。
「うぜえ」
「けんちゃん、でもそうなっとるやろ~~」
「なっちゃんと山村、いつか結婚するやろな―って思いよったで」
健太は両手で顔を隠した。健太の耳が少し赤くなっていた。
「なっちゃんのウエディングドレス姿、絶対綺麗やったろうに」
「なっちゃん、絶対ニコニコしながら協会のバージンロード歩いたと思う」
「間違いない。夏海、ここにいたら・・・。」
健太が目を細めて、夏海の写真を見た。健太は、夏海と結婚して、夏海が子供を授かり、家庭を持っていたらどんな人生を歩んでいたのかと思った。健太は、写真の中で満面の笑みで笑っている夏海が、もうこの世にいないかと思うと、胸が苦しくなった。
愛は、健太が家を出た後、傍に飾ってある、4人での2ショットを見た。中学3年の時の修学旅行の時の写真だ。夏海は笑っていた。夏海だけ歳をとらない。そのことが信じれなかった。
「・・・・・・・・・生きよう」
愛、そして達也。2人とも夏海の死を受け入れるときがきた。
―ガチャ
夏海が死んで、21年という月日が流れた。健太は、夏海のことをいつまでも忘れれないでいた。健太は有村家の玄関のドアを開け、そして、近くの公園へとッ向かった。空は赤く染まっていた。健太は、ベンチに座った。
―は~
健太は思いだしていた。夏海との日々を、夏海と生きた日々を。有村家の家の外で煙草を吸い始めた。マールボロの煙の臭いが鼻に突き刺さった。咲はラッキーストライクを吸いよったな~と思いながら煙草を吸っていた。健太が煙草を吸い始めたのは20歳のころだった。そして、辺り一面に広がる、真っ赤な空を見た。ふと泣きそうになった。
―夏海は、この世にいない
―夏海は17で死んだ
―夏海の、笑顔が好きやった
―夏海に会いたい
夏海がこの世にいない。健太はその事実を受け止めきるには時間がかかった。健太は、煙草を吸い始めた。マールボロの臭いが鼻を突いた。この町の空は、何年経っても、相変わらず色褪せなかった。真っ赤に染まった空が健太の心を悲しくさせた。健太は、ふと、泣きそうになった。健太の心には、ずっと、夏海がいた。そして、健太は夏海が好きだった音楽を流した。夏海が、よく聴いていた曲だ。健太は、煙草を吸った。煙草の煙が宙をまいた。なんで、夏海がこの世にいないのか、受け止めるに時間がかかった。すると
―健太
(え・・・・)
ふと、声のした方を向くと、高校生ぐらいのカップルが並んで帰っていた。彼女の方は、よく話す感じの笑顔溢れる子で、彼氏の方は、多分バスケ部で、そして、バスケ部のショルダーバックを肩にかけていた。
「ばーか」
「お前にばかって言われたくないし」
「そういうとこも、可愛いで」
「もう」
空は、茜色に染まっていた。健太は、またも煙草を吸い始めた。健太は、ふっと、ため息をついた。夏海は、いつまでも皆の心の中で生きてる、そう思った。川村家の玄関には、夏海が生前付けていた、ハートのネックレスが飾られている。健太は、今でも空の上にいる、夏海を想っている。そして、いつまでも、ずっと、健太は夏海を想い続けるだろう。今日も、健太は、夏海と生きた日々を頭の脳裏に焼き付けながら生きていた。空は、綺麗だった。茜色に染まった空は、健太の気持ちを明るくさせた。
―夏海、いつまでも、愛してるー
夏海と、健太。2人の愛は、いつまでも変わらずに、永遠に続くのであった。
—この小説を執筆するにあたって、コメントします。
皆、それぞれの人生を生きています。
この物語は、2021年ごろから考えていました。
私は、愛媛県で生まれ育ちました。
18歳まで愛媛で過ごし、悩んだり苦しんだりしたことも
ありました。でも、幸せだったこともたくさんあります。
皆様、これからの人生で悩むこともたくさんあると思います。
でも、近くには絶対、自分のことを必要としてくれている人、
見てくれている人、自分のことを愛してくれている人がいることを
忘れないでください。最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
皆様、それぞれの人生が輝きますように、と、ここに
記させて頂きます。誠に、ありがとうございました。
令和5年 12月31日 椎名のん