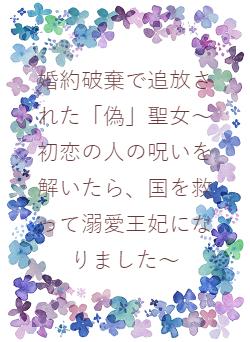偽りの初恋~不遇令嬢は狂愛の“夫”に捕らわれて~
第1話 “貴方”は誰?
私にとってクリフォード様は、たったひとつの希望の光だった。
弱小伯爵家と大侯爵家という身分差を越えて親しくなった、初恋の人。
「今も、そう思ってくれているのか?」
騎士侯爵としての正装に身を包んだクリフォード様が、珍しく自信なさげなに眉を下げる。
いつも堂々としてらっしゃる方が、どうしてそんな顔して私の考えを聞くのだろう。逆に困惑していると、クリフォード様は私の手を取り、白い手袋越しに唇を落とした。
「美しい我が花嫁が自分のことをどう思ってくれているのか、気になるのは夫として当然だ」
花嫁と夫。
私が頬を赤らめると、クリフォード様は愛しさがあふれたように目を細める。
「ウエディングドレス、とても似合っている。女神のように美しい」
柔らかな陽射しが部屋を包んでいる。私はその光のような純白の花嫁衣装を身にまとっていた。
今日、私達は聖堂で結婚式を挙げる。
忙しくなる一日を控えて、今は二人きりの時間だ。
「それはさすがに贔屓目ですわ」
「そうだろうか?」
クリフォード様はキョトンとしてらっしゃるけれど、自分の容姿が地味なことくらい自分が一番よくわかっている。今だって、素敵なドレスに気後れしているほどだ。母様譲りのブロンドは腰まで波打っているけれど、それにしたってクリフォード様の横に並んでいいような女ではない。
クリフォード様は、侯爵家の若き当主として理想的な体格のうえ、一目見たら忘れられないほど美しい顔立ちをしている。少年の頃はもっと柔らかな印象だったけれど、今は精悍さの方が勝っていてそれもまた素敵だ。
(この人が、私の夫だなんて)
式当日を迎えた今ですら、夢なんじゃないかと疑ってしまう。
けれどクリフォード様は、確かに私を妻に望んでくれた。
家族から爪弾きにされ、悲惨な結婚を強いられそうになった私を、幼い頃に育んだ恋心のまま、颯爽と助けに来てくれたのだ。
「どれほど辛く孤独でも、貴方との思い出が私に勇気をくれた。貴方は私にとって希望の光です。……愛しています、クリフォード様」
クリフォード様がこの上なく幸せそうに破顔し、たくましい胸へと私を抱き寄せる。
式まで待てないとばかりに、どちらからともなく唇を重ねた。蜜のように甘いキスだった。
「僕もだ。世界の全てを敵に回してもいいくらい、君をずっと、愛している」
――――こうして不遇な伯爵令嬢フレデリカ・メアリローズは、初恋の人クリフォード・スターリー騎士侯爵の妻となった。
ハッピーエンドを迎えたヒロインはヒーローに永遠の愛を捧げられ、それまでの悲しみを覆い尽くすほどの幸せに包まれて生きていく……はずだった。
■
フレデリカの慎ましくも平穏だった人生は、十二歳の時に実母を亡くしたことで悲劇へと転落した。
政略結婚した両親は元々不仲だったが、実父は喪も明け切らぬうちに後妻を迎えた。継母は父が密かに囲っていた愛人で、既に五歳下の娘もいた。
義母と妹は、長らく日陰者だったという逆恨みから、フレデリカを露骨に嫌って憚らなかっただ。そのため正式に伯爵家の妻と令嬢となって我が侭放題の義母と妹から、そして母娘を溺愛していた実父からさえも、フレデリカは奴隷のような扱いを受けるようになった。
フレデリカが生来素直で優しく、人に尽くすことを厭わない性格であったことも、いじめを助長させる一因となったのかもしれない。いつかきっと家族と和解できるはずだと耐えていたフレデリカだが、それは逆効果だったと言えよう。
そんな暮らしに耐え続けた24歳のある日、フレデリカに突然結婚話が舞い込んだ。
父から言い渡された嫁ぎ先は二十歳上の男爵で、金はあるが素行も容姿も最悪だと、社交界に疎いフレデリカですら噂を耳にするほどだった。
フレデリカには持参金がつけられたが、男爵からはそれを上回って余りあるほどの「贈り物」がなされた。領地や高価な陶器、そして宝石やドレス。
つまりフレデリカは、欲にまみれた家族によって、俗悪な男に「売られた」のだ。
義母や妹にとって自分はモノ同然で、実父からすら愛情の欠片も向けられていなかった。フレデリカは絶望し、死すら考えるようになった。
今までだって何度か亡き母の元へ向かおうと考えたことはあった。その度にフレデリカが思い留まってきたのは、クリフォードへの初恋をずっと胸に宿していたからだ。
(もう一度、あの方に会いたい。クリフォード様を、もう一度だけこの目に映したい)
若くして深刻な病を得た母は、亡くなるまでの一年ほどを実家の領地にある別荘で過ごした。
湖畔の村であるそこは長閑な時間が流れで、フレデリカにとっては弱っていく母を見守る悲しみがある一方で、人生で一番幸福な時を過ごした地だ。
そこで出会ったのが、隣接する領地に住んでいた四つ歳上のクリフォードだった。
彼はスターリー家の跡取り息子で、先祖が騎士として功績を残したため、今も尊敬を込めて“騎士侯爵”と呼ばれている由緒正しい家柄だ。
まだ外歩きのできた母に連れられ挨拶に行ったフレデリカは、幼いながらも失礼がないよう緊張しきりだったが、クリフォードは十代初めとは思えぬほど威厳に満ちた態度と丁寧な振る舞いで、母娘を歓待してくれた。
以来、フレデリカとクリフォードは頻繁に互いの家を行き来し、二人で遊ぶようになる。
時には書庫にこもって読書を、時には花咲く庭でお茶会を、そして時にはクリフォードが手綱を握る馬に二人乗りをして遠出を。
「フレデリカといると時間を忘れてしまうな」
「私もです、クリフォード様」
西に傾いていく夕陽が帰路を促しても、二人はいつも別れがたく肩を寄せあっていた。
「周りは大人ばかりで、同年代とは話したことなんてなかったんだ。……いや、こんなに楽しいのはフレデリカだからだ」
茜色の光を受けて、クリフォードのブラウンの瞳が金色にきらめく。
そのまっすぐな眼差しと見つめ合うと、フレデリカの鼓動は否応なしに高鳴った。
「約束するよ、フレデリカ。僕は大人になったら君を必ず迎えに行く。君とずっと一緒にいられように」
「そんな誓いともとれるお言葉は、将来お迎えする花嫁にこそおっしゃるべきですわ」
「だから、君に言っているんだ」
クリフォードは真剣だった。
フレデリカの心臓がキュウッと痛みを訴える。
どれほど親しくなろうとも、婚姻関係になるには家格が釣り合わない。クリフォードは次期当主。大人になった彼が、幼い日の約束のために愚かな選択をするはずがない。
(私の初恋に望みはない。せめて今だけは、貴方の隣にいさせてください)
「嬉しいです、クリフォード様」
クリフォードの顔が喜色で光り輝く。
その顔をフレデリカは目に焼きつけた。この先どれほど辛いことがあっても、この初恋の人の笑顔を思えばきっと耐えていけると思った。
■
(まさかあの時の約束が現実になるだなんて、思いもしなかったわ)
私室の窓辺に立ち、私は懐かしい日々に思いを馳せていた。
昔、胸弾ませながら通ったクリフォード様のお屋敷は、今は私達夫婦の家となっている。
見渡すのは懐かしき湖畔と平原、そして彼方を囲む丘陵の稜線。あの頃と同じく、夕焼け空が輝いている。
母が亡くなると同時に実家に戻され、以来私は屋敷に閉じ込められているも同然だった。それでも有名貴族の動向は耳に入っててくるもので、クリフォード様がほどなくしてご両親を事故で亡くし、若くしてご当主になられたということ。その際、当主継承についてトラブルがあったということは、私も噂で知っていた。
(クリフォード様も、きっとご苦労なさったのだわ)
私が男爵の元に嫁がされかけたとき、クリフォード様が突然伯爵家にやってきた。
『初恋の人が結婚すると聞いて、居ても立ってもいられず馬を駆ってきた』
家族は皆驚いていたけれど、私が一番、これが現実だなんて到底信じられなかった。
だってまさか、今や侯爵家当主となられたクリフォード様が、儚い口約束を覚えていただなんて。
『もしこの婚姻がフレデリカの意に添ったものであれば、おとなしく引き下がろう。しかしもし、あの悪名高い男爵の元へ無理矢理送られるようならば、花嫁を奪うことにためらいはない』
お義母様はこれを好機と、あの手この手で妹の方をクリフォード様と縁付かせようとしたけれど、クリフォード様は全く靡かず、私を望むことを頑として譲らなかった。
家族からのさまざまな妨害と向けられた悪意は、思い出すだけでも胸が痛む。同時に、クリフォード様と共に障害を乗り越えてついに結婚に至った顛末は、噛み締めるほど幸福に包まれる。
(生きることを諦めなくて、本当によかった)
支えてくれたのはいつだって初恋の人の笑顔。
クリフォード様。私の希望の光。
そんな大事な旦那様は、所属する騎士団の用事で先週から王都に出張していた。帰宅予定日は明後日だが、お出かけになったその日から一日千秋の思いで帰りを待ちわびている。
結婚以来こんなに長い間離れているのは初めてで、夜の独り寝が泣きたくなるほど寂しい。夫婦になったことで、私はなんて欲深くなってしまったのだろう。
(でも、早く帰ってきて、抱き締めてほしい)
クリフォード様のたくましい体と温もりを思い出しながら、両腕で自分を抱く。
その時、部屋の扉を激しくノックする音が聞こえた。
「奥様、大変です!」
ただならぬ様子に慌てて扉を開ける。
クリフォード様と一緒に王都に行っていたはずの従者が肩で息をしながら立っていて、青ざめた顔で彼は早口にまくしたてた。
「旦那様が、王都で暴漢に襲われました……!」
*
夜、散歩に出た帰りが遅いことを案じた従者が探しに行くと、クリフォード様は川の側で倒れているのを発見された。何者かに突然後ろから殴られたのだと、半ば気を失いながらおっしゃったそうだ。
大事をとってしばらく王都で静養してはという進言を退け、クリフォード様はすぐに屋敷へ――私の元に帰ると言い張った。いつになく感情的なクリフォード様に従者達は困惑したらしいが、主の指示に従い、急ぎ屋敷へ馬車を走らせてきたらしい。
数日後の午後、私はクリフォード様の寝室にいた。
彼は帰ってきてから日の大半を眠って過ごしており、私は使用人達が止めるのも聞かずずっと付き添っていた。容態が急変する心配もあったし、目を覚ましたらすぐにその無事を確認したかったからだ。
そして今日、クリフォード様は久しぶりに目を覚ました。
ベッドで上体を起こしているが、頭に巻いたままの包帯と青白い顔が痛々しい。
「起きていて大丈夫ですか?」
私はベッドの傍らの椅子に腰かけ、クリフォード様のお顔を覗き込む。
「辛かったら、すぐ横になってくださいね」
「もう痛みもない。それに君が部屋にいるのに、寝てなんていられないだろう」
「私のせいで無理をなさっているのなら部屋に戻ります」
「それはいけない、ここにいてくれ!」
いつになく強い語気で身を乗り出してくるクリフォード様に目を丸くする。
声を荒げられたのは初めてだ。やはりまだ本調子でなく、いつも冷静なクリフォード様も心細いのだろう。
(心が不安定になるくらい、大変な目に遭われたんだわ)
一報を聞いた時の衝撃と恐怖を思い出し、思わず涙ぐんでしまう。
思えばクリフォード様が帰ってきてから今まで、緊張で精神が張りつめて泣いている余裕すらなかった。今こうして言葉を交わせるようになってやっと、恐怖に震える余裕ができた。
「……無事でよかった。本当に、本当に……貴方が生きていてよかった」
急に泣き出した私にクリフォード様は驚いたようだが、すぐ肩を抱き寄せ慰めてくれた。
「心配をかけたね、フレデリカ」
「クリフォード様が悪いのではありません。……でも、もし貴方に何かあったら、私は今度こそ完全に生きる希望を失ってしまうんです」
貴方という光のない世界では、もう生きていけない。
その果てしない暗闇は、考えるだけで涙があふれてきて止まらなかった。
「僕だってそうだ。君を失うことなんてもう考えられない。……僕の不注意で要らぬ心労をかけた。すまなかった」
目元をぬぐう指先に顔を上げれば、案じる彼の瞳と目があった。気配を感じて目蓋を閉じる。
「……っ」
息を飲む音。
しかし口づけは待てども訪れず、うっすら目を開けると彼は困ったように顔を背けていた。
(まだ怪我の癒えきっていないクリフォード様に、私はなんて恥じらいのないことを!)
恥ずかしさで頬に血がのぼる。妻として自惚れ過ぎな自分を心の中で戒めて、私は居住まいを正した。
「……それより、怪我のせいか、記憶が曖昧になっている気がする」
「そう、なのですね」
一番懸念されていたのは後遺症が残ることだ。幸い、寝起きながら受け答えはハッキリしているが、まだ予断は許されない。
(今度は私がクリフォード様の支えにならなくては。しっかりするのよ、フレデリカ)
「大丈夫ですわ、わからないことがあれば何なりとご質問ください」
「ああ、助かる」
「それに、不安なことがあったらちゃんと頼ってくださいね。私は、貴方の妻なのですから」
「……そうだな。君は、僕だけのものになったんだった」
クリフォード様が安心したように微笑んだので、私もつられて頬を緩める。
「ずっと寝ていらっしゃったから、お腹がすいていますでしょう?」
「ああ、まあ……そうかもしれない」
意識したせいか、クリフォード様のお腹がクゥと小さく鳴った。
彼はバツが悪そうだったが、普段完璧な紳士であるクリフォード様の愛らしい姿が見られて、私はちょっと得した気分になる。
「今、食事を用意させております。その前に小腹を満たしてくださいね。リンゴを剥いておきましたから、さあ、どうぞ」
フォークに刺した半月型のリンゴを、クリフォード様の口元に差し出す。
みずみずしいリンゴは彼の好物なので喜んでもらえると思ったのだが、彼は怪訝な顔でリンゴを凝視している。
「クリフォード様?」
「これは君が手づからナイフで切ったのか? 令嬢がするべきことではないだろう」
「え……?」
私は思わず言葉を失う。
さらに差し出した手を見たクリフォード様が咎めるように眉根を寄せたので、その困惑はさらに深まった。
「どうして手がこんなに荒れているんだ? まるで使用人のようではないか」
「だって、それは……」
(記憶が曖昧とおっしゃったけれど……まさか、こんな大事なことまで忘れてしまったの?)
クリフォード様がおっしゃる通り、私の手は貴族令嬢のものではなく労働者階級のものだ。長年使用人に交じって働いてきたせいでくたびれた自分の手を、私はずっと恥じてきた。
けれど虐げられてきた証である手を見て、クリフォード様は「よく耐えてきた」と恭しく口付けてくれたのだ。
その一言で、私がどれだけ救われたことか。
侯爵妻となった今でもリンゴを自分で切るのだって、働いてきた自分をクリフォード様が認めてくださったから。恥ではなく取り柄なのだと、辛かった過去を許せたから。
私の落胆に気づいたのだろう。クリフォード様は慌てて私の手を両手で包み込む。
「許してくれフレデリカ、僕は失言したらしい。君を傷つけるつもりはなんてなかったんだ」
「いいえ、私の方こそ聞いていたのに取り乱してしまって……ごめんなさい」
そうだ、支えるとは動じないこと。
私は背筋をピンと伸ばし、ニッコリと笑みを作る。クリフォード様が私を安心させてきてくれたように、クリフォード様の不安を和らげられるように。
「この手にまつわる貴方との思い出があります。貴方がどれだけ私を救ってくださったのか、ゆっくりお話しさせてください」
「僕が、君を救った、思い出……」
「聞きながら、リンゴを召し上がってください。ね?」
「……ああ、わかった。いただくとしよう」
(よかった、笑ってくださったわ)
それから私はクリフォード様といろいろな話をした。彼の曖昧になっているという過去を、できる限り語って聞かせた。
二人が再会してからの思い出を振り返り、話しながら彼への想いを再確認もした。
やがてクリフォード様は、「少し疲れたようだ」とおっしゃって、私の手を握ったまま、すうすうと寝息を立て始めた。
気づけばもう日が傾き始めている。久しぶりに二人きりで話せた嬉しさに浮かれて、時間を忘れてしまっていたらしい。
「ゆっくりお休みになってくださいね、クリフォード様」
私は手を握り返し、少し照れながらその長い指先にそっと口づけた。
*
夕食後、サイラスという従者から襲撃犯調査についての報告を受けた。
本来ならクリフォード様御本人へ先にお話しするべきだが、まだ調子が優れないご様子ということで、私が代理で聞くことになったのだ。
「……ということで、人気のない川沿いだったことと夜だったため、目撃者が見つかっておりません」
「そう……。クリフォード様も顔を見ていないとおっしゃられているし、やはり手がかりを探すのは難しそうなのね」
「今のところは。しかし必ず捕まえてみせます」
「お願いします。クリフォード様は今日お目覚めなられました。後遺症もなさそうですけれど、心身ともにショックを受けられたと思うの」
「ええ。……奥様がお傍についていらっしゃることが、クリフォード様にとっては一番心強いことだと思いますよ」
力強く頷いたサイラスは恰幅のよい年長者で、クリフォード様が子供の頃から仕えている腹心的存在でもある。スターリー家に忠誠を誓っている彼に“奥様”として認められるのは、とても嬉しいことだった。
そんな彼が少し表情を曇らせる。
何かを言いあぐねているようで、口が開いては閉じを繰り返している。
「どうか、されましたか?」
「……これはむしろ、奥様にだけお話した方がいいかもしれません」
実は、と彼は切り出した。
「クリフォード様がお出かけになる直前、手紙が届いていたのです」
「手紙?」
それは初耳だ。
「それを読むやいなや、急にクリフォード様は身支度を始めました。私が供を申し出ましたが、一人で行くからとお断りになり、行き先も告げずに出かけられたのです」
「……それは、クリフォード様らしくありませんね」
クリフォード様は周りを心配させるような軽はずみな行動はしない。私とは二人きりで遠乗りに出ることもあるが、その時も行き先はハッキリさせていく。
「その手紙はどなたからのものだったんですか?」
「探しましたが見つかっていません。もしかしたら、クリフォード様ご自身が持ち出されたのかもしれません」
仮に手紙がきっかけで外出したのだとしたら、送り主に会いに行ったと考えるのは自然だ。ならばその誰かの名を従者に告げるだろうし、実際会えたのなら襲撃の場にいたのかもしれない。
なのにクリフォード様は一度も、その手紙のことも“誰か”のことも言及していない。
向かい合って座る従者の疑問が私にも理解できて、二人の間に重たい沈黙が流れる。
明日クリフォード様に聞いてみるべきだろうか。私がそう考えていると、彼がポツリと呟いた。
「……もしや、ルーカス様が呼び出したのでは」
「ルーカス? どなたですか、それは?」
私が身を乗り出すと、彼は一瞬目を丸くした後ハッと息をのんだ。しまった、とでもいわんばかりの反応を見過ごすことはできない。
「お心当たりがあるのですね?」
「いや、あの、てっきりクリフォード様は既にルーカス様のことを奥様にお話になったのかと……すいません、忘れてください」
それは暗に私が、クリフォード様から何か大事なことを秘密にされていると白状したようなものだ。
(ルーカスっていったい誰なの? クリフォード様が慌てて会いに行くような相手って?)
気になって仕方ない。心臓がドクドク音を立てる。
しかし口を滑らせたことを心底悔いているらしい彼を追及するのはさすがに気の毒で、私は飛び出しそうになる質問をグッと喉の奥に押し込んだ。
「わかりました。腹心である貴方の判断は、クリフォード様の考えを一番汲み取っていらっしゃるはずだわ」
私がすんなり引き下がったことが、逆に彼の後ろめたさを刺激したらしい。
しばらく腕を組んで逡巡したのち、神妙な顔で口を開いた。
「……スターリー家ご当主の妻でいらっしゃる以上、知らないままでは障りがあるかもしれません。ひとつだけ、お伝えしておきます」
「はい。……お願いします」
ただならぬ話だと察して、私は膝の上の手をギュッと握りしめる。
「クリフォード様が当主となられる際、家督争いのようなものが起きたことはご存知ですか?」
「いえ……あ、何かトラブルがあったということだけは。クリフォード様は嫡男で一人息子なのにどんなトラブルが、と疑問に思っておりました」
実家で両親が話していたのを耳にした覚えがある。詳細は貴族のスキャンダルが大好きな父ですら知らないようだったから、家督争いという具体的な話はほとんど外に出ていないのではないだろうか。
「実はこの家には、半年前まで……クリフォード様が奥様を助けに行く前まで、クリフォード様とご当主の座を争われた方がいらっしゃったのですよ」
「当主の座を、争った?」
「クリフォード様と同じ立場でありながら、表に出ることを禁じられていた……“ルーカス様”がいらっしゃったのです」
もう一人の当主候補。隠されていた人。
――――ルーカス。
*
深夜の暗闇の中、私はベッドの中でまんじりともできないでいた。
サイラスの教えてくれた「ルーカス」という名が、頭の中をずっとぐるぐる回っている。
そんな大事なことを知らされていなかったというショックだけでなく、そもそもクリフォード様と同じ立場って? という疑問だけでもなく、その名に何故か聞き覚えがあったからだ。
「ルーカス……」
呟いてみると、不思議なほど違和感がない。けれど、どこでその名を知ったのかまるで思い出せない。
代わりによみがえってくるのは、昔クリフォード様と見た夕焼けだ。
空に溶けていくような光を受けて、金色に輝くクリフォード様の瞳がとても綺麗で、そんな約束果たされるはずがないって悲しくて。
(どうしてルーカスという名で、あの日のことを思い出すのかしら)
コンコンッ、と扉を叩く音が響いた。
思考の渦に溺れかけていた私の意識が急に引き戻される。
(こんな夜中に、いったい誰が?)
使用人達も寝静まっているような深夜だ。あまりに不審で身を固くしていると、急かすように再び扉が叩かれる。
私は覚悟を決めてベッドを抜け出し、火をともした燭台片手に扉へと向かった。
「……どなた?」
「僕だ、フレデリカ」
扉の向こうから聞こえた声に、緊張していた体が一気に弛緩する。へなへなと膝から崩れてしまいそうになった。
「どうなさったのですか、クリフォード様?」
薄く開いた扉の隙間から、クリフォード様がするりと中に身を滑り込ませてきた。
私が扉を閉めると、急に抱き締められる。
「きゃっ!」
「君に会いにきた」
取られた手の甲に、冷たい唇が押し当てられた。
唇だけでなく、密着した全身が夜の気配を孕んで冷えている。まるでついさっきまで外にいたかのように。
「クリフォード様、あの、どこかにお出かけになるのですか?」
蝋燭の淡い光に照らされる彼の姿は夜着ではなく、外出用のものだ。それに頭に巻いていたはずの包帯もない。
「クリフォード様、どうなさったのですか? 眠れないのですか?」
「…………」
「クリフォード様?」
(どうして答えてくださらないの?)
微笑みは見慣れたものなのに、蝋燭の炎を映して揺らめくブラウンの――金色に見える瞳に見つめられると、全身を糸で絡めとられたように動けない。何かがおかしい、いろいろとおかしいのに、けれどこの人はクリフォード様で間違いないと、抱き締められた体が言っている。
「フレデリカ。結婚式の君は純白のドレスをまとい、本当に女神のようだった。あの日君は僕の、妻になったんだ」
「え? ええ、そうです。私はクリフォード様の……」
「僕の、妻だ」
否定するかのように言葉をかぶせてきた彼が、そのまま顔を近づけてくる。
そして結婚式の日に聞いた優しい睦言を、耳に囁いた。
「愛しているよフレデリカ。世界の全てを敵に回してもいいくらい、君を愛している」
「……んっ」
しっとりと重なる唇を拒めない。
口づけが深くなればなるほど、違和感に反して体が彼を受け入れる。何度も触れ合い夜を共にした夫に間違いないと、心より体が知っているから。
(でも、違う。この人を私の知っているけれど……怪我をしてベッドで眠っているはずのクリフォード様じゃない!)
「貴方は、誰?」
唇が離された時、彼の腕の中から抜け出せないまま、私は尋ねていた。
彼は愉悦を湛えた金色の目を細める。あの日夕焼けに照らされた瞳と、その眼差しが重なって――――
「僕はフレデリカの――本物の“夫”だ」