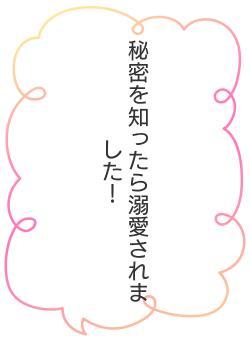捨てられ側妃なので遠慮なく自由にさせていただきます ~妹にご執心な陛下は放っておいて、気ままな皇宮生活を楽しみます~
両親の性格が悪いものだから、出来損ない、いや、存在していないかのように扱われている私の性格が悪くて神経が図太くてもしょうがない。生まれてくる場所を間違えてしまっただけだ。
下を向いて、事なかれ主義で生きていくのも嫌よ。前向きに生きてやるわ!
そう思ってからの私は、ジュリエッタに何を言われようが、あまり気にしなくなった。あまり、というのは、傷つくのではなく、苛立ちを抑えることができなかったから。
「わたしが正妃だってわかりきっているのに、どうして間違えたのかしら」
嫁入り準備を整え、宮殿に向かう馬車の中でジュリエッタはずっとぶつぶつ言っていた。
独り言があまりにも大きいことと「間違えた」という言葉が気になって、無視していられなくなった私は、ジュリエッタに話しかける。
「いつもみたいにお父様にお願いすれば良かったのに」
「……お姉様はまだ何も知らないのよね?」
ジュリエッタは笑みを浮かべて尋ねてきた。
「何の話?」
「いいえ。何でもないわ。わたしのほうが可愛いってことはみんなが知っているのに、どうして最初から正妃に選んでくれなかったのかしら」
決めたのは私じゃない。私が皇帝陛下の正妃だなんて恐れ多い話だけど、選ばれたのなら喜んで務めを果たすわ!
そう意気込んだのに、皇帝陛下は壇上から私とジュリエッタを見るなり言った。
「あ、姉はお前のほうか。あー、うん、やっぱり無理だな」
「……無理?」
謁見の間には、別の馬車でやってきた私の家族だけでなく、宰相などの国の重鎮が集まっている。そんな人たちの前で皇帝陛下であるパクト・ド・レイシス様は意味のわからないことを言い出した。
無理ってどういうこと?
ジュリエッタは私の隣でショックを受けたふりをして、顔を両手で隠しているけれど、指の隙間から見える目は、明らかに笑っている。
こうなることはわかっていた、といったところかしら。
「無理すぎる。お前の顔はオレのタイプじゃないんだよ。地味すぎて顔も見たくない。だから、お前は側妃のひとりにする」
「……はい?」
正妃じゃなくて側妃? そんな簡単に変更できるものなの? しかも顔で? 皇帝だからって勝手すぎるんじゃない? もしかして皇帝陛下って、お兄様と同じタイプだったりするのかしら。
そうだとしたら、この国の行く末が心配だわ。
「間抜けな顔しやがって」
壇上の豪奢な椅子に、すらりとした長い足を組んで座っている皇帝陛下は、年は私よりも四つ年上の二十三歳。金色の髪にシルバーの瞳。切れ長の目に細い唇を持っていて息を呑むくらいに美しい顔立ちだ。
言葉遣いや態度は悪いが決断力があるということで、国民から支持されている。ただ、実物を見てみると、顔の良さに圧倒されて文句が言えないだけのような気がした。それほどまでに外見だけは人を惹きつけるオーラを放っている。
……と、そんなことを考えている場合ではないわね。私に向かって発された間抜けな顔は決して褒め言葉じゃないもの。
私はにこりと微笑んで、皇帝陛下に承諾の意を示すためにカーテシーをする。
「承知いたしました」
「……は?」
「喜んで側妃の座につかせていただきます!」
下を向いて、事なかれ主義で生きていくのも嫌よ。前向きに生きてやるわ!
そう思ってからの私は、ジュリエッタに何を言われようが、あまり気にしなくなった。あまり、というのは、傷つくのではなく、苛立ちを抑えることができなかったから。
「わたしが正妃だってわかりきっているのに、どうして間違えたのかしら」
嫁入り準備を整え、宮殿に向かう馬車の中でジュリエッタはずっとぶつぶつ言っていた。
独り言があまりにも大きいことと「間違えた」という言葉が気になって、無視していられなくなった私は、ジュリエッタに話しかける。
「いつもみたいにお父様にお願いすれば良かったのに」
「……お姉様はまだ何も知らないのよね?」
ジュリエッタは笑みを浮かべて尋ねてきた。
「何の話?」
「いいえ。何でもないわ。わたしのほうが可愛いってことはみんなが知っているのに、どうして最初から正妃に選んでくれなかったのかしら」
決めたのは私じゃない。私が皇帝陛下の正妃だなんて恐れ多い話だけど、選ばれたのなら喜んで務めを果たすわ!
そう意気込んだのに、皇帝陛下は壇上から私とジュリエッタを見るなり言った。
「あ、姉はお前のほうか。あー、うん、やっぱり無理だな」
「……無理?」
謁見の間には、別の馬車でやってきた私の家族だけでなく、宰相などの国の重鎮が集まっている。そんな人たちの前で皇帝陛下であるパクト・ド・レイシス様は意味のわからないことを言い出した。
無理ってどういうこと?
ジュリエッタは私の隣でショックを受けたふりをして、顔を両手で隠しているけれど、指の隙間から見える目は、明らかに笑っている。
こうなることはわかっていた、といったところかしら。
「無理すぎる。お前の顔はオレのタイプじゃないんだよ。地味すぎて顔も見たくない。だから、お前は側妃のひとりにする」
「……はい?」
正妃じゃなくて側妃? そんな簡単に変更できるものなの? しかも顔で? 皇帝だからって勝手すぎるんじゃない? もしかして皇帝陛下って、お兄様と同じタイプだったりするのかしら。
そうだとしたら、この国の行く末が心配だわ。
「間抜けな顔しやがって」
壇上の豪奢な椅子に、すらりとした長い足を組んで座っている皇帝陛下は、年は私よりも四つ年上の二十三歳。金色の髪にシルバーの瞳。切れ長の目に細い唇を持っていて息を呑むくらいに美しい顔立ちだ。
言葉遣いや態度は悪いが決断力があるということで、国民から支持されている。ただ、実物を見てみると、顔の良さに圧倒されて文句が言えないだけのような気がした。それほどまでに外見だけは人を惹きつけるオーラを放っている。
……と、そんなことを考えている場合ではないわね。私に向かって発された間抜けな顔は決して褒め言葉じゃないもの。
私はにこりと微笑んで、皇帝陛下に承諾の意を示すためにカーテシーをする。
「承知いたしました」
「……は?」
「喜んで側妃の座につかせていただきます!」