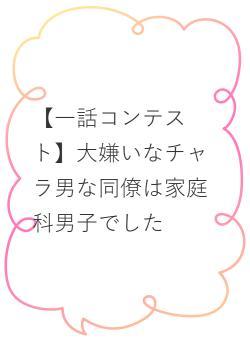その酔いが醒めたなら
好きだと自覚したのは、もういつだったか忘れてしまった。
幼馴染の翔太とは実家も隣同士、幼稚園から大学までもずっと一緒で、彼の存在は私の生活の一部でもあり、いつの間に翔太がいること自体が当たり前になっていた。
それでも私達はただの幼馴染で、それが崩れることなんて、いつか来ることだったのに、私はそれに最後まで気づけないまま、翔太は就職すると実家を離れて一人暮らしを始めた。
私に、何も言うことなく。
そして今、私は目の前の事態に、ただただ驚き言葉を無くしている。
「本社からやってきました。東翔太です。皆さんよろしくお願いします」
本社から一人、営業担当として人手不足のうちに助っ人が来た。
まさかそれが、私の幼馴染だなんて、誰が予想した?
それにうちの本社に勤めていただなんて、私は初耳だ。
呆然としている私に、翔太の視線が向かう。
私を見ても余裕そうな久しぶりのその涼し気な切れ長の瞳に、どきりと鼓動が胸を打つも、なんだか妙に腹が立って、私はすぐに眉を顰めて視線を逸らした。
あぁ、可愛くない。
本当は嬉しくてたまらないのに、会わなくなって寂しかったのは私だけで、翔太は翔太で余裕で楽しくしていたのかと思うと、なんだか無性に腹が立ってしまった。
その日は一日、私にとっては集中できない苛立ちの連続だった。
何しろ、翔太はモテるのだ。
本当は不器用で不愛想な癖に外面だけは良いし、すらりとした高身長で顔も良い。
スーツ姿がまたよく似合っていて、これが嫌いな女子はいないだろう。
その日一日、私は妙な腹立たしさを胸に、淡々と自分の仕事を終えた。
***
「ぷはぁーっもぉーっ!! 腹立つ腹立つ腹立つ―っ!! なんなのあの余裕打っこいた顔!!」
「唯奈ちゃん、飲みすぎ」
薄暗い室内に心地の良いジャズが流れ、ところどころに飾られたランプの灯りがぼんやりと室内を照らすジャズバー。
私の行きつけの店で、仕事帰りに一人、度数の高いお酒ばかりを飲み続けている。
こんな気持ちのまま、一人の家に一人で帰ってもきっとただ悶々と過ごすだけで余計に子のいら立ちが増幅しそうだった。
どこかで、誰かに聞いてもらわなければ、心の持っていく場所がわからなかったのだ。
「だってマスタァ~。私だけ翔太の事気にし続けてたの、なんかすごく腹立つんだもんっ!! 女の子に囲まれて鼻の下伸ばしちゃってさ!! 私とは目が合っても何も話しに来ないくせに、なんなのあいつっ!!」
「おーおー、盛大なやきもちだねー。可愛いねぇ唯奈ちゃん」
「マスター!! わらし、本気れ怒ってんらよ!?」
だんだんとろれつが回らなくなってきた私に、マスターが苦笑いをしてお水を差し出す。
「とりあえずもうお酒はやめとこうか。ほい、水」
「むぅ……ありがと……」
私は素直にそれを受け取ると、ごくごくとそれを流し込んでのどを潤す。
「ほれ、今日はもう帰って休みな。いくら明日から週末とはいえ、終電逃したら帰れなくなっちゃうよ?」
「あ……」
その言葉に我に返った私が店内の時計を見ると、もう終電ぎりぎりの時間。
私が今一人暮らしをしているアパートは電車で3駅のところにあるから、さすがに終電を逃したらまずい。
「やばっ。わらし、帰る!! お金ここ置いとくね!!」
「気を付けて帰るんだよー」
私はマスターに応えるように手を振ると、テーブルの上にお金を置いて急いでバーを後にした。
***
「はぁっ、はぁっ、はぁっ……」
やっばい飲みすぎた。
しかもヒールを履いているから走りにくくてスピードが出ない。
飲んだもの全部がお腹の中でちゃぷんちゃぷんと混ざり合っているかのような感覚を抱えながら、私は走った。
そしてようやく駅が目の前に見えてきた──ところだった……。
ガタンガタンガタンガタン──……。
「行っ……ちゃっ……た……」
目の前で最終電車が発車して、私は思わずその場にペタンと力なく崩れ落ちた。
何てついてないんだ。
今日は踏んだり蹴ったりの最悪な日だ。
何もかもがうまくいかない。これも全部あいつのせいだ。
「馬鹿翔太……」
「────誰が馬鹿だコラ」
つぶやいたそれに返って来た声に驚いて振り返ると、そこには今日一日私の頭の中を支配していた憎らしい顔。
会社で見せていたような人懐こい顔ではなく、むっすりとしたガラの悪い顔。
あぁ、翔太だ。
見慣れたその素の表情に、苛立ちながらもほっとしている自分がいる。
「こんなところで何してんだよ。座り込んで……って、酒くさっ!! 酔っ払いかお前!?」
「うっさいわね!! 誰のせいでこんな時間まで飲んでたと思ってんのよ馬鹿翔太!!」
「はぁ!? なんで俺が怒られんだよ!? ったく……ほれ、立てる?」
ぶつぶつ言いながらも私にその大きく骨張った手を差し出す翔太に、胸がぎゅんと痛くなるのを気にしないようにしながら、私は差し出された手に自分のそれを重ねると、強く引き上げられた。
「ひゃっ!?」
「おっ、と……。大丈夫か?」
強い力で引き揚げられた私は、バランスを崩してすっぽりと翔太のその硬い胸元へとダイブしてしまった。
程よく付いた筋肉とそのぬくもりに、鼓動がうるさい。
ずっと、ここに居たい。
思わずそう思ってしまった。
「っ、ご、ごめっ……!!」
「いや……」
すぐに我に返った私が翔太から身体を離すと、翔太は右手で自分の口元を覆ってからそっぽを向いてしまった。
きっと他の可愛い女の子だったら、もっと違ったのかもしれない。
私は所詮、ただの幼馴染で、家族みたいなもので、でもきっと翔太にとってはそれ以上でもそれ以下でもない。
特別に思っているのは、そう、私だけ。
あの日、翔太が就職して家を出たと母から聞いた時に、積み重ねてきた翔太との絆が、自分が信じてきた自分の立場が間違いであると気づいて、自信なんて一瞬にして崩れてしまったのだから。
「……」
「……」
二人黙り込んでいる間にも人々が行き交い、車が車道を絶え間なく流れる。
こうしていても何も意味がないのに、何を言っていいのかわからずに立ち尽くしていると、頭上から「はぁ」と短くため息が落ちてきた。
「終電逃しちまったな……」
「え? 翔太も?」
まさか同じだと思っていなかった私は思わず顔を上げて翔太と見上げる。
「お前もだったのか。実は、今まで残業しててさ。急いでここまで来たけど目の前で終電逃したわ」
「え、私も。行きつけのバーで飲んでて終電逃して……」
私の言葉に、翔太の眉がぴくりと顰められた。
「行きつけのバー? 一人で? それとも、男と?」
「へ?」
妙に不機嫌そうに尋ねられて、私は目をぱちぱちさせて翔太を見た。
なんでこんなに不機嫌そうになったのだろう。
私が誰と呑んでいようが、翔太には関係のない事なのに、まるで──そう、嫉妬、しているかのように少しばかりの切なさを孕んだ表情に、私の鼓動がまた大きく鳴った。
「ひ、一人だよ!! 一人でバーでやけ酒飲んで、マスターに話聞いてもらってたの!!」
「やけ酒って……何やってんだよ」
呆れたようにそう言う翔太に、私はじっとりと彼を見る。
誰のせいで今日一日モヤモヤイライラしていると思っているのだろう。
人の気も知らないで……。
「いいれしょっ!! 翔太には関係ないんらからっ!!」
「いいれしょ、って……相当酔ってるなお前……。まぁいい。とりあえずそこの公園で座って少しでも酔いを醒ますぞ」
「へ!? ちょ、なっ、翔太!?」
翔太に手を引かれるがままに、私は駅のすぐそばにある小さな公園へと足を進めた。
***
昼間は子どもたちや近くのオフィスの会社員の憩いの場所になっている公園も、夜ともなればしんと静まり誰もいない。
月明かりと小さな街頭だけが照らすベンチに二人並んで座ると、久しぶりの翔太の隣の心地良さに苦しくなる。
当たり前だったこの場所。
当たり前じゃないと気づいたこの場所。
私はまたそこにいる。
求めてやまなかった場所に、思わず目頭が熱くなる。
「んで? 何でやけ酒飲んでた? 何か嫌なことでもあった?」
「それは……えっと……。しょ、翔太こそ、今日は驚いたよ。うちの会社に助っ人に来るとか、本社の人だとか、まさか思ってもみなかったから……」
まさか翔太が原因です、だなんて口が裂けても言えない私は、無理矢理に話を切り替えた。
「ん? あぁ、まぁ。そっちの会社で人手が足りないから誰か助っ人にって言われてさ、唯奈が働いてるのは知ってたから、俺が手を上げたんだよ」
さらっととんでもないことを発言した翔太に、私はぎょっとして翔太を見た。
「ちょ、ちょっと待って!! 私があそこで働いてるの知ってたの!?」
私は翔太が本社にいるなんて知らなかったって言うのに?
いったいどこからそんな情報を入手していたんだろう。
「おばさんに聞いた」
「お母さん……」
そんなこと一言も私には言っていなかったのに、いったいいつの間に……。
ということは、お母さんは本社の方に翔太がいるということを知っていたということだろう。
「何でお母さん、教えてくれなかったんだろう……」
知っていたならば、私のあの時の苛立ちも、虚無感も少しは違っただろうに。
ぼそりとつぶやいた言葉に、翔太が歯切れ悪く口を開いた。
「あー……すまん。それ俺が口止めしてた」
「は!? 翔太が!?」
「あぁ。どうしてもさ、少しでも社会人としてしっかりしてから、唯奈の前に颯爽と現れたかった、っていうか……。まぁ、子どもみたいなプライドなんだけどさ。でも、あのままじゃダメだって気づいたから」
「翔太……?」
いつになく真剣な翔太の表情に、思わず引き込まれそうになる。
すると翔太は、まっすぐに私を見つめながら続けた。
「幼稚園から大学まで、ずっと一緒でさ、唯奈はもう俺の人生の一部になってて、だけど、そのままずるずる幼馴染の安定ポジションでいるのは、何か嫌で……。社会人になって、一人暮らし初めて、しっかり独り立ちできてきたら、唯奈に連絡するつもりだったんだよ。ただ、その間めちゃくちゃ心配だったから、定期的におばさんにリサーチ入れて、唯奈の近況報告聞いてた」
「なっ、何それ!?」
定期的な私の近況報告って、私に黙ってお母さんそんなことしてたの!?
まって、この男はいったい私のどこまでを知っているのだろう。
そう疑問に思った私は、恐る恐る尋ねた。
「あの、近況報告って、どういうことを……?」
「え、あぁ、唯奈が一人暮らし始めた、とか、仕事が忙しそうだとか、恋人の有無とか」
「こいび──っ!?」
私の知らないところでプライバシーが大公開されているという異常事態に、私は頬を引きつらせ言葉を無くした。
誰が身内に伏兵がいるなどと考えるだろうか。
だけどわからないのは翔太がなぜそんなことを私に黙って母に聞いていたのかというところだ。
気になるなら私に連絡の一つでもしてくれたらよかったのに、彼は大学を卒業してから一切連絡をよこさなかった。
それまでは他愛のない事でもよく連絡をし合っていたというのに、まるで”もう自分の世界にお前はいらない”とでも言われているかのようにぱたりと連絡がなくなった。
私も私で、大学を卒業してすぐ何も言わずに家を出て連絡一つよこさない幼馴染に苛立ち、こちらから連絡することを放棄していたから、疎遠になったのを翔太だけに責任を押し付けるのも違うのだろうけれど、それでも何か、何か一つアクションがあったなら、と思ってしまう。
「……何でそんなこと……」
私がつぶやくと、翔太はバツの悪そうに視線を逸らして口を開いた。
「悪い。気持ち悪いよな。だけど、俺がしっかりと社会人になる前にお前に恋人が出来たらって思うと、気が気でなかった。自分のプライドに従って自分で勝手に決めたことなのにさ。我ながら女々しいなって思うわ」
「翔太……?」
何よそれ。
さっきから、それじゃまるで、翔太も私と同じ気持ちなんじゃないかって、錯覚してしまうじゃない。
そう思ってからふと翔太の手元に視線を落とすと、彼の右手薬指の銀の指輪が目に飛び込んできた。
右手の薬指。だいたいの人において、恋人とのおそろいの指輪をつける場所だ。
結婚はしていないけれど、結婚を意識した恋人がいる、という認識の象徴であるそれに、さっきまで沸いていた私の頭がひゅうっと冷たく冷やされていった。
「なんだ、いるんじゃん。恋人」
「え……」
自嘲気味に笑った私を呆然と見つめる翔太に、私はベンチから立ち上がると、彼に背を向けたまま言った。
「恋人がいるのに他の女と二人きりなんて良くないし、私、行くね。漫画喫茶でも探してみる」
「は? え、ちょ、何言って──」
「久々に話せてうれしかった。じゃ、ね。さよなら」
溢れかけたものをぐっと我慢して、少しだけ翔太の方へと振り向いて笑顔でそう言うと、私はまだおぼつかない足取りで歩き始めた。
これで本当にさよならだ。
もういい。もうこのうだうだした思いに蓋をしよう。
二度と開けて出てしまわないように、瓶の中に詰め込んで、上から鎖で覆ってしまおう。
零れそうになる涙を留めるように空を仰いだ、その時だった──。
「行くな──」
「っ……!?」
突然背中から引き寄せられて、そこから熱が広がっていく。
後ろから抱きしめられているという状況を理解した時には、既にがっちりと絡めとられて離れられなくなっていた。
「しょ、翔太? ちょっ、あんた何して──っ」
「お前がどっか行くからだろ。そんな顔で」
「っ……」
気づかれていた。
涙をこらえていた事。
気づかれないように、笑顔でサヨナラをしたつもりだったのに。
「何で……。彼女、いるじゃん。駄目だよ、こんなことしちゃ……」
「は? いねーよそんなん!!」
力いっぱい否定する翔太に、右手の薬指のそれに気づいている私の中で何かが弾けた。
「っ、右手の薬指!! 気づかないと思った? そんなところに指輪してたら普通気づくよ!! 結婚考えてる彼女がいるってこと。なのになんでこんなことするの!? こんな……。同情とか、心配でされても、虚しいだけだよ……!!」
「は……? お前……」
「だからもう放っておい──っ!?」
やけくそになった私の言葉は、最後まで終わることの無いまま、吸い込まれてしまった。
翔太の、少しかさついた唇によって。
永遠とも、一瞬とも思えるようなそれがゆっくりと離されると、私は身体中の力が抜けたようにふらりと脱力し、翔太がそれを支えた。
そして何かに耐えるように眉間に皺を寄せてから、真剣な眼差しで私と見つめた。
「すまん。こんな、いきなりするつもりはなかったんだけど……。でも、その誤解はされたくなかった」
「……ご、かい……?」
少しだけ酔いもさめてきた私は、まわり切らない頭に叱咤しながらやっとというように言葉を放つと、翔太は「はぁ、ったく……」とぼやいてから言った。
「とりあえず、よく見てみろ。これ、お前が高校の修学旅行でシルバーアクセ作りでサイズ間違えて作ったやつだぞ」
「へ……?」
そう言われてまじまじと翔太の指に光る指輪を見て見ると、たしかにこの少し歪なカーブは、私が修学旅行の体験学習でサイズを間違えて作ったシルバーリングだった。
皆が自分の指に合わせて作っている中、横着をしてだいたいの目安で作ってしまった私は、大きすぎるからとたまたま指にぴったりだった翔太に渡したのだ。
あの時はあまり気にせず、貰い手がいて丁度良かったくらいにしか思っていなかったけれど、今冷静に考えると何をしているんだと思う。
「何で……まだ、持ってたの?」
「ん、まぁ。唯奈からもらった指輪だし。これあるとわりと虫よけになるし」
「虫よけって……」
確かにすでに結婚を見越した相手がいると勘違いして身を引く女性は多いだろうけれど。私のように。
それでもこんなの付けてたら彼女なんてできないんじゃないだろうか。
「今までと同じ関係じゃ満足できなかったからってお前に何も言わずにいなくなって、連絡も経ってたのは俺が悪い。ごめんな。不安にさせて。だけど、俺がつけたいと思うのは唯奈からもらった指輪だけだし、恋人の存在が気になるのもお前だけだし、口を口で塞ぐなんてのもお前だけだよ。それに俺、お前じゃなきゃ酔っ払いなんて放っとくよ。めんどくさい」
「めんどくさいって……」
あぁでも翔太はこんな奴だ。
誰にでも優しいと思えば、そうでもない。
当たり障りなく人付き合いはしても、決して踏み込むことは無いし、自分から誰かを心から気にかけることはない。
あるとすれば、それは家族や私みたいな幼馴染、気心の知れた人間に暗いだろう。
深いところでは一線を引いて、掴みどころのない男。それが翔太だ。
あれ? でも今翔太、とんでもないこと──。
「あ、あの、翔太? それって──むぐっ!?」
私が先ほどの言葉について問おうとすると、翔太は今度は自身の大きな手で私の口を覆った。
「あーもー!! 今は言わん!!」
「むぐぐ!?」
与えられそうで与えられない餌を前にお預けを食らっているようで、私は抗議の声を彼の手の中で上げた。
「酔っ払いには言ってやんね」
そう拗ねたように言ってから翔太は私の口からゆっくりと手を離すと、少しだけいたずらっぽく笑って続けた。
「大切な言葉は、酔いがさめてから伝えるよ」
終電を逃したその夜、止まっていたはずの時間が再び動き出す。
月明かりの下、彼のその赤くなった耳が、その思いを伝えてくれているようで、私はつられるようにして目を細めた。
END