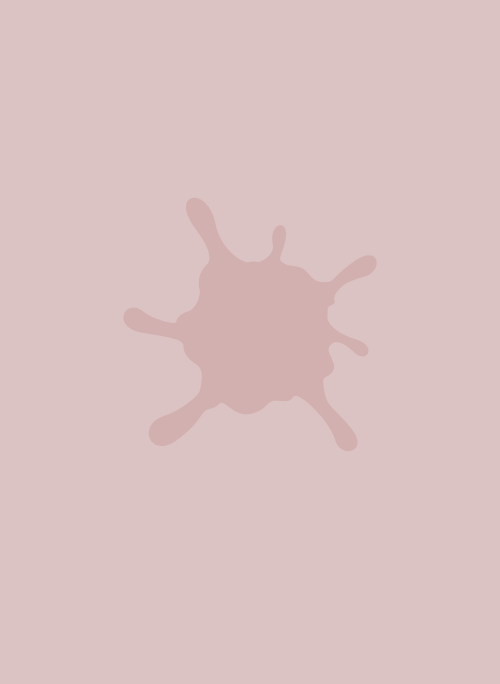レンズの先に
――月曜日の朝――
早坂萌は起きてすぐ、枕元の携帯電話を手に取った。画面を触り、表示された時間に絶句する。
「ヤバイ」
昨夜は塾から帰った時間が二十一時だった。そこから夕食を始末して、浴室に。風呂からでたら化粧水と乳液を顔に染みこませ、ドライヤーで髪を乾かす。
自室で宿題をして、塾の時間に溜まっていたSNSに返信。ベッドに潜り込んだのは、おそらく日をまたいでいただろう。
登校時間に間に合わせるには、超特急で家を出なければいけない。
萌は階段を十六ビートで踏み鳴らして、降りる。洗面所に急ぐと、社会人の姉が場所を独占していた。
「よう、寝坊助。ようやく起きたか」
「お姉ぇ。いつからここに……すぐに化粧は終わる?」
「ファンデを始めた所。これから私の美しさは作りあげられていく」
「あたしは遅刻しそうだから、譲ってよ」
「私も会社に遅れそうだし同条件だ。会社員の場合は査定に響くからお給料が減っちゃう。だから、こっちの方が深刻なの」
さすが私の姉だ。駄目さ加減が自分とそっくりだ、と萌は諦めた。
姉の動きに合わせて、反復横跳びをする。鏡の両端で髪を確認して、櫛でとかす。隙を突いて顔を洗う。
鏡台の引き出しから、先週購入した1dayコンタクトレンズを取り出した。
自室に戻って机上のスタンドミラーを見ながら、レンズをつける。
つけ終わるとすぐに、全長一メートル程度のおじさんが鏡に映った。長髪を揺らしながら、萌のベッド奥にある枕に忍びよっている。
「また出た! この枕フェチ。変態っ。いい加減にさらせ」
萌は叫んだ。開けっ放しの窓から金切り声がとどろき、電線の鳥たちが飛び去っていく。
おじさんを睨みつけると、小男は枕に駆け寄った。枕をひっくり返して、満足げに萌に笑顔を送る。
萌は食卓に置いてあるスープを一気飲みして、食パンにバターを塗りたくった。食べやすいように二つに折ったパンを掴みながら、玄関へ。
居間のテレビ前におかっぱをした子供がいた。赤いちゃんちゃんこを着て、毬を抱きかかえている。子は構って欲しそうに萌を見つめていた。
「学校に行くんだから、今は遊べないよ。そうだ、もうTVのリモコンは隠さないでね」
推しの韓流アイドルのダンスを数分、見損じたことを思い出し、子供に注意する。
晴天の下に庭で洗濯物を干していた母が、それを耳にした。誰もいない部屋に呼びかける娘の姿に「受験ノイローゼって色々な症例があるのね」と独りごちた。
不安感を吹き飛ばすかのように、豪快に布団のシーツを上下に振る。青空に白いシーツが鮮やかにたなびいた。
――先週――
満員電車でスマホを取りだせない萌は、先週末に行った先見堂を思いだしていた。商店街に昔からある眼鏡屋。萌が初めてコンタクトレンズを買ったのは、この店だった。
店奥の機器で、店主の老人に視力検査をしてもらい、細やかな説明を受けた。今では彼は亡くなって、その妻が一人で店を経営している。
「婆ちゃん。だから明日から学校があるし、新しいレンズは二週間後って言われても困るってば」
「仕方ないでしょうが。既製品だったらすぐ渡せるけど、あんたのコンタクトは乱視も入っているし工場で作ってもらうんだ」
老婆はレジ内で舌打ちして、伝票の数字を確認している。客は萌一人。有線放送もかけない店は静かで、二人の言い合いがよく響く。
「レンズの手入れで擦り洗いしていたら破けるなんてある? 不良品掴ませたでしょ」
「ゴリラみたいな腕力で乱暴に扱うからだろが。だいたい一年以上たっているんだから経年劣化だよ。とんでもないクレーマーだ。いたいけなババアをいじめるつもりか」
萌の頭上に大きめの疑問符が浮かぶ。"いたいけな"という形容詞が、この婆ちゃんに繋がらない。"暑苦しい"ペンギンぐらいに、意味不明だ。
「仕方ないねえ」
老婆はぶつぶついいながら、コンタクトの箱の山から数個を引っ張り出した。眼鏡を取り外して、箱の側面をためつすがめつ眺める。そして萌に一つを差し出した。
「ほれ、度数があっている箱。1dayで二週間分あるから。手元とか近いところは見づらいかもしれないけどさ。これでしのぎな」
「やった。ありがとう婆ちゃん、愛してる。店の都合だから勿論サービスだよね」
「馬鹿を言ってんじゃない。完全にあんたが悪いし、定価販売だ。さっさと洗面台で一つ付けてみな」
はいはい、と萌は鏡前の椅子に腰かけた。コンタクトの封を開けて目に取り付ける。途端、萌の体に衝撃が走った。
ぼやけた風景が鮮明に見えて感動した……からではない。店の入口に妙な者が見えたのだ。中背の人型だが人間ではない。真っ白の体で、頭部に髪の毛がない。なにより全身が目だらけだ。
「ば、婆ちゃん。自動扉の脇に変な人がいる」
「なに? 妙なこと言っても、一つ使ったんだから取り替えないよっ」
老婆は、萌が指さす方にずんずん歩く。
「誰もいないよ。この辺かい?」
空中をかき混ぜるように、右手をまわした。
「全身が目だらけの人がいるじゃんっ。あああ、婆ちゃん目つぶししているよ。目人間がめっちゃ怒ってる」
「何言ってんだい。そんな大量の目玉をもつ奴がいたら、眼鏡屋のあたしゃ今頃大金持ちだよ。早く金を払って帰りな」
目人間はレジに向かう老婆へ、両手を揺らしていた。うちわを扇ぐかのようだが、呪いを飛ばしているのではないか……萌は見ないふりをして勘定をすませる。店を飛ぶように出て、帰宅した。
それからは萌がコンタクトをつけると、子供のお化けや枕フェチおじさんが見えるようになってしまった。
別の1dayコンタクトに換えてもらおうと、翌日再び来店した。
しかし先見堂は閉まっていた。閉じたシャッターに、《店長、発熱の為しばらく休み》とよれた字で書かれた紙が、貼ってあった。
――月曜日の午後――
授業が終わり、放課後となった。かれこれ十分以上、萌は校舎三階の廊下をうろついている。
逡巡する通路の中央には、奇々怪々会という部屋がある。ここには世の怪奇現象を全て知っている、と豪語する男がいた。中二病の痛々しい妄言のようで、皆不気味に思っているらしく、この部屋の前は足早に通り過ぎていく。
萌はぴたりと扉の前で足を止めて、ノックしようか悩んだ。「やっぱり怖いからやめよ」と踵を返すと、何かにぶつかって転ぶ。
見上げるとそこには奇々怪々会、唯一の会員にして会長、北条智司がいた。彼は尻もちをつく萌に手を差し伸べた。
「早坂じゃないか。入会希望なのか?」
「入会? 怖い話は苦手だし、入らないよ。お尻が痛いっ。あんた体が大きすぎ。廊下を歩くときはもっと気をつけて。突然、壁が出現したかと思った」
「壁……ぬりかべってことか。悪くない。何か用があるんだろ。取りあえず入れ」
北条は口角を上げ、扉を開いて萌を招き入れた。
室内はカーテンが閉じられており、暗く湿っぽい。掃除も行き届いていないのか、埃の香りが漂う。
中央に長机があり、椅子が数脚おかれていた。机の両端には、黒を基調にした怪しげな雑誌が乱雑に放ってあった。部屋の隅に分厚い本がうずたかく積まれている。
二人は長机に向かい合って座った。周囲を見回す萌に、北条が訊ねる。
「で、どうした」
そこからは萌の独壇場だった。ここ一週間の摩訶不思議な生物との出会いと不満を、激流のように彼にぶつける。
北条は黙って頷き続けた。
とっぷりと日も暮れた頃、永久機関かと思われた萌の唇が停止した。
「ようやく終わったか。早坂……愚痴ばっかりじゃなくてポイントを押さえて明瞭に喋れ。その妖怪の姿形・様子・いた場所とか。このままじゃ入試の面接に落ちるぞ、お前」
北条は大きく息を吐いた。
「酷い。あたしみたいなか弱い乙女には、親身に同情しなさいよ。優しく『大丈夫だったか?』『無事で良かった』でしょうが。残酷な指摘をして追い込むな! 苦しい受験期に恐ろしい目にあっているんだから。可哀そうでしょ」
「可哀そう? とんでもない。俺はこれ程、人を羨んだことは無い。頭脳明晰で定期テストは常に上位。良家の出で欲しいものは何でも手に入る。
だが、超常現象に遭遇することに焦がれているのに、一度も経験がない。何で早坂ごとき素人に先を、越されねばならんのだ」
北条はこぶしを握り、小刻みに震わせた。
怒りの表現なのか、それとも妖怪の目撃談を聞いた興奮かは分からない。
「早坂と怪奇との輝かしい出会いを説明してやる。そこになおれ」
萌は背筋を伸ばして、居住まいを正した。
「まずはお前が言うところの、変態枕フェチ。この方は妖怪、枕返しだ。人間の枕をひっくり返したりずらしたりすることを好む。東北地方で目撃されたという文献が多い。出現し始めたのは江戸時代で――」
会長の早口かつ冗長な話に、萌の耳は(精神的に)ただちに折りたたまれた。お前こそポイントを押さえて喋れや、と心の中で毒づく。
何も聞こえなくなったが、よそ見をすると懇々と説明する北条に失礼だ。萌は漫然と北条を見る。目鼻立ちは良い。身長も壁のようにそびえ立つ高さ。遠目で見たらイケメンだ。
だがもっさりとした長髪と、太い黒フレームの眼鏡が邪魔をしている。致命的なのはちょっとぽっちゃりしているのだ。外見を気にして磨けば、光る残念男子……
「おい。聞いているのか」
北条が萌の眼前で手を振る。
彼女の漂っていた目の焦点が合った。
「情報量が多すぎる。あたしの脳スペックでも分かるように簡易説明書を書いてよ」
萌は通学鞄から、文房具を取り出す。ノートを開き、ボールペンと一緒に長机の上に置いた。
「話が高度過ぎたか。仕方ない。早坂でも分かるように図解してやる」
怒りだすかと思いきや、北条は嬉々としてA4ノートにペンを走らせた。【コイツ、趣味を話せる相手が来て嬉しいんだろうな。可愛い所あるじゃん】と萌は思った。
「しかし、なぜ早坂は急に妖怪を見ることができるようになったんだ? 俺はお百度参りをしたり、何度も神に祈ったが無駄だった」
北条が妖怪を子細に描きながら、萌に訊ねる。彼女は先見堂の件を正直に話すか迷って、秘密とすることにした。
あの婆ちゃんはむかつくが、世話にはなっている。変なものが見えるなど悪い噂がたったら、さすがに気の毒だ。また、こんなレンズが複数あるはずはない。たまたまの一箱だ。
「……ダイエット! 過度だと健康に悪いから、適度なダイエット」
と、萌は声高に嘘をつく。
「そうか。高僧が断食するのは精神を高める為と思ったが、眼も澄んで見えるようになるのか。でも簡単すぎないか」
「それ、と、毎日の腕立て伏せを百回。加えて朝夕にランニング」
我ながら苦しい言い訳だ。
「腹が減るじゃないか。俺にとって食事は生き甲斐だというのに。でも、確かに立派な苦行だ。得心した」
北条は腕を組んで、ゆっくりと首を上下に振る。妖怪の絵と対処方法の書かれたノートを萌に手渡した。
俺はもう少し調べ物をするから早坂は帰れ、と部屋の扉を開く。「気をつけてな」と、萌の肩を叩いた。
妙な友人ができてしまったという後悔が萌に生まれたが、理解者を得た安心感もあった。彼女の帰り道の足取りは軽かった。
ふとノートを開き、北条の描いた妖怪を確認する。目撃したことは無い、という言葉が嘘なのではないかと思うほど、萌が見た生物にそっくりなイラストがそこにはあった。
――木曜日――
北条のアドバイスを受けてからは、萌は心に余裕ができた。火・水曜日は妖怪を歯牙にもかけない、という程ではないが、気を取られずに過ごせた。
今朝などは枕返しに、「おはよう」と声をかけれたぐらいだ。長髪のおじさんは面白くない顔をして、部屋の隅に消えていったけど。
コンタクトの枚数もあと二日分。土曜日のレンズで終わり。
放課後、萌は奇々怪々会の部屋にいった。北条に苺クッキーを作って、持ってきたのだ。「ほれ。お礼」と萌が、椅子に座る北条に菓子を渡そうとする。
「感謝する。有難く受け取るが、今は食べん。節制を続けているんでな」
萌はハッとして彼の様子を確認する。顔痩せ、と疲れからか物憂げにみえる瞳。イケメン度がぐぐっと上昇していた。
そういえば。クラスの女子が「青白い顔をした美男の霊が、校舎三階に深夜あらわれる」と噂していた。それは北条のことなのではないだろうか。あのダイエット話を真剣に受け止めたのか……
「ちょ、ちょっとは食事しているんでしょうね?」
「飢え死にしない程度には。昨日の夜はカツカレー一杯に留めた。普段、五杯はお代わりするんだが。ダイエットってこんなに苦しいものなのか」
「心配して損した。どれだけ代謝がいいんだよ。あたしの作ったクッキーも食え」
北条は手のひらを萌にかざして、拒否の姿勢をみせる。
「今は遠慮しておく。妖魔を見えるようになったらいただくよ。それより、どうだ彼らへの対応は? 順調なのか」
「お陰様で。枕返しも座敷童も害のない妖怪だからね。今朝は座敷童と毬を投げ合ったよ。そう言えば、塾帰りにべとべとさんに出くわした」
「夜道を歩く人間の後をつけてくる妖怪だな。足音も気配もあるけど、姿が見えない。べとべとさん先をお通り、と言ったのか?」
「うん。北条の妖怪ノートに書いてあったからね。そうしたら足音も消えた」
羨ましいぃ、と北条は顔を紅潮させ、全身をわななかせた。鼻息が荒くてせっかくのイケメンが台無しになる。
帰宅後、萌は先見堂に電話してみたが繋がらなかった。
まだ婆ちゃんは高熱にうなされているのだろうか。土曜日には開店することを祈りながら、彼女は床に就いた。
――金曜日――
この日も萌は奇々怪々会で、放課後を過ごした。
妖怪について北条と話し合う。新しい怪異の話を彼女から聞けなかった会長は、ひどく落胆していた。
萌は何事もなく明日のコンタクト最終日を迎えられると、ほっとしていた。
しかしこの後、彼女は自分の見通しの甘さを思い知ることになる。
学校帰り。部屋に残った北条と別れて、時間は十八時頃。
夕陽が沈んで空が暗くなり始めていた。昼と夜が移り変わる。萌の体にまとわりつくような、生ぬるい風が吹いていた。
細道を萌が歩いていると、背後に人の気配がした。振り返って確認するのもはばかれるので、カーブミラーを利用する。制服やユニフォームを着ていないので学生ではない。二十人ぐらいか? ずいぶん大勢だ。人通りの少ない通りなので珍しい。
【横に広がって歩くなよ】と萌は忌々しく思うと同時に、体が固まった。
全員、人間ではない。
異形の者であることは明らかだった。首が長く伸びている、顔に目鼻がない、剥き出しの手足が緑色で尖った口をしている。多種多様な妖怪が揃っていた。
萌は足が震えて、歩を進めることができなくなった。
何とか通学鞄から、北条が魔除けだと渡してくれたアイテムを取り出す。紙袋に包まれていたそれは、角の生えたプラスチック製の赤ら顔……節分の時に使う鬼のお面だ。――生きて帰れたらアイツ、ぶっ飛ばす。
藁にもすがる思いで、萌はお面をつけたが、足は金縛りにあったように動かない。
行列の先頭にいる坊主頭に追いつかれた。男は顔を萌に向けて、全身を睨め回してくる。皺のおおい好々爺に見えるが、威圧感が凄かった。妖怪の行進が一斉に足を止めた。
何者かがぐっと萌の襟首を、後ろから引いた。
振り返ると着物を着た美少年がいた。二本の赤い角が頭部に生えており、長い白髪。手には雅な盆を携えている。甘い酒の匂いが萌の鼻をくすぐる。
彼は萌から鬼のお面を剥がして、自分の側頭部に引っ掛けた。萌の顔をじっと見て、にこやかな笑顔を浮かべる。
美少年は彼女の肩をだき、ゆるやかに歩き出した。道の先を指さして行進を促すと、老人が顔を前に戻し、行進を再開した。
長い舌をちらつかせる鼠の化物、不気味な音を立てて歩く骸骨。中央に顔のついた燃える車輪。妖怪たちは萌に好奇の目を向けるが、隣にいる少年が睨みつけると、慌てて視線を逸らす。
横道に差し掛かり、少年は萌を脇道に引っ張った。萌に顔を寄せて、人差し指を口にあてる。
【黙っていろということ? 助けてくれたの】
少年の鬼は何事も無かったかのように、萌を置いて行列に戻っていった。
へたり込んだ萌はしばらくして、震える手で北条に電話をかけた。状況と場所を説明すると彼は興奮気味に返す。
《本当か! なんて素晴らし……いや、大変だったな。それは百鬼夜行だ。先頭の坊主は妖怪の大将、ぬらりひょん。間近でその行進を見ると死ぬのだけど、良く生きていたな》
《お盆を抱えた鬼が助けてくれた。お酒臭かったけど、格好よかった》
《ん? 酒呑童子かな。鬼化する前は女性に好かれたらしいから、女子に優しかったのかも。曲がったことが許せない性格と聞くから、きっと守ってくれたんだ。
そして、見てくれが良かったならば変身前だ。完全に鬼に変化したら背が高くなるから》
《え、イケメンなうえに高身長になるの? どのくらい》
《六メートル》
《は? 恐竜じゃん》
《鬼の頭領だから、強力なんだ。しかし早坂が無事で良かった。百鬼夜行を実体験した人間から、詳細を聞けるとは。もっと話せ。俺は自転車通学だから迎えに行こう》
あっという間に、北条がママチャリでやってきた。
後部キャリアに萌を乗せて、自転車を走らせる。
萌は血の気の引いた体を温めるように、北条の体にきつく手を回した。
びくりとした彼は文句を言おうと口を開きかけたが、萌の身体が震えているのに気がついて止めた。
夕方のランニング代わりに、北条は萌を自転車で家まで送った。早く俺も妖怪が見えるようにならないかな、と思いながら。
すっかり暗くなった夜道に、自転車のライトが流れるような白線を描いた。
――土曜日――
萌は晴れ晴れと目を覚ました。なぜならば今日で1dayコンタクトが終わりとなるから。
開店時間と同時に先見堂には電話して、婆ちゃんが復調したこと、新しいコンタクトが届いていることを確認した。
最終日だと思うと、部屋にいる枕返しの頭も撫でてやりたくなる。北条とも眼鏡屋への道中で落ち合う約束をした。
自動扉が開き、北条と萌が二人で入店する。着いて早々、萌は老婆に飛びついた。
「二週間待ちに待ったよ、婆ちゃんを。前回とんでもない不良品を寄越すんだもの」
「なんだ事前に試着させてやったろ。見づらかったのかい?」
「違う……見え過ぎて困ったの」
「良く見えたら結構なことじゃないか。しかも、急ぎだったら他の店で買えばいいこったろ。既製品なんだし」
老婆はコンタクトの箱の側面にある度数を指し示す。
「それはパニックになり過ぎて思いつかなかった……」
新しいコンタクトレンズを出してもらい、最後の呪われたコンタクトを捨てて、すぐに目につけた。装着後に店内を見渡して、妖怪がいないことを確認する。
婆ちゃんの訝しげな視線を無視して、店前にでて左右の道路を見渡す。妖怪がいない! 途中死にそうな目に遭いながらも、二週間を乗り切れた。
萌は北条の手を取り、上下に振りながら
「あんたもその野暮ったい眼鏡を外して、コンタクトにしなよ。格好良くなるよ。元が良いんだからさ」
と上機嫌で言った。
無関心な北条の肩を、婆ちゃんががっちり掴む。新規顧客を逃してなるものか、と洗面台まで連れていく。北条は仕方なしに眼鏡を外した。鏡を見て、格好いい? と首を傾げる。
萌は北条の整った横顔に見とれた。食事制限のおかげで、重なっていた顎も一つになっている。
【レンズの先にいたのは恐ろしい妖怪だけじゃなかった。あたしは学校一のイケメンも見つけたぞ】
萌は幸せだった。北条が婆ちゃんに勧められたコンタクトを、恐る恐るつけて、次の言葉を発するまでは。
「おおっ、とうとうダイエット効果が。そこに百々目鬼がいる! さすがコンタクトレンズだ。はっきりと見える。店主、店にあるコンタクトを全て売ってくれ!」
萌はがっくりと肩を落とした。そして、あの目だらけ妖怪って百々目鬼って名前なんだ、と思った。
〈 了 〉
早坂萌は起きてすぐ、枕元の携帯電話を手に取った。画面を触り、表示された時間に絶句する。
「ヤバイ」
昨夜は塾から帰った時間が二十一時だった。そこから夕食を始末して、浴室に。風呂からでたら化粧水と乳液を顔に染みこませ、ドライヤーで髪を乾かす。
自室で宿題をして、塾の時間に溜まっていたSNSに返信。ベッドに潜り込んだのは、おそらく日をまたいでいただろう。
登校時間に間に合わせるには、超特急で家を出なければいけない。
萌は階段を十六ビートで踏み鳴らして、降りる。洗面所に急ぐと、社会人の姉が場所を独占していた。
「よう、寝坊助。ようやく起きたか」
「お姉ぇ。いつからここに……すぐに化粧は終わる?」
「ファンデを始めた所。これから私の美しさは作りあげられていく」
「あたしは遅刻しそうだから、譲ってよ」
「私も会社に遅れそうだし同条件だ。会社員の場合は査定に響くからお給料が減っちゃう。だから、こっちの方が深刻なの」
さすが私の姉だ。駄目さ加減が自分とそっくりだ、と萌は諦めた。
姉の動きに合わせて、反復横跳びをする。鏡の両端で髪を確認して、櫛でとかす。隙を突いて顔を洗う。
鏡台の引き出しから、先週購入した1dayコンタクトレンズを取り出した。
自室に戻って机上のスタンドミラーを見ながら、レンズをつける。
つけ終わるとすぐに、全長一メートル程度のおじさんが鏡に映った。長髪を揺らしながら、萌のベッド奥にある枕に忍びよっている。
「また出た! この枕フェチ。変態っ。いい加減にさらせ」
萌は叫んだ。開けっ放しの窓から金切り声がとどろき、電線の鳥たちが飛び去っていく。
おじさんを睨みつけると、小男は枕に駆け寄った。枕をひっくり返して、満足げに萌に笑顔を送る。
萌は食卓に置いてあるスープを一気飲みして、食パンにバターを塗りたくった。食べやすいように二つに折ったパンを掴みながら、玄関へ。
居間のテレビ前におかっぱをした子供がいた。赤いちゃんちゃんこを着て、毬を抱きかかえている。子は構って欲しそうに萌を見つめていた。
「学校に行くんだから、今は遊べないよ。そうだ、もうTVのリモコンは隠さないでね」
推しの韓流アイドルのダンスを数分、見損じたことを思い出し、子供に注意する。
晴天の下に庭で洗濯物を干していた母が、それを耳にした。誰もいない部屋に呼びかける娘の姿に「受験ノイローゼって色々な症例があるのね」と独りごちた。
不安感を吹き飛ばすかのように、豪快に布団のシーツを上下に振る。青空に白いシーツが鮮やかにたなびいた。
――先週――
満員電車でスマホを取りだせない萌は、先週末に行った先見堂を思いだしていた。商店街に昔からある眼鏡屋。萌が初めてコンタクトレンズを買ったのは、この店だった。
店奥の機器で、店主の老人に視力検査をしてもらい、細やかな説明を受けた。今では彼は亡くなって、その妻が一人で店を経営している。
「婆ちゃん。だから明日から学校があるし、新しいレンズは二週間後って言われても困るってば」
「仕方ないでしょうが。既製品だったらすぐ渡せるけど、あんたのコンタクトは乱視も入っているし工場で作ってもらうんだ」
老婆はレジ内で舌打ちして、伝票の数字を確認している。客は萌一人。有線放送もかけない店は静かで、二人の言い合いがよく響く。
「レンズの手入れで擦り洗いしていたら破けるなんてある? 不良品掴ませたでしょ」
「ゴリラみたいな腕力で乱暴に扱うからだろが。だいたい一年以上たっているんだから経年劣化だよ。とんでもないクレーマーだ。いたいけなババアをいじめるつもりか」
萌の頭上に大きめの疑問符が浮かぶ。"いたいけな"という形容詞が、この婆ちゃんに繋がらない。"暑苦しい"ペンギンぐらいに、意味不明だ。
「仕方ないねえ」
老婆はぶつぶついいながら、コンタクトの箱の山から数個を引っ張り出した。眼鏡を取り外して、箱の側面をためつすがめつ眺める。そして萌に一つを差し出した。
「ほれ、度数があっている箱。1dayで二週間分あるから。手元とか近いところは見づらいかもしれないけどさ。これでしのぎな」
「やった。ありがとう婆ちゃん、愛してる。店の都合だから勿論サービスだよね」
「馬鹿を言ってんじゃない。完全にあんたが悪いし、定価販売だ。さっさと洗面台で一つ付けてみな」
はいはい、と萌は鏡前の椅子に腰かけた。コンタクトの封を開けて目に取り付ける。途端、萌の体に衝撃が走った。
ぼやけた風景が鮮明に見えて感動した……からではない。店の入口に妙な者が見えたのだ。中背の人型だが人間ではない。真っ白の体で、頭部に髪の毛がない。なにより全身が目だらけだ。
「ば、婆ちゃん。自動扉の脇に変な人がいる」
「なに? 妙なこと言っても、一つ使ったんだから取り替えないよっ」
老婆は、萌が指さす方にずんずん歩く。
「誰もいないよ。この辺かい?」
空中をかき混ぜるように、右手をまわした。
「全身が目だらけの人がいるじゃんっ。あああ、婆ちゃん目つぶししているよ。目人間がめっちゃ怒ってる」
「何言ってんだい。そんな大量の目玉をもつ奴がいたら、眼鏡屋のあたしゃ今頃大金持ちだよ。早く金を払って帰りな」
目人間はレジに向かう老婆へ、両手を揺らしていた。うちわを扇ぐかのようだが、呪いを飛ばしているのではないか……萌は見ないふりをして勘定をすませる。店を飛ぶように出て、帰宅した。
それからは萌がコンタクトをつけると、子供のお化けや枕フェチおじさんが見えるようになってしまった。
別の1dayコンタクトに換えてもらおうと、翌日再び来店した。
しかし先見堂は閉まっていた。閉じたシャッターに、《店長、発熱の為しばらく休み》とよれた字で書かれた紙が、貼ってあった。
――月曜日の午後――
授業が終わり、放課後となった。かれこれ十分以上、萌は校舎三階の廊下をうろついている。
逡巡する通路の中央には、奇々怪々会という部屋がある。ここには世の怪奇現象を全て知っている、と豪語する男がいた。中二病の痛々しい妄言のようで、皆不気味に思っているらしく、この部屋の前は足早に通り過ぎていく。
萌はぴたりと扉の前で足を止めて、ノックしようか悩んだ。「やっぱり怖いからやめよ」と踵を返すと、何かにぶつかって転ぶ。
見上げるとそこには奇々怪々会、唯一の会員にして会長、北条智司がいた。彼は尻もちをつく萌に手を差し伸べた。
「早坂じゃないか。入会希望なのか?」
「入会? 怖い話は苦手だし、入らないよ。お尻が痛いっ。あんた体が大きすぎ。廊下を歩くときはもっと気をつけて。突然、壁が出現したかと思った」
「壁……ぬりかべってことか。悪くない。何か用があるんだろ。取りあえず入れ」
北条は口角を上げ、扉を開いて萌を招き入れた。
室内はカーテンが閉じられており、暗く湿っぽい。掃除も行き届いていないのか、埃の香りが漂う。
中央に長机があり、椅子が数脚おかれていた。机の両端には、黒を基調にした怪しげな雑誌が乱雑に放ってあった。部屋の隅に分厚い本がうずたかく積まれている。
二人は長机に向かい合って座った。周囲を見回す萌に、北条が訊ねる。
「で、どうした」
そこからは萌の独壇場だった。ここ一週間の摩訶不思議な生物との出会いと不満を、激流のように彼にぶつける。
北条は黙って頷き続けた。
とっぷりと日も暮れた頃、永久機関かと思われた萌の唇が停止した。
「ようやく終わったか。早坂……愚痴ばっかりじゃなくてポイントを押さえて明瞭に喋れ。その妖怪の姿形・様子・いた場所とか。このままじゃ入試の面接に落ちるぞ、お前」
北条は大きく息を吐いた。
「酷い。あたしみたいなか弱い乙女には、親身に同情しなさいよ。優しく『大丈夫だったか?』『無事で良かった』でしょうが。残酷な指摘をして追い込むな! 苦しい受験期に恐ろしい目にあっているんだから。可哀そうでしょ」
「可哀そう? とんでもない。俺はこれ程、人を羨んだことは無い。頭脳明晰で定期テストは常に上位。良家の出で欲しいものは何でも手に入る。
だが、超常現象に遭遇することに焦がれているのに、一度も経験がない。何で早坂ごとき素人に先を、越されねばならんのだ」
北条はこぶしを握り、小刻みに震わせた。
怒りの表現なのか、それとも妖怪の目撃談を聞いた興奮かは分からない。
「早坂と怪奇との輝かしい出会いを説明してやる。そこになおれ」
萌は背筋を伸ばして、居住まいを正した。
「まずはお前が言うところの、変態枕フェチ。この方は妖怪、枕返しだ。人間の枕をひっくり返したりずらしたりすることを好む。東北地方で目撃されたという文献が多い。出現し始めたのは江戸時代で――」
会長の早口かつ冗長な話に、萌の耳は(精神的に)ただちに折りたたまれた。お前こそポイントを押さえて喋れや、と心の中で毒づく。
何も聞こえなくなったが、よそ見をすると懇々と説明する北条に失礼だ。萌は漫然と北条を見る。目鼻立ちは良い。身長も壁のようにそびえ立つ高さ。遠目で見たらイケメンだ。
だがもっさりとした長髪と、太い黒フレームの眼鏡が邪魔をしている。致命的なのはちょっとぽっちゃりしているのだ。外見を気にして磨けば、光る残念男子……
「おい。聞いているのか」
北条が萌の眼前で手を振る。
彼女の漂っていた目の焦点が合った。
「情報量が多すぎる。あたしの脳スペックでも分かるように簡易説明書を書いてよ」
萌は通学鞄から、文房具を取り出す。ノートを開き、ボールペンと一緒に長机の上に置いた。
「話が高度過ぎたか。仕方ない。早坂でも分かるように図解してやる」
怒りだすかと思いきや、北条は嬉々としてA4ノートにペンを走らせた。【コイツ、趣味を話せる相手が来て嬉しいんだろうな。可愛い所あるじゃん】と萌は思った。
「しかし、なぜ早坂は急に妖怪を見ることができるようになったんだ? 俺はお百度参りをしたり、何度も神に祈ったが無駄だった」
北条が妖怪を子細に描きながら、萌に訊ねる。彼女は先見堂の件を正直に話すか迷って、秘密とすることにした。
あの婆ちゃんはむかつくが、世話にはなっている。変なものが見えるなど悪い噂がたったら、さすがに気の毒だ。また、こんなレンズが複数あるはずはない。たまたまの一箱だ。
「……ダイエット! 過度だと健康に悪いから、適度なダイエット」
と、萌は声高に嘘をつく。
「そうか。高僧が断食するのは精神を高める為と思ったが、眼も澄んで見えるようになるのか。でも簡単すぎないか」
「それ、と、毎日の腕立て伏せを百回。加えて朝夕にランニング」
我ながら苦しい言い訳だ。
「腹が減るじゃないか。俺にとって食事は生き甲斐だというのに。でも、確かに立派な苦行だ。得心した」
北条は腕を組んで、ゆっくりと首を上下に振る。妖怪の絵と対処方法の書かれたノートを萌に手渡した。
俺はもう少し調べ物をするから早坂は帰れ、と部屋の扉を開く。「気をつけてな」と、萌の肩を叩いた。
妙な友人ができてしまったという後悔が萌に生まれたが、理解者を得た安心感もあった。彼女の帰り道の足取りは軽かった。
ふとノートを開き、北条の描いた妖怪を確認する。目撃したことは無い、という言葉が嘘なのではないかと思うほど、萌が見た生物にそっくりなイラストがそこにはあった。
――木曜日――
北条のアドバイスを受けてからは、萌は心に余裕ができた。火・水曜日は妖怪を歯牙にもかけない、という程ではないが、気を取られずに過ごせた。
今朝などは枕返しに、「おはよう」と声をかけれたぐらいだ。長髪のおじさんは面白くない顔をして、部屋の隅に消えていったけど。
コンタクトの枚数もあと二日分。土曜日のレンズで終わり。
放課後、萌は奇々怪々会の部屋にいった。北条に苺クッキーを作って、持ってきたのだ。「ほれ。お礼」と萌が、椅子に座る北条に菓子を渡そうとする。
「感謝する。有難く受け取るが、今は食べん。節制を続けているんでな」
萌はハッとして彼の様子を確認する。顔痩せ、と疲れからか物憂げにみえる瞳。イケメン度がぐぐっと上昇していた。
そういえば。クラスの女子が「青白い顔をした美男の霊が、校舎三階に深夜あらわれる」と噂していた。それは北条のことなのではないだろうか。あのダイエット話を真剣に受け止めたのか……
「ちょ、ちょっとは食事しているんでしょうね?」
「飢え死にしない程度には。昨日の夜はカツカレー一杯に留めた。普段、五杯はお代わりするんだが。ダイエットってこんなに苦しいものなのか」
「心配して損した。どれだけ代謝がいいんだよ。あたしの作ったクッキーも食え」
北条は手のひらを萌にかざして、拒否の姿勢をみせる。
「今は遠慮しておく。妖魔を見えるようになったらいただくよ。それより、どうだ彼らへの対応は? 順調なのか」
「お陰様で。枕返しも座敷童も害のない妖怪だからね。今朝は座敷童と毬を投げ合ったよ。そう言えば、塾帰りにべとべとさんに出くわした」
「夜道を歩く人間の後をつけてくる妖怪だな。足音も気配もあるけど、姿が見えない。べとべとさん先をお通り、と言ったのか?」
「うん。北条の妖怪ノートに書いてあったからね。そうしたら足音も消えた」
羨ましいぃ、と北条は顔を紅潮させ、全身をわななかせた。鼻息が荒くてせっかくのイケメンが台無しになる。
帰宅後、萌は先見堂に電話してみたが繋がらなかった。
まだ婆ちゃんは高熱にうなされているのだろうか。土曜日には開店することを祈りながら、彼女は床に就いた。
――金曜日――
この日も萌は奇々怪々会で、放課後を過ごした。
妖怪について北条と話し合う。新しい怪異の話を彼女から聞けなかった会長は、ひどく落胆していた。
萌は何事もなく明日のコンタクト最終日を迎えられると、ほっとしていた。
しかしこの後、彼女は自分の見通しの甘さを思い知ることになる。
学校帰り。部屋に残った北条と別れて、時間は十八時頃。
夕陽が沈んで空が暗くなり始めていた。昼と夜が移り変わる。萌の体にまとわりつくような、生ぬるい風が吹いていた。
細道を萌が歩いていると、背後に人の気配がした。振り返って確認するのもはばかれるので、カーブミラーを利用する。制服やユニフォームを着ていないので学生ではない。二十人ぐらいか? ずいぶん大勢だ。人通りの少ない通りなので珍しい。
【横に広がって歩くなよ】と萌は忌々しく思うと同時に、体が固まった。
全員、人間ではない。
異形の者であることは明らかだった。首が長く伸びている、顔に目鼻がない、剥き出しの手足が緑色で尖った口をしている。多種多様な妖怪が揃っていた。
萌は足が震えて、歩を進めることができなくなった。
何とか通学鞄から、北条が魔除けだと渡してくれたアイテムを取り出す。紙袋に包まれていたそれは、角の生えたプラスチック製の赤ら顔……節分の時に使う鬼のお面だ。――生きて帰れたらアイツ、ぶっ飛ばす。
藁にもすがる思いで、萌はお面をつけたが、足は金縛りにあったように動かない。
行列の先頭にいる坊主頭に追いつかれた。男は顔を萌に向けて、全身を睨め回してくる。皺のおおい好々爺に見えるが、威圧感が凄かった。妖怪の行進が一斉に足を止めた。
何者かがぐっと萌の襟首を、後ろから引いた。
振り返ると着物を着た美少年がいた。二本の赤い角が頭部に生えており、長い白髪。手には雅な盆を携えている。甘い酒の匂いが萌の鼻をくすぐる。
彼は萌から鬼のお面を剥がして、自分の側頭部に引っ掛けた。萌の顔をじっと見て、にこやかな笑顔を浮かべる。
美少年は彼女の肩をだき、ゆるやかに歩き出した。道の先を指さして行進を促すと、老人が顔を前に戻し、行進を再開した。
長い舌をちらつかせる鼠の化物、不気味な音を立てて歩く骸骨。中央に顔のついた燃える車輪。妖怪たちは萌に好奇の目を向けるが、隣にいる少年が睨みつけると、慌てて視線を逸らす。
横道に差し掛かり、少年は萌を脇道に引っ張った。萌に顔を寄せて、人差し指を口にあてる。
【黙っていろということ? 助けてくれたの】
少年の鬼は何事も無かったかのように、萌を置いて行列に戻っていった。
へたり込んだ萌はしばらくして、震える手で北条に電話をかけた。状況と場所を説明すると彼は興奮気味に返す。
《本当か! なんて素晴らし……いや、大変だったな。それは百鬼夜行だ。先頭の坊主は妖怪の大将、ぬらりひょん。間近でその行進を見ると死ぬのだけど、良く生きていたな》
《お盆を抱えた鬼が助けてくれた。お酒臭かったけど、格好よかった》
《ん? 酒呑童子かな。鬼化する前は女性に好かれたらしいから、女子に優しかったのかも。曲がったことが許せない性格と聞くから、きっと守ってくれたんだ。
そして、見てくれが良かったならば変身前だ。完全に鬼に変化したら背が高くなるから》
《え、イケメンなうえに高身長になるの? どのくらい》
《六メートル》
《は? 恐竜じゃん》
《鬼の頭領だから、強力なんだ。しかし早坂が無事で良かった。百鬼夜行を実体験した人間から、詳細を聞けるとは。もっと話せ。俺は自転車通学だから迎えに行こう》
あっという間に、北条がママチャリでやってきた。
後部キャリアに萌を乗せて、自転車を走らせる。
萌は血の気の引いた体を温めるように、北条の体にきつく手を回した。
びくりとした彼は文句を言おうと口を開きかけたが、萌の身体が震えているのに気がついて止めた。
夕方のランニング代わりに、北条は萌を自転車で家まで送った。早く俺も妖怪が見えるようにならないかな、と思いながら。
すっかり暗くなった夜道に、自転車のライトが流れるような白線を描いた。
――土曜日――
萌は晴れ晴れと目を覚ました。なぜならば今日で1dayコンタクトが終わりとなるから。
開店時間と同時に先見堂には電話して、婆ちゃんが復調したこと、新しいコンタクトが届いていることを確認した。
最終日だと思うと、部屋にいる枕返しの頭も撫でてやりたくなる。北条とも眼鏡屋への道中で落ち合う約束をした。
自動扉が開き、北条と萌が二人で入店する。着いて早々、萌は老婆に飛びついた。
「二週間待ちに待ったよ、婆ちゃんを。前回とんでもない不良品を寄越すんだもの」
「なんだ事前に試着させてやったろ。見づらかったのかい?」
「違う……見え過ぎて困ったの」
「良く見えたら結構なことじゃないか。しかも、急ぎだったら他の店で買えばいいこったろ。既製品なんだし」
老婆はコンタクトの箱の側面にある度数を指し示す。
「それはパニックになり過ぎて思いつかなかった……」
新しいコンタクトレンズを出してもらい、最後の呪われたコンタクトを捨てて、すぐに目につけた。装着後に店内を見渡して、妖怪がいないことを確認する。
婆ちゃんの訝しげな視線を無視して、店前にでて左右の道路を見渡す。妖怪がいない! 途中死にそうな目に遭いながらも、二週間を乗り切れた。
萌は北条の手を取り、上下に振りながら
「あんたもその野暮ったい眼鏡を外して、コンタクトにしなよ。格好良くなるよ。元が良いんだからさ」
と上機嫌で言った。
無関心な北条の肩を、婆ちゃんががっちり掴む。新規顧客を逃してなるものか、と洗面台まで連れていく。北条は仕方なしに眼鏡を外した。鏡を見て、格好いい? と首を傾げる。
萌は北条の整った横顔に見とれた。食事制限のおかげで、重なっていた顎も一つになっている。
【レンズの先にいたのは恐ろしい妖怪だけじゃなかった。あたしは学校一のイケメンも見つけたぞ】
萌は幸せだった。北条が婆ちゃんに勧められたコンタクトを、恐る恐るつけて、次の言葉を発するまでは。
「おおっ、とうとうダイエット効果が。そこに百々目鬼がいる! さすがコンタクトレンズだ。はっきりと見える。店主、店にあるコンタクトを全て売ってくれ!」
萌はがっくりと肩を落とした。そして、あの目だらけ妖怪って百々目鬼って名前なんだ、と思った。
〈 了 〉