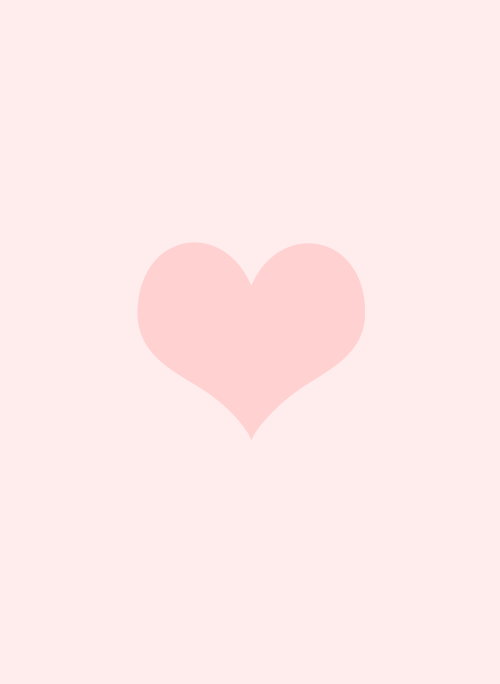高校三年生
高校三年生
先生に触れたのは、三年間でたった一回だった。
姉ちゃんよりも年上で、一回り年上の先生が可愛く見えたのは本当にただの偶然だった。
「進路志望調査票、でてませんけど?」
先生はいつもこんな口調で話を切り出す。
先生の巣になっている英語準備室はちらかっていて、赤い夕日が部屋を真っ赤に染め上げている。
先生は窓を背に美顔器で顔をマッサージしていた。元々まじめっぽくなくて、ちょっと肩の力の抜けたところのある先生は生徒たちから好感を持たれていた。
あの先生ならある程度自由を許してくれる。だからオレたちも先生が許してくれる範囲内で自由にしようぜっていう空気がなんとなくあった。
実際先生が俺達の担任じゃなかったらたぶん俺達の学生生活はもっと窮屈なものになっていたと思う。
俺は先生の近くに置かれたデスクにもたれて答えた。
「ごめん、忘れた」
半分は本当、半分は嘘だった。
将来のことなんてあんまり考えたくない。だって俺は部活命だけど、勉強は常に国語と歴史が赤点。進路どころか留年すれすれだ。将来のことを考えても暗い未来しか思い浮かばない。
「ふうん」
先生は美顔器で顔をコロコロしながら足を組み替え、うーん、と唸りながら目を伏せた。
俺は話の本題よりも先生の足が思っていたよりも短いな、普段はヒールで底上げしてるんだな、と全く話とは関係の無いことを思っていた。
「実業団狙い?」
「いや、何の話も来てないっす」
「そっかぁ……。ま、逃げてても不利になるだけなんで……その辺わきまえつつ……考えておいて。これ、参考資料ね」
先生はデスクの上におかれたいろんな専門学校や大学のパンフレットを指差した。
「これ、俺のっすか」
「うん。あっちこっち電話して集めたんだから見るくらい見てね」
「進学なんて無理じゃないすか。俺……赤点二つだし」
「私、高校のときの赤点、最大3つだったよ」
「嘘。先生ヤッベー」
思わず笑ってしまうと、先生は美顔器を倍速で動かしながら俺をにらんだ。
「よそで言わないでね」
「ハハハ、先生がクビになったらやばいから言わない」
「こんな事で優秀な教師がクビになったりしませんけど!」
優秀って。
よく言うな。この間、学年主任の高幡に偉そうに説教されているのを見たんだけどな。俺らがそういうの、知らないとでも思ってるのかな。
自分たちが先生に庇われているってこと、気付かないほど高校生は子どもじゃないんだけど。
「先生」
「ん?」
「俺、部活行ってくる。練習試合が近いからさ」
「ハイハイ、じゃーもう行きな」
先生は苦笑して犬を追い払うみたいに手を動かした。そうやって説教すべきところを中途でよしてしまうから先生は高幡に甘いのなんだのって言われるのに、先生はこのスタイルを崩す気は無いらしい。
うるさく言うのも言われるのも、たぶん先生は嫌いなんだろう。
なんでも自分で決めろ。決まらなかったら自己責任な。でも手は貸してやる。
普段は女子力がどうのとかいっているくせにそういうところはちょっと男らしい。
俺、この人好きだなあ……。
先生といると、すごく好きだとかやりたいとか、そういう同年代の女子に抱く生々しい気持ちとはまた違った、どこか柔らかい気持ちになる。
不思議な人だな。この人には反抗する気になれないわ、俺。
結局それから一ヶ月もしないうちに俺は大学受験を決めた。
いくら部活でいい成績を残そうと、高校生の部活はあくまで部活。時期が来れば熱狂からさめてしかるべき道を選び取らなければいけない。
勉強なんて今まで適当に形だけやっていた俺は生まれて初めて本気で勉強した。慣れない内は辛かったけれど、元々負けん気の強い性質なので、いつの間にか俺は勉強にまで根性を発揮するようになった。
夢中になって勉強しているうちに……俺は第一志望を落とし、第二志望の大学に滑り込みで合格した。どうしてこんなに夢中になって頑張れたのか、これは今でもよく分からない。
もう一週間もしないうちに卒業する。
そう思うと急に学校が懐かしくなる。そう感じるのは俺だけではなかったようで、急に付き合い始めるやつらが現れたり、意味もなく校舎やクラスメイトの写真を撮るやつらが増えた。まだ進路がきまっていないやつらはそれどころじゃなかったようだが。
幸い俺はなんとか進路を決めることができ、残りの高校生活をゆるーく楽しんでいた。
その日はひどい雪だった。
雪まみれの電車がホームに遅れて入ってくる。電車の遅れを詫びるアナウンスが入る中、俺はやっと来た電車に押し込まれる。
車内の誰もが不快な顔をしていた。
ぎゅうぎゅうに込み合った車内で天井を見つめていると、ドア付近でごそごそと動いている先生を見つけた。
先生は迷惑そうに後ろのサラリーマンをにらみながら、ときどきからだの向きを変えようとし、そのたびに近くの人に舌打ちされていた。
何やってるんだ、あの人。
俺は人を押しのけるようにして無理やりに先生の側に移動した。先生はうつむいて顔を赤くしている。
その決定的な場面を目で確認したわけでは無いけれど、なんとなく勘が働いた。俺は先生の後ろに張り付いているオッサンと先生の間に体を割り込ませ、周囲の人には悪いが先生を囲むように壁に手をついて空間を作った。ものすごい圧力が背中を押してきたけれど、三年間毎日バスケをやってた俺がそう簡単に押しつぶされるはずもなく。簡単に、というわけには行かなかったけれど、先生のための空間を確保することに成功した。
「センセ、おはよ」
先生は驚いたように目を上げ、そして壁に着いた俺の手が震えているのをみて情けなさそうに眉をハの字にした。
「ありがと……」
「いつから?」
俺は逃げるようにその場を離れるオッサンを横目でにらみながら尋ねた。
「一週間……くらい」
「毎日?」
先生は気まずそうに俺から目をそらす。先生が悪いわけじゃないのに。
「あんたは気にしなくていいから」
呆れた。
少しも悪くないのに、なぜか恥ずかしそうに小さくなっている先生を見ていると、なんだか頭にくる。
「アイツ、つかまえてやろうか」
先生は顔色を変えた。
「いい、危ないから」
居心地悪そうにうつむいた先生の頭は俺の胸くらいまでしかない。教室で見るときは少なくとも同じ目線で話していた先生なのに、こんなに小さいなんて知らなかった。
こんな小さな人に、俺らは庇われていたんだな……。
その瞬間、なぜか突然先生が、ものすごくいたいけで、誰かが守らなきゃすぐに押しつぶされてしまう気がした。
そんなことを思っては失礼なのかもしれないけれど、なぜか猛烈にあの痴漢のオッサンに腹が立った。義憤というよりは個人的な怒りに近い。まるで自分のものを不当に奪われたような怒りに似ていた。
先生は俺の先生だけど俺の女じゃない。
そんなことは分かっているのにこの小さな女の人を守りたかった。
俺はもうすぐ地元を離れて東京の大学に行くのに。
毎朝こうやって先生を守ることなんて不可能だとわかっているのに。
先生は生徒に助けられて気まずいのか、そのまま電車を降りるまで何も言わなかった。
俺も、何も言えず。ただ車内の壁に手を突っ張って先生のために小さな空間を作るだけに徹していた。
思い返せばあれは恋というには淡すぎる想いだったのかもしれない。
当時の俺は「先生」という大人の女相手に何をいえるわけでもなく、ただ残された一週間、先生の姿を目で追うだけだった。
その後、俺は予定通り東京の大学に行き、他の学生と変わらない生活を送った。彼女らしき女の子も何度か出来た。
自分では何も意識していないつもりだったけれど、俺の付き合う子はみんなすこし顔がぽっちゃりしていて背が低くて足も短い。
自分でもうんざりするほど、彼女らはみな先生に似た雰囲気を持っていた。
あの日から五年の歳月が流れた。
今日は朝も早くから家を出たというのに、あの朝のようにひどい雪のせいで電車は随分と遅延していた。
家を出たときはそれほどでもなかったはずだが、雪は次第にひどくなり、もう線路も見えないほどにあたりは真っ白になっている。
転勤そうそう遅刻なんて随分な話だと思いながら駅のホームを歩いていると、誰かが俺にぶつかってよろめいた。
「あ、すみません」
咄嗟に相手の腕をつかんで転ばないように手を引いてやる。
「すみません、ありがとう」
髪をかきあげながら恥ずかしそうに微笑んだその相手。
コートの肩や髪から、はらはらと雪が落ちる。
俺は凍りついたように動けず、相手はいつまでも手を離せずにいる俺を不審そうに見上げ、そして「あ、」と小さくつぶやいた。
「先生……」
運命は突然やってくる。何の準備もしていない、身構えてすらいなかった俺は二度目の運命にもただただ戸惑うばかりだった。
ただ、五年の歳月は俺を少しは大人にしたようで、俺はつかんだ先生の手を簡単に離したりはしなかった。