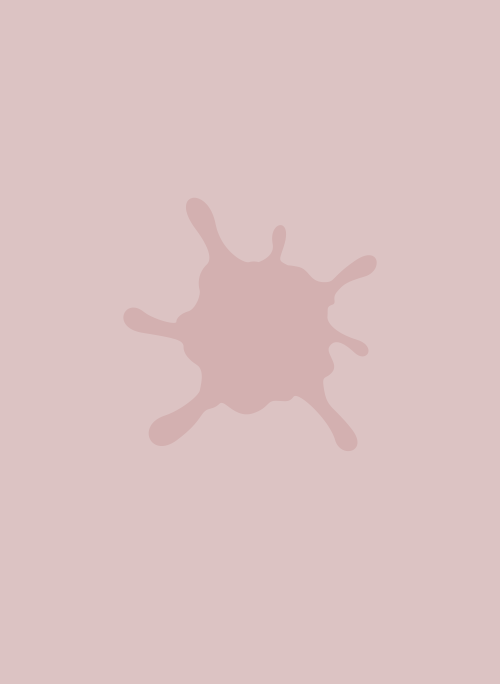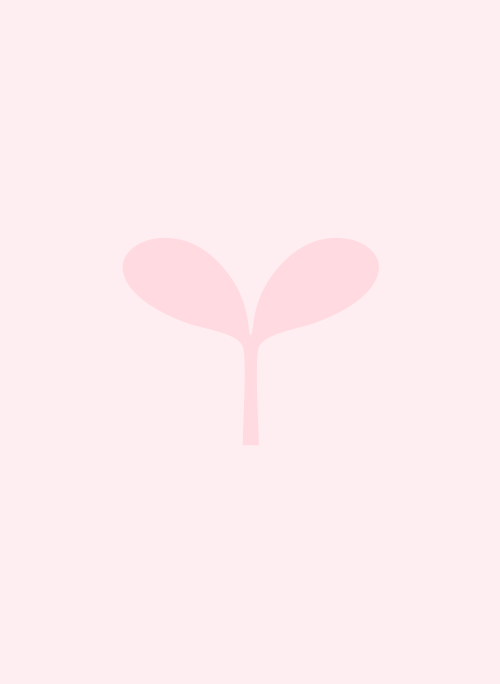掟やぶりの妖精
掟やぶりの妖精
妖精たちが生きたこの時代、人間の世界では戦争真っただ中だった。
当然、戦争だもの、負傷者はたくさんいた。でもね、それを助けたのは、言うまでもなく人間であって、妖精たちが手助けをすることはなかったんだ。
じゃあ、なんで? ってぎもんに思ったひとのために、教えよう。
むかし、人間たちが妖精たちのすみかを見つけたんだ。けれど、見つけた妖精たちを人間たちは、つかまえて、売りものにしてしまったんだ。ってなわけで、かわいそうに、妖精たちは小さな瓶に閉じこめられてしまったんだ。
けれど人間たちは、妖精たちの気持ちを気にもとめなかった。生活のために、必死だったんだね。
そんで、売られていった妖精たちをかわいそうに思った仲間のみんなは、掟をつくったんだ。二度と、こんな悲劇が起きないように、人間をみつけても近づいてはいけないよ、話してはいけないよってね。
こうして、妖精たちは、掟を守りつづけたおかげで、誰も傷つく妖精なんかいなくなったんだ。今までは、ね。
さて、これからがお話のはじまりなんだ。よくお聞き。
ちいと変わり者の妖精、クストディアは、いつも夜ふかしして、森に出かけるんだ。
月が出ていて、みんな寝入っている時間なのに、なんで? って思うよね。そうさ、これが、変わり者の妖精だってみんなに呼ばれたクストディアなんだ。
クストディアはね、好奇心旺盛な子で、夜になると出てくるって噂のあった怪物を一目見たいという夢を持っていた。そんで、毎晩、夜ふかしして、森に出かけているってわけ。
「夜って、やっぱ面白いわ」クストディアは森のなかを歩きながら、呟いた。「だって、めずらしい生き物がたくさん出てくるんですもの」
クストディアは、なんてのんきなことか。って言うのは、このあたりの森は、妖精が行くことを禁止されている場所なんだ。なぜかって? この森をぬけた先は、人間たちがすむ世界に入ってしまうからさ。つまり、妖精の世界と、人間の世界の境界線ってこと。
「おや?」
クストディアは、目を大きくした。
何を見つけたのやら……おや? なんてことだろう! 僕まで驚いて目を大きくしてしまったじゃないか。
人間が、木に背中を寄っかからせて、腰を下ろしていた。それも、うつむいていて、元気がなさそうだった。服は、銀色にかがやく鎧、胴体のあちらこちらに、人間の放った矢が刺さったままだった。
こうしてはいられないって思ったクストディアは、人間に近づいてしまったんだ。掟をすっかり破ってしまったんだね。
「あなた、平気?」
「いや、これを見て、平気だと思うのかい?」人間は、うつむいたまま言ってた。「どこやの嬢ちゃんだかしらんが、はやいとこ、家にもどったほうがいい。お母さんは心配しているだろう。そして、このあたりの森は平和だが、この俺がここに逃げ込んだからには、いつなんとき追っ手が来るかもわからねえんだ。いいね、嬢ちゃん。はやくお家へ……」
ようやくここで、人間は気がついたんだ。顔をあげたしゅんかんに、顔色がますます真っ青になってしまった。
そりゃあ、そうだろうね。じぶんの小指くらいの大きさしかなくって、羽の生えた人間なんて、いないもの。
「ば、化けもの!」
人間がそう叫んだもんで、クストディアは頬を膨らまして言い返してやった。
「いやね、失礼だわ! 私は、クストディア。ほかの妖精にはね、変わり者のクストディアって言われているわ。だって、こんな夜中にお出かけする妖精なんて、ほかにいないもの!」
「ははあ! 妖精をこの目で見たのははじめてだ」
人間は、身体の痛みはどこへやら、目を大きくした。
「さあ、私のじこしょうかいはしたわ。今度はあなたのばんよ。そうしなきゃ、きずの手当てしてやんないわよ。だって、はじめての人にあいさつするのは常識なんですから」
「お、おう、それもそうだな。俺は、エンリケ。今年で三〇になる、もうおやじだな。俺は小さな頃から、騎士をやってきた。両親が、早くに天へ旅たって行ってしまったからだ」
そう言って、人間――エンリケは、クストディアの爪楊枝みたいなちっちゃな手を包みこむようにして、握手してみせていた。
「ああ! それから、お前さんは変わり者だとみんなには言われるそうだが、ちいとも変わり者じゃあないな。負傷者をみて、助けたいという気持ちがあることは立派なことだ。ましてや、人間というじぶんたちとは違った生き物にな」
「そうよ。そうでしょ! みんなには、人間には近づくなといわれるけれど、あんたみたいにいい人間だっていることに、気がついていないみたいでね。ああ、呆れちゃうわ!」
「そうか、そうか。君と話しているのは楽しいものだが、ほかの人間が来てしまうと、君たちの身が危険だよ。クストディア、君のいうように、いい人間もいれば、悪い人間もいるんだ。傷の手当てをしてくれるというなら、早くにすましてくれなさい」
「わかったわ」
素直に、クストディアはふところにしまいこんでいた薬草をとりだすと、傷の手当てを見る見るうちにこなしていったんだ。あっという間にね。
いいかい? 僕がほんとうに言いたいのは、思いやり合うことに、種族は関係ないってことさ。クストディアとエンリケの言うとおりで、いい人間もいれば、悪い人間もいる。そして、いい妖精もいれば、悪い妖精もいる。それは、どの生き物や種族の間にも共通する事なんだ。だから、ようするに、あんな掟なんて馬鹿馬鹿しいものだったわけ! 肌の色が白かろうと、黒かろうと、そんなことは関係ない。仲良くなれば、それは友達になったしょうこだし、あの生き物は危険だっていう考え方も、くだらなかったという証明になるわけだ!
ほら、ごらん、二人とも笑顔だ。
ただ、それをほかの妖精たちが気づくのかってこと。
じつは、ここの森でくらすカラスが、みんなに伝えていたんだ。クストディアが掟を破ったことをね。
この瞬間、みんなカンカンで、森へ一目散に飛んでいったんだ。
クストディアと、エンリケが仲良く会話している姿が目に入ってくると、すぐに、一人の妖精がこう言い出した。
「クストディア! 掟を破ったな!」
だけど、しだいに、眉間のしわがうすくなって、今度は、こんなことを言い出した。
「掟を破ったことは、罰に値するものだ。だけど、王様が取り消してくださった。王様は、お気づきになったのだ。それで、われわれも気がついた。クストディア、君のおかげで、気がついたのだよ。悪い人間ばかりではないことを。そして、変わりに王様は、こんな掟をお作りになった。『二度と人間は危険だなんて、さべつに値する言葉はひかえること』とね」
したら、クストディアは、涙を流したんだ。嬉しかったんだ。そのことを、みんなが気がついてくれたことにね。
エンリケは、クストディアのおかげですぐ元気になって、人間のすむ世界へつづく森のさきへ去っていったんだ。それも、エンリケはとっても笑顔だった。
クストディアも、他のみんなも、笑顔でエンリケを見送った。
ああ、よかった、よかった。
まったく、クストディアには感心させられたよ。――(おしまい)
当然、戦争だもの、負傷者はたくさんいた。でもね、それを助けたのは、言うまでもなく人間であって、妖精たちが手助けをすることはなかったんだ。
じゃあ、なんで? ってぎもんに思ったひとのために、教えよう。
むかし、人間たちが妖精たちのすみかを見つけたんだ。けれど、見つけた妖精たちを人間たちは、つかまえて、売りものにしてしまったんだ。ってなわけで、かわいそうに、妖精たちは小さな瓶に閉じこめられてしまったんだ。
けれど人間たちは、妖精たちの気持ちを気にもとめなかった。生活のために、必死だったんだね。
そんで、売られていった妖精たちをかわいそうに思った仲間のみんなは、掟をつくったんだ。二度と、こんな悲劇が起きないように、人間をみつけても近づいてはいけないよ、話してはいけないよってね。
こうして、妖精たちは、掟を守りつづけたおかげで、誰も傷つく妖精なんかいなくなったんだ。今までは、ね。
さて、これからがお話のはじまりなんだ。よくお聞き。
ちいと変わり者の妖精、クストディアは、いつも夜ふかしして、森に出かけるんだ。
月が出ていて、みんな寝入っている時間なのに、なんで? って思うよね。そうさ、これが、変わり者の妖精だってみんなに呼ばれたクストディアなんだ。
クストディアはね、好奇心旺盛な子で、夜になると出てくるって噂のあった怪物を一目見たいという夢を持っていた。そんで、毎晩、夜ふかしして、森に出かけているってわけ。
「夜って、やっぱ面白いわ」クストディアは森のなかを歩きながら、呟いた。「だって、めずらしい生き物がたくさん出てくるんですもの」
クストディアは、なんてのんきなことか。って言うのは、このあたりの森は、妖精が行くことを禁止されている場所なんだ。なぜかって? この森をぬけた先は、人間たちがすむ世界に入ってしまうからさ。つまり、妖精の世界と、人間の世界の境界線ってこと。
「おや?」
クストディアは、目を大きくした。
何を見つけたのやら……おや? なんてことだろう! 僕まで驚いて目を大きくしてしまったじゃないか。
人間が、木に背中を寄っかからせて、腰を下ろしていた。それも、うつむいていて、元気がなさそうだった。服は、銀色にかがやく鎧、胴体のあちらこちらに、人間の放った矢が刺さったままだった。
こうしてはいられないって思ったクストディアは、人間に近づいてしまったんだ。掟をすっかり破ってしまったんだね。
「あなた、平気?」
「いや、これを見て、平気だと思うのかい?」人間は、うつむいたまま言ってた。「どこやの嬢ちゃんだかしらんが、はやいとこ、家にもどったほうがいい。お母さんは心配しているだろう。そして、このあたりの森は平和だが、この俺がここに逃げ込んだからには、いつなんとき追っ手が来るかもわからねえんだ。いいね、嬢ちゃん。はやくお家へ……」
ようやくここで、人間は気がついたんだ。顔をあげたしゅんかんに、顔色がますます真っ青になってしまった。
そりゃあ、そうだろうね。じぶんの小指くらいの大きさしかなくって、羽の生えた人間なんて、いないもの。
「ば、化けもの!」
人間がそう叫んだもんで、クストディアは頬を膨らまして言い返してやった。
「いやね、失礼だわ! 私は、クストディア。ほかの妖精にはね、変わり者のクストディアって言われているわ。だって、こんな夜中にお出かけする妖精なんて、ほかにいないもの!」
「ははあ! 妖精をこの目で見たのははじめてだ」
人間は、身体の痛みはどこへやら、目を大きくした。
「さあ、私のじこしょうかいはしたわ。今度はあなたのばんよ。そうしなきゃ、きずの手当てしてやんないわよ。だって、はじめての人にあいさつするのは常識なんですから」
「お、おう、それもそうだな。俺は、エンリケ。今年で三〇になる、もうおやじだな。俺は小さな頃から、騎士をやってきた。両親が、早くに天へ旅たって行ってしまったからだ」
そう言って、人間――エンリケは、クストディアの爪楊枝みたいなちっちゃな手を包みこむようにして、握手してみせていた。
「ああ! それから、お前さんは変わり者だとみんなには言われるそうだが、ちいとも変わり者じゃあないな。負傷者をみて、助けたいという気持ちがあることは立派なことだ。ましてや、人間というじぶんたちとは違った生き物にな」
「そうよ。そうでしょ! みんなには、人間には近づくなといわれるけれど、あんたみたいにいい人間だっていることに、気がついていないみたいでね。ああ、呆れちゃうわ!」
「そうか、そうか。君と話しているのは楽しいものだが、ほかの人間が来てしまうと、君たちの身が危険だよ。クストディア、君のいうように、いい人間もいれば、悪い人間もいるんだ。傷の手当てをしてくれるというなら、早くにすましてくれなさい」
「わかったわ」
素直に、クストディアはふところにしまいこんでいた薬草をとりだすと、傷の手当てを見る見るうちにこなしていったんだ。あっという間にね。
いいかい? 僕がほんとうに言いたいのは、思いやり合うことに、種族は関係ないってことさ。クストディアとエンリケの言うとおりで、いい人間もいれば、悪い人間もいる。そして、いい妖精もいれば、悪い妖精もいる。それは、どの生き物や種族の間にも共通する事なんだ。だから、ようするに、あんな掟なんて馬鹿馬鹿しいものだったわけ! 肌の色が白かろうと、黒かろうと、そんなことは関係ない。仲良くなれば、それは友達になったしょうこだし、あの生き物は危険だっていう考え方も、くだらなかったという証明になるわけだ!
ほら、ごらん、二人とも笑顔だ。
ただ、それをほかの妖精たちが気づくのかってこと。
じつは、ここの森でくらすカラスが、みんなに伝えていたんだ。クストディアが掟を破ったことをね。
この瞬間、みんなカンカンで、森へ一目散に飛んでいったんだ。
クストディアと、エンリケが仲良く会話している姿が目に入ってくると、すぐに、一人の妖精がこう言い出した。
「クストディア! 掟を破ったな!」
だけど、しだいに、眉間のしわがうすくなって、今度は、こんなことを言い出した。
「掟を破ったことは、罰に値するものだ。だけど、王様が取り消してくださった。王様は、お気づきになったのだ。それで、われわれも気がついた。クストディア、君のおかげで、気がついたのだよ。悪い人間ばかりではないことを。そして、変わりに王様は、こんな掟をお作りになった。『二度と人間は危険だなんて、さべつに値する言葉はひかえること』とね」
したら、クストディアは、涙を流したんだ。嬉しかったんだ。そのことを、みんなが気がついてくれたことにね。
エンリケは、クストディアのおかげですぐ元気になって、人間のすむ世界へつづく森のさきへ去っていったんだ。それも、エンリケはとっても笑顔だった。
クストディアも、他のみんなも、笑顔でエンリケを見送った。
ああ、よかった、よかった。
まったく、クストディアには感心させられたよ。――(おしまい)