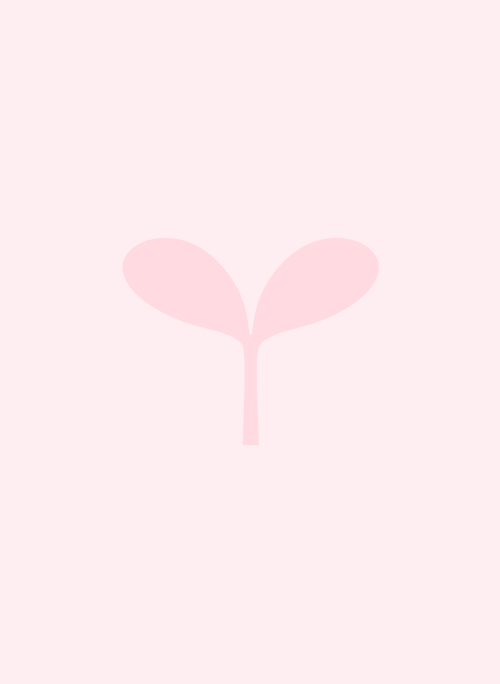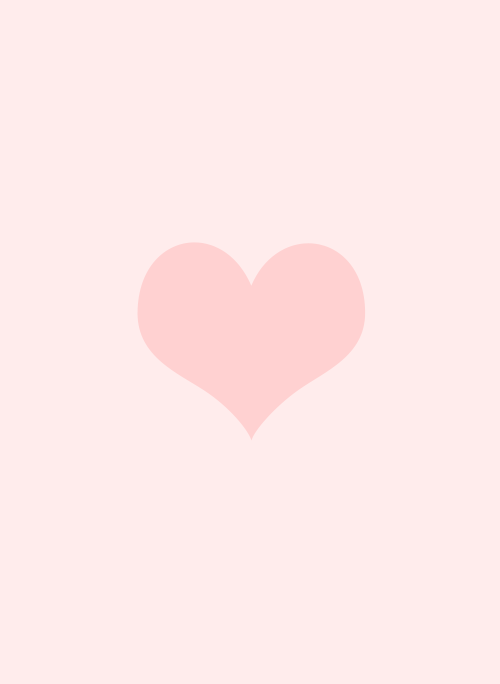内緒で優しくして欲しい
事務の新人の彼女は私をみてあきれた顔をした。
「明石さん、まだ時間内なのに。何やってるんですか。課長が捜してましたよ。」
「えへへ。ちょっと脳にブドウ糖を補給しようと思って。」
「ケーキ。1人だけ先に食べちゃったんですか。」
「ごめーん。だって、お腹がすいて頭がクラクラして来ちゃって。」
「課長の頂き物ですよ。定時になったらみんなで分けろって言われてたのに。」
「課長!明石さんいましたよ〜。」
彼女が廊下に声をかける。
「こら明石。まだ資料もできてないのに、何をやっとるかっ。」
彼女の後ろから、課長が現れた。私を捜していたらしい。
「はい。今やりますぅっ。やってますぅ。」
「まったく。お前は。油断も隙もないな。」
私は最後の一口をあわてて頬張ると、マグカップを冷蔵庫の上に忘れたまま、走ってデスクに戻った。
「いつもいつも、慌ただしいなぁ。あいつは。」
彼は、ため息をついて、笑顔で言う。
「まあ、がんばれ。またケーキ冷やしといてやるから。」
給湯室の彼 = 冷蔵庫