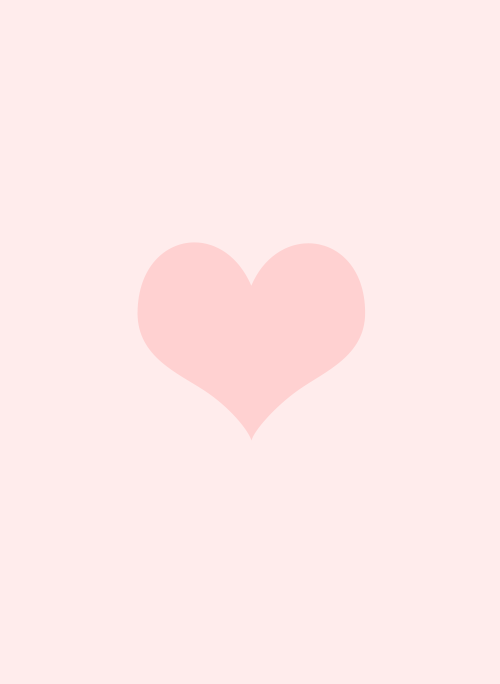七月八日のながれぼし
あたしはずっと、織姫と彦星が羨ましかった。
年に1度でも愛しい人に会える空の上の住人が、あたしにはもう2度と叶わない願いを叶えていることが妬ましくて苦しかった。
だけど違ったんだ。
あたしは失っていなかった。
遠い星の向こうに落ちたと思っていた流れ星は、本当は、あたしのそばにコトンと落ちていた。
空に流れる一筋の光。
大切な彼。大好きな彼。
あたしはやっと、あなたを見つけた。
「来年はあたし、ここに来ないから。受験生になるから、前からずっとそのつもりだった」
「……うん、わかっていたよ」
ああ、だから君の告白は今年だったんだ。
気づいていなかった理由に、あたしはなにもかも君に知られていたんだなぁと実感する。
「だから再来年、大学生になって、きっと会いに来て」
ふっと小さく息をもらして、彼に手を伸ばす。
昨日と違って今度は、そっと頰を包みこんだ。
「あたしは君を────光流を待っている」
彼は、くしゃりと泣きそうに笑った。
『もしも大人になったら。今度は迎えに行くのは俺だ』
そう言ったあんたはもういない。
あの日のあいつにはもう会えないけど、でもちゃんと光流はいる。
あたしの大好きな人は触れられない星ではないから。
あたしのそばで輝いているんだ。
星が空を流れ行く。
織姫の涙のように、彦星の誓いのように。
約束は、きっと果たされる。
fin.