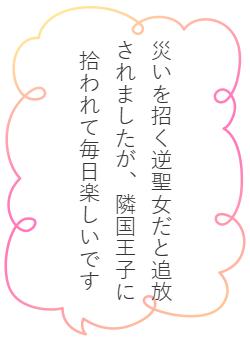隣国王子に婚約破棄されたのは構いませんが、義弟の後方彼氏面には困っています
24.元婚約者を返却しに来たら……驚きの事態になりました
魔物が寄ってくる迷惑なカイルを、親であるマルシェヴァ帝国の王に突き返すため、王城にやってきた。
まさか、再びここへ訪れることがあるとは思わなかったけれど。
カイルを連れているだけに、すんなりと国王との面会出来た。以前よりもさらに痩せているように見える。
「国王様、お久しぶりでございます」
「クリスティーナ殿、久しぶりだな」
国王の顔色は悪い。それはそうだろう。魔物と戦ってボロボロの私とアルバート、そして数人の討伐隊のメンバーに囲まれるように息子であるカイルがいるのだから。
「国王様にはお話があって参りました。カイル様のことですわ」
「……愚息が、また問題を起こしてしまった……のか」
「はい。魔物の卵を食べたそうです」
「はぁ?!」
国王様が驚きのあまり大声を出して、むせている。
あまり興奮して欲しくはないのだけれど、まぁ、魔物の卵を食べたなんて聞いたら驚くに決まっている。
「大丈夫です。どうやら頑丈らしく、お腹を壊した程度ですんだとのことですわ」
「そ、そうか」
「ですが、卵を食べたのは事実。臭いがするのか、魔物の群れからカイル様は狙われております。おかげで、カイル様がいらっしゃると魔物が寄ってきてとても迷惑ですの。ですから、国内でちゃんと面倒を見ていただきたいのです」
国王様はカイルを見た。カイルは気まずそうに俯く。それを見た国王様は大きなため息を付いた。
「愚息が本当に、申し訳ないことをした。カイルは責任を持って幽閉することを誓おう。イシュリア王国に迷惑をかけたことも心から謝罪する。賠償は、そちらの要求をすべてのむ」
「わたくしには賠償の話をするような権利はありません。別途、イシュリア王国から来る使節と協議になるかと。ですが、すべてなど簡単に口にしてはいけませんわ、国王様。下手をしたら国を明け渡すことになるやもしれません」
「それでも構わぬ。国を背負っていける人材がいないのだから。無能な人物を王に付けるくらいなら、イシュリア王国に下った方が国民のためになる」
国王様の悲痛な面持ちに、カイルを突き返しに来た勢いがしぼんでいく。
このような身勝手な息子を野放しにした国王様に、少し腹が立っていた。でも、この人は病に伏せりながらも結界を張り続けているのだ。息子のことまで気に掛けろというのは酷かもしれない。身内よりも国民を守ろうとしているこの人は、やはり立派な王様なのだろう。
そこに、国王様の後ろに控えていた宰相が恐る恐るといった様子で歩み出てきた。
「宰相、いかがした?」
国王様の問いに、宰相はビクッと肩をふるわせた。だが、決心したように顔を上げる。
「実は、前回からずっと気になっていたのです。クリスティーナ様のお連れの方が、もしや、あの方の忘れ形見では……と」
「忘れ形見……若くして亡くなった先代王のか?」
国王様と宰相の視線が、こちらに向けられる。だが、私ではなく、私の横に控えているアルバートに向かっていた。
「……は? 俺?」
アルバートは意味が分からないとばかりに、眉間にしわを寄せた。
「髪色といい瞳の色といい、年頃も生まれた男児と同じです。それに、母御である女性の面影があります」
急な話の展開についていけない。まさか、アルバートが隣国の先代王の忘れ形見だというの?
嫌だと思った。アルバートは、ずっと私の隣にいてくれないと嫌だ。マルシェヴァ帝国に渡したくなどない。きっと、宰相の勘違いに決まってる。
私は思わずアルバートの手を握った。アルバートは一瞬、驚いた様に固まったが、ちゃんと握り返してくれた。
大丈夫。アルバートはここにいる。私のところにいてくれる。
「だが宰相よ。それだけでは証拠にはならないだろう」
「あれからちゃんと調べたのです。先代王の側室はもとはローセン家に仕えていた女性で、たまたま先代王が隣国を訪れた際に見初めたのです。くわえて、男児を一番に生んだのも彼女だった。ですが、身分が低いがゆえに後ろ盾もなく、正妃や他の側室に目を付けられ、命を狙われた」
嫌だ。宰相の話すことがすべて、私の知らないアルバートの空白の過去をぴったりと埋めていく。
アルバートは確かに、女の人とやってきた。必死で逃げてきたのだと、女の人が説明しているのが聞こえた。そう、私は興味本位で兄と一緒に聞き耳を立てていたのだ。なんで聞いてしまったのだろう。聞かなければ良かった。そうすれば、今の話が嘘だって思えたのに。
怖くて、震えてくる。
やめて、私からアルバートを取らないで!
「クリスティーナ、大丈夫。俺はクリスティーナの隣にいるよ」
アルバートがそっとささやいてくる。その優しい響きに、強ばっていた心が少しだけほどけた。
「ちょっと良いですか」
アルバートが声をあげた。
「俺は確かにローセン家に養子として引き取られている。状況的にこの国から亡命した子どもの可能性は高いと思う。だが、それが分かったとして、あなた方はどうしたいんだ?」
アルバートの問いかけに、宰相と国王様が顔を見合わせた。そして、国王様が口を開いた。
「そなたが望むなら、我が国の王族として迎え入れよう」
「俺が望まなかったら?」
「無理強いするつもりはない。ただ、クリスティーナ殿が信頼しているそなただ、きっと人柄も良いのだろう。出来たら、我が国に来て欲しいとは思っている」
「つまり……俺を次期国王として見ている、と思っていいのか?」
「そうだな。わたしは親としては失格だが、王としてはそれなりに人を見抜く自信はある。クリスティーナ殿を次代の王妃にと選んだのも、わたしの王としての目だ」
国王様とアルバートは、お互いの腹を探り合っているような厳しい顔をしている。だが、アルバートが先に表情を緩めた。
「クリスティーナのすごさを見抜いたとか言われてしまうと、俺は信じるしかなくなっちゃうんだよなぁ」
独り言のように、アルバートは言葉を吐き出す。
「アルバート? もしかして、マルシェヴァ帝国に行く気なの?」
「そんなに不安そうな顔しないでよ。言っただろ、俺はクリスティーナの隣を離れるつもりはないって」
「じゃあ、さっきの言葉はなに?」
アルバートが何を考えているのか分からない。私の隣にいるって言うけれど、不安でたまらない。
「嫌よ、アルバート。わたくしの隣にずっといてよ」
「クリスティーナ。あぁ泣かないで」
アルバートの指が、目元をそっとぬぐっていく。気付かぬうちに泣いてしまっていたらしい。こんな人前で泣くだなんて恥ずかしいけれど、でも、止められない。
「クリスティーナ。ずっと、ずっと前からクリスティーナだけが好きなんだ。だから、俺は弟としてではなく、夫として君の隣にいたい」
今、好きって言われた。
いつも言われていたのに、全然違って聞こえるのは何故だろう。
アルバートの言葉に、いろんな小難しいことが飛び去っていく。
弟とか、姉離れとか、隣国の王族とか……そんなものは一気に空の彼方だ。
アルバートが片膝を付いて、私の手を取った。
「俺と、結婚してください」
まっすぐにアルバートが見上げてくる。そのきらきらとした眼差しに、胸が熱くなる。嬉しくて、でも気恥ずかしくもあって、どうしようと叫びだしてしまいそう。
「……わたくしで、いいのですか?」
「もちろん。クリスティーナじゃないと、俺は一生独身だよ」
「そ、それは、困りますわ」
「だろ? だからさ、観念して俺と結婚してよ」
アルバートがいつもの子犬のような顔で、私が絆されるのを待っている。
殿方のような顔と、弟の顔を両方使ってくるだなんてずるい。
でも、それがアルバートなのだ。私の可愛い弟で、私をときめかせる殿方でもある。
「ふふっ、しょうがない子ね。いいわ、結婚しましょう」
「やった!! やったぞ! な、聞いてた?」
アルバートは嬉しさが抑えきれない様子で、周囲に同意を求めていく。
恥ずかしいからちょっと落ち着いて欲しい。でも、喜びを爆発させているアルバートはとても可愛くて、愛しいなと思った。
***
私は結局、隣国王子に嫁ぐことになった。相手はもちろんカイルではない。可愛くて頼りになるアルバートだ。
「アルバートは王様とか興味がないと思っていましたわ」
今はイシュリア王国に帰る馬車の中だ。実は病の重かった国王様には、真奈美様から受け取っていた回復薬を渡したのだ。病によって体力が削られているところに、結界を張り続ける負担が重なり、治癒が追いついていなかったのだ。だが、回復薬のおかげでだいぶ体調も良くなり安定したため、ひとまずは報告も兼ねて自国へ帰ろうということになった。
「そう? 好きな相手を手に入れるためには最高の位だからね」
「えっ……まさか、そんな理由でマルシェヴァ帝国の王子になることにしたの?」
「もちろんだよ」
「呆れた! ちょっとこれは婚約破棄よ。マルシェヴァ帝国の皆さまに申し訳ないわ」
「待って待って、落ち着いてよクリスティーナ。確かにクリスティーナを他の男に取られたくなくて、高い地位が欲しいと思ったのは事実だよ。でも、やるからにはちゃんと責任は果たす。そうしなきゃクリスティーナに愛想を尽かされるって分かってるから」
「本当に、ちゃんとやる気はあるのね?」
「もちろん! クリスティーナがいてくれるんだ、どんな困難だって乗り越えられる自信しか無い!」
調子よく宣言するアルバートに、思わず笑ってしまう。
でも、そうだなと思った。
私も、アルバートがいてくれるのなら、きっとどんな困難だって乗り越えられると思う。
だから、アルバートとこれからも一緒に進んでいきたい。
「アルバート、わたくしのそばにいてくれて、本当にありがとう」
私はそっと、アルバートの手をにぎる。
「クリスティーナ……、その、我が儘言って良い?」
アルバートがうるうるとした瞳で私を見つめてくる。相変わらず可愛い。どんな我が儘でも聞いてあげたくなってしまう。
「ええ、もちろん」
「キスしたい」
「キス?!」
子犬のようなうるうるとした瞳が、いつのまにか熱っぽさを伴っていた。
じぃっと見つめられ、逃がさないとばかりに背中に手が回ってくる。
どうしよう。キスなどしたことがないのに。
「ねえ、ダメ?」
アルバートが顔を寄せて、耳元でささやく。
吐息の熱さに、火傷してしまいそう。
「だめ……ではないわ」
「本当? 嬉しい!」
アルバートが幸せそうに目を細める。
あぁ、彼は幸せなんだ。
いろんなことがめまぐるしく変わったけれど、私にとっての幸せも、ずっと隣にあったんだ。
お互いがお互いの幸せになれるって、なんて素敵な奇跡なんだろう。
私はそんな奇跡に感謝しつつ、そっと目を閉じたのだった。
【了】