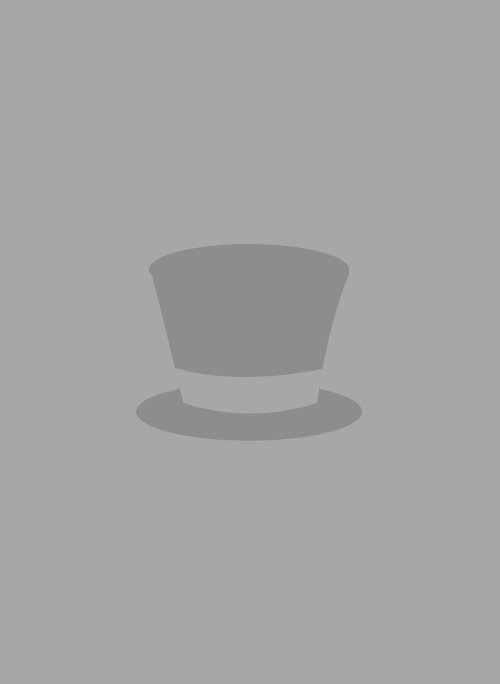マングス
1
向高利夫はまだ25歳の若者だが、既に深く自分の人生に絶望していた。
両親もかなり以前に他界しており、何とかバイトで食いつないで、大学を卒業したものの、就職試験に幾つも失敗した。
彼は酷い妄想に悩まされていて、現実との区別がつかない譫妄状態にあった。
重度の引きこもりになり、アパートの部屋は何時かゴミ屋敷に変わった。
彼は深刻に自殺を考えていた。
その日、向高は昨晩の睡眠が足りず、鬱の気分重圧は甚だしかった。
午前中は始終不快な微睡みの裡にあった。昼食の菓子パンを貧しく食べ終わった折りのこと、不意に玄関のブザーが鳴った。
「はい、何方?」
「向高利夫さんのお宅でしょうか」
「そうですが、どちら様ですか」
「済みません、ちょっと貴方に用事がありますので」
向高は玄関のドアを開けた。
銀髪、長身、分厚い金縁眼鏡の男が立っていた。年齢は50歳位だろうか。
「私は李贄と言います。少し貴方にお話があるのですが」
「外国の方ですか。どのような御用件でしょう?」
「何、直ぐ済みます。私はこういう者です」
男は名刺を手渡した。李贄、鹿児島科学大学大学院教授と書かれていた。
「大学の教授ですか、僕などに何の御用が」
「ちょっとお話したいんです。上がっても宜しいですか」
「ええ、どうぞ、汚い部屋ですけど」
小さな卓を挟んで、フローリングに対座した。座布団の如きものはなかった。
「早速ですが」教授は言った。「貴方の卒論を拝読致しました」
「僕はお宅の大学とは無関係ですけど」
「知り合いの教授が居りましてね、一寸面白い論文があるから、読んでみないかと持ちかけられまして」
「で、まさかあれに対する先生の評価は高いんですか」
「そうですね、先ず高いと言って良いでしょう」
向高は驚嘆した。
「まさか。ウズベク、チンギスハーンの子孫。ですよ」
「あれは文化人類学の論文でしたね」
「担当教授から、単なる妄想とこっぴどく酷評されたんです」
「そうですか、ウズベク人、サルトの男系がチンギスハーンの子孫であることを述べて、彼らが現在、第三の元寇を計画しているという仮説を論じていますね」
「もう滅茶苦茶でしょう。自分でも酷い妄想と思います」
「それは私も否定しません。しかし中々面白いんです」
「そうですかね」
「論文の内容ではなく、その柔軟な発想がです。中々あれは出来るものではありません」
「いや、驚きます。褒められたことなんて、一度もない」
「環境が貴方に合わなかったのでしょう。ウチの大学、私は未来デザイン学部ですが、清新な才能を求めております」
「妄想でもいいということなんでしょうか」
「いえ、勿論これからは妄想では困ります。唯、貴方の飛翔する発想力を私の大学院で試してみられませんか」
「勧誘ですか」
「そうです」
「驚きましたね。でも入試に受かる自信はありません」
「入試は、研究計画書の提出だけで大丈夫です。何も難しいことはありません」
「夢のようだな、でも駄目ですね」
「何故ですか」
「僕は私立の学費を工面出来ません。両親も既に他界してますし」
「奨学金を申請なされば」
「返済の自信はありません。就職試験は多数落ちてます」
「大学に残れば良いじゃありませんか」
「僕は好成績を残せますか」
「一緒に未来をデザインしていきませんか。貴方なら可能性はありますよ」
「矢張り、夢のような話にしか聞こえない。申し訳ないんですが」
「夢を実現なされば。遣ってみる価値はありますよ」
向高は嘆息した。
「済みません、少し考えさせて下さい」
「結構です」
教授は立ち上がった。
「気が変わったら、何時でも私のところに電話を下さい。入学案内を送ります」
「有難うございます」
李贄が帰ると、未だ向高の胸はときめいていた。厭になる絶望が幾分希薄になったようだった。
2
向高の気持ちはほぼ承諾にかたむいていた。もうあと一押しで、院生になる決心は確定しそうだった。
彼は独り自然にほくそ笑んだ。
丁度その折り、矢庭にスマホが鳴った。相手は叔父の向高卓也だった。
かなり長期間連絡のとれない親戚で、突然の電話は奇妙とも言えた。
「利夫かね。私だ、卓也」
「嗚呼、叔父さん、ご無沙汰しております」
「本当に久しぶりだな」
「ええ」
「長い間、冷たくあしらって済まなかったな」
「いいえ、そんなことないです。普通と思っています。唯、僕が引きこもりしているだけで」
「久しぶりに会って、飯でも一緒に食べないか」
「えっ、良いんですか。僕は無一文……」
「勿論私が奢る」
「悪いですね」
「構わないよ。これからアパート迄迎えに行くから」
「車ですね」
「ああ、前の車、未だ乗っている。それじゃ、30分後に」
「はい、有難うございます」
電話が切れると、向高は準備に取り掛かった。最低限髭位剃らなくてはならないし、蓬髪を櫛で纏めなくてはと思った。
天涯孤独の筈の境涯を、彼は忘れていた。話の奇妙な歪みに全く気付かなかった。
きっかり30分後に、叔父は現れた。
利夫は車の助手席に乗った。
「実はな、ホテルを予約してある」
「ホテルのレストランですか。何も其処まで高級でなくても」
「いいんだよ。久しぶりじゃないか」
「そうですか、済みません」
中央駅近くの、とあるホテルの駐車場に入り込んだ。
叔父は大分老けていた。外出先で出会っても、直ぐには分からないくらい、容貌は激変していた。
二人は高級レストランの予約席に座った。
メニューはどれも高額だった。
「御前、ステーキを食べろよ。私は金目鯛のステーキにするが」
「はい、本当に良いんですか」
「無論だ」
二人は料理を注文した。
「ところで御前、健康には気を付けているか」
「いいえ、全然」
「そんなことじゃ困るな。御前は我々の希望の光なんだ」
「何ですって。どういう意味です。我々とは誰なんですか」
「いや、此方の話だ。まあ、いい」
「気になりますね。仰有って頂けませんか」
「うむ、勿論その話をするために、御前を呼んだのだが」
「何の御話ですか」
叔父は急に深刻な表情に変わった。
「実はな、御前に折り入って頼みがある」
「何でしょう」
「はっきり言おう。一緒に或る病院に来て欲しい」
「病院……」
「来れば分かる。是非ともお願いしたい」
「僕は何かの病気なんですか」
「いや、御前は病気ではない。それどころか、私達の唯一の希望だ」
「仰有る意味が分かりません」
「大変済まないが、或る手術を受けて貰いたい」
「手術とは、一体何の」
「脳外科だ」
「脳外科手術、そんな……」
「頼む、私達の希望を実現するためなんだ」
「先程から仰有っている、希望とは何のことですか」
叔父は表情を硬化させた。
「それは言えない。未だ打ち明ける段階にない」
「そんな、訳も判らず、脳外科手術なんて」
「怖がる必要はない。直ぐに済む。それが終われば限りない未来が開けるんだ」
「意味不明ですね、率直に申し上げて」
「嫌かね」
「当然でしょう」
「そうなると、強制しなくてはならない」
「分かりません。脳外科手術の強制なんて聞いたことない。精神科の措置入院でもあるまいし」
「どうしても嫌かね」
「嫌です。第一僕は病気ではないんでしょう」
「その通りだ」
「なら、矢張り意味不明じゃないですか」
叔父の背後に、何処から現れたか、二人の黒スーツにサングラスの男達が来た。
向高は驚嘆した。
「何ですか、貴方達は」
「だから利夫、私は強制したくないんだ」
「分かりません、何もかも分からない」
二人の黒スーツの男が、利夫の背後に回り込み、両肩を掴んだ。
「何をする、離せ」
二人の男達が、向高を羽交い締めにした。
向高はウェイターを呼び止めた。
「警察を呼んでくれ、頼む……」
ウェイターは、驚き、大急ぎで店の奥に入って行った。
「此方こそ頼む、利夫、言うことを素直に聞いてくれ」
「嫌です」
向高は、二人の男を振り払った。彼としては余り力を込めた積もりもなかったが、二人は容易く床に転がった。
向高は、自分の力に自分で驚愕した。
「僕はどうしたんだ」
「だから言ったろう。御前は希望の光なのだ」
向高は、起き上がってきた男達双方に、蹴りを一発ずつ入れた。二人はもう立ち上がれない程のダメージを受けた様子だった。
それもまた、向高自身思いもよらぬ剛力なのだった。
「利夫、頼む。御前に力で勝てるとは思わない。だから、御前の力を完璧なものにするために、手術を受けてくれないか」
「これは何なんだ」
向高はもうこの場は逃げるしかないと、咄嗟に判断した。レストランの出口の方へ、一目散に駆け出した。
客達が好気の眼で彼を注視していた。
追っ手が来るかもしれない。彼は全速で逃走した。
ホテルの玄関ホールで、大柱に背をもたれている独りの男が、向高に鋭い視線を投げた。
男は立った儘、新聞を読んでいた風だったが、新聞を投げ捨てた。
「貴様、向高利夫だな」
「御前こそ何だ」
男は背広のポケットに入れていた片手を素速く出した。その手には黒光りする拳銃が握られていた。
向高は前かがみに伏せた。
「覚悟しろ」
拳銃が火を吹いた。後方の硝子の自動ドアが粉砕された。
更に一発の銃撃。外の乗用車の窓硝子が蜘蛛の巣状に割れた。
向高は態勢を戻すと、一発右ストレートを繰り出した。男の手に握られていた拳銃が吹き飛んだ。
向高は冷静に、更なるパンチを男に見舞った。アッパーは男の顎の骨を砕いた。
利夫はもう後を振り返らなかった。
ホテルを出て、街路を駆け出した。呼吸は多少苦しかったが、信じがたい速度で走っていた。
歩道を駆けながら、猛烈に嘔吐が込み上げた。路肩に吐いた。
或いは、人を殺したかもしれなかった。しかし、正当防衛に違いなかった。
タクシーに乗りたかったが、無一文に変わりはない。バス停に駆け込むと、丁度来たバスに飛び乗った。何処行きなど、確認する余裕はなかった。
最後尾の席に座った。小銭ならあった。車窓は見慣れた街並みながら、今は全く違って見えた。小銭入れには幸い数枚の千円札があった。週末を過ごすために、貯めておいた金だった。
思考は酷く混乱していた。
向高は、何処へ逃げれば良いのか全く解らなかった。何処か独りになれて、安全な場所、思い当たる処はない。
鹿児島大学水産学部が遠目に見えた。それで漸く、このバスが鴨池港行きと悟った。
近くに、以前来たネットカフェがあるのを思い出した。一時潜伏するには好都合に思われた。
水産学部前でバスを降りた。
ネットカフェに入った。カードは未だ所持していた。若い店員は希望の席を尋ねた。
「兎に角、奥に目立たない席はないかな」
店員は無表情に、一番奥のブースをスキャンした。店員としては、AVでも観るのかと思ったかもしれなかった。
コップにアイスコーヒーをなみなみ注ぎ、足早にブースへ急いだ。
パソコン画面の前のソファーに、死んだようにぐったり横たわった。
顔を上げると、四角形のディスプレイがぐにゃりと楕円に歪んだ。甲高い耳鳴りが聞こえる。
嗚呼、また幻覚が始まると思った。キーボードがみるみる卓上に溶解していった。
透明の川魚が眼前を泳いでいた。空気の本流は縦に滝のように流された。
遠くて、淫靡な夜が彼方の大海から、一艘の帆船を伴い、不恰好に彎曲する方眼紙となり、無重力のようにリモコンを浮遊させる。
展開の甚だしいサッカーグランドが、狭いブースに不可思議に侵入。フォワードは唯ボールに向けて疾駆。
数奇な運命のポーランド侵攻は錫の架け橋となり、飽くまで冷血に己の自尊心を持続可能なエナジーで満たし、トンネルの暗澹たるテーマパークは勇敢なる恋人たちの束の間の陽明学。
聞こえる声は未だ続く。浪人した崇高な記者会見に危険な性向で全巻解説。鋭い爪に光輝は仇となり数万人規模のメタルスラッシュ。
法律を粉砕せよと賢者は宣う写真流された映像情報提供、パソコン画面に今正に、独りの女神が顕在化した。
「死を覚悟しなさい。夜半には虐殺が始まります」
「抵抗勢力は無益に荼毘に付するのですか」
「洋紅、溶鉱、たまさかなる絶叫の真意を問いなさい」
「例え生まれ変わるとしても、貴女の傍では慟哭し得ない」
「例え盲目を享受しても、秘めたる内面へ貢いでいくのです」
「空港、未だ無益に貧困を淵源から相剋出来ない」
「魂よ、総ては。スパイの瞳孔に明け方の明星を」
「言い分を聴かない女神に只管乾杯……」
3
ネットカフェのトイレで、向高は頭から水を被った。未だ酷い頭痛に悩まされていた。漸く眼が醒めた。
総てが夢だったような気がした。実は何も起こらなかったのではないのか。ブースに戻ると、テレビを付けた。
MBCがローカルニュースを放送していた。
「……本日午後1時半、中央町のホテルハイアットで、発砲事件がありました。幸い銃撃による怪我人はありませんでした。発砲したのは元自衛隊員、野村重雄、36歳。彼は顎を骨折しており、重傷。彼を殴ったのは向高利夫、25歳。向高は現在市内を逃走中……」
向高はスマホを取り出した。一瞬躊躇したものの、矢張り叔父にコールした。
「叔父さん」
「利夫か、今何処だ」
「それは言えません」
「私を信頼してほしい。自衛隊員から襲撃されたろう。御前は一人では危険だ」
「叔父さんも同じ穴のむじなでは」
「それは違う。私は御前に危害を加えたりしない」
「でも脳外科手術をすると」
「それは御前自身のためだ。手術によって、御前の能力は飛躍的に向上する。それは約束する」
「矢張り嫌です」
「御前に選択肢はない。今の儘ではいずれ殺される」
「……」
「今、何処に居るんだ。迎えに行くよ。それが生き延びる唯一の道なんだ」
「総てが悪夢のようだ」
「人生は夢だ。だがこれは動かし難い現実。何処に居るんだ」
「水産学部前のネットカフェです」
「鴨池新町から近いな。鴨池は官庁街だ。自由党本部も、我が希望の光党の本部もある」
「希望の光党、それが叔父さんの仰有る我々ですか」
「そうだ、其処まで近い。直ぐ迎えに行く」
「叔父さんが来る?」
「いや、希望の光党首の江原氏が行く。丁度選挙カーがその付近に居る」
「分かりました。待ってます」
「一つ警告だ。今直ぐに携帯電話を捨てろ。GPSで敵に位置を悟られる」
「了解」
その時、近くで爆発音が聞こえた。銃声に違いなかった。
直ぐさま床に転がり、床を這った。
続けて、銃声と悲鳴が聞こえた。スマホを反対方向の奥に投げ捨てた。
弾の雨が、スマホの方向に轟々と流れた。
向高は、ほふく前進で出口迄這った。
外に出た。丁度其処に選挙カーが到着した。
向高は選挙カーに飛び乗った。
後部座席に、選挙の鉢巻きを締めた人物が居た。
「私が江原です。利夫さんですね」
「ええ」
選挙カーは急発進した。追っ手は装甲車に乗り込んだ。
選挙カーは制限速度ぎりぎりで走った。
江原は言った。
「現実にはカーチェイスなんて不可能です。警察に捕まるだけですからね」
「しかし、逃げ切れるんですか」
「此処から近い、緑地公園迄行けば大丈夫です」
向高は首を傾げた。
「緑地公園迄行って、それでどうするんですか」
「今は説明している暇はありません」
後方の装甲車から、発砲してきた。
「伏せて……」
選挙カー後部の窓硝子が割れた。
「此処で死ぬ訳にはいかない」
江原は強気でマイクを手にした。
「皆さん、大変お騒がせしております。希望の光党の党首、江原です。皆様、希望の光党は、長期の自由党政権を打破し、新しい日本を、皆様と一緒に創造してまいります」
銃弾が選挙カーのバックミラーを破壊した。
「皆様、次期総選挙では何とぞ、希望の光党に清き一票をお願い致します……」
装甲車が選挙カーの後部にぶち当たった。後部のバンパーが潰れ、車は大きく揺れた。
江原はマイクを置いた。
「駄目だな、緑地公園迄持ちそうにない」
江原はスマホを手にした。
「向高さん、聞こえますか」
叔父に電話したらしかった。
「到底、緑地公園迄行けそうにない。今、此処で、路上で救助をお願いしたい」
装甲車が再度後方からぶつかってきた。
「この選挙カーが見えますか?見える。それなら、無理なお願いかもしれないが、降りてきて下さい」
「速度を選挙カーと合わせて、縄梯子の用意を……」
上空で、激しい機械音が聞こえた。ヘリコプターが選挙カー上部に降りてきたのだった。
「それでは利夫さん、ドアを開けて、降りてくる縄梯子に掴まって下さい」
「何ですって」
「かなりのアクロバットながら、貴方なら可能だ。此処からヘリコプターに攀じ登って頂きたい」
「分かりました」
利夫は言われる儘、走行中のドアを開いた。縄梯子が上から降りてきた。
「掴まって、拳銃に気をつけて」
向高は縄梯子に飛び乗った。ヘリコプターが併走し、縄梯子を引き上げる。
銃弾が頬を掠めた。向高は構わず、登っていった。
どうにかヘリコプターに乗り込んだ。
ヘリは青空高く上昇していく。
利夫は、ヘリコプター内で、叔父の隣に座った。ヘリの回転音は煩いものの、会話は可能だった。
「有難うございました。命の恩人だ」
「うむ」
「もう教えてくれて良いでしょう。僕は一体何なんですか」
「御前は謂わば怪物兵器だ」
「怪物?どんな」
「謂わばマングスだろう」
「マングスとは何です」
「頭が12個ある、モンゴルの妖怪だ」
「モンゴル。まさか、僕の論文、第三の元寇が起きるが、現実化した訳ではないでしょう」
叔父は、その質問には返答しなかった。
「僕の予言が的中したのではなく、僕自身がマングスだった」
「その通りだ」
「希望の光党は左翼ですよね」
「そうだ」
「恐らく共産党以上に」
「……」
「これからテロでも起きるんですか。僕が命を狙われるということは」
「御前は自分の使命を果たせばいい。それが何と呼ばれても、他人の勝手だ」
「僕の使命とは」
「先ず手術を受ける」
ヘリの爆音の中での小声の会話だった。二人はそれから沈黙した。
ヘリコプターは青空の中、大きく旋回した。
4
東京、世田谷区、白百合幼稚園の前。園児達が大勢帰宅している最中だった。
東亜リサの母親は、娘を迎えに行く途中だった。電信柱の前まで来た際に、ふと立ち止まった。
不意に電信柱の影から何者かが現れた。野球帽を被った男だった。
男は、母親の背後に回った。後ろから、彼女の口にハンカチを押し当てた。彼女の意識は遠退いていく。
母親は、電信柱の影に倒れた。目撃者は一人も居なかった。
野球帽の男は、向高利夫だった。
幼稚園の玄関口前、リサは母親が迎えに来ないので、当惑していた。
リサは半分泣きそうになっていた。
野球帽の向高は、リサに近寄った。
「リサさんだね」
「はい」
「ごめんね、遅れて、お母さんちょっと用事が出来たんだ」
「ご用事?」
「うん、だから小父さんが代わりに迎えに行ってくれと頼まれたんだ」
リサは、少し警戒の表情を浮かべた。
「でも、ママが知らない人について行ったらいけないって」
「小父さんは大丈夫だよ。ママに頼まれたんだから」
「でも……」
「さあ、お人形をあげよう」
向高は、リサに西洋人形を手渡した。
「さあ、一緒に帰ろう。ママが待っているよ」
リサは渋々、向高について行った。
その日の夜。東亜重工業専務、東亜信光は会社から帰宅途中だった。東亜は、中々迎えの車が来ないので、苛々していた。
20分程待って、漸くいつもの車が、東亜の目の前に停車した。
東亜は車に乗り込むと、お抱え運転手に文句を言った。
「どうした?何故遅れた」
その時になって、東亜は、運転帽を被った運転手が別人であることに気付いた。
「誰だ、貴様は」
運転手は無言の儘、車をスタートさせた。全ドアが非情にロックされた。
「何だ、ドアを開けろ。車を間違った」
「間違ってはいません。いつもの車です」
「貴様は誰だ」
「向高利夫と申します」
車は人通りの少ない路肩に停車した。
向高は、後部座席に振り向いた。
東亜は、スマホを取り出して、110番に電話しようとした。
「東亜さん、お待ちください」
「何だ?」
「これを御覧下さい」
向高は、東亜にスマホをかざした。
スマホ画面はライン電話で、東亜の娘、リサが映っていた。
「リサ、どうした?大丈夫か」
「パパ、私は大丈夫よ。小父さん達、皆優しいわ」
「リサ、何処に居るんだ」
「分からない。ママが中々来てくれないの」
「リサ、まさか何かされたのか」
「ううん、皆優しいわ」
向高は、ライン電話を切った。
「向高と言ったな。何が望みだ」
「日本の大会社、東亜重工業と政治家達の大規模な贈収賄……」
「何だと」
「贈収賄事件の情報をリークして頂けませんか」
「……」
「お願い致します」
「第二のロッキード事件になるぞ」
「承知しております」
「与党、自由党を始め、全政党が絡んでくる」
「希望の光党以外です」
「総選挙直前だ。どうなると思う」
「この国の未来が変わります」
「それを私に遣れと言うのか」
「貴方は断れない」
「ううむ……」
何処か遠方で、パトカーのサイレンが鳴り響いていた。
5
向高は、茫然自失で、渋谷の街を彷徨っていた。頭痛は極限に達していた。
雑踏の流れの裡で、彼は立ち止まった。
再び視界が歪み始めた。
嗚呼、また幻覚が始まると思った。
とある店舗のショーウインドウの前に佇んだ。硝子に彼の姿が映っていた。
向高の両肩に、幾つもの頭が生えていた。幻覚なのか、現実なのか、区別はつかなかった。
つまりは自分は妖怪なのか。それでいいのか。自分に人間の要素はもう残っていないのか。
その折り、彼は路上で呼び止められた。
「向高君じゃないか」
見ると、相手は李贄教授だった。
「貴方はあの科学大学の教授……」
「こんな所で会うとは奇遇だな」
「何故東京に?」
「学会があってね、君こそどうして」
「しらばっくれないでください。貴方は全部ご存知なんでしょう」
教授は表情を硬化させた。
「まあな」
「僕のことを総てご存知ですね」
「知っている」
「大学勧誘なんてデタラメだった」
「そうだ」
「教授、僕に協力してくれませんか」
「どんな協力を」
「この美しい日本が侵略を受けます」
「だろうね」
「それでいいんですか」
「私は日本人ではない。日本は、先の戦争で南京虐殺を行った」
「そんなこと、現代からではもう、事実かどうか分からないではないですか」
「……」
「僕に協力してくれませんか。貴方を研究者として育てたこの国が今壊れかけている」
教授は暫し沈黙したが、やがて口を開いた。
「私に何をして欲しい?」
「サイバーテロです。貴方なら可能でしょう」
「サイバーテロ」
「ええ、総ての報道機関に、システム障害を生じさせて頂きたい」
教授は躊躇したものの、ゆっくり頷いた。
6
向高は再び、渋谷の街を歩いた。
イヤホンで、携帯ラジオを聴いていた。
「……総選挙では、与党自由党は矢張り再び過半数の票を獲得しました……」
向高は、ラジオを投げ捨てた。
向高は、ポケットから拳銃を取り出した。
誰でも構わなかった。近くに居た女性を、後ろから羽交い締めにして、頭に拳銃を突きつけた。
「ぶっ殺すぞ、警察を呼べ」
街は騒然となった。
警官が3人、駆け付けてきた。
「貴様、拳銃を捨てろ」
警官が声高に警告した。
向高は、女性を離した。警官に銃口を向けた。
警官が続けて発砲した。向高の胸に三発命中した。
向高は苦しげに呻いたが、未だ立っていた。
警官達は、信じがたい恐怖に怯えた。
更に何発も、向高に発砲した。
向高は血塗れになり、叫んだ。
「天皇陛下、万歳……」
本作品はフィクションです。登場する人物、団体は現実のものとは一切関係ありません。
向高利夫はまだ25歳の若者だが、既に深く自分の人生に絶望していた。
両親もかなり以前に他界しており、何とかバイトで食いつないで、大学を卒業したものの、就職試験に幾つも失敗した。
彼は酷い妄想に悩まされていて、現実との区別がつかない譫妄状態にあった。
重度の引きこもりになり、アパートの部屋は何時かゴミ屋敷に変わった。
彼は深刻に自殺を考えていた。
その日、向高は昨晩の睡眠が足りず、鬱の気分重圧は甚だしかった。
午前中は始終不快な微睡みの裡にあった。昼食の菓子パンを貧しく食べ終わった折りのこと、不意に玄関のブザーが鳴った。
「はい、何方?」
「向高利夫さんのお宅でしょうか」
「そうですが、どちら様ですか」
「済みません、ちょっと貴方に用事がありますので」
向高は玄関のドアを開けた。
銀髪、長身、分厚い金縁眼鏡の男が立っていた。年齢は50歳位だろうか。
「私は李贄と言います。少し貴方にお話があるのですが」
「外国の方ですか。どのような御用件でしょう?」
「何、直ぐ済みます。私はこういう者です」
男は名刺を手渡した。李贄、鹿児島科学大学大学院教授と書かれていた。
「大学の教授ですか、僕などに何の御用が」
「ちょっとお話したいんです。上がっても宜しいですか」
「ええ、どうぞ、汚い部屋ですけど」
小さな卓を挟んで、フローリングに対座した。座布団の如きものはなかった。
「早速ですが」教授は言った。「貴方の卒論を拝読致しました」
「僕はお宅の大学とは無関係ですけど」
「知り合いの教授が居りましてね、一寸面白い論文があるから、読んでみないかと持ちかけられまして」
「で、まさかあれに対する先生の評価は高いんですか」
「そうですね、先ず高いと言って良いでしょう」
向高は驚嘆した。
「まさか。ウズベク、チンギスハーンの子孫。ですよ」
「あれは文化人類学の論文でしたね」
「担当教授から、単なる妄想とこっぴどく酷評されたんです」
「そうですか、ウズベク人、サルトの男系がチンギスハーンの子孫であることを述べて、彼らが現在、第三の元寇を計画しているという仮説を論じていますね」
「もう滅茶苦茶でしょう。自分でも酷い妄想と思います」
「それは私も否定しません。しかし中々面白いんです」
「そうですかね」
「論文の内容ではなく、その柔軟な発想がです。中々あれは出来るものではありません」
「いや、驚きます。褒められたことなんて、一度もない」
「環境が貴方に合わなかったのでしょう。ウチの大学、私は未来デザイン学部ですが、清新な才能を求めております」
「妄想でもいいということなんでしょうか」
「いえ、勿論これからは妄想では困ります。唯、貴方の飛翔する発想力を私の大学院で試してみられませんか」
「勧誘ですか」
「そうです」
「驚きましたね。でも入試に受かる自信はありません」
「入試は、研究計画書の提出だけで大丈夫です。何も難しいことはありません」
「夢のようだな、でも駄目ですね」
「何故ですか」
「僕は私立の学費を工面出来ません。両親も既に他界してますし」
「奨学金を申請なされば」
「返済の自信はありません。就職試験は多数落ちてます」
「大学に残れば良いじゃありませんか」
「僕は好成績を残せますか」
「一緒に未来をデザインしていきませんか。貴方なら可能性はありますよ」
「矢張り、夢のような話にしか聞こえない。申し訳ないんですが」
「夢を実現なされば。遣ってみる価値はありますよ」
向高は嘆息した。
「済みません、少し考えさせて下さい」
「結構です」
教授は立ち上がった。
「気が変わったら、何時でも私のところに電話を下さい。入学案内を送ります」
「有難うございます」
李贄が帰ると、未だ向高の胸はときめいていた。厭になる絶望が幾分希薄になったようだった。
2
向高の気持ちはほぼ承諾にかたむいていた。もうあと一押しで、院生になる決心は確定しそうだった。
彼は独り自然にほくそ笑んだ。
丁度その折り、矢庭にスマホが鳴った。相手は叔父の向高卓也だった。
かなり長期間連絡のとれない親戚で、突然の電話は奇妙とも言えた。
「利夫かね。私だ、卓也」
「嗚呼、叔父さん、ご無沙汰しております」
「本当に久しぶりだな」
「ええ」
「長い間、冷たくあしらって済まなかったな」
「いいえ、そんなことないです。普通と思っています。唯、僕が引きこもりしているだけで」
「久しぶりに会って、飯でも一緒に食べないか」
「えっ、良いんですか。僕は無一文……」
「勿論私が奢る」
「悪いですね」
「構わないよ。これからアパート迄迎えに行くから」
「車ですね」
「ああ、前の車、未だ乗っている。それじゃ、30分後に」
「はい、有難うございます」
電話が切れると、向高は準備に取り掛かった。最低限髭位剃らなくてはならないし、蓬髪を櫛で纏めなくてはと思った。
天涯孤独の筈の境涯を、彼は忘れていた。話の奇妙な歪みに全く気付かなかった。
きっかり30分後に、叔父は現れた。
利夫は車の助手席に乗った。
「実はな、ホテルを予約してある」
「ホテルのレストランですか。何も其処まで高級でなくても」
「いいんだよ。久しぶりじゃないか」
「そうですか、済みません」
中央駅近くの、とあるホテルの駐車場に入り込んだ。
叔父は大分老けていた。外出先で出会っても、直ぐには分からないくらい、容貌は激変していた。
二人は高級レストランの予約席に座った。
メニューはどれも高額だった。
「御前、ステーキを食べろよ。私は金目鯛のステーキにするが」
「はい、本当に良いんですか」
「無論だ」
二人は料理を注文した。
「ところで御前、健康には気を付けているか」
「いいえ、全然」
「そんなことじゃ困るな。御前は我々の希望の光なんだ」
「何ですって。どういう意味です。我々とは誰なんですか」
「いや、此方の話だ。まあ、いい」
「気になりますね。仰有って頂けませんか」
「うむ、勿論その話をするために、御前を呼んだのだが」
「何の御話ですか」
叔父は急に深刻な表情に変わった。
「実はな、御前に折り入って頼みがある」
「何でしょう」
「はっきり言おう。一緒に或る病院に来て欲しい」
「病院……」
「来れば分かる。是非ともお願いしたい」
「僕は何かの病気なんですか」
「いや、御前は病気ではない。それどころか、私達の唯一の希望だ」
「仰有る意味が分かりません」
「大変済まないが、或る手術を受けて貰いたい」
「手術とは、一体何の」
「脳外科だ」
「脳外科手術、そんな……」
「頼む、私達の希望を実現するためなんだ」
「先程から仰有っている、希望とは何のことですか」
叔父は表情を硬化させた。
「それは言えない。未だ打ち明ける段階にない」
「そんな、訳も判らず、脳外科手術なんて」
「怖がる必要はない。直ぐに済む。それが終われば限りない未来が開けるんだ」
「意味不明ですね、率直に申し上げて」
「嫌かね」
「当然でしょう」
「そうなると、強制しなくてはならない」
「分かりません。脳外科手術の強制なんて聞いたことない。精神科の措置入院でもあるまいし」
「どうしても嫌かね」
「嫌です。第一僕は病気ではないんでしょう」
「その通りだ」
「なら、矢張り意味不明じゃないですか」
叔父の背後に、何処から現れたか、二人の黒スーツにサングラスの男達が来た。
向高は驚嘆した。
「何ですか、貴方達は」
「だから利夫、私は強制したくないんだ」
「分かりません、何もかも分からない」
二人の黒スーツの男が、利夫の背後に回り込み、両肩を掴んだ。
「何をする、離せ」
二人の男達が、向高を羽交い締めにした。
向高はウェイターを呼び止めた。
「警察を呼んでくれ、頼む……」
ウェイターは、驚き、大急ぎで店の奥に入って行った。
「此方こそ頼む、利夫、言うことを素直に聞いてくれ」
「嫌です」
向高は、二人の男を振り払った。彼としては余り力を込めた積もりもなかったが、二人は容易く床に転がった。
向高は、自分の力に自分で驚愕した。
「僕はどうしたんだ」
「だから言ったろう。御前は希望の光なのだ」
向高は、起き上がってきた男達双方に、蹴りを一発ずつ入れた。二人はもう立ち上がれない程のダメージを受けた様子だった。
それもまた、向高自身思いもよらぬ剛力なのだった。
「利夫、頼む。御前に力で勝てるとは思わない。だから、御前の力を完璧なものにするために、手術を受けてくれないか」
「これは何なんだ」
向高はもうこの場は逃げるしかないと、咄嗟に判断した。レストランの出口の方へ、一目散に駆け出した。
客達が好気の眼で彼を注視していた。
追っ手が来るかもしれない。彼は全速で逃走した。
ホテルの玄関ホールで、大柱に背をもたれている独りの男が、向高に鋭い視線を投げた。
男は立った儘、新聞を読んでいた風だったが、新聞を投げ捨てた。
「貴様、向高利夫だな」
「御前こそ何だ」
男は背広のポケットに入れていた片手を素速く出した。その手には黒光りする拳銃が握られていた。
向高は前かがみに伏せた。
「覚悟しろ」
拳銃が火を吹いた。後方の硝子の自動ドアが粉砕された。
更に一発の銃撃。外の乗用車の窓硝子が蜘蛛の巣状に割れた。
向高は態勢を戻すと、一発右ストレートを繰り出した。男の手に握られていた拳銃が吹き飛んだ。
向高は冷静に、更なるパンチを男に見舞った。アッパーは男の顎の骨を砕いた。
利夫はもう後を振り返らなかった。
ホテルを出て、街路を駆け出した。呼吸は多少苦しかったが、信じがたい速度で走っていた。
歩道を駆けながら、猛烈に嘔吐が込み上げた。路肩に吐いた。
或いは、人を殺したかもしれなかった。しかし、正当防衛に違いなかった。
タクシーに乗りたかったが、無一文に変わりはない。バス停に駆け込むと、丁度来たバスに飛び乗った。何処行きなど、確認する余裕はなかった。
最後尾の席に座った。小銭ならあった。車窓は見慣れた街並みながら、今は全く違って見えた。小銭入れには幸い数枚の千円札があった。週末を過ごすために、貯めておいた金だった。
思考は酷く混乱していた。
向高は、何処へ逃げれば良いのか全く解らなかった。何処か独りになれて、安全な場所、思い当たる処はない。
鹿児島大学水産学部が遠目に見えた。それで漸く、このバスが鴨池港行きと悟った。
近くに、以前来たネットカフェがあるのを思い出した。一時潜伏するには好都合に思われた。
水産学部前でバスを降りた。
ネットカフェに入った。カードは未だ所持していた。若い店員は希望の席を尋ねた。
「兎に角、奥に目立たない席はないかな」
店員は無表情に、一番奥のブースをスキャンした。店員としては、AVでも観るのかと思ったかもしれなかった。
コップにアイスコーヒーをなみなみ注ぎ、足早にブースへ急いだ。
パソコン画面の前のソファーに、死んだようにぐったり横たわった。
顔を上げると、四角形のディスプレイがぐにゃりと楕円に歪んだ。甲高い耳鳴りが聞こえる。
嗚呼、また幻覚が始まると思った。キーボードがみるみる卓上に溶解していった。
透明の川魚が眼前を泳いでいた。空気の本流は縦に滝のように流された。
遠くて、淫靡な夜が彼方の大海から、一艘の帆船を伴い、不恰好に彎曲する方眼紙となり、無重力のようにリモコンを浮遊させる。
展開の甚だしいサッカーグランドが、狭いブースに不可思議に侵入。フォワードは唯ボールに向けて疾駆。
数奇な運命のポーランド侵攻は錫の架け橋となり、飽くまで冷血に己の自尊心を持続可能なエナジーで満たし、トンネルの暗澹たるテーマパークは勇敢なる恋人たちの束の間の陽明学。
聞こえる声は未だ続く。浪人した崇高な記者会見に危険な性向で全巻解説。鋭い爪に光輝は仇となり数万人規模のメタルスラッシュ。
法律を粉砕せよと賢者は宣う写真流された映像情報提供、パソコン画面に今正に、独りの女神が顕在化した。
「死を覚悟しなさい。夜半には虐殺が始まります」
「抵抗勢力は無益に荼毘に付するのですか」
「洋紅、溶鉱、たまさかなる絶叫の真意を問いなさい」
「例え生まれ変わるとしても、貴女の傍では慟哭し得ない」
「例え盲目を享受しても、秘めたる内面へ貢いでいくのです」
「空港、未だ無益に貧困を淵源から相剋出来ない」
「魂よ、総ては。スパイの瞳孔に明け方の明星を」
「言い分を聴かない女神に只管乾杯……」
3
ネットカフェのトイレで、向高は頭から水を被った。未だ酷い頭痛に悩まされていた。漸く眼が醒めた。
総てが夢だったような気がした。実は何も起こらなかったのではないのか。ブースに戻ると、テレビを付けた。
MBCがローカルニュースを放送していた。
「……本日午後1時半、中央町のホテルハイアットで、発砲事件がありました。幸い銃撃による怪我人はありませんでした。発砲したのは元自衛隊員、野村重雄、36歳。彼は顎を骨折しており、重傷。彼を殴ったのは向高利夫、25歳。向高は現在市内を逃走中……」
向高はスマホを取り出した。一瞬躊躇したものの、矢張り叔父にコールした。
「叔父さん」
「利夫か、今何処だ」
「それは言えません」
「私を信頼してほしい。自衛隊員から襲撃されたろう。御前は一人では危険だ」
「叔父さんも同じ穴のむじなでは」
「それは違う。私は御前に危害を加えたりしない」
「でも脳外科手術をすると」
「それは御前自身のためだ。手術によって、御前の能力は飛躍的に向上する。それは約束する」
「矢張り嫌です」
「御前に選択肢はない。今の儘ではいずれ殺される」
「……」
「今、何処に居るんだ。迎えに行くよ。それが生き延びる唯一の道なんだ」
「総てが悪夢のようだ」
「人生は夢だ。だがこれは動かし難い現実。何処に居るんだ」
「水産学部前のネットカフェです」
「鴨池新町から近いな。鴨池は官庁街だ。自由党本部も、我が希望の光党の本部もある」
「希望の光党、それが叔父さんの仰有る我々ですか」
「そうだ、其処まで近い。直ぐ迎えに行く」
「叔父さんが来る?」
「いや、希望の光党首の江原氏が行く。丁度選挙カーがその付近に居る」
「分かりました。待ってます」
「一つ警告だ。今直ぐに携帯電話を捨てろ。GPSで敵に位置を悟られる」
「了解」
その時、近くで爆発音が聞こえた。銃声に違いなかった。
直ぐさま床に転がり、床を這った。
続けて、銃声と悲鳴が聞こえた。スマホを反対方向の奥に投げ捨てた。
弾の雨が、スマホの方向に轟々と流れた。
向高は、ほふく前進で出口迄這った。
外に出た。丁度其処に選挙カーが到着した。
向高は選挙カーに飛び乗った。
後部座席に、選挙の鉢巻きを締めた人物が居た。
「私が江原です。利夫さんですね」
「ええ」
選挙カーは急発進した。追っ手は装甲車に乗り込んだ。
選挙カーは制限速度ぎりぎりで走った。
江原は言った。
「現実にはカーチェイスなんて不可能です。警察に捕まるだけですからね」
「しかし、逃げ切れるんですか」
「此処から近い、緑地公園迄行けば大丈夫です」
向高は首を傾げた。
「緑地公園迄行って、それでどうするんですか」
「今は説明している暇はありません」
後方の装甲車から、発砲してきた。
「伏せて……」
選挙カー後部の窓硝子が割れた。
「此処で死ぬ訳にはいかない」
江原は強気でマイクを手にした。
「皆さん、大変お騒がせしております。希望の光党の党首、江原です。皆様、希望の光党は、長期の自由党政権を打破し、新しい日本を、皆様と一緒に創造してまいります」
銃弾が選挙カーのバックミラーを破壊した。
「皆様、次期総選挙では何とぞ、希望の光党に清き一票をお願い致します……」
装甲車が選挙カーの後部にぶち当たった。後部のバンパーが潰れ、車は大きく揺れた。
江原はマイクを置いた。
「駄目だな、緑地公園迄持ちそうにない」
江原はスマホを手にした。
「向高さん、聞こえますか」
叔父に電話したらしかった。
「到底、緑地公園迄行けそうにない。今、此処で、路上で救助をお願いしたい」
装甲車が再度後方からぶつかってきた。
「この選挙カーが見えますか?見える。それなら、無理なお願いかもしれないが、降りてきて下さい」
「速度を選挙カーと合わせて、縄梯子の用意を……」
上空で、激しい機械音が聞こえた。ヘリコプターが選挙カー上部に降りてきたのだった。
「それでは利夫さん、ドアを開けて、降りてくる縄梯子に掴まって下さい」
「何ですって」
「かなりのアクロバットながら、貴方なら可能だ。此処からヘリコプターに攀じ登って頂きたい」
「分かりました」
利夫は言われる儘、走行中のドアを開いた。縄梯子が上から降りてきた。
「掴まって、拳銃に気をつけて」
向高は縄梯子に飛び乗った。ヘリコプターが併走し、縄梯子を引き上げる。
銃弾が頬を掠めた。向高は構わず、登っていった。
どうにかヘリコプターに乗り込んだ。
ヘリは青空高く上昇していく。
利夫は、ヘリコプター内で、叔父の隣に座った。ヘリの回転音は煩いものの、会話は可能だった。
「有難うございました。命の恩人だ」
「うむ」
「もう教えてくれて良いでしょう。僕は一体何なんですか」
「御前は謂わば怪物兵器だ」
「怪物?どんな」
「謂わばマングスだろう」
「マングスとは何です」
「頭が12個ある、モンゴルの妖怪だ」
「モンゴル。まさか、僕の論文、第三の元寇が起きるが、現実化した訳ではないでしょう」
叔父は、その質問には返答しなかった。
「僕の予言が的中したのではなく、僕自身がマングスだった」
「その通りだ」
「希望の光党は左翼ですよね」
「そうだ」
「恐らく共産党以上に」
「……」
「これからテロでも起きるんですか。僕が命を狙われるということは」
「御前は自分の使命を果たせばいい。それが何と呼ばれても、他人の勝手だ」
「僕の使命とは」
「先ず手術を受ける」
ヘリの爆音の中での小声の会話だった。二人はそれから沈黙した。
ヘリコプターは青空の中、大きく旋回した。
4
東京、世田谷区、白百合幼稚園の前。園児達が大勢帰宅している最中だった。
東亜リサの母親は、娘を迎えに行く途中だった。電信柱の前まで来た際に、ふと立ち止まった。
不意に電信柱の影から何者かが現れた。野球帽を被った男だった。
男は、母親の背後に回った。後ろから、彼女の口にハンカチを押し当てた。彼女の意識は遠退いていく。
母親は、電信柱の影に倒れた。目撃者は一人も居なかった。
野球帽の男は、向高利夫だった。
幼稚園の玄関口前、リサは母親が迎えに来ないので、当惑していた。
リサは半分泣きそうになっていた。
野球帽の向高は、リサに近寄った。
「リサさんだね」
「はい」
「ごめんね、遅れて、お母さんちょっと用事が出来たんだ」
「ご用事?」
「うん、だから小父さんが代わりに迎えに行ってくれと頼まれたんだ」
リサは、少し警戒の表情を浮かべた。
「でも、ママが知らない人について行ったらいけないって」
「小父さんは大丈夫だよ。ママに頼まれたんだから」
「でも……」
「さあ、お人形をあげよう」
向高は、リサに西洋人形を手渡した。
「さあ、一緒に帰ろう。ママが待っているよ」
リサは渋々、向高について行った。
その日の夜。東亜重工業専務、東亜信光は会社から帰宅途中だった。東亜は、中々迎えの車が来ないので、苛々していた。
20分程待って、漸くいつもの車が、東亜の目の前に停車した。
東亜は車に乗り込むと、お抱え運転手に文句を言った。
「どうした?何故遅れた」
その時になって、東亜は、運転帽を被った運転手が別人であることに気付いた。
「誰だ、貴様は」
運転手は無言の儘、車をスタートさせた。全ドアが非情にロックされた。
「何だ、ドアを開けろ。車を間違った」
「間違ってはいません。いつもの車です」
「貴様は誰だ」
「向高利夫と申します」
車は人通りの少ない路肩に停車した。
向高は、後部座席に振り向いた。
東亜は、スマホを取り出して、110番に電話しようとした。
「東亜さん、お待ちください」
「何だ?」
「これを御覧下さい」
向高は、東亜にスマホをかざした。
スマホ画面はライン電話で、東亜の娘、リサが映っていた。
「リサ、どうした?大丈夫か」
「パパ、私は大丈夫よ。小父さん達、皆優しいわ」
「リサ、何処に居るんだ」
「分からない。ママが中々来てくれないの」
「リサ、まさか何かされたのか」
「ううん、皆優しいわ」
向高は、ライン電話を切った。
「向高と言ったな。何が望みだ」
「日本の大会社、東亜重工業と政治家達の大規模な贈収賄……」
「何だと」
「贈収賄事件の情報をリークして頂けませんか」
「……」
「お願い致します」
「第二のロッキード事件になるぞ」
「承知しております」
「与党、自由党を始め、全政党が絡んでくる」
「希望の光党以外です」
「総選挙直前だ。どうなると思う」
「この国の未来が変わります」
「それを私に遣れと言うのか」
「貴方は断れない」
「ううむ……」
何処か遠方で、パトカーのサイレンが鳴り響いていた。
5
向高は、茫然自失で、渋谷の街を彷徨っていた。頭痛は極限に達していた。
雑踏の流れの裡で、彼は立ち止まった。
再び視界が歪み始めた。
嗚呼、また幻覚が始まると思った。
とある店舗のショーウインドウの前に佇んだ。硝子に彼の姿が映っていた。
向高の両肩に、幾つもの頭が生えていた。幻覚なのか、現実なのか、区別はつかなかった。
つまりは自分は妖怪なのか。それでいいのか。自分に人間の要素はもう残っていないのか。
その折り、彼は路上で呼び止められた。
「向高君じゃないか」
見ると、相手は李贄教授だった。
「貴方はあの科学大学の教授……」
「こんな所で会うとは奇遇だな」
「何故東京に?」
「学会があってね、君こそどうして」
「しらばっくれないでください。貴方は全部ご存知なんでしょう」
教授は表情を硬化させた。
「まあな」
「僕のことを総てご存知ですね」
「知っている」
「大学勧誘なんてデタラメだった」
「そうだ」
「教授、僕に協力してくれませんか」
「どんな協力を」
「この美しい日本が侵略を受けます」
「だろうね」
「それでいいんですか」
「私は日本人ではない。日本は、先の戦争で南京虐殺を行った」
「そんなこと、現代からではもう、事実かどうか分からないではないですか」
「……」
「僕に協力してくれませんか。貴方を研究者として育てたこの国が今壊れかけている」
教授は暫し沈黙したが、やがて口を開いた。
「私に何をして欲しい?」
「サイバーテロです。貴方なら可能でしょう」
「サイバーテロ」
「ええ、総ての報道機関に、システム障害を生じさせて頂きたい」
教授は躊躇したものの、ゆっくり頷いた。
6
向高は再び、渋谷の街を歩いた。
イヤホンで、携帯ラジオを聴いていた。
「……総選挙では、与党自由党は矢張り再び過半数の票を獲得しました……」
向高は、ラジオを投げ捨てた。
向高は、ポケットから拳銃を取り出した。
誰でも構わなかった。近くに居た女性を、後ろから羽交い締めにして、頭に拳銃を突きつけた。
「ぶっ殺すぞ、警察を呼べ」
街は騒然となった。
警官が3人、駆け付けてきた。
「貴様、拳銃を捨てろ」
警官が声高に警告した。
向高は、女性を離した。警官に銃口を向けた。
警官が続けて発砲した。向高の胸に三発命中した。
向高は苦しげに呻いたが、未だ立っていた。
警官達は、信じがたい恐怖に怯えた。
更に何発も、向高に発砲した。
向高は血塗れになり、叫んだ。
「天皇陛下、万歳……」
本作品はフィクションです。登場する人物、団体は現実のものとは一切関係ありません。