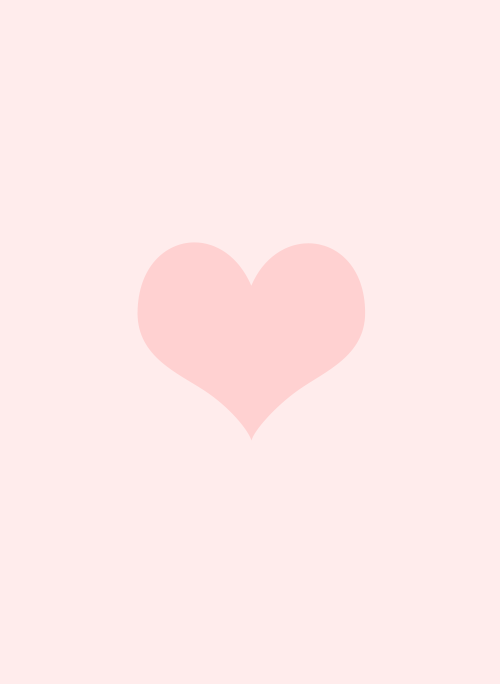あますことなく愛をあげる
小さい頃からずっと言われてきた。真面目に、嘘はつかずに、ルールを守りなさいねって。
学校からも、親からも。
それが当たり前だと思っていたし、なにより規則正しい生活は、私も気持ちが良かった。
『松倉に任せておけば大丈夫だな』
『碧がいい子に育ってくれてよかったわ~』
先生や親には信頼されて、気分も良かった。
でも、この堅すぎるくらいの真面目な性格を、今でも好いてくれるのは大人だけ。
中学生になった時から、少しずつ、私を見る周りの目は変わっていった。
高校生になった今、もう誰も私のことを「えらい」とか「しっかりしてる」なんて言わない。
むしろ……
「──学校にピアスをつけてくるのは校則違反です。高橋さんこれで3度目の注意ですよ。没収します」
「はーっ!?」
朝、校門の前。
女子生徒の不満げな大きな声に、なんだなんだと登校中の生徒たちの視線が集まる。
「いやいやっ、見逃してよ。まだ安定してないし外したら塞がっちゃうんだって」
「それならちょうどいいですね。この際その穴も塞いでしまいましょう」
ん、と手のひらを差し出す私に、目の前の女子生徒が眉を寄せる。
「うわ~でたよ"堅物"。今日も元気に真面目ってるね~」
「ね~ちょっとくらい見逃してあげてもいいのに」
「先生からの評価でも気にしてるんでしょ。冗談も通じないしさ。なんていうか、うざいよねー」
聞こえてきた野次馬の小さな会話に、心の中でため息を吐いた。
松倉碧、高校2年生。
風紀委員の腕章をつけた私は、今では"堅物"とあだ名をつけられ、周りから疎まれる存在になってしまっている。
「生活指導の先生に渡しておくので、放課後自分で取りに行ってください」
「〜〜っ最悪!」
2週間に1回の朝の風紀検査では、風紀委員と生活指導の先生が校門で生徒をチェックすることになっていて。
校則に従えばなんの問題もないのに、どうしてこんなにもルールを破る人が多いんだろう。
真面目に、嘘はつかずに、ルールを守る。これが高校2年生になるまでの年月で出来た私のモットー。
皆だって小学校の時に習ったはずなのに、どうして今でもこのモットーのもとで生きている私が非難されてしまうのか。
そんなことを考えていると、ざわっと周りの空気が変わった。
「見てみて、紅谷くんだよ……朝から見れるなんてラッキー……!」
「いつ見ても神々しいよねっ。同じ学校で同じ空気吸えるなんて幸せだよ……っ」
"紅谷くん"。
その響きにすかさず私の耳が反応する。
生徒の視線を追うように、私も校門の方を見た。
柔らかい黒い髪、すらりと伸びた手足、白い肌。気怠げな瞳に、校則違反のピアス。
儚くて妖しい。そんな雰囲気を纏った紅谷圭くんは、今日も皆の視線を奪っている。
しかもあのルックスに加えて、この学校の理事長の息子とか。
魅力的、だからこその人気っぷりなんだろうけど……。正直言うと、私は苦手だ。
「おはよう碧ちゃん」
「……」
私と目があった紅谷くんは、そのまま真っ直ぐに私のところへと来た。ゆるり笑って挨拶をしてくる紅谷くんに、「おはようございます」と短く返す。
極力関わりたくないし、話もしたくないんだけど、きらりと光るピアスはいつものように彼の両耳についている。
風紀委員としてこれを見逃すことはできない。
「紅谷くん。ピアス、校則違反なので外してください」
もう何度目かもわからない注意。普通なら嫌そうな顔をするのに、紅谷くんはなぜか満足そうに笑う。
「いつも俺のこと避けるくせに、こーいう時は絶対無視しないよね」
「仕事ですから。あの、早く外してください──っ!」
いきなり私の腕を掴んで引っ張ってきた紅谷くんに目を見開く。
自分の耳元に私の手を持ってきて、紅谷くんは言った。
「碧ちゃんが取って」
……紅谷くんのこういうところが、本当に苦手。私のことを揶揄ってくるこの感じが心底嫌。
「ふざけないで。叩きますよ」
「はは。冗談だって」
そう言いながら、紅谷くんはするりと私の腕を離してくれた。
「またね」
「あ!ちょっとピアス……」
私の声はフル無視で、紅谷くんはスタスタと行ってしまう。
もう、なんなの。
紅谷くんはいつもこう。気まぐれなのか知らないけど、こうやって私を揶揄ってくる。
距離近いし、簡単に触ってくるし、そのせいで他の女子たちからさらに冷たい目を向けられてしまう。
ただでさえ疎まれているのに、私の周りを引っかき回すのはやめてほしい。
*
紅谷くんは、ちょっとした問題児だ。
授業はサボるし、校則違反のピアスもつけてる。
なのになぜか定期試験の成績は良い。スポーツだってそつなくこなしてしまう。
理事長の息子ということもあって、先生たちも強く注意できないみたい。
廊下でたむろしている紅谷くんとその取り巻きを見ながら、心の中でため息を吐いた。
「碧〜、お待たせ!なに見てたの……って、紅谷くんか。碧も紅谷くんファン?」
「そんなのじゃないよ。なんていうか、紅谷くん見てるとむずむずするの。ビシッと整えたくなる……」
「じゃあそうすればいいのに」って笑うのは、隣のクラスの宍戸 茉冬。
茉冬とは幼なじみで、中学は違ったけど高校で再会した。同じクラスになったことはないけど、週に一回は一緒にお昼ご飯を食べる約束をしている。
茉冬のクラスの前で待ち合わせて、ベンチのある談話スペースでお弁当を食べる時間が、私にとっては唯一の落ち着ける時間。
「なんか、紅谷くんにはあんまり関わりたくないっていうか」
「ふぅん?やっぱり碧って紅谷くんのこと苦手だよね?女子はみーんな紅谷くんにメロメロなのに」
「それは茉冬もでしょ?」
「私は彼氏一筋ですから!」
玉子焼きをぱくりと食べる茉冬は楽しそう。
「んまぁ、碧と仲良くなれるタイプではないよね。紅谷くんって」
「2年になって初めて同じクラスになったけど、ちょっと怖い」
「え〜?怖いかなぁ」
「だって、ピアスとか授業態度とか制服の乱れとか注意したら笑うんだよ?みんな面倒くさーって顔するのに」
嬉しそうっていうか、満足気っていうか……。そんな反応する人今までいなくて、気味が悪いっていうか。
『ピアスは校則違反ですよ』
一ヶ月前の四月、風紀委員として、初めて紅谷くんを注意した日のことをよく覚えてる。
あの時の紅谷くんも笑ってた。ゆるく口角をあげて、鬱陶しそうだけどどこか嬉しそうに。
思えば、あの時から紅谷くんは私を揶揄ってくるようになった気がする。仲良くもないのに下の名前で呼んでくるし。私に対する嫌がらせ?
「あれじゃない!?"おもしれー女"状態!」
「なにそれ……」
「真っ向から注意してくる碧が珍しくて気になる〜みたいな!ていうかすでにちょっと好きみたいな!?」
「ッゴホ、な、なに言ってるの……!?」
喉に詰まらせた食べ物を急いでお茶で流し込んで、ケラケラ楽しそうに笑っている茉冬をジトっと睨む。
「もしもの話だよ〜。紅谷くんが下の名前で呼んでる女子、実際碧しかいないしね〜」
「嫌がらせに決まってるよ。他の女子たちの反感買おうとしてるんでしょ、どうせ……って、」
自分で言ってて変に納得した。
そっか。注意してくる私がむかつくから、あえて構ってくるのかも……。そうすれば女子たちに嫌われるのは間違いないし。
「オッケー。解決した」
「えぇ?解決したの?」
「とりあえず私はいつも通りで大丈夫そう。くだらないことでルール破ってる人を見逃すなんて馬鹿みたいだし」
「よくわからないけど……とりあえずガンバ!」
*
昼休みの予鈴が鳴って、茉冬と教室に戻ることになった。「じゃ、また来週ね〜」と笑って手を振ってくれる茉冬に頷いて、自分の教室の扉に手をかける。
あ、そういえば次は体育だった。私としたことが……急いで着替えに行かないと……。
「やっべ、次体育じゃん!!」
「ぅわっ……!?」
瞬間、教室から飛び出してきたクラスメイトとぶつかってしまった。
ドン、と廊下に逆戻り。ぶつけてしまったおでこをおさえながら、クラスメイトの男子をジロリ睨む。
「田村くん、急に飛び出さないでください」
「うわ、堅物……!?いや〜ごめんごめん、俺急いでるから見逃して!」
「見逃しません。廊下走ろうとしてましたね?シャツの裾もちゃんとしまってください」
「も〜、母ちゃんみたいなこと言わないでよ。俺急いでるからさ!」
「あっ、ちょっと──」
廊下を走り出そうとする田村くんの腕を咄嗟に掴もうとした時。
「田村ぁー」
後ろから聞こえてきた低い声に、ビクッと肩が震えた。
この声……紅谷くん?
振り返れば、教室の窓から顔を覗かせている紅谷くんが。窓枠に頬杖をついて、いつもの気怠そうな目でこっちを見ている。
「なにしてんの、おまえ」
いつも通りに見えるけど、どうしてだろう。ちょっと怖い。紅谷くんの目に、光がないように見えるからかな……。
「なにって、着替えに行くんだよ……」
田村くんも紅谷くんのオーラに圧倒されてるのか、顔が引き攣ってる。
当の紅谷くんは、田村くんの言葉に笑った。「はは」って、いつもみたいに。ただ、目が全く笑ってない。
「違うだろ。まずは碧ちゃんに謝りなよ」
冷たい声に、私まで動けなくなってしまう。
こんな紅谷くん初めて見た。紅谷くんは学校の人気者で、でも、何かに対して感情を表に出すような人には見えなかったから。
クラスメイトと笑っていてもどこかつまらなさそうで、人にも物にも執着しなさそうだと思っていたのに。
「聞いてる?」
そんな顔、するんだ。助けてくれたりするんだ。
「っごめんなさい……!!」
「あっ、だから廊下は!」
早口の謝罪と、逃げるように廊下を走っていく田村くん。慌てて田村くんを止めようとしたら名前を呼ばれた。もちろん紅谷くんに。
「あんな奴どうでもいいだろ。いちいち注意しなくていいよ」
「……」
「こっち来て」
ため息を吐いて、仕方なく紅谷くんの元へ。
窓から教室の中が見えたけど、みんな更衣室へ行ったのか紅谷くん以外誰もいなかった。
「風紀委員なので注意はしますよ。……まぁでも、さっきはありがとうございました」
謝りなよって言ってくれたこと。まさか紅谷くんがそんなことを言うとは思わなかったけど。
ちら、と私を見上げる紅谷くん。
私も人のこと言えないと思うけど、相変わらず何考えてるのかわからないな、この人は。
「……その風紀委員ってやつ、やめちゃえば?」
「……はい?」
次の瞬間、紅谷くんの腕が伸びた。リボンタイをぐいっと引っ張ってくるから、体のバランスがあっという間に崩れていく。
至近距離で紅谷くんの焦茶色の瞳と目があって、その綺麗な顔に不覚にもドキッと胸が鳴った。
「ダメって言うの、俺だけにしてよ」
まるで本気で言っているかのような紅谷くんに目を見開く。
……やっぱりよくわからない。紅谷くんは、真面目すぎる私のことを鬱陶しいって思わないんだろうか。
「……普通に無理です。離してください」
そう言ったら、彼はゆるり笑った。
「はは。やっぱり碧ちゃんいいなー」
「っ!?ちょっと……」
するり、紅谷くんの指が掴んでいたリボンタイから首へ触れた。冷たい感触にふるっと体が震える。
紅谷くんの表情は変わらない。でも、私のことを逃さないようにじっと見つめている。
心臓がうるさいのは、身の危険を感じているから?それとも、紅谷くんの距離にドキドキしてしまっているから?
「何かに執着することはないと思ってたけど、碧ちゃんだけは、まぁいいやで終わらないんだよね」
「べ、紅谷くん、」
流れるように後頭部を手のひらでおさえられて、逃げたほうがいいはずなのに、なぜか体が動かない。
「どうにかしてでも俺のものにならないかなって。この気持ち、何だろうね?碧ちゃん」
知らなかった。
紅谷くんが、こんなに危険な人だったなんて。