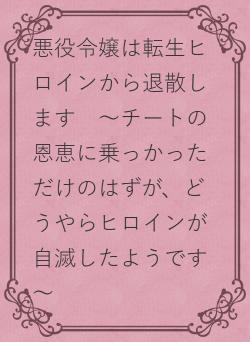出来損ないと呼ばれた私は売られた先で幸せになります ~転生チート始めました。これからは辺境伯家だけが私の家族です~
アストン辺境伯邸の執務室にて、当主代理と私は対峙していた。
青みがかった銀髪に琥珀色の瞳をした美青年――ハルトシェイク・アストン。これが和やかな雰囲気の中でのことなら、華やかな容姿で次期辺境伯な彼との対面を喜べたであろう。もっとも、彼とは違って髪も瞳も胡桃色でパッとしない私が相手では、甘い展開など期待できなかっただろうが。
「我が領へ送られる人材として、君が選ばれた理由を聞いているだろうか? フェリアン・コーデラー嬢」
ハルトシェイクが、今し方私が渡した手紙――コーデラー侯爵家からの返信を片手に尋ねてくる。
言い方こそ質問形式であるが、彼の本音は「何故、役立たずのお前が来た」といったものに違いない。にもかかわらず眉一つ動かさないのは、さすが『氷の貴公子』と呼ばれるだけある。私が逆の立場なら、きっと少なくとも渋い顔はしていた。
何故なら、不本意ながら世間での私の評判は「コーデラー侯爵家の汚点」だからだ。
代々魔術師の家系であるコーデラー侯爵家に生まれながら、唯一魔術師のスキルを授からなかった出来損ない。しかも代わりに授かったのは『写生』スキル。希少で職に困ることがないと言われるため平民には人気があるが、だからこそ貴族からは嘲笑を買うことになった。
写生スキルが活躍する場は、主に図書館となる。傷んだ書物を新しい紙へ間違いなく書き写す……それだけのスキルだ。魔物討伐の前線基地であるこの地への人材支援として不適切なのは、誰が見ても明らか。よって、そんな私を敢えて選んだとなれば、コーデラー侯爵がアストン辺境伯を軽んじていることになる。そして実際、そうなのだろう。父と最後に交わした会話から察するに。
しかし、それを馬鹿正直に言ってしまうほど愚かではない。私はハルトシェイクの手にある手紙を一瞥しながら、小さな溜め息をつくに留めた。
「私の方はどうぞフェリアンとお呼びください。それから、選任の理由については父からは何とも。ですが、私個人としてはコーデラー侯爵家の人間で最もアストン領のお役に立てるのは私だと、自負しております」
「ほぅ?」
僅かにだが、ハルトシェイクの眉がピクリと動く。
どうやら興味を引くことに成功したらしい。すかさず私はこの地まで一人で乗ってきた侯爵家の馬車の中で書き上げた一枚の紙を、ハルトシェイクに差し出した。
「これは……描かれているのは魔法陣だろうか?」
「はい。その紙――スクロールは、生活魔道具に使う程度の魔力を流すだけで発動します」
「まさか!」
今度はさすがの氷の貴公子も相当驚いたらしい。目を瞠った彼の様子に、にやけそうになるのを堪えながら、私は道すがら摘んできた萎れた花を執務机の上に置いた。
「描かれているのは、回復魔法の魔法陣です。どうぞこの花で確かめてみてください」
ハルトシェイクが半信半疑といった顔つきで、けれどどこか期待を孕んだ目で花を手にする。
そして、スクロールを持った彼の指先が光を帯びた瞬間――
「萎れた花が……蘇った」
唖然とした表情でハルトシェイクが言うのを、私は心の中で「よしっ」と歓喜した。
行ける。我ながら冷や汗ものの強気な発言だったけど、これは……行けるわ!
「一体、どういうカラクリになっている?」
「ハルトシェイク様もご存じのように、魔術師が唱える呪文の役割は、魔力で魔法陣を描くためのものです。つまり、あくまで描く手段であり、描けさえすればそれが呪文である必要はないのです」
「簡単に言うが、写生スキルは既に存在するものしか書き写せなかったはずだ。君がどうして魔法陣を描ける? 理屈の上では魔法陣の図鑑なるものがあれば可能だと言われているが、そんなものは机上の空論。呪文で浮き上がった魔法陣は一瞬で消える上、同じ魔法を唱えても個人差がある。万人に通用する魔法陣の手本など、未だ夢物語の域を脱していなかったと思うが?」
「そうですね。だからこそ私は、その机上の空論が現実になったなら、喉から手が出るほど欲しい人材になれると確信できたのです」
「‼」
実はカラクリは至って単純だ。
私はただ、写生スキルを普通に使っただけ。ただし、その対象はこの世界に存在しない図鑑ではあったが。
(プレイしてたゲームに異世界転生とか、本当にあるんだそんなこと……)
そう、異世界転生。私には日本人として過ごした前世が……この世界がRPG――『エニスヒル』の舞台である記憶がある。このゲームをやり込んでいた私だったので、初めて自国の国名が『エニスヒル王国』だと知った三歳にして、前世を思い出した。
とはいえ、今回の一件があるまではいわゆる転生チートを使う場面もなかった。魔法が存在する世界でせっかく魔術師の家系に生まれたのだから、そのまま魔術師として生きるのも悪くないと思っていたのだ。だから昔は一日でも早く立派な魔術師になろうと、実家にある魔法の本を読み漁っていた。
――十二歳のスキル選定の儀で、私のスキルが『写生』だと判明するまでは。
その瞬間から、私の世界はガラリと変わった。
魔術師としての未来が無くなったことを残念に思う暇も与えられなかった。
スキル選定の儀が行われた神殿から両親と一緒に帰宅した私は、本邸へ入ることを許されずそのまま庭にある小屋へと移された。自室にあった私物を持ち出すことも叶わなかった。
古びた小屋にあったのは、固いベッドと、ところどころ穴の開いた木製の机にガタついた椅子のみ。後になって聞いたのは、元々小屋は庭師が使っていたという。その庭師が所帯を持ったのを機に、本邸にある一室を与えられたのだとか。直系の娘が庭に住み、使用人は本邸で暮らしているとは、笑えない話だ。
だから私は十八になるまでのこの五年間、転生チートを家族に隠し続けてきた。
私は『エニスヒル』にあったシステム――図鑑を今世でもウィンドウに呼び出して閲覧することができる。『アイテム図鑑』、『魔法図鑑』、『魔物図鑑』と三種類あり、RPGらしく一度情報を入手することで都度開示されて行く仕様となっていた。
そして私は、その三つの図鑑の完成度がいずれも百パーセント。正直、『アイテム図鑑』だけでも一財産築けるほど希有な能力だろう。伝説級のアイテムすら鑑定できてしまうのだから。
けれど、『魔法図鑑』と『魔物図鑑』に『写生』スキルという組み合わせが、それが霞むほどのトンデモスキルなことに私は気づいてしまった。
「ハルトシェイク様が言われたように、魔法陣には個人差が出ます。しかし、それは文字を書くときの癖のようなもの。実は魔法陣にも、文字と一緒で基本になる形があるのです」
「確かに……同じ魔法であれば、微妙に違いはあれど似た魔法陣が描かれている。フェリアン嬢は何らかの手段で、その基本の形の知識を手に入れたということか。回復魔法の使い手が増えるだけでも、かなり戦線は楽になる。コーデラー侯爵家で最も役立てると言ってのけた理由が理解できた」
「いえ、それとは別に攻撃魔法の方も用意できます」
「何だと⁉」
すっかり氷が溶けた氷の貴公子を前に、緩みそうになる頬を何とか気合いで引き締める。私は新たなスクロールに今度は五枚の書類を添えて、ハルトシェイクに差し出した。
「攻撃魔法そのもののスクロールを作ることも可能でしたが、敢えて武器に魔法を付与するタイプにしました。理由は添付書類にあるように、アストン領の魔物が一様に物理と火が弱点なためです」
「いや、待ってくれ。そもそもこの資料は一体……現地の我が領さえ、魔物についてこれほど詳細な情報は持っていない。どこでこれを?」
ここまで話すときはずっとこちらの目を見てきたハルトシェイクが、食い入るようにして書類を見ながら聞いてくる。
書類は魔物図鑑の写しで、この地方の魔物の項目を抜粋した。RPGでは何の変哲もない、HP、MP、属性への耐性、それからドロップ品が書かれている様式になる。しかし、日々魔物と戦っている彼の目には、あるいは金銀財宝より価値あるものとして映ったに違いない。
魔物の速やかな討伐は、一番重要な財産である領民の死傷者減少に繋がる。加えて、ドロップ品の情報を上手く使えば、通年資金難である状況を改善することだってできるだろう。
私はようやく顔を上げたハルトシェイクに、自分の勝利を確信した。
私はコーデラー侯爵家に「売られた」者ではなく、「売り込みに来た」者に変われたのだ。
「そちらも私が写生スキルで作成しました。アストン領の求める人材は、魔術師でしたね? ですが、ここにいる兵士の方々が魔法を使えるようになるなら、コーデラー侯爵家の魔術師一人が来るより、私の能力の方が役立つと思われませんか?」
胸を張って、ハルトシェイクに尋ねる。
さすがに隠しきれない私の浮かれた気持ちが態度に出てしまっていたのか、一瞬キョトンとした彼は次に「はははっ」と声を上げて笑った。
その光景に、逆に私の方が呆気に取られる。
ゲーム中のハルトシェイクは既に家門を継いでおり、氷の貴公子改め氷の辺境伯だった。辺境伯の彼はその異名の通り、本当にピクリとも笑わないキャラだったのだ。
「よくアストン領へ来てくれた。歓迎しよう、フェリアン嬢」
「! ありがとうございます」
どうやら無事に明るいセカンドライフが始まりそうである。
私はこの場での緊張、そして威圧的な実家からの解放に、踊り出したい気分で執務室を後にした。
五日前。コーデラー侯爵家にて――
「アストン辺境伯家からの要請には、フェリアン、お前を送る」
夕食の席にて放たれた、父――ゴードン・コーデラーの信じられない一言に、私は危うくフォークを取り落とすところだった。珍しく同席を求められたかと思えば案の定、ろくな用件ではなかったようだ。
彼の家門からの要請とは、常に魔物の脅威に晒されている辺境伯領への人材支援のこと。数日前に届いた一通の手紙は、今日までコーデラー侯爵家をざわつかせていた。
当主すら凌駕する魔力を持つ兄か、それともテクニックに優れた長女か。はたまた、威力こそ劣るものの複数の属性魔法を操る三女が選ばれるのか。
何れにせよ魔術師ではない私には関係の無い話……のはずだった。
「……アストン辺境伯は当然、我が家からは魔術師の誰かを送ると考えていると思いますが?」
「さあな。どんな奴を寄越せという指定はなかった。それなら有能な我が子をわざわざ行かせる必要もない。要望に応えて、コーデラー侯爵家の者をちゃんと送ってやるんだ。期待するのも向こうの勝手であれば、期待に応えられないお前のことも私の知るところではない」
話は終わりだと言わんばかりに、ゴードンが黙々と食事を口に運ぶ。
周りを見れば、母、兄、姉はいつもと変わらぬ様子で食事をしており、妹のシャルロットだけがおかしそうに笑っていた。
「フェリアンお姉様。戦死者の遺族には、見舞金が出るんですって! ああでも、あまりに役に立たなすぎて戦死扱いされなかったらどうしましょう」
明け透けなシャルロットの言葉にも、家族の誰もが咎めようとしない。
他の家族も妹同様、無関心を装った表情の裏では私の死を願っているのだろう。「コーデラー侯爵家の汚点」が合法的に消えてくれることを。
私は目の前の料理を口の中に詰め込み、咀嚼しながら席を立った。
そんな貴族らしからぬマナー違反をしても、そのまま食堂を出ても、誰一人私に声を掛ける者はいない。
結局、翌日辺境伯邸に着くまでに私に掛けられた言葉は、侯爵家で一番ボロい馬車を操る御者の「早く乗れ」というたった一言だけだった。
青みがかった銀髪に琥珀色の瞳をした美青年――ハルトシェイク・アストン。これが和やかな雰囲気の中でのことなら、華やかな容姿で次期辺境伯な彼との対面を喜べたであろう。もっとも、彼とは違って髪も瞳も胡桃色でパッとしない私が相手では、甘い展開など期待できなかっただろうが。
「我が領へ送られる人材として、君が選ばれた理由を聞いているだろうか? フェリアン・コーデラー嬢」
ハルトシェイクが、今し方私が渡した手紙――コーデラー侯爵家からの返信を片手に尋ねてくる。
言い方こそ質問形式であるが、彼の本音は「何故、役立たずのお前が来た」といったものに違いない。にもかかわらず眉一つ動かさないのは、さすが『氷の貴公子』と呼ばれるだけある。私が逆の立場なら、きっと少なくとも渋い顔はしていた。
何故なら、不本意ながら世間での私の評判は「コーデラー侯爵家の汚点」だからだ。
代々魔術師の家系であるコーデラー侯爵家に生まれながら、唯一魔術師のスキルを授からなかった出来損ない。しかも代わりに授かったのは『写生』スキル。希少で職に困ることがないと言われるため平民には人気があるが、だからこそ貴族からは嘲笑を買うことになった。
写生スキルが活躍する場は、主に図書館となる。傷んだ書物を新しい紙へ間違いなく書き写す……それだけのスキルだ。魔物討伐の前線基地であるこの地への人材支援として不適切なのは、誰が見ても明らか。よって、そんな私を敢えて選んだとなれば、コーデラー侯爵がアストン辺境伯を軽んじていることになる。そして実際、そうなのだろう。父と最後に交わした会話から察するに。
しかし、それを馬鹿正直に言ってしまうほど愚かではない。私はハルトシェイクの手にある手紙を一瞥しながら、小さな溜め息をつくに留めた。
「私の方はどうぞフェリアンとお呼びください。それから、選任の理由については父からは何とも。ですが、私個人としてはコーデラー侯爵家の人間で最もアストン領のお役に立てるのは私だと、自負しております」
「ほぅ?」
僅かにだが、ハルトシェイクの眉がピクリと動く。
どうやら興味を引くことに成功したらしい。すかさず私はこの地まで一人で乗ってきた侯爵家の馬車の中で書き上げた一枚の紙を、ハルトシェイクに差し出した。
「これは……描かれているのは魔法陣だろうか?」
「はい。その紙――スクロールは、生活魔道具に使う程度の魔力を流すだけで発動します」
「まさか!」
今度はさすがの氷の貴公子も相当驚いたらしい。目を瞠った彼の様子に、にやけそうになるのを堪えながら、私は道すがら摘んできた萎れた花を執務机の上に置いた。
「描かれているのは、回復魔法の魔法陣です。どうぞこの花で確かめてみてください」
ハルトシェイクが半信半疑といった顔つきで、けれどどこか期待を孕んだ目で花を手にする。
そして、スクロールを持った彼の指先が光を帯びた瞬間――
「萎れた花が……蘇った」
唖然とした表情でハルトシェイクが言うのを、私は心の中で「よしっ」と歓喜した。
行ける。我ながら冷や汗ものの強気な発言だったけど、これは……行けるわ!
「一体、どういうカラクリになっている?」
「ハルトシェイク様もご存じのように、魔術師が唱える呪文の役割は、魔力で魔法陣を描くためのものです。つまり、あくまで描く手段であり、描けさえすればそれが呪文である必要はないのです」
「簡単に言うが、写生スキルは既に存在するものしか書き写せなかったはずだ。君がどうして魔法陣を描ける? 理屈の上では魔法陣の図鑑なるものがあれば可能だと言われているが、そんなものは机上の空論。呪文で浮き上がった魔法陣は一瞬で消える上、同じ魔法を唱えても個人差がある。万人に通用する魔法陣の手本など、未だ夢物語の域を脱していなかったと思うが?」
「そうですね。だからこそ私は、その机上の空論が現実になったなら、喉から手が出るほど欲しい人材になれると確信できたのです」
「‼」
実はカラクリは至って単純だ。
私はただ、写生スキルを普通に使っただけ。ただし、その対象はこの世界に存在しない図鑑ではあったが。
(プレイしてたゲームに異世界転生とか、本当にあるんだそんなこと……)
そう、異世界転生。私には日本人として過ごした前世が……この世界がRPG――『エニスヒル』の舞台である記憶がある。このゲームをやり込んでいた私だったので、初めて自国の国名が『エニスヒル王国』だと知った三歳にして、前世を思い出した。
とはいえ、今回の一件があるまではいわゆる転生チートを使う場面もなかった。魔法が存在する世界でせっかく魔術師の家系に生まれたのだから、そのまま魔術師として生きるのも悪くないと思っていたのだ。だから昔は一日でも早く立派な魔術師になろうと、実家にある魔法の本を読み漁っていた。
――十二歳のスキル選定の儀で、私のスキルが『写生』だと判明するまでは。
その瞬間から、私の世界はガラリと変わった。
魔術師としての未来が無くなったことを残念に思う暇も与えられなかった。
スキル選定の儀が行われた神殿から両親と一緒に帰宅した私は、本邸へ入ることを許されずそのまま庭にある小屋へと移された。自室にあった私物を持ち出すことも叶わなかった。
古びた小屋にあったのは、固いベッドと、ところどころ穴の開いた木製の机にガタついた椅子のみ。後になって聞いたのは、元々小屋は庭師が使っていたという。その庭師が所帯を持ったのを機に、本邸にある一室を与えられたのだとか。直系の娘が庭に住み、使用人は本邸で暮らしているとは、笑えない話だ。
だから私は十八になるまでのこの五年間、転生チートを家族に隠し続けてきた。
私は『エニスヒル』にあったシステム――図鑑を今世でもウィンドウに呼び出して閲覧することができる。『アイテム図鑑』、『魔法図鑑』、『魔物図鑑』と三種類あり、RPGらしく一度情報を入手することで都度開示されて行く仕様となっていた。
そして私は、その三つの図鑑の完成度がいずれも百パーセント。正直、『アイテム図鑑』だけでも一財産築けるほど希有な能力だろう。伝説級のアイテムすら鑑定できてしまうのだから。
けれど、『魔法図鑑』と『魔物図鑑』に『写生』スキルという組み合わせが、それが霞むほどのトンデモスキルなことに私は気づいてしまった。
「ハルトシェイク様が言われたように、魔法陣には個人差が出ます。しかし、それは文字を書くときの癖のようなもの。実は魔法陣にも、文字と一緒で基本になる形があるのです」
「確かに……同じ魔法であれば、微妙に違いはあれど似た魔法陣が描かれている。フェリアン嬢は何らかの手段で、その基本の形の知識を手に入れたということか。回復魔法の使い手が増えるだけでも、かなり戦線は楽になる。コーデラー侯爵家で最も役立てると言ってのけた理由が理解できた」
「いえ、それとは別に攻撃魔法の方も用意できます」
「何だと⁉」
すっかり氷が溶けた氷の貴公子を前に、緩みそうになる頬を何とか気合いで引き締める。私は新たなスクロールに今度は五枚の書類を添えて、ハルトシェイクに差し出した。
「攻撃魔法そのもののスクロールを作ることも可能でしたが、敢えて武器に魔法を付与するタイプにしました。理由は添付書類にあるように、アストン領の魔物が一様に物理と火が弱点なためです」
「いや、待ってくれ。そもそもこの資料は一体……現地の我が領さえ、魔物についてこれほど詳細な情報は持っていない。どこでこれを?」
ここまで話すときはずっとこちらの目を見てきたハルトシェイクが、食い入るようにして書類を見ながら聞いてくる。
書類は魔物図鑑の写しで、この地方の魔物の項目を抜粋した。RPGでは何の変哲もない、HP、MP、属性への耐性、それからドロップ品が書かれている様式になる。しかし、日々魔物と戦っている彼の目には、あるいは金銀財宝より価値あるものとして映ったに違いない。
魔物の速やかな討伐は、一番重要な財産である領民の死傷者減少に繋がる。加えて、ドロップ品の情報を上手く使えば、通年資金難である状況を改善することだってできるだろう。
私はようやく顔を上げたハルトシェイクに、自分の勝利を確信した。
私はコーデラー侯爵家に「売られた」者ではなく、「売り込みに来た」者に変われたのだ。
「そちらも私が写生スキルで作成しました。アストン領の求める人材は、魔術師でしたね? ですが、ここにいる兵士の方々が魔法を使えるようになるなら、コーデラー侯爵家の魔術師一人が来るより、私の能力の方が役立つと思われませんか?」
胸を張って、ハルトシェイクに尋ねる。
さすがに隠しきれない私の浮かれた気持ちが態度に出てしまっていたのか、一瞬キョトンとした彼は次に「はははっ」と声を上げて笑った。
その光景に、逆に私の方が呆気に取られる。
ゲーム中のハルトシェイクは既に家門を継いでおり、氷の貴公子改め氷の辺境伯だった。辺境伯の彼はその異名の通り、本当にピクリとも笑わないキャラだったのだ。
「よくアストン領へ来てくれた。歓迎しよう、フェリアン嬢」
「! ありがとうございます」
どうやら無事に明るいセカンドライフが始まりそうである。
私はこの場での緊張、そして威圧的な実家からの解放に、踊り出したい気分で執務室を後にした。
五日前。コーデラー侯爵家にて――
「アストン辺境伯家からの要請には、フェリアン、お前を送る」
夕食の席にて放たれた、父――ゴードン・コーデラーの信じられない一言に、私は危うくフォークを取り落とすところだった。珍しく同席を求められたかと思えば案の定、ろくな用件ではなかったようだ。
彼の家門からの要請とは、常に魔物の脅威に晒されている辺境伯領への人材支援のこと。数日前に届いた一通の手紙は、今日までコーデラー侯爵家をざわつかせていた。
当主すら凌駕する魔力を持つ兄か、それともテクニックに優れた長女か。はたまた、威力こそ劣るものの複数の属性魔法を操る三女が選ばれるのか。
何れにせよ魔術師ではない私には関係の無い話……のはずだった。
「……アストン辺境伯は当然、我が家からは魔術師の誰かを送ると考えていると思いますが?」
「さあな。どんな奴を寄越せという指定はなかった。それなら有能な我が子をわざわざ行かせる必要もない。要望に応えて、コーデラー侯爵家の者をちゃんと送ってやるんだ。期待するのも向こうの勝手であれば、期待に応えられないお前のことも私の知るところではない」
話は終わりだと言わんばかりに、ゴードンが黙々と食事を口に運ぶ。
周りを見れば、母、兄、姉はいつもと変わらぬ様子で食事をしており、妹のシャルロットだけがおかしそうに笑っていた。
「フェリアンお姉様。戦死者の遺族には、見舞金が出るんですって! ああでも、あまりに役に立たなすぎて戦死扱いされなかったらどうしましょう」
明け透けなシャルロットの言葉にも、家族の誰もが咎めようとしない。
他の家族も妹同様、無関心を装った表情の裏では私の死を願っているのだろう。「コーデラー侯爵家の汚点」が合法的に消えてくれることを。
私は目の前の料理を口の中に詰め込み、咀嚼しながら席を立った。
そんな貴族らしからぬマナー違反をしても、そのまま食堂を出ても、誰一人私に声を掛ける者はいない。
結局、翌日辺境伯邸に着くまでに私に掛けられた言葉は、侯爵家で一番ボロい馬車を操る御者の「早く乗れ」というたった一言だけだった。