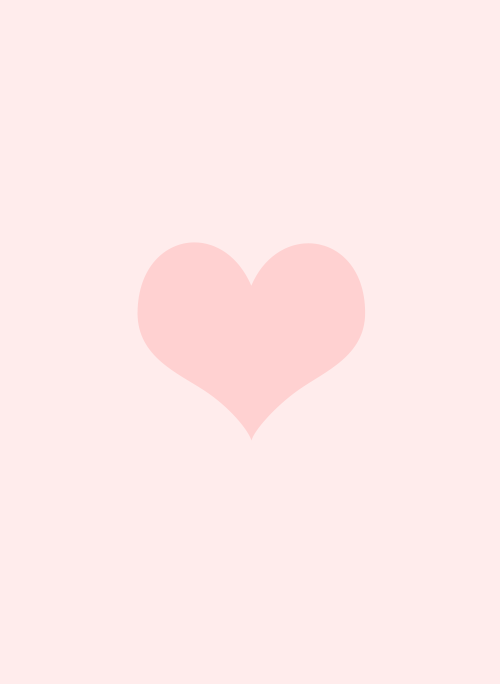十日古道
僕は、前の道をずーっと先に進んで行ったことや、それなのにまた元の大木のところに戻って来たことを説明した。男は、それは当然だと言った。そして、消えた道の事と消えた麦わら帽子の人のことも話した。
「麦わら帽子って、何人いた?」
「えーっと、二人だった」
「そうだろな」
「知ってるの?」
「お前たちは何人だ?」
「二人だけど」
「そういう事だ」
何がそういう事なのか解らなかった。佑樹も首を横に振っている。麦わら帽子の二人がいったい何だって言うのだろう。
「なぞなぞかも知れないよ」
考えてる僕に佑樹が顔を寄せて言った。
「なぞなぞ?」
「うん」
なぞなぞねえ・・・・
二人と二人。
「ねえ、おじさん」
「何だ?」
「あの麦わら帽子の二人は何処へ行ったの?」
「あの二人はなあ・・・」
男が立ちあがってゆっくりと近付いてきた。僕と佑樹はビックリして後退りした。
「お前らの家に戻ったんだよ」
「戻った?」
「ああ、戻ったんだよ」
佑樹が「どういう事?」と言った。
「お前らが入った細い道に何か書いてなかったか?」
僕と祐樹はヒソヒソと話し合った。
「確か、十日古道だったと思う」
男は、十日古道は一年間の内、十日しか道が開かないと言う。それが十日連続だったり一日ずつだったり。または、二日だったり三日だったり。
「それがたまたま今日だったってこと?」
「そういう事だな」
「麦わら帽子のあの二人は、どうして?」
男は面倒くさそうな素振りを見せた。そして、こう言った。
「さっき言った通りだ。お前ら二人が十日古道に入ってきたので、その代わりにあの二人が出る事になっただけだ」
「えっ?」
どうして僕らが十日古道に入ったのが分かったのか、僕らは顔を見合わせたがお互いに分かるはずもなかった。
「もしかしたら・・・」
「何?」
「入り口にカメラがあるとか」
そうだ。あそこでは気付かなかったけど、佑樹の言う通りかも知れない。
「おじさん、入り口の防犯カメラを見てたんでしょ?」
僕は言い当てた気分になった。佑樹も僕の方をポンポンと叩いた。
「ね、そうでしょ?」
僕はドヤりながら追撃した。
男は、微かに首を振りながら否定する素振りをした。そして、こう言った。
「ここはしち屋だからな。解るんだよ」
「えっ?」
「誰かが入ったら、誰かを代わりに放出する。だから、誰が何人入って来たか、俺の中で解るんだよ。出すのも俺が決めてるよ。相手に見合う様な奴をな」
解り難かった。というより、何ここは?という気持ちのほうがより強くなった。
「僕たち、どうしたら帰れるの?」
「お前らはもうここの人間になったんだよ。この村がお前らの住処なんだから、何処でも好きな家を探して住めば良い。それに食い物は、外を探して回れば何かしらあるから心配するな。それを食べても良いし、誰かと交換しても良い」
男はそう言って奥に向かい、また畳の上に上がって寝転んだ。
「あのー、何処に行けば?」
「だから、その辺の好きなところを探せ」
男は背中を向けた。
「祐樹・・・・」
「・・・・」
「取り敢えず、探そうか」
「うん・・・・」
しち屋を出ようとした時、祐樹が振り返り大声で叫んだ。
「僕らはいつ戻れますか?」
男は右手を上げて追い払うように手の甲を
二、三度降った。
「知らん」
もう、それ以上答える気はなさそうだった。
あの麦わら帽子の二人、何十年前の格好だったんだろう。
「麦わら帽子って、何人いた?」
「えーっと、二人だった」
「そうだろな」
「知ってるの?」
「お前たちは何人だ?」
「二人だけど」
「そういう事だ」
何がそういう事なのか解らなかった。佑樹も首を横に振っている。麦わら帽子の二人がいったい何だって言うのだろう。
「なぞなぞかも知れないよ」
考えてる僕に佑樹が顔を寄せて言った。
「なぞなぞ?」
「うん」
なぞなぞねえ・・・・
二人と二人。
「ねえ、おじさん」
「何だ?」
「あの麦わら帽子の二人は何処へ行ったの?」
「あの二人はなあ・・・」
男が立ちあがってゆっくりと近付いてきた。僕と佑樹はビックリして後退りした。
「お前らの家に戻ったんだよ」
「戻った?」
「ああ、戻ったんだよ」
佑樹が「どういう事?」と言った。
「お前らが入った細い道に何か書いてなかったか?」
僕と祐樹はヒソヒソと話し合った。
「確か、十日古道だったと思う」
男は、十日古道は一年間の内、十日しか道が開かないと言う。それが十日連続だったり一日ずつだったり。または、二日だったり三日だったり。
「それがたまたま今日だったってこと?」
「そういう事だな」
「麦わら帽子のあの二人は、どうして?」
男は面倒くさそうな素振りを見せた。そして、こう言った。
「さっき言った通りだ。お前ら二人が十日古道に入ってきたので、その代わりにあの二人が出る事になっただけだ」
「えっ?」
どうして僕らが十日古道に入ったのが分かったのか、僕らは顔を見合わせたがお互いに分かるはずもなかった。
「もしかしたら・・・」
「何?」
「入り口にカメラがあるとか」
そうだ。あそこでは気付かなかったけど、佑樹の言う通りかも知れない。
「おじさん、入り口の防犯カメラを見てたんでしょ?」
僕は言い当てた気分になった。佑樹も僕の方をポンポンと叩いた。
「ね、そうでしょ?」
僕はドヤりながら追撃した。
男は、微かに首を振りながら否定する素振りをした。そして、こう言った。
「ここはしち屋だからな。解るんだよ」
「えっ?」
「誰かが入ったら、誰かを代わりに放出する。だから、誰が何人入って来たか、俺の中で解るんだよ。出すのも俺が決めてるよ。相手に見合う様な奴をな」
解り難かった。というより、何ここは?という気持ちのほうがより強くなった。
「僕たち、どうしたら帰れるの?」
「お前らはもうここの人間になったんだよ。この村がお前らの住処なんだから、何処でも好きな家を探して住めば良い。それに食い物は、外を探して回れば何かしらあるから心配するな。それを食べても良いし、誰かと交換しても良い」
男はそう言って奥に向かい、また畳の上に上がって寝転んだ。
「あのー、何処に行けば?」
「だから、その辺の好きなところを探せ」
男は背中を向けた。
「祐樹・・・・」
「・・・・」
「取り敢えず、探そうか」
「うん・・・・」
しち屋を出ようとした時、祐樹が振り返り大声で叫んだ。
「僕らはいつ戻れますか?」
男は右手を上げて追い払うように手の甲を
二、三度降った。
「知らん」
もう、それ以上答える気はなさそうだった。
あの麦わら帽子の二人、何十年前の格好だったんだろう。