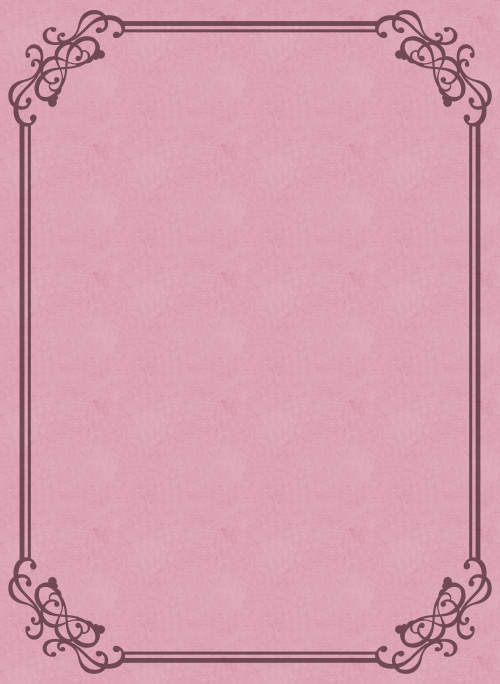冷徹専務は、私の“嘘”に甘くなる
エピローグ
朝のダイニングに、香ばしいトーストの匂いが漂っていた。
フライパンの前には、エプロン姿の澪。
彼女の隣では、相変わらず不器用な手つきでベーコンをひっくり返す心春――もう中学生になった彼女は、制服姿が少し大人びて見える。
「焦げてない? 焦げてないよね?」
「うん、大丈夫。じょうず、じょうず」
ふたりで笑いながら作業する姿は、見慣れた朝の風景になっていた。
その様子を新聞を読みながら眺めていると、心春がふとこっちを見た。
「ねぇ、パパ」
「ん?」
「澪さんのこと、好きになったのって……会社に入ってから?」
唐突な問いに、新聞の活字が一瞬にして目から消えた。
コーヒーをひと口飲んで、さりげなく新聞を折りたたむ。
「……どうして、そんなこと聞くんだ?」
「うーん、なんとなく?」
心春は、トーストにいちごジャムを塗りながら、飄々と答えた。
「この前、澪さんが大学のテニス部の頃の話してたの。でさ、テニスコートの隣の保育園にパパ、たまに迎えに来てたでしょ? まさかあのときから、澪さんのこと知ってたんじゃないの〜?」
そう言って、心春はわざとからかうようにニヤッと笑った。
俺は、一瞬だけ視線を逸らした。
たしかに、金網の外から――
彼女が笑っている姿を、密かに見ていた。
無邪気な少女と楽しそうに言葉を交わす、若い女子大生。
その笑顔が、やけにまぶしくて。
その声が、なぜか耳に残って――
自分でも理由がわからないまま、足を止めた。
「……言ってないよ」
少しの沈黙のあと、俺はそう答えた。
「え、なにを?」
「澪には、言ってない。あの頃、見てたことも、覚えてたことも」
心春は目を丸くしたあと、吹き出すように笑った。
「だよねぇ〜。三十過ぎのおっさんが女子大生のこと陰から見てたって、キモいもんね」
「……お前な」
「でも、ちょっとロマンチックかも」
そう言って心春は、ジャムのついた指をぺろりと舐めて、ウインクする。
「うん、安心して。あたしも一生、澪さんには言わないでおく」
その言葉が、あまりにも自然すぎて、俺はつい苦笑した。
「……頼むよ、ほんとに」
「任せて。“オトナの秘密”ってことで」
どこでそんな言葉覚えてきたのかと呆れつつも、
俺の胸の奥には、確かに少しだけ温かいものが灯っていた。
やがて、澪が「できたよー」とトレーを持って席に戻ってきた。
焼きたてのトースト、フルーツヨーグルト、スクランブルエッグ。
澪はふたりの様子を見て、少し首を傾げた。
「どうしたの、何か話してた?」
「んー、ひみつ」
心春がそう言って笑うと、澪は不思議そうに目を細めたが、
すぐに優しく笑って「じゃあ、後でこっそり教えてね」と言った。
この空気が、愛おしいと思った。
この何でもない朝が、何よりの幸せだと――
心から思った。
過去の金網越しの記憶も、
すれ違い続けた日々も、
たくさんの誤解や、言えなかった想いも――
全部この朝のためにあったのかもしれない。
隣にいる彼女と、
これからの未来を、一緒に歩いていける。
そして、その未来には――
心春がいて、笑い声があって、パンの香りがある。
それだけでいい。
たとえ何も言わなくても、
彼女の笑顔が“今”を愛してくれていることを知っているから。
俺は、黙って胸の奥に決めた。
――この秘密は、一生、胸の中にしまっておこう。
フライパンの前には、エプロン姿の澪。
彼女の隣では、相変わらず不器用な手つきでベーコンをひっくり返す心春――もう中学生になった彼女は、制服姿が少し大人びて見える。
「焦げてない? 焦げてないよね?」
「うん、大丈夫。じょうず、じょうず」
ふたりで笑いながら作業する姿は、見慣れた朝の風景になっていた。
その様子を新聞を読みながら眺めていると、心春がふとこっちを見た。
「ねぇ、パパ」
「ん?」
「澪さんのこと、好きになったのって……会社に入ってから?」
唐突な問いに、新聞の活字が一瞬にして目から消えた。
コーヒーをひと口飲んで、さりげなく新聞を折りたたむ。
「……どうして、そんなこと聞くんだ?」
「うーん、なんとなく?」
心春は、トーストにいちごジャムを塗りながら、飄々と答えた。
「この前、澪さんが大学のテニス部の頃の話してたの。でさ、テニスコートの隣の保育園にパパ、たまに迎えに来てたでしょ? まさかあのときから、澪さんのこと知ってたんじゃないの〜?」
そう言って、心春はわざとからかうようにニヤッと笑った。
俺は、一瞬だけ視線を逸らした。
たしかに、金網の外から――
彼女が笑っている姿を、密かに見ていた。
無邪気な少女と楽しそうに言葉を交わす、若い女子大生。
その笑顔が、やけにまぶしくて。
その声が、なぜか耳に残って――
自分でも理由がわからないまま、足を止めた。
「……言ってないよ」
少しの沈黙のあと、俺はそう答えた。
「え、なにを?」
「澪には、言ってない。あの頃、見てたことも、覚えてたことも」
心春は目を丸くしたあと、吹き出すように笑った。
「だよねぇ〜。三十過ぎのおっさんが女子大生のこと陰から見てたって、キモいもんね」
「……お前な」
「でも、ちょっとロマンチックかも」
そう言って心春は、ジャムのついた指をぺろりと舐めて、ウインクする。
「うん、安心して。あたしも一生、澪さんには言わないでおく」
その言葉が、あまりにも自然すぎて、俺はつい苦笑した。
「……頼むよ、ほんとに」
「任せて。“オトナの秘密”ってことで」
どこでそんな言葉覚えてきたのかと呆れつつも、
俺の胸の奥には、確かに少しだけ温かいものが灯っていた。
やがて、澪が「できたよー」とトレーを持って席に戻ってきた。
焼きたてのトースト、フルーツヨーグルト、スクランブルエッグ。
澪はふたりの様子を見て、少し首を傾げた。
「どうしたの、何か話してた?」
「んー、ひみつ」
心春がそう言って笑うと、澪は不思議そうに目を細めたが、
すぐに優しく笑って「じゃあ、後でこっそり教えてね」と言った。
この空気が、愛おしいと思った。
この何でもない朝が、何よりの幸せだと――
心から思った。
過去の金網越しの記憶も、
すれ違い続けた日々も、
たくさんの誤解や、言えなかった想いも――
全部この朝のためにあったのかもしれない。
隣にいる彼女と、
これからの未来を、一緒に歩いていける。
そして、その未来には――
心春がいて、笑い声があって、パンの香りがある。
それだけでいい。
たとえ何も言わなくても、
彼女の笑顔が“今”を愛してくれていることを知っているから。
俺は、黙って胸の奥に決めた。
――この秘密は、一生、胸の中にしまっておこう。