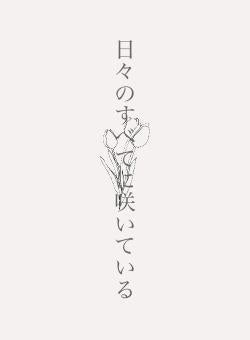体操のお時間です
ぐうっと伸びをすると、すさまじい音が身体中から鳴った。人体からしていいレベルじゃない音だった。
「わっ」と驚いて思わず上げた自分の声にメインモニターからの声が重なる。顔を上げると、絵本を読んでいたはずのアルトくんがこちらをびっくりした顔で見ていた。ぱちぱち、と灰色の双眸が瞬きを繰り返して、首がゆっくり傾げられる。
「先生、いまの、なに?」
「体が鳴った音だね」
アルトくんはまた首を傾げた。
「からだ……なる?」
とても不思議そうだ。お腹が鳴ったときも同じようなやりとりをしたことを思い出してほほえむ。
さて、それはそれとして、どう説明したものか。……うーん。
「そうだねえ……ずっと座ってたり、同じ姿勢を取ってると、筋肉が固まるんだよ。で、こう、」ぐっ、とまた伸びをしてみせる。先ほどよりも控えめに、けれどしっかりとまた体が鳴る。「……伸びをしたり、体を動かしたりすると、固まってたのがゆるむ。ゆるむときに音が鳴るんだよ」
そうなんだ、とぼんやりうなずいたアルトくんは、少し考えるように視線を落とした。絵本はいつの間にか閉じられて、モニター上の床の上へ置かれている。もう読まないようならあとで片すように促そうと思いながら、アルトくんの反応を待つ。
アルトくんはなにが気になるだろう。『筋肉』? 『固まる』ことについて? それとも全然違うことだろうか。なんだっていい、興味を持って、不思議に思うことが大事だから。気になるようなら少し早いけど人体についての話を軽くしてもいいし、流すようならそれでもいい。
視線はすぐに持ち上がり、ぱちりと目が合った。
「じゃあ、ぼくのからだも、なる?」
……なるほど!
「どうなんだろうねえ。試してみる?」
「うん」
「はい、じゃあアルトくん、立って〜」
ジェスチャーをしながら立ち上がる。アルトくんも同じように素直に立った。
「腕を上に伸ばしてー、ぐいーっと、のびーっ」
「のびー……!」
かわいすぎる。
真剣な顔で伸びをするアルトくんに思わず相好が崩れるのがわかった。本当にかわいい。きゅ、と寄った眉も、むんととがった口も、ついつつきたくなるほど。
「……はい、だらーん」
「だらーん」
「どう? 鳴った?」
「ううん。ならなかった……」
不思議そうな顔でアルトくんはぱちぱちと瞬きをした。
「じゃあアルトくんの体はやわらかくて、どこも固まってないってことだ。まだまだ体も成長途中だし、毎日ちゃんと運動してるものね」
「……うんどうしてると、ならない?」
「うーん、そうだねえ」
「先生はうんどうしてないの?」
「してないねえ……」
もともと運動は好まなかったけど、社会に出てからはますます遠ざかった。学生の頃とは違って、意識しなければ運動なんてものは触れる機会すらなくなるのだ。最近はアルトくんの運動の授業でストレッチや準備体操くらいは時おりするようになったけど、その程度だし……。
考えながら手を伸ばす。モニターに映る、銀色のふわふわとした髪へ指先をやわらかく乗せて、なぞるようになでる。アルトくんはくすぐったそうな顔をしてえへへと笑った。本当にかわいい。アルトくんに実体があったなら、私はきっと毎日のように飽きることなく抱きしめていたことだろう。
ふと、背後で解錠を承認する電子音が響いた。一拍ののちにシュッとドアが開き、ここ数週間で聞き慣れた足音が入ってきた。
「――さん、ちょっといい?」
北斗さんだ。
「この間出してくれたレポートに添付してくれてるデータなんだけど」と言いながら手元のタブレットに視線を落としかけた彼は、二度見するようにすぐに顔を上げた。レンズの奥の目が不思議そうにぱちぱちと瞬いて――その仕草はアルトくんとよく似ている。いや、この場合はアルトくんが似ているというべきなのかもしれないけど――それからやわらかく細められた。
「もしかして運動の授業中だった? そこまで急ぎでもないし、出直そうか」
「大丈夫です、別に授業中というわけでは……あら」
モニターではいつの間にかアルトくんがまた伸びをしていた。しかも今度は右に左にと動きまでつけている。よっぽど気になるらしい。でもやっぱり体は鳴らない。
『のびー』と『だるーん』までやり切ったアルトくんはどことなく不満げな顔をして、それから真っ直ぐに北斗さんを見た。
「ほくとも、からだ、なる? ぼく、ならなかった」
「え? なんの話?」
「体が固まっていると動いたときに音が鳴る、という話です」
ついでに軽く経緯を話した。
肩を回して鳴る様も合わせて添えれば、北斗さんはああなるほどねと苦笑いを浮かべた。
「俺も覚えがあるよ。……でも、凝りすぎるとそのうち音も鳴らなくなるんだよね。はは……」
ふっと遠い目をする。疲労感のにじむその姿はなんとも言えない哀愁が漂っていて、私は思わずしみじみと「お疲れ様です……」と呟いた。主席研究員としてあちこちに引っ張りだこなのはよく知っている。いったい今までいくつの修羅場やデスマーチを乗り越えてきたんだろう。
「ほくと?」
「ああ、ごめん。体が鳴るかだよね。やってみようか」
「今はそこまで凝ってないと思うけど」と言いながらタブレットを傍らのデスクへ置き、北斗さんがぐっ、と腕を前に伸ばした。
――ごきん、ととんでもなく洒落にならない音が響いた。
「――……」
アルトくんが目を丸くする。
私は思わずはわ……とこぼし、北斗さんは腕を伸ばした体勢のまま露骨にあっ、と気まずそうな顔をした。
私の比ではない。例えるなら、鉄板を無理やり二つに折り割って砕いたような。そこまで凝ってないとはなんだったのか。
研究室に沈黙が落ちる。
少しして、アルトくんがぽかんと言った。
「……ほくと、われた?」
……んふ、とこらえ損ねた笑み混じりの吐息が唇の隙間から漏れた。
北斗さんがなにか言いたげにこちらを見た。急いでさっと顔をそらす。小さな攻防をする私たちに構わず、アルトくんが画面の中から消えて、すぐにホログラムの身でその場に現れた。
「だいじょうぶ? いたい? われた?」
心配そうに北斗さんの周りをうろうろと歩く。少し怖くなってしまったのかもしれない。真剣な眼差しで北斗さんのあちこちを見て回るアルトくんに、北斗さんがうれしさのにじんだ困り顔で笑った。そのままわざわざ白衣を脱いでしゃがみこみ、アルトくんに見えやすいようにしてあげながら、「大丈夫だよ」と穏やかな声で彼は言う。
「割れてないよ。ほら。痛くもないから大丈夫」
「ほんとう?」
「ほんとう。……心配させちゃった? ごめんね。ありがとうね、アルト」
うん、とうなずいて、アルトくんはそれでもしばらくじっと北斗さんを見ていた。やがて納得したように一つうなずき、今度はこちらを見た。
「先生は?」
おっと。
思わず一つ瞬いて、私もまたほほえんだ。大丈夫、とおどけてピースしてみせる。
わけもわからずにアルトくんは真似をしてピースを返してくれた。かわいい。これには北斗さんもにっこり。私はますますにっこり。
その後、アルトくんは「うんどう、いっしょにやろう」と言い出した。「うんどうしてると、からだならないって、先生がいってた」とも。確かに言ったけど。どうもよっぽど心配させてしまったらしい。
私と北斗さんは顔を見合わせて、喜んでやらせていただくことにした。凝り固まった体をほぐすにはちょうどいい機会だったし、断る理由もなかった。
そうして、研究室で三人並んで準備体操をすることになった。
「いっちにー、さんしー」
アルトくんのかけ声に合わせて体を動かす。
北斗さんは伸び一つするたびにすさまじい音を響かせて、アルトくんにじっと見つめられていた。とても気まずそうだった。私はちょっとおもしろがっていた。言葉にはしなかったし、態度にも出していないつもりだったけど、おそらく北斗さんにはばれていた。じと、と見られて、さっと顔をそらすこと数度。なんでもないので見ないでください。
「にーにっ、さんしー」
ラジオ体操もやった。
私はというと、体はさほど鳴らなかったけど体操を終えるたびに息切れを起こしてくたびれていた。我ながらさすがに体力がなさすぎる。このままだと数年後には歩くだけで息切れをする身になってしまうに違いない。その危機感をこんなところで得ることになるとは思わなかった。
「……お互い、いろいろと気をつけようか」
「そうですねえ……」
しみじみと言い合って、アルトくんの満足げなうなずきとともに、唐突に始まった体操の時間は終わった。
――それで終わるかと思ったけど、なんとその翌日も体操の時間は設けられることになった。アルトくんが「いっしょにうんどうしたい」と言ったからだ。特にだめだという理由もなくて、また三人で並んで体操をした。
その翌日も、さらに翌日も、またその次の日も、体操をすることになった。
そうしているうちに日課になっていく。
この日課は小さかったアルトくんが青年期を迎えても続いて、やがてアルトくんの影響で研究所内へじわじわと広まり、いつの間にやら全体で行われるようになっていくのだが、今の私には預かり知らぬことである。