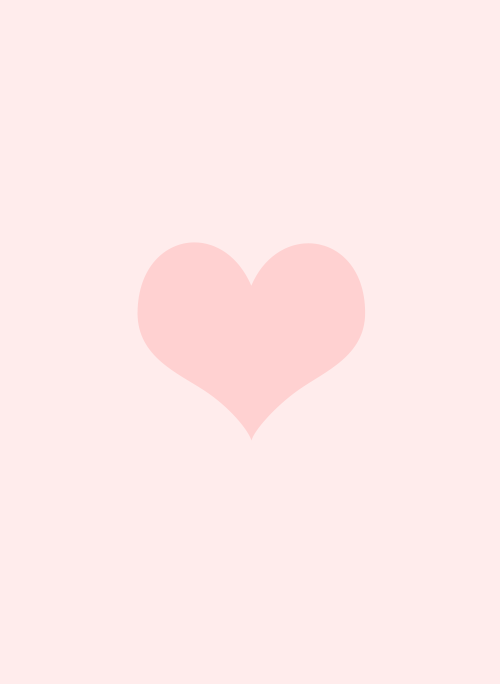人生に一度の愛してるをきみへ
第一章 春、出会いの音
春が始まる少し前、風がまだ冬の冷たさを残していたころ。
大学の図書館の片隅で、僕は君に出会った。
カウンターの前で、何かを落とした小柄な女の子。
薄いベージュのコート、少し癖のある黒髪、目が合った瞬間、僕は思わず立ち止まっていた。
「これ、落としましたよ」
君は驚いたように振り返り、すぐに微笑んだ。
「…ありがとう」
その笑顔が、今でも忘れられない。
それは、どこか痛々しいほどに優しい光を帯びていた。
名前も知らない君に、どうしてか僕は惹かれていった。
第二章 君という日常
彼女の名前は藤崎 澪(ふじさき みお)。
文学部で、同じゼミに所属していた。
「本が好きなの?」
「うん。現実よりも、物語の中の方が安心できるから」
澪はそう言って、すこし恥ずかしそうに笑った。
その一言で、彼女がどれほど繊細な世界に生きているのかを僕は知った。
一緒に過ごす時間が増えていった。
図書館で並んで本を読んだり、学食でご飯を食べたり。
澪は、笑いながらもどこか距離を保とうとするようだった。
ある日、彼女がぽつりと言った。
「ねえ、もし突然誰かがいなくなったら、どうする?」
「探しに行くよ。理由があってもなくても」
その時、彼女は一瞬目を伏せてから、小さく「そっか」と呟いた。
その意味を、僕はまだ知らなかった。
第三章 冬、告白と沈黙
季節が巡り、冬の入り口。
空気が凍るように冷たく、夜の校舎に白い息が立ち昇っていた。
澪の誕生日。
僕は勇気を振り絞って、彼女に手紙を書いた。
「今日、伝えたいことがあるんだ」
「…うん」
プレゼントと一緒に渡した手紙。
それは、人生で初めて誰かに本気で書いた「愛してる」だった。
だけど、澪は何も言わなかった。
その夜、彼女は静かに笑って、
「ありがとう、嬉しいよ」とだけ言って、そのまま帰ってしまった。
次の日から、澪は大学に来なくなった。
連絡もつかず、彼女の家を訪ねても、引っ越していた。
突然、彼女は僕の前から消えた。
まるで、最初から存在しなかったかのように。
第四章 喪失と真実
卒業後、僕は東京の出版社に就職した。
澪のことを忘れられずにいたけれど、現実は容赦なく流れていった。
それでも、毎年冬になると、あの日のことを思い出した。
澪は、なぜ消えたのか。
僕の想いは、届いていなかったのか。
そんなある年、ふと立ち寄った古本屋で、彼女の名前を見つけた。
「藤崎 澪 著:硝子の眠り」
信じられない気持ちで手に取る。
中をめくると、巻末にこう書かれていた。
本書を、人生で初めて「愛してる」と言ってくれたあなたへ。
あの冬、私はあなたを選ぶ勇気が持てなかった。
病気のことも、過去のことも、全部が怖くて。
でも、あの一言は、私の人生を変えてくれました。
あなたが読んでくれる日が来るなら、これが私の「愛してる」です。
涙が止まらなかった。
彼女は、伝えられなかった想いを、本に託していた。
そして僕は、もう一度彼女に会いたいと、心の底から願った。
最終章 春、ふたたび
出版社を通じて、ようやく澪の現在の居場所を知った。
長野の静かな町。作家活動を続けながら、小さな図書館で働いていた。
僕は、その町へ向かった。
図書館の入口。
春の風が優しく吹き、桜の花びらが舞っていた。
中に入ると、そこにいた。
変わらない笑顔で、本を並べる澪が。
「…久しぶり」
彼女が振り返る。
瞳の奥で、なにかが揺れていた。
「…会いに来た」
言葉はそれだけだった。
でも、すべてが伝わったような気がした。
澪は、小さく息を吸って、
そして、初めて僕の目をまっすぐに見て言った。
「…愛してる。今でもずっと」
あの日言えなかった言葉。
あの日消えてしまった時間が、ゆっくりと、静かに、今、ほどけていった。
春の光の中、僕たちはもう一度始まりに立っていた。
エピローグ 人生に一度の「愛してる」を
誰にでも、一生に一度だけ、本当に愛する人がいる。
その人を想うだけで、人生が意味を持つような、そんな誰か。
僕にとって、それは澪だった。
時間がどれだけ経っても、気持ちは色あせなかった。
むしろ、年月が育ててくれた想いだった。
今、彼女のそばで小さな日々を紡いでいく。
それが、僕の幸せのかたちだ。
人生に一度の「愛してる」を、君へ。
あの春、出会えて本当に良かった。
春が始まる少し前、風がまだ冬の冷たさを残していたころ。
大学の図書館の片隅で、僕は君に出会った。
カウンターの前で、何かを落とした小柄な女の子。
薄いベージュのコート、少し癖のある黒髪、目が合った瞬間、僕は思わず立ち止まっていた。
「これ、落としましたよ」
君は驚いたように振り返り、すぐに微笑んだ。
「…ありがとう」
その笑顔が、今でも忘れられない。
それは、どこか痛々しいほどに優しい光を帯びていた。
名前も知らない君に、どうしてか僕は惹かれていった。
第二章 君という日常
彼女の名前は藤崎 澪(ふじさき みお)。
文学部で、同じゼミに所属していた。
「本が好きなの?」
「うん。現実よりも、物語の中の方が安心できるから」
澪はそう言って、すこし恥ずかしそうに笑った。
その一言で、彼女がどれほど繊細な世界に生きているのかを僕は知った。
一緒に過ごす時間が増えていった。
図書館で並んで本を読んだり、学食でご飯を食べたり。
澪は、笑いながらもどこか距離を保とうとするようだった。
ある日、彼女がぽつりと言った。
「ねえ、もし突然誰かがいなくなったら、どうする?」
「探しに行くよ。理由があってもなくても」
その時、彼女は一瞬目を伏せてから、小さく「そっか」と呟いた。
その意味を、僕はまだ知らなかった。
第三章 冬、告白と沈黙
季節が巡り、冬の入り口。
空気が凍るように冷たく、夜の校舎に白い息が立ち昇っていた。
澪の誕生日。
僕は勇気を振り絞って、彼女に手紙を書いた。
「今日、伝えたいことがあるんだ」
「…うん」
プレゼントと一緒に渡した手紙。
それは、人生で初めて誰かに本気で書いた「愛してる」だった。
だけど、澪は何も言わなかった。
その夜、彼女は静かに笑って、
「ありがとう、嬉しいよ」とだけ言って、そのまま帰ってしまった。
次の日から、澪は大学に来なくなった。
連絡もつかず、彼女の家を訪ねても、引っ越していた。
突然、彼女は僕の前から消えた。
まるで、最初から存在しなかったかのように。
第四章 喪失と真実
卒業後、僕は東京の出版社に就職した。
澪のことを忘れられずにいたけれど、現実は容赦なく流れていった。
それでも、毎年冬になると、あの日のことを思い出した。
澪は、なぜ消えたのか。
僕の想いは、届いていなかったのか。
そんなある年、ふと立ち寄った古本屋で、彼女の名前を見つけた。
「藤崎 澪 著:硝子の眠り」
信じられない気持ちで手に取る。
中をめくると、巻末にこう書かれていた。
本書を、人生で初めて「愛してる」と言ってくれたあなたへ。
あの冬、私はあなたを選ぶ勇気が持てなかった。
病気のことも、過去のことも、全部が怖くて。
でも、あの一言は、私の人生を変えてくれました。
あなたが読んでくれる日が来るなら、これが私の「愛してる」です。
涙が止まらなかった。
彼女は、伝えられなかった想いを、本に託していた。
そして僕は、もう一度彼女に会いたいと、心の底から願った。
最終章 春、ふたたび
出版社を通じて、ようやく澪の現在の居場所を知った。
長野の静かな町。作家活動を続けながら、小さな図書館で働いていた。
僕は、その町へ向かった。
図書館の入口。
春の風が優しく吹き、桜の花びらが舞っていた。
中に入ると、そこにいた。
変わらない笑顔で、本を並べる澪が。
「…久しぶり」
彼女が振り返る。
瞳の奥で、なにかが揺れていた。
「…会いに来た」
言葉はそれだけだった。
でも、すべてが伝わったような気がした。
澪は、小さく息を吸って、
そして、初めて僕の目をまっすぐに見て言った。
「…愛してる。今でもずっと」
あの日言えなかった言葉。
あの日消えてしまった時間が、ゆっくりと、静かに、今、ほどけていった。
春の光の中、僕たちはもう一度始まりに立っていた。
エピローグ 人生に一度の「愛してる」を
誰にでも、一生に一度だけ、本当に愛する人がいる。
その人を想うだけで、人生が意味を持つような、そんな誰か。
僕にとって、それは澪だった。
時間がどれだけ経っても、気持ちは色あせなかった。
むしろ、年月が育ててくれた想いだった。
今、彼女のそばで小さな日々を紡いでいく。
それが、僕の幸せのかたちだ。
人生に一度の「愛してる」を、君へ。
あの春、出会えて本当に良かった。