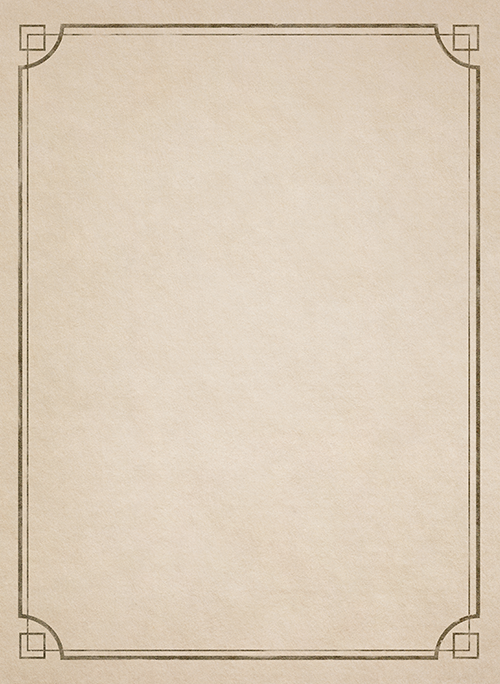忘れたあなたと、知らないふりして
第五話
あの日、事故現場の交差点に立ってから、私の心は変な静けさを取り戻してた。いや、それはきっと、前向きなものじゃなくって、諦めにも似たものだったのかもしれない。
けれど、私は、そのいつか来る「その時」に対する覚悟が、無意識のうちに固まりつつあった。
日記アプリに吐き出した身勝手な本音は、私の心の奥底に沈んで、重たい泥みたいになって横たわってた。
そして、運命の日がやってきた。
次の授業日。インターホンの音に、私はもう驚かなかった。ドアを開けると、そこに立ってた彼の表情はいつもよりちょっと硬いように見えた。彼もまた、あの日の記憶の断片に心をゆさゆさ揺さぶられてるのかも。
部屋に入って、机に向かい合う。二人の間に流れる空気は目に見えないくらい薄くて、ピーンと張り詰めてた。まるで、指でちょっと触れただけでパリンって音を立てて砕けちゃいそう。
授業は、何事もなかったかのように始まった。教科書を開いて、彼が問題を指し示す。私は言われるがままにペンを動かすけど、その内容は少しも頭に入ってこない。私の全神経は、彼のあらゆる変化を捉えようとキーンと研ぎ澄まされてた。彼の息遣い、視線の動き、指先の微かな動揺。そのすべてが、これから起こることの予兆みたいに感じられた。
どれくらいの時間が経っただろうか。
私が解き終えた問題を、彼が覗き込むようにして確認してた、その時だった。私のシャーペンの先が、ノートの上でカチリと小さな音を立てた。ごくありふれた、何の変哲もない音。
けれど、その瞬間、彼の動きがピタリと止まった。
空気が、固まった。
彼は、ノートに落ちてた視線をゆっくりと、まるで錆びついた機械みたいにぎこちなく持ち上げた。その焦点が、だんだん私の顔に結ばれてく。
彼の瞳。
その奥で、今まで見たことのない光がビカビカ激しく点滅してるのが分かった。それは混乱であり、驚愕であり、そして失われた記憶の断片が一つに繋がった瞬間の、稲妻だった。
彼の唇が、わずかに開く。
そして、静寂を破って私の名前を呼んだ。
「――ユキ」
その調子は、私がずっと焦がれてた、昔と同じ呼び方だった。
さん付けじゃない、ただの「ユキ」。
そのたった二文字の音が、私と彼を隔ててた三年っていう時間の壁を、容赦なくバーンと打ち砕いた。
ああ、来たんだ。
ついに、この時が。
私は、ペンを握ったまま動くことができなかった。彼の視線から、逃げることもできない。まるで、金縛りにあったみたい。
「……思い、出した……」
彼の声はひどくかすれてた。自分の声に、自分で驚いてるかのようだった。
「全部……。俺たち、幼馴染だったんだな。あの公園で、いつも……」
記憶の奔流が、彼の中で逆巻いてるのが分かった。彼の瞳は、目の前にいる私と、過去の記憶の中にいる私を必死に行き来してる。
「どうして……」
彼の表情が、変わってく。
「どうして、今まで初対面のふりなんて……」
そして、彼の記憶は核心へとたどり着いた。
「あの日のこと……事故の日のことも、思い出した。俺は、君からのメッセージを待ってて……」
彼の視線が、私を射抜く。それは、怒りっていうよりも、もっと深くて悲しい色をしてた。
「事故の原因は……君が、関係してるのか?」
それは問いかけの形をしてたけど、答えを確信してる人の言葉だった。
もう、嘘はつけない。
言い訳も、できない。
私の目から、堪えてた涙が一筋、頬を伝った。視界がじんわり滲んで、彼の顔がぼやけて見える。
「……そう、だよ」
喉の奥から、やっとのことで絞り出した声は、自分でも驚くくらいか細くて、不安定だった。
「私のせいなの。全部」
堰を切ったみたいに、言葉と涙が溢れ出した。もう、止めることはできなかった。三年間、心の奥底に溜め込んで、鍵をかけてきたすべての感情が濁流となって私の口から吐き出されてく。
「私が、タクミ君に『大事な話がある』なんてメッセージを送ったから……。私が、あなたを呼び出したから……。だから、あなたは事故に遭って、記憶を失って……! ごめんなさい……本当に、ごめんなさい……! あなたの時間を、あなたの記憶を、私が奪っちゃった……。あなたに会わせる顔なんてなかった。だから、ずっと言えなかった……!」
嗚咽が、言葉を遮る。息が苦しい。それでも、私は話すのをやめなかった。今すべてを話さなければ、私はきっと一生この罪の重さに潰されちゃう。
私は、椅子から崩れ落ちるようにして床にペタンと膝をついた。もう彼の顔を見ることさえできない。ただ、床の一点を涙でべちゃべちゃ濡らしながら、謝罪の言葉を繰り返すことしかできなかった。
私の罪の告白が、静まり返った部屋に響き渡る。
やがて、私の嗚咽だけが残った部屋に重たい沈黙が訪れた。
終わった。
すべて、終わったんだ。
彼に軽蔑されて、憎まれて、もう二度と会ってもらえなくなるだろう。それが、私が受けるべき当然の罰。そう、覚悟した。
◇
どれくらいの時間が、流れただろうか。
不意に、頭上から彼の声が降ってきた。
「……顔を、上げて」
その声は、意外なほど静かだった。私は、こわごわ涙でぐしゃぐしゃになった顔を上げる。
そこに立ってた彼は、ひどく混乱した顔をしてた。そして、それ以上に深く、傷ついたような表情をしてた。
「……事故のことが、君のせいだけだなんて思わない」
彼は、ゆっくり言葉を選ぶようにして言った。
「メッセージに気を取られて、周りを見てなかったのは俺自身の責任だ。君が、自分を責める必要は……」
「でも!」
私は、彼の言葉を遮って叫んだ。
「私が呼び出さなければ、こんなことには……!」
「……分からないだろ、そんなこと」
彼は、静かに首を振った。
「それに……もし、そうだとしても……君が、この三年間ずっと一人でそんな重たいものを抱えてきたのかと思うと……」
彼の言葉が、途切れる。その瞳が、悲しみと、そして私に対する憐れみみたいなもので潤んでるように見えた。
彼は、私の向かい側にゆっくりしゃがみ込んだ。その視線が、私の視線の高さと同じになる。
「……正直、まだ頭の中がぐちゃぐちゃだ。思い出した記憶と、今の現実がうまく繋がらない。君がずっと嘘をついてたことだって、ショックじゃなかったと言えば、嘘になる」
彼は、正直な気持ちを一つ一つ、丁寧に言葉にしてくれた。
「でも……」
彼は、そこで一度言葉を切った。そして、ためらうような手で私の頬にそっと触れた。その指先が、私の涙を優しく拭う。
「でも、この事故があったから……俺は、君がどれだけ俺を想ってくれてたか、改めて知ることができたのかもしれない」
その、思いがけない言葉に、私はハッとした。
「もし、事故がなくて、俺が君の想いを知らないままだったら……俺たちは、ただの幼馴染のまま、何か大事なことを見過ごしちゃったかもしれない。こうして家庭教師として君の隣に座って、君の苦しみも喜びも、こんなに近くで感じることもなかった。そう考えたら……この三年間は、失われただけの時間じゃなかったんだって、思うんだ」
彼の言葉は、私の固く閉ざされた心の中に、温かい光みたいにゆっくり差し込んできた。
そんな考え方、私には思いつきもしなかった。私は、ただ失われたものばかりを数えて自分を責め続けてきた。でも、彼はその空白の時間の中に、新しい意味を見出そうとしてくれてた。
「だから……もう、自分を責めるのは、やめてくれ」
彼はそう言って、私の手を両手でそっと包み込んだ。その手の温かさが、私の凍りついた心を少しずつ溶かしてく。
「過去は、もう変えられない。でも、これから先のことは、俺たちで変えてけるだろ?」
私は、彼の言葉にただコクコク頷くことしかできなかった。涙はまだ止まらなかったけど、それはもう罪悪感からくるものじゃなかった。安堵と、感謝と、そして彼への愛しさがごちゃごちゃになった、温かい涙だった。
私たちは、過去を乗り越えたわけじゃない。きっと、この傷跡はこれからもずっと私たちの心に残り続けるだろう。
でも、二人でなら、その傷を抱えたまま前に進んでける。
初めて、そう思えた。
◇
あの日から、私たちの関係はちょっとだけ形を変えた。
彼は、家庭教師を辞めなかった。そして、私も生徒であり続けた。けれど、私たちの間にあった見えない壁は、もうどこにもなかった。
彼は、時々思い出した過去の話をしてくれた。二人で遊んだ公園のこと、一緒に食べたアイスの味、他愛ない会話。そのたびに、私たちは失われた時間を取り戻すみたいに笑い合った。
そして、私の心から罪悪感っていう重たい鎖が外れた時、不思議なことが起きた。今まで、あれほど分からなかった教科書の内容が、すんなり頭に入ってくるようになったんだ。
やがて、中間テストが返却された。
放課後の教室。私は、答案用紙をぎゅっと握りしめて彼の待ついつものファミレスへ急いだ。
「どうだった?」
席に着くなり、彼は尋ねてきた。私は、黙って数学の答案をテーブルの上に置く。
そこに書かれてたのは、今まで見たこともないような高い点数だった。
「……すごいじゃないか!」
彼は、自分のことみたいに目をキラキラ輝かせて喜んでくれた。
「やったな、ユキ!」
「……うん!」
私も、満面の笑みでコクコク頷く。
「先生のおかげです。本当に、ありがとう」
「違うよ。ユキが、頑張ったからだ」
彼はそう言って、あの日と同じように私の頭を優しく撫でてくれた。
窓の外では、夕日が街をオレンジ色に染めてる。
三年前、私は彼に想いを伝えることができなかった。でも、今はもう言葉にしなくても伝わってるような気がする。
私たちの前には、新しい未来がどこまでも広がってた。
けれど、私は、そのいつか来る「その時」に対する覚悟が、無意識のうちに固まりつつあった。
日記アプリに吐き出した身勝手な本音は、私の心の奥底に沈んで、重たい泥みたいになって横たわってた。
そして、運命の日がやってきた。
次の授業日。インターホンの音に、私はもう驚かなかった。ドアを開けると、そこに立ってた彼の表情はいつもよりちょっと硬いように見えた。彼もまた、あの日の記憶の断片に心をゆさゆさ揺さぶられてるのかも。
部屋に入って、机に向かい合う。二人の間に流れる空気は目に見えないくらい薄くて、ピーンと張り詰めてた。まるで、指でちょっと触れただけでパリンって音を立てて砕けちゃいそう。
授業は、何事もなかったかのように始まった。教科書を開いて、彼が問題を指し示す。私は言われるがままにペンを動かすけど、その内容は少しも頭に入ってこない。私の全神経は、彼のあらゆる変化を捉えようとキーンと研ぎ澄まされてた。彼の息遣い、視線の動き、指先の微かな動揺。そのすべてが、これから起こることの予兆みたいに感じられた。
どれくらいの時間が経っただろうか。
私が解き終えた問題を、彼が覗き込むようにして確認してた、その時だった。私のシャーペンの先が、ノートの上でカチリと小さな音を立てた。ごくありふれた、何の変哲もない音。
けれど、その瞬間、彼の動きがピタリと止まった。
空気が、固まった。
彼は、ノートに落ちてた視線をゆっくりと、まるで錆びついた機械みたいにぎこちなく持ち上げた。その焦点が、だんだん私の顔に結ばれてく。
彼の瞳。
その奥で、今まで見たことのない光がビカビカ激しく点滅してるのが分かった。それは混乱であり、驚愕であり、そして失われた記憶の断片が一つに繋がった瞬間の、稲妻だった。
彼の唇が、わずかに開く。
そして、静寂を破って私の名前を呼んだ。
「――ユキ」
その調子は、私がずっと焦がれてた、昔と同じ呼び方だった。
さん付けじゃない、ただの「ユキ」。
そのたった二文字の音が、私と彼を隔ててた三年っていう時間の壁を、容赦なくバーンと打ち砕いた。
ああ、来たんだ。
ついに、この時が。
私は、ペンを握ったまま動くことができなかった。彼の視線から、逃げることもできない。まるで、金縛りにあったみたい。
「……思い、出した……」
彼の声はひどくかすれてた。自分の声に、自分で驚いてるかのようだった。
「全部……。俺たち、幼馴染だったんだな。あの公園で、いつも……」
記憶の奔流が、彼の中で逆巻いてるのが分かった。彼の瞳は、目の前にいる私と、過去の記憶の中にいる私を必死に行き来してる。
「どうして……」
彼の表情が、変わってく。
「どうして、今まで初対面のふりなんて……」
そして、彼の記憶は核心へとたどり着いた。
「あの日のこと……事故の日のことも、思い出した。俺は、君からのメッセージを待ってて……」
彼の視線が、私を射抜く。それは、怒りっていうよりも、もっと深くて悲しい色をしてた。
「事故の原因は……君が、関係してるのか?」
それは問いかけの形をしてたけど、答えを確信してる人の言葉だった。
もう、嘘はつけない。
言い訳も、できない。
私の目から、堪えてた涙が一筋、頬を伝った。視界がじんわり滲んで、彼の顔がぼやけて見える。
「……そう、だよ」
喉の奥から、やっとのことで絞り出した声は、自分でも驚くくらいか細くて、不安定だった。
「私のせいなの。全部」
堰を切ったみたいに、言葉と涙が溢れ出した。もう、止めることはできなかった。三年間、心の奥底に溜め込んで、鍵をかけてきたすべての感情が濁流となって私の口から吐き出されてく。
「私が、タクミ君に『大事な話がある』なんてメッセージを送ったから……。私が、あなたを呼び出したから……。だから、あなたは事故に遭って、記憶を失って……! ごめんなさい……本当に、ごめんなさい……! あなたの時間を、あなたの記憶を、私が奪っちゃった……。あなたに会わせる顔なんてなかった。だから、ずっと言えなかった……!」
嗚咽が、言葉を遮る。息が苦しい。それでも、私は話すのをやめなかった。今すべてを話さなければ、私はきっと一生この罪の重さに潰されちゃう。
私は、椅子から崩れ落ちるようにして床にペタンと膝をついた。もう彼の顔を見ることさえできない。ただ、床の一点を涙でべちゃべちゃ濡らしながら、謝罪の言葉を繰り返すことしかできなかった。
私の罪の告白が、静まり返った部屋に響き渡る。
やがて、私の嗚咽だけが残った部屋に重たい沈黙が訪れた。
終わった。
すべて、終わったんだ。
彼に軽蔑されて、憎まれて、もう二度と会ってもらえなくなるだろう。それが、私が受けるべき当然の罰。そう、覚悟した。
◇
どれくらいの時間が、流れただろうか。
不意に、頭上から彼の声が降ってきた。
「……顔を、上げて」
その声は、意外なほど静かだった。私は、こわごわ涙でぐしゃぐしゃになった顔を上げる。
そこに立ってた彼は、ひどく混乱した顔をしてた。そして、それ以上に深く、傷ついたような表情をしてた。
「……事故のことが、君のせいだけだなんて思わない」
彼は、ゆっくり言葉を選ぶようにして言った。
「メッセージに気を取られて、周りを見てなかったのは俺自身の責任だ。君が、自分を責める必要は……」
「でも!」
私は、彼の言葉を遮って叫んだ。
「私が呼び出さなければ、こんなことには……!」
「……分からないだろ、そんなこと」
彼は、静かに首を振った。
「それに……もし、そうだとしても……君が、この三年間ずっと一人でそんな重たいものを抱えてきたのかと思うと……」
彼の言葉が、途切れる。その瞳が、悲しみと、そして私に対する憐れみみたいなもので潤んでるように見えた。
彼は、私の向かい側にゆっくりしゃがみ込んだ。その視線が、私の視線の高さと同じになる。
「……正直、まだ頭の中がぐちゃぐちゃだ。思い出した記憶と、今の現実がうまく繋がらない。君がずっと嘘をついてたことだって、ショックじゃなかったと言えば、嘘になる」
彼は、正直な気持ちを一つ一つ、丁寧に言葉にしてくれた。
「でも……」
彼は、そこで一度言葉を切った。そして、ためらうような手で私の頬にそっと触れた。その指先が、私の涙を優しく拭う。
「でも、この事故があったから……俺は、君がどれだけ俺を想ってくれてたか、改めて知ることができたのかもしれない」
その、思いがけない言葉に、私はハッとした。
「もし、事故がなくて、俺が君の想いを知らないままだったら……俺たちは、ただの幼馴染のまま、何か大事なことを見過ごしちゃったかもしれない。こうして家庭教師として君の隣に座って、君の苦しみも喜びも、こんなに近くで感じることもなかった。そう考えたら……この三年間は、失われただけの時間じゃなかったんだって、思うんだ」
彼の言葉は、私の固く閉ざされた心の中に、温かい光みたいにゆっくり差し込んできた。
そんな考え方、私には思いつきもしなかった。私は、ただ失われたものばかりを数えて自分を責め続けてきた。でも、彼はその空白の時間の中に、新しい意味を見出そうとしてくれてた。
「だから……もう、自分を責めるのは、やめてくれ」
彼はそう言って、私の手を両手でそっと包み込んだ。その手の温かさが、私の凍りついた心を少しずつ溶かしてく。
「過去は、もう変えられない。でも、これから先のことは、俺たちで変えてけるだろ?」
私は、彼の言葉にただコクコク頷くことしかできなかった。涙はまだ止まらなかったけど、それはもう罪悪感からくるものじゃなかった。安堵と、感謝と、そして彼への愛しさがごちゃごちゃになった、温かい涙だった。
私たちは、過去を乗り越えたわけじゃない。きっと、この傷跡はこれからもずっと私たちの心に残り続けるだろう。
でも、二人でなら、その傷を抱えたまま前に進んでける。
初めて、そう思えた。
◇
あの日から、私たちの関係はちょっとだけ形を変えた。
彼は、家庭教師を辞めなかった。そして、私も生徒であり続けた。けれど、私たちの間にあった見えない壁は、もうどこにもなかった。
彼は、時々思い出した過去の話をしてくれた。二人で遊んだ公園のこと、一緒に食べたアイスの味、他愛ない会話。そのたびに、私たちは失われた時間を取り戻すみたいに笑い合った。
そして、私の心から罪悪感っていう重たい鎖が外れた時、不思議なことが起きた。今まで、あれほど分からなかった教科書の内容が、すんなり頭に入ってくるようになったんだ。
やがて、中間テストが返却された。
放課後の教室。私は、答案用紙をぎゅっと握りしめて彼の待ついつものファミレスへ急いだ。
「どうだった?」
席に着くなり、彼は尋ねてきた。私は、黙って数学の答案をテーブルの上に置く。
そこに書かれてたのは、今まで見たこともないような高い点数だった。
「……すごいじゃないか!」
彼は、自分のことみたいに目をキラキラ輝かせて喜んでくれた。
「やったな、ユキ!」
「……うん!」
私も、満面の笑みでコクコク頷く。
「先生のおかげです。本当に、ありがとう」
「違うよ。ユキが、頑張ったからだ」
彼はそう言って、あの日と同じように私の頭を優しく撫でてくれた。
窓の外では、夕日が街をオレンジ色に染めてる。
三年前、私は彼に想いを伝えることができなかった。でも、今はもう言葉にしなくても伝わってるような気がする。
私たちの前には、新しい未来がどこまでも広がってた。