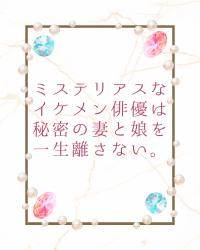【1話だけ】この恋を運命にするために。
この恋を運命にするために。
私は自分の直感というものを大切にしている。
根拠はなくてもビビッときたなら、その第六感を信じて進む。
それは、恋愛もだ。
「私と結婚してください」
たとえ今日会ったばかりの人だとしても、私の直感が告げているのだ。
運命の人はこの人なのだ、と。
「結婚って、今日会ったばかりなのに?」
「はい。会ったばかりでも、です」
「んー。私があなたを助けたのは刑事として当然のことですよ?」
「そういうことじゃないです! あなたがいいって思ったんです!」
私は過去の恋愛も一目惚れというか、直感惚れが多い。
そして好きだ! と思ったらいてもたってもいられなくなってしまう。
恋の駆け引きなんてできなくて、いつでも直球勝負。
「あなたが好きです」
彼の目を真っ直ぐに見ていった。
大抵の人の反応は訝しげな視線を返されるか、かなり戸惑ったように苦笑いされるか、唐突すぎて引かれるか。
だけどこの人は、私から視線を逸らさずに柔らかく微笑む。
「はは、光栄だなぁ」
「! じゃあ!」
「でも、ごめんなさい。私があなたのことを好きになることはないと思います」
にこやかな笑顔に似つかわしくない辛辣な言葉をかけられているのに、私の心は震えていた。
むしろ絶対にこの人だ、この人が私の運命の人なのだと確信していた。
* * *
私の名前は千寿蘭、二十四歳。
華道の名門、千寿華道流家元の娘で私も華道家の端くれとして活動させてもらっている。
次期家元は早々に兄と決まっていたため、私は気楽に楽しくのびのびと花を生ける日々を送っている。
元々家元には興味がなく、私は私の思うがままに花を生けたい。
伝統ばかりにとらわれず、どんどん新しいことに挑戦していきたい。
父は兄には厳しかったが、私に対してうるさく言うことはなかったので有難く好き勝手させてもらっていた。
ある日、次の展覧会でメインとなる花を任せてもらえることになる。
一番大きくて広い場所に飾ってもらえるのは初めてのことだったので、私は人一倍気合いが入っていた。
念入りに花を選び、花瓶にもこだわった。
悩みに悩み抜いたが、自分の名前でもあるランの花を中心とした作品にすることに決めた。
だけど展覧会の一週間前、ある事件が起こる。
展覧会で使用する花瓶の一つが紛失してしまったのだ。
その花瓶は億はくだらない一級品の花瓶であったため、警察に届出をした。
警察が捜査にあたり、なんと私が使用している控室のロッカーから花瓶が発見された。
昨日までなかったはずなのに、突然私のロッカーから魔法のように現れたのだ。
「まさか、犯人が蘭さんだったなんて」
その場にいる人物全員が私に疑いの眼を向けた。
「違います! 私じゃない!」
「後は署で話を伺いましょう」
警察官の一人が私の腕を掴む。
「離して! 私じゃありませんっ!」
その日、両親は別の仕事で不在だった。
兄は結婚して今はフランスにいる。
私に味方してくれる者は一人もいなかった。
誰もが私に非難の視線を向けていて、悲しかったし悔しかった。
涙を堪え、唇を噛み締めることしかできない私を救ってくれたのが、あの人だった。
「待ちたまえ。彼女は犯人ではない」
その人は黒いスーツを見にまとった若い刑事だった。
清潔感に溢れた若々しい見た目でありながら、妙な貫禄がある。
「家元のお嬢様、千寿蘭さんでしたね」
「は、はい」
「単刀直入に言いましょう、あなたは嵌められたのです」
私は思わず唾を飲み込み、自信たっぷりな若い刑事を見返す。
「は、はめられた……?」
「ええ。私の推理はこうです――」
淡々と論理的に語られたその推理は、とても明快だった。
理路整然としており無駄がない。素人でもわかりやすく丁寧に、そして鮮やかに謎を解き明かしてしまった。
結論から言って犯人は展覧会に出展する華道家の一人だった。
前々から私に難癖をつけてくることが多く、私がメインの花を生けることが気に入らなかったらしい。
花瓶を盗んだ犯人に仕立て上げ、私を失脚させようとしていたのだ。
「あの、ありがとうございましたっ」
私は刑事さんにお礼を言った。
「いえ、当然のことをしたまでです」
刑事さんはにこやかに微笑む。
その笑顔に思わずドキッとしてしまった。
この刑事さん、よく見るとものすごくイケメンだわ……。
「あの、お名前を伺ってもよろしいですか?」
「私の? 名乗る程の者ではありませんが、こういう者です」
刑事さんは名刺を渡してくれた。
その名刺を見て驚く。
「警部さん!? お若いのに警部さんなんですか?」
「ええ、まあ。生意気にも警部をやらせていただいてます」
おどけた口調に何故かときめいてしまう。
「まんざきさん……?」
「みつさき、と読みます。満咲信士です」
その名前を聞いた時、私の全身を駆け巡る何かを感じた。
私の第六感がこの人だと告げている。
彼こそが、私の運命の人なのだと。
根拠もなければ今日初めて会った相手だ。
それでも私は勢いでプロポーズし、あっさりと撃沈するのだった――。
* * *
「私、結婚したい人ができたの」
その日の夕食を囲む時、私は両親にそういった。
父は驚いて目を丸くし、母は少し嬉しそうに頬を染めた。
「結婚だと?」
「まあ、蘭ちゃんにもそんな人が!」
「誰なんだ?」
父はじろりと査定する視線を送る。
兄の結婚相手を決めたのも父だ、千寿に相応しい男なのかと言いたいのだろう。
「花瓶の盗難騒動で私を助けてくれた刑事さんよ」
「なに、刑事だとっ」
気に入らなかったのか、父の目が三角になる。
「警察官なんてダメだ」
「どうして? 立派な方よ。誰も私を信じてくれない中、私の無実を証明してくれた優秀な刑事さんなんだから」
「刑事の妻なんてお前が苦労するだけだ」
ふんっと鼻息を荒くする父とは対象的に母は遠慮がちに訊ねる。
「蘭ちゃん、その刑事さんって今日初めてお会いした方じゃないの?」
「そうよ」
「初対面の方といきなり結婚はどうなのかしら?」
母は職業よりも初対面というのが気がかりらしい。
「大丈夫、これから彼のことをもっと知っていくつもりだから。でも私の直感は本物よ」
「そうかしらねぇ……」
「全く、お前のいつも後先考えずに突っ走るのは悪い癖だぞ。とにかく、結婚なんてダメだ」
「お父さんが決めることじゃないでしょ! 私はあの人が――満咲信士さんがいいの!」
それを聞くと、父は訝しげに聞き返す。
「満咲……だと?」
「ええ、お名刺をいただいたの。お若いのにもう警部なのよ」
私は信士さんの名刺を差し出す。
それを見た父の表情がみるみるうちに変わっていった。
「おま……っ、あの満咲家のご子息じゃないか!」
父にしては珍しく大声だった。
想定外の父の反応に思わず何度も瞬きしてしまう。
「知ってるの?」
「知ってるも何も! 警察界隈で絶大な権力を持つ一族だぞ。警察庁の満咲刑事局長の息子さんだ」
「えっ」
既に警部なんて相当優秀な方だと思ったけど、刑事局長の息子さんだったなんて。
「まさかあの満咲なんて……お前は何を考えているんだ」
「なんで? 何が問題なの?」
「問題しかない! うちとは比べ物にならないくらいの家系だぞ」
「蘭ちゃん、私から説明するわね」
母曰く、満咲家は旧華族の末裔であり一言で言ってしまえばやんごとない家柄なのだそうだ。
代々警察官の一族だが政界にも顔が利き、噂では国内の裏組織にも精通しているらしい。
家柄も良ければ権力も絶大。簡単に言うと、絶対に敵に回してはいけない一族なのだという。
「悪いことは言わん、諦めろ」
父はきっぱりといった。
「お前では無理な相手だ」
「なんで無理なのよ!」
「とにかくその男には二度と近づくな!」
「なんでお父さんがそんなこと決めるの!」
久々に父と大喧嘩してしまった。
華道家としては尊敬している父だけど、いつも体裁を気にするし千寿流にとって利益があるかどうかが最優先事項だ。
界隈で大きな権力を持つ満咲に関わり、面倒ごとに巻き込まれるのが嫌なのだろう。
とにかく父さんに何と言われようが、私は信士さんのことを諦めるつもりはない。
「まずは展覧会の成功ね! 信士さん、来てくれるかなぁ」
私は展覧会の招待チケットを信士さんに渡していた。
きっと仕事が忙しいだろうし、来てくれない可能性が高いと思うけど――でももし来てくれたら、とびきりの花を楽しんでいってもらいたい。
私は更に気合いを入れ、最終調整に取り組んだ。
例の華道家は破門になったため、一人分の作品が足らなくなってしまったので急遽もう一作品生けることになった。
調整に調整を重ね、ギリギリまでレイアウトにこだわり、ようやく完成した。
無事に展覧会を迎えられた時は、ほっと安堵していた。
「こんにちは」
正直前日までバタバタしていて招待状のことをすっかり忘れていたので、信士さんが現れた時はとても驚いた。
「信士さん! 来てくださったのですね」
信士さんは今日もスーツを上品に着こなしていた。
ハイブランドのスーツも腕時計も信士さんのために作られたと言っても過言ではない程よく似合っている。
「仕事で近くに寄ったので。千寿流の生け花にも興味ありましたしね」
「どうぞゆっくりご覧になってください!」
本当に来てくださるとは思っていなかった。
すごく嬉しくてそれだけで好きになってしまう。
信士さんは一人で来られたようで、ゆっくりじっくりと一つ一つの作品を眺めていた。
私はこの後の来賓者をもてなさないといけないため、信士さんとは入口で挨拶したきりだった。
信士さん、私の作品見てくれたかしら?
つい信士さんのことを視線で探してしまう。
「らーんちゃん」
チャラそうな声が聞こえた時、思わず顔が引き攣りそうになったが何とか笑顔を作った。
「こんにちは、八代さん。来てくださってありがとうございます」
「蘭ちゃんのためなら絶対行くよー」
彼の名前は八代蔦彦。
ヤシロ百貨店の御曹司でうちのお得意様だ。
「蘭ちゃん、この後の予定は? ディナーでもどう?」
「あーー……今日は一日忙しいんですよねぇ」
「えー? 家元の娘なんだし誰かに任せちゃえばいいじゃん」
「そういうわけにもいかないんです」
はっきり言ってこの人のことは苦手だ。
軽いしチャラいし、こうして言い寄ってこられるのも迷惑でしかない。
だけどお得意様の息子さんだから邪険にするわけにもいかず、なあなあに濁してかわすのが精一杯だ。
「いつなら空いてるの?」
「えっと、しばらく立て込んでるんですよね〜」
本当はあなたに割く時間は一秒たりともありません、と言いたいところだけど流石に我慢。
生け花に興味なんかないくせに、早く帰ってくれないかしら。
「蘭さん、少しよろしいですか」
そこへ話しかけてきたのは、なんと信士さんだった。
「すこしお聞きしたいことがあるのですが……」
「はい! 大丈夫です!」
信士さんから話しかけてくれるなんて……!
「すみません、八代さん。これで失礼します。是非楽しんでいってくださいね」
「あっ、蘭ちゃん!」
信士さんに話しかけられただけで頭の中がお花畑になってしまう。
しかも生け花に興味を持ってくださったみたいですごく嬉しい。
「どんな質問ですか? なんでもお答えします!」
「いえ、君が困っているように見えたから」
「え?」
「早く帰って欲しいって顔してた。違いますか?」
「あ……」
信士さん、助けてくれたのね――。
「ありがとうございます」
簡単にときめいてしまう私は、今のだけで更に好きになる。
友達に言われたことがあるが、私は恋をすると盲目的になりやすい。
好きな人のすべてがよく見えてしまうし、些細なことにすぐキュンとしてしまう。
我ながらチョロいと思うけど、会って二度目にして信士さんのさりげない優しさに完全に落ちていた。
「せっかくなので、本当に質問してもいいですか?」
信士さんにうっとりと見惚れていたが、ハッと我に返る。
「はいっ! なんでしょう?」
「こちらの花はなんというのですか?」
「オンシジュームです」
「これがオンシジュームですか」
「こちらはすべてラン科の花で統一されてるんですよ」
「ああ、“蘭”だから」
不意に呼び捨てされたみたいでドキッとした。
「素敵ですね。私も好きですよ、ランの花」
「……!」
自分のことではなく、花が好きだと言っていることはわかっている。
それでもきゅうっと胸が締め付けられてしまう。
「好きです」
そして口から無意識に漏れ出ていた。
「やっぱり信士さんのことが好きです。私じゃダメですか?」
「――、ダメと判断できるほど君のことを知りません」
「じゃあ知ってください。私ももっと信士さんのこと知りたいです」
熱のこもった視線で信士さんのことを見つめる。
信士さんは少し考える仕草をしたのち、私に向かって向き直る。
「正直に言いますが、君がどうということではなく今は誰とも恋愛する気はないんですよ。仕事に集中したくてね」
「お仕事、ですか」
「刑事というのは常に危険が伴う仕事です」
「それは存じています」
「恨みも買いやすい職業です。こんなことを言っては難ですが、刑事の妻なんて君には相応しくない」
その言葉には少しムッとした。
「私では刑事の妻は務まらないと言いたいのですか」
「そうじゃない、美しい花を生ける君にこそ相応しい相手は他にもいると言いたいんです」
「私の花、美しいと思ってくださったんですか?」
「当然でしょう」
信士さんは真顔で答える。
「華道に関してはズブの素人ですが、独創的で美しいと思いました」
「ほ、本当ですか」
「ラン科の花だけで生けているというのも大胆で面白い。蘭さんらしいと思いました」
信士さんは真犯人を指名した時と同じように淡々と語った。
一見冷たく感じるが、私にはとても誠実な人に映っていた。
私らしいと言ってくれたことが何より嬉しい。
ランの花こそ一番のこだわりだったから。
自分自身をそのまま映した作品を褒められ、私自身のことを認めてくれたように感じる。
淡々としているからこそ、この人は思ったことをそのまま述べているのだとわかった。
「やっぱり、信士さんの妻になりたいです」
「いや……話聞いてました?」
流石の信士さんも呆れた口調になる。
「君のためを思って言ってるのに……」
「私のためと言ってくださるなら、一度デートしてください」
「え?」
私は真剣な表情で信士さんの目を見ていう。
「お仕事が理由ではなく、私自身を見て判断して欲しいんです。デートしてみてそれでもダメだと思ったら、潔くフってください」
「……面白いですね」
信士さんはふっ、と笑みをこぼす。
「わかりました」
「本当ですか!?」
「但し、仕事柄急に呼び出されることが多々あります。その場合迷わずデートをすっぽかしますが、それでもいいですか?」
「もちろんです!」
信士さんとデートできる。それだけで充分だ。
「このデートで絶対好きにさせてみせます」
「ははっ、楽しみだね」
信士さんは穏やかに笑っていた。
きっと内心では好きになるはずがない、と思っているのだろう。
もしダメだと思ったら潔くフって欲しいと言ったが、私が諦めるかどうかはまた別の話だ。
* * *
今日は信士さんとのデートの日。
私が計画したのは横浜デートだ。
みなとみらいを散歩するだけでも楽しいし、美味しいレストランもたくさんある。中華街で食べ歩きも楽しいだろう。
今日はとにかくたくさん会話をして私のことを少しでも知ってもらいたいし、信士さんのことも知りたい。
今日のデートは絶対成功させるんだ……!
「――あれっ」
待ち合わせ場所には十分程早く着いたのに、既に信士さんが待っていた。
「信士さん!? 早いですね!」
慌てて駆け寄ると、信士さんは穏やかに微笑む。
「こんにちは。今着いたところですよ」
「そうなんですか?」
「ええ。さあ、行きましょうか」
「は、はいっ」
スーツ姿しか見たことがなかったので、ラフな私服姿の信士さんが新鮮でドキドキしてしまう。
「その花柄のワンピース、よくお似合いですね」
「本当ですか」
「ええ、素敵です」
私は今日、ネイビーに白いカラーの花柄ワンピースを着ていた。やっぱり花柄が自分らしいかなと思ったし、褒めてもらえて嬉しい。
「信士さんのシャツも素敵ですね」
「そうですか?」
着ている服もさりげない小物も上品でセンスが良い。
「まずはランチですよね。何を食べますか?」
「行きつけの中華料理屋がありますが」
「信士さんのおすすめですか! 行ってみたいです!」
「わかりました」
そうして中華街の方に向かってたどり着いたお店は、見たことのある高級中華料理店だった。
「あれ、ここTVで見ました……」
確かミシュランで一つ星を獲得したという中華料理屋じゃなかったっけ?
そんなところが行きつけなの!?
「おお、信士くん! 久しぶりだねぇ!」
「ご無沙汰しています」
お店から出てきたのはTVに出演していたシェフだ。
「なんだ、デートかい? 個室を用意しようか」
「いえ、予約もなく急に押しかけたのに申し訳ないです」
「いやいや、うちのお得意様なんだから遠慮しないでくれ」
そうして案内されたのは明らかなVIPルームだった。
驚きの連続でまともに挨拶した記憶がないまま、気づいたら豪奢な椅子に座っていた。
「ランチコースでいいですか? 蘭さん」
「は、はい……」
「ではいつもので」
運ばれてきた料理はどれもランチとは思えない、贅沢な品ばかり。あまりの美味しさに声も出せずにいると、信士さんが訊ねる。
「お口に合いませんか?」
「いえ! あまりの美味しさにびっくりしてしまって。こんなにすごいお店が行きつけなんですね」
「シェフと父は昔ながらの仲でね。家族でお世話になっているんですよ」
「そうなのですか」
やっぱり信士さんのご実家ってすごいんだなぁ。
ミシュラン一つ星が行きつけなんて、相当のセレブよね。
「信士くんが子どもの頃から知ってるけど、まさか恋人を連れて来てくれるようになるなんてなぁ」
シェフは私の方を見てニヤニヤしている。
「いえ、まだ恋人じゃないです」
「そうなのかい? でもまだってことは?」
「恋人志望です」
「そうなのか! 信士くんもスミに置けないなぁ!」
シェフは豪快に笑った後、「ごゆっくり」なんて言って出て行ってしまった。
信士さんは明らかにげんなりした表情をしていた。
「……なんであんなこと言うんですか」
「本当のことです」
「この際だから聞きますけど、君は私の家のことはご存知ですか?」
「はい、父に少し聞いた程度ですけど、お父様は警察庁の刑事局長さんだとか」
「ええ、祖父は警察庁長官で親族含め皆警察関係者です。満咲の名を聞けば、恐れて関わりたくないと思う者がほとんどなんです」
信士さんの言いたいことがわからず、黙って水餃子を食べて聞いていた。
「単刀直入に聞きますが、君の目的はなんですか?」
「目的?」
「満咲というパイプが欲しいのですか? 千寿流が財産目当てとは考えにくいのですが」
「ちょっと待ってください! 目的なんてありません」
思わず口に入れた水餃子を吐き出しそうになったが、全部飲み込んだ。
「私は信士さんが好きなんです。それだけです」
「初対面の人間を好きになれるものですか?」
「いけませんか」
「いえ、理解に苦しむだけです」
信士さんは飲茶を一口飲んでから、淡々と語り始めた。
「前にも話しましたが、警察官というのは時に恨みを買うこともあります。ですが満咲は買いやすい、なんてものじゃない。代々国内警察の中枢を担ってきた一族です。命を狙われるなんてこともザラにある」
そういった信士さんの瞳はとても冷たい瞳をしていた。
「満咲に生まれたら宿命のように警察官になる、それは自分自身を守るためでもあります。しかも私は本家の長男、人付き合いにはどうしても慎重になるんですよ」
信士さんは出会った時から穏やかで柔和な人だと思っていたけれど、その優しげな笑顔にどこか踏み込ませまいとする壁を感じていた。
それは誰のことも信用できないからなのかもしれない。
「人は見かけで判断できませんからね。いい人のように思えても腹の内では何を考えているかわからない。君の目的をずうっと考えているのですが、よくわからなくて」
「っ、信士さんは一目惚れしたことないんですか?」
「ないですね」
「この人が運命の人だ! ってビビッときたことはないんですか?」
「ないですね」
「えーっ、私は何度もあるのに」
初めてビビッときたのは幼稚園の頃だった。
私の恋はいつも一目惚れから始まる。
「私は華道も恋愛も直感を大事にしてるんです」
「直感、ねぇ。でも今までビビッときた人たちは、結局運命の人じゃなかったんだよね」
「違いました。でもそれは、信士さんが運命の人だからだと思うんです」
「どうしてそう思うの?」
「上手く言えないんですけど……」
一目惚れして告白することは学生時代から何度もあったけど、プロポーズしたのは信士さんが初めてだ。
「すっごく感覚的なんですけど、赤い糸で結ばれた先を見つけたというか、この人だ! って思ったんです」
我ながら恥ずかしいことを言っている自覚はあった。
何言ってんだって思われているかもしれない。
それでも、この想いに確信を持っている。
「信士さんが運命の人だったらいいなって、本気で思ってるんです」
「フフッ」
真剣に熱弁する私に対し、信士さんはおかしそうに笑う。
「やっぱり俺と君とじゃ合わないと思うけどなぁ」
――あれ? 何となく信士さんの雰囲気が変わった?
しかも“俺”って言ったよね?
「君の一直線なところは好ましいとは思うけど、俺は君のいう運命ってやつが信じられないから」
「……」
「そもそも他人のことを信用できない俺には一生理解できない話だと思うよ」
「…………しい」
「え?」
「嬉しい!」
流石に信士さんも呆気に取られたように私を見ていた。
「嬉しいって、何が?」
「だって信士さん、今“素”で話してくれてるでしょう?」
はっきりと私のことは好きになれないと言われているようなものなのに、思わず顔がにやけてしまう。
職業や家庭のことを理由にするのではなく、初めて信士さん自身の本音を聞けたから。
「実は毒舌なのも素敵だわ」
「……君、相当変わってるって言われない?」
「あ、それは褒め言葉ですね」
昔から変わってると言われることは嬉しかった。
いつも普通じゃないことがしたいと思っているし、型にハマらない花を生けたいと思っているから。
「今日は信士さんをたくさん知るためのデートなんですよ? 他人が信じられない、運命がわからないってことが知られて嬉しいじゃないですか」
私は本気で信士さんのことが知られることが嬉しかったけれど、信士さんは困ったように頭を掻いていた。
「参ったな……今まで出会ってこなかったタイプだ」
「え、私が初めてってこと?」
「そんな露骨に嬉しそうにされても困るんだけど。別に褒めてないしね」
「やっぱり毒舌なところも好き」
「…………」
やっぱりデートに誘ったのは正解だった。
だって信士さんの新しい一面がたくさん知られるんだもの。
「……調子が狂うな」