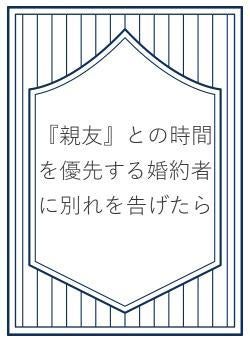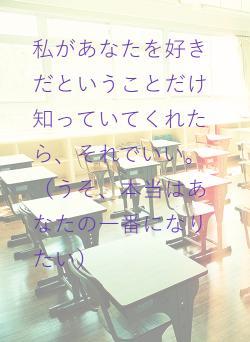会えば喧嘩ばかりの婚約者と腹黒王子の中身が入れ替わったら、なぜか二人からアプローチされるようになりました
エピローグ
ペンネッタ伯爵家の長女ソフィアは、王城内の庭園にあるガゼボにいた。この場を用意したのは、立太子間近の第一王子クリスティアーノだ。彼女が城を出る前にと、わざわざ彼の母親である王妃に許可を取ってくれたらしい。なお、王妃はこのガゼボから見える庭園風景をいたく気に入っており、一息つきたい時によく利用しているのだとか。
ソフィアは貴重な体験に感謝をしながら庭園を眺め、ほうっと息を漏らした。
(目に優しい色合いの花々と、時折鼻腔をくすぐる上品な薫り。王妃様がお気に召すのもわかるわ……。まるで別世界。ここだけ天国のよう)
もしかしたら、日頃心休まることのない王妃やクリスティアーノにとって、この場所は数少ない憩いの場なのかもしれない。
そんなことを考えながら、ソフィアは視線を彼らへと向けた。
左斜め前にはレオンが、右斜め前にはクリスティアーノが座っている。――どちらも本来の姿で。
クリスティアーノの予想通り、朝目覚めた時には入れ替わりの効果は消え、元に戻っていたらしい。
「よかったよ。間に合って」
とクリスティアーノがほほえむ。彼が言う「間に合って」とは「ソフィアの退城」を指している。
そう、今日ソフィアは城を出て自領へと戻る。もともと、ソフィアの滞在が許されていたのは、二人の入れ替わりが解消される……と推定された八日間だけ。たとえその期間を過ぎても、彼らが元に戻らなかったとしても、ソフィアは城を去る予定だった。
ソフィアも次期当主としてやるべきことは多い。いくらクリスティアーノからの要請だとはいえ、これ以上長く留まることはできなかったのだ。
しかし、彼らはこうして無事元に戻った。フォロー役を任されていたソフィアとしても、これで心残りなく去ることができる。
ソフィアは安堵の思いを込めて、「本当にね」とうなずいた。
わかっているのかいないのか、レオンが「うんうん」と深くうなずく。
「やっぱ、自分の体が一番だよな~」
呆れたような視線を向けるのはクリスティアーノ。
「レオン。嬉しいのはわかるけど、アレはやりすぎだと思うよ?」
ソフィアは「アレ?」と首を傾げた。
答えてくれたのはクリスティアーノだった。当のレオンは、気まずげに視線をそらしている。
「レオンってば、早朝から部下を叩き起こしてね。護衛任務が始まるまでの間、ずっと指導だなんだって言って模擬戦闘訓練付き合わせていたんだよ」
「ええ?! ちょっと、なにしてるのよ」
「べ、別にいいだろ。あいつら、俺が休暇中なまっちょろい訓練しかしてなかったみたいだし」
その言葉に、クリスティアーノの眉がピクリと動く。ソフィアはぎょっとした。今の言い方では、まるで入れ替わっていたクリスティアーノのせいで騎士たちに怠け癖がついたと言っているようにも聞こえる。慌ててフォローに入るソフィア。
「あのね、そういうのを『パワハラ』っていうのよ」
「ぱわはら? なんだよそれ」
「他国で流行っている言葉で、上司が部下に仕事の範囲外で精神的・身体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させる行為のことらしいわよ」
「はあ? 騎士なら精神的・肉体的苦痛なんて当たり前だろ。その苦痛を耐えて己を磨き上げるのが騎士なんだから。それに、あいつらも喜んでいたし」
「ええ? ……ああ、そう」
そんな馬鹿なと思ったが、よくよく考えてみたらフィンを筆頭としたあの部下たちなら、確かに喜びそうだという結論に至ってしまった。
しかし、思案に耽るタイミングが悪かった。その数秒の隙を突くかのように、レオンが最悪の言葉を放ったのだ。
「ってかさー、その『ぱわはら』って言葉が似合うのは、俺よりもクリスじゃね?」
そう言って丁寧にクリスティアーノを指し示す。ソフィアは固まった。レオンは止まらない。
「まさに今回の件だってそうじゃん!」
「レ、レオン……」
「なんだよソフィー……」
首を傾げるレオンの隣から、普段よりも一段低い声色が響いた。
「へえ……レオンは、私の対応に不満を持ってたんだ?」
「そりゃあ不満の一つや二つ……」
「レオン!」
止めようとしたが、間に合わなかった。
「ふーん。心外だなあ……これでも随分と抑えていたつもりなんだけど……」
「え?」
「じゃあ、今後は遠慮なくいかせてもらうね。レオンのパワハラ基準を正すためにも」
にっこり微笑んだクリスティアーノの圧に、今さら気づいたらしいレオン。顔面を蒼白にし、言葉を失ったまま頬を引きつらせる。なんとかこの窮地を打開しようと、彼は必死に口を開いた。
「で、でもよ……感謝もしてるんだぜ!」
「へえ?」
「クリスのおかげで、俺らの仲は改善されたんだから。なあ、ソフィー?」
話を振られたソフィアは、反射的に「え、ええ」と返した。
クリスティアーノがすっと目を細め、ソフィアとレオンを交互に見やる。
「改善ねえ……むしろ、ここからがスタートだと僕は思うんだけど……」
「なんだ? 聞こえなかった。もう一回言ってくれ」
「いや。今のはただの独り言だから気にしないで。それよりもソフィー」
「な、なに?」
声色が元に戻ったことにホッとしながら、ソフィアは問い返す。
「本当に、今日帰っちゃうの?」
「ええ。私もたまっている仕事を片付けないといけないから……」
「だよね。わかっているけど……ソフィーがいないと、やっぱり困る……というか、寂しいなあ……」
感傷的になっている様子のクリスティアーノを見て、ソフィアは申し訳なさそうに眉尻を下げる。
「まあ俺は、ソフィーの婚約者だからいつでも会えるけどな!」
と、ここで空気を読まずに口を挟んだレオン。それどころか、なぜか得意げな顔までしている。
しかし、クリスティアーノがにっこり微笑んだ。その、底の見えない笑顔を見て、レオンも――ついでにソフィアもぎょっとする。
「レオン、そんな暇があるといいねえ」
「んなっ!」
「王弟派もいなくなって、本格的に立太子の準備に取り掛からなきゃいけない。となると、私は今まで以上に多忙を極めるだろう。……当然、私の護衛隊長である君も道連れになる。と思うんだけど、違う?」
「そ、それは……」
「というか、私はパワハラ上司なんだろう? なら、そんな私が君に休みを与えるなんて、どうして思えたのかな?」
呆れたように追い詰められ、レオンは青ざめる。
たまらずソフィアが横やりを入れた。
「クリス。それ以上いじめないでやってちょうだい」
「えー」
「これ以上意地悪するなら、結婚式に呼ばないわよ」
「それは嫌だ」
即答だった。
「親友とソフィーの結婚式に、僕が出ないなんてありえないからね」
「し、しんゆう……」
さっきまで青ざめていたくせに、今度は嬉しそうに顔を赤らめるレオン。そういえば、レオンはよくクリスティアーノのことを『親友』だと呼んでいたが、その逆はあまりなかったように思う。クリスティアーノも、公言できるほどにレオンを、レオンとの絆を信じられるようになったということだろう。
まあ、だからといってレオンのこの反応はあまりにも素直すぎるが。でも、そういう表裏のなさをソフィアは気に入っているのだ。そしておそらく、同じようにレオンを見ているクリスティアーノも。
ソフィアとクリスティアーノは顔を見合わせ、楽しげに肩をすくめ合った。そんな二人を見たレオンはうなり声を上げる。その言動が、さらに二人の笑いを誘うとも知らずに。
「ああ、もうそろそろ時間みたいだ」
不意に、クリスティアーノがそう告げた。彼の視線を追えば、見覚えのある文官にたどり着く。どうやら迎えのようだ。彼は次いで、ソフィアをまっすぐに見つめた。
「ソフィー。改めて……ありがとうね。いろいろ」
「……別に、私は大したことはしていないわ」
「そんなことないよ。ソフィーのおかげで助かったことは、数えきれないくらいにあるから」
「そう。……それなら、よかった」
「うん。あ、そうだ。『約束』は忘れないでね。絶対に」
その『約束』という響きにレオンがピクリと反応したが、口は挟んでこない。ソフィアはすぐに栞のことだと理解してうなずき返した。
「わかった。帰ったら忘れずに頼まれていた物を送るから」
「うん、よろしくね」
「ああ。なんだそういう……」と納得しかけたレオンだが、憮然とした表情でクリスティアーノを睨んだ。
「一応念を押しておくが、ソフィーは俺の婚約者だからな」
「わかっているよ」と笑うクリスティアーノ。
「おまえはさっさと新しい婚約者でも見つけろ」
「はいはい。まあでも……私が自分で探さなくても、そのうち父上がふさわしい相手を見繕ってくれるさ。……今度こそ、ね」
皮肉たっぷりの言葉に、レオンもソフィアも言葉を失った。さすがに笑えない。
レオンは気まずげに視線を泳がせ、ごまかすように紅茶に口をつけた。
その反応をじっと見ながら、クリスティアーノは「ああそうだ……」と続ける。
「まだ試していない魔女の秘薬がいくつかあるんだけど……」
彼の視線が捉えているのは、レオンが今まさに口にしたカップだ。それに気づいたレオンは、瞬時に顔色を変えた。
「お、おまえまさかっ。こ、これに入れてないだろうな?!」
その質問に対して、クリスティアーノは「ふふ」と意味深に笑うだけ。
ソフィアはその返しでからかっているだけだと即座に理解したが、レオンはそうはいかなかったらしい。まあ、一度魔女の秘薬の餌食になっている彼にしてみれば、仕方ないことなのかもしれない。
指を口内に突っ込み、なんとか吐こうとするレオンに、ソフィアは待ったをかけた。
「大丈夫よ、レオン。クリスはただ、からかっているだけだから」
「本当か?」という疑いの視線を向けるレオンに、ソフィアは大きく頷いてみせる。
「魔女の秘薬は今回の件を受けて、保管体制を厳重に見直すことが決まったそうよ。だから、いくらクリスでもそう簡単には持ち出せないはずだわ」
その言葉に、レオンは安堵の息を漏らした。
一方でクリスティアーノは、「ソフィーは本当に、僕のことをよくわかってくれているなあ」と、どこまで本気か読めない笑顔で笑っていたのだった。
ひとしきりレオンをからかって満足したのか、クリスティアーノは徐に立ち上がった。
城内に戻る前に、ソフィアには「気をつけて帰ってね」と優しく一言告げ、レオンには「きちんと見送るように」と厳命する。
それに対し、レオンは「言われなくても! それよりおまえこそ、さっさと溜まった仕事片付けに行けよ。サボんなよ!」と威勢よく返した。その相変わらずの言葉遣いにハラハラしているソフィア。
だが、やはり一枚上手なのはクリスティアーノだった。
「はいはい。きちんとやりますよ~。……ただ、また限界が来たときはよろしくね」
そう言って懐をポンポンと叩く仕草をしてみせると、悪戯っぽくウインクをして、ひらひらと手を振りながら背を向け去っていったのだ。
その背中に向かって、レオンは「二度とごめんだ!」と全力で叫び返したのだった。
クリスティアーノが手配してくれたペンネッタ伯爵領行きの馬車。その前で、ソフィアとレオンは向き合って立っていた。先ほどまで三人で騒いでいたのが嘘のように、二人きりになると気恥ずかしいような、なんとも言えない空気が流れる。けれど、それは決して嫌なものではなかった。
「ソ、ソフィー」
「な、なに?」
「あー……その、き、気をつけて帰れよ」
「ええ。レオンも……お仕事、頑張ってね」
「ああ。……その、手紙を書くから」
「え?」
「会えない間は手紙を書く。……その代わり、字が汚くても許せよな」
顔を真っ赤にして早口で告げるレオン。そんな彼を見て、ソフィアは自然と目元を和らげた。
「わかったわ。楽しみに待っているから」
「お、おう! それと……これからは婚約者としてのマナーもきちんとする。そんで、『デート』にも行こう」
「ええ。そうして頂戴。私も楽しみにしてる。ただ……しばらくは相当忙しくなるでしょうから、無茶はしないでね? 連絡さえきちんとくれれば、私は……」
「……いや」
遮るように、レオンが首を横に振った。
「無茶をしてでも会いに行く。馬を飛ばせば日帰りできる距離だしな」
「そこまでする必要は……」
「俺がしたいんだ」
「え……」
「婚約者のマナーとか、そんなの関係なくて。俺が、俺自身がソフィーに会いたいから、多少の無茶はさせてくれ」
驚いて目を丸くするソフィアの手を、無骨なレオンの手がそっと優しく取った。
「自覚する前は、こんなこと思いもしなかったんだけどな……」
そう言ってソフィアの手をじっと見つめながら、親指で手の甲を軽くさする。ソフィアの体がピクッと反応したが、手は離れなかった。
「……本当は、このまま行かせたくねえ。できることなら、ずっと俺の目の届く範囲にいてほしい」
「っ、そんなのできるわけ……」
「ああ、無理だってわかってるよ。それに城にはクリスもいるしな……。あいつの近くには寄らせたくねえから、帰るのを止めはしない。けどその代わり、何としてでも時間を作って会いに行くから」
「……ええ。待っているわ」
「ああ」
レオンが顔を上げ、ソフィアに熱い眼差しを向ける。
重なっていた手が離れた瞬間、それを「残念だ」と思っている自分にソフィアは驚いた。恥ずかしさに耐えきれず、彼女はレオンから顔を背けた。
「じゃ、じゃあね」
逃げるように馬車に乗り込もうとした時、後ろからぐいっと腕を引かれ、バランスを崩した。文句を言おうと顔を向けた瞬間、視界が、唇が塞がれる。レオンと、彼の熱い唇で。
「んっ……」
「……また、な」
「う、うん……また」
今度こそ、ソフィアは馬車に乗り込んだ。
ソフィアを乗せた馬車が、ゆっくりと走り出す。レオンは馬車が見えなくなるまで、その場に立ち尽くしていた。そして、その光景を遠くから見送る影がもう一つ。王城のとある窓にあるその影はレオンがその場を動いてからもしばらくの間じっとしていた。
車内のソフィアは唇を指先で押さえ、熱い息を漏らしながら、窓に頭を寄せていた。
(レオン……)
今別れたばかりだというのに。もう会いたい。そんな自分に戸惑いを覚える。
これではまるで恋愛に浮かれた乙女のようだ。恋愛小説好きな友人が知ったら、根掘り葉掘り聞かれそうだと想像し、フッと自嘲気味に笑った。
冷静さを取り戻したからか、ふと座面に違和感を覚えた。
「あら、これは……?」
長距離でも腰を痛めないようにと、クリスティアーノが用意してくれたのであろうクッション。それをどけると、下から一冊の本が現れた。
(クリスが用意してくれたのかしら……)
だが、一目見ただけでソフィアの好みではないとわかった。典型的な恋愛小説のようだ。
(まさか、これで恋愛の勉強でもしろと?)
眉根を寄せながらも、これも暇潰しくらいにはなるだろうと読み進めることにした。
しかし、物語を最後まで読み終えた時、ソフィアの顔は険しいものに変わっていた。
その小説は、以前劇場で観たオペラの原作となった恋愛小説の『続編』だったのだ。
続編の主人公は妹。その内容はあまりに衝撃的で、前巻の印象を根底から覆すものだった。
前巻『悲劇の姫君と真実の愛』は、不遇な扱いを受けてきた第一王女がようやく真実の愛を見つける物語だった。幸せを妬んだ非道な妹によって恋人を奪われ、二人は引き裂かれる。しかし、絶望の中でも愛を貫き、最後には王家の不正を暴いた第一王女が女王として戴冠し、愛する彼と結ばれるハッピーエンド――。
しかし続編『仮面の王女の逆転劇』で明かされた真実は、その『美談』を真っ向から否定していた。 実は前作の出来事はすべて、現女王である姉の筋書きだったのだ。彼女は自身を悲劇のヒロインに仕立て上げるため、妹に悪役を演じるよう強要し、陰で虐げ続けていた。 奴隷同然の扱いに耐えていた妹は、姉のさらなる野望――恋人と共謀して王家の不正を捏造し、国王を追い落として国を乗っ取るという陰謀に巻き込まれ、離宮へと幽閉されてしまう。 すべてを諦めかけていた妹だったが、彼女の真の姿を知る唯一の友人と、その恋人が救いの手を差し伸べる。彼らの必死の説得により、妹は失われた誇りを取り戻すことを決意。離宮を脱走し、命懸けで姉たちの真相を公に暴いていくというストーリー。
「なるほど……」
ソフィアはぽつりと呟いた。 クリスティアーノの意図は明白だった。今後、この続編を王都で流行させる予定なのだろう。そのために、ソフィアにも別ルートからこの本を広めてほしいという協力要請だ。 劇場や出版社、そして筆者。そのどこかに王弟派の息がかかっていることは察していたが、これで確信に変わった。クリスティアーノはそれを逆手にとり、この『続編』で世論を上書きするつもりなのだ。彼らの身勝手な不倫劇を、『美談』にはさせないために。
「これでは浸る余裕もないわね。帰ったらやることがいっぱいだわ」
非日常から日常――仕事ばかりの日々に戻ることを想像してため息を吐く。
だが、以前とは違うこともあるのだと思い直し口角を上げた。
次に会う時、彼はきっと約束通り、汗だくで馬を飛ばして現れるだろう。
少しでも彼が余裕をもって会いに来れるよう。そのためなら、ソフィアもいくらだって手を貸せる。
そもそも、ソフィアにとってクリスティアーノは戦友のようなもの。なにより、次の国王になるのは彼しかいないと思っている。彼の隣で戦うことはできないけれど。別の場所から力を貸すことならできる。
それにこの貸しは回り巡ってレオンとソフィアのためにもなるのだ。
ソフィアはもう一度、指先で唇に触れた。
(まさか、レオン相手にこんな気持ちになる日がくるとはね……)
遠ざかる王都に背を向け、ソフィアは心地よい余韻を胸に、深く座席に身を沈めたのだった。
ソフィアは貴重な体験に感謝をしながら庭園を眺め、ほうっと息を漏らした。
(目に優しい色合いの花々と、時折鼻腔をくすぐる上品な薫り。王妃様がお気に召すのもわかるわ……。まるで別世界。ここだけ天国のよう)
もしかしたら、日頃心休まることのない王妃やクリスティアーノにとって、この場所は数少ない憩いの場なのかもしれない。
そんなことを考えながら、ソフィアは視線を彼らへと向けた。
左斜め前にはレオンが、右斜め前にはクリスティアーノが座っている。――どちらも本来の姿で。
クリスティアーノの予想通り、朝目覚めた時には入れ替わりの効果は消え、元に戻っていたらしい。
「よかったよ。間に合って」
とクリスティアーノがほほえむ。彼が言う「間に合って」とは「ソフィアの退城」を指している。
そう、今日ソフィアは城を出て自領へと戻る。もともと、ソフィアの滞在が許されていたのは、二人の入れ替わりが解消される……と推定された八日間だけ。たとえその期間を過ぎても、彼らが元に戻らなかったとしても、ソフィアは城を去る予定だった。
ソフィアも次期当主としてやるべきことは多い。いくらクリスティアーノからの要請だとはいえ、これ以上長く留まることはできなかったのだ。
しかし、彼らはこうして無事元に戻った。フォロー役を任されていたソフィアとしても、これで心残りなく去ることができる。
ソフィアは安堵の思いを込めて、「本当にね」とうなずいた。
わかっているのかいないのか、レオンが「うんうん」と深くうなずく。
「やっぱ、自分の体が一番だよな~」
呆れたような視線を向けるのはクリスティアーノ。
「レオン。嬉しいのはわかるけど、アレはやりすぎだと思うよ?」
ソフィアは「アレ?」と首を傾げた。
答えてくれたのはクリスティアーノだった。当のレオンは、気まずげに視線をそらしている。
「レオンってば、早朝から部下を叩き起こしてね。護衛任務が始まるまでの間、ずっと指導だなんだって言って模擬戦闘訓練付き合わせていたんだよ」
「ええ?! ちょっと、なにしてるのよ」
「べ、別にいいだろ。あいつら、俺が休暇中なまっちょろい訓練しかしてなかったみたいだし」
その言葉に、クリスティアーノの眉がピクリと動く。ソフィアはぎょっとした。今の言い方では、まるで入れ替わっていたクリスティアーノのせいで騎士たちに怠け癖がついたと言っているようにも聞こえる。慌ててフォローに入るソフィア。
「あのね、そういうのを『パワハラ』っていうのよ」
「ぱわはら? なんだよそれ」
「他国で流行っている言葉で、上司が部下に仕事の範囲外で精神的・身体的苦痛を与えたり職場環境を悪化させる行為のことらしいわよ」
「はあ? 騎士なら精神的・肉体的苦痛なんて当たり前だろ。その苦痛を耐えて己を磨き上げるのが騎士なんだから。それに、あいつらも喜んでいたし」
「ええ? ……ああ、そう」
そんな馬鹿なと思ったが、よくよく考えてみたらフィンを筆頭としたあの部下たちなら、確かに喜びそうだという結論に至ってしまった。
しかし、思案に耽るタイミングが悪かった。その数秒の隙を突くかのように、レオンが最悪の言葉を放ったのだ。
「ってかさー、その『ぱわはら』って言葉が似合うのは、俺よりもクリスじゃね?」
そう言って丁寧にクリスティアーノを指し示す。ソフィアは固まった。レオンは止まらない。
「まさに今回の件だってそうじゃん!」
「レ、レオン……」
「なんだよソフィー……」
首を傾げるレオンの隣から、普段よりも一段低い声色が響いた。
「へえ……レオンは、私の対応に不満を持ってたんだ?」
「そりゃあ不満の一つや二つ……」
「レオン!」
止めようとしたが、間に合わなかった。
「ふーん。心外だなあ……これでも随分と抑えていたつもりなんだけど……」
「え?」
「じゃあ、今後は遠慮なくいかせてもらうね。レオンのパワハラ基準を正すためにも」
にっこり微笑んだクリスティアーノの圧に、今さら気づいたらしいレオン。顔面を蒼白にし、言葉を失ったまま頬を引きつらせる。なんとかこの窮地を打開しようと、彼は必死に口を開いた。
「で、でもよ……感謝もしてるんだぜ!」
「へえ?」
「クリスのおかげで、俺らの仲は改善されたんだから。なあ、ソフィー?」
話を振られたソフィアは、反射的に「え、ええ」と返した。
クリスティアーノがすっと目を細め、ソフィアとレオンを交互に見やる。
「改善ねえ……むしろ、ここからがスタートだと僕は思うんだけど……」
「なんだ? 聞こえなかった。もう一回言ってくれ」
「いや。今のはただの独り言だから気にしないで。それよりもソフィー」
「な、なに?」
声色が元に戻ったことにホッとしながら、ソフィアは問い返す。
「本当に、今日帰っちゃうの?」
「ええ。私もたまっている仕事を片付けないといけないから……」
「だよね。わかっているけど……ソフィーがいないと、やっぱり困る……というか、寂しいなあ……」
感傷的になっている様子のクリスティアーノを見て、ソフィアは申し訳なさそうに眉尻を下げる。
「まあ俺は、ソフィーの婚約者だからいつでも会えるけどな!」
と、ここで空気を読まずに口を挟んだレオン。それどころか、なぜか得意げな顔までしている。
しかし、クリスティアーノがにっこり微笑んだ。その、底の見えない笑顔を見て、レオンも――ついでにソフィアもぎょっとする。
「レオン、そんな暇があるといいねえ」
「んなっ!」
「王弟派もいなくなって、本格的に立太子の準備に取り掛からなきゃいけない。となると、私は今まで以上に多忙を極めるだろう。……当然、私の護衛隊長である君も道連れになる。と思うんだけど、違う?」
「そ、それは……」
「というか、私はパワハラ上司なんだろう? なら、そんな私が君に休みを与えるなんて、どうして思えたのかな?」
呆れたように追い詰められ、レオンは青ざめる。
たまらずソフィアが横やりを入れた。
「クリス。それ以上いじめないでやってちょうだい」
「えー」
「これ以上意地悪するなら、結婚式に呼ばないわよ」
「それは嫌だ」
即答だった。
「親友とソフィーの結婚式に、僕が出ないなんてありえないからね」
「し、しんゆう……」
さっきまで青ざめていたくせに、今度は嬉しそうに顔を赤らめるレオン。そういえば、レオンはよくクリスティアーノのことを『親友』だと呼んでいたが、その逆はあまりなかったように思う。クリスティアーノも、公言できるほどにレオンを、レオンとの絆を信じられるようになったということだろう。
まあ、だからといってレオンのこの反応はあまりにも素直すぎるが。でも、そういう表裏のなさをソフィアは気に入っているのだ。そしておそらく、同じようにレオンを見ているクリスティアーノも。
ソフィアとクリスティアーノは顔を見合わせ、楽しげに肩をすくめ合った。そんな二人を見たレオンはうなり声を上げる。その言動が、さらに二人の笑いを誘うとも知らずに。
「ああ、もうそろそろ時間みたいだ」
不意に、クリスティアーノがそう告げた。彼の視線を追えば、見覚えのある文官にたどり着く。どうやら迎えのようだ。彼は次いで、ソフィアをまっすぐに見つめた。
「ソフィー。改めて……ありがとうね。いろいろ」
「……別に、私は大したことはしていないわ」
「そんなことないよ。ソフィーのおかげで助かったことは、数えきれないくらいにあるから」
「そう。……それなら、よかった」
「うん。あ、そうだ。『約束』は忘れないでね。絶対に」
その『約束』という響きにレオンがピクリと反応したが、口は挟んでこない。ソフィアはすぐに栞のことだと理解してうなずき返した。
「わかった。帰ったら忘れずに頼まれていた物を送るから」
「うん、よろしくね」
「ああ。なんだそういう……」と納得しかけたレオンだが、憮然とした表情でクリスティアーノを睨んだ。
「一応念を押しておくが、ソフィーは俺の婚約者だからな」
「わかっているよ」と笑うクリスティアーノ。
「おまえはさっさと新しい婚約者でも見つけろ」
「はいはい。まあでも……私が自分で探さなくても、そのうち父上がふさわしい相手を見繕ってくれるさ。……今度こそ、ね」
皮肉たっぷりの言葉に、レオンもソフィアも言葉を失った。さすがに笑えない。
レオンは気まずげに視線を泳がせ、ごまかすように紅茶に口をつけた。
その反応をじっと見ながら、クリスティアーノは「ああそうだ……」と続ける。
「まだ試していない魔女の秘薬がいくつかあるんだけど……」
彼の視線が捉えているのは、レオンが今まさに口にしたカップだ。それに気づいたレオンは、瞬時に顔色を変えた。
「お、おまえまさかっ。こ、これに入れてないだろうな?!」
その質問に対して、クリスティアーノは「ふふ」と意味深に笑うだけ。
ソフィアはその返しでからかっているだけだと即座に理解したが、レオンはそうはいかなかったらしい。まあ、一度魔女の秘薬の餌食になっている彼にしてみれば、仕方ないことなのかもしれない。
指を口内に突っ込み、なんとか吐こうとするレオンに、ソフィアは待ったをかけた。
「大丈夫よ、レオン。クリスはただ、からかっているだけだから」
「本当か?」という疑いの視線を向けるレオンに、ソフィアは大きく頷いてみせる。
「魔女の秘薬は今回の件を受けて、保管体制を厳重に見直すことが決まったそうよ。だから、いくらクリスでもそう簡単には持ち出せないはずだわ」
その言葉に、レオンは安堵の息を漏らした。
一方でクリスティアーノは、「ソフィーは本当に、僕のことをよくわかってくれているなあ」と、どこまで本気か読めない笑顔で笑っていたのだった。
ひとしきりレオンをからかって満足したのか、クリスティアーノは徐に立ち上がった。
城内に戻る前に、ソフィアには「気をつけて帰ってね」と優しく一言告げ、レオンには「きちんと見送るように」と厳命する。
それに対し、レオンは「言われなくても! それよりおまえこそ、さっさと溜まった仕事片付けに行けよ。サボんなよ!」と威勢よく返した。その相変わらずの言葉遣いにハラハラしているソフィア。
だが、やはり一枚上手なのはクリスティアーノだった。
「はいはい。きちんとやりますよ~。……ただ、また限界が来たときはよろしくね」
そう言って懐をポンポンと叩く仕草をしてみせると、悪戯っぽくウインクをして、ひらひらと手を振りながら背を向け去っていったのだ。
その背中に向かって、レオンは「二度とごめんだ!」と全力で叫び返したのだった。
クリスティアーノが手配してくれたペンネッタ伯爵領行きの馬車。その前で、ソフィアとレオンは向き合って立っていた。先ほどまで三人で騒いでいたのが嘘のように、二人きりになると気恥ずかしいような、なんとも言えない空気が流れる。けれど、それは決して嫌なものではなかった。
「ソ、ソフィー」
「な、なに?」
「あー……その、き、気をつけて帰れよ」
「ええ。レオンも……お仕事、頑張ってね」
「ああ。……その、手紙を書くから」
「え?」
「会えない間は手紙を書く。……その代わり、字が汚くても許せよな」
顔を真っ赤にして早口で告げるレオン。そんな彼を見て、ソフィアは自然と目元を和らげた。
「わかったわ。楽しみに待っているから」
「お、おう! それと……これからは婚約者としてのマナーもきちんとする。そんで、『デート』にも行こう」
「ええ。そうして頂戴。私も楽しみにしてる。ただ……しばらくは相当忙しくなるでしょうから、無茶はしないでね? 連絡さえきちんとくれれば、私は……」
「……いや」
遮るように、レオンが首を横に振った。
「無茶をしてでも会いに行く。馬を飛ばせば日帰りできる距離だしな」
「そこまでする必要は……」
「俺がしたいんだ」
「え……」
「婚約者のマナーとか、そんなの関係なくて。俺が、俺自身がソフィーに会いたいから、多少の無茶はさせてくれ」
驚いて目を丸くするソフィアの手を、無骨なレオンの手がそっと優しく取った。
「自覚する前は、こんなこと思いもしなかったんだけどな……」
そう言ってソフィアの手をじっと見つめながら、親指で手の甲を軽くさする。ソフィアの体がピクッと反応したが、手は離れなかった。
「……本当は、このまま行かせたくねえ。できることなら、ずっと俺の目の届く範囲にいてほしい」
「っ、そんなのできるわけ……」
「ああ、無理だってわかってるよ。それに城にはクリスもいるしな……。あいつの近くには寄らせたくねえから、帰るのを止めはしない。けどその代わり、何としてでも時間を作って会いに行くから」
「……ええ。待っているわ」
「ああ」
レオンが顔を上げ、ソフィアに熱い眼差しを向ける。
重なっていた手が離れた瞬間、それを「残念だ」と思っている自分にソフィアは驚いた。恥ずかしさに耐えきれず、彼女はレオンから顔を背けた。
「じゃ、じゃあね」
逃げるように馬車に乗り込もうとした時、後ろからぐいっと腕を引かれ、バランスを崩した。文句を言おうと顔を向けた瞬間、視界が、唇が塞がれる。レオンと、彼の熱い唇で。
「んっ……」
「……また、な」
「う、うん……また」
今度こそ、ソフィアは馬車に乗り込んだ。
ソフィアを乗せた馬車が、ゆっくりと走り出す。レオンは馬車が見えなくなるまで、その場に立ち尽くしていた。そして、その光景を遠くから見送る影がもう一つ。王城のとある窓にあるその影はレオンがその場を動いてからもしばらくの間じっとしていた。
車内のソフィアは唇を指先で押さえ、熱い息を漏らしながら、窓に頭を寄せていた。
(レオン……)
今別れたばかりだというのに。もう会いたい。そんな自分に戸惑いを覚える。
これではまるで恋愛に浮かれた乙女のようだ。恋愛小説好きな友人が知ったら、根掘り葉掘り聞かれそうだと想像し、フッと自嘲気味に笑った。
冷静さを取り戻したからか、ふと座面に違和感を覚えた。
「あら、これは……?」
長距離でも腰を痛めないようにと、クリスティアーノが用意してくれたのであろうクッション。それをどけると、下から一冊の本が現れた。
(クリスが用意してくれたのかしら……)
だが、一目見ただけでソフィアの好みではないとわかった。典型的な恋愛小説のようだ。
(まさか、これで恋愛の勉強でもしろと?)
眉根を寄せながらも、これも暇潰しくらいにはなるだろうと読み進めることにした。
しかし、物語を最後まで読み終えた時、ソフィアの顔は険しいものに変わっていた。
その小説は、以前劇場で観たオペラの原作となった恋愛小説の『続編』だったのだ。
続編の主人公は妹。その内容はあまりに衝撃的で、前巻の印象を根底から覆すものだった。
前巻『悲劇の姫君と真実の愛』は、不遇な扱いを受けてきた第一王女がようやく真実の愛を見つける物語だった。幸せを妬んだ非道な妹によって恋人を奪われ、二人は引き裂かれる。しかし、絶望の中でも愛を貫き、最後には王家の不正を暴いた第一王女が女王として戴冠し、愛する彼と結ばれるハッピーエンド――。
しかし続編『仮面の王女の逆転劇』で明かされた真実は、その『美談』を真っ向から否定していた。 実は前作の出来事はすべて、現女王である姉の筋書きだったのだ。彼女は自身を悲劇のヒロインに仕立て上げるため、妹に悪役を演じるよう強要し、陰で虐げ続けていた。 奴隷同然の扱いに耐えていた妹は、姉のさらなる野望――恋人と共謀して王家の不正を捏造し、国王を追い落として国を乗っ取るという陰謀に巻き込まれ、離宮へと幽閉されてしまう。 すべてを諦めかけていた妹だったが、彼女の真の姿を知る唯一の友人と、その恋人が救いの手を差し伸べる。彼らの必死の説得により、妹は失われた誇りを取り戻すことを決意。離宮を脱走し、命懸けで姉たちの真相を公に暴いていくというストーリー。
「なるほど……」
ソフィアはぽつりと呟いた。 クリスティアーノの意図は明白だった。今後、この続編を王都で流行させる予定なのだろう。そのために、ソフィアにも別ルートからこの本を広めてほしいという協力要請だ。 劇場や出版社、そして筆者。そのどこかに王弟派の息がかかっていることは察していたが、これで確信に変わった。クリスティアーノはそれを逆手にとり、この『続編』で世論を上書きするつもりなのだ。彼らの身勝手な不倫劇を、『美談』にはさせないために。
「これでは浸る余裕もないわね。帰ったらやることがいっぱいだわ」
非日常から日常――仕事ばかりの日々に戻ることを想像してため息を吐く。
だが、以前とは違うこともあるのだと思い直し口角を上げた。
次に会う時、彼はきっと約束通り、汗だくで馬を飛ばして現れるだろう。
少しでも彼が余裕をもって会いに来れるよう。そのためなら、ソフィアもいくらだって手を貸せる。
そもそも、ソフィアにとってクリスティアーノは戦友のようなもの。なにより、次の国王になるのは彼しかいないと思っている。彼の隣で戦うことはできないけれど。別の場所から力を貸すことならできる。
それにこの貸しは回り巡ってレオンとソフィアのためにもなるのだ。
ソフィアはもう一度、指先で唇に触れた。
(まさか、レオン相手にこんな気持ちになる日がくるとはね……)
遠ざかる王都に背を向け、ソフィアは心地よい余韻を胸に、深く座席に身を沈めたのだった。