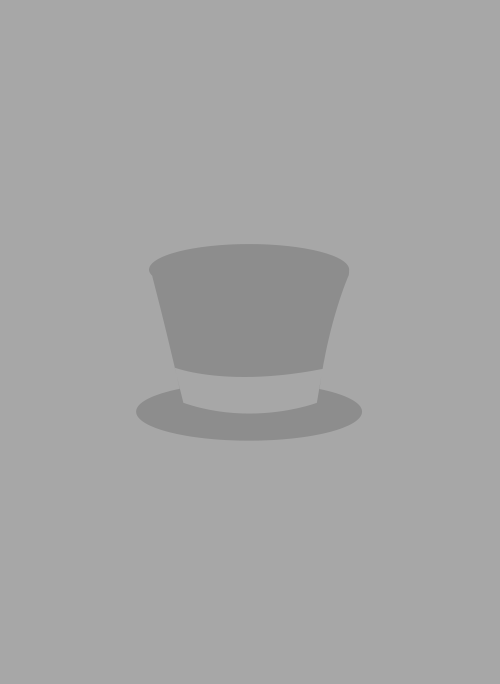東京リッパー
東京リッパー
@shgil55
第1話
1
夜闇の舞い降り始めた、時刻。
国際外語大学、ロック同好会、サークル室。テーブル上にはパソコンがユーチューブ動画を流していた。Whitechapel Hymns in Dissonance.
コアメタルのサウンドが室内に響いている。
「ヘヴィメタルは奇形に進化した」
「情緒的なハードロックから、感情を抑制。ギターの音色をディストーションで潰し、無機的に。更にヴォーカルを故意に潰し、人間の声から離脱。デス声はもうワードを伝えない。唯、溢れんばかりの怒りを表現するのみ」
「もうヘヴィメタルはチャートアクションは期待しない」
「ゴーストの例外はあるとしても」
「あれはアメリカのバンドではない。米国では既にロックは死滅した」
「もうハードロックに回帰は不可能。クラシックロックだけが執拗に未だ存在するが」
「フェアウェルコンサートが盛んだ。軈て全て終焉する。時間の問題だ」
ロック同好会のメンバーは、美青年の青田晃司、その恋人の高村麗子、妹の高村奈津美、島村麻里、塚田僚一の5人だった。
青田と麗子は仲睦まじく、手を握っている。それを奈津美は嫉妬の眼差しで睨めつけていた。
また塚田と麻里は明らかに、接近しかけていた。
「要するに、ブルージーなヴォーカルの時代にはもう決して戻れないということだ。Zepやバッドカンパニーは過去の遺物だから」
塚田はそう話を締めくくると、島村麻里に合図した。塚田と麻里は席を立った。
どうやらトイレらしかったが、どんな目的のトイレかは甚だ怪しいものだった。
塚田と麻里は内緒で、男性トイレに二人で入った。ドアを施錠すると、途端に塚田は麻里を求めてきた。
島村麻里は便座に両手を付いて、立ったまま四つん這いになった。ハーフスリーブニットドッキングワンピースのスカートが、背後からたくし上げられた。塚田はズボンのジッパーを下ろした。
「塚田さん、貴方、高村麗子さんが好きなんでしょう?」
麻里の突然の質問に、塚田は萎えた様子だった。塚田は麻里の尻を叩いて、ズボンのジッパーを上げた。
「煩いな、その気が失せたよ」
「何よ、貴方って」
麻里は泣き崩れそうになりながら、扉を開けて出た。
島村麻里は大学を出ると、夜の渋谷に出た。彼女としては真剣に愛していた、塚田の造反はショックだった。否、そうとも限らない。その不安定さが余計に神経を刺激した。
麻里は渋谷駅を出ると、当てもなく夜の街を彷徨した。道玄坂から、円山町に入ったかと思うと、次には宇田川町に向かった。無茶苦茶だった。麻里は正体を無くし、彷徨い続ける。
気付くと夜闇に人通りも絶えていた。
その折だった。矢庭に背後から羽交い締めにされた。麻里は悲鳴を上げた。
相手は大きなソフト帽子、サングラスに黒マスクで顔を隠し、焦げ茶色のレインコートを着ていた。
妖しい賊は、ポケットから刃渡りの長いナイフを取り出した。ナイフの銀色の煌めきが、麻里の眼を射た。
賊はナイフを高々と振り上げた。
素速く振り下ろす。麻里の胸部にナイフは刺さった。麻里は倒れた。その上から更にナイフの一撃。
賊は麻里の胸を切り開いた。
鮮血が迸った。肋骨が露わになった。次に心臓にナイフを突き立てた。
路面にどす黒い血が拡がる。
麻里は絶命した。
前のエピソード――第1話
第2話
2
国際外語大学のロック同好会、サークル室。青田晃司、高村麗子、高村奈津美、塚田僚一が警察の事情聴取を受けていた。田村警部補と恩田刑事が学生達に、根掘り葉掘り質問した。身近な者が惨殺されたので、彼らは一様に恐怖に駆られていた。
「塚田さん、貴方は島村麻里さんの恋人だったんですか」
田村警部補が尋ねた。塚田は首を振って即答した。
「いいえ、恋人とまでは言えません。唯の友達です」
「しかし、肉体関係はありましたか」
塚田は口籠もった。
「いえ、あの、そうですね。なかったとは言いません。しかしそれ程深い関係ではありませんでした」
「そうですか」
「僕は、容疑者になるんでしょうか」
「そこまで考えてはいません。この事件の犯人は、女性を切り刻むことに快楽を覚えている異常者です。塚田さんは、精神科の門をくぐったことはないですか」
「いいえ、とんでもありません」
「調べれば分かることですが、精神科の病を持っていないのなら、さほど容疑濃厚とは思いません。但し、痴情の縺れについては一応確認しておきたいのですが」
「縺れと仰有ると」
「私生活を調べられるのは嫌でしょう。調べれば分かることですから、此処は一つ忌憚なく話してくださいませんか。秘密は確実に守ります」
「そうですね」塚田は言った。「かなり以前ですが、僕は高村麗子さんと付き合っていた時期があります」
「麗子さん、確かですか」
「もう昔のことです。今は青田晃司さんとしかお付き合いしていません」
「言った方が良いと思いますが」青田は言った。「麗子さんの妹の奈津美さんも、僕のことが好きで、嫉妬しているらしい」
「酷いわ」高村奈津美は声を詰まらせた。「それは、殺された島村さんと無関係よ」
「奈津美さん、この場は何でも打ち明けた方が良いよ。痛くない腹は探られたくないからね」
「なる程、事情は分かりました」田村警部補は頷いた。「かなりの縺れがありますな。そのうち、島村さんに直接関係するのは、塚田さんと高村麗子さんの過去な訳ですが」
「殺意を抱くほどの縺れなんか、何処にもありませんわ」
麗子が吐き捨てた。
警部補は同意した。
「そうですな、犯人は異常者です。被害者の交際関係を探るより、我々は各地の精神病院を当たるべきなのでしょう」
「未だ殺人が起きるのでしょうか」
不安な眼差しで、麗子は問うた。
「残念ながら、起きるでしょう。猟奇殺人は始まったばかりです」
神保町の外れ、御茶ノ水小の近くに、国分探偵事務所はあった。古いビルの2階で、一人孤独に開業している国分幸夫は昼過ぎに漸く事務所に出勤した。
事務所のドアを開けると、殺風景な内部は書類棚とパソコン以外に目立つ調度品はなかった。依頼者も殆ど訪れないような探偵事務所なのだった。
国分は事務椅子に座り、嘆息した。
腕時計を見る。警察が来ることになっていた。国分は心底、悲嘆に暮れていたのだ。何という悲劇だろう。昨日殺害された島村麻里は、国分の実の娘だった。既に妻とは離婚し、親権も失っているが娘であることに変わりはない。
全てを失って酒浸りの毎日だったが、妻や娘は幸福な側の人間であるべきだった。そうあることを祈って、疫病神の国分は身を引いたのだ。
田村警部補と恩田刑事が事務所を訪れた。国分はパイプ椅子を広げて、恩田刑事に勧めた。警部補には来客用の椅子に掛けて貰った。
「まずお悔やみを申し上げます」田村警部補は言った。「今回は大変なことでしたな。昨夜は警察にお呼びしたのに、貴方はいらっしゃらなかった」
「私はもう親権を失っていますから、前妻の陽子に全てを任せました」
「確かにそうですな。麻里さんは母親の姓を名乗っていらした」
「もう一人、娘が居ります。島村麗奈、今年19になります」
「娘さん達とは、離婚後もう付き合いはないのですか」
「陽子が会わせたがらなかった。実は、娘達は隠れて此処にたまに立ち寄っていましたが」
「離婚の原因は何ですか」
「私が廃品になったんです。以前は銀行員をしていましたが、アルコール依存症で、職を失いました」
「それから、探偵事務所を開設なさったのですね」
「仕事とは言えないような閑職です。いや、ちゃんと探偵業法に則った営業をしていますがね。私はもう既に廃品です」
「麻里さんの男性関係について、ご存知ではないですか」
「幾つか聞いていますが、あの年頃の常識的な範囲内です。格別淫乱だった訳ではない」
「誰か異常者に付き纏われたりはなかったですか」
「私が知る限りはありません。相手は大抵同じ大学の学生らしかった」
「ところで、失礼ながら、貴方は精神科に掛かっていますか」
「ええ、お恥ずかしい話、アルコール依存症です」
「近くに、変態的異常者はいませんか」
「さあ、患者との付き合いはありません」
「麻里さんに、躰を切り刻む程の怨恨の線は?」
「それはあり得ません。他人の恨みを買うような娘ではなかった。犯人は異常者でしょう」
警部補は頷いた。
「警察としても、プロファイラーを招聘して、その専門の捜査を行うつもりです」
「女を切り刻んで、何が楽しいんですかね」
「さあ、快楽殺人ですからね」
「兎に角、早く犯人を捕まえてください。娘の敵を討ってほしい」
「承知致しました」
本田智美は女子大学の3年生だった。フロントフリルのブラウスに、センタープレステーパードパンツを身に着けていた。
智美はゼミで、担当教授と少しく揉めていた。彼女が割に渾身に書いたレポートが全く評価されなかった。教授に理由を尋ねても、思わしい答えは返ってこない。
智美としては、カフカの新しい解釈を提示し得たつもりだったが、評価は落第点なのだ。旧態依然とした文学解釈に、一介の学生が新説を打ち立てることは元より許されないのか。
智美はゼミ形式の講義は苦手だった。全て講義形式であれば良いのにと、思うほどだ。
智美は夕闇の目立ち始めた青山通りを独り歩いて、表参道に向かった。
未だ週末には間があるせいか、思ったより遥かに人通りは疎らだった。
智美は大学を退学しようかとすら考えていた。しかし中退して、彼女に何が出来るだろうか。勉学は好きな文学にだけ打ち込んで、簿記の基礎すら彼女は持たない。これでは事務に雇う会社など有る筈もない。
薄着のせいか、夜風が冷たく感じられた。
大学を入り直そうかとも考えた。例えば管理栄養士の資格を取得出来るコースに。文学を選択したのは全く若気の至りと思われた。もっと実業に特化した学部は他に幾らもあるではないか。
気が付くと、更に人通りの見えない神宮前に紛れ込んでいた。
そうだ、明日女子大に退学届けを出そうと決めた。
その時だった。
背後から背中に焼け火箸を打ち込まれたような耐え難い激痛を覚えた。
背中に、刃渡りの長いナイフを突き込まれたのだった。
智美は殆どスローモーションのように倒れた。
レインコートにソフト帽の殺人者が、更に上部からナイフを突き刺した。
智美は喉から血を吐いた。
殺人者は彼女の腹部をじりじりとナイフで切開した。そして更に突き立てた、幾度となく。
前のエピソード――第2話
第3話
3
国分は大学に電話して、塚田僚一を呼び出して貰った。そして、その日の夕刻に大学のサークル室にて、塚田と会う約束を取り付けた。
国分は、島村麻里の父親であると伝えた。また職業が私立探偵であることも明かした。
案外簡単に塚田は、会うことを了承した。
国分は不慣れな大学キャンパス内を右往左往し、グランドのラグビー部の学生に訊いて、ロック同好会部室を探し当てた。
「島村、いや、国分さんと仰有いましたね。遅かったですね」
塚田が迎えた。サークル室には他に青田晃司と高村麗子、奈津美の姉妹が居た。
「広くて迷いました。で、麻里の件なんですが」
国分は勧められた椅子に腰を下ろした。
「何なりとお尋ねください。もっとも事件については僕は余り知りませんが」
塚田は言った。
「どんなことでもいいんです。麻里は本当に異常者と関係はなかったでしょうか」
「ないと思いますが、そうだ、ユーチューブにこんな動画が上がっています。何かの参考になりませんでしょうか」
「拝見します」
塚田はパソコンを操作した。
〈……見ためはノーマルな人間で、私達の中に紛れ込んでいる。この事件の犯人はそんなマニアックでしょう〉
コメンテーターは高名な心理学者、或るワイドショーでの解説だった。
〈鋭利なナイフは性的象徴、ナイフを被害者に突き立てる行為は性交そのものなのです。それから被害者の腹部を切り開いたりする。これは帝王切開を意味するかもしれません。犯人は被害者に存在しない赤子まで産ませる。完全な女性の籠絡、所有を意味します。動機は恐らく性的不能者の女性憎悪でしょう〉
国分は礼を言った。
「精神科の退院には精神医療審査会の審査が必要です」塚田が言った。「警察は審査会から完全な情報を引き出すでしょう。または入院中の患者が外出して犯行に及んでいる場合、何処かの精神病院からその旨、情報提供がある筈です」
「なる程」
「ですから、犯人逮捕は時間の問題かと思いますが」
「しかし」国分は言った。「今の解説のように、見た目は普通の人間で、社会の中に紛れ込んでいる場合は厄介ですね」
「そうとしても、犯人は重度の精神障害でしょう。精神科医は彼らについて把握しています。また精神保健福祉手帳交付の際に、あらゆる個人情報を取得しています。犯人逮捕は容易だと思うのですが」
「そうなんですね」
「僕は楽観的過ぎますかね」
「そうでもないと思います。しかし塚田さんはその方面、お詳しいのですね」
「僕は、北欧諸国の地域文化研究の際に、社会福祉も学びました」
「なる程、しかし社会福祉が進歩する中で、ノーマライゼーションが犯人逮捕の弊害にならないでしょうか」
「そうまではならないでしょう。ノーマライゼーションの鍵概念の一つ、自己決定権は、この国では認められてはいませんから。憲法13条、幸福追求権を根拠に、自己決定権を導き出す手はありますが、一学説に過ぎません」
「塚田はこの分野、信頼出来ると思います」青田が言った。
「塚田さん、抜けているところはありますが、自分の専門分野にはたけていますわ」高村麗子が言った。
「警察はもっと切れ者の専門家を招聘していますわ。塚田君のレベルじゃなく」奈津美は少しく意地悪を言った。
「なる程、皆さん、大変参考になりました」
国分は頭を下げた。
「あと、僕が考えているのは」塚田が続けた。「麻里さんは何処かの総合病院を受診していないかですか」
「総合病院というと」
「精神科を含む大病院です。例えば風邪で受診なさっても、何処かの廊下で、異常者とすれ違う可能性はある訳です」
「なる程、私は既に親権を失っているので、麻里の私生活に詳しくありませんが、そういうことはあるかもしれませんね」
高村麗子は秋葉原に買い物に出ていた。海外ドラマのDVDを買い求めに訪れたのだ。普段は通販サイトを利用するのだが、久しぶりに店頭を漁ってみたくなった。
麗子は最近、青田晃司との関係で悩んでいた。事あるごとに、一つ違いの妹の奈津美が青田にちょっかいを出してくるのだった。
奈津美の心理は計りがたかった。姉の青田に対する深い愛は分かっている筈だった。
にも拘わらず、平然と青田に交際を挑んでくる様子なのだ。
一体妹は何を考えているのか。青田が妹に寝返ることはないと、充分信頼はしていたものの、奈津美は主に肉体的に男性にとっては魅力的な存在である筈だった。乳房が大きく、スタイルも良かった。それに比べれば、自分は容貌は兎も角、容姿は劣ると思われた。身長も妹の方が、かなり高かった。
麗子は買い物を足早に済ませると、秋葉原を無為に散歩した。
青田とは大学を卒業し次第、結婚を約束していた。その堅い約定が揺らぐなどという事態が一体想定為うるのだろうか。
麗子は、クロップドTシャツとデニムパンツの軽装だった。呆然とヨドバシカメラ前を通り、住友不動産を通り、公園へと向かった。
もう春も終わり、そろそろ梅雨に入ろうかとする時候、季節外れの冷風が吹いていた。
時刻は夕方だと思っていたが、いつの間にか闇が辺りを支配していた。
麗子が公園に差し掛かった折だった。
不意に何やら不吉な殺気が、麗子の脚を止めさせた。
周囲に人通りは皆無だった。
ふと上方を見上げると、其処に銀色に煌めくナイフの刃があった。
麗子は絹を裂くような悲鳴を上げた。革手袋の手が掴んだナイフが、麗子の喉元に突き刺さった。
鮮血が飛散した。ナイフが引き抜かれると、今度は腹部に突き込まれた。
麗子は倒れた。殺人者は、ナイフで冷酷に彼女の腹を切り裂いた。
前のエピソード――第3話
第4話
4
国分幸夫は、朝方のテレビニュースにて、高村麗子が殺害された事実を知った。塚田に会いに行った折に、話を聞いた、あの女性も殺されたのかと、非常に意外だった。
東京各地、渋谷、表参道近く、そして秋葉原にて連続猟奇殺人が発生していた。都内はある種のパニックを起こしていた。
国分の憂鬱はほぼ極限に達していた。思い直して、私立探偵のデスクワークに取り掛かった。暴力団山川組の組員、佐藤軍師の依頼で、恐喝のネタのポルノ写真をパソコンごと奪い返す、という些か穢い仕事だった。
仕事自体は割に円滑に進んで、無事に強請のネタを取り返していた。
ワードのキーボードを叩きながらも、国分の憂鬱は少しも癒えなかった。国分はパソコンの手を止めた。
或る想念が突如湧いてきた。
雑念として振り払おうとしたが、想念は国分の裡で膨張する一方だった。
相当に苦悩したものの、国分は漸く決心した。
机上の電話の受話器を取った。
佐藤軍師のスマホの番号をプッシュした。
「ああ、佐藤か?国分だが」
「嗚呼、国分さんか、この前は助かったよ。礼を言う」
「簡単な仕事だった。何でもない」
「そうか、それで今日は何か?」
国分は暫し嘆息した。
「実は、折り入って頼みがあるんだが」
「何だ。頼みにくいことらしいな」
「実はそうだ」
「構わない。言ってみろよ」
「……拳銃を一丁、用立てて貰えないか」
「何だって、ハジキか」
「そうだ」
「素人がそんなものを持つと、刑務所行きだが」
「構わない。覚悟は出来ているつもりだ」
「ふぅん、そうか。なら何も愚痴は言うまい」
「用立てて貰えるか」
「OK、いいだろう。他ならぬ国分さんの頼みだ」
「済まないな、本当に」
「明日、其方の事務所に届ける」
「有難う、恩に着る」
「何に使うか知らないが、死ぬなよ」
「分かった」
電話は切れた。
国分は椅子の上で、伸びをした。
大きく深呼吸してから、元の姿勢に戻った。
国分は更に数分間、躊躇してから、娘の麗奈のスマホ番号を押した。
「もしもし、麗奈か。私だ」
「お父さん」
「元気か。急に何だが、明日は暇かな」
「何よ、突然。明日も学校よ」
「講義、休めないかな。どうしても御前に会って、少し話したいんだが」
「何の用事。電話では話せないの」
「話せないな。明日、昼飯を奢るよ」
「何だか恐いわね。分かった、講義はさぼるわ」
「有難う。悪いが相変わらず持ち合わせが少ないんだ。ファミレスでいいだろう?」
「いいわよ、じゃ、明日」
「待てよ。余り軽く返事されても困るんだ。かなり重大な内容だから」
「本当に困るわね。どう答えればいいの」
「兎に角、一生のお願いなんだ。詳しくは会ってから話す」
「分かった、かなり覚悟しておきます。明日、家まで迎えに来てくれるの」
「嗚呼、行くよ、昼前に」
電話は切れた。
もう後に引くのは無しにしようと、国分は思った。俺の思念は現実離れしているだろうか。yesだ。しかし現実離れしたことが、身の回りで起きているではないか。それに対処して、何が悪いのだろう。普段からヤクザ絡みの案件を扱う私立探偵はどの道、命懸けにならざるを得ないのだ。
今夜は酒を喰らって、寝ようと思った。
翌朝、国分が早く事務所に出勤すると、9時頃に佐藤が訪れた。
何も言わず、小包みを手渡した。
「手助けはいらないか?」
「今のところ、独りで大丈夫だ」
「一つ確認する。拳銃の入手先で、俺を売るようなアンタじゃないよな」
「その点は心配するな、保証する」
「そうか、それじゃ俺も多忙だから帰る」
「嗚呼、本当に有難う」
佐藤は、そそくさと帰って行った。
兎に角、計画の一点は成功した。あと一点はどうなるか分からなかった。この行動が正しいか否かを自問するなら、正しくないという即答しか返せない。それでも尚遣らねばならないという義務感は、一体何処から湧くのだろうか。
11時過ぎ、麗奈の独り暮らしのマンションの前で、国分は中古車を停めた。
暫く待つと、麗奈がマンションから出て来た。ポロラルフローレンのニットが良く似合っていた。
麗奈は助手席に乗り込んだ。
「待たせたわね」
「いや、今来たばかりだ」
「それじゃ、行きましょうか。話はそれからでしょう?」
「ああ、人混みの中では、却って秘密を守れる」
車をスタートした。
ファミレスに着くと、店員の案内を半ば無視して、一番奥の席に陣取った。
ハンバーグで構わないという麗奈を制して、国分はステーキを二人前、タッチパネルで注文した。
軈て、ステーキをロボットが運んできた。国分は二人分の盆を取り分けた。
「それで一体何?」半分程、肉を平らげたところで、麗奈が訊いてきた。
国分は咳払いした。
「頼みがある」
「私に出来ることなの」
「ああ、私に一時、命を預けて欲しい」
「う~ん、それは余り正気に思えない」
「確かに正気ではないかもしれない。しかし是非とも頼みたいんだ」
「何をすればいいの」
「何もしなくていい。唯、夜間に街を歩き回って欲しい。私が常に後方で尾行しているから」
「それはどういうこと?」
「悪いが、囮になって貰いたいと言ってるんだ」
「私が囮になって、殺人者をおびき出すというの」
「そうだ」
「お姉さんの敵を討ちたいのね」
「そうだ」
「それは、正気ではないわ」
「その通りだ。だが私は本気だ」
国分は服の内ポケットから、僅かに拳銃を引き出して見せた。
「拳銃なの」
「嗚呼、本物だ。だから必ず御前を守る」
「でも、相当に危険よね」
「その通りだ」
麗奈は深刻な表情になった。
「少し考えさせて」
「それで構わない」
麗奈は首を振った。
「やっぱり無理だわ。私は当たり前の日常生活に軸足を置いているの。お父さんみたいに、ヤクザ世界に身を置いていない」
「それは重々承知している」
「無理だわ」麗奈は繰り返した。「私には到底出来ない」
新宿駅の地下通路。午後7時半、高村奈津美は塚田僚一に呼び出されて、其処に来ていた。
呑みに行こうという誘いだったが、奈津美は新宿駅まで出て来はしたものの、誘い自体は断った。
「一体何を考えているの。姉が亡くなったばかりなのに」
「だからだよ。寂しいだろうと思って誘ったんだ」
「そんなこと。神経を疑うわ」
「じゃ、正直に言おう」
「何を?」
「奈津美さんは青田が好きなんだろう。青田の恋人だったお姉さんが亡くなった今、青田に接近するチャンスだよな」
「何を言っているの」
「僕も不謹慎だとは思う。しかし事実だろう」
「知らないわ。貴方に関係ない」
「あるんだ。僕は実は密かに、君が好きだったから、青田に取られる前に、君に交際を申し込もうと思う」
「何よ、それ。最低の求愛ね。分かってる?」
「酷く不器用なのは重々自覚している。でも不器用だから、こう言うしかないんだ」
「貴方は頭でっかちなのよ。そんな調子では、どんな女も引っ掛からないわよ」
奈津美は塚田から離れようとした。
「待ってくれ。行かないで」
「知らないわ、貴方なんか」
奈津美は地下通路を駆けた。
塚田は追い掛けたが、遠慮がちな追い掛け方なので、中々追い付けない。
奈津美は新宿駅東口を出て、更に歌舞伎町へと駆け抜けた。
奈津美は体力的に優れているので、猛スピードで疾走した。カジュアルワンピースが風に靡いた。
疾駆して、新宿の外れ迄来た。
奈津美は息を荒げていた。
パークシティイセタン1を通り抜けた。
雑沓は既に途絶えた。
その刹那、奈津美の眼前高く、銀色に煌めくナイフが振り翳された。
奈津美は心底から悲鳴を上げた。
革手袋の手が、素速くナイフを振り下ろした。ナイフは奈津美の肩に刺さった。激痛が走った。
その時だった。
「何をしているんだ」
サラリーマンらしい、男性二人の通行人が近寄って来た。
「貴様、何者だ。何をしている?」
ソフト帽、焦げ茶色のレインコートの賊はナイフを引き抜くと、回れ右して素速く逃走した。
サラリーマン二人は、奈津美の介抱に当たり、賊を追い掛けなかった。当然だろう。刃物を持つ相手を捕まえようと試みる程の命知らずは居ない。
第5話
5
国分幸夫の探偵事務所、小型テレビが今回の事件を報じている。エアコンを除湿に入れてあったが、室内は早くも異様な暑さだ。
国分は回転椅子に腰掛け、ハンカチで額の汗を拭った。
〈……東京各地に突如現れたジャックザリッパーが、初めてミスを犯しました。高村奈津美さんは幸い、偶然通り掛かったサラリーマン二人に助けられ、殺害は未遂に終わりました。警察は高村さんと救助者二人から、犯人のモンタージュを作成しようと画策しましたが、犯人はソフト帽とサングラス、
黒マスクで顔を隠して居り、全く要領を得ません。東京中が今回の連続猟奇殺人事件により、酷いパニックに陥っています……〉
国分はあれから然したる仕事も舞い込んで来ず、焦燥に駆られていた。
机上の電話が鳴った。
徐に面倒くさそうに、国分は受話器を取った。
「お父さん、私よ」
「麗奈か、どうした?」
「私、あれから余り眠れない日が続いているの。私も様々悩んだのよ」
「で、気が変わったとでも言うのか」
「ええ」
「本当か、それは凄い。囮を引き受けてくれるのか」
「ええ、私遣ります。私も、お姉さんの敵を討ちたくなった」
「そうか、遣ってくれるか。今から来れるか?」
「ええ、今から其方に行きます。でも私、一体何処を歩けばいいのかしら」
「この殺人者は、順不同ながら殆ど順繰り、東京の街を回っている。渋谷、表参道、秋葉原、新宿と。次は六本木か赤坂か、池袋辺りだろう。このパニック状態だから、若い女性の夜間の独り歩きは激減した。御前が歩けば、犯人は必ず食いついてくるだろう。砂漠で針を拾うのとは訳が違う」
「分かりました」
「心配するな。拳銃もあるし、私が必ず御前を守る」
一夜目、六本木にて、麗奈は夜道を彷徨い、気付かれないよう充分注意を払って、国分がぴったり尾行した。
東京ミッドタウンの中を、二人は歩いた。生命の危険を賭けながら。
二日目、池袋辺りを二人は歩いた。
東池袋を、帝京平成大学や、東京国際大学の周囲を緊張感に包まれながら、歩いた。
三日目、西池袋を彷徨した。
四日目、六本木ヒルズ付近を二人は歩いた。
麻布区民センター前を通った辺りで、矢庭に麗奈は脚を止めた。
ソフト帽に焦げ茶色のレインコートの賊が、麗奈の眼前に現れた。
賊は、ポケットから、刃渡りの長いナイフを取り出した。麗奈は悲鳴を上げた。
後方から、国分が拳銃を発砲した。
銃弾は賊の右肩に命中した。賊はナイフを取り落とした。
国分は相手に拳銃を突きつけながら、前面に進んだ。
「動くな。手を上げろ」
殺人者は動じない。
「マスクを取れ。顔を晒せ。撃つぞ」
更に一発撃った。殺人者の頬を弾は掠めた。
殺人者はソフト帽を、サングラスを、マスクを外した。
「……貴様は」
焦げ茶色のレインコートを着て、其処に立ち竦んでいたのは、高村奈津美だった。
「貴様は会ったことがある」驚いて、国分は言った。「高村奈津美だな。貴様が犯人だったのか」
奈津美は沈黙を続けた。
「何故だ。何故そんなに人を殺した?」
「私は青田晃司を愛していた。でも晃司には姉の麗子がいた。唯単に麗子だけを殺せば、警察は直ぐ私が犯人だと見なす。だから連続猟奇殺人を偽装した。猟奇殺人なら、犯人は異常者の男性と見なされて、私は容疑の圏外に居られる」
「それだけの理由で、沢山の人を惨殺したのか。貴様は私の娘も殺した」
「麻里も晃司を狙っていた。私はそう思っていた。だから殺した」
「しかし、貴様も賊に襲われている。あれは何者だった?」
「渋谷のホームレスを金で雇って、人通りのある所で私を襲わせた。未遂に終わるように」
「そのホームレスはどうした?」
「殺した。ホームレスの死は新聞にも出なかった」
「何て奴だ。覚悟しろ、娘の敵……」
「お父さん、止めて」
その折だった。パトカーが傍らに停車した。警官が三人、降りて来ると、殺人者と国分に拳銃を突きつけた。
奈津美は突然逃走した。
警官が銃を発砲した。
その時、大型トラックが来た。
奈津美はトラックに身投げした。
奈津美の頭部は、トラックの前輪に轢かれてグシャリとスイカのように潰れた。