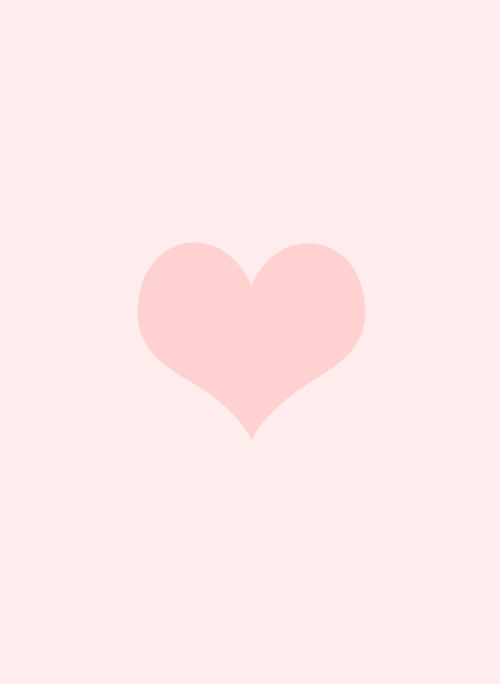君の隣、1メートル
CHAPTER.1
---ボヤっとする白いフィルターが私の視界を包み込み、その中央にはポツンと1人の男の子が立っている。
その男の子は周りをキョロキョロと何かを探しているようで、私と目が合った瞬間満面の笑みで私の方へ走ってきた。
『なーちゃん!これ!』
男の子が私に差し出したのは1輪の花。
私は言葉を発せないまま、彼から花を受け取る。
『ぼくね、なーちゃんとずっといっしょにいたいんだ!』
男の子は少し照れながらも私にこれ以上にない笑みをくれる。
---どことなく、懐かしい情景だった。
チュンチュンと雀のさえずりが私の鼓膜を振動させ、カーテンからは太陽の日差しが差し込み、私の目元を照らす。
少しずつ目を開け、枕元に充電してあるスマホを手探りで探す。
時刻は6:25、アラームが鳴る5分前だ。
いつもはアラームが鳴って起きるか、それかお母さんが起こしにきて起きるかなのに、久しぶりに自力で起きれた。
---あの夢を見ちゃったから起きたのかな。
ごく稀で彼が私の夢に出てくる。
もう何年も会ってない彼が何かを訴えてくるかのように私の夢に出てきて、話しかけてくる。
私はベットから抜け出し、一階のリビングへと降りた。
「あら菜穂、今日は起きるの早いわね。」
キッチンで朝食の準備をしていたお母さんが私に気づき、まるでいつもは起きるのが遅いわよ、と皮肉めいたように話しかけてきた。
「おはよう、お母さん。なんか起きちゃったんだよね。」
「自分で起きたもらった方が私的には起こしに2階まで上がる手間が省けるからいいわ。まだご飯できてないから先準備しなさい。」
私は顔を洗いに洗面台へ向かう。
「あ、菜穂姉おっはー」
ちょうど脱衣所から出てきたのは、2つ年下の弟の蒼だった。
中学2年生の蒼は中学校で野球部に所属していて、朝練に行くためにいつも朝はすれ違うことが多い。
私と違って誰にでも愛嬌が良く、元気いっぱいの蒼は私の自慢の弟だ。
「そうだ、菜穂姉。この前商店街通りでさ、ひー兄見かけたんだよね。」
蒼の言葉に私は時が止まったように体が固まってしまった。
「そ、そうなんだ…。」
やっと喉から言葉を絞り出して、私の体が動き出した。
「なんでさ、ひー兄と仲悪くなっちゃったのさ。俺、ひー兄大好きだったのに、なーんか気まづいじゃん。」
蒼は少し不服そうに口を曲げながら、リビングへと歩いて行った。
私は蒼から出たあの人の名前を聞いて、少しずつドクドクと鼓動が早くなるのを感じた。
今日は朝からあの夢を見て、蒼からさっきの話をされて、いつもの日常ではないことを察知した。
学校に行く準備をし、朝食を食べるためにリビングへ向かう。
リビングには蒼の姿はなく、ご飯を食べ終えた食器たちがテーブルの上に置いてある。
「菜穂、早くご飯食べちゃいなさい、冷めちゃうわよー。」
お母さんはテーブルに私の朝ごはんを置き、蒼の食べた食器たちを片付けた。
「今日、何時ごろ帰ってくるの?」
お母さんは片手にコーヒーを持ちながら、私の正面に座った。
「んー、なんか今日凜々花が一緒に来てほしいところがあるって言ってたから、帰ってくるのは6時くらいじゃない」
「本当に凜々花ちゃんと仲良いわね、今日蒼のナイターの送迎あるから少しご飯遅くなるわね。」
「はーい。多分菜摘ご飯とかじゃないと思うから大丈夫かな。」
私の普通の日常が少しずつ取り戻してきたような感じがした。
朝ご飯食べるときは、お母さんと何か最近の話など雑談をする。
心のどっかでさっきの胸の鼓動がゆっくりになっている。
「じゃあ、行ってきます。」
リュックを背負い、靴を履く。
「行ってらっしゃい、菜穂。」
玄関まで見送ってくれるお母さんを背に、扉を閉めた。
今日はいつもより日差しが強く、まだ6月なのにもう春が終わり、夏だなと実感する。
少し歩いたところに、凜々花がスマホをいじりながら私を待っていた。
「おはよ、凜々花。」
「あ!おはよ、菜穂!」
「なんか凜々花、いつもよりオシャレしてない?」
凜々花はいつも胸より下の黒髪を丁寧に真っすぐにしていて、人形のような顔に綺麗にメイクされてある。
しかし、今日の凜々花は髪の毛を巻いていて、メイクも少し艶っぽくなっている。
「さーすが菜穂!ちゃんとリリのことを見てくれてる!今日少し気合入れちゃったんだ♪」
凜々花は目をキラキラと輝かせ、私の腕をぎゅっと抱きしめる。
甘くバニラのような香水の匂いがふわっと香り、凜々花は本当にお姫様みたいだった。
凜々花とは中学2年生のクラス替えで、席が隣になってから常に一緒にいるようになり、親友になった。
いつもキラキラしていて、凜々花に対する恋愛感情を持つ異性も多いが凜々花は誰一人振り向かなった。
言えば高嶺の花のような立ち位置にいた。
「凜々花、今日の放課後どこに行くつもりなの?」
「んー、内緒!ま、後からのお楽しみってことで!」
凜々花はニコッと笑いながら、巻いた髪の毛をくるくると指で弄ぶ。
プリクラでも撮るのかな、と思いながら学校へと向かった。
学校へ着き、教室へと向かう。
凜々花とはやっぱり縁なのか高校でも同じクラス、でも席は少し遠いけど。
自分の席に座り、リュックから今日の授業の教科書類を出して、机の中にしまう。
「菜穂ちゃーん、おっはよ!」
横から元気いっぱいの聞きなれた声がして、振り向くとそこには隣の席の瑞樹がいた。
瑞樹は入学当初から何かと近い席に座っていて、ついにこの間の席替えで隣になった。
赤に近い茶髪に少しウェーブがかっている長い髪はピン止めで止めてある。
お調子者の瑞樹は常にハイテンションでよく絡んでくる。
「おはよ、瑞樹。今日も相変わらず元気だね。」
「そーゆー菜穂ちゃんは今日も冷静だねぇ。ねぇねぇ、今日の古典の宿題やってきた!?」
瑞樹は私の机の上にミルクティーのパックジュースを置いた。
「やってきたけど、これ何よ。」
「お願い!それあげるから宿題写させて!今日提出しないとまたバンド停止させられちゃう!」
瑞樹は手を合わせこれでもか、というくらい懇願をしてくる。
「もー、これで最後にしてよ。今度のテストの方が危ないんじゃないの?」
「よっしゃ!まじ菜穂ちゃん神!俺、テストは短期間で覚える能力あるから任せとけって!」
机の中から古典のノートを取り、瑞樹に渡す。
瑞樹は嬉しそうに古典のノートを受け取り、すぐに自分のノートに今回の宿題を写し始めた。
私は瑞樹から半強制的にもらったミルクティーを飲み、しばらくして担任の先生が教室の中に入ってきた。
全ての授業が終わり、教科書類をリュックへしまう。
「本当に菜穂ちゃん今日ありがとね!まじで助かった!さすが俺の女神様だわ!」
「女神様って…、次の宿題はちゃんと自分でやってね。」
「ほいほーい!あ、凜々花ちゃん!」
帰る準備をした凜々花が私たちの席の方まで来て、私たちの前の席に座った。
「ほら、菜穂早く準備して!瑞樹も菜穂にちょっかい出さないで!」
「この後なんか用事でもあんの、お2人さん。」
「この後、菜穂とデート行くんだから。瑞樹まじ邪魔!」
瑞樹と凜々花は何か波長は合うけどよく対立しているイメージ。
「邪魔って言いすぎだと思わなーい、菜穂?」
「いっつも菜穂の邪魔しているのは瑞樹の方でしょ、ね菜穂?」
この2人は仲が良いのか悪いのか分からないけど、常に学校にいる時に一緒にいる友達だ。
「用意できたから、じゃあね瑞樹。また明日ね。」
「あちゃー、凜々花ちゃんに菜穂ちゃん取られたわ。悔しいけどまた明日イチャイチャしようね!」
「さすがにきもすぎるでしょ、瑞樹。じゃあね。」
私と凜々花は教室を後に学校を出た。
「で、今日どこに行くのよ。」
「今日は立花高校に行くのであります!」
凜々花がそう言った後、私は今日の朝蒼に話しかけられたみたいにフリーズをした。
また鼓動が早くなってきている。
「え…?」
ポカンと立ち止まる私に、凜々花はニコッと笑う。
「大丈夫!相原君には絶対に会わないから。そんな運命的な出会い方ロマンチックだけどね。」
---相原 輝。
私の幼馴染であり、中学中頃までは一緒にいたけど気づいた時には距離を置かれていた。
今朝、蒼が話していた”ひー兄”は輝のことであり、家族ぐるみで仲良くしていた。
あの件があってから疎遠になってしまい、輝は県内有名な不良校立花高校に進学した。
中学校を卒業した以来、輝は引っ越しをし、私の前に二度と姿を現さなくなった。
会いたいけど、会えない、そんな気持ちがいつも私の心にふわふわと浮いている。
「そ、そうだけどなんで立花高なの?」
「よくぞ聞きました!リリ、最近よく通ってるカフェ行ってたの話してたじゃん。そこの店員さん!」
目をキラキラと輝かせながら話す凜々花。
---駅前のゆっくりとした時間を過ごせるカフェ内。
『30番のお客様ー。』
凜々花は自分のレシートの番号を確認し、受け渡し口まで向かった。
『うわー、おいしそう!』
そこに置かれていたのはこのカフェの新作のストロベリーココアフラペチーノであり、凜々花のテンションは上がっていた。
『お客様、最近よくいらっしゃいますよね。』
凜々花が上を見上げると、そこには金髪の美形の店員が立っていた。
『え…、あ…。』
あまりのかっこよさに言葉が詰まる凜々花。
『あ、なんか困らせちゃってすいません。いつも宝石見るような笑顔でうちの商品見てますから。なんか、俺も嬉しくなっちゃいます。』
凛々花は店員がニコッと微笑んだ瞬間、恋に落ちた。
そこから凛々花の頭の中は店員でいっぱいになり、彼が「片山」という名前を覚え、そして立花高校の生徒だということも探偵のように調べ上げた。
「いや、怖いよ凛々花。それストーカーじゃん。」
ズバッと言う私に、凛々花は目がハートのまま。
「立花高校の生徒だって分かった時は少し怖かったけど、あの店員さんは悪い人じゃないって!」
恋は盲目、本当にその言葉が今の凛々花にはぴったりだと思う。
「だから、リリの目的はその店員さん!相原君とは無関係なのであります!」
今日は本当に非日常すぎて何が起きるのか分からなく、胸がざわざわとしていた。
立花高校につき、校門の少し離れたところで私と凛々花はその店員が出てくるのを待っていた。
「でも、菜穂なんで相原君と話さなくなっちゃったの?喧嘩?」
あの日の出来事は胸の奥深くにしまっていたのだが、少しずつその扉が開かれようとしている。
「うーん、…喧嘩ていうのかな。」
「菜穂と仲良くなってすぐくらいに相原君と話さなくなって、最初リリのせいかなって思ってたんだけど。」
「あ、凛々花のせいじゃないよ!うーん、思春期のせいだったかもね…。」
「ならよかったけど、相原君菜穂のこと好きそうだったからリリが那覇を奪って嫉妬して怒ってたんじゃないかなって。」
ドクンっと胸が大きく高鳴った。
「ひ、輝に会ったとしても気まずいだけだよ。」
「リリ的には相原君と仲直りして欲しいけどね!てか、中学の時ずっと付き合ってるて思ってたし!」
『無理だよ』
そう言いたかったけど心のうちに止め、私はなんとも言えない顔で立花高校を見上げた。
「なーにしてるの、可愛い子たち。」
後ろから声がして、振り返るとそこにはガラの悪い男の人たちが数人立っていた。
「え、なに?」
私が声を出した瞬間、1人の男が凛々花の腕をぐいっと引っ張り、凛々花は「やめて!」と叫ぶ。
「こんなところに来て、やめてなんて馬鹿すぎるぜ。俺たちと遊ぼーぜ。」
話しかけてきた男が私の肩に手を置き、私はすぐにその手を振り落とす。
「や、やめてください!」
「ちっ。だから、ここでやめてくださいは通用しないんだわ!」
男は無理やり私の腕を掴み、ぎりっと強い力が私の顔を歪ませた。
「痛っ…。」
「おい、そこで何してんだよ。」
聞き慣れた声が聞こえ、後ろを振り向くとそこにいたのは…、
「…ひ、輝…。」
聞こえるか聞こえないかくらいの小さな声の私の目の前に、輝はまったく動じないまま私たちに絡んできたガラの悪い人たちに近づく。
「お前、1年の相原だろ?この前、俺の仲間のこと可愛がってくれたんだろ。ちょーどよかったわ、その恩返せるわ。」
私の腕を掴んでいた男はパッと手を離し、標的を輝に変えた。
まるで野生動物の喧嘩のような、実感したことがない殺伐とした空気は私はなかなか息が吸えなかった。
「お姉さんたち、ここは危ないからあっちに行こう。」
私と凛々花に話しかけてきた綺麗な顔をした金髪の人がニコッとまるで警戒心を解くように話しかけてきた。
「う、嘘…。」
隣にいる凛々花は顔をタコのように顔を真っ赤にさせ、口元に手を当て、その人をじっと見ていた。
とりあえず、私はその金髪の人を信じてその場から離れた。
あのガラの悪い人たちと輝が殴り合ってるのは分からないけど、あの空気感的に話し合いだけで済むなんてあり得ない。
立花高校の指定の学ランに、中学の時よりも身長は高くなり、また隣にいた時よりも体ばずっと男らしくなっていた。
漆黒のような黒髪は襟足まで長く、スッと切長の瞳はあの頃とは違い、何かフィルターがかかっているかのような曇りが見えた。
中学2年のあの日を境に距離を置かれ、互いに避け合うかのように残りの中学生活を送っていた為、久しぶりにちゃんと輝を見て懐かしさが込み上げてきた半分、私の知ってる輝ではない別人のような悲しさがあった。
金髪の人に連れてきてもらったのは私がよく昔来ていたカフェだった。
凛々花は金髪の人が私たちに話しかけてからまったく一言も話さず、ずっと顔を赤くしていた。
席を案内され、私たちは奥の席に座った。
「君さ、よく俺のバイト先に来てくれる子だよね。」
金髪の人はメニューを私たちに見せながら、凛々花にそう言った。
…やっぱり。
「あ、め、迷惑かけてすみません…!あ、あそこに友達がいてま、待っていたんですけど…」
凛々花は金髪の人にあなたを待っていたんですよ、とは言わず、嘘をついた。
「なるほどね、でもタチコーは悪い人が多いからもう来ないようにだよ。」
「は、はい…!」
凛々花はたじたじになりながらも顔を赤くし、金髪の人をキラキラとした目で見つめていた。
「さっき怖い目遭ったでしょ、ここ俺が払うから好きなの飲んで。」
「い、いや、自分で払います!」
私は貸し借りが嫌いなのもあるし、さっき出会ったまだいい人なのかも悪い人なのかも知らない人に奢ってもらうのは違うと思った。
「あはは、君、奥川菜穂ちゃんでしょ?」
金髪の人からまさか自分の名前が出るなんて思いもよらず、私はポカンと開いた口が閉じれなかった。
「輝からよく聞いてたからさ、もしかしてそうかなって思った。俺、輝の親友の藤平李人。よろしくね。君の名前は?」
「リリは…、あ、片山凛々花です…。」
しどろもどろになりながら凛々花は自分の名前を言った。
「凛々花ちゃんね、2人とも何飲むのか決めた?」
私たちと多分同い年であろう李人さんは何か余裕があるような大人な雰囲気がした。
「じゃあ、私アイスコーヒーでお願いします。砂糖ミルクなしで大丈夫です。」
「リリは、キャラメルマキアートで…お願いします!」
「了解、本当に凛々花ちゃんは甘いの大好きだね。」
李人さんはクスッと笑い、凛々花はさらに顔を真っ赤にさせた。
李人さんは金髪のゆるいパーマがかかって、中性的な綺麗な顔立ちをしている。
右耳にリングのシルバーピアスをしていて、私たちの高校にはいないタイプだった。
だからか、同じ学生には見えなく、大人のように見えた。
「あの、輝は…。」
注文を終えた李人さんに私が問い、李人さんは壁にかけてある時計をチラッと見た。
「あー、そろそろ帰ってくるんじゃない?そんなに輝が気になる?」
子供が悪戯をするような少し意地の悪い笑みを浮かべた李人さん。
「き、気になるっていうかあんな大勢対1人は心配します。」
「大丈夫だよ、輝は弱くないから。あいつ色んな人から恨み買いすぎだし。」
「輝から私のことなんて聞いているんですか?」
初対面の人には聞きすぎかなって思ったけど、喉の手前ギリギリまでつっかえるように気になっていたので聞いてしまった。
「うーん、大事な幼馴染、かな?あいつ女に興味ないのにあいつの家に写真飾ってあったから聞いたら菜穂ちゃんの話してくれた、て感じ。別に深掘りとかはしてないからね。」
「そうですか…。」
「正直ね、うちの高校って悪い輩が多くて2人のように安易に来ちゃう女の子多いんだよね。俺たちも下校する時とか無理やりナンパされてる場面とか見てるし。でも、今日俺よりも早く輝が菜穂ちゃんに気づいて行ったからさ、ヒーローみたいだったでしょ。」
ニヤリと微笑む李人さん。
その微笑みがどういう意味を持っているのか分からなかった。
「リ、リリも菜穂と相原君仲直りして欲しい…!」
「仲直り、て…。…分かんないよ。」
ちょうど李人さんが注文してくれた飲み物たちが届き、私は緊張を解くかのようにアイスコーヒーを一口飲んだ。
「…李人。」
アイスコーヒーのカップを持ち、置いた瞬間に上を見上げると輝が私たちの卓に座ろうとしていた。
その刹那、輝とバチっと何年かぶりにちゃんと目が合った。
「あー、輝おつかれ。」
李人さんはこの場を楽しんでるかのように意地悪な笑みを浮かべる。
ドサっと李人さんの隣に輝は座り、ジッと私の目を曇った瞳で見続けていた。
「…ひ、ひか…。」
「なんで、あんなところに来るんだよ。」
怒っているかのような低い声に、私の声はかき消された。
「あ…。」
鼓動がバクバクとスピードを上げ、喉から言葉が出てこない。
まるで輝の圧に押されてるみたいに。
「リ、リリが連れてきちゃったの!だ、だから菜穂は悪くない…!」
隣にいる凛々花は輝の圧に押されている私を庇うように必死で弁解をしていた。
「まぁ、今日は俺と輝がちょうどいたから良かったけど、いなかったら2人あいつらに連れていかれてたからね。」
李人さんがこの場の空気を柔らかくするように話し、私は輝の冷たい視線から逃げるようにアイスコーヒーを飲んだ。
「何があってもあそこに来るな。」
輝は冷たく言い放し、飲み物を注文しにレジへ席を立った。
「あいつなりに心配してるんだよ。」
李人さんがそうつぶやき、私は自分が知らないところでいつの間に大きくなった輝の背中を見つめることしかできなかった。
少しして片手にココアを持って、席に帰ってきた輝。
私はこの光景に懐かしさを感じて、胸がギュッとなった。
幼い頃からこのカフェに輝と来て、一番角の席に座り、その日にあった出来事を話すのが日課だった。
輝は絶対にココアを頼み、その当時は私も同じココアを飲んでいた。
しかし、自分が今頼んでいるのはアイスコーヒーであり、輝は変わらずココアのまま。
その瞬間だけ、ずっと一緒にいた時の輝のような気がして嬉しい反面、自分が変わってしまったという悲しさが相まっていた。
「凜々花ちゃんさ、俺たちこれ飲んだら店出ない?」
李人さんが何を考えているのか分からず、さっきと同様子供のような悪戯な笑みを浮かべていた。
凜々花も何かを察したのか「はい!」と返事をして、勢いよくキャラメルフラペチーノを飲み始めた。
…つまり、私と輝を2人きりにすることなのか。
私は正面に座っている輝の顔をチラッと見るが、輝は何一つ顔色を変えなかった。
凜々花がキャラメルフラペチーノを飲み終え、帰る準備をする。
「じゃ、俺たち先出るねー。」
「じゃあね、菜穂!また、明日!」
本当に先ほど自己紹介をしたのか?と疑うくらい、息がぴったりな2人はそそくさと店から出ていった。
2人がいなくなってから、私と輝の空気はまるで無音のような全く音が聞こえない空気だった。
むしろ、自分の心臓の音が輝に聞こえているのではないか、と思うくらいにドキドキと大きな音をたてている。
「…おい。」
私が視線を輝の方に向けると、透き通っていない曇り眼が私の瞳に映った。
「コーヒー、飲めるんだな。」
そう言い、視線をコーヒーに向けた。
「の、飲めるよ。いつまでも子供じゃないし。」
「そう。じゃあ俺はまだまだ子供なんだな。」
輝はくすっと表情を崩し、ココアを飲んだ。
その笑った顔に私は安堵を覚えたのか、緊張して吸いづらかった息が吸いやすくなった。
「このカフェ、懐かしいね。」
私はキョロキョロと店内を見渡し、今他の人が使用している角の席を昔の思い出と重ねるように見つめた。
「あぁ。」
輝も覚えているように、頷いた。
「わ、私ね、輝と久しぶりにこうやって話せるのなんか不思議な気持ちになる。前まで一緒にいたのに。」
真っすぐ輝の顔を見れずに、私の視線は輝のココアに向いてしまった。
少し言い過ぎたかなって後悔をした。
「…あぁ。」
少し間を置いて、輝はそう答えた。
「俺は菜穂がいない世界で生きていくって決めてたから、正直会いたくなかった。」
今まで以上にない鼓動が私の心臓を震わせた。
ぐるぐると輝の話した『会いたくなかった』が頭の中でフラッシュバックし、私は胸が苦しくなった。
輝はそんな私を見て、ココアを飲み干し、帰る準備をし始めた。
「今日会ったことは変えられないから、家まで送る。」
正直、今ここで気を抜いたら私は泣いてしまうと思い、グッと涙をこらえ、残ってたコーヒーを飲み干した。
「…うん、帰ろ。」
店を出て、久しぶりの隣同士で輝と歩いた。
隣に並ぶと、やはり輝は昔よりもずっと身長が高くなっていて私の身長の頭1.5個分くらい大きくなっていた。
昔はほぼ同じ身長だったのに、見ないうちに大きくなっていた輝に何とも言えない気持ちになった。
「…輝って引っ越したんだっけ。」
「あぁ。」
昔から一緒にいた理由が互いの家が近所にあることから、親同士が仲良くなり、そのまま私と輝は幼馴染になった。
だから、学校行くときや遊びに出かけるときは輝と一緒の帰り道だった。
しかし、距離を置いた中学2年生の終わりに私の近所の家から遠いところへ引っ越しをしてしまった。
学校は登校圏内だったため転校はしなかったが、家の方向が違う為、学校の中以外で輝を見ることはなかった。
なぜ引っ越しをしたのかは分からないけど、最初引っ越しの話を教えてくれたのはお母さんだった。
「この道通るの久しぶりだな。」
私の家までの帰る道をほぼ何も話さないで歩く私たち。
さっきカフェであんなことを言われてしまったから、むしろなんて話せばいいのか分からなくて無言になっているのもある。
「あいつもいればな…。」
輝はボソッと呟き、私は思わず輝の方を見た。
輝はどこか遠くを見ながら歩いていて、私はすぐに視線を戻した。
聞き間違いではないとは思うけど…。
ほぼ互いに何も話すことがなく、私たちの足音だけが虚しく響いていた。
私の家まで帰る途中に、輝と通っていた小学校や放課後によく遊んでいた公園などを通り、昔の思い出が蘇っていた。
少しして私の家の前まで着き、久しぶりの輝との一緒にいる時間も惜しくも終わりを迎えていた。
「…ありが…。」
家まで送ってくれたことに感謝を伝えようとすると、
「あれ、菜穂帰ってたの?」
ちょうど玄関からこれから夜の練習に向かう蒼と蒼の送迎をするお母さんが出てきた。
お母さんと蒼は私の隣にいる輝を見た。
「ひー兄だ!」
蒼は嬉しそうに持っていた野球用のバックを地面に置き、こちらに走ってきた。
「久しぶりね、輝君。こんなに大きくなっちゃって!」
お母さんも久しぶりに私と輝がいることが嬉しそうだ。
「お久しぶりです、菜穂のお母さんと蒼。」
迷惑だったかなと思い、チラッと輝の顔色を伺うと輝は本心か分からないけど笑っていた。
その男の子は周りをキョロキョロと何かを探しているようで、私と目が合った瞬間満面の笑みで私の方へ走ってきた。
『なーちゃん!これ!』
男の子が私に差し出したのは1輪の花。
私は言葉を発せないまま、彼から花を受け取る。
『ぼくね、なーちゃんとずっといっしょにいたいんだ!』
男の子は少し照れながらも私にこれ以上にない笑みをくれる。
---どことなく、懐かしい情景だった。
チュンチュンと雀のさえずりが私の鼓膜を振動させ、カーテンからは太陽の日差しが差し込み、私の目元を照らす。
少しずつ目を開け、枕元に充電してあるスマホを手探りで探す。
時刻は6:25、アラームが鳴る5分前だ。
いつもはアラームが鳴って起きるか、それかお母さんが起こしにきて起きるかなのに、久しぶりに自力で起きれた。
---あの夢を見ちゃったから起きたのかな。
ごく稀で彼が私の夢に出てくる。
もう何年も会ってない彼が何かを訴えてくるかのように私の夢に出てきて、話しかけてくる。
私はベットから抜け出し、一階のリビングへと降りた。
「あら菜穂、今日は起きるの早いわね。」
キッチンで朝食の準備をしていたお母さんが私に気づき、まるでいつもは起きるのが遅いわよ、と皮肉めいたように話しかけてきた。
「おはよう、お母さん。なんか起きちゃったんだよね。」
「自分で起きたもらった方が私的には起こしに2階まで上がる手間が省けるからいいわ。まだご飯できてないから先準備しなさい。」
私は顔を洗いに洗面台へ向かう。
「あ、菜穂姉おっはー」
ちょうど脱衣所から出てきたのは、2つ年下の弟の蒼だった。
中学2年生の蒼は中学校で野球部に所属していて、朝練に行くためにいつも朝はすれ違うことが多い。
私と違って誰にでも愛嬌が良く、元気いっぱいの蒼は私の自慢の弟だ。
「そうだ、菜穂姉。この前商店街通りでさ、ひー兄見かけたんだよね。」
蒼の言葉に私は時が止まったように体が固まってしまった。
「そ、そうなんだ…。」
やっと喉から言葉を絞り出して、私の体が動き出した。
「なんでさ、ひー兄と仲悪くなっちゃったのさ。俺、ひー兄大好きだったのに、なーんか気まづいじゃん。」
蒼は少し不服そうに口を曲げながら、リビングへと歩いて行った。
私は蒼から出たあの人の名前を聞いて、少しずつドクドクと鼓動が早くなるのを感じた。
今日は朝からあの夢を見て、蒼からさっきの話をされて、いつもの日常ではないことを察知した。
学校に行く準備をし、朝食を食べるためにリビングへ向かう。
リビングには蒼の姿はなく、ご飯を食べ終えた食器たちがテーブルの上に置いてある。
「菜穂、早くご飯食べちゃいなさい、冷めちゃうわよー。」
お母さんはテーブルに私の朝ごはんを置き、蒼の食べた食器たちを片付けた。
「今日、何時ごろ帰ってくるの?」
お母さんは片手にコーヒーを持ちながら、私の正面に座った。
「んー、なんか今日凜々花が一緒に来てほしいところがあるって言ってたから、帰ってくるのは6時くらいじゃない」
「本当に凜々花ちゃんと仲良いわね、今日蒼のナイターの送迎あるから少しご飯遅くなるわね。」
「はーい。多分菜摘ご飯とかじゃないと思うから大丈夫かな。」
私の普通の日常が少しずつ取り戻してきたような感じがした。
朝ご飯食べるときは、お母さんと何か最近の話など雑談をする。
心のどっかでさっきの胸の鼓動がゆっくりになっている。
「じゃあ、行ってきます。」
リュックを背負い、靴を履く。
「行ってらっしゃい、菜穂。」
玄関まで見送ってくれるお母さんを背に、扉を閉めた。
今日はいつもより日差しが強く、まだ6月なのにもう春が終わり、夏だなと実感する。
少し歩いたところに、凜々花がスマホをいじりながら私を待っていた。
「おはよ、凜々花。」
「あ!おはよ、菜穂!」
「なんか凜々花、いつもよりオシャレしてない?」
凜々花はいつも胸より下の黒髪を丁寧に真っすぐにしていて、人形のような顔に綺麗にメイクされてある。
しかし、今日の凜々花は髪の毛を巻いていて、メイクも少し艶っぽくなっている。
「さーすが菜穂!ちゃんとリリのことを見てくれてる!今日少し気合入れちゃったんだ♪」
凜々花は目をキラキラと輝かせ、私の腕をぎゅっと抱きしめる。
甘くバニラのような香水の匂いがふわっと香り、凜々花は本当にお姫様みたいだった。
凜々花とは中学2年生のクラス替えで、席が隣になってから常に一緒にいるようになり、親友になった。
いつもキラキラしていて、凜々花に対する恋愛感情を持つ異性も多いが凜々花は誰一人振り向かなった。
言えば高嶺の花のような立ち位置にいた。
「凜々花、今日の放課後どこに行くつもりなの?」
「んー、内緒!ま、後からのお楽しみってことで!」
凜々花はニコッと笑いながら、巻いた髪の毛をくるくると指で弄ぶ。
プリクラでも撮るのかな、と思いながら学校へと向かった。
学校へ着き、教室へと向かう。
凜々花とはやっぱり縁なのか高校でも同じクラス、でも席は少し遠いけど。
自分の席に座り、リュックから今日の授業の教科書類を出して、机の中にしまう。
「菜穂ちゃーん、おっはよ!」
横から元気いっぱいの聞きなれた声がして、振り向くとそこには隣の席の瑞樹がいた。
瑞樹は入学当初から何かと近い席に座っていて、ついにこの間の席替えで隣になった。
赤に近い茶髪に少しウェーブがかっている長い髪はピン止めで止めてある。
お調子者の瑞樹は常にハイテンションでよく絡んでくる。
「おはよ、瑞樹。今日も相変わらず元気だね。」
「そーゆー菜穂ちゃんは今日も冷静だねぇ。ねぇねぇ、今日の古典の宿題やってきた!?」
瑞樹は私の机の上にミルクティーのパックジュースを置いた。
「やってきたけど、これ何よ。」
「お願い!それあげるから宿題写させて!今日提出しないとまたバンド停止させられちゃう!」
瑞樹は手を合わせこれでもか、というくらい懇願をしてくる。
「もー、これで最後にしてよ。今度のテストの方が危ないんじゃないの?」
「よっしゃ!まじ菜穂ちゃん神!俺、テストは短期間で覚える能力あるから任せとけって!」
机の中から古典のノートを取り、瑞樹に渡す。
瑞樹は嬉しそうに古典のノートを受け取り、すぐに自分のノートに今回の宿題を写し始めた。
私は瑞樹から半強制的にもらったミルクティーを飲み、しばらくして担任の先生が教室の中に入ってきた。
全ての授業が終わり、教科書類をリュックへしまう。
「本当に菜穂ちゃん今日ありがとね!まじで助かった!さすが俺の女神様だわ!」
「女神様って…、次の宿題はちゃんと自分でやってね。」
「ほいほーい!あ、凜々花ちゃん!」
帰る準備をした凜々花が私たちの席の方まで来て、私たちの前の席に座った。
「ほら、菜穂早く準備して!瑞樹も菜穂にちょっかい出さないで!」
「この後なんか用事でもあんの、お2人さん。」
「この後、菜穂とデート行くんだから。瑞樹まじ邪魔!」
瑞樹と凜々花は何か波長は合うけどよく対立しているイメージ。
「邪魔って言いすぎだと思わなーい、菜穂?」
「いっつも菜穂の邪魔しているのは瑞樹の方でしょ、ね菜穂?」
この2人は仲が良いのか悪いのか分からないけど、常に学校にいる時に一緒にいる友達だ。
「用意できたから、じゃあね瑞樹。また明日ね。」
「あちゃー、凜々花ちゃんに菜穂ちゃん取られたわ。悔しいけどまた明日イチャイチャしようね!」
「さすがにきもすぎるでしょ、瑞樹。じゃあね。」
私と凜々花は教室を後に学校を出た。
「で、今日どこに行くのよ。」
「今日は立花高校に行くのであります!」
凜々花がそう言った後、私は今日の朝蒼に話しかけられたみたいにフリーズをした。
また鼓動が早くなってきている。
「え…?」
ポカンと立ち止まる私に、凜々花はニコッと笑う。
「大丈夫!相原君には絶対に会わないから。そんな運命的な出会い方ロマンチックだけどね。」
---相原 輝。
私の幼馴染であり、中学中頃までは一緒にいたけど気づいた時には距離を置かれていた。
今朝、蒼が話していた”ひー兄”は輝のことであり、家族ぐるみで仲良くしていた。
あの件があってから疎遠になってしまい、輝は県内有名な不良校立花高校に進学した。
中学校を卒業した以来、輝は引っ越しをし、私の前に二度と姿を現さなくなった。
会いたいけど、会えない、そんな気持ちがいつも私の心にふわふわと浮いている。
「そ、そうだけどなんで立花高なの?」
「よくぞ聞きました!リリ、最近よく通ってるカフェ行ってたの話してたじゃん。そこの店員さん!」
目をキラキラと輝かせながら話す凜々花。
---駅前のゆっくりとした時間を過ごせるカフェ内。
『30番のお客様ー。』
凜々花は自分のレシートの番号を確認し、受け渡し口まで向かった。
『うわー、おいしそう!』
そこに置かれていたのはこのカフェの新作のストロベリーココアフラペチーノであり、凜々花のテンションは上がっていた。
『お客様、最近よくいらっしゃいますよね。』
凜々花が上を見上げると、そこには金髪の美形の店員が立っていた。
『え…、あ…。』
あまりのかっこよさに言葉が詰まる凜々花。
『あ、なんか困らせちゃってすいません。いつも宝石見るような笑顔でうちの商品見てますから。なんか、俺も嬉しくなっちゃいます。』
凛々花は店員がニコッと微笑んだ瞬間、恋に落ちた。
そこから凛々花の頭の中は店員でいっぱいになり、彼が「片山」という名前を覚え、そして立花高校の生徒だということも探偵のように調べ上げた。
「いや、怖いよ凛々花。それストーカーじゃん。」
ズバッと言う私に、凛々花は目がハートのまま。
「立花高校の生徒だって分かった時は少し怖かったけど、あの店員さんは悪い人じゃないって!」
恋は盲目、本当にその言葉が今の凛々花にはぴったりだと思う。
「だから、リリの目的はその店員さん!相原君とは無関係なのであります!」
今日は本当に非日常すぎて何が起きるのか分からなく、胸がざわざわとしていた。
立花高校につき、校門の少し離れたところで私と凛々花はその店員が出てくるのを待っていた。
「でも、菜穂なんで相原君と話さなくなっちゃったの?喧嘩?」
あの日の出来事は胸の奥深くにしまっていたのだが、少しずつその扉が開かれようとしている。
「うーん、…喧嘩ていうのかな。」
「菜穂と仲良くなってすぐくらいに相原君と話さなくなって、最初リリのせいかなって思ってたんだけど。」
「あ、凛々花のせいじゃないよ!うーん、思春期のせいだったかもね…。」
「ならよかったけど、相原君菜穂のこと好きそうだったからリリが那覇を奪って嫉妬して怒ってたんじゃないかなって。」
ドクンっと胸が大きく高鳴った。
「ひ、輝に会ったとしても気まずいだけだよ。」
「リリ的には相原君と仲直りして欲しいけどね!てか、中学の時ずっと付き合ってるて思ってたし!」
『無理だよ』
そう言いたかったけど心のうちに止め、私はなんとも言えない顔で立花高校を見上げた。
「なーにしてるの、可愛い子たち。」
後ろから声がして、振り返るとそこにはガラの悪い男の人たちが数人立っていた。
「え、なに?」
私が声を出した瞬間、1人の男が凛々花の腕をぐいっと引っ張り、凛々花は「やめて!」と叫ぶ。
「こんなところに来て、やめてなんて馬鹿すぎるぜ。俺たちと遊ぼーぜ。」
話しかけてきた男が私の肩に手を置き、私はすぐにその手を振り落とす。
「や、やめてください!」
「ちっ。だから、ここでやめてくださいは通用しないんだわ!」
男は無理やり私の腕を掴み、ぎりっと強い力が私の顔を歪ませた。
「痛っ…。」
「おい、そこで何してんだよ。」
聞き慣れた声が聞こえ、後ろを振り向くとそこにいたのは…、
「…ひ、輝…。」
聞こえるか聞こえないかくらいの小さな声の私の目の前に、輝はまったく動じないまま私たちに絡んできたガラの悪い人たちに近づく。
「お前、1年の相原だろ?この前、俺の仲間のこと可愛がってくれたんだろ。ちょーどよかったわ、その恩返せるわ。」
私の腕を掴んでいた男はパッと手を離し、標的を輝に変えた。
まるで野生動物の喧嘩のような、実感したことがない殺伐とした空気は私はなかなか息が吸えなかった。
「お姉さんたち、ここは危ないからあっちに行こう。」
私と凛々花に話しかけてきた綺麗な顔をした金髪の人がニコッとまるで警戒心を解くように話しかけてきた。
「う、嘘…。」
隣にいる凛々花は顔をタコのように顔を真っ赤にさせ、口元に手を当て、その人をじっと見ていた。
とりあえず、私はその金髪の人を信じてその場から離れた。
あのガラの悪い人たちと輝が殴り合ってるのは分からないけど、あの空気感的に話し合いだけで済むなんてあり得ない。
立花高校の指定の学ランに、中学の時よりも身長は高くなり、また隣にいた時よりも体ばずっと男らしくなっていた。
漆黒のような黒髪は襟足まで長く、スッと切長の瞳はあの頃とは違い、何かフィルターがかかっているかのような曇りが見えた。
中学2年のあの日を境に距離を置かれ、互いに避け合うかのように残りの中学生活を送っていた為、久しぶりにちゃんと輝を見て懐かしさが込み上げてきた半分、私の知ってる輝ではない別人のような悲しさがあった。
金髪の人に連れてきてもらったのは私がよく昔来ていたカフェだった。
凛々花は金髪の人が私たちに話しかけてからまったく一言も話さず、ずっと顔を赤くしていた。
席を案内され、私たちは奥の席に座った。
「君さ、よく俺のバイト先に来てくれる子だよね。」
金髪の人はメニューを私たちに見せながら、凛々花にそう言った。
…やっぱり。
「あ、め、迷惑かけてすみません…!あ、あそこに友達がいてま、待っていたんですけど…」
凛々花は金髪の人にあなたを待っていたんですよ、とは言わず、嘘をついた。
「なるほどね、でもタチコーは悪い人が多いからもう来ないようにだよ。」
「は、はい…!」
凛々花はたじたじになりながらも顔を赤くし、金髪の人をキラキラとした目で見つめていた。
「さっき怖い目遭ったでしょ、ここ俺が払うから好きなの飲んで。」
「い、いや、自分で払います!」
私は貸し借りが嫌いなのもあるし、さっき出会ったまだいい人なのかも悪い人なのかも知らない人に奢ってもらうのは違うと思った。
「あはは、君、奥川菜穂ちゃんでしょ?」
金髪の人からまさか自分の名前が出るなんて思いもよらず、私はポカンと開いた口が閉じれなかった。
「輝からよく聞いてたからさ、もしかしてそうかなって思った。俺、輝の親友の藤平李人。よろしくね。君の名前は?」
「リリは…、あ、片山凛々花です…。」
しどろもどろになりながら凛々花は自分の名前を言った。
「凛々花ちゃんね、2人とも何飲むのか決めた?」
私たちと多分同い年であろう李人さんは何か余裕があるような大人な雰囲気がした。
「じゃあ、私アイスコーヒーでお願いします。砂糖ミルクなしで大丈夫です。」
「リリは、キャラメルマキアートで…お願いします!」
「了解、本当に凛々花ちゃんは甘いの大好きだね。」
李人さんはクスッと笑い、凛々花はさらに顔を真っ赤にさせた。
李人さんは金髪のゆるいパーマがかかって、中性的な綺麗な顔立ちをしている。
右耳にリングのシルバーピアスをしていて、私たちの高校にはいないタイプだった。
だからか、同じ学生には見えなく、大人のように見えた。
「あの、輝は…。」
注文を終えた李人さんに私が問い、李人さんは壁にかけてある時計をチラッと見た。
「あー、そろそろ帰ってくるんじゃない?そんなに輝が気になる?」
子供が悪戯をするような少し意地の悪い笑みを浮かべた李人さん。
「き、気になるっていうかあんな大勢対1人は心配します。」
「大丈夫だよ、輝は弱くないから。あいつ色んな人から恨み買いすぎだし。」
「輝から私のことなんて聞いているんですか?」
初対面の人には聞きすぎかなって思ったけど、喉の手前ギリギリまでつっかえるように気になっていたので聞いてしまった。
「うーん、大事な幼馴染、かな?あいつ女に興味ないのにあいつの家に写真飾ってあったから聞いたら菜穂ちゃんの話してくれた、て感じ。別に深掘りとかはしてないからね。」
「そうですか…。」
「正直ね、うちの高校って悪い輩が多くて2人のように安易に来ちゃう女の子多いんだよね。俺たちも下校する時とか無理やりナンパされてる場面とか見てるし。でも、今日俺よりも早く輝が菜穂ちゃんに気づいて行ったからさ、ヒーローみたいだったでしょ。」
ニヤリと微笑む李人さん。
その微笑みがどういう意味を持っているのか分からなかった。
「リ、リリも菜穂と相原君仲直りして欲しい…!」
「仲直り、て…。…分かんないよ。」
ちょうど李人さんが注文してくれた飲み物たちが届き、私は緊張を解くかのようにアイスコーヒーを一口飲んだ。
「…李人。」
アイスコーヒーのカップを持ち、置いた瞬間に上を見上げると輝が私たちの卓に座ろうとしていた。
その刹那、輝とバチっと何年かぶりにちゃんと目が合った。
「あー、輝おつかれ。」
李人さんはこの場を楽しんでるかのように意地悪な笑みを浮かべる。
ドサっと李人さんの隣に輝は座り、ジッと私の目を曇った瞳で見続けていた。
「…ひ、ひか…。」
「なんで、あんなところに来るんだよ。」
怒っているかのような低い声に、私の声はかき消された。
「あ…。」
鼓動がバクバクとスピードを上げ、喉から言葉が出てこない。
まるで輝の圧に押されてるみたいに。
「リ、リリが連れてきちゃったの!だ、だから菜穂は悪くない…!」
隣にいる凛々花は輝の圧に押されている私を庇うように必死で弁解をしていた。
「まぁ、今日は俺と輝がちょうどいたから良かったけど、いなかったら2人あいつらに連れていかれてたからね。」
李人さんがこの場の空気を柔らかくするように話し、私は輝の冷たい視線から逃げるようにアイスコーヒーを飲んだ。
「何があってもあそこに来るな。」
輝は冷たく言い放し、飲み物を注文しにレジへ席を立った。
「あいつなりに心配してるんだよ。」
李人さんがそうつぶやき、私は自分が知らないところでいつの間に大きくなった輝の背中を見つめることしかできなかった。
少しして片手にココアを持って、席に帰ってきた輝。
私はこの光景に懐かしさを感じて、胸がギュッとなった。
幼い頃からこのカフェに輝と来て、一番角の席に座り、その日にあった出来事を話すのが日課だった。
輝は絶対にココアを頼み、その当時は私も同じココアを飲んでいた。
しかし、自分が今頼んでいるのはアイスコーヒーであり、輝は変わらずココアのまま。
その瞬間だけ、ずっと一緒にいた時の輝のような気がして嬉しい反面、自分が変わってしまったという悲しさが相まっていた。
「凜々花ちゃんさ、俺たちこれ飲んだら店出ない?」
李人さんが何を考えているのか分からず、さっきと同様子供のような悪戯な笑みを浮かべていた。
凜々花も何かを察したのか「はい!」と返事をして、勢いよくキャラメルフラペチーノを飲み始めた。
…つまり、私と輝を2人きりにすることなのか。
私は正面に座っている輝の顔をチラッと見るが、輝は何一つ顔色を変えなかった。
凜々花がキャラメルフラペチーノを飲み終え、帰る準備をする。
「じゃ、俺たち先出るねー。」
「じゃあね、菜穂!また、明日!」
本当に先ほど自己紹介をしたのか?と疑うくらい、息がぴったりな2人はそそくさと店から出ていった。
2人がいなくなってから、私と輝の空気はまるで無音のような全く音が聞こえない空気だった。
むしろ、自分の心臓の音が輝に聞こえているのではないか、と思うくらいにドキドキと大きな音をたてている。
「…おい。」
私が視線を輝の方に向けると、透き通っていない曇り眼が私の瞳に映った。
「コーヒー、飲めるんだな。」
そう言い、視線をコーヒーに向けた。
「の、飲めるよ。いつまでも子供じゃないし。」
「そう。じゃあ俺はまだまだ子供なんだな。」
輝はくすっと表情を崩し、ココアを飲んだ。
その笑った顔に私は安堵を覚えたのか、緊張して吸いづらかった息が吸いやすくなった。
「このカフェ、懐かしいね。」
私はキョロキョロと店内を見渡し、今他の人が使用している角の席を昔の思い出と重ねるように見つめた。
「あぁ。」
輝も覚えているように、頷いた。
「わ、私ね、輝と久しぶりにこうやって話せるのなんか不思議な気持ちになる。前まで一緒にいたのに。」
真っすぐ輝の顔を見れずに、私の視線は輝のココアに向いてしまった。
少し言い過ぎたかなって後悔をした。
「…あぁ。」
少し間を置いて、輝はそう答えた。
「俺は菜穂がいない世界で生きていくって決めてたから、正直会いたくなかった。」
今まで以上にない鼓動が私の心臓を震わせた。
ぐるぐると輝の話した『会いたくなかった』が頭の中でフラッシュバックし、私は胸が苦しくなった。
輝はそんな私を見て、ココアを飲み干し、帰る準備をし始めた。
「今日会ったことは変えられないから、家まで送る。」
正直、今ここで気を抜いたら私は泣いてしまうと思い、グッと涙をこらえ、残ってたコーヒーを飲み干した。
「…うん、帰ろ。」
店を出て、久しぶりの隣同士で輝と歩いた。
隣に並ぶと、やはり輝は昔よりもずっと身長が高くなっていて私の身長の頭1.5個分くらい大きくなっていた。
昔はほぼ同じ身長だったのに、見ないうちに大きくなっていた輝に何とも言えない気持ちになった。
「…輝って引っ越したんだっけ。」
「あぁ。」
昔から一緒にいた理由が互いの家が近所にあることから、親同士が仲良くなり、そのまま私と輝は幼馴染になった。
だから、学校行くときや遊びに出かけるときは輝と一緒の帰り道だった。
しかし、距離を置いた中学2年生の終わりに私の近所の家から遠いところへ引っ越しをしてしまった。
学校は登校圏内だったため転校はしなかったが、家の方向が違う為、学校の中以外で輝を見ることはなかった。
なぜ引っ越しをしたのかは分からないけど、最初引っ越しの話を教えてくれたのはお母さんだった。
「この道通るの久しぶりだな。」
私の家までの帰る道をほぼ何も話さないで歩く私たち。
さっきカフェであんなことを言われてしまったから、むしろなんて話せばいいのか分からなくて無言になっているのもある。
「あいつもいればな…。」
輝はボソッと呟き、私は思わず輝の方を見た。
輝はどこか遠くを見ながら歩いていて、私はすぐに視線を戻した。
聞き間違いではないとは思うけど…。
ほぼ互いに何も話すことがなく、私たちの足音だけが虚しく響いていた。
私の家まで帰る途中に、輝と通っていた小学校や放課後によく遊んでいた公園などを通り、昔の思い出が蘇っていた。
少しして私の家の前まで着き、久しぶりの輝との一緒にいる時間も惜しくも終わりを迎えていた。
「…ありが…。」
家まで送ってくれたことに感謝を伝えようとすると、
「あれ、菜穂帰ってたの?」
ちょうど玄関からこれから夜の練習に向かう蒼と蒼の送迎をするお母さんが出てきた。
お母さんと蒼は私の隣にいる輝を見た。
「ひー兄だ!」
蒼は嬉しそうに持っていた野球用のバックを地面に置き、こちらに走ってきた。
「久しぶりね、輝君。こんなに大きくなっちゃって!」
お母さんも久しぶりに私と輝がいることが嬉しそうだ。
「お久しぶりです、菜穂のお母さんと蒼。」
迷惑だったかなと思い、チラッと輝の顔色を伺うと輝は本心か分からないけど笑っていた。