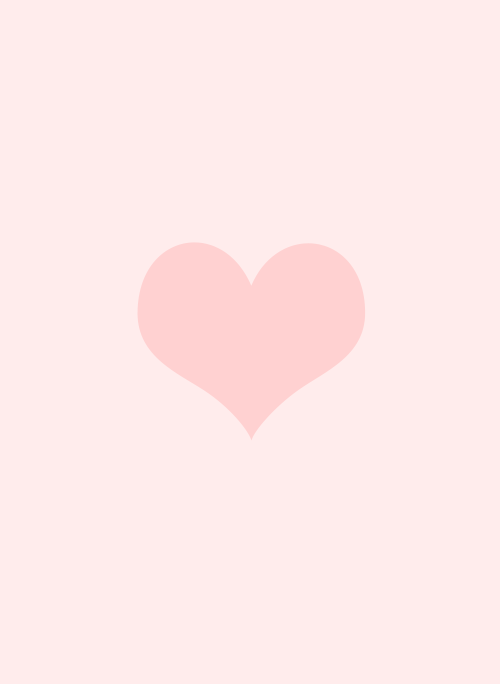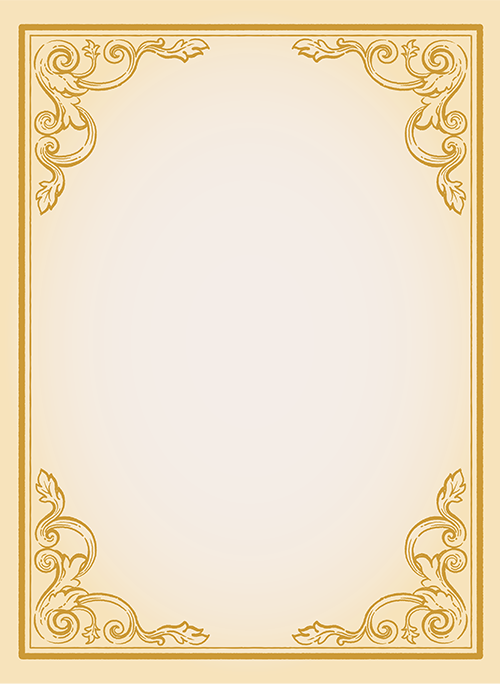私の彼氏はスーパーツンデレ
私は、彼と待ち合わせしている公園の時計台のそばにやってきた。
ただ今の時刻は10時50分。
待ち合わせ場所で彼を見つけるのは簡単だ。人だかりができている場所を探せばいい。
「すみません、ごめんなさい。通してくださーい……!」
女の子たちの人垣をかきわけて進み、なんとか輪を抜けてほっと息をつくと――
「遅い! 僕を待たせるなんて、いいご身分だね」
両腕を胸の前に組み、時計台に背中を預けながら長い脚をクロス。
私の目の前にいる、このいかにもイケてるメンズみたいな立ち方をしている彼こそ、最近お付き合いを始めた彼氏・一ノ瀬玲央くんだ。
(きょ、今日も眩しい……!)
艶のある黒髪から覗く瞳はガラス玉みたいに綺麗で、肌は陶器のように白い。幻覚で後光が差して見えるほどだ。
「待たせちゃってごめんね。でも、まだ待ち合わせ時間の10分前じゃ……」
「僕は1時間前からここにいた」
「1時間!? なんでそんなに早く……?」
「君に早く会いたかったからに決まってるでしょ。恋人なら、僕の愛情の強さを見越して1時間前行動して」
「そ、そんな無茶な」
(でも、怒ってる理由が可愛すぎる……寂しかったのかな~~??)
そう。
私・小松ひよりの彼氏は、ものすごくツンデレなのである。
「どうしてこんなに遅くなったわけ?」
「あ……実は服選びに迷っちゃって」
結局、一周回ってサロペットスカートにボーダーのTシャツを合わせてお団子ヘアというカジュアルコーデにしたけれど、かれこれ30分は鏡の前でうなっていた。
「つまり、好きな人にちょっとでも可愛く思われたい乙女心と申しますか」
(まあ、人波に揉まれて服はシワくちゃになっちゃったし、お団子も原型を留めてるかわからないけど……)
「……まったく、君は優柔不断だね」
玲央くんは、短くため息をつく。
今日の彼のコーデのように、シンプルなシャツとスラックスを身に着けるだけでサマになってしまう玲央くんからすると、私の悩みはあまりピンとこないのかもしれない。
彼は私の頭にポンと手を置いて、真面目な顔で言った。
「ひよりは何を着たって可愛いんだから、迷う必要ない。次からはクローゼットを開けて最初に手に取った服に決めること。いい?」
「……!」
玲央くんのナチュラルなデレに、脳内にいる私の分身が富士山の頂上からこう叫んだ。
『あま――い!』
「ひより? 聞いてるの?」
「うん、聞いてる聞いてる。一瞬、富士山頂にトリップしてただけ」
「……よくわからないけど、さっさと行くよ。これ以上君とのデート時間が減るのは嫌だ」
口元に柔らかな笑みを浮かべた彼に手を握られ、胸が甘い音を立てる。
そのまま彼が歩き出すと、周囲を取り囲んでいた女の子たちの輪が割れて道が出来た。
手を引かれながらその道を通る時――
「カッコいいのに彼女は普通じゃない?」
なんて声がかすかに聞こえ、胸をちくりと刺す。
(……まあ、そう思うよね。私も思ってるし)
でも、すぐに気を取り直して笑顔を作ると彼の隣を並んで歩いた。こんな風に言われるのは、別に初めてじゃないから。
(まだ2回目のデートなのにな)
***
――公園へやってきたのは、今日ここでB級グルメのフードフェスタが開かれているからだった。
広島お好み焼きに富士宮やきそば、佐世保バーガーや金沢カレーなど、ご当地の魅力満載の屋台がずらりと勢ぞろいしている。
「わあ、どれも美味しそう……!」
「どこの屋台も結構列ができてるみたいだ。手分けして食べたいものを買ってくる?」
「いい案だね、ふたりで半分こしよっか」
「決まりだ。じゃあ、この辺りで集合しよう」
玲央くんが、広い芝生の上に臨時でずらりと並べられたベンチを指さす。
お昼には少し早い時間だからか、まだわずかに空席があり、ふたり同時に動いても大丈夫そうだ。
「うん、わかった! 玲央くん、後でね」
彼と別れた私はすぐに、食欲をそそる濃厚で強烈な香りを放つ屋台に吸い寄せられた。
甘辛の黒いルーがたっぷりかかったカレーを片手にベンチへ戻ってくると、彼の姿はまだない。
(よかった……集合した時みたいに、また待たせちゃったら悪いもんね。危うく『僕よりカレーが大事なの!?』なんて言われるところだったかも)
そんな姿を想像しながらベンチに座り、膝の上に置いたカレーを見つめていると……そこに人影が落ちた。
「あ、おかえ――」
(えっ)
顔を上げると、そこに立っていたのは彼ではなく、にこやかな笑みを浮かべた見知らぬお兄さんだった。
スポーティーなパーカーにスキニーパンツ姿で、私の顔を覗き込むように彼が身を乗り出すと、派手めのネックレスがじゃらりと鳴った。
「ねー、ひとり? 俺もひとり」
(うわ……もしかしてだけどナンパだ)
思わず身構えてしまいながら、その人から目を逸らす。
「……い、今はひとりですけど、彼氏を待っています」
「じゃ、その彼氏が帰ってくるまで一緒にいていい?」
私の返事を待たず、ナンパ男さんは勝手に隣に座ってきた。
(……これは、彼氏がいるの嘘だと思われてるな)
周囲に目を向けると、私と同じようにひとりでいる女性や、キラキラした女の子グループもいる。
(わざわざ私に声をかけるなんて……たぶん“ちょうどいい”感じだと思われたんだろうな)
大学生になってしばらくして玲央くんとお付き合いすることになったけれど、そのずっと前――高校1年生の冬、初めて出来た彼氏もそうだった。
スクールカースト上位の子には手が届かないから“ちょうどいい”私で手を打ったのだと、彼氏が友人に話すのを放課後の廊下で偶然聞いてしまった時は……しばらくうまく笑えなかった。
(……嫌なこと思い出しちゃった)
可もなく、不可もなく。どこにでもいて、たぶんモブの中でも2番手くらいの大学生B。それが私だ。
(玲央くんは、そんな風に私を選んだわけじゃない。……頭では、ちゃんとわかってるはずなのに)
自然と俯いてしまい、膝の上に置いていたカレーのお皿を持つ手に力が入った時――
「……誰?」
聞き慣れたツンとした声が聞こえて顔を上げると、紙皿にのったお好み焼きを片手に眉をひそめる彼がいた。
「玲央くん……!」
「うわ、マジで彼氏登場」
「……そこどいて。早くその子から離れて」
玲央くんが冷えきった声で言うと、ナンパ男さんは何がおかしいのか、ぷっと吹き出しながら立ち上がった。
「いーよ別に。この子くらいなのは他にゴロゴロいるし」
「……は?」
玲央くんの声のトーンが一段下がる。
「てか余計なお世話だけどさ、あんたくらいのスペックなら他にもっといい彼女作れんじゃね?」
(っ……)
ざわついていた胸をさらにえぐられた気がして、心に暗い影が差したその時――
玲央くんが、手に持っていたお好み焼きをパイ投げのごとくお兄さんの顔面に押しつけた。
(えっ!?)
「……これ、彼女の地元のB級グルメ。美味しいでしょ」
「熱っ、熱いって!」
「ああ、でも“その辺にゴロゴロいる”ようなナンパ男には味なんてわからないか。彼女の良さもわからないんだから」
ナンパ男さんがお好み焼きを顔からはがして地面に叩きつけると、ソースで顔が真っ茶色だ。
玲央くんは私の膝の上のカレーを手に取り、再び彼に向き直る。
「お好み焼きだけで足りないなら、このカレーもご馳走してあげる。遠慮しないで、こっちは彼女からのおごりだ。ね、ひより?」
「えっ? あっ、うん……」
「わ、悪かったって」
慌てて立ち去ろうとするナンパ男さんを「ちょっと待ちなよ」と引き留めた玲央くんがぴしゃりと言う。
「それ拾って。ちゃんと食べてよね」
「っ……!」
ぼろぼろに崩れたお好み焼きを紙皿にかき集めて、お兄さんは去っていった。
***
――ちょっとした騒ぎになってしまったので、私たちは場所を移して別のベンチで向かい合っていた。
「あの……玲央くん、怒ってる……?」
「もし僕が楽しんでいるように見えるなら、いい眼科を紹介するよ」
「……えっと……とにかくカレー、食べよっか。もう冷めちゃったかもだけど……」
「うん」
ふたつもらってきていたスプーンのひとつを手に取った彼は、ひとくちすくって口に運んだ。私も同じように口に入れるけれど、なんだか味がしない。
たくさん置かれたベンチのそこかしこから賑やかな声が響いているのに、私たちだけが静まり返っていた。
(いつもなら、そっけないことを言ってもすぐにデレてくれるのに……もしかして、何も言い返せなかった私に呆れちゃった……?)
玲央くんは、最初はツンと屈折していても、最後にはデレてまっすぐな想いを私に向けてくれる。けれど、まっすぐなのは愛情に限ったことじゃない。
嫌なものは嫌、間違っていることは間違っている、ちゃんとそう言える人だ。さっきみたいに。
(なんか私……全然だめだな……)
すぐ隣にいても、彼と私はあまりにかけ離れている――そう思ってしまったら、視界がゆらゆら滲んでくる。
「う……」
「えっ……ひより?」
「うう~っ……」
泣いたって余計に呆れられるだけだとわかっているのに、勝手に涙が溢れてくる。
「ど、どうして泣くわけ……? あっ、さっきのナンパ男、そんなに怖かったの……!?」
(えっ……)
思ってもない彼の言葉に驚き、涙が止まる。
思わず目を瞬かせていると、彼が困惑したように私の肩に両手を置いた。
「な、なんで今度はきょとんとするの。違った……?」
「……私に、呆れたんじゃ」
「はぁ……? 呆れるわけない」
「……じゃあ、嫌いになった……?」
「っ、嫌いになんてなるわけない。さっきから何をわけのわからないこと言ってるの」
「だって…………怒ってる、から……」
私の言葉にはっと目を見開いた彼は、何度も首を横に振った。
「違う、怒ってたのは自分にだ。……君をひとりにしたせいで、嫌な思いをさせてしまったから」
優しい手のひらが、そっと頬に添えられる。
「その上、今は君を不安にもさせてた。……本当にごめん」
「玲央くん……」
「こんなにも君が好きなのに、嫌いになるわけない。なれるわけ、ない」
彼の顔が近付いてきて……一瞬、唇が触れ合う。
その時だけ、まるで世界から音が消えたみたいだった。
「僕の気持ち、伝わった?」
「れ、玲央くん……!」
「ここにいる人たちは大抵お酒が入っている上に、グルメに夢中で僕たちなんて見ていない。こうした方が早いと思って」
私を見守るようなあたたかい微笑みはすぐに離れていったけれど、唇に残った余韻が心を少しずつ幸せで満たしていく。
「ふふ……えへへ。嬉しい」
「ひよりの感情はジェットコースター並みだね。次のデートは遊園地に行くのもいいかもしれない。絶叫マシンの前で狼狽えている君を見るのは楽しそうだ」
「っ……そんなのが楽しいなんて、ドSキャラになったの?」
「……なんの話?」
「だめだよ、玲央くんはツンデレなんだから」
「だから、なんの話なの」
冷めたカレーを食べるのを再開した彼が首をひねる。
「ツンデレっていうのは、言葉はちょっとキツくて『ツン』としてるけど、甘いことを言って『デレ』てくれるような、二面性がある人のことだよ」
「……なるほど、なんとなくわかった。でも、僕はツンデレじゃないと思う」
「そんなわけないよ、ツンデレだよ!」
「なんでそんなにムキになるの……。だってツンデレっていうのは、ツンの後に必ずデレるものなんでしょ。僕は言い方はきつくてツンとしてるかもしれないけど、デレはしない」
「え?」
(じ、自覚ないんだ)
「ぷっ……あはは!」
「ちょっと、なに笑ってるの」
そうツッコむ玲央くんだって笑っている。
ふたりで笑っていたら、なんだかぜんぶ小さなことのように思えてきた。
「……安心しなよ。たとえジェットコースターの前で生まれたての子鹿みたいにガクガク震えていたとしても、君は可愛い」
玲央くんは、緩んでいた私の頬をむぎゅっと摘まんで言う。
「どんなに情けない姿を見せたとしても、僕は君を好きでいるから。……君だってそうでしょ」
「……うん」
(今日みたいに不安になることも、劣等感に押し潰されそうになることも、この先何度もあるかもしれない。だけど……彼氏が玲央くんならきっと大丈夫だ)
私は玲央くんみたいに完璧じゃない。それでも、彼と一緒に歩くことを選ぼう。
「よーし。このカレーを食べ終わったらお好み焼きの屋台に行こっか。さっき食べ損なっちゃったから」
「ああ。今度はふたりで一緒に並ぶよ」
晴れ晴れとした私の気持ちのように、見上げた空は青く澄んでいる。
私たちのデートは、まだ始まったばかりだ。
ただ今の時刻は10時50分。
待ち合わせ場所で彼を見つけるのは簡単だ。人だかりができている場所を探せばいい。
「すみません、ごめんなさい。通してくださーい……!」
女の子たちの人垣をかきわけて進み、なんとか輪を抜けてほっと息をつくと――
「遅い! 僕を待たせるなんて、いいご身分だね」
両腕を胸の前に組み、時計台に背中を預けながら長い脚をクロス。
私の目の前にいる、このいかにもイケてるメンズみたいな立ち方をしている彼こそ、最近お付き合いを始めた彼氏・一ノ瀬玲央くんだ。
(きょ、今日も眩しい……!)
艶のある黒髪から覗く瞳はガラス玉みたいに綺麗で、肌は陶器のように白い。幻覚で後光が差して見えるほどだ。
「待たせちゃってごめんね。でも、まだ待ち合わせ時間の10分前じゃ……」
「僕は1時間前からここにいた」
「1時間!? なんでそんなに早く……?」
「君に早く会いたかったからに決まってるでしょ。恋人なら、僕の愛情の強さを見越して1時間前行動して」
「そ、そんな無茶な」
(でも、怒ってる理由が可愛すぎる……寂しかったのかな~~??)
そう。
私・小松ひよりの彼氏は、ものすごくツンデレなのである。
「どうしてこんなに遅くなったわけ?」
「あ……実は服選びに迷っちゃって」
結局、一周回ってサロペットスカートにボーダーのTシャツを合わせてお団子ヘアというカジュアルコーデにしたけれど、かれこれ30分は鏡の前でうなっていた。
「つまり、好きな人にちょっとでも可愛く思われたい乙女心と申しますか」
(まあ、人波に揉まれて服はシワくちゃになっちゃったし、お団子も原型を留めてるかわからないけど……)
「……まったく、君は優柔不断だね」
玲央くんは、短くため息をつく。
今日の彼のコーデのように、シンプルなシャツとスラックスを身に着けるだけでサマになってしまう玲央くんからすると、私の悩みはあまりピンとこないのかもしれない。
彼は私の頭にポンと手を置いて、真面目な顔で言った。
「ひよりは何を着たって可愛いんだから、迷う必要ない。次からはクローゼットを開けて最初に手に取った服に決めること。いい?」
「……!」
玲央くんのナチュラルなデレに、脳内にいる私の分身が富士山の頂上からこう叫んだ。
『あま――い!』
「ひより? 聞いてるの?」
「うん、聞いてる聞いてる。一瞬、富士山頂にトリップしてただけ」
「……よくわからないけど、さっさと行くよ。これ以上君とのデート時間が減るのは嫌だ」
口元に柔らかな笑みを浮かべた彼に手を握られ、胸が甘い音を立てる。
そのまま彼が歩き出すと、周囲を取り囲んでいた女の子たちの輪が割れて道が出来た。
手を引かれながらその道を通る時――
「カッコいいのに彼女は普通じゃない?」
なんて声がかすかに聞こえ、胸をちくりと刺す。
(……まあ、そう思うよね。私も思ってるし)
でも、すぐに気を取り直して笑顔を作ると彼の隣を並んで歩いた。こんな風に言われるのは、別に初めてじゃないから。
(まだ2回目のデートなのにな)
***
――公園へやってきたのは、今日ここでB級グルメのフードフェスタが開かれているからだった。
広島お好み焼きに富士宮やきそば、佐世保バーガーや金沢カレーなど、ご当地の魅力満載の屋台がずらりと勢ぞろいしている。
「わあ、どれも美味しそう……!」
「どこの屋台も結構列ができてるみたいだ。手分けして食べたいものを買ってくる?」
「いい案だね、ふたりで半分こしよっか」
「決まりだ。じゃあ、この辺りで集合しよう」
玲央くんが、広い芝生の上に臨時でずらりと並べられたベンチを指さす。
お昼には少し早い時間だからか、まだわずかに空席があり、ふたり同時に動いても大丈夫そうだ。
「うん、わかった! 玲央くん、後でね」
彼と別れた私はすぐに、食欲をそそる濃厚で強烈な香りを放つ屋台に吸い寄せられた。
甘辛の黒いルーがたっぷりかかったカレーを片手にベンチへ戻ってくると、彼の姿はまだない。
(よかった……集合した時みたいに、また待たせちゃったら悪いもんね。危うく『僕よりカレーが大事なの!?』なんて言われるところだったかも)
そんな姿を想像しながらベンチに座り、膝の上に置いたカレーを見つめていると……そこに人影が落ちた。
「あ、おかえ――」
(えっ)
顔を上げると、そこに立っていたのは彼ではなく、にこやかな笑みを浮かべた見知らぬお兄さんだった。
スポーティーなパーカーにスキニーパンツ姿で、私の顔を覗き込むように彼が身を乗り出すと、派手めのネックレスがじゃらりと鳴った。
「ねー、ひとり? 俺もひとり」
(うわ……もしかしてだけどナンパだ)
思わず身構えてしまいながら、その人から目を逸らす。
「……い、今はひとりですけど、彼氏を待っています」
「じゃ、その彼氏が帰ってくるまで一緒にいていい?」
私の返事を待たず、ナンパ男さんは勝手に隣に座ってきた。
(……これは、彼氏がいるの嘘だと思われてるな)
周囲に目を向けると、私と同じようにひとりでいる女性や、キラキラした女の子グループもいる。
(わざわざ私に声をかけるなんて……たぶん“ちょうどいい”感じだと思われたんだろうな)
大学生になってしばらくして玲央くんとお付き合いすることになったけれど、そのずっと前――高校1年生の冬、初めて出来た彼氏もそうだった。
スクールカースト上位の子には手が届かないから“ちょうどいい”私で手を打ったのだと、彼氏が友人に話すのを放課後の廊下で偶然聞いてしまった時は……しばらくうまく笑えなかった。
(……嫌なこと思い出しちゃった)
可もなく、不可もなく。どこにでもいて、たぶんモブの中でも2番手くらいの大学生B。それが私だ。
(玲央くんは、そんな風に私を選んだわけじゃない。……頭では、ちゃんとわかってるはずなのに)
自然と俯いてしまい、膝の上に置いていたカレーのお皿を持つ手に力が入った時――
「……誰?」
聞き慣れたツンとした声が聞こえて顔を上げると、紙皿にのったお好み焼きを片手に眉をひそめる彼がいた。
「玲央くん……!」
「うわ、マジで彼氏登場」
「……そこどいて。早くその子から離れて」
玲央くんが冷えきった声で言うと、ナンパ男さんは何がおかしいのか、ぷっと吹き出しながら立ち上がった。
「いーよ別に。この子くらいなのは他にゴロゴロいるし」
「……は?」
玲央くんの声のトーンが一段下がる。
「てか余計なお世話だけどさ、あんたくらいのスペックなら他にもっといい彼女作れんじゃね?」
(っ……)
ざわついていた胸をさらにえぐられた気がして、心に暗い影が差したその時――
玲央くんが、手に持っていたお好み焼きをパイ投げのごとくお兄さんの顔面に押しつけた。
(えっ!?)
「……これ、彼女の地元のB級グルメ。美味しいでしょ」
「熱っ、熱いって!」
「ああ、でも“その辺にゴロゴロいる”ようなナンパ男には味なんてわからないか。彼女の良さもわからないんだから」
ナンパ男さんがお好み焼きを顔からはがして地面に叩きつけると、ソースで顔が真っ茶色だ。
玲央くんは私の膝の上のカレーを手に取り、再び彼に向き直る。
「お好み焼きだけで足りないなら、このカレーもご馳走してあげる。遠慮しないで、こっちは彼女からのおごりだ。ね、ひより?」
「えっ? あっ、うん……」
「わ、悪かったって」
慌てて立ち去ろうとするナンパ男さんを「ちょっと待ちなよ」と引き留めた玲央くんがぴしゃりと言う。
「それ拾って。ちゃんと食べてよね」
「っ……!」
ぼろぼろに崩れたお好み焼きを紙皿にかき集めて、お兄さんは去っていった。
***
――ちょっとした騒ぎになってしまったので、私たちは場所を移して別のベンチで向かい合っていた。
「あの……玲央くん、怒ってる……?」
「もし僕が楽しんでいるように見えるなら、いい眼科を紹介するよ」
「……えっと……とにかくカレー、食べよっか。もう冷めちゃったかもだけど……」
「うん」
ふたつもらってきていたスプーンのひとつを手に取った彼は、ひとくちすくって口に運んだ。私も同じように口に入れるけれど、なんだか味がしない。
たくさん置かれたベンチのそこかしこから賑やかな声が響いているのに、私たちだけが静まり返っていた。
(いつもなら、そっけないことを言ってもすぐにデレてくれるのに……もしかして、何も言い返せなかった私に呆れちゃった……?)
玲央くんは、最初はツンと屈折していても、最後にはデレてまっすぐな想いを私に向けてくれる。けれど、まっすぐなのは愛情に限ったことじゃない。
嫌なものは嫌、間違っていることは間違っている、ちゃんとそう言える人だ。さっきみたいに。
(なんか私……全然だめだな……)
すぐ隣にいても、彼と私はあまりにかけ離れている――そう思ってしまったら、視界がゆらゆら滲んでくる。
「う……」
「えっ……ひより?」
「うう~っ……」
泣いたって余計に呆れられるだけだとわかっているのに、勝手に涙が溢れてくる。
「ど、どうして泣くわけ……? あっ、さっきのナンパ男、そんなに怖かったの……!?」
(えっ……)
思ってもない彼の言葉に驚き、涙が止まる。
思わず目を瞬かせていると、彼が困惑したように私の肩に両手を置いた。
「な、なんで今度はきょとんとするの。違った……?」
「……私に、呆れたんじゃ」
「はぁ……? 呆れるわけない」
「……じゃあ、嫌いになった……?」
「っ、嫌いになんてなるわけない。さっきから何をわけのわからないこと言ってるの」
「だって…………怒ってる、から……」
私の言葉にはっと目を見開いた彼は、何度も首を横に振った。
「違う、怒ってたのは自分にだ。……君をひとりにしたせいで、嫌な思いをさせてしまったから」
優しい手のひらが、そっと頬に添えられる。
「その上、今は君を不安にもさせてた。……本当にごめん」
「玲央くん……」
「こんなにも君が好きなのに、嫌いになるわけない。なれるわけ、ない」
彼の顔が近付いてきて……一瞬、唇が触れ合う。
その時だけ、まるで世界から音が消えたみたいだった。
「僕の気持ち、伝わった?」
「れ、玲央くん……!」
「ここにいる人たちは大抵お酒が入っている上に、グルメに夢中で僕たちなんて見ていない。こうした方が早いと思って」
私を見守るようなあたたかい微笑みはすぐに離れていったけれど、唇に残った余韻が心を少しずつ幸せで満たしていく。
「ふふ……えへへ。嬉しい」
「ひよりの感情はジェットコースター並みだね。次のデートは遊園地に行くのもいいかもしれない。絶叫マシンの前で狼狽えている君を見るのは楽しそうだ」
「っ……そんなのが楽しいなんて、ドSキャラになったの?」
「……なんの話?」
「だめだよ、玲央くんはツンデレなんだから」
「だから、なんの話なの」
冷めたカレーを食べるのを再開した彼が首をひねる。
「ツンデレっていうのは、言葉はちょっとキツくて『ツン』としてるけど、甘いことを言って『デレ』てくれるような、二面性がある人のことだよ」
「……なるほど、なんとなくわかった。でも、僕はツンデレじゃないと思う」
「そんなわけないよ、ツンデレだよ!」
「なんでそんなにムキになるの……。だってツンデレっていうのは、ツンの後に必ずデレるものなんでしょ。僕は言い方はきつくてツンとしてるかもしれないけど、デレはしない」
「え?」
(じ、自覚ないんだ)
「ぷっ……あはは!」
「ちょっと、なに笑ってるの」
そうツッコむ玲央くんだって笑っている。
ふたりで笑っていたら、なんだかぜんぶ小さなことのように思えてきた。
「……安心しなよ。たとえジェットコースターの前で生まれたての子鹿みたいにガクガク震えていたとしても、君は可愛い」
玲央くんは、緩んでいた私の頬をむぎゅっと摘まんで言う。
「どんなに情けない姿を見せたとしても、僕は君を好きでいるから。……君だってそうでしょ」
「……うん」
(今日みたいに不安になることも、劣等感に押し潰されそうになることも、この先何度もあるかもしれない。だけど……彼氏が玲央くんならきっと大丈夫だ)
私は玲央くんみたいに完璧じゃない。それでも、彼と一緒に歩くことを選ぼう。
「よーし。このカレーを食べ終わったらお好み焼きの屋台に行こっか。さっき食べ損なっちゃったから」
「ああ。今度はふたりで一緒に並ぶよ」
晴れ晴れとした私の気持ちのように、見上げた空は青く澄んでいる。
私たちのデートは、まだ始まったばかりだ。