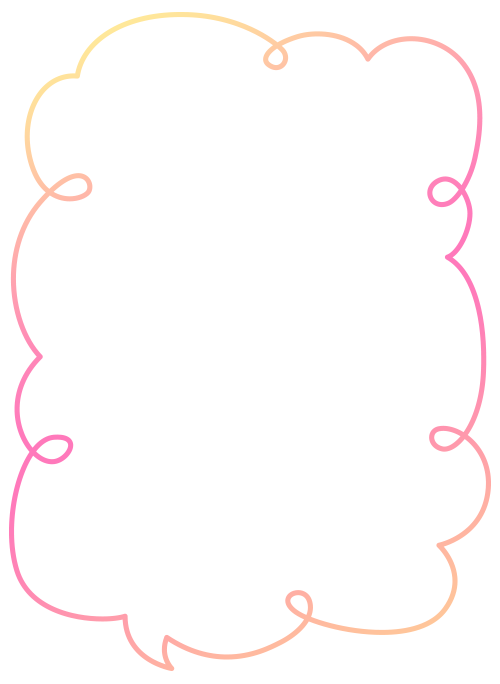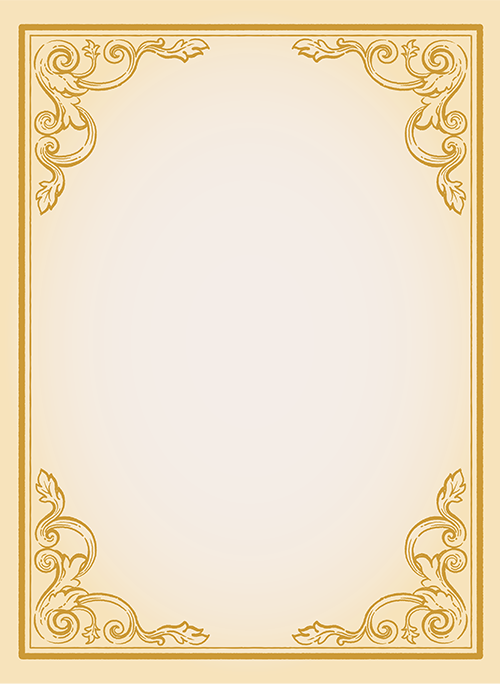元・ぬいぐるみのヤンデレニャンコはご主人さまをマーキング済。
星が美しく輝いている、ある日の夜――
「うっ……うう、ひどすぎる……っ」
私、小鳥遊 夢芽は、大学まで6駅の1DKに帰ってくるなりベッドに突っ伏し、怨念を放っていた。
「私が! 誰のために! 頑張ってたと思ってるんだぁ~~~~!」
枕を濡らしながらマットレスをタコ殴りにし、バタ足で散々蹴って疲れ果てると、そばに置いている猫のぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた。
この子は『ミルク』。私がつけた名前だ。
白いふわふわの毛並みに、明るいブラウンのプラスチックボタンの目が可愛い30センチほどのぬいぐるみ。
小学生の頃に買ってもらって以来の長い付き合いのミルクに、私は訴えた。
「涼馬がスマートウォッチ欲しいって言ってたからさぁ……ぐすっ、サプライズで誕生日にプレゼントしようと思って、シフト増やして頑張ってたのにぃ……」
鼻をすすり、怒りをぶつけるようにミルクのお腹をもみくちゃにする。
「その間に浮気するって、ありえなくない!?」
どうやら相手は隣のゼミの女の子らしい。
今日のバイト帰り、ふたりが手を繋いで歩いているところに鉢合わせし――そのままフラれてしまったのだ。
泣いて泣いて、ひたすら泣いて。何時間経ったかわからなくなった頃。
「はぁ……」
ラグを敷いたサイドテーブルの前で膝を抱えて座り、電子レンジでチンした牛乳をひとくち飲む。
少し落ち着いた私は、隣に座らせたふわふわの相棒を見てぽつりとつぶやいた。
「もしミルクが彼氏だったら、私だけを愛して大事にしてくれるのかな……」
このシリーズのぬいぐるみには、それぞれ『設定』がある。
たとえば、オレンジのくまは『お外で遊ぶのが大好きな元気っ子』、ピンクのうさぎは『可愛いものに目がない甘えん坊』のように。
ミルクこと、この白い猫のぬいぐるみについてきた設定カードには『ご主人さまだけが大好きな、マイペースボーイ』と書かれていたのだ。
ご主人さまだけ――私だけ。
再びベッドに寝転がり、お腹の上でミルクをだっこしながらぽつりと呟く。
「あーあ……ミルクみたいな彼氏がいたらいいのに」
ふと目をやったカーテンの隙間から見えた夜空に、光の筋が走ったのが見えた。
「あ、流れ星」
その瞬間、ずしりと身体の上に重みを感じて視線を自分のお腹に移すと――
(……へっ?)
白みがかった銀色の髪にブラウンの瞳を持つ、同い年くらいの男の人が私に覆いかぶさっていた。
「ギャーッ!!」と叫ぼうとした口元は、「ギ」と発声した時点でその人に塞がれてしまう。
「落ち着いて、ゆめ。おれはミルクだよ」
「ほふははほは……!」
「あ、ごめん。いつまでも口を塞いでたらしゃべれないよね」
大きくてあたたかな手のひらが離れていくと、私は改めて言った。
「そんな馬鹿な……!」
「ゆめの気持ちはわかるけど、ほんとうだよ。おれは昔からずっとゆめが好きで、“かれし”になりたいと思ってた。おれたちが同じ気持ちになったから、流れ星が願いを叶えてくれたんだ」
(説明を聞いても『そんな馬鹿な』って感想は変わらないけど……)
彼の頭の両脇からはふわふわの耳が、そしておしりからは気まぐれに揺れる尻尾が生えている。
それ以外は人間と同じように見えるけれど、その耳と尻尾はとても作り物には見えない。
(それに、状況的にミルクしか考えられない……よね?)
抱きしめていたぬいぐるみはどこかへ消えてしまっているし、毛や瞳の色がとても似ている。
いや、待って。というか――
「なんで裸!?」
「だって、ぬいぐるみの頃のおれは服を着てなかったでしょ?」
覆いかぶさられているせいで、細身だけどほどよく筋肉のついた胸板が嫌でも視界に入ってしまう。
(……胸板どころか、その下まで!)
「め、目のやり場に困るから早く隠して! ほら、この毛布とかで!」
ベッドの脇でくちゃくちゃになっていた毛布を掴み、顔を背けながら彼に突き出した右手をきゅっと握られる。
そして、そのままシーツの上に縫い止められた。
「ねえ、ゆめ。つらいことは、おれがぜーんぶ忘れさせてあげる」
「え……」
「だから、おれにまかせて……?」
顎にそっと手を添えられて、彼の方を向かされる。
キャラメルみたいに甘いブラウンの瞳と間近で視線が交わると、鼓動が勝手に速くなった。
ミルクの顔がゆっくり近付いてきて……
「えっ、えっ……!?」
(まさか、このままキスする気!?)
どうにかしなければと頭をフル回転させた私は――
――掴まれていない方の手で、彼の顎の下を優しく撫でた。
「ふにゃ~~、ゴロゴロゴロ……」
「隙あり!」
ミルクの手の力が緩んだ隙に、ベッドから転がり落ちるように抜け出した。
「はっ……! おれとしたことが」
必死に這いつくばった私は肩で息をしていたけれど、なぜか勝ち誇ったように笑いながらこう言った。
「はっはっは……! いくらぬいぐるみでも、DNAに刻まれた設定には抗えないみたいだね!」
カードには『ご主人さまだけが大好きな、マイペースボーイ』という設定だけでなく、猫らしく『顎の下を撫でられるのも大好き』と書かれていたことを思い出したのだ。
(……ぬいぐるみにDNAがあるのか謎だけど!)
私の言葉にきょとんと目を瞬かせていたミルクは、力の抜けた顔で笑う。
「よくわからないけど……よかった。ゆめが笑えるようになって」
「……!」
不本意ながら、その言葉と笑顔にキュンとしてしまった。
……きっとこれは、落ち込んでいる私に神様が見せてくれた一夜の夢だ。
(失恋女の元にイケメンニャンコが来るなんて、漫画みたいな展開だし)
きっと、明日になったらミルクはぬいぐるみに戻って――
――いなかった。
「おはよう、ゆめ」
カーテンの隙間から朝日が差し込む中、毛布にくるまった裸のミルクとベッドの中で目が合う。
(……なんで?)
そして、私を抱きしめたまま彼はへらりと笑った。
「今日からは、おれを“かれし”にしてくれる?」
「はぁ……!?」
***
いつまでも裸では困るので、ひとまず私のオーバーサイズのパーカーを着させてブランケットで下半身を隠してもらい、なんとか落ち着いて話ができる姿になった。
ベッドの横に置いているサイドテーブルの前に彼を座らせ、マグカップを手渡す。
「わあ……ゆめがいつも飲んでるあったかい牛乳だ」
ちなみに、人型の彼をミルクと呼ぶのは少し違和感があったので、ふたりで話し合い、仮で『ミーくん』と呼ぶことに決めた。
「ミーくん」
「なぁに? ゆめ」
微笑みながら湯気の立つ白い水面にふーふー息を吹きかけている彼に、私は真剣ですと伝えるようにぐっと身を乗り出して尋ねた。
「昨日『流れ星が願いを叶えてくれた』とか言ってたけど……その話をもっと詳しく教えて。ずっとこのままの姿なのか、何か戻る条件があるのかとか」
(このままじゃ、いろいろ困るよね……)
ミーくんをひとりでどこかに行かせるわけにはいかないけれど、彼がいたら遊びに来た友だちや両親に紹介しなければいけない。別れたばかりで即新しい彼氏を作ったとは思われたくなかった。
かと言って、素直に「彼はぬいぐるみです」と説明したら、私がバイトのしすぎでおかしくなったと思われる。
それに何より――
(ほぼ初めまして状態の男性との共同生活は刺激が強すぎる!)
1年付き合った涼馬とすら同棲してなかったのに、ありえない。
心の中で七転八倒している私の気も知らず、ミーくんは視線を宙に彷徨わせた。
「んーとね……正確には、星の神様みたいな人がこの姿にしてくれたんだ」
「星の神様……?」
にわかには信じがたい話だけれど、ミーくんを前にそれを疑うのも意味のないことだ。私は続く言葉を待つ。
「あの時、ゆめがすごく悲しんでたから、なんとかしてあげたいって思ったんだ。そうしたら神様がおれの願いに気づいて叶えてくれたんだよ。……でも、この姿でいられるのは永遠じゃないみたいなんだ」
ミーくんは、口の周りについた牛乳ひげをぺろりと舐め取る。
「ゆめがまた誰かを好きになって、その人に『好き』って伝えられるようになるまで、なんだって」
(私が、また誰かを……)
――いつか、そんな日がくるのだろうか。
「……今はまだ全然想像できないや」
涼馬は初恋の相手で、初めての彼氏で……たくさんの初めてを彼と経験した。
きらきらと輝いていた日々は、今は思い出すたびに胸を刺すようだった。
「考えられなくて当たり前だよ。……ゆめがどれだけあの子のことを好きだったか、おれも知ってる。でもね、おれはいつまでもゆめが悲しんでるなんて嫌なんだ。ゆめがいつも飲んでるあったかいミルクみたいに、おれが心をぽかぽかにしてあげたい」
マグカップを置いたミーくんが、甘えるように上目遣いで私を見つめる。
「だから……今日からはおれを“かれし”にすればと思うんだ」
「えっ」
(……そういえば、さっきもそんなこと言ってたよね)
彼は、私が背もたれにしていたベッドに手をついた。まるで逃げ場を封じるように。
「おれはゆめのことだけを大事にするし、いっぱい気持ちよくしてあげる」
「な、何する気……?」
「ふふ……なんだと思う?」
ゆっくりとミーくんの顔が近付いてきて、彼の白銀の前髪が私の髪にかかる。
(こ、心の準備が……!)
思わず固く目を閉じると――首筋にちりっとした痛みを感じた。
(っ……?)
てっきりキスされると思っていたから慌ててまぶたを開けると、目の前にふわふわの髪と猫耳が見えた。
ミーくんが顔を上げ、へらりと笑う。
「えへへ。きれいについたよ、ゆめ」
「えっと……何がどういう……?」
「おれのだってわかるように、ちゃんとマーキングしとかないとね」
その言葉でやっと、首筋に赤い痕を――キスマークをつけられたのだと理解した。
「っ、どこでこんなこと覚えてきたの……!」
「ゆめのタブレットに入ってる漫画」
(っ、そういえば、ぬいぐるみの時のミーくんを抱えて読んでたっけ……ちょっとえっちなやつ!)
TL漫画が教科書なら、彼の一連の刺激的すぎる言動に納得がいった。
「そ、そんなこと正直に言わなくていいから!」
「聞かれたから答えたのに……」
ミーくんが尻尾を丸め、眉をハの字に下げる。
「大体、こんなのつけたら誰も近付いてこないでしょ!」
「……それの何がだめなの?」
ミーくんは、本当にわからないかのように首をかしげた。
私は頭に手を当てながら、さっきの彼の話を踏まえて説明する。
「何がって……私を失恋から立ち直らせるためにミーくんは人間の姿になったんじゃないの?」
「ああ……確かに星の神様はそのつもりだったかもね。でも昨日言ったでしょ、おれはゆめのことがずっと好きだったって。だから……」
へらりと笑い、ミーくんはなんでもないことのように言う。
「誰も近付かせる気ないよ。当たり前でしょ?」
私の脳裏に、カードに記された設定がよぎる。『ご主人さまだけが大好きな、マイペースな子』。
「もう一生、ゆめが変な男に傷つけられたりしないように、おれが守ってあげる」
――ご主人さまだけ。
「ゆめはずっとずーっと、おれだけに愛されてればいいんだよ」
――私だけ。
(……ミーくんって、もしかしてちょっとヤバい猫ちゃんなんじゃ……)
ブラウンの瞳に危うい光を宿して、彼は私に微笑みかける。
「あらためて“かれし”としてよろしくね、ゆめ♡」
「お、お断りします!」
「まあまあ、そう言わずに~」
異様に大きな愛情に包まれるかのように、ミーくんの両腕に閉じ込められる。
(……そういえば、キスマークつけられたのって初めてだ)
この胸のドキドキはときめきなのか――それとも不安からなのか。
頬ずりしてくる彼に、されるがままでいる私だった。
「うっ……うう、ひどすぎる……っ」
私、小鳥遊 夢芽は、大学まで6駅の1DKに帰ってくるなりベッドに突っ伏し、怨念を放っていた。
「私が! 誰のために! 頑張ってたと思ってるんだぁ~~~~!」
枕を濡らしながらマットレスをタコ殴りにし、バタ足で散々蹴って疲れ果てると、そばに置いている猫のぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた。
この子は『ミルク』。私がつけた名前だ。
白いふわふわの毛並みに、明るいブラウンのプラスチックボタンの目が可愛い30センチほどのぬいぐるみ。
小学生の頃に買ってもらって以来の長い付き合いのミルクに、私は訴えた。
「涼馬がスマートウォッチ欲しいって言ってたからさぁ……ぐすっ、サプライズで誕生日にプレゼントしようと思って、シフト増やして頑張ってたのにぃ……」
鼻をすすり、怒りをぶつけるようにミルクのお腹をもみくちゃにする。
「その間に浮気するって、ありえなくない!?」
どうやら相手は隣のゼミの女の子らしい。
今日のバイト帰り、ふたりが手を繋いで歩いているところに鉢合わせし――そのままフラれてしまったのだ。
泣いて泣いて、ひたすら泣いて。何時間経ったかわからなくなった頃。
「はぁ……」
ラグを敷いたサイドテーブルの前で膝を抱えて座り、電子レンジでチンした牛乳をひとくち飲む。
少し落ち着いた私は、隣に座らせたふわふわの相棒を見てぽつりとつぶやいた。
「もしミルクが彼氏だったら、私だけを愛して大事にしてくれるのかな……」
このシリーズのぬいぐるみには、それぞれ『設定』がある。
たとえば、オレンジのくまは『お外で遊ぶのが大好きな元気っ子』、ピンクのうさぎは『可愛いものに目がない甘えん坊』のように。
ミルクこと、この白い猫のぬいぐるみについてきた設定カードには『ご主人さまだけが大好きな、マイペースボーイ』と書かれていたのだ。
ご主人さまだけ――私だけ。
再びベッドに寝転がり、お腹の上でミルクをだっこしながらぽつりと呟く。
「あーあ……ミルクみたいな彼氏がいたらいいのに」
ふと目をやったカーテンの隙間から見えた夜空に、光の筋が走ったのが見えた。
「あ、流れ星」
その瞬間、ずしりと身体の上に重みを感じて視線を自分のお腹に移すと――
(……へっ?)
白みがかった銀色の髪にブラウンの瞳を持つ、同い年くらいの男の人が私に覆いかぶさっていた。
「ギャーッ!!」と叫ぼうとした口元は、「ギ」と発声した時点でその人に塞がれてしまう。
「落ち着いて、ゆめ。おれはミルクだよ」
「ほふははほは……!」
「あ、ごめん。いつまでも口を塞いでたらしゃべれないよね」
大きくてあたたかな手のひらが離れていくと、私は改めて言った。
「そんな馬鹿な……!」
「ゆめの気持ちはわかるけど、ほんとうだよ。おれは昔からずっとゆめが好きで、“かれし”になりたいと思ってた。おれたちが同じ気持ちになったから、流れ星が願いを叶えてくれたんだ」
(説明を聞いても『そんな馬鹿な』って感想は変わらないけど……)
彼の頭の両脇からはふわふわの耳が、そしておしりからは気まぐれに揺れる尻尾が生えている。
それ以外は人間と同じように見えるけれど、その耳と尻尾はとても作り物には見えない。
(それに、状況的にミルクしか考えられない……よね?)
抱きしめていたぬいぐるみはどこかへ消えてしまっているし、毛や瞳の色がとても似ている。
いや、待って。というか――
「なんで裸!?」
「だって、ぬいぐるみの頃のおれは服を着てなかったでしょ?」
覆いかぶさられているせいで、細身だけどほどよく筋肉のついた胸板が嫌でも視界に入ってしまう。
(……胸板どころか、その下まで!)
「め、目のやり場に困るから早く隠して! ほら、この毛布とかで!」
ベッドの脇でくちゃくちゃになっていた毛布を掴み、顔を背けながら彼に突き出した右手をきゅっと握られる。
そして、そのままシーツの上に縫い止められた。
「ねえ、ゆめ。つらいことは、おれがぜーんぶ忘れさせてあげる」
「え……」
「だから、おれにまかせて……?」
顎にそっと手を添えられて、彼の方を向かされる。
キャラメルみたいに甘いブラウンの瞳と間近で視線が交わると、鼓動が勝手に速くなった。
ミルクの顔がゆっくり近付いてきて……
「えっ、えっ……!?」
(まさか、このままキスする気!?)
どうにかしなければと頭をフル回転させた私は――
――掴まれていない方の手で、彼の顎の下を優しく撫でた。
「ふにゃ~~、ゴロゴロゴロ……」
「隙あり!」
ミルクの手の力が緩んだ隙に、ベッドから転がり落ちるように抜け出した。
「はっ……! おれとしたことが」
必死に這いつくばった私は肩で息をしていたけれど、なぜか勝ち誇ったように笑いながらこう言った。
「はっはっは……! いくらぬいぐるみでも、DNAに刻まれた設定には抗えないみたいだね!」
カードには『ご主人さまだけが大好きな、マイペースボーイ』という設定だけでなく、猫らしく『顎の下を撫でられるのも大好き』と書かれていたことを思い出したのだ。
(……ぬいぐるみにDNAがあるのか謎だけど!)
私の言葉にきょとんと目を瞬かせていたミルクは、力の抜けた顔で笑う。
「よくわからないけど……よかった。ゆめが笑えるようになって」
「……!」
不本意ながら、その言葉と笑顔にキュンとしてしまった。
……きっとこれは、落ち込んでいる私に神様が見せてくれた一夜の夢だ。
(失恋女の元にイケメンニャンコが来るなんて、漫画みたいな展開だし)
きっと、明日になったらミルクはぬいぐるみに戻って――
――いなかった。
「おはよう、ゆめ」
カーテンの隙間から朝日が差し込む中、毛布にくるまった裸のミルクとベッドの中で目が合う。
(……なんで?)
そして、私を抱きしめたまま彼はへらりと笑った。
「今日からは、おれを“かれし”にしてくれる?」
「はぁ……!?」
***
いつまでも裸では困るので、ひとまず私のオーバーサイズのパーカーを着させてブランケットで下半身を隠してもらい、なんとか落ち着いて話ができる姿になった。
ベッドの横に置いているサイドテーブルの前に彼を座らせ、マグカップを手渡す。
「わあ……ゆめがいつも飲んでるあったかい牛乳だ」
ちなみに、人型の彼をミルクと呼ぶのは少し違和感があったので、ふたりで話し合い、仮で『ミーくん』と呼ぶことに決めた。
「ミーくん」
「なぁに? ゆめ」
微笑みながら湯気の立つ白い水面にふーふー息を吹きかけている彼に、私は真剣ですと伝えるようにぐっと身を乗り出して尋ねた。
「昨日『流れ星が願いを叶えてくれた』とか言ってたけど……その話をもっと詳しく教えて。ずっとこのままの姿なのか、何か戻る条件があるのかとか」
(このままじゃ、いろいろ困るよね……)
ミーくんをひとりでどこかに行かせるわけにはいかないけれど、彼がいたら遊びに来た友だちや両親に紹介しなければいけない。別れたばかりで即新しい彼氏を作ったとは思われたくなかった。
かと言って、素直に「彼はぬいぐるみです」と説明したら、私がバイトのしすぎでおかしくなったと思われる。
それに何より――
(ほぼ初めまして状態の男性との共同生活は刺激が強すぎる!)
1年付き合った涼馬とすら同棲してなかったのに、ありえない。
心の中で七転八倒している私の気も知らず、ミーくんは視線を宙に彷徨わせた。
「んーとね……正確には、星の神様みたいな人がこの姿にしてくれたんだ」
「星の神様……?」
にわかには信じがたい話だけれど、ミーくんを前にそれを疑うのも意味のないことだ。私は続く言葉を待つ。
「あの時、ゆめがすごく悲しんでたから、なんとかしてあげたいって思ったんだ。そうしたら神様がおれの願いに気づいて叶えてくれたんだよ。……でも、この姿でいられるのは永遠じゃないみたいなんだ」
ミーくんは、口の周りについた牛乳ひげをぺろりと舐め取る。
「ゆめがまた誰かを好きになって、その人に『好き』って伝えられるようになるまで、なんだって」
(私が、また誰かを……)
――いつか、そんな日がくるのだろうか。
「……今はまだ全然想像できないや」
涼馬は初恋の相手で、初めての彼氏で……たくさんの初めてを彼と経験した。
きらきらと輝いていた日々は、今は思い出すたびに胸を刺すようだった。
「考えられなくて当たり前だよ。……ゆめがどれだけあの子のことを好きだったか、おれも知ってる。でもね、おれはいつまでもゆめが悲しんでるなんて嫌なんだ。ゆめがいつも飲んでるあったかいミルクみたいに、おれが心をぽかぽかにしてあげたい」
マグカップを置いたミーくんが、甘えるように上目遣いで私を見つめる。
「だから……今日からはおれを“かれし”にすればと思うんだ」
「えっ」
(……そういえば、さっきもそんなこと言ってたよね)
彼は、私が背もたれにしていたベッドに手をついた。まるで逃げ場を封じるように。
「おれはゆめのことだけを大事にするし、いっぱい気持ちよくしてあげる」
「な、何する気……?」
「ふふ……なんだと思う?」
ゆっくりとミーくんの顔が近付いてきて、彼の白銀の前髪が私の髪にかかる。
(こ、心の準備が……!)
思わず固く目を閉じると――首筋にちりっとした痛みを感じた。
(っ……?)
てっきりキスされると思っていたから慌ててまぶたを開けると、目の前にふわふわの髪と猫耳が見えた。
ミーくんが顔を上げ、へらりと笑う。
「えへへ。きれいについたよ、ゆめ」
「えっと……何がどういう……?」
「おれのだってわかるように、ちゃんとマーキングしとかないとね」
その言葉でやっと、首筋に赤い痕を――キスマークをつけられたのだと理解した。
「っ、どこでこんなこと覚えてきたの……!」
「ゆめのタブレットに入ってる漫画」
(っ、そういえば、ぬいぐるみの時のミーくんを抱えて読んでたっけ……ちょっとえっちなやつ!)
TL漫画が教科書なら、彼の一連の刺激的すぎる言動に納得がいった。
「そ、そんなこと正直に言わなくていいから!」
「聞かれたから答えたのに……」
ミーくんが尻尾を丸め、眉をハの字に下げる。
「大体、こんなのつけたら誰も近付いてこないでしょ!」
「……それの何がだめなの?」
ミーくんは、本当にわからないかのように首をかしげた。
私は頭に手を当てながら、さっきの彼の話を踏まえて説明する。
「何がって……私を失恋から立ち直らせるためにミーくんは人間の姿になったんじゃないの?」
「ああ……確かに星の神様はそのつもりだったかもね。でも昨日言ったでしょ、おれはゆめのことがずっと好きだったって。だから……」
へらりと笑い、ミーくんはなんでもないことのように言う。
「誰も近付かせる気ないよ。当たり前でしょ?」
私の脳裏に、カードに記された設定がよぎる。『ご主人さまだけが大好きな、マイペースな子』。
「もう一生、ゆめが変な男に傷つけられたりしないように、おれが守ってあげる」
――ご主人さまだけ。
「ゆめはずっとずーっと、おれだけに愛されてればいいんだよ」
――私だけ。
(……ミーくんって、もしかしてちょっとヤバい猫ちゃんなんじゃ……)
ブラウンの瞳に危うい光を宿して、彼は私に微笑みかける。
「あらためて“かれし”としてよろしくね、ゆめ♡」
「お、お断りします!」
「まあまあ、そう言わずに~」
異様に大きな愛情に包まれるかのように、ミーくんの両腕に閉じ込められる。
(……そういえば、キスマークつけられたのって初めてだ)
この胸のドキドキはときめきなのか――それとも不安からなのか。
頬ずりしてくる彼に、されるがままでいる私だった。