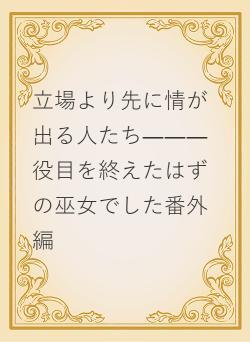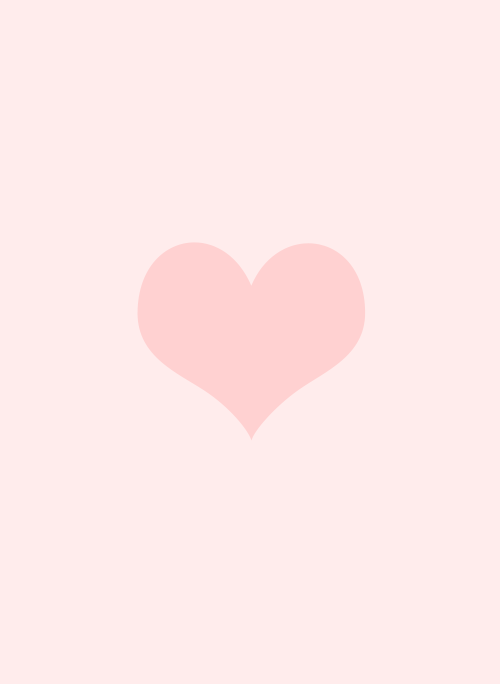静かな異常―――役目を終えたはずの巫女でした番外編
静かな異常―――役目を終えたはずの巫女でした番外編
■特別師団長ヴァルター視点
最初に違和感を覚えたのは、数字だった。
報告書の件数が増えたわけではない。
処理が滞っているわけでもない。
判断は速く、配置も的確で、指示に無駄はなかった。
だから、異常はない。
少なくとも、表向きには。
だが、クロトは仕事に没頭しすぎていた。
本来なら部下に回せる案件を、自分で引き取っている。
前に出る必要のない局面でも、判断を先取りする。
責任感の範疇に収まってはいるが、判断と判断のあいだに余白がない。
呼吸を挟まずに、次へ進んでいる。
そういう印象だった。
そして、もうひとつ。
クロトの魔力が、揺れている。
常にではない。
一瞬だけ、ほんのわずかに。
数値には出ず、記録にも残らない程度の揺らぎ。
長く見ていなければ、気づかない。
気づいたとしても、証明はできない。
それでも、ヴァルターには分かった。
――これは、平常ではない。
取り乱してはいない。
感情を表に出すこともない。
命令違反も、判断ミスもない。
だが、耐えている。
そういう状態だった。
止めるべきか。
配置を変えるべきか。
一度、明確に線を引くべきか。
選択肢はいくつも浮かぶ。
だが、そのどれもが最善ではないことを、ヴァルターは理解していた。
クロトは止まらない。
止めれば、別の形で前に出る。
それを、彼自身が一番よく分かっている。
だから、見るしかない。
越えてはいけない線を、踏み越えないかどうか。
原因については、考える必要もなかった。
巫女の交代が起きた。
それ以上を、彼が口にすることはないだろうと、ヴァルターは理解していた。
クロトは、その事実について語らなかった。
説明も、感想も、ない。
だが、仕事の密度だけが増していく。
それが、答えだった。
若い巫女は、まだ力の制御が安定していなかった。
制度として任せきるには、早すぎた。
その結果として、サクラが再び呼び戻された。
報告は簡潔だった。
再召喚。
本人は無事。
クロトの態度は、外から見れば何も変わらない。
表情も、口調も、距離も。
敬語のまま、線は保たれている。
だが、その日の終わり、ヴァルターは気づいた。
魔力が、揺れていない。
あれほど微細だった揺らぎが、完全に消えている。
仕事量は変わらない。
だが、判断に余裕が戻っている。
――呼吸を、している。
そう理解した瞬間、ヴァルターの中で張りつめていたものが、静かにほどけた。
それからのクロトは、少しだけ変わった。
部下への接し方は変わらない。
無理をさせず、危険を前に出さない。
問題は、サクラに関する配置だった。
即応距離が短い。
危険度が低い事案でも、最悪想定を切らない。
起こりうる可能性を、すべて拾っている。
表向きの理由は、すべて正しい。
巫女の安全。
結界への即応。
国家としての合理性。
だが、理由が多すぎる。
これは、通常運用ではない。
明確な例外だった。
過保護だが、制御されている。
踏み越えてはいない。
だから、止めない。
これは反動だ。
失ったあと、戻ってきた。
――もう、失いたくない。
その一念が、判断を前に押し出している。
私情と呼ぶには、あまりに静かで。
任務と呼ぶには、あまりに個別だった。
それでも、破綻はしていない。
ヴァルターは、書類を閉じる。
この状態は、危うい。
だが同時に――
彼が壊れずにいられる状態でもある。
可能であれば。
本当に、可能であれば。
彼女が、この世界を選ぶ未来を、
最初から否定する判断だけは、下したくなかった。
それが願いだと、
自覚することはない。
最初に違和感を覚えたのは、数字だった。
報告書の件数が増えたわけではない。
処理が滞っているわけでもない。
判断は速く、配置も的確で、指示に無駄はなかった。
だから、異常はない。
少なくとも、表向きには。
だが、クロトは仕事に没頭しすぎていた。
本来なら部下に回せる案件を、自分で引き取っている。
前に出る必要のない局面でも、判断を先取りする。
責任感の範疇に収まってはいるが、判断と判断のあいだに余白がない。
呼吸を挟まずに、次へ進んでいる。
そういう印象だった。
そして、もうひとつ。
クロトの魔力が、揺れている。
常にではない。
一瞬だけ、ほんのわずかに。
数値には出ず、記録にも残らない程度の揺らぎ。
長く見ていなければ、気づかない。
気づいたとしても、証明はできない。
それでも、ヴァルターには分かった。
――これは、平常ではない。
取り乱してはいない。
感情を表に出すこともない。
命令違反も、判断ミスもない。
だが、耐えている。
そういう状態だった。
止めるべきか。
配置を変えるべきか。
一度、明確に線を引くべきか。
選択肢はいくつも浮かぶ。
だが、そのどれもが最善ではないことを、ヴァルターは理解していた。
クロトは止まらない。
止めれば、別の形で前に出る。
それを、彼自身が一番よく分かっている。
だから、見るしかない。
越えてはいけない線を、踏み越えないかどうか。
原因については、考える必要もなかった。
巫女の交代が起きた。
それ以上を、彼が口にすることはないだろうと、ヴァルターは理解していた。
クロトは、その事実について語らなかった。
説明も、感想も、ない。
だが、仕事の密度だけが増していく。
それが、答えだった。
若い巫女は、まだ力の制御が安定していなかった。
制度として任せきるには、早すぎた。
その結果として、サクラが再び呼び戻された。
報告は簡潔だった。
再召喚。
本人は無事。
クロトの態度は、外から見れば何も変わらない。
表情も、口調も、距離も。
敬語のまま、線は保たれている。
だが、その日の終わり、ヴァルターは気づいた。
魔力が、揺れていない。
あれほど微細だった揺らぎが、完全に消えている。
仕事量は変わらない。
だが、判断に余裕が戻っている。
――呼吸を、している。
そう理解した瞬間、ヴァルターの中で張りつめていたものが、静かにほどけた。
それからのクロトは、少しだけ変わった。
部下への接し方は変わらない。
無理をさせず、危険を前に出さない。
問題は、サクラに関する配置だった。
即応距離が短い。
危険度が低い事案でも、最悪想定を切らない。
起こりうる可能性を、すべて拾っている。
表向きの理由は、すべて正しい。
巫女の安全。
結界への即応。
国家としての合理性。
だが、理由が多すぎる。
これは、通常運用ではない。
明確な例外だった。
過保護だが、制御されている。
踏み越えてはいない。
だから、止めない。
これは反動だ。
失ったあと、戻ってきた。
――もう、失いたくない。
その一念が、判断を前に押し出している。
私情と呼ぶには、あまりに静かで。
任務と呼ぶには、あまりに個別だった。
それでも、破綻はしていない。
ヴァルターは、書類を閉じる。
この状態は、危うい。
だが同時に――
彼が壊れずにいられる状態でもある。
可能であれば。
本当に、可能であれば。
彼女が、この世界を選ぶ未来を、
最初から否定する判断だけは、下したくなかった。
それが願いだと、
自覚することはない。