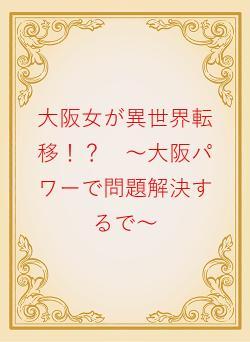スィーツしか見てなかったら天才イケメンパティシエに愛された
第一話 フィナンシェ
今日、職場でミスの犯人にさせられた。
理不尽すぎるが、ミスを被せてきた人間は社長の親族。平社員の灯里に抗う術はなかった。
「リカバリーできたし顔色が悪いから、今日はもう帰りなさい」と上司に気を使われ、まだ夕方なのに灯里は職場を出た。
下を向いたまま会社を出て電車に乗って最寄駅で降りて、灰色の地面を見つめながらトボトボと歩き出す。
(もうやだ、消えたい……)
込み上げる涙を抑えようと、ぎゅっと目を瞑る灯里。その時、風が強く吹いた。
「……ん?」
ふわり。
焼き菓子の甘く香ばしい匂いが灯里の鼻をかすめる。
どうやら香りの元は、駅の反対側らしい。
(そういえば、今日はミスのカバーで忙しくて昼ごはん食べてなかったな……)
甘い香りに刺激されたのか、急に空腹を感じた灯里は、匂いを辿って普段通らない道を歩き出した。
公園の脇にある寂れた細道を抜けると、そこはーー
「わ……ぁ……」
色とりどりの花達が咲き乱れるイングリッシュガーデンだった。
灯里が入った箇所以外は、ぐるりと高い生垣に囲まれていて外からは見えない。
まるで、子供の頃に読んだ本に出てきそうな秘密の庭。
その中央には、アンティーク調の白いテーブルと椅子のセットが置いてある。
(え、もしかして人様のおうちの庭に入っちゃった!?)
急いで庭から出ようと灯里は忍び足で踵を返す。
「あら、いらっしゃいませ。こちらのお席にどうぞ」
背後から落ち着いた女性の声が聞こえ、振り返る。
柔らかそうな銀髪を後ろでまとめた、薄紫色のワンピースの上に白いエプロンをした緑色の目の中年女性が、柔らかく微笑んでいる。
どうやらここは民家の庭ではなく、カフェのテラス席だとわかり、灯里はホッと安堵の息をした。
「は、はい」
促されて白い椅子に腰かける。
「あっあの、駅で美味しそうな香りがして辿ったら、ここに……」
灯里の言葉に女性は目を細めて微笑む。
「今日は風が強いものね。フィナンシェの香りかしら」
そう言いながら店内に入った女性は、手にバスケットを持って灯里のテーブルに戻って来た。
バターの匂いが濃くなる。
「あっそうです!」
女性が持つバスケットの中には長方形の焼き菓子ーーフィナンシェがどっさり入っている。
「二つください!」
自然と口が動いた。
「飲み物はロイヤルミルクティーがおすすめよ」
「ではそれをお願いします」
女性は頷き、店内の厨房に入っていった。
ほどなくして灯里のテーブルに戻って来た女性は、手に持ったトレイから皿とティーセットを並べる。
(本当に美味しそう!ああ、やっと食べられる……!)
灯里はもうフィナンシェを食べることしか頭になかった。
焼きたてのフィナンシェが二つ乗った皿の前で手を合わせた後、フィナンシェにかぶりつく。
表面はカリッと香ばしく、噛み締めるとバターがじゅわりと口の中いっぱいに広がった。それから優しい甘み。
咀嚼して飲み込んで、あたたかいロイヤルミルクティーを流し込む。
「なんて幸せな味……」
灯里が漏らした独り言に女性は少し目を見開いたが、食べることに没頭中の灯里は気付かない。
あっという間にフィナンシェを食べ、ミルクティーを飲み干して、ティーカップを静かに置く。
(よし、明日も仕事がんばろう)
お腹だけじゃなくて心も満たされて、灯里は駅に降り立った時と違って前向きになっていた。
立ち上がり、会計をするため女性に声をかける。レシートを持って来たので、テーブルで支払いをした。
「……私、今日仕事でミスを被せられて落ち込んでたんです。でも、フィナンシェのおかげで幸せな気持ちになれて……明日も頑張ろうって思えました」
灯里は一気に言って、ありがとうございましたと女性に頭を下げた。
「パティシエにも伝えておくわね」
顔を上げると、柔らかく微笑む女性と目が合った。
「はい!また来ます!」
*****
「あんたの口癖と同じことを言ったから、びっくりしちゃった。伝わってよかったわねぇ」
女性が話しかけた先は厨房。
白いコックコートを着た緑色の目の黒髪美男子は、オーブンを見つめながら小さく頷いた。
「ああいう人ばかりなら、俺も……」
続く
理不尽すぎるが、ミスを被せてきた人間は社長の親族。平社員の灯里に抗う術はなかった。
「リカバリーできたし顔色が悪いから、今日はもう帰りなさい」と上司に気を使われ、まだ夕方なのに灯里は職場を出た。
下を向いたまま会社を出て電車に乗って最寄駅で降りて、灰色の地面を見つめながらトボトボと歩き出す。
(もうやだ、消えたい……)
込み上げる涙を抑えようと、ぎゅっと目を瞑る灯里。その時、風が強く吹いた。
「……ん?」
ふわり。
焼き菓子の甘く香ばしい匂いが灯里の鼻をかすめる。
どうやら香りの元は、駅の反対側らしい。
(そういえば、今日はミスのカバーで忙しくて昼ごはん食べてなかったな……)
甘い香りに刺激されたのか、急に空腹を感じた灯里は、匂いを辿って普段通らない道を歩き出した。
公園の脇にある寂れた細道を抜けると、そこはーー
「わ……ぁ……」
色とりどりの花達が咲き乱れるイングリッシュガーデンだった。
灯里が入った箇所以外は、ぐるりと高い生垣に囲まれていて外からは見えない。
まるで、子供の頃に読んだ本に出てきそうな秘密の庭。
その中央には、アンティーク調の白いテーブルと椅子のセットが置いてある。
(え、もしかして人様のおうちの庭に入っちゃった!?)
急いで庭から出ようと灯里は忍び足で踵を返す。
「あら、いらっしゃいませ。こちらのお席にどうぞ」
背後から落ち着いた女性の声が聞こえ、振り返る。
柔らかそうな銀髪を後ろでまとめた、薄紫色のワンピースの上に白いエプロンをした緑色の目の中年女性が、柔らかく微笑んでいる。
どうやらここは民家の庭ではなく、カフェのテラス席だとわかり、灯里はホッと安堵の息をした。
「は、はい」
促されて白い椅子に腰かける。
「あっあの、駅で美味しそうな香りがして辿ったら、ここに……」
灯里の言葉に女性は目を細めて微笑む。
「今日は風が強いものね。フィナンシェの香りかしら」
そう言いながら店内に入った女性は、手にバスケットを持って灯里のテーブルに戻って来た。
バターの匂いが濃くなる。
「あっそうです!」
女性が持つバスケットの中には長方形の焼き菓子ーーフィナンシェがどっさり入っている。
「二つください!」
自然と口が動いた。
「飲み物はロイヤルミルクティーがおすすめよ」
「ではそれをお願いします」
女性は頷き、店内の厨房に入っていった。
ほどなくして灯里のテーブルに戻って来た女性は、手に持ったトレイから皿とティーセットを並べる。
(本当に美味しそう!ああ、やっと食べられる……!)
灯里はもうフィナンシェを食べることしか頭になかった。
焼きたてのフィナンシェが二つ乗った皿の前で手を合わせた後、フィナンシェにかぶりつく。
表面はカリッと香ばしく、噛み締めるとバターがじゅわりと口の中いっぱいに広がった。それから優しい甘み。
咀嚼して飲み込んで、あたたかいロイヤルミルクティーを流し込む。
「なんて幸せな味……」
灯里が漏らした独り言に女性は少し目を見開いたが、食べることに没頭中の灯里は気付かない。
あっという間にフィナンシェを食べ、ミルクティーを飲み干して、ティーカップを静かに置く。
(よし、明日も仕事がんばろう)
お腹だけじゃなくて心も満たされて、灯里は駅に降り立った時と違って前向きになっていた。
立ち上がり、会計をするため女性に声をかける。レシートを持って来たので、テーブルで支払いをした。
「……私、今日仕事でミスを被せられて落ち込んでたんです。でも、フィナンシェのおかげで幸せな気持ちになれて……明日も頑張ろうって思えました」
灯里は一気に言って、ありがとうございましたと女性に頭を下げた。
「パティシエにも伝えておくわね」
顔を上げると、柔らかく微笑む女性と目が合った。
「はい!また来ます!」
*****
「あんたの口癖と同じことを言ったから、びっくりしちゃった。伝わってよかったわねぇ」
女性が話しかけた先は厨房。
白いコックコートを着た緑色の目の黒髪美男子は、オーブンを見つめながら小さく頷いた。
「ああいう人ばかりなら、俺も……」
続く