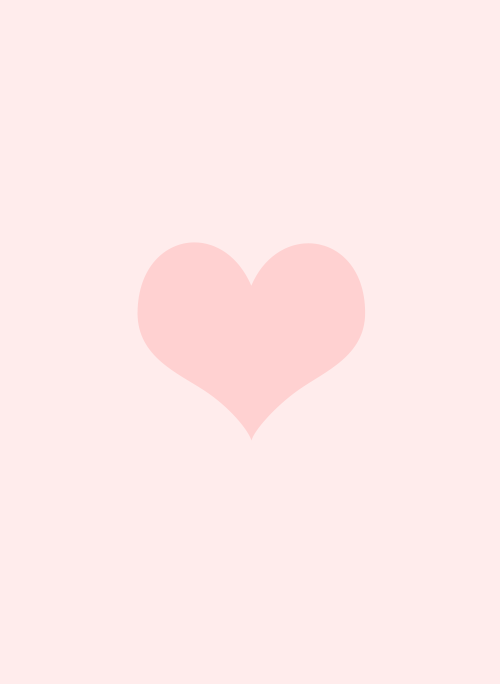気付いてよ
「はぁ~疲れたっっ!!校長の話ってなんであんなに長いんだろ。」
教室への帰り道、真那が言った。
「ホントにね。あれは辛いよね。」
本当に辛いのはこれからだと思ってしまう、女々しい自分に気付かないふりをして相槌を打った。
「ねぇ。奏?」
「ん?」
「これからどーすんの?」
「なにが?」
少しトーンを低くした真那が私に尋ねる。
なにが?そんなことを言ったところで誤魔化せないことは分かり切っているのに、逃げたい気持ちが悪あがきをする。
「なにが?じゃないでしょーが。」
「うん。分かってるんだけど。…もう諦める。」
「まぁ、奏がいいならそれでいいけどね。」
「違うよ。諦めるのを諦めるの。」
そう。もう決めた。
好きでいるだけなら迷惑は掛からないはずだから。
「…そっ…か。うん。そうだね!よく言った!」
そう言って私の髪の毛をわしゃわしゃ撫でる真那。
ホント、いつも助けてもらってるなぁ。
言葉にしたら、すごく腑に落ちた感覚に襲われた。
すぐに諦めきれるような半端な気持ちじゃない。
だって、この気持ちは朋にだって、どうにも出来ないんだから。