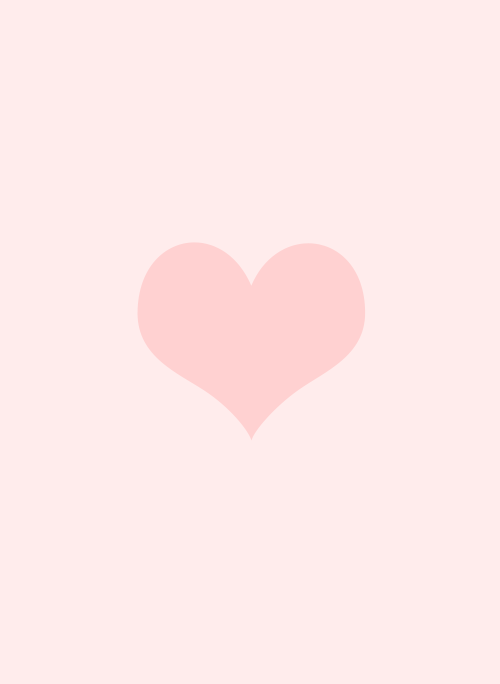無愛想なCinderella
乱れた吐息でそう呟いた彼は、私を抱き抱えるとベッドに移動させた。
「―――千尋さん?」
「キスだけでいいから。お願い、許して…」
………それからどのくらいそうしていたのか。
私は途中から意識を手放してしまっていて、夢と現実の区別もつかなかった。
テーブルの上にはいつの間にか上から箱で覆われたケーキと、開けっ放しの小さな箱。
その小さな箱から出されたモノは、私の指で輝いていた。
「―――愛してるよ、菜月」
そっと囁かれた愛の言葉が、指輪に光った。
【Fin】