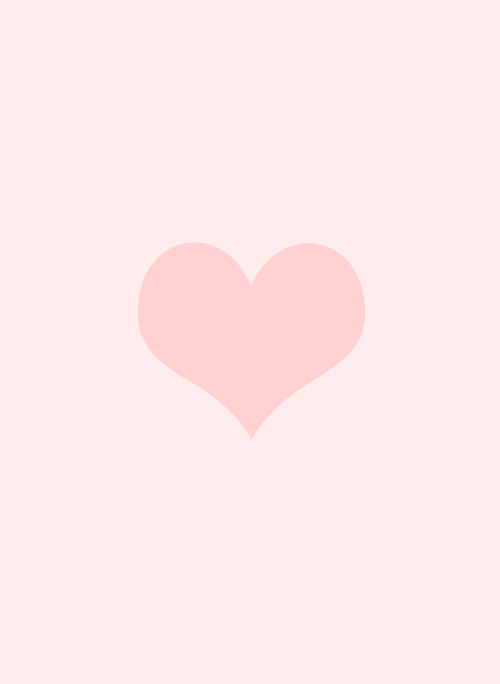KISS
その一言だけで、ひどく安心できたんだ。
「静さんみたいに、魔法の一言が言えたらいいのにね?」
あたしには、相手を安心させられるような言葉を言うことは難しい。
深い深いため息を自分の影に落としたそのとき、墓地に敷き詰めてある砂利の音。
振り向くと、肌の色素が極端に薄くて、青い瞳の色をした女の子が立っていた。
被っている麦藁帽子からは眩しいくらいの金髪を覗かせている。
こちらを見つめたまま、ちっとも動こうとしない彼女を、あたしも見つめ返すしかなくて。
「…あなた、確か」
流暢な日本語でボソリとつぶやいたかと思うと、つかつかとこちらに歩み寄ってきた。
次の瞬間には、女の子の来ていたワンピースが目の前で翻っていて。
「えみ、でしょう!」