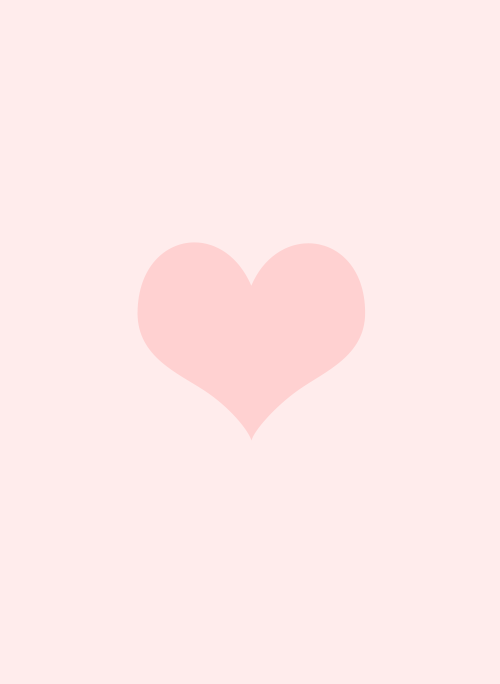副社長は溺愛御曹司
「俺、はそのままでいいと思いますよ。ですますだけ、気にしてみましょうか」
「うまくいくかな」
「語尾にひっぱられて、全体の語調も整うと思います。ついでに言わせていただきますと、ヤマトさんは、フランクすぎるんですよ」
社内でも、たいていの人には、タメ口でしょう、と指摘され、先輩が、うん、と小さく反省したような声を出す。
「感覚としては、役員朝礼の感じですね。知っている人ばかりですが、公式の発言をなさるでしょう?」
「ああ、そっか」
なるほど、とヤマト先輩が得心したように笑う。
少し身をかがめて、彼の相談を受けていた秘書さんは、にこっとつつましく微笑んで。
私も同席したほうが、よろしいですか? と先輩に尋ねた。
「うん、いて」
「かしこまりました」
失礼いたします、と私に断って、先輩からひとつ空けた下座の席に腰を下ろす。
メモをとるんだろう、ペンと手帳を用意して、もうインタビューを聞く準備を整えている彼女は、知的で、頼もしい。
私は改めて、レコーダーのスイッチを入れ、質問を開始した。
「就任された時の、正直なお気持ちは?」
「動転して、ました。実のところ、もう一期、先になるかと思っていたので」
謙虚な答えに吹き出すと、先輩も秘書さんも、楽しそうに笑う。
場がほぐれてきた。
これは、いいインタビューがとれそうだ。
「今は?」
「周囲に、助けられて。求められているていどには、なんとか務まっていると思います」
そう言って、ヤマト先輩が一瞬、優しい視線で秘書さんを見る。
秘書さんは、自分の手帳から顔を上げず、だけどその口元は、柔らかく微笑んでいた。
「なぜ、副社長になりたいと?」
こうして会ってみても、やっぱり先輩が、そんな野心家とは思えない。
ずっと気になっていたことを、ぶつけてみると。
ヤマト先輩は、ちょっと意表を突かれたように、目を見開いて。
同じタイミングで顔を上げた秘書さんと、目を見合わせると。
ちょっと、照れたような、困ったような、あの、昔とちっとも変わらない微笑みを浮かべて。
「内緒です」
恥ずかしそうに、そう言った。
Fin.