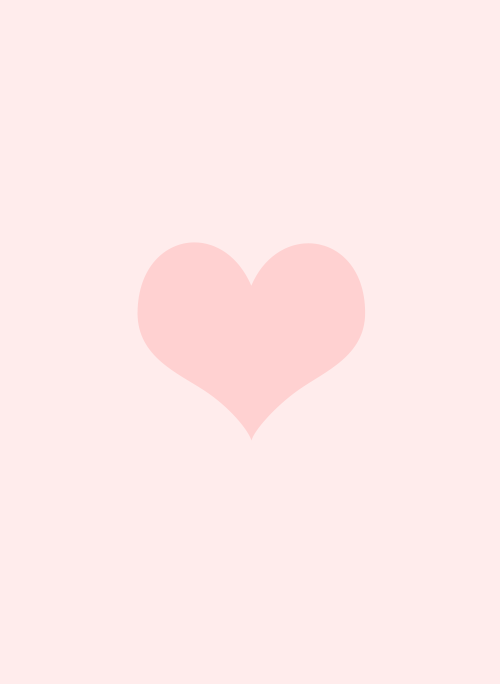甘くない現実
「分かった。もらっとくよ。」
「ごめんね、なんか、余ったのあげちゃったみたいな感じで。」
そんなことを言うなら、お前が食え、お前が。
「だったら小暮先輩にあげればいいんじゃねーの。」
「いや、だってさ。小暮先輩、4月から製菓学校通って、パティシエ目指すぐらい、お菓子上手なんだよ。」
なんだよ、それ。
「自分のヨレヨレな感じのチョコ、恥ずかしくって。」
その恥ずかしいチョコを食わされる、恥ずかしい僕にも気を配ってくれ。
「あのさ……」
「なあに?」
口から出そうになった暴言を、ごくりと飲み込んだ。
「一応さ、ありがと。」
「どういたしまして。あんまりおいしくなかったら、ごめんね。」
いや、ふわふわな君の作るものは、何より甘くて、僕を魅了し続けるんだ。
全く甘くない現実の前で、僕はいつまでもふわふわな彼女に恋している。