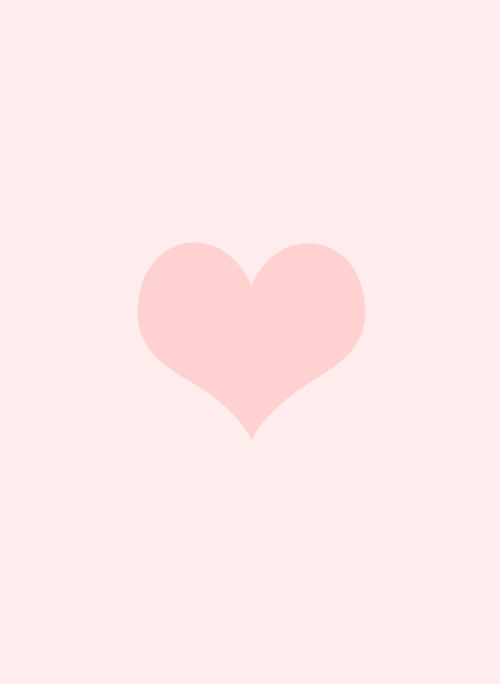幼なじみにわたしの生死がかかってる件
どんどん暗くなっていく思考を振り払うように大きく首を横に振る。
『よーし、こういうときはケーキを食べるのだ!それに限りまする。』
『全くもって正論でござる』と、ひとりで相槌を打って、階段を降りた。
冷蔵庫からケーキの箱を取り出す。
箱の中には好物のフルーツタルトがきらきらと鎮座している。
『これは我が愛しの殿様からのサプライズプレゼントなのでござる。』
にやける、にやけちまうぜ。
いつも一切れじゃ足りないフルーツタルトをホールで食べれちゃうんだぜ!?ひとりで全部食らっちゃっていいんだぜ!?
しかし、
『プレート付きの誕生日ケーキをひとりぼっちで食べるのはさすがに気が引けるのである。』
『世間の目に可哀想な子として映ってしまうのはどうかと思うのだ。』
『いや、今ここにはわたししかいないから世間の目はないのだが、やはり気が引けるのであります。』
簡単に言ってしまうと、
『これは愛しの殿が帰られたら一緒に食したいのでござる。』
というわけなのだ。
箱の中にそうっとケーキを戻して、再び冷蔵庫のど真ん中に座らせた。