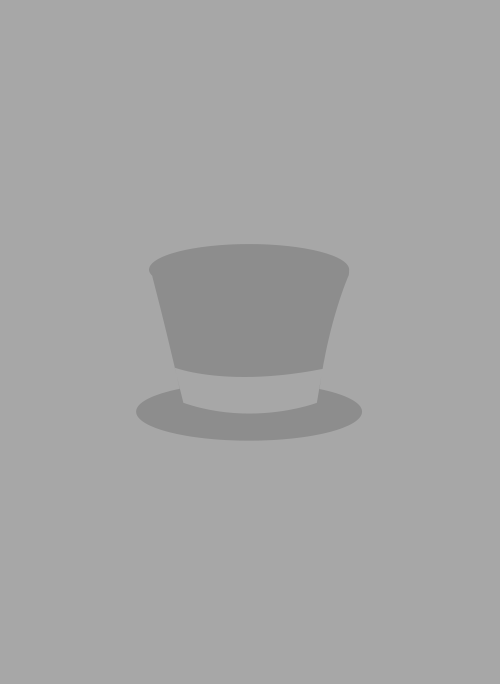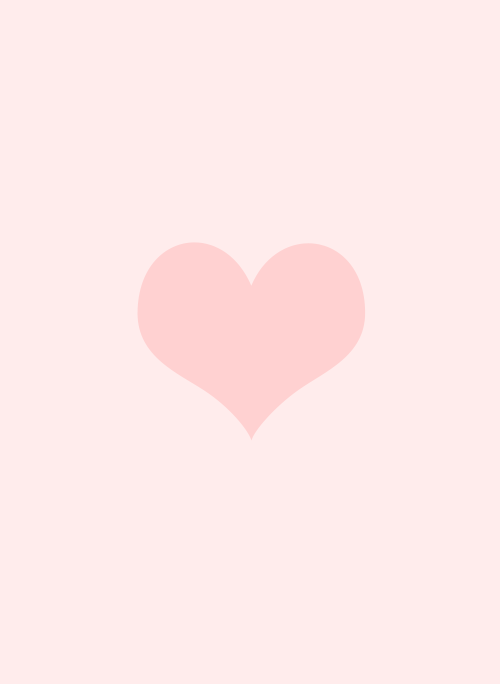ねえ、撫でて
草間さんにもっと近づきたい。誘ってほしい。寄り添いたい。
そう思いながらキッチンで水玉模様のカップに猫舌でも飲めるミルクたっぷりのカフェラテを入れていた。
私も草間さんも猫舌。ホットコーヒーは念入りにフーフーしないと飲めない。
しかもブラックは苦手。
「僕たち、似てるね」
雪が降り、運行見合わせでごった返す駅前。そこで偶然、草間さんと会い、二人でカフェへ。その時、草間さんがそう言って笑った。
草間さんの笑顔はタンポポの花束みたい。綿毛をふーっと飛ばして遊ぶような無邪気だけど複雑な私に幸せをくれる。
今日もいつもみたいに笑ってくれるかな。ちょっと期待しながら、大きめにカットしたチーズケーキとカフェラテをテーブルに置いた。
「どうぞ」
「ありがとう。いただきます」
どうしたんだろう。声のトーンがいつもより低い気がする。
何度も視線を感じて草間さんを見ると、草間さんはそっと目を逸らした。
小春さんはハート柄のブランケットの上で眠ったまま。私と違ってハート柄がよく似合う。
無言でチーズケーキを一口含んだ草間さんは、フォークを置いて小春さんを撫ではじめた。
いつも「おいしい」って微笑んでくれるのに。
きっと口に合わないんだ……。
私にもあんな風に。そう思いながら俯いた時、大きな手のひらが目の前にひろがった。そして、草間さんが私の頭を撫でた。
「髪、綺麗だなと思って。さらさらだし、いい香りがする。僕、香りに敏感なんだ。普段、消毒液の中にいるような生活だから」
私の目から無意識のうちに涙が零れ落ちた。
「ごめん。泣かないで。そうだよね、手術ばかりしてる手で触られたくないよね」
「ううん、違うの」
「えっ……」
「ずっと、こうしてほしかったの」
「じゃあ……、もっと撫でさせて」
私は紫陽花のような蒼い瞳を見つめて、素直にコクンと頷いた。
こうしてほしくてショートボブだった髪を伸ばし、ヘアパフュームをつけるようになった。
その香りと艶が私と草間さんの距離を縮めてくれた。
「ケーキ食べてくれないし、目も合わせてくれないから、嫌われたかと思った」
「ごめんね。なんだか照れちゃって。夏希ちゃんが……綺麗だから」
頬をほんのり赤く染めた草間さんが私の髪を指でクルクルしている。そして、何度も何度もやさしく頭を撫でる。
小春さんはそんな私たちを見て、大きく伸びをした後、再び目を閉じた。これから起こるであろうことを愛らしい耳で察知したかのように。
【ねえ、撫でて*END】