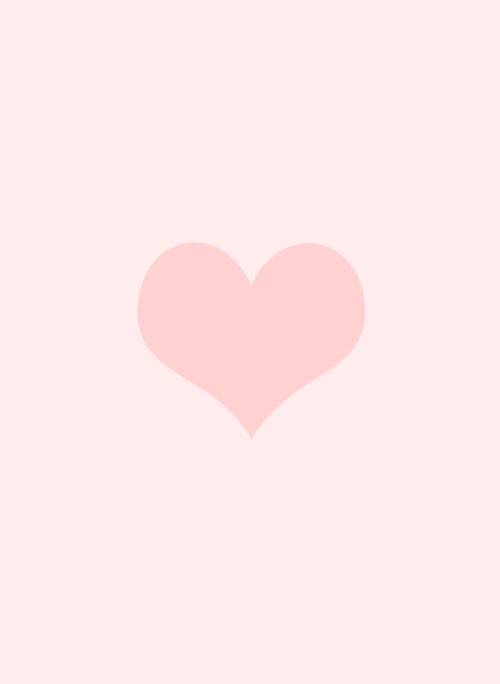血液は恋の味
しかし、その息子からの酷い仕打ちに、完全に打ちのめされてしまった。
「僕、帰るよ」
「ゆっくりしていきなさい」
「そうだけど、今の話を聞いたら二人っきりの方がいいと思って。それじゃあ、また遊びに来るよ」
そう言葉を残すと、カイルは両手を振りながら建物から出て行ってしまう。
その後姿にリディアは微笑むと、息子のささやかな優しさに感謝をした。
無論、エルドも同じであった。
「悪いことをした」
「あのように気を使うなんて、何処で覚えたのかしら」
「子供の学習能力は、意外に高いものだ」
「ええ、そうね」
カイルに気を使わせてしまったことに多少の罪悪感はあったが、今日は二人の結婚記念日。
あの当時を思い出し、愛の言葉を囁くのも、また一興。カイルもそれを望み、帰っていった。
二つのティーカップが触れ合う。
その瞬間、カツンと鈍い音が響き、静寂の中に広がっていく。
エルドの身体のことを考え、酒ではなく紅茶での乾杯。しかし、ほのかに酔いが回る。
「我儘を言うと思うが、これからも頼む」
「わかっています。貴方の妻ですもの」
「そうだな……」
リディアはエルドに微笑みかけると、再びティーカップを合わせる。それはまるで、新たに誓い合う光景でもあった。
そう、愛の誓いを――