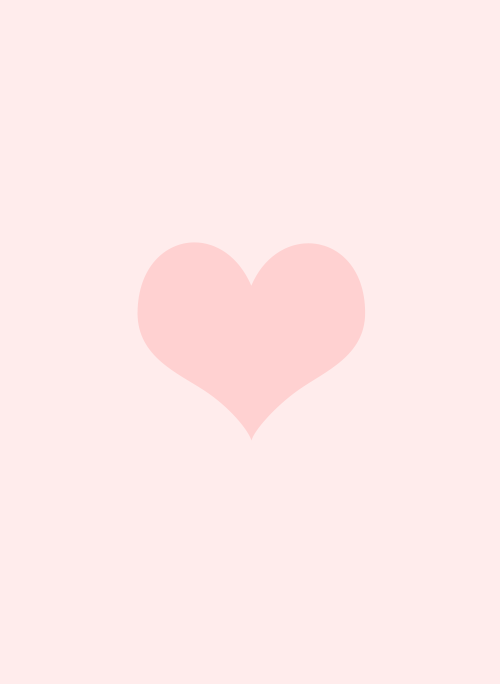この幸せをかみしめて
そんな麻里子の目の前では、敏三と喜代子は鶏肉を頬張りながら、パン屋のことをあれこれと喋り続けていた。
「麻里子のバイトが終わったころじゃ、もう、売り切れてないか?」
「そっかあ? 大丈夫だろ」
「最近はよ、となり町からも、買いに来る客がいるらしいぞ」
「そうなんかあ?」
「なんだとよ。だから普段の日でもな、夕方にはなくなってることもあるんだとよ」
「あれぇ。そっかぁ。そんなら、電話して取っといてもらうか?」
「そのほうが、いいかもなあ」
「繁盛してるんだあ。よかったなあ。小鈴さんも安心してるなあ」
二本、三本……と、きれいにしゃぶりつくされた鳥の骨が山となって、空き皿に積まれていく。
いつもながらすごい食欲だなあと、まだ一本目の鶏肉にかじり付いている麻里子は、その骨の山を呆れ半分感心半分に眺めた。
麻里子がこの家で暮らすようになって驚いたことの一つが、二人のこの食べっぷりだった。
敏三も喜代子も、とにかく、よく食べる。
肉でも魚でも辛いものでも脂っこいものでも、孫の麻里子よりも食べる。
老人とは思えない健啖ぶりだった。
そのうえ、食べながらよく喋る。
会話のない食卓に慣れていた麻里子には、それがなにより驚きだった。
「ホントになあ。ずっと、テツが心配の種だったからなあ」
「まあ、テツも最後に、少-っしは親孝行できたろぉ」
「そろそろ、三回忌かあ?」
「それはもう、済んだよぉ。テツがあそこでバン屋を始めてぇ、二年になるんだぞぉ」
「もう、そんなになったかあ。早いなあ」
「早いねえ」
聞くともなしに聞いていた敏三と喜代子の会話に、麻里子はなるほどと頷きつつ、その情報を整理して脳内メモリーにインプットしていく。
パン屋の男は通称『テツ』。
二年ほど前に、この村でパン屋を始めた。
今は、売れ切れてしまうこともあるくらい、パンは売れている。
売れているのかなどと心配していた自分に対して、麻里子は小さな苦笑を浮かべて肩を竦めた。
そんな麻里子に気づいたのか、喜代子はちらりと麻里子を見て「それにしてもなあ」と笑い出した。
「麻里子は、面白いこと言うなあ。タレ目のプータかあ。面白いなあ」
笑いながらプータ、プータと繰り返す喜代子に、もう勘弁してほしいと、麻里子はただひたすら体を小さくした。
「麻里子のバイトが終わったころじゃ、もう、売り切れてないか?」
「そっかあ? 大丈夫だろ」
「最近はよ、となり町からも、買いに来る客がいるらしいぞ」
「そうなんかあ?」
「なんだとよ。だから普段の日でもな、夕方にはなくなってることもあるんだとよ」
「あれぇ。そっかぁ。そんなら、電話して取っといてもらうか?」
「そのほうが、いいかもなあ」
「繁盛してるんだあ。よかったなあ。小鈴さんも安心してるなあ」
二本、三本……と、きれいにしゃぶりつくされた鳥の骨が山となって、空き皿に積まれていく。
いつもながらすごい食欲だなあと、まだ一本目の鶏肉にかじり付いている麻里子は、その骨の山を呆れ半分感心半分に眺めた。
麻里子がこの家で暮らすようになって驚いたことの一つが、二人のこの食べっぷりだった。
敏三も喜代子も、とにかく、よく食べる。
肉でも魚でも辛いものでも脂っこいものでも、孫の麻里子よりも食べる。
老人とは思えない健啖ぶりだった。
そのうえ、食べながらよく喋る。
会話のない食卓に慣れていた麻里子には、それがなにより驚きだった。
「ホントになあ。ずっと、テツが心配の種だったからなあ」
「まあ、テツも最後に、少-っしは親孝行できたろぉ」
「そろそろ、三回忌かあ?」
「それはもう、済んだよぉ。テツがあそこでバン屋を始めてぇ、二年になるんだぞぉ」
「もう、そんなになったかあ。早いなあ」
「早いねえ」
聞くともなしに聞いていた敏三と喜代子の会話に、麻里子はなるほどと頷きつつ、その情報を整理して脳内メモリーにインプットしていく。
パン屋の男は通称『テツ』。
二年ほど前に、この村でパン屋を始めた。
今は、売れ切れてしまうこともあるくらい、パンは売れている。
売れているのかなどと心配していた自分に対して、麻里子は小さな苦笑を浮かべて肩を竦めた。
そんな麻里子に気づいたのか、喜代子はちらりと麻里子を見て「それにしてもなあ」と笑い出した。
「麻里子は、面白いこと言うなあ。タレ目のプータかあ。面白いなあ」
笑いながらプータ、プータと繰り返す喜代子に、もう勘弁してほしいと、麻里子はただひたすら体を小さくした。