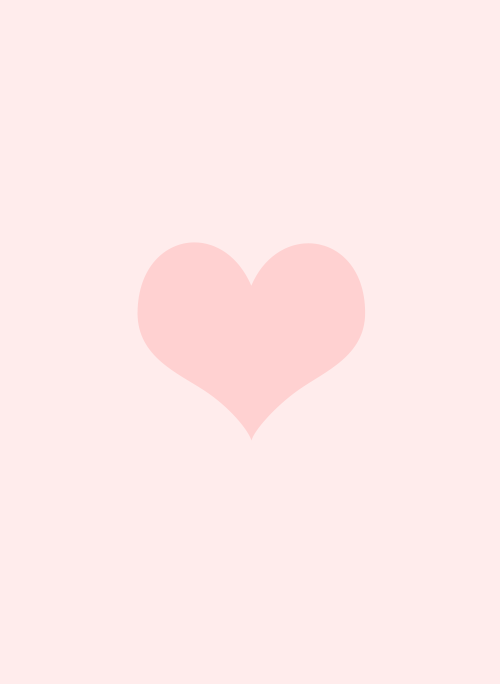いつもので。
拒んだことがお気に召さなかったらしく、きれいな顔の眉間にシワが寄った。
「真面目なやつだな」
そう言ってるときですら、彼の指先はわたしの手の甲を撫で続けてる。
それがどうにもいやらしく見えてしまうのは、彼のせいだと思いたい。
神経が手に集っていく感覚が自分じゃないみたいで少し怖い。
触れ合うのが手だけじゃなくなったとき、どうなってしまうんだろう。
「…ま、真面目というか、モラルの問題だと思います…」
「まあ、今客が来ても行かせないけど」
甲を撫でるのをやめた彼の手がわたしの手を包みこんで口元に持って行って、指先に唇が押し当てられた。
「っ」
「すずな」
まるでその声は催眠術みたいで、わたしは彼の瞳を見つめていて彼もわたしの指先にキスしながらもわたしをじっと見つめる。
「すずな」
熱くなった手が解放されて、ほっとしたのも束の間で、後頭部に手を伸ばした彼によって顔が至近距離ほどに近づいた。
「あの、ほんとに、だめです…」
抵抗らしい抵抗ができるほどの余裕なんてものはない。
どうにか口に出すけれど、あまり彼には効いていないみたい。
「キスはいいのか?」
指先で唇を撫でられてぞくぞくして、いやと言えなくて困っていると裏口のドアが開いた音がして、「すずちゃん、ただいまー」という店長ののんびりした声が店内に響いた。
「……ちょ、篤さん放してくださいっ」
小声で訴えるけど、彼にとっては友達が現れただけのことらしく気にしてない。
座ったままの篤さんと腰を屈めるわたしは、「うちの社員に手出すなって」とあっという間に店長に見つかってしまう。
「うるさい。邪魔するな」
固まったままのわたしを気にすることなく、篤さんはむしろ店長を邪魔だと言う始末。
…ここ店長のお店なのに
「すずちゃん、困ってるよ」
そうなんです。困ってるんです。この状況に。
「ああ。困ってる顔もいいよな」
会話になってませんよ。
というか困ってる顔もいいってなに?
やっぱりどS?
「すずな、よそ見するな」
「…んっ」
ぐいっと引き寄せられて、抵抗するまでもなく重なったキス。
「やっぱりお前にすずちゃん任せるんじゃなかった…」
という店長の呟きが小さくなっていく足音と共に篤さんの耳には届いていたらしい。
(仕事なんか辞めて俺の部屋に住めばいいのにという思いに気づいて欲しいけど、気づかれたくない。つーか、付き合った翌日にこれじゃ先が思いやられるな…)
End