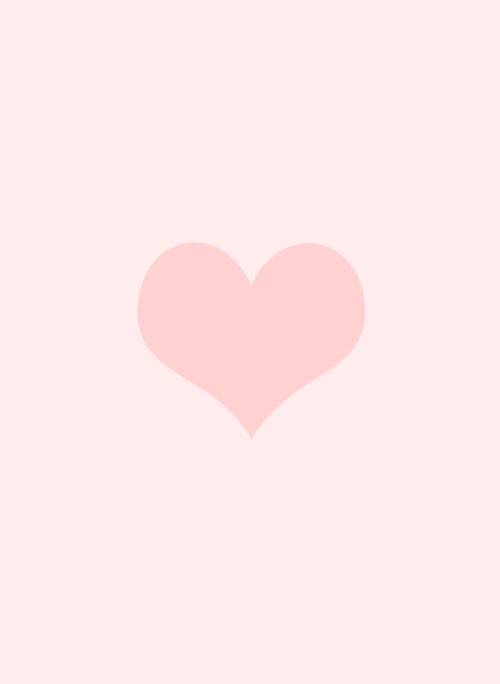現実は小説よりきなり
ああ、この上なく惨めだ。
楽しそうな家族、幸せそうな老人、無邪気な子供達。
自分だけが不幸に思えてくる。
スランプと言うのは、こんなにも辛いものだったのね。
第三者的に漠然と思った。
恋愛小説...経験した事もないのに、今まで書けてたのが奇跡だったのかも知れない。
そう思えて仕方ない。
「ああ、どうしたら良いんだろ」
空へと視線を向けた。
青い空の中を凪がれる白い雲。
私も何処かに流れてしまいたい。
「情けないなぁ、完全に現実逃避だ」
漏れたのは苦笑い。
人としてどうなの?
も、本当、やだ。
キャッ、キャッと無邪気にはしゃぐ子供の声が耳の届く。
少し早めのセミの声も。
無心になろうとしても、ここじゃダメだなぁ。
人の居ない場所なんてないよね。
ってか、一人になっても思い付く気はしないけどね。
情な...一人で笑った私は、きっと周りから見れば変な子に見えるんだろうなぁ。
「よぉ。なに変顔してんだよ」
の声も同時に頬に押さえ付けられた缶ジュースにピクッと肩を上げた。
「ヒヤァ...」
声のする方に視線を向けたら、そこには妖艶に微笑んだ琉希也君が居た。
「ククク...驚き過ぎだろ?」
なんて笑いながら私の隣へドンと座った。
いやいや、どうしてここに居るのよ?
「...る、琉希也君?ど、どうして...」
慌てて喋ったら舌が縺れた。
「落ち着いて喋れよ。たまたま歩いてるのを見掛けたんだよ」
「へっ?それでつけてきたの?」
そう言う事だよね?
見掛けたから、ついてきたって事だよね。
「おい、人をストーカー呼ばわりすんなよ」
と額を指で小突かれた。
「...ったぁ」
額を押さえて琉希也君を見れば、
「ま、これ飲めよ」
とさっき頬に当てられた缶ジュースを差し出された。
「あ、うん。ありがと」
「どういたしまして」
優しく微笑んだ琉希也君にドキッと胸が高鳴った。
な、なんだ?これ?
ドキドキするんですけど。
それを知られないように、貰った缶ジュースに視線を落としてプルタブを引き上げた。
隣でも同じ音がして、チラッと目だけを動かして見れば琉希也君は自分用の缶珈琲を手に持っていた。
「ん?こっちのが良いか?」
見てたのが見つかった。
「あ、ううん。これで良い」
開けた缶ジュースを見せてそれを口に運んだ。