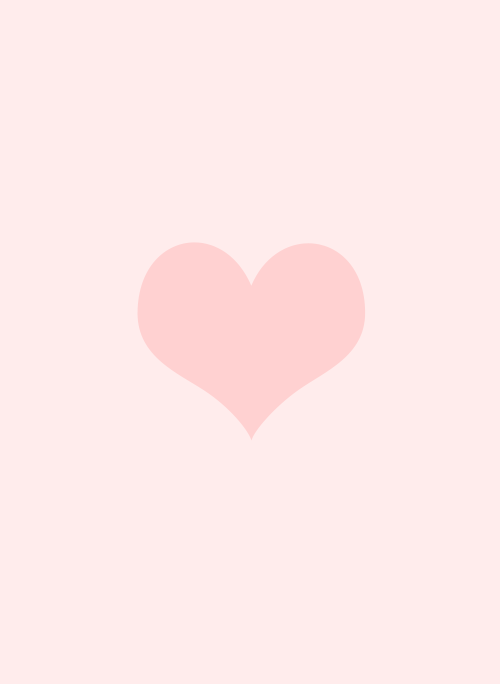あの続きは給湯室にて
背中に言葉を受けた彼は、驚いたように振り返る。
目を見開いた姿は、まさに"猫"だ。
「えっ、今!?」
「……あれ、口が勝手に。」
「こんなムードのない告白、初めてだわ……。」
「ありがとう。」
誉めてねーよ、と目をそらす彼の耳は赤く染まっている。
きっと告白なんて、数え切れないほどされているのだろうに、毎回その反応をしているのだろうか。
だとしたら、相当罪作りな男だ。
しばらく無言が続いた。けど、その沈黙を破ったのは彼だった。
「……とにかく、仕事するぞ。」
「は、はい。」
そう言い残し、私の分のカップを持ちながら給湯室を後にしようとする。
突然の告白に、若干自己嫌悪に陥りながらも彼の背中を追う。
すると、再びオフィスに足を踏み入れるその時、彼がゆっくりと振り返った。
目の縁がほんのりと赤い。なかなかレアな表情だ。
ぼうっとその表情を見つめていると、彼は少しだけムッとしたものに変わった。
そして彼はその目をまた細めながら、口を開く。
「……もしこれで仕事が進まなかったら」
責任取れよ、お前が。
と、照れたような声で言った言葉は、今度は私の頬を染めた。
Fin.