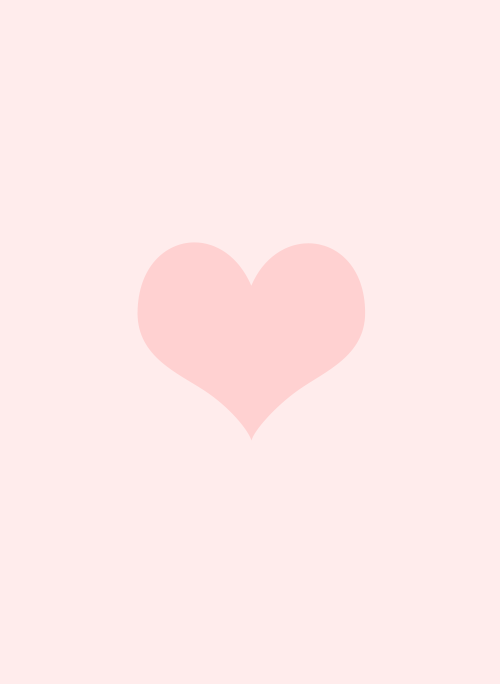濡れてもいいから
「気持ちいい?」
「うーん、いい」
「ここ?」
「んー……」
「どこがいいか、ちゃんといいなよ」
「そこっ……!」
優しく指で擦られて、甘いタメ息がもれる。
「まったく。なんでぼくがこんなことしてるのさ?」
口では文句をいいながらも丁寧に仕事をこなす泰成に、目を閉じた紀美香の口元がゆるむ。
「洗ってあげるって、泰成がいったんだよ」
泰成の指が、紀美香の泡まみれの頭を優しくマッサージしている。
口ではなんだかんだいいながら、やっていることからは愛が溢れていた。
愛を交わして、体も頭も洗ってもらってすっかりぴかぴかになった紀美香。
部屋へ戻ると、現実に気持ちが重くなった。
満たされたはずなのに、それでも明日のことを思うと気持ちが沈む。
わがままかもしれないけれど、やっぱり特別な日は特別な人と一緒にいたい。
半ば諦めつつも、紀美香はバッグを持って席を立った。
「そろそろ帰るね」
「泊まっていきなよ」
壁に寄りかかり座ったままの泰成が、紀美香の手を掴んで呼び止める。
「明日は仕事でしょ」
「……そんなの忘れた」
泰成が紀美香の腕を引っぱる。強く引っぱられ、バランスを崩して足の上に落ちてくる紀美香を泰成が受け止めた。
「社長命令なんでしょ」
身を強ばらせたまま、紀美香は呟く。
「……仕事は行くよ。もちろん仕事も大事だけど、ぼくにとってもっと大事なのは紀美香と過ごす時間。だから、紀美香にはおかえりっていってもらいたいから、待っててほしいんだ」
「お留守番?」
「うん。さっさと終わらせて帰ってくる。だから、ふたりで誕生日祝おう。じつはさ、もう冷蔵庫にケーキは入ってるんだ。日付変わったら食べようよ」
「ケーキ!?」
本当? キラキラ輝いた瞳が、泰成を見る。
「紀美香が好きなやつ入ってる。でも……」
壁に手をついて、紀美香を腕の中に閉じ込めた。
「しばらくケーキはおあずけだよ」
泰成の顔が近づいて、頬に息がかかる。目を閉じた泰成の唇が迫り、紀美香は顔を上げてその唇を迎えた。
END.
「うーん、いい」
「ここ?」
「んー……」
「どこがいいか、ちゃんといいなよ」
「そこっ……!」
優しく指で擦られて、甘いタメ息がもれる。
「まったく。なんでぼくがこんなことしてるのさ?」
口では文句をいいながらも丁寧に仕事をこなす泰成に、目を閉じた紀美香の口元がゆるむ。
「洗ってあげるって、泰成がいったんだよ」
泰成の指が、紀美香の泡まみれの頭を優しくマッサージしている。
口ではなんだかんだいいながら、やっていることからは愛が溢れていた。
愛を交わして、体も頭も洗ってもらってすっかりぴかぴかになった紀美香。
部屋へ戻ると、現実に気持ちが重くなった。
満たされたはずなのに、それでも明日のことを思うと気持ちが沈む。
わがままかもしれないけれど、やっぱり特別な日は特別な人と一緒にいたい。
半ば諦めつつも、紀美香はバッグを持って席を立った。
「そろそろ帰るね」
「泊まっていきなよ」
壁に寄りかかり座ったままの泰成が、紀美香の手を掴んで呼び止める。
「明日は仕事でしょ」
「……そんなの忘れた」
泰成が紀美香の腕を引っぱる。強く引っぱられ、バランスを崩して足の上に落ちてくる紀美香を泰成が受け止めた。
「社長命令なんでしょ」
身を強ばらせたまま、紀美香は呟く。
「……仕事は行くよ。もちろん仕事も大事だけど、ぼくにとってもっと大事なのは紀美香と過ごす時間。だから、紀美香にはおかえりっていってもらいたいから、待っててほしいんだ」
「お留守番?」
「うん。さっさと終わらせて帰ってくる。だから、ふたりで誕生日祝おう。じつはさ、もう冷蔵庫にケーキは入ってるんだ。日付変わったら食べようよ」
「ケーキ!?」
本当? キラキラ輝いた瞳が、泰成を見る。
「紀美香が好きなやつ入ってる。でも……」
壁に手をついて、紀美香を腕の中に閉じ込めた。
「しばらくケーキはおあずけだよ」
泰成の顔が近づいて、頬に息がかかる。目を閉じた泰成の唇が迫り、紀美香は顔を上げてその唇を迎えた。
END.