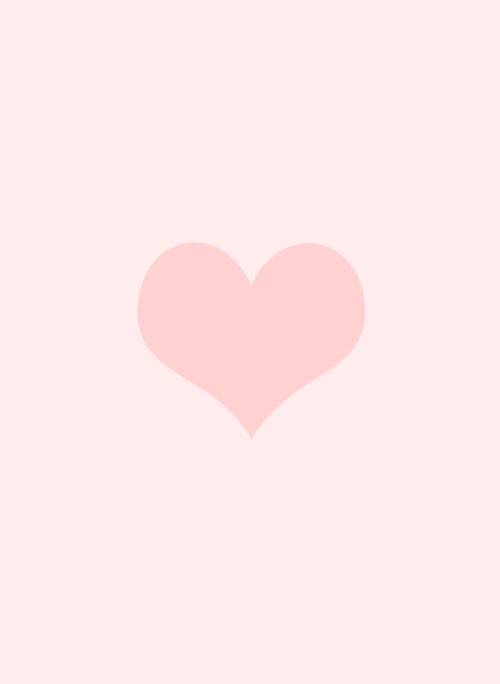【反省は】玉の輿なのにやらかした件。【していない。】
元夫とラインで何を話せというのだろう。
私は呆れながら携帯を取り出した。
ラインごとき、勝手に彰久から聞けばいいのにわざわざ東京まで出てきて私とライン交換したいだなんて本当におかしな人だ。
「アプリはもう入っているんですね?じゃあふりふり(交換)しますよ」
「はい」
景久さんはにっこりと天使の微笑みを浮かべて携帯を取り出した。
ホテルの地下駐車場で向かい合って携帯を振りあっている大人二人の図というのはなかなかシュールなものがあるな。
私は携帯に景久さんのラインアカウントが入ったのを確認して携帯をバッグに片付けた。
「んじゃ、もう用は済みましたよね。
景久さん、今夜はこのホテルを予約しているんですか。このホテルの朝ご飯はベーカリーが人気ですよ。私、朝ご飯を食べそこねたときに出社ついでにここでパンを買うんです」
私は東京は不慣れかもしれない景久さんにさりげなくおいしい朝ご飯情報を提供した。
景久さんはそんな私の一言に何がおかしいのかくすっと笑った。
「いえ、北条家所有のマンションに宿泊します。
できればあなたのマンションにお邪魔したかったのですが、元夫婦とは言え今は法律上他人ですし、いきなり押しかけるのはご迷惑かと思いまして」
「……うん、法律上他人っていうか、法律上だけでなくあらゆる方面からみて私達は完全なる他人ですから自宅に押しかけるのは絶対にやめてくださいね。来ても泊めませんから」
最近出歩きがちなのもあって、私のマンションはものすごく散らかっている。家で自炊することが少ないので生ゴミの類は少ないが、読もうと思って買ったものの、読む時間がなくてそのままになっているファッション誌や出そうと思いつつも回収に出せなかった新聞紙、通販のダンボール、洗ってそのままになっているペットボトルなどが手狭な玄関に山と積まれていて、とても人様をお招きできる状態ではない。
「一年ぶりに会えたというのに冷たい人ですね」
「一年ぶりにまた私を騙した人にこの対応はまだ寛大なほうだと思いますけど」
彼の言葉に即座に言い返してから、私はふと景久さんの顔を見上げた。彼の表情にはどこか私とのやり取りを楽しむような笑みが滲んでいる。
もしかしたら、この人はあまりこういう応酬をする相手に恵まれていないのかもしれないな。もともと友達も少なそうだし、桜子さんには振られたらしいしな……。
なんと哀れな。
そんな失礼なことを考えていると、私は迷惑だなと感じていたこういう接触を、自分がそれほど嫌っていないことに気がついた。
この人と結婚をすると決めたときにもやはり同じ事を感じていたような記憶がある。
私はとうとう表情を崩して笑ってしまった。
「景久さん」
「はい」
私はすぐには言葉を続けなかった。
景久さんは私の次の言葉をゆっくりとした態度で待っていてくれている。
一分、二分と過ぎていく時間を苛立ちもせずに私の次の言葉のために待っていてくれる。
あの時と同じだ。
記憶の蓋がゆっくりと開き、一年の間すっかり忘れてしまっていたほのかな慕わしさが蘇る。
まったく、しょうがない人だ。景久さんはもちろんだが、私も。
私は微笑みながら彼から目をそらし、自分の足元に目をやった。
いくら彼氏が出来ないからって、あんな事情で別れた元夫にこんな気持ちを感じるなんて。
「なんでもないです。もういい時間ですし、そろそろ帰りますね」
「送ります。まだあなたと離れたくありません」
「いえ、今日はいろんなことがありすぎてなんだか疲れましたので一人で帰ります。じゃあ」
私はそれ以上引き止められないうちにさっと踵を返す。
「美穂さん」
次の瞬間、私の体は彼の腕の中にさらわれ、景久さんの唇が私のそれに重なっていた。
彼の服から漂う品の良い香りが私を包み込み、私はあっという間に彼と一緒に過ごしたあの日々に引き戻されてしまう。
突然こんな事をしたくせに、彼の唇はかすかに震えていた。
私もキスごときで動揺するような年齢ではないが、でもさすがに一年ぶりに再会した元夫にこんな事をされたら驚いてしまう。
私は真っ赤になって彼の胸に手を突っ張って互いの体を離した。
「な、何を、するんですか。いきなり……。アグレッシブすぎますよ!」
「すみません……驚かせてしまって」
景久さん自身も自分の行動に戸惑っているようで、しみ一つない白い頬を赤らめた。なぜか自身の唇を手の甲で拭っている。自ら私にキスをしておいて失礼な男だ。
彼は頬を赤らめたまま、色素の薄いその美しい瞳で私を見つめた。
「この一年、ずっと考えていたのです。あなたが僕に残したあの言葉の意味を」
「言葉、ですか。ええと、なんでしたっけ」
短い結婚生活だったけれど、景久さんは正直言って変人なので、私は何度か妻としていくつか指摘させてもらった。景久さんはそのうちのどれかについて言っているのだろうが、今の私にはそれがどんな言葉だったのかはっきりとは思い出せない。
景久さんは神経質そうな細い眉をよせて、軽く私をにらんだ。
「本当に、あなたはいろんな意味で前しか見ない人ですね……!
あなたは『今度こそ義務にとらわれず、自分自身の手で幸せを探り当てて、迷わずそれをつかみとって欲しい。あなたが幸せになるために、足りないのはそれだけです。』と、書き残しておいてくれましたよね」
私はぽんと手を打った。
「ああ!それね!!覚えてます覚えてます」
「僕は、あの言葉のために桜子と別れ、あなたを追いかけることを選んだのです。
たとえあなたが二度と僕を見てくれなくとも、僕はこの一生をすべて賭けてでも自分自身の手で幸せを手に入れようと、そう思ったのです」
「……えっ」
そういう意味にとられるとは思わなかった。
「さきほどの行動については僕も予定していたわけではありませんが、ですが、間違っていたとは思いません。
自分の幸せを自分自身の手でつかみとる。決して迷わない。
僕にそれを教えたのは、あなたなのですから」
あの言葉を離婚届の欄外に書き残したときは、私っていいこと言うじゃないの的な感じで悦に入っていたのだが、今その一言が引き起こした結果を思えば自分で自分の首を締めてしまったのだという事がわかる。
景久さんと結婚したこと、朱雀を天に帰したこと、そして離婚の道を選んだこと。そのどれ一つとして、私は微塵も後悔していない。けれど、景久さんに残したこの言葉については……想定外の結果を招いてしまったようだ。
反省、したほうがいいのかな。さすがに。
私は再び目の前に現れた変人を前に、深い深いためいきをついたのだった。
おわり