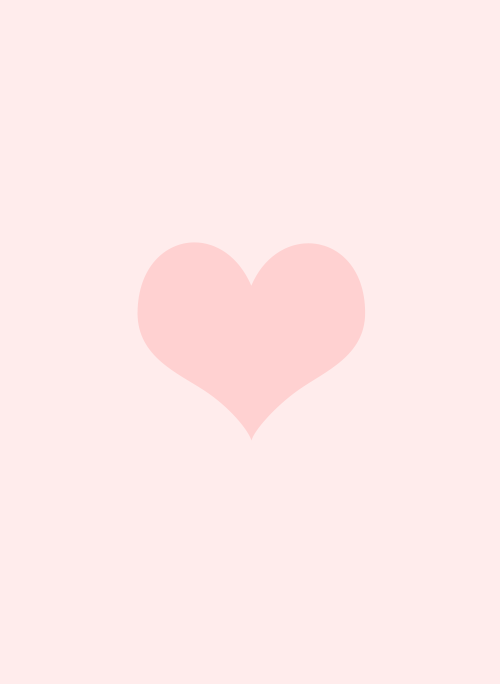あのころ、
一年半前、母さんから連絡があって、様子が変だという仁の話を聞くため、俺は東京へ行った。そのとき、仁と初めて飲みに行った。どうでもいい思い出話に花を咲かせ、お互いの知らない三年半を語り合った。ただ、サキのことだけは、その名前さえ酒の肴になることはなかった。結局その後も、俺が東京にいる間、サキの話は出なかった。
東京を発つ日、東京駅には、母さんが見送りに来てくれた。仁はいなかった。大事な用があるらしい、と母さんは言った。
大事な用──それだけで、俺には分かった。これでもう東京に思い残すことはない。これで、『帰れる』。そう思った。
「じゃ、俺は帰るよ」
別れ際、改札でそう言うと、母さんは一瞬、寂しそうな顔を浮かべた。母親の勘というものだろうか、そのたった一言で俺の心境の変化というものに気づいたようだった。東京がもう俺にとって『帰る』場所ではなくなったことを。また遊びに来てね、という声はどこか自信無げだった。
博多までの新幹線に乗りこみ、窓の外でめまぐるしく変わる景色をずっと眺めていた。連なるビルが低くなって、住宅街へと変わり、青々とした畑が広がる。そんな変化が何度も繰り返されて、ちょうど、京都にさしかかるかというころだった。仁からメールが届いた。読まなくても、内容は分かっていた。やっときたか、という感じだった。
それは、『吉報』だった。
ようやく、サキとヨリを戻せました──そんな文章と一緒に、チュー顔の顔文字が送られてきていた。俺は『顔文字がきもい』と返した。
あれから、一年半。くだらないメールと気色悪い顔文字はたまに仁から送られてくるものの、気恥ずかしくて、サキとのことは聞けていなかった。
「順調そうだな」
ほっと安堵して、無意識にぼんやりとつぶやいていた。
仁は「え、なに?」と惚けた顔で振り返った。
「なんでもねぇよ。独り言だ」
頬がゆるんでいたことに、そのとき気づいた。あわてて顔を引き締め、頬杖ついてそっぽを向いた。
仁の面倒くさい性格はよく知ってる。一人で感慨に浸っていたなんて知れたら、からかわれるに決まっている。
「早く電話してこいよ」仁が何か言い出す前に、俺は先手を打った。「待ってるんじゃねぇの?」
「廉は根は優しいのに、ちょっと素直じゃないよね。不器用っていうのかな」
「は? なんだよ、突然?」
「真帆ちゃんを泣かせないようにね」
「うるせぇな、偉そうに」
「『お兄ちゃん』だからね」
窓の開く音がして、師走に騒ぐ冷たい風が流れこんで来た。
俺はふんと鼻で笑った。
「双子に兄貴もクソもあるかよ。数分の違いだろうが」
「──三分だよ」
「!」
俺はハッとして固まった。窓が閉まる音に続いて「博多に着いたよ」と話す声はずいぶん遠くに聞こえた。
そうっと振り返ると、仁の後ろ姿はすでに窓の向こうだった。
ジーンズの後ろポケットからはみ出た小さな手鞠がゆらゆらと揺れている。
羽織ってるのがカーディガンだけじゃ寒いのだろう。仁は身を縮こませながら、足をばたばたさせている。それでも無邪気な笑い声が聞こえて、長くなりそうだ、と思った。
「三分……か」
生まれたときはそれだけだった俺たちの距離は、二十二年経って、新幹線で約五時間だ。住む場所も家庭も違う俺たちは、もう『他人のそら似』に近いのかもしれない。
俺はなんとか仁と自分を区別しようと必死だった。双子として生まれた俺たちは何もかもが一緒で、俺はそれが嫌だった。
だから仁とは別の道を選び続けて、気づけば、俺たちの共通点は、見た目と声だけになっていた。
こうなることを望んでいたはずなのに、仁と間違われたころを懐かしく思うときがある。なんであんなに意固地になっていたんだろう、と虚しくなることがある。
歳を取るにつれて時間が足りなくなっていくのは、こうして後悔する時間が増えていくからなんだろう。
不思議だよな。子供のころ、くだらないことにかけた時間ほど、今ではずっと有意義に思えるんだ。
* * *
「まだかよ?」
脱衣所の扉を開けてみると、真帆がまだ鏡と睨めっこを続けていた。手には鉛筆のようなものが握られている。目の大きさが、さっきの二倍くらいになっていた。メイク直しというレベルじゃなくなっている。
「そこまで気合い入れる必要ないだろ。仁はスッピンでも気にしないぞ」
「私が気にします!」
「ああ、そう」
閉めた扉によりかかり、俺はため息まじりに苦笑した。
素顔のほうが好きだ、と何度も言ってるのだが、真帆はまったく聞く耳を持たない。どうやら、メイクはそういう問題ではないらしい。メイクには女のプライドでもかかっているんだろうか。
「そういえば」と口紅を唇に当てながら、真帆は切り出した。「お昼、何かつくりますよ。お兄さんになにが食べたいか聞いてくれますか?」
「焼きそば」
間髪入れず、迷わずそう答えると、真帆は手を止め、じろりと俺を睨みつけてきた。
「聞いてました? 廉さんが食べたいものじゃなくて、仁さんが何を食べたいかを聞いてるんですよ」
「だから、焼きそばだよ」
真帆は訝しそうに顔をしかめた。
「なんで、そう言い切れるんですか? もう聞いたんですか?」
「聞かなくても分かるんだよ」俺は肩をすくめ、ニッと得意げに笑った。「双子だからな」
東京を発つ日、東京駅には、母さんが見送りに来てくれた。仁はいなかった。大事な用があるらしい、と母さんは言った。
大事な用──それだけで、俺には分かった。これでもう東京に思い残すことはない。これで、『帰れる』。そう思った。
「じゃ、俺は帰るよ」
別れ際、改札でそう言うと、母さんは一瞬、寂しそうな顔を浮かべた。母親の勘というものだろうか、そのたった一言で俺の心境の変化というものに気づいたようだった。東京がもう俺にとって『帰る』場所ではなくなったことを。また遊びに来てね、という声はどこか自信無げだった。
博多までの新幹線に乗りこみ、窓の外でめまぐるしく変わる景色をずっと眺めていた。連なるビルが低くなって、住宅街へと変わり、青々とした畑が広がる。そんな変化が何度も繰り返されて、ちょうど、京都にさしかかるかというころだった。仁からメールが届いた。読まなくても、内容は分かっていた。やっときたか、という感じだった。
それは、『吉報』だった。
ようやく、サキとヨリを戻せました──そんな文章と一緒に、チュー顔の顔文字が送られてきていた。俺は『顔文字がきもい』と返した。
あれから、一年半。くだらないメールと気色悪い顔文字はたまに仁から送られてくるものの、気恥ずかしくて、サキとのことは聞けていなかった。
「順調そうだな」
ほっと安堵して、無意識にぼんやりとつぶやいていた。
仁は「え、なに?」と惚けた顔で振り返った。
「なんでもねぇよ。独り言だ」
頬がゆるんでいたことに、そのとき気づいた。あわてて顔を引き締め、頬杖ついてそっぽを向いた。
仁の面倒くさい性格はよく知ってる。一人で感慨に浸っていたなんて知れたら、からかわれるに決まっている。
「早く電話してこいよ」仁が何か言い出す前に、俺は先手を打った。「待ってるんじゃねぇの?」
「廉は根は優しいのに、ちょっと素直じゃないよね。不器用っていうのかな」
「は? なんだよ、突然?」
「真帆ちゃんを泣かせないようにね」
「うるせぇな、偉そうに」
「『お兄ちゃん』だからね」
窓の開く音がして、師走に騒ぐ冷たい風が流れこんで来た。
俺はふんと鼻で笑った。
「双子に兄貴もクソもあるかよ。数分の違いだろうが」
「──三分だよ」
「!」
俺はハッとして固まった。窓が閉まる音に続いて「博多に着いたよ」と話す声はずいぶん遠くに聞こえた。
そうっと振り返ると、仁の後ろ姿はすでに窓の向こうだった。
ジーンズの後ろポケットからはみ出た小さな手鞠がゆらゆらと揺れている。
羽織ってるのがカーディガンだけじゃ寒いのだろう。仁は身を縮こませながら、足をばたばたさせている。それでも無邪気な笑い声が聞こえて、長くなりそうだ、と思った。
「三分……か」
生まれたときはそれだけだった俺たちの距離は、二十二年経って、新幹線で約五時間だ。住む場所も家庭も違う俺たちは、もう『他人のそら似』に近いのかもしれない。
俺はなんとか仁と自分を区別しようと必死だった。双子として生まれた俺たちは何もかもが一緒で、俺はそれが嫌だった。
だから仁とは別の道を選び続けて、気づけば、俺たちの共通点は、見た目と声だけになっていた。
こうなることを望んでいたはずなのに、仁と間違われたころを懐かしく思うときがある。なんであんなに意固地になっていたんだろう、と虚しくなることがある。
歳を取るにつれて時間が足りなくなっていくのは、こうして後悔する時間が増えていくからなんだろう。
不思議だよな。子供のころ、くだらないことにかけた時間ほど、今ではずっと有意義に思えるんだ。
* * *
「まだかよ?」
脱衣所の扉を開けてみると、真帆がまだ鏡と睨めっこを続けていた。手には鉛筆のようなものが握られている。目の大きさが、さっきの二倍くらいになっていた。メイク直しというレベルじゃなくなっている。
「そこまで気合い入れる必要ないだろ。仁はスッピンでも気にしないぞ」
「私が気にします!」
「ああ、そう」
閉めた扉によりかかり、俺はため息まじりに苦笑した。
素顔のほうが好きだ、と何度も言ってるのだが、真帆はまったく聞く耳を持たない。どうやら、メイクはそういう問題ではないらしい。メイクには女のプライドでもかかっているんだろうか。
「そういえば」と口紅を唇に当てながら、真帆は切り出した。「お昼、何かつくりますよ。お兄さんになにが食べたいか聞いてくれますか?」
「焼きそば」
間髪入れず、迷わずそう答えると、真帆は手を止め、じろりと俺を睨みつけてきた。
「聞いてました? 廉さんが食べたいものじゃなくて、仁さんが何を食べたいかを聞いてるんですよ」
「だから、焼きそばだよ」
真帆は訝しそうに顔をしかめた。
「なんで、そう言い切れるんですか? もう聞いたんですか?」
「聞かなくても分かるんだよ」俺は肩をすくめ、ニッと得意げに笑った。「双子だからな」