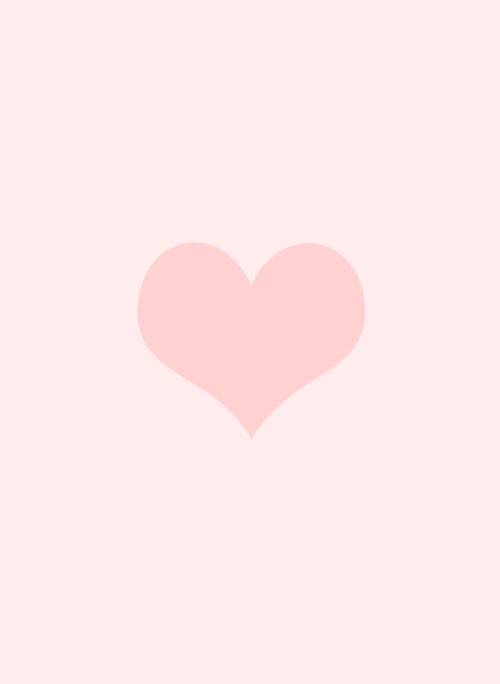蜜愛フラストレーション
目の前にいるのは優斗なのに。大切な人の温かい手だったのに。
昨日の“あんなモノ”と重なって見えたことが悔しくて。記憶ごと塗り潰してしまいたい。
「ひとりじゃないよ。萌は俺が守るから、もう絶対に」
そこで彼の言葉が途切れる。きっと昨日のことを思い出させないために口にできなかったはず。
私が優斗を守りたかったように、彼はそれ以上に私のことを陰で守り続けてくれたから。
この心を蝕んでいる黒い陰が一刻も早く消えて欲しい。声を早く取り戻したい。元気になって働きたい。夜に安心して眠れるようになりたい。
どれもが当たり前にしていたことなのに、今となってはそれが難しいなんて。何より、優斗の顔を曇らせているのが私、この現実が堪らなくなるのだ。
“ありがとう。優斗だって身体を大切にしてね”、とスケッチブックに書き伝えることが精いっぱいだった。
* * *
優斗はその後、会社から呼び出しがかかり、名残惜しい表情で帰っていった。
きっと無理を承知で仕事を抜けてきたはず。
暫く今回の一件でごたつくようなので、体調面でも心配だけれど、今の私が課長や彼を憂慮するほうが滑稽な話だ。
夕食を終えてそんなことをぼんやり考えながらソファに座っていた時、ふと女性医師が病室を訪れた。
体調や心境の変化を尋ねられた私は、スケッチブックに搔い摘んで書き伝えることにした。
正面のソファに座った女性医師はそれを見て、「そう、良かったわ」と小さく微笑んだ。
じめじめした感情を記してしまった私は、彼女の反応に目を丸くさせられる。
“愚痴を吐いてしまってすみません”
そして自然と、疑念と後悔がスケッチブックに謝罪の文字を生み出していた。
「斉藤さんは口に出せたのなら、もう一歩前に進んでる。その勇気を出した自分を自分で褒めなきゃ。それに人にとって欲望は欠かせないものだから、あれこれ願うのも当然よ」
女性医師は柔らかな声で、頑なな私の心にゆっくりと語りかけてくる。
人は欲張りなんて言うけれど、どうやら本当らしい。
享受されたものに当たり前なんて保証はないのに、なんら感謝せずに日々過ごしてしまう。
突然それを奪われた瞬間、日常は一変するのに。同時に当たり前の幸せにそこで気づくのだから、じつに皮肉なものだ。