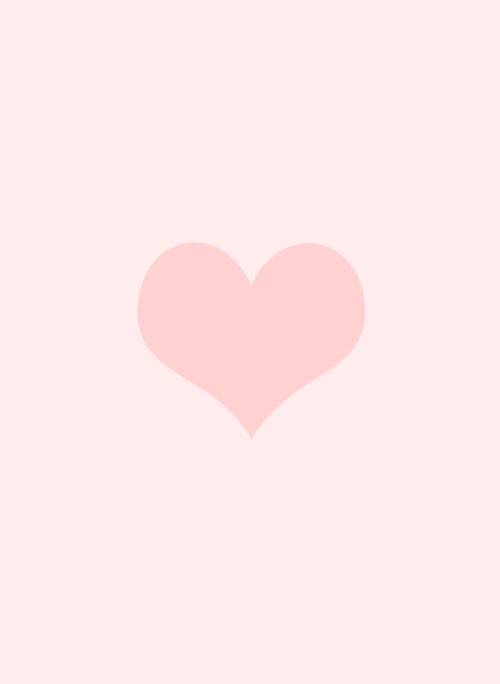草花治療師の恋文
≪現在≫
「……おばあ様って、やっぱり昔から超人だったんだね…。」
はぁーっと息を吐いて、リアンは肩を落とした。
「え?何歳の時の話だ?」
サクマはリーに聞いた。
「14、15歳頃の出来事だったと存じます。」
「14、5⁈」
俺何歳だったかな?と考えるようにサクマは天井を仰いだ。
サクマもリアンも17歳で、父親に治癒の療法を施したマーガレットのほうが幼かった。
今のテンペスト一族は、マーガレットの幼少時期に比べると強い規律は少ない。
マーガレットが逃げだした厳しい想記の訓練もなく、個々の能力に合わせてゆっくりと才能を開花させるようになっている。
なので、サクマ達が若い頃のマーガレットより治療師としてのスキルが低いのは仕方がない事なのだ。
「っはぁー…すっげー…」
サクマは仰いだ顔を両手で隠した。
「マーガレット様は治療師としての素質はありましたが、決して生まれながらの超人ではありませんよ。」
リーが苦笑いしながら話した。
「泣く泣く努力した結果だったのです。」
「そうだろうけど…。じゃあ、今はなぜ昔と同じような治療師の教育をしないの?」
リアンは少し不満げに問いかけた。
その問いに、リーはゆっくりと首を横に振った。
「マーガレット様がご自身のお子様、つまりサクマ様とリアン様のお父様に同じ教育をすることができなかったからです。」
「できなかった?なぜ?」
リアンはリーを見た。
「答えは簡単ですよ。ご子息2人を溺愛していたからです。自分と同じような教育をするのは可哀想だと…。なにせ自分自身が逃げては泣いてを繰り返したのですから。」
リーはクスクスと笑った。
それを聞いたサクマとリアンはポカンとした。
「…え?そんな理由?」
リアンは、まさか…という顔をした。
「そんな理由なのですよ。」
リーは笑うのを堪えて答えた。
えー…?
と、声には出なかったが、サクマもリアンも顔が喋っていた。
その表情をみてリーが聞いた。
「意外でしたか?」
「いや…うーん…。」
リーの問いに、サクマは言葉を詰まらせた。
しかし、よくよく思い出したら、自由奔放ではあったが人に無理強いをする人ではなかった。
昔から決められた古臭い規律を取り払い、「テンペスト一族の治療師」という名の品質を維持する為の教育は廃止し、テンペスト一族以外の子供や大人も治療師やそれに関する仕事を選択できるように、全員に自由があるのだという意思を貫き、現在の教育方針ができた。
早朝に薬草を持って訪問してきた薬草堂のサラも、昔の規律なら薬草師の家系ではないという理由で薬草師にはなれていなかった。
優秀な才能がどれだけ隠されていたのか…。
マーガレットが当主になってから、隠されていた才能がたくさん咲いた。
そして、マーガレット亡きこれからもきっと。
「まぁ、おばあ様はこうと決めたら絶対な人だったけど、周りを泣かせる人ではなかったなぁ。」
リアンは頬杖をついた。
自分たちは甘やかされてたんだと自覚して、なんだか恥ずかしくなって、ため息をついた。
「そうですね。マーガレット様は泣く姿を見るのがお嫌いでしたから、困っている方がいらしたら放っておけない方でした。」
リーは思い起こして微笑んだ。
「しかしまぁ、おばあ様の奔放さに誰も文句言わなかったのか?おじい様とか。」
「あ、そうだよね。当主はおばあ様だったとしても、同じ権限を持つおじい様もいたわけだよね。規則の事とか反対しなかったの?」
その言葉に、リーの表情が一気に陰った。
それに2人はすぐに気付いた。
「…….リー?」
リアンは普段の表情とは違うリーに、どうしたらいいのかわからなくなった。
それに気が付いたリーは、慌てて表情を通常運転に戻した。
「旦那様…スバル様は…、マーガレット様と婚姻式をされたあとすぐに遠方へ出張した先で…行方が分からなくなったのです。」
「えっ…」
サクマとリアンは、ほとんど声が出なかった。
それは孫にあたる2人には知らされていなかった事実だったのだ。
驚く2人を見て、リーは少し困ったような顔をした。
「本当に…今日はなんて日なんでしょうね…。」
リーは肩の力を抜きながら呟いた。
「こうも秘密をお話ししてしまう日が来るとは…思いもしませんでした。」
マーガレットの幼少期の出来事に続き、孫に隠して来た祖父の事実。
長年仕えてきた執事だからこそ、テンペスト家と共有してきた記憶がある。
ただ、それを誰かに話す日が来るなど思ってもいなかった。
(まいりましたよ…マーガレット様)
リーは心の中で呟いた。
「……おばあ様って、やっぱり昔から超人だったんだね…。」
はぁーっと息を吐いて、リアンは肩を落とした。
「え?何歳の時の話だ?」
サクマはリーに聞いた。
「14、15歳頃の出来事だったと存じます。」
「14、5⁈」
俺何歳だったかな?と考えるようにサクマは天井を仰いだ。
サクマもリアンも17歳で、父親に治癒の療法を施したマーガレットのほうが幼かった。
今のテンペスト一族は、マーガレットの幼少時期に比べると強い規律は少ない。
マーガレットが逃げだした厳しい想記の訓練もなく、個々の能力に合わせてゆっくりと才能を開花させるようになっている。
なので、サクマ達が若い頃のマーガレットより治療師としてのスキルが低いのは仕方がない事なのだ。
「っはぁー…すっげー…」
サクマは仰いだ顔を両手で隠した。
「マーガレット様は治療師としての素質はありましたが、決して生まれながらの超人ではありませんよ。」
リーが苦笑いしながら話した。
「泣く泣く努力した結果だったのです。」
「そうだろうけど…。じゃあ、今はなぜ昔と同じような治療師の教育をしないの?」
リアンは少し不満げに問いかけた。
その問いに、リーはゆっくりと首を横に振った。
「マーガレット様がご自身のお子様、つまりサクマ様とリアン様のお父様に同じ教育をすることができなかったからです。」
「できなかった?なぜ?」
リアンはリーを見た。
「答えは簡単ですよ。ご子息2人を溺愛していたからです。自分と同じような教育をするのは可哀想だと…。なにせ自分自身が逃げては泣いてを繰り返したのですから。」
リーはクスクスと笑った。
それを聞いたサクマとリアンはポカンとした。
「…え?そんな理由?」
リアンは、まさか…という顔をした。
「そんな理由なのですよ。」
リーは笑うのを堪えて答えた。
えー…?
と、声には出なかったが、サクマもリアンも顔が喋っていた。
その表情をみてリーが聞いた。
「意外でしたか?」
「いや…うーん…。」
リーの問いに、サクマは言葉を詰まらせた。
しかし、よくよく思い出したら、自由奔放ではあったが人に無理強いをする人ではなかった。
昔から決められた古臭い規律を取り払い、「テンペスト一族の治療師」という名の品質を維持する為の教育は廃止し、テンペスト一族以外の子供や大人も治療師やそれに関する仕事を選択できるように、全員に自由があるのだという意思を貫き、現在の教育方針ができた。
早朝に薬草を持って訪問してきた薬草堂のサラも、昔の規律なら薬草師の家系ではないという理由で薬草師にはなれていなかった。
優秀な才能がどれだけ隠されていたのか…。
マーガレットが当主になってから、隠されていた才能がたくさん咲いた。
そして、マーガレット亡きこれからもきっと。
「まぁ、おばあ様はこうと決めたら絶対な人だったけど、周りを泣かせる人ではなかったなぁ。」
リアンは頬杖をついた。
自分たちは甘やかされてたんだと自覚して、なんだか恥ずかしくなって、ため息をついた。
「そうですね。マーガレット様は泣く姿を見るのがお嫌いでしたから、困っている方がいらしたら放っておけない方でした。」
リーは思い起こして微笑んだ。
「しかしまぁ、おばあ様の奔放さに誰も文句言わなかったのか?おじい様とか。」
「あ、そうだよね。当主はおばあ様だったとしても、同じ権限を持つおじい様もいたわけだよね。規則の事とか反対しなかったの?」
その言葉に、リーの表情が一気に陰った。
それに2人はすぐに気付いた。
「…….リー?」
リアンは普段の表情とは違うリーに、どうしたらいいのかわからなくなった。
それに気が付いたリーは、慌てて表情を通常運転に戻した。
「旦那様…スバル様は…、マーガレット様と婚姻式をされたあとすぐに遠方へ出張した先で…行方が分からなくなったのです。」
「えっ…」
サクマとリアンは、ほとんど声が出なかった。
それは孫にあたる2人には知らされていなかった事実だったのだ。
驚く2人を見て、リーは少し困ったような顔をした。
「本当に…今日はなんて日なんでしょうね…。」
リーは肩の力を抜きながら呟いた。
「こうも秘密をお話ししてしまう日が来るとは…思いもしませんでした。」
マーガレットの幼少期の出来事に続き、孫に隠して来た祖父の事実。
長年仕えてきた執事だからこそ、テンペスト家と共有してきた記憶がある。
ただ、それを誰かに話す日が来るなど思ってもいなかった。
(まいりましたよ…マーガレット様)
リーは心の中で呟いた。