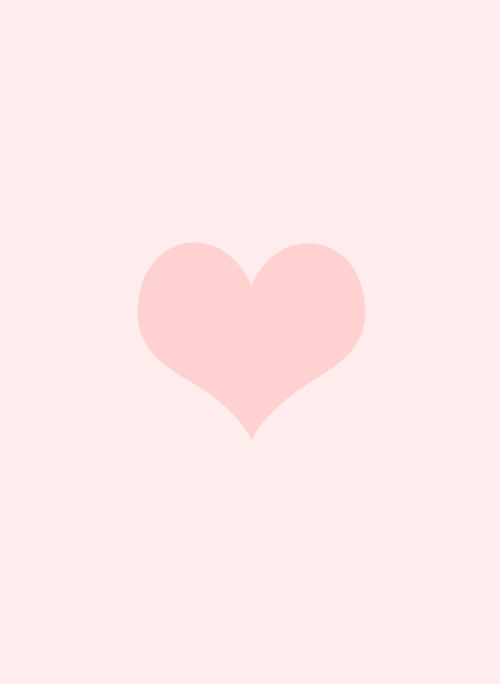月はもう沈んでいる。
陽が泣くことなんてめったにない。
だから俺は。俺だけは、知っているんだ。
陽が涙をこぼすとき、背を丸めてちいさくなることを。陽が涙をぬぐうとき、顔を上げて空を仰ぐことを。
どうしてそこまで来て、俯いちゃうんだよ。
「早く行けって……」
教師に見つかったらどうするんだ。連れ戻されるとか、冗談じゃねえぞ。
「……っきら、」
ふざけるな。今日くらい、かっこよく終わらせてくれよ。
不器用な想いも、不慣れなキスも、貰っておいて涙ながらにお別れなんて。『待ってる』も『迎えに行く』も、俺たちには必要のない言葉に思えるのに。
それでも体は正直に、もどかしいほど大ざっぱに窓のサッシを踏み越えて、ベランダの手すりへ身を乗り出していた。
大きく、大きく、肺いっぱいに春の風を吸い込んで。
「陽あああああ!!」
息が続かなくなるまで吠えると、ぽたりと涙がひと粒こぼれた。
ちくしょう、と心の中でつぶやく。
陽だけを想い続けられる自分でいたかった。
陽しか大事にできない自分でいられたらよかった。
俺も、陽以外いらないって、言ってやりたかったよ。
たったひとりを愛して死ねる奴がいたら、俺はそいつを心の底から妬むだろう。悔しくて悔しくて、俺だって本当は、と決まり文句のように繰り返すだろう。
そうやって俺たちはどうしようもない感情と一緒に何度も朝を迎えて、大人になっていくしかない。
「がんばれ……っ、負けんな! がんばれよっ!!」
初めて口にしたあと、返事をするかのように勢いよくスクーターのエンジンがかかる。
陽は空を見上げるとこちらへ振り仰いで、めいっぱい頭上に手を上げた。
俺の視力はそんなに良くないけれど、思わず微笑みが浮かんだってことは、陽は満面の笑みをくれたのだろう。
走り去る影法師を見送って、携帯を手に取る。
「さて……」
自分の装いを確認してから、空へと微笑みかけた。
月はもう沈んでいる。
透き通った青空は晴れ舞台にぴったりで、春をまとう風はゆるやかに背を押してくれる。
「あ、じいちゃん? あのさ、卒業式始まる前に、ネクタイ持ってきてくれない?」
――さあ、旅立ちの時間だ。
【END】