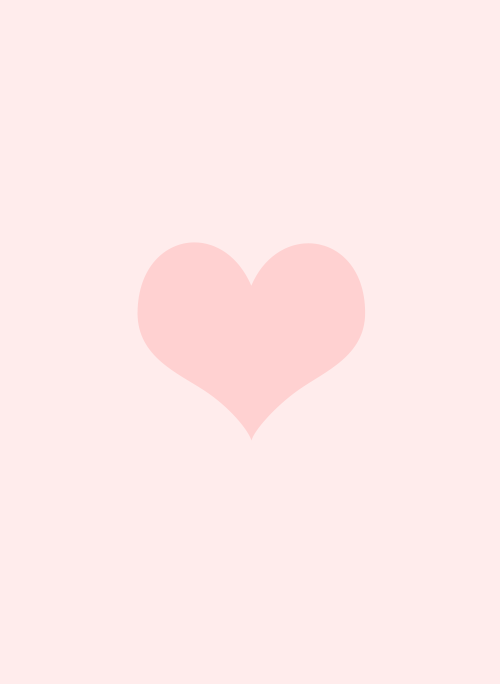彼は私を抱き締めた。
「君のことを閉じこめて、離したくない。いつだってそう思ってる」
そのささやきに腰から砕けそうになりながら、彼に身を預けてしまいたくなる。
「……だめ、です。仕事、しなきゃ」
必死で理性を食い止めて、肩にある彼の手をとめる。
耳に直接流れこんできたため息にびくりと肩を跳ねつつも、首を横に振った。
彼が私の正面にいなくてよかった。
だって絶対に赤い今の顔、みっともなくて見せられない。
本当は私もそうして欲しいって、ばれてしまう。
「仕方がない。仕事を頑張る君のことを好きになったからね」
惚れた弱みだ、と彼が幸福と独占欲をにじませた声を落とした。
私の心を乱す。
「それじゃあまた、帰りに」
髪に名残惜しげに触れた唇が離れ、力がわずかに緩められる。
ふわりと浮かぶように、私はそっと彼の腕から抜け出してフロアへと足を踏み出した。
*
会社の【エレベーター】で。